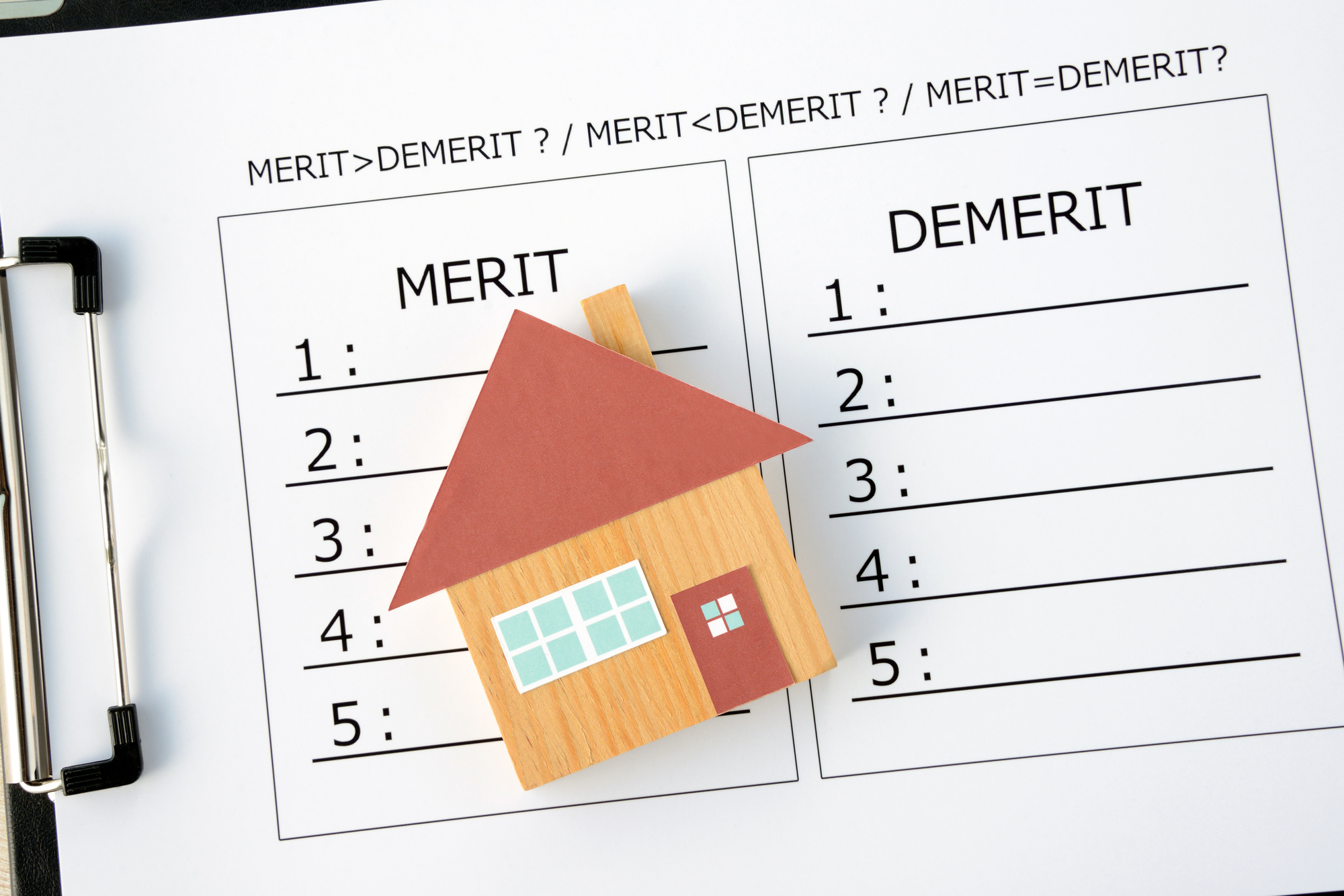公開日:2025.10.02 更新日:2025.09.26
再建築不可物件とは?仕組みと対策を徹底解説

再建築不可物件は、新築や建替えに法的な制限があり、その背景には都市整備や法律改正の歴史が関わっています。活用や売却の方法は限られますが、条件次第で価値を引き出す道もあります。この記事では、再建築不可物件のメリット・デメリット、取引時の注意点から活用戦略までを解説。ご自身に合った選択肢を見極めるためのヒントをお届けします。
目次
再建築不可物件の定義と具体例

不動産の売買を検討する際、特に注意が必要なのが「再建築不可物件」です。契約書や重要事項説明書にその旨が記載されていても、仕組みや背景を正しく理解していなければ、売却代金や将来の活用方法に大きな制約が生じる恐れがあります。
再建築不可とは、建築基準法などの法律上の条件を満たさないために、新たな建物を建てられない土地や建物を指します。接道義務の不備や建ぺい率・容積率の超過など、理由はさまざまです。まずは、売主・買主双方が契約前に確認しておきたい具体例や注意点を解説します。
土地の接道義務を満たしていないケース
建築基準法第43条1項では、建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないと定められています。これは「接道義務」と呼ばれ、災害時の避難経路確保や都市インフラの整備を安全に行うための重要な条件です。
再建築不可物件の多くは、この接道義務の要件を満たしていないことが原因です。例えば、物件の前面道路が4m未満だったり、土地が道路にごくわずかしか面していなかったりするケースが該当。このような土地は消防車や救急車の進入が難しく、都市の安全面にも支障をきたします。
対策としては、隣地の一部を購入して接道幅を確保する方法が考えられます。しかし、実現には土地売買契約書の作成、契約金額や登記費用の調整、印紙税の納付、近隣住民や自治体との交渉など、多くの手続きと費用が伴います。
売主・買主双方にとって慎重な事前確認が不可欠であり、契約書や重要事項説明書にしっかり記載し、トラブルを未然に防ぐ姿勢が求められるでしょう。
建ぺい率や容積率の制限を満たさないケース
建築基準法では、土地面積に対する建物の建築面積割合(建ぺい率)や延べ床面積割合(容積率)が定められています。既存建物がこれらの基準を超えている場合、一度取り壊すと現行法規上の基準に適合する建物しか再建築できません。
特に古い住宅地では、用途地域の変更や法改正により、現行基準を大きく上回っているケースが少なくありません。再建築を行うには建物規模を縮小し、契約書や必要書類を整えて所有権移転登記を行う必要がありますが、それでも許可が下りないこともあります。
こうした不動産は、不動産売買契約時に重要事項説明書で条件を明確にしなければ、引き渡し後のトラブルにつながります。契約前に不動産会社や宅地建物取引士と十分に内容を確認し、将来的な利用計画を踏まえて購入やリフォームを検討することが大切です。
なぜ再建築不可物件が生まれるのか
再建築不可物件が存在する背景には、法律の制定時期や都市整備の歴史的経緯が深く関係しています。建築基準法は昭和25年(1950年)に施行され、その後も幾度となく改正が行われました。
しかし、施行以前から建ち並んでいた家屋の中には、改正後の接道義務や建ぺい率などの基準を満たさなくなったものが少なくありません。当時の法規では適法でも、現行制度では増改築や新築、建替えができない状態に置かれるケースです。
また、都市計画や再開発が進まないまま、狭い路地や坂の多い住宅街に古い建物が残っていることもあります。景観保護や文化財保全の観点から、あえて再建築を制限するエリアもあり、こうした政策判断も再建築不可物件の存在に影響を与えています。
結果として、法改正前から存在する建物が現行制度に適合せず、既存不適格建築物として残り、不動産売買や活用の場面で課題となっているのです。
再建築不可物件のメリット・デメリット

再建築不可物件は、不動産売買契約の中でも特に注意すべき物件のひとつ。接道義務や建ぺい率などの法的要件を満たさないため、売買代金や将来の利用方法に制約が生じます。
一方で、売主・買主双方にとって価格や維持費の面で魅力がある場合もあります。契約書や重要事項説明書に記載される条件を正しく理解しないまま購入すると、引き渡し後にトラブルへ発展する恐れも。
ここでは、不動産会社や宅地建物取引士と確認すべきメリットとリスクを具体的に解説します。
価格が安いなどのメリット
再建築不可物件は、接道義務をはじめとした法的条件を満たさないため、市場価値が下がりやすいという特徴があります。その結果、同じエリアの再建築可能な物件より低価格で売買されるケースが多く、契約金額が市価の1〜5割程度安い事例も見られます。
さらに、固定資産税が低く抑えられる場合もあり、長期的な維持費を軽減したい買主にとっては魅力的。投資用としても、取得費用を抑えられる分、賃貸運用時に高い利回りを見込める可能性があるでしょう。
ただし、価格の安さだけで購入を決めるのは危険です。土地売買契約書や重要事項説明書に記載された接道や法規上の問題を確認し、売買契約書の内容を十分に理解したうえで判断することが重要です。
建替え不可によるリスクなどのデメリット
最大のデメリットは、新たな建物を建てられない点です。既存の建物が老朽化しても建替えができず、安全性や快適性の確保が難しくなる恐れがあります。
融資面でも、銀行などの金融機関から通常の住宅ローンを利用するのは困難で、買主は自己資金や別の担保を準備する必要があります。
また、抵当権の設定が難しいため、リフォームや改修費用を追加融資で賄うことも難しくなるケースがあります。
こうした不動産売買契約では、必要書類の確認や契約書の作成段階から専門家に相談し、所有権移転や登記の可否、負担金額まで慎重に検討することが不可欠です。契約後のトラブルを防ぐためにも、事前の情報収集と適切な判断が求められます。
再建築不可物件でも建替えが可能になるケース
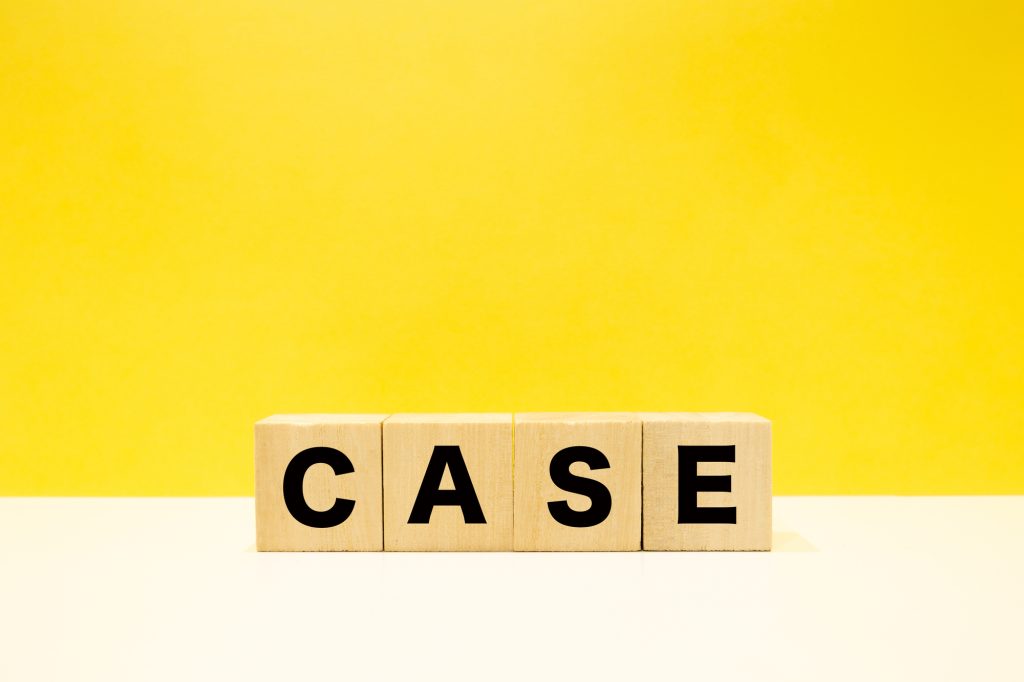
再建築不可物件であっても、一定の条件を満たせば建替えが認められる場合があります。隣地の取得や道路条件の改善など、方法はいくつか存在しますが、いずれも契約書や必要書類の準備、登記手続き、費用負担などが伴います。
売主・買主双方が法的要件と実務面を理解し、事前に不動産会社や専門家と確認することが、トラブル防止と円滑な不動産売買につながります。
隣地の買取や合筆による接道義務の解消
隣接する土地を買い足して合筆し、接道面を2m以上確保できれば、再建築不可の状態を解消できる場合があります。この方法は比較的直接的な解決策ですが、前提として隣地が売却可能であるか、または交渉によって購入できるかどうかが鍵となります。
仮に売買が成立しても、土地境界の確定測量、土地売買契約書の作成、所有権移転登記や合筆登記など、多くの書類作成や契約手続きが必要です。さらに、相場より高い契約金額で提示されることもあり、売買代金に加えて印紙税や登記費用といった諸費用の負担も発生します。
接道義務を満たせば建替えは可能となりますが、リフォーム・新築工事費、固定資産税の変動、将来の売却時の市場価値まで含めた総合的な資金計画が重要です。
道路の条件を満たすための交渉や手続き
前面道路の幅員が4m未満の場合、自治体や周辺住民と協力し、道路を拡幅して基準を満たす方法があります。具体的には、敷地の一部を道路用地として提供し、行政が整備することで4m以上を確保する手法です。
ただし、この取り組みは個人の判断だけでは進められず、行政への働きかけや地域住民の合意形成が不可欠です。負担割合や費用配分の調整は難航することが多く、売買契約や重要事項説明書で条件を明確化しておく必要があります。
また、すでに道路整備計画がある地域でも、実施までに長い年月がかかる場合があり、再建築を急ぎたい買主にとっては現実的とは言いがたい面があります。
再建築不可物件と住宅ローン・資金調達

再建築不可物件は、法的要件を満たさないことから担保価値が低く評価されやすく、通常の住宅ローンが使えないケースがほとんど。
売買契約や資金計画を立てる際には、金融機関の融資条件や担保評価の基準を理解し、必要書類や契約内容を事前に確認することが重要です。
ここでは、利用が難しい理由と代替的な資金調達方法について解説します。
通常の住宅ローン利用が難しい理由
再建築不可物件は、将来的に新築ができないため金融機関から担保価値が低いと判断されます。融資は、借り手が返済不能となった場合に担保を売却し貸出金を回収できることが前提ですが、この物件は売却市場での需要が限られ、価格も低くなりがちです。
加えて、老朽化した際の大規模改修も制限されるため、リスクはさらに高まります。その結果、多くの銀行や信用金庫では通常の住宅ローン商品では取り扱わず、契約時点で融資不可とされることが一般的です。
購入検討時には、必ず不動産会社や金融機関に確認し、売買契約書や重要事項説明書にもその旨を明記しておくことが望ましいでしょう。
現金購入や他物件の担保設定などの対処法
もっとも確実な方法は、自己資金による現金購入です。借入を行わないため審査は不要ですが、多額の資金を一度に用意する必要があります。
もう一つの手段は、別の不動産を抵当権の目的物として担保設定する方法です。たとえば、自宅や投資用の所有物件を抵当に入れることで、再建築不可物件の低い担保評価を補い、融資を受けやすくできます。
ただし、その物件に既に抵当権が設定されていたり、担保評価額が不足していたりする場合は追加融資が難しいこともあります。契約金額や必要書類、担保条件については、必ず事前に金融機関へ相談し、契約前に条件を確認しておきましょう。
再建築不可物件の購入方法・ポイント

再建築不可物件は、通常の不動産売買と比べて契約や資金調達に制約が多く、購入後の活用にも法的要件やリスクが伴います。売主・買主ともに、契約書や必要書類、所有権移転登記などの手続きを正しく理解しましょう。
ここでは、現金購入や特殊ローンの利用、将来の売却・活用を見据えた判断のポイントを解説します。
条件とリスクを把握した現金買い
再建築不可物件を最も確実に取得する方法は現金購入です。融資が利用できない、または厳しい条件が付く場合でも、現金であれば売買契約をスムーズに進められます。
ただし、相応の資金力が必要であり、物件の法的リスクや修繕費を見落とすと大きな損失になりかねません。購入前には、土地売買契約書や重要事項説明書を確認し、老朽化した建物の場合は耐震性や設備の状況も調査が必要です。
契約金額や印紙税、改修費用などを含めた総合的な資金計画を立て、リスクとリターンを慎重に比較検討することをおすすめします。
特殊ローンやリフォームローンの活用
一部の金融機関では、再建築不可物件でもリフォームローンや投資用ローンを活用できる場合があります。これらは金利が高めで審査も厳しい傾向がありますが、まとまった資金を確保できれば購入や改装の選択肢が広がります。とはいえ、ローン商品は条件や金額上限が変更されることも多く、事前確認が必須です。
また、担保価値が低く評価されるため、金融機関によっては融資対象外となることもあります。売買契約前に必ず事前相談を行い、契約書に条件を明記するとともに、返済計画や必要書類を揃えて準備しましょう。
将来的な売却や活用プランの確認
再建築不可物件は市場流動性が低く、将来の売却では値下がりリスクを伴います。そのため、購入時点で出口戦略を明確にすることが重要です。
立地や建物の特徴によっては、古民家再生や宿泊施設などの観光資源としての活用が可能な場合もあります。こうした収益化の可能性を検討する場合でも、用途変更には都市計画法、建築基準法その他の法令による制限や許認可が関わることがあります。
売主・買主双方で活用方法を共有し、宅地建物取引士や行政機関、施工業者と連携しながら計画を進めることで、契約後のトラブルや費用負担のリスクを軽減できます。
再建築不可物件売却時のポイント

再建築不可物件を売却する際は、通常の不動産売買よりも注意すべき点が多く存在します。
まずは、買主候補には契約前に必ず「再建築不可」である旨を明確に説明し、重要事項説明書や売買契約書に正確に記載を。これを怠ると、所有権移転後に売主の契約不適合責任の追及や損害賠償請求といったトラブルに発展する恐れがあります。
また、多くの不動産流通サイトでは、検索条件で再建築不可が敬遠されやすく、反響が得にくい傾向があります。そのため、不動産会社との契約形態や販売戦略を事前に検討し、限られたターゲット層に的確にアプローチする方法を構築することが重要です。
さらに、条件次第では隣地との合筆や道路拡幅により再建築不可を解消できる可能性もあります。追加費用や手続きは発生しますが、将来的な利用価値を提示できれば、売却成立の可能性を高められるでしょう。
再建築不可物件を正しく理解し、自分に合った選択を
再建築不可物件は、法的制約や市場価値の低さといったリスクがある一方で、低価格で取得できる可能性や独自の活用法といった魅力も兼ね備えています。購入・売却の判断には、接道義務や建ぺい率などの法的要件、住宅ローンの可否、リフォーム費用など多角的な視点が必要です。
情報を正しく整理し、売主・買主双方が納得できる条件を整えることが、円滑な取引の第一歩。専門家の助言を活用し、自分にとって最適な活用や評価の方向性を見極めていきましょう。
再建築不可物件の相談・活用も「アキサポ」へ
再建築不可物件の活用や売却には、法律や市場動向を踏まえた専門的な判断が欠かせません。「アキサポ」では、空き家や特殊な条件を持つ不動産の相談から活用プランの提案、売却戦略まで一貫してサポートしています。接道や建ぺい率などの条件整理から、将来性を引き出すための方法まで、状況に合わせた最適な選択肢をご提案。まずはお気軽にご相談ください。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。