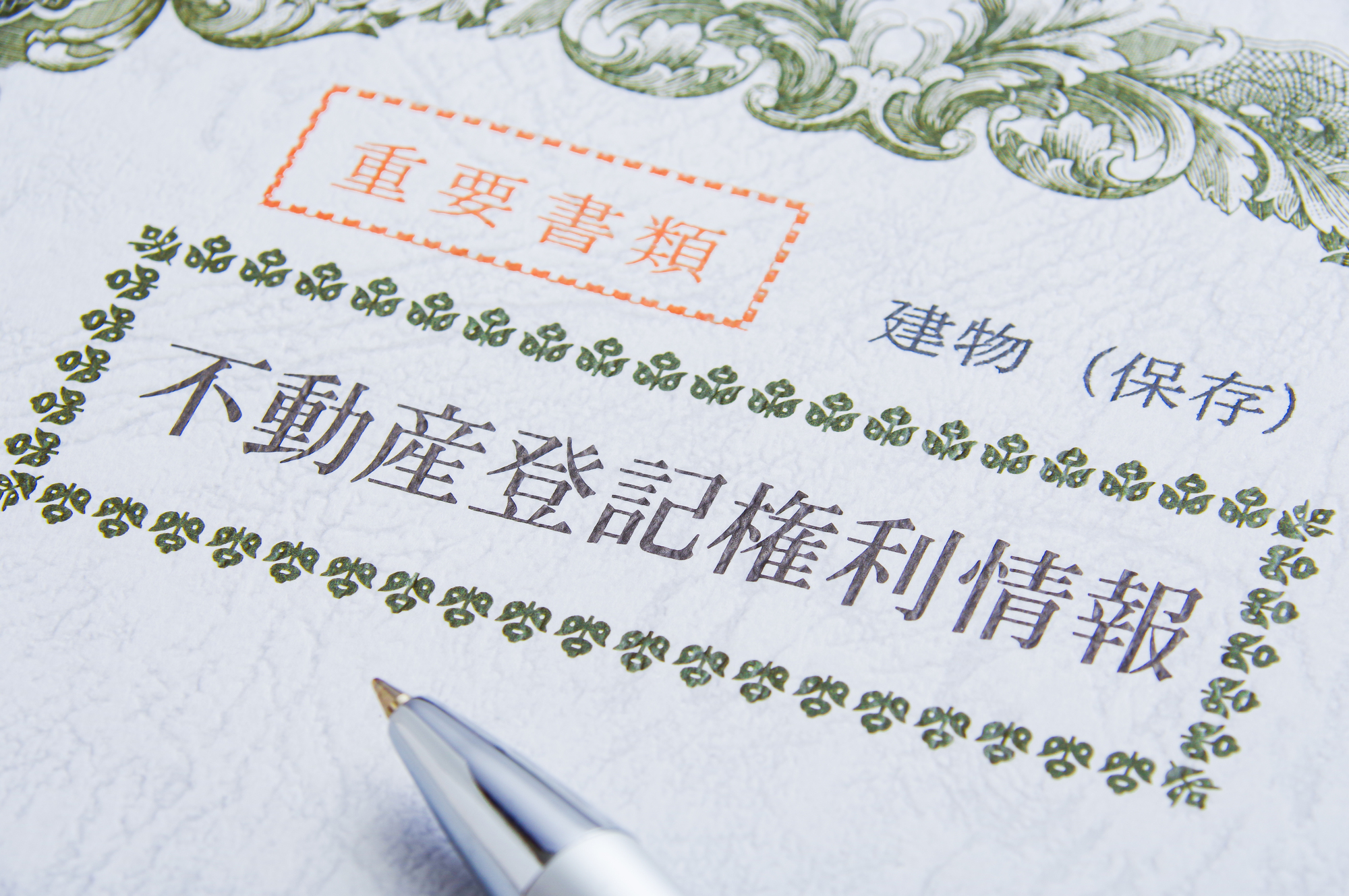公開日:2025.07.12 更新日:2025.08.12
相続放棄と空き家の管理義務を徹底解説〜2023年の法改正にも対応〜

空き家や借金を引き継ぎたくない…そういった理由から深く考えずに相続放棄を進めてしまうと、想像以上のリスクやトラブルにつながることも。特に、2023年の民法改正により、保存義務をめぐる管理責任が明確に規定されました。この記事では、相続放棄の基本から空き家に関する管理義務、さらに国庫帰属制度まで、将来の相続や不動産管理に不安を感じている方に向けてわかりやすく解説します。
目次
空き家の相続放棄とは?知っておきたい基本知識

実家を相続したけれど、管理や費用の負担が重くて頭を抱えている…そんなときに検討されるのが「相続放棄」という選択肢です。相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を一切相続しないことを家庭裁判所に申述する手続きです。対象となるのは現金や不動産だけでなく、借金や未払い金なども含まれます。
つまりこの手続きを通じて、老朽化した空き家の管理義務や占有責任、不動産の売却準備にかかる費用負担など、マイナスの負債を避けられる場合があります。
ただし相続放棄が認められると、預貯金や土地といったプラスの相続財産もすべて放棄することになります。思い入れのある実家や将来的に活用できる土地でも、一度放棄すれば自分のものにはできないため、しっかり検討することが大切です。
相続放棄の基本的な手順と注意点
相続放棄をするには、「被相続人が亡くなったことを知った日から原則3ヵ月以内」に、家庭裁判へ申し立てをする必要があります。
この「3ヵ月以内」という期限は、民法第915条「相続の承認または放棄の期間」に基づきます。 期限を過ぎてしまうと相続を承認したとみなされ、基本的に放棄は認められません。
また手続きには、被相続人の戸籍謄本、自分(相続人)の戸籍謄本、相続放棄申述書などの書類が必要です。書類の不備や記載ミスがあると手続きが遅れ、期限に間に合わないリスクもあります。
空き家が遠方にある場合や、財産の構成が複雑なときは、特に迅速な対応が重要です。
相続放棄を選択するメリットは?
相続放棄の最大のメリットは、借金や管理にかかる費用・責任を一切引き継がなくてよいという点です。
たとえば、売却も管理もできない空き家、今後も活用予定のない不動産、相続人間でトラブルが起きているといった状況下では、有効な手段となります。
また、もし親が借金を抱えていた場合でも、その返済義務から解放されます。多額の借金があり、将来の負担を手放したい…という場合にもメリットがあるでしょう。
相続放棄を選択するデメリットも
一方で、相続放棄を選択するデメリットは、預貯金・土地・建物といったプラスの財産も受け取れなくなることです。
たとえば、預貯金や収益化できそうな土地、思い出のつまった不動産なども含まれます。あとになって、やっぱり相続しておけばよかったと思っても、原則として取り戻すことはできません。
収益化できそうな土地が含まれている…遺言書に特別な指示がある…というケースでは、放棄以外の方法も慎重に検討する必要があります。
空き家の相続放棄で問題となる管理義務

相続放棄を選んだとしても、空き家の管理責任が一時的に残るケースもあります。すぐにすべての負担から解放されるわけではないことも覚えておきましょう。ここからは、2023年の法改正もふまえて、相続放棄後に求められる管理義務について解説します。
相続放棄後も管理責任が残るって本当?
相続放棄の手続きを家庭裁判所で終えたとしても、空き家に遺品が残っていたり、実家の鍵を持っていたりして実質的に占有している状態であれば、その空き家を完全に放っておくことはできません。
老朽化によって屋根が崩れ近隣に損害を与えた場合、民法709条・940条に基づく損害賠償責任を問われる可能性があります。 相続人ではなくても損害賠償を求められるリスクもあります。
つまり「相続しない=完全に手放せる」ではありません。放棄後も最低限の管理をする必要があることを忘れないようにしましょう。
相続人すべてが放棄した場合はどうなる?
もし相続人全員が放棄を選んだ場合、空き家を含む財産の行き先は国庫へ帰属する可能性があります。ただし、すぐに国が引き取るわけではありません。
その間に、実際に空き家や土地を誰かが占有していれば、その人に保存義務が発生します。また、家庭裁判所が相続財産管理人や清算人を選任して、空き家を売却したり処分したりすることもあり、それまでは管理責任が残るのです。
相続人がいないから放置でいいと考えていると、周囲の安全や景観を損なうことによる行政指導や近隣トラブルにつながるリスクも。公共の安全面からも、早めの相談や手続きが必要不可欠です。
2023年法改正で「保存義務」に変わった管理義務
2023年4月1日施行の改正民法第940条により、相続放棄後も保存義務が明記されました。これは『相続する意思があるかどうかにかかわらず、現に建物を占有している場合、最低限の管理をする責任がある』という意味合いがあります。
この制度は、法定単純承認(うっかり財産を使ってしまうことで相続を認めたとみなされるケース)とは異なり、放棄の意思に関係なく課される義務です。
もし相続人がいない、全員放棄しているといったケースでは、早めに相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることが、安全で確実な対応につながるでしょう。
「相続財産清算人」で管理の責任を手放す方法
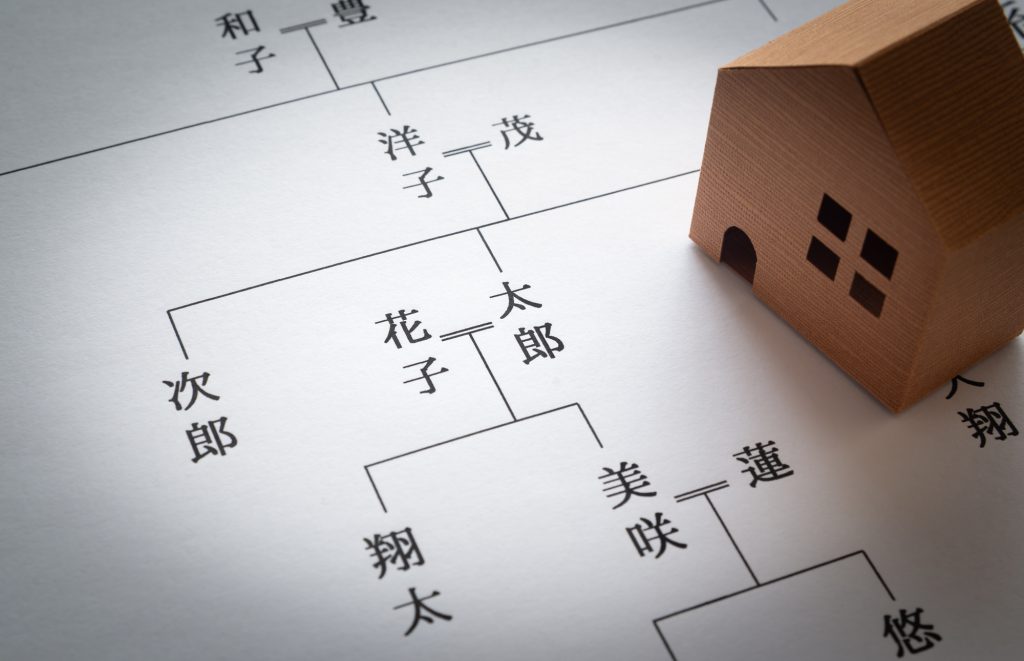
空き家の相続問題にもう関わりたくない…責任だけが残るのは不安…。そんな状況から抜け出すために検討したいのが、「相続財産清算人」の選任という方法です。
これは、相続人全員が放棄した相続財産を整理したり処分したりするために、家庭裁判所が選任する専門の第三者のこと。言い換えれば、お手上げ状態のときにバトンをわたせる心強い代理人といえるでしょう。
相続財産清算人と相続財産管理人の違いとは?
よく似た言葉に相続財産管理人があります。相続財産清算人も相続財産管理人も、家庭裁判所が選ぶ財産の管理者ですが、役割は異なります。
<相続財産管理人>
相続人が不明または不在のときに、財産を一時的に守る役割。主に財産の保全や債務の調査が中心で、積極的な処分までは行いません。
<相続財産清算人>
相続人が全員放棄したときに、残した空き家や土地などを整理・処分する役割。空き家を売却したり、解体したり、債権者への支払いを行ったりと、最終的な清算までを任される立場です。
空き家を売却したり、最終的に国庫に帰属させたりするには、相続財産清算人の存在が欠かせないケースが多くあります。
相続財産清算人を選任するには?手続きと費用について
相続財産清算人の選定は、近隣住民や債権者などの利害関係人や検察官が、家庭裁判所への申し立てをすることから始まります。このとき、被相続人の戸籍や財産目録、相続人全員が相続放棄したことを証明する書類が必要です。
一般的には、弁護士や司法書士といった法律のプロが清算人として担当するケースが多く、その手続きには数千円程度の申し立て手数料のほか、清算人の報酬や事務費用などに充てられる数十万円の予納金が求められるでしょう。
決して安いとは言えませんが、空き家の管理責任から解放され、のちのちの相続トラブルや損害賠償のリスクを避けられるというメリットがあります。
清算人が選ばれたあとの空き家処分の流れは?
清算人が選任されると、その空き家の処分は専門家の手で段階的に進められていきます。
相続財産清算人はまず、残された遺産の内容や債務を確認したうえで、必要に応じて空き家の売却や解体などの対応を検討します。売却の難易度が高い物件であれば、不動産会社などを通して売りだしたり、老朽化が激しく市場価値が低い物件であれば、解体して更地にするケースも。
それでも処分が難しいときには、国庫に帰属させるなど、家庭裁判所の監督のもと法律に基づいた対応が取られます。
2023年施行の相続土地国庫帰属制度とは
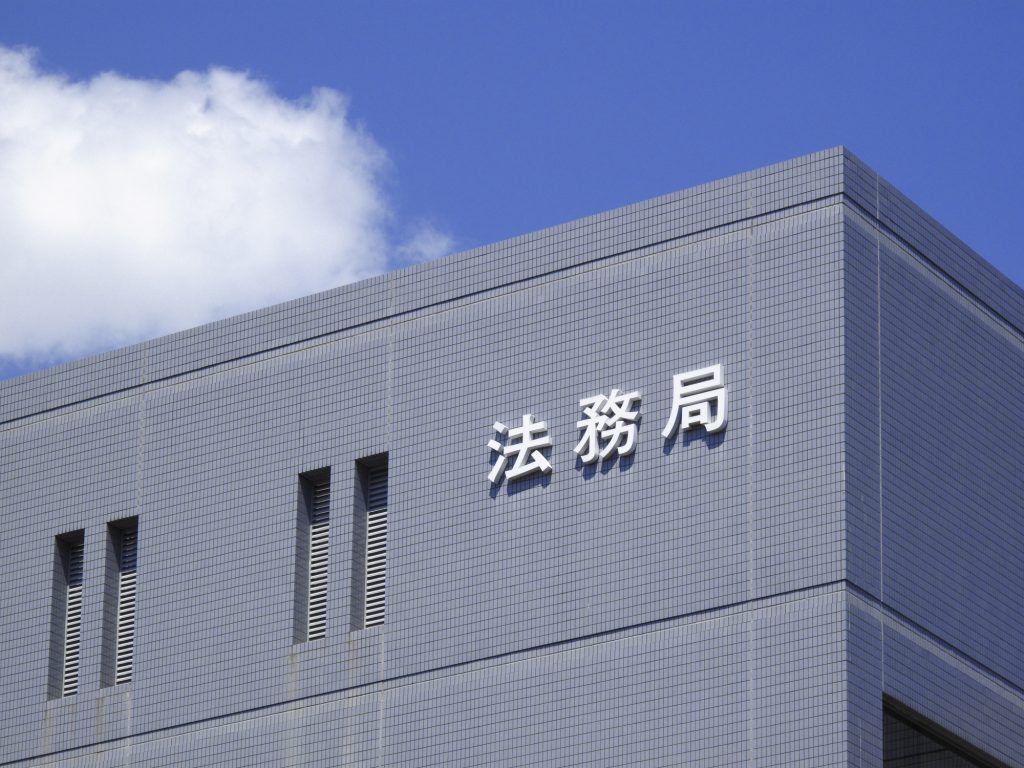
相続したけれど、活用の見込みがない土地がある…そんなお悩みを抱えている方にとって、2023年にスタートした相続土地国庫帰属制度は、現実的な選択肢のひとつかもしれません。
この制度は、不要な土地の管理責任や費用負担から相続人を解放し、一定の条件のもとで国庫に帰属させることができる仕組みです。活用すれば、相続放棄とは違い土地だけを手放すことができます。
相続土地国庫帰属制度の条件
ただしこの制度は、遠方の山林や使われていない宅地などが対象になりますが、どんな土地でも国に引き取ってもらえるわけではありません。
たとえば、アスベストを含む建物や大規模な造成が必要だったり、土壌汚染や危険物ある土地など公共の安全に影響を及ぼすおそれがあったりする場合は対象外です。また、申請には法務局への手続きや審査費用がかかるうえに、必ずしも国庫に帰属できるとは限りません。
とはいえ、空き家や使われない土地を放置するよりも、制度を利用することのほうが、将来的なトラブルを回避しやすいといえます。
国庫帰属制度を利用するメリット・デメリット
この制度を活用する最大のメリットは、相続人が土地の管理や相続税、固定資産税といった費用から解放されることです。また、空き家を手放すことで、管理リスクや遺産分割トラブルも回避しやすくなるでしょう。
一方で、古い家が建っている場合は、その解体費用は自己負担となります。そのほか、審査手数料や調査費用なども発生することが考えられるため、手放したいと思っても、かえって管理責任や費用が膨らんでしまうケースもあります。
国庫帰属制度を使うかどうかは、土地の条件と自分の状況をしっかり見極めることが大切です。
相続放棄と国庫帰属制度の違いとは?
借金や不動産などを含めた遺産すべてを引き継がず、相続人としての立場そのものを失う法的手続きが相続放棄。それに対して国庫帰属制度は、すでに相続した土地だけを対象に国に引き取ってもらう制度です。また申請窓口もそれぞれ異なります。
相続放棄
・借金ごと遺産を全部放棄したい
・手続きは家庭裁判所
国庫帰属制度
・家やお金は受け取り土地だけ手放したい
・手続きは法務局
共通していえるのは、どちらにも手続き費用や時間がかかること。それぞれのメリット・デメリットを理解し、将来的なリスクを総合的に検討しながら自分のケースに合った方法を選びましょう。
空き家を放置した場合に考えられるリスク

相続した空き家をそのまま放置していると、思わぬ責任やトラブルを招く可能性も。ここでは、空き家を放置した場合にどんなトラブルや費用負担が生じるか、代表的な3つのリスクをわかりやすくご紹介します。
倒壊などによる損害賠償責任が発生するリスク
相続した空き家の築年数が古く、雨漏りやひび割れがあるような家は、強風や地震などで簡単に倒壊するおそれがあります。
隣家の車や通行人に被害を与えた場合、民法940条(相続財産の保存義務)に基づき、たとえ相続放棄していたとしても、実質的に管理・占有していた場合には、保存行為を怠ったとして損害賠償責任を問われることがあります。
「特定空き家」指定による行政代執行のリスク
長く手入れをしていない空き家が景観を損ねたり、衛生上の問題を引き起こしたりすると、自治体から「特定空き家」に指定されるリスクがあります。
この指定を受けると、行政から改善指導や勧告、命令が下されます。それでも放置した場合は、最終的に行政代執行というかたちで強制的に空き家の解体を進められてしまうことも。
その費用は所有者や実質的な管理者に請求され、数百万円にものぼる経済的負担が発生するケースもあります。
他の相続人や近隣とのトラブルが起きる可能性
遺産分割協議が済んでおらず、相続の話し合いが不十分なまま空き家を放置すると、誰が管理するの?解体の費用はどうするの?といったことで、相続人同士の関係がぎくしゃくしてしまうことも少なくありません。
また、空き家がゴミの不法投棄場所になったり、害虫や雑草で近隣に迷惑をかけたりすれば、近隣住民から苦情が寄せられることも。場合によっては、地域全体で問題視されて自治体に通報されるなど、人間関係のトラブルに発展することも考えられるでしょう。
相続放棄後にも関わる費用・税金とは

相続放棄をしても完全に費用負担から逃れられるとは限りません。その土地や建物を引き続き使っていたり、管理していたと見なされたりすると、思わぬ税金や費用が発生するケースがあります。
相続人が全員放棄した場合でも、放置され老朽化が進んだ空き家には補修や解体といったコストがついてまわるため、どのように処分するかを考えておかなければなりません。
空き家の固定資産税・都市計画税について
自治体は相続放棄の手続き状況まで自動的に把握しているわけではありません。相続放棄をしても、名義変更されないまま土地や建物を占有・使用していると、固定資産税や都市計画税の請求が続くことがあります。
必要に応じて相続放棄した事実を証明できる書類(家庭裁判所の受理証明など)を税務署や市区町村に提出して、状況を伝えることが必要です。
老朽化に伴う解体費・補修費用の負担
屋根や外壁が崩れかけている状態の空き家は、危険を回避するために解体や補修が求められるケースがあります。相続放棄をしたとしても、もし近隣へ被害を加えてしまった場合は、民法940条の保存義務に基づき賠償責任に問われる可能性があります。
放棄したから関係ないと言い切れないというリスクも踏まえて、相続財産清算人の選任や相続土地国庫帰属制度などを検討し、明確な処分方針を立てておくことが重要です。
相続放棄の手続きを行う際の注意点と手順

親が亡くなったけれど借金があって抱えきれない…。遠方の空き家を相続しても管理が大変…。そんなときの選択肢が相続放棄。ただし、手続きの期限や他の相続人への影響、管理責任の残り方など、見落としやすいポイントがあるため、慎重な判断と準備が必要です。
相続放棄は3カ月以内に行う必要がある
相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
この『知った日』というのは人によって異なります。遺品の整理や葬儀の対応に追われているうちに、あっという間に期限が過ぎてしまった…といったミスを避けるために、まずはいつから3カ月がカウントされ、起算日がいつなのかを把握しましょう。
この期限を過ぎてしまうと、借金や不動産など、すべての相続財産を承継しなければならないリスクが発生するため注意が必要です。
放棄を撤回できるケースとリスク
相続放棄をしたけれど、やっぱり撤回したいと思うことがあるかもしれませんが、相続放棄は原則として一度申し立てると撤回することはできません。
例外として、詐欺や脅迫などにより誤って放棄の判断をしてしまった場合には、家庭裁判所の判断で撤回が認められることもあります。ただしこれは非常に限られたケース。
仮に撤回が認められたとしても、他の相続人との関係がこじれる可能性や、法的な手続きが複雑化するリスクがあることを理解しておきましょう。
他の相続人へ与える影響と事前連絡の重要性
相続は財産の分け方だけでなく、家族や親族との関係性も大きく左右する繊細な問題です。自分には関係ないと思って安易に相続放棄の判断をしてしまうと、他の相続人に大きな影響を与えてしまうことも。
たとえば、兄弟姉妹や甥姪など相続の権利と同時に、空き家の管理責任や固定資産税の支払いなどがのしかかる可能性があります。相続放棄を考えている段階で、他の相続人としっかり情報共有をしておくことで、そういったトラブルを避けることができるでしょう。
専門家への相談が必要になる場面とそのメリット
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申し立てれば終わりではありません。実際には、放棄の判断そのものから遺産の全容把握、税金の対応、不動産の管理責任まで、さまざまな課題が絡みます。
特に2023年以降は、相続土地国庫帰属制度も加わりました。判断が難しい場合は、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することで、正確な対応ができるうえに、余計な費用やトラブルを避けることができるメリットがあります。
まとめ|相続放棄=解決ではない、空き家管理のリスクにご用心
空き家を相続するか放棄するか。その判断は、私たち自身の今後の生活にも大きく影響します。相続放棄すれば空き家のことは関係ないではなく、その後もトラブルや費用の負担が続くケースがあります。2023年の法改正で保存義務というルールもはっきりしたことで、近所に迷惑をかけて損害賠償が発生したり、特定空き家に指定されて強制的に解体されたりするリスクもあるでしょう。
その打開策として、相続財産清算人を立てる方法や相続土地国庫帰属制度を使って国に引き取ってもらうという選択肢もあります。まずは自分の状況を整理して、家族や親族とも話し合いながら、できるだけ早い段階で弁護士や専門家に相談することが大切です。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。