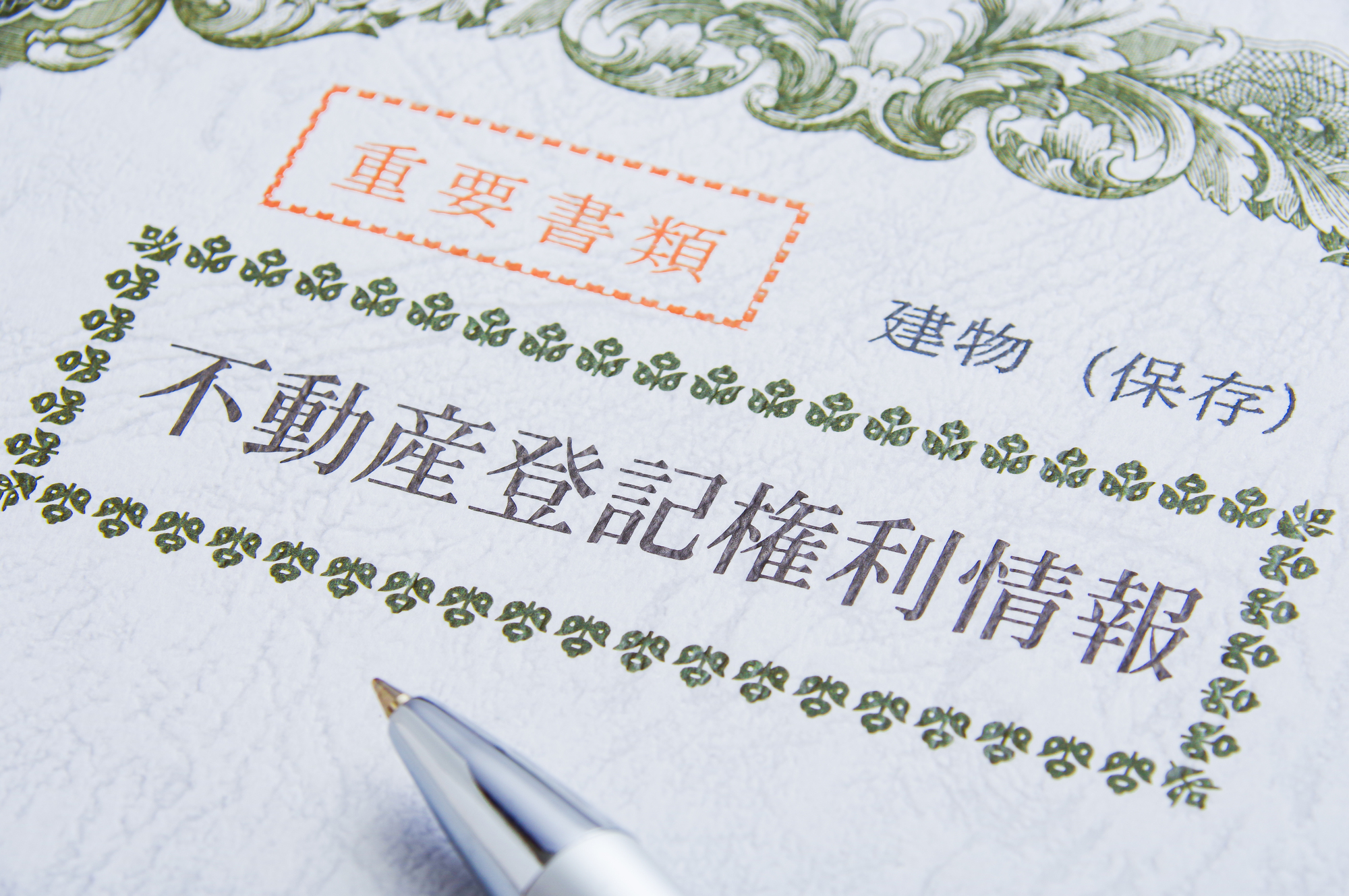公開日:2025.09.06 更新日:2025.08.04
不動産売買と認知症の親|成年後見制度や家族信託など徹底解説

親が認知症を患っている場合、不動産売買の手続きが難しくなると聞いたことがある人は多いと思います。実際に不動産売買を成立させるには、所有者の意思能力が十分であることが求められるので、認知症の場合はそもそも契約自体が難しくなることがあるのです。
では、具体的にはどのような状態だと契約ができなくなるのでしょうか?この記事では、認知症の進行状況に応じた不動産売買の可否や、対応策である成年後見制度や家族信託などを活用するためのポイントを網羅的に解説します。
目次
認知症になると不動産売買が難しくなる理由

認知症を発症すると不動産売買が難しくなる理由は、民法において、法律行為を行う当事者が自ら理解や判断をするに足る意思能力を有していなかった場合、その法律行為が無効になるためです。
つまり、不動産売買の契約を結んだとしても、認知症によって意思能力がなかったと判断されれば、契約が白紙に戻る可能性があるのです。
これは、認知症の人を守る観点でも大切なことです。中には認知症であることを利用して、自分に都合のよい条件で不動産を買おうとする人もいます。親や祖父母の認知症が疑われた場合は、早めに医師の診断を受けて認知症であることを明らかにし、不動産売買に関するリスクを減らしておいた方がよいでしょう。
売買契約に必要な意思能力とは
民法上の「意思能力」を具体的に説明すると、自ら法律行為の意味や結果を理解し、判断できる精神的能力を指します。不動産売買契約においては、契約内容(物件の売却目的・価格・条件など)を正しく認識し、合理的に判断・同意できる状態であることが求められます。
なお、契約の有効・無効が争われた場合は、裁判所が契約当時の本人の状態を勘案して意思能力の有無を判断することになります。
認知症になるとすべての契約が無効になる?
認知症を発症していても、必ずすべての不動産売買契約が無効になるわけではありません。症状が軽度で意思能力があると判断されれば、契約は有効と認められる可能性もあります。
契約が無効になる恐れが大きいのは、契約の仕組みや内容の理解が難しい中度~重度に進行した場合です。
気を付けたいのが、他者から見た本人の様子と実際の本人の状態に差があるケースです。一見しっかりしているように見えても、実際は思ったよりも認知症が進行している場合もあります。もし不動産売買の話が出た場合は、まず病院で認知症の進行度をチェックしてもらいましょう。
認知症の親の不動産売買を巡る主なトラブル事例

認知症の親の不動産売買をする場合、特に気を付けたいのが以下の2点です。
- 売却できず介護費用を捻出できなくなる
- 第三者から不正な取引・契約を持ち掛けられる
どちらも大きなリスクがあるため、絶対に避けたいことです。では、どのように対策をすればよいのか、それぞれ詳しく見ていきましょう。
第三者から不正な取引や契約を持ち掛けられる
認知症の高齢者は、詐欺師や悪質な不動産業者などから不利な条件の契約を結ばされる恐れが高まります。特に家族と離れて暮らしている場合は要注意です。
中には「地面師詐欺」という不動産そのものを標的にした手口もあります。地面師とは、他人の土地を勝手に売却する詐欺師のことで、偽造書類を用いて所有者になりすまし、第三者と売買契約を勝手に結ぶことで現金を手に入れます。特に、認知症の高齢者が所有している物件や長年放置している物件は狙われやすい傾向にあります。
これらの契約の無効を主張するには、裁判所を通じた法的手続きが必要になります。手続きには多くの時間と費用がかかり、家族に精神的な負担を強いることになります。
売却できず介護費用を捻出できなくなる
親の意思能力が疑わしい場合は、本人による売却ができないのはもちろん、家族が代理で売却することもできません。そうなると、家を売却できなくなり、介護費用のあてがなくなってしまう恐れがあります。
このような場合は、第三者が財産管理や契約行為などのサポートや代理を行う「成年後見制度」を利用する必要があります。ただ、実際に制度を利用するためには、手続きに2~3か月かかることもあるので、実際に売却できるまで時間がかかる可能性があります。
では、成年後見制度はどのような制度で、どんな手順を踏んで利用するのか、次の見出しで詳しく見ていきましょう。
成年後見制度とは?基本からメリット・デメリットまで

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になった場合に家庭裁判所に申し立てを行って「成年後見人」を選出し、本人に代わって法律行為(意思能力が必要な行為)を行えるようにする制度です。
本人の状態に応じて、支援の範囲が異なる「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。
たとえば親が認知症を発症して不動産の売却が難しくなった場合は、成年後見人が本人に代わって契約や財産管理を行うことになります。
なお、制度開始後は本人が単独で契約することが原則としてできなくなりますので、成年後見人の選出は、本人との関係や住んでいる場所などを踏まえたうえで考えましょう。
法定後見制度と任意後見制度の違い
成年後見制度は、発症のタイミングや本人の判断能力の有無によって「法定後見制度」と「任意後見制度」に分かれます。
まず法定後見制度は、認知症などで判断能力が不十分になったあとに家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
一方で、任意後見制度は、本人の判断能力がまだ十分ある段階で、将来に備えて後見人となる人と公正証書で契約を結ぶ制度です。将来的に判断能力が低下した際に、あらかじめ指定しておいた任意後見人が支援を開始できるため、柔軟性があり、本人の意思を反映させやすい仕組みとなっています。
なお、両制度は権限が一部異なっており、法定後見制度では本人の行為能力が制限され、本人自身が締結した契約について後見人が取り消すことができる一方で、任意後見制度では本人が締結した契約は取り消せなくなっています。
成年後見人ができること・できないこと
成年後見人は、家庭裁判所からの審判を受けて選任されると、本人(被後見人)に代わって財産管理や契約の代理行為を行う法的権限を持ちます。たとえば、不動産の売買や賃貸契約、預貯金の管理、介護施設への入所契約などが挙げられます。
ただし、遺言の作成や婚姻・離婚といった身分に関する行為は本人の意思が不可欠であるため、成年後見人が代理することはできません。また、後見人の行為はすべて家庭裁判所の監督下に置かれ、財産管理状況の報告義務が課されます。
なお、後見人といえども、本人の生活の希望や価値観を無視して動くことはできません。制度の趣旨は「本人の意思の尊重」にあり、本人にとって最善の利益を第一に考えて行動する義務があります。
成年後見制度の利用時の必要書類と費用

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。申し立てに必要な書類と費用は以下のとおりです。
必要書類
- 収入印紙(申立手数料)
- 郵便切手
- 収入印紙(登記用)
- 鑑定費用の余剰金を返金するための申立人名義の口座情報
- 本人の戸籍謄本(全部事項証明書/発行から3か月以内のもの)
- 住民票又は戸籍附票
- 後見・保佐・補助開始等申立書
- 申立事情説明書、親族関係図、親族の意見書、後見人等候補者事情説明書
- 本人が後見登記されていないことの証明書(法務局で取得/発行から3か月以内のもの)
- 診断書(発行から3か月以内のもの)
- 本人情報シートの写し(主に病院で取得)
- 本人の財産目録(後見開始又は保佐・補助開始で代理権をつける場合)
- 本人の収支予定表(後見開始又は保佐・補助開始で代理権をつける場合)
- 本人の健康状態に関する資料(介護保険被保険者証、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳などの写し)
手続きにかかる費用
- 申立手数料 800円
- 登記費用 2,600円
- 住民票取得費用 数百円(1部)
- 戸籍謄本取得費用 数百円(1部)
- 医師による鑑定料 10万~20万円程度
- 医師の診断書作成料 数千~1万円程度
- 郵送料(裁判所に確認)
- 専門家への依頼料(司法書士・弁護士) 10万~30万円程度
手続きには通常2〜3か月程度かかり、その間に家庭裁判所からの照会や調査官の面接が行われることがあります。また、家を売却する場合は必要に応じて「居住用不動産処分の許可の申し立て」を別途行います。
成年後見制度を利用するリスクと注意点
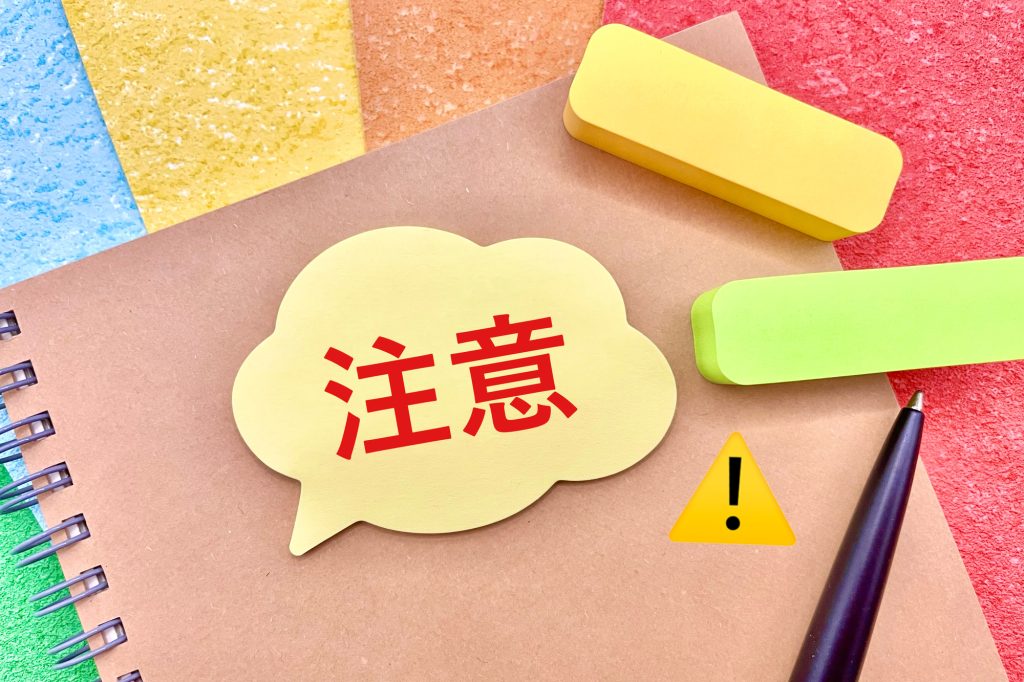
成年後見制度のもっとも大きな制約は、制度開始後に本人の法律行為が制限されることです。原則として、自分で契約や不動産売却などができなくなるので、人によっては「自由が奪われた」と感じるかもしれません。
また、成年後見人は家庭裁判所の監督下に置かれ、財産管理に関する報告義務や帳簿の作成などを定期的に求められるため、実務的な負担が発生します。
なお、一度制度を開始すると、本人の判断能力が回復した場合を除き、原則として終了や変更はできません。制度を利用する際にはこれらのリスクを踏まえたうえで、可能な限り本人の意志を尊重しながら進めましょう。
家族信託や生前贈与で早めに対策する方法
親が認知症になった場合の別の対策として、本人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産管理を任せる「家族信託」や、判断能力があるうちに財産を子どもに名義変更しておく「生前贈与」を活用する方法があります。
ここではそれぞれの仕組みや活用法、メリットなどを解説します。
家族信託の仕組みと活用で得られるメリット
家族信託は、財産の所有者(委託者)が受託者(主に子などの家族)に管理・処分権限を与える契約です。
家族信託のメリットは、認知症になる前に契約を結んでおくことで、認知症発症後も以前と同じように不動産を管理し続けられることです。また、家庭裁判所の監督が不要な点や、本人の意向をあらかじめ反映しやすい点も大きなメリットといえます。
ただし、契約内容が曖昧だと将来的に親族間でトラブルになるリスクがあるため、信託契約書には、信託の目的、財産の範囲、受益者の指定、終了条件などを明確に記載しましょう。
生前贈与の仕組みと活用で得られるメリット
生前贈与は、本人が亡くなる前に財産を子や孫などに贈与することをいいます。相続税対策として用いられることが多いですが、認知症のリスク回避にも使える方法です。たとえば、所有する不動産を子に贈与しておけば、認知症発症後も管理や売却が可能になります。
生前贈与の注意点は、贈与税や相続税の課税対象になる可能性があることです。原則として「年110万円の非課税枠」を超えた贈与は贈与税の対象になります。贈与税を回避する方法として、2,500万円までの贈与を非課税にして、相続時に相続税を課税しなおす「相続時精算課税制度」がありますが、どちらにせよ税負担がかかることは把握しておきましょう。
成年後見制度を活用した不動産売却の流れ

成年後見制度を利用した不動産売却は、以下の4ステップで進めていきます。
- 1.家庭裁判所への申立と後見人の選任
- 2.売却許可の申立と許可取得
- 3.査定依頼・媒介契約締結と販売活動
- 4.買主との売買契約から決済・引き渡しまで
この一連の手続きは、家庭裁判所の監督下で進められ、完了までに2〜3か月程度かかります。それぞれのステップを詳しく見ていきましょう。
1. 家庭裁判所への申立と後見人の選任
まずは成年後見人を選任するために家庭裁判所に申し立てを行います。成年後見人になれるのは、配偶者や子などの親族が多いですが、必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人候補者として申し立てをすることも可能です。また、申立人が親族以外の場合、例えば自治体職員が申し立てるケースもあります。
申し立てから選任までには、通常2〜3か月程度かかります。売却を急ぐ場合でもこの期間は避けられないため、早めに準備を進めましょう。
2. 売却許可の申立と許可取得
後見人が選任されたあとは、家を売却するために別途「居住用不動産処分の許可の申し立て」が必要です。本人の住居は生活基盤に関わる重要財産であるため、裁判所が厳格に審査を行います。
申立書には、申し立ての理由や本人の同意の有無、今後の居住場所などを記載し、不動産の全部事項証明書や不動産売買契約書の案、処分する不動産の評価証明書、不動産業者作成の査定書などを添付します。
3. 査定依頼・媒介契約締結と販売活動
売却許可の見込みが立ったら、不動産会社に査定を依頼し、媒介契約を締結します。このとき、後見人は手数料や販売価格、販売期間などをよく確認し、本人に不利益がないことを確認しましょう。
媒介契約を締結したら、内覧対応・価格交渉・広告などの販売活動に移ります。交渉や売買契約の締結は後見人が主導して行います。
4. 買主との売買契約から決済・引き渡しまで
買い手が見つかり条件が合意に至ったら、売買契約書を締結し、手付金の受領や残代金の決済、所有権移転登記を経て引き渡しを行います。
このとき、契約書には家庭裁判所による売却の許可を停止条件(または解除条件)とする特約を盛り込んでおきましょう。これにより、家庭裁判所から許可が出なかった場合に契約が無効となります。
売却代金は後見人が後見財産として適切に管理し、介護費や生活費などに充てます。売却後も後見人の職務は継続し、使途の記録保存や定期的な家庭裁判所への報告義務が発生します。
まとめ:認知症対策は早めに行い、制度を正しく活用しよう
不動産の持ち主である親が認知症になった場合は、まず本人の意思能力を確認し、成年後見制度をはじめとする各種制度の活用を検討しましょう。手続きの間にも認知症が進行する可能性があるので、なるべく速やかに行うのがポイントです。
また、現在認知症で無い場合でも、計画的に相続を進める必要があるのなら、あらかじめ準備を始めてきましょう。いざというときに慌てることのないよう、家族で将来の方向性を話し合うことが、認知症対策の第一歩です。
この記事の監修者

山下 航平 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
ハウスメーカーにて戸建住宅の新築やリフォームの営業・施工管理を経験後、アキサポでは不動産の売買や空き家再生事業を担当してきました。
現在は、地方の空き家問題という社会課題の解決に向けて、日々尽力しております。