公開日:2025.10.17 更新日:2025.09.26
不動産評価額の調べ方を徹底解説|基本から実践まで
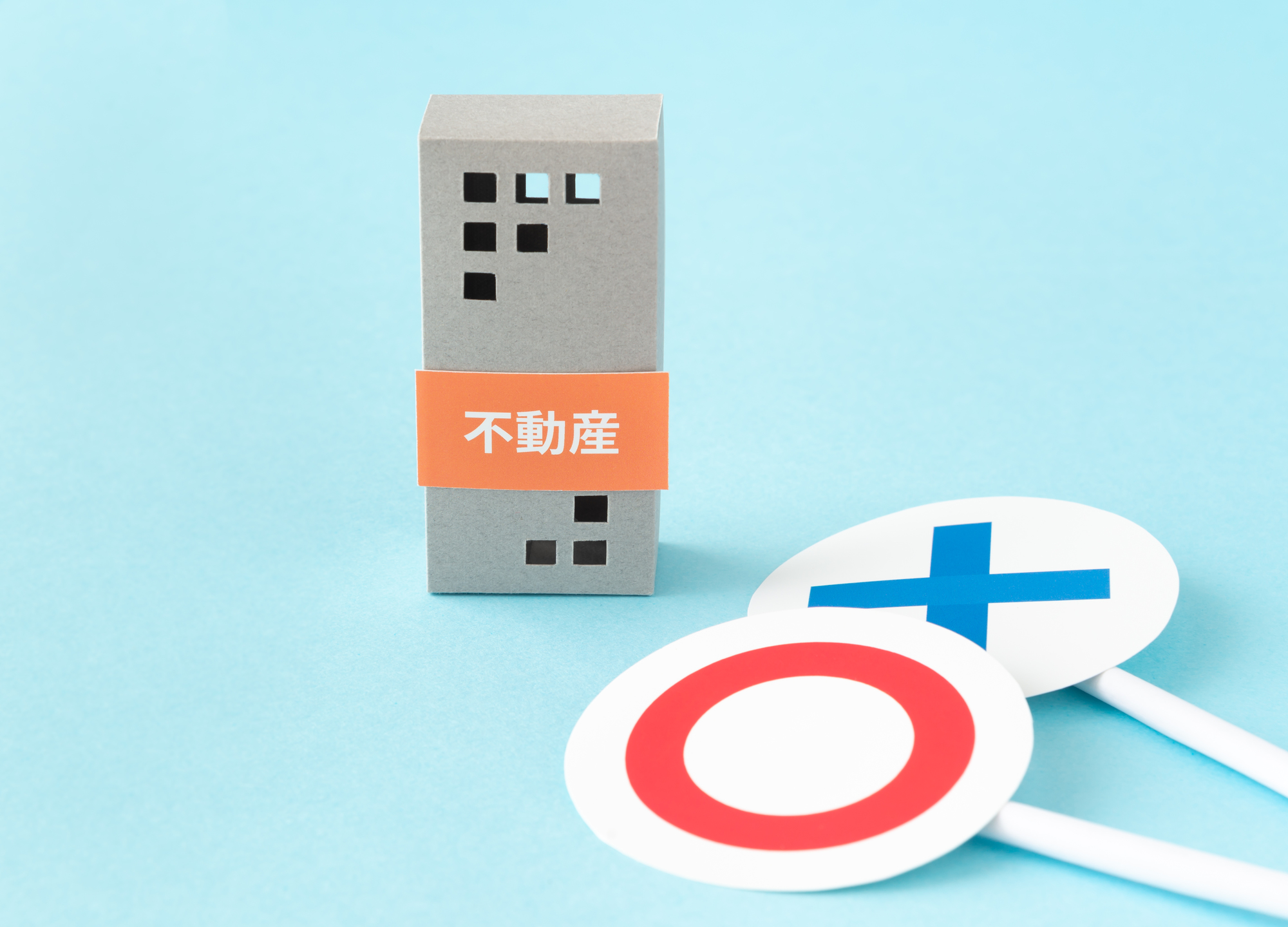
不動産評価額は、売却価格の目安や相続・贈与にかかる税金の計算などで欠かせない基準です。ただし不動産の「評価額」には、公示価格や路線価、固定資産税評価額など複数の種類が存在するため、それらの違いを正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、不動産評価額の基本知識から具体的な調べ方、税制上のポイントや評価額を下げるための工夫まで網羅的に解説します。
目次
不動産評価額とは?まずは基本を押さえよう

不動産の売却や相続、税金の算定など、あらゆるシーンで欠かせない基準となる不動産評価額。土地や建物の種類、立地条件、利用目的によって基準が変わるため、まずはその全体像を理解することが大切です。ここでは、評価額の基本的な考え方と押さえておきたいポイントを整理します。
不動産評価額の意味と仕組み
不動産評価額とは、不動産にどれほどの価値があるかを数値で示したものです。土地や建物といった物件の種類、周辺環境や立地条件といった外的要因を総合的に踏まえて算出されます。
大きな特徴は、利用目的に応じて参考にする評価額が変わる点です。例えば相続税の計算には「相続税評価額」、固定資産税には「固定資産税評価額」、売買時には「実勢価格」など、それぞれ異なる基準が用いられます。
評価額が高ければ売却時に有利に働く一方で、固定資産税や相続税といった税負担が増える可能性があります。逆に評価額が低ければ税金面ではメリットがありますが、不動産担保ローンの審査では融資額が少なくなる場合もあります。不動産の担保価値は、一般的に融資額に直結するため、評価額が低いと、希望する融資額に満たない可能性を理解しておく必要があります。
つまり、評価額は高ければ良い、低ければ安心といった単純な話ではなく、自分が直面している状況や目的に応じて使い分けることが重要になります。
さらに、不動産評価額は誰が算定するかによっても差が出る点にも要注意。国や自治体、不動産鑑定士など、主体によって評価手法や基準が異なるため、同じ物件でも複数の評価額が存在することは珍しくありません。そのため、「どの場面で」「どの評価額を基準にするのか」を理解しておくことが、賢く不動産と付き合うために必要不可欠といえるでしょう。
不動産評価額が必要となる主なケース
不動産評価額の必要性が特に増す場面として代表的なのは、不動産を売却する場合です。適正な価格を設定するために評価額は欠かせません。
また、相続や贈与では税額計算の根拠となり、離婚時の財産分与など重要な指標になります。さらに、不動産を担保に金融機関から融資を受ける場合、銀行は評価額を審査材料として重視します。
このように、評価額は日常的な売買からライフイベントまで幅広く関係してきます。背景として、行政が課税のために算定する評価額と、市場の需給を反映した実勢価格との間に差がある点が挙げられます。
例えば、固定資産税評価額は実際の市場価格より低めに設定されるケースが一般的です。税務の観点だけでなく、実際に売却や購入を考える際には「どの評価額が使われているのか」を意識する必要があります。
実際に金銭が動く場面ほど、評価額の違いが大きな意味を持ちます。複数の評価手法を理解しておけば、不動産の価値をより正確に判断でき、自分に有利な選択が可能になります。評価額を「知る」だけでなく「使いこなす」ことが、資産を守るためには重要です。
不動産評価額の6つの種類と特徴

不動産の評価額には複数の種類があり、それぞれ用途や算定基準が異なります。売却や相続、税務対応など、状況によって参考にすべき評価額は変わるため、全体像を整理しておくことが大切です。ここでは代表的な6つの評価額と、その特徴について解説します。
1)実勢価格(時価)
実勢価格は時価とも呼ばれ、実際の売買事例をもとに推測される市場価格です。もっとも現実の取引に近い金額であり、売買の際に最終的な判断材料となるケースが多く見られます。インターネット上の不動産ポータルサイトや取引事例の公開情報を調べることで、周辺の相場をおおまかに把握することができます。
ただし、近隣の取引事例が自分の物件と同じ条件とは限りません。築年数やリフォーム履歴、日当たり、接道状況など細部は物件ごとに異なるため、正確な金額を知るにはプロの査定が必要です。
自分で相場をざっくり掴んだうえで複数の不動産会社に査定を依頼し、提示された金額を比較することが、より現実に即した実勢価格を知るためのコツです。
2)公示価格
公示価格は、国土交通省が毎年3月に公表する標準地の価格で、土地取引の指標として用いられます。公共事業での用地買収価格の算定根拠になるなど、公的な性格が強いのが特徴です。一般の売買においても参考基準とされ、信頼度の高いデータといえます。
公示価格と実際の取引価格は必ずしも一致しません。人気エリアや再開発地域では、実際の売買価格が公示価格を大きく上回ることもあります。それでも、国の機関が算定している点で信頼性が高く、地価の動向を確認するには有用な指標です。
インターネットで簡単に調べられるため、まずは自分の物件周辺の公示価格をチェックし、地域の相場感を掴むと良いでしょう。
3)基準地価
基準地価は、都道府県が毎年9月に公表する土地価格で、公示価格と並んで土地評価の代表的な指標です。公示価格が国の調査で1月1日時点の評価なのに対し、基準地価は7月1日基準の価格となるため、若干のタイムラグが生じます。
公示価格と基準地価の両方を確認することで、半年ごとの地価動向を把握できるメリットがあります。特に地価の変動が大きいエリアでは、どちらのデータも確認して総合的に判断したほうが実態を掴みやすくなるでしょう。
ただし、基準地価も指標地を基準にした数値であるため、個々の物件にそのまま当てはめられるわけではありません。実勢価格との差を考慮しながら、参考データとして活用しましょう。
4)固定資産税評価額
固定資産税評価額は、地方自治体が不動産に課税するために3年に一度の評価替えを中心に算出する金額です。一般的には実勢価格より低めに設定される傾向があり、納税通知書を見て思ったより安いと感じる人も少なくありません。
この評価額は、固定資産税や都市計画税といった毎年の税負担を決める重要な基準です。もし評価額に納得できない場合は、役所で課税台帳を閲覧して算定根拠を確認することが可能です。
必要に応じて再調査や修正を求めることもできます。税負担を左右する基準になるため、不明点がある場合は早めにチェックしましょう。
5)相続税評価額(路線価)
相続や贈与の際に必ず登場するのが、国税庁が毎年7月に発表する路線価図・評価倍率表を基準とした相続税評価額です。路線価とは、宅地が面している道路に付された1㎡あたりの価格を示し、相続税や贈与税の計算に使われます。
実勢価格との差はあるものの、税務においては欠かせない指標です。土地の形状や奥行き、角地や二面道路といった条件に応じて加減算されるため、同じ道路沿いでも評価額が異なることがあります。資産規模が大きい場合は評価額ひとつで税額に大きな差が出るため、正確な確認が不可欠です。
路線価を参考に自分の土地の評価額を把握し、必要に応じて税理士などの専門家に相談しながら節税策を検討すると安心です。
6)不動産鑑定評価額
不動産鑑定評価額は、不動産鑑定士という国家資格を持つ専門家が、多角的な調査を行って算定する価格です。不動産鑑定評価基準に基づき、公示価格や実勢価格のほか、物件特有の条件を加味して作成されるため、客観性と信頼性が非常に高い評価といえます。
売買や相続、さらには裁判・訴訟など、重要な場面で不動産の価値を示す資料として使われることが多く、公的な証拠力を持つことも特徴です。
鑑定には費用や時間がかかりますが、その分得られる安心感は大きいでしょう。特に大規模な不動産売買や投資判断を行う際には、鑑定評価を検討してみるのも有効です。
土地・建物別に見る不動産評価額の違い

不動産は土地と建物を一括で評価するのではなく、それぞれ別の基準で算定されます。
土地は立地条件や形状、周辺環境といった外部要因が価格に直結し、公示価格や基準地価、路線価などの公的データを参考に評価されるのが一般的です。
一方で建物は、築年数や構造、延床面積、設備のグレードなどが重要な判断基準となります。特に木造と鉄筋コンクリート造では耐用年数が異なり、経過年数による評価額の下がり方に差が出ます。
また建物は同じ広さでも、内装のリフォーム状況や耐震補強の有無、設備更新の有無によって価値が変動します。マンションであれば共用部分の管理状態や管理組合の体制が資産価値を左右します。
木造家屋とマンションの評価額のポイント
木造家屋は法定耐用年数が短いため、築年数が進むと急速に評価額が下がる傾向があります。定期的にリフォームを施しても、構造自体の寿命には限界があるため、固定資産税評価額や市場価格の低下を避けることは難しいのが現実です。特に築年数が20年を超えると、資産価値は大きく減少するケースが少なくありません。
一方でマンションは鉄筋コンクリート造が主流。耐用年数が長いのが特徴です。さらに管理組合による計画的な修繕や共用部分の維持管理が行われることで、建物全体の評価額が下がりにくい側面があります。その結果、建物全体の評価額が極端に下がりにくいこともあります。
ただし、マンション特有のリスクもあります。将来の大規模修繕に備えた積立金や管理組合の運営状況によっては、逆に資産価値が下がる場合もあるのです。戸建とマンションでは評価額に影響する要素が大きく異なるため、自分の物件の特徴を理解したうえで評価の見方を考えることが重要です。
不動産評価額を調べる5つの方法

不動産評価額を調べる方法はひとつではなく、自治体や国が公表するデータから、インターネットで手軽に調べる手段、専門家に依頼する方法までさまざま。ここでは代表的な5つの方法を紹介します。
方法1:固定資産税納税通知書・課税台帳を確認する
最も手軽な方法は、毎年送付される固定資産税の納税通知書を確認することです。通知書には土地と建物それぞれの評価額が記載されており、税金の算定基準が直感的に把握できます。さらに詳細を知りたい場合は、市区町村役場で課税台帳の閲覧や評価証明書を請求することも可能です。
方法2:公示地価・路線価をWeb上で調べる
国土交通省の地価公示サイトや国税庁の路線価公開ページを利用すれば、自宅周辺の地価をインターネットで簡単に確認できます。地価公示は地域全体の平均的な土地価格を示し、路線価は相続税や贈与税の算定に用いられる価格として位置づけられています。どちらも毎年更新されるため、最新の傾向をつかむのに有効です。
両方のデータを照らし合わせることで、市場での取引価格と税務上の評価額の差を推測することができます。ただし、路線価は土地の評価に特化しており、建物の評価は含まれません。建物の資産価値を含めて把握するには、別途築年数や構造、設備などの要素を考慮する必要があります。
方法3:不動産一括査定サイトを活用する
複数の不動産会社に一度で査定を依頼できるのが、一括査定サイトです。売却を検討している人や相場感を素早く知りたい人にとって便利な仕組みで、各社の査定額を比較できるメリットがあります。
各社の査定結果に差が出ることも少なくありませんが、これは不動産会社ごとの販売戦略や地域の捉え方が反映されているためです。複数の数字を並べて見れば、極端に高い、あるいは低い査定の背景を推測できるでしょう。
無料で利用できる点は魅力ですが、その後不動産会社からの営業連絡が増える可能性も理解しておきたいところです。売却意欲がある人には有効ですが、資産価値を正しく知りたいだけの場合は、専門家の鑑定も選択肢に入れると安心です。
方法4:売買事例比較法を用いて自力で推定する
国土交通省が公開する「不動産取引価格情報提供システム」を使えば、周辺で実際に行われた売買事例を調べられます。築年数や面積、駅からの距離など条件の近い物件を複数比較し、平均的な数値を出すことで、大まかな相場を自力で推定できます。
自分で調査するには時間と労力がかかりますが、相場を理解するうえで得るものは多いでしょう。その後の査定依頼や専門家との相談にも役立ちます。
しかし、まったく同じ条件の物件は存在しないため、あくまで「近い条件から相場をつかむ」という姿勢が大切です。また、土地の形状や境界条件といった詳細までは把握できないため、参考値として活用すると良いでしょう。
方法5:不動産会社や不動産鑑定士に依頼する
もっとも正確性の高い方法は、専門家に依頼することです。不動産会社の査定は無料で受けられる場合も多く、売却を前提に動きたい人にとっては有効です。
一方で、不動産鑑定士による評価は国家資格に基づき、法的効力や客観性を備えた信頼度の高い結果を得られます。費用はかかりますが、相続で多額の税金が発生する場合や企業間取引、大規模な不動産売買では特に有効です。
相続や贈与、財産分与での不動産評価額の活用ポイント

相続や贈与の場面では、不動産の評価額が税額や財産分与の公平性に直結します。相続税や贈与税は国税庁が公表する路線価を基準に算出されるため、評価額を正確に把握しているかどうかで納める税金が大きく変わることもあります。相続人が複数いる場合には、統一された評価額を根拠に話し合うことで納得感を得やすく、手続きがスムーズに進みます。
また、離婚時の財産分与においても不動産は大きな比重を占める資産です。評価をめぐって争いになることも珍しくありませんが、客観的な評価額を提示することで公平性を確保しやすくなります。その際には固定資産税評価額や路線価、実勢価格など複数の指標を参照し、バランスを取ることが望ましいでしょう。
相続税の申告・納付期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内と定められています。余裕を持って準備するためにも、事前に評価額を調べておきましょう。
小規模宅地特例や軽減制度を上手に活用する
相続税を軽減する有効な制度のひとつが「小規模宅地特例」です。これは一定の条件を満たすと、被相続人が居住していた宅地や事業用宅地などについて、評価額を大幅に減額できる制度です。特定居住用宅地等であれば、330㎡を限度として、評価額の80%が減額されます。結果として相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
ただし、適用には「相続開始直前に被相続人等の居住の用に供されていたこと」や「相続人がその宅地を相続税の申告期限まで引き続き保有し、居住していること」など厳しい要件が設けられています。
条件を満たさないと適用できないため、制度の内容を正しく理解し、ケースによっては税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。
配偶者の税額軽減や相続税の基礎控除など、ほかにも複数の優遇制度が存在します。いずれの制度を活用するにしても、不動産評価額をもとに計算されます。軽減制度を正しく適用するためにも、まずは評価額を正確に把握しましょう。
固定資産税・都市計画税算出に用いる評価額の読み解き方

評価額は建物の構造や築年数などを考慮して決められており、その違いが税額に直結します。ここでは、固定資産税評価基準に基づいて評価額がどう算定されるのか、納得できない場合の確認方法まで整理します。
建物構造や築年数による評価額の違い
固定資産税評価額は、同じ延床面積でも建物の構造や築年数によって大きく変わります。木造住宅は法定耐用年数が短く、早い段階から評価額が下がりやすいのが特徴です。
一方、鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨造は耐用年数が長く、築浅の時期は高めの評価額を維持しやすい傾向があります。
また、大規模リフォームや増改築を行った場合は、設備や構造が改善されることで評価額が上がるケースも見られます。こうした評価は課税額に直結するため、内容が正しく反映されているかどうかは重要な確認ポイントです。
評価額に納得がいかない場合の対応策
通知書に記載された評価額や課税内容に疑問を持ったときは、まず市区町村の固定資産税担当部署に相談しましょう。課税台帳の閲覧請求をすれば、評価額の算定根拠を確認でき、誤りがあれば修正を求める手続きに進めるケースもあります。
修正が認められるかどうかは、評価の根拠に誤認があるかどうかが鍵に。例えば「建物の構造が誤って登録されている」「既に取り壊された建物が課税対象になっている」といったケースでは、訂正が通る可能性が高いでしょう。
手続きが複雑になったり、自治体との調整が難航することもあります。そのような場合は、不動産鑑定士や税理士といった専門家に相談するのも有効。専門的な知見を借りることで、対応がスムーズになり、納得のいく評価額を得られる可能性が高まります。
不動産評価額を下げるための工夫と注意点

不動産評価額は高いほど売却には有利ですが、固定資産税や相続税の負担が重くなる要因にもなります。場合によっては「評価額を適正に見直したい」と考える人も少なくありません。土地や建物の状況を丁寧に確認し、必要に応じて専門家へ相談することで、不要な税負担を抑えられることがあります。
現地の物理的条件や権利関係を再確認する
土地や建物には、思わぬ物理的条件や権利関係が潜んでいることがあります。たとえば、第三者の通行権が設定されている場合や、境界が曖昧で確定していないケースは、実際の利用価値を下げる要因となり、評価額を下げる可能性があります。
道路斜線制限や建築基準法による制限がある土地も、建築の自由度が低いため、評価額に影響することがあります。こうした条件が固定資産税評価や相続税評価に十分反映されていない場合は、役所に相談して見直しを依頼するのもひとつの方法。
現地調査を実施したり、地籍測量図を取り寄せるなど、一次情報を確認する手間はかかるものの、結果的に適正な評価につながります。
専門家(不動産鑑定士・税理士)に相談するメリット
評価額の見直しで大きな減額が期待できる場合や、相続人同士のトラブルを防ぎたい場合には、専門家に相談するのが得策です。
不動産鑑定士は、公平で客観的な立場から評価報告書を作成し、役所や関係者に示せる根拠資料を整えてくれます。税理士は、相続税や固定資産税に関する豊富な知識を持ち、適用できる特例の有無や必要な資料について具体的に助言してくれます。
費用が発生することを懸念する人もいますが、高額な相続税や固定資産税が軽減されれば、結果的に十分なメリットを得られるでしょう。専門家に依頼すると安心感が高まり、時間と労力の節約にもつながるはずです。
不動産評価額を正しく知ることが資産を守る一手に
不動産評価額は、売買や相続、税金の算定といった幅広い場面に関わる大切な基準です。目的に応じて評価方法を使い分け、複数の指標を照らし合わせることで、資産価値をより正確に把握できます。
公示価格や固定資産税評価額など公開情報は積極的に活用し、自力で相場を確認しておくことも有効。さらに専門家へ相談することで、安心と精度の高い判断が得られます。適切な評価を知ることが、資産を守る大きな一歩となるでしょう。
アキサポで不動産のお悩みを相談してみませんか?
評価額の調べ方は分かったけれど、自分のケースにどう当てはめればよいのか不安…という方は、アキサポへお気軽に相談してみませんか?
アキサポでは、空き家や遊休不動産の活用を幅広くサポートしており、専門知識を持つスタッフに無料で相談できます。
売却や相続、賃貸活用など状況に合わせた提案を受けられるので、判断に迷ったときの強い味方に。大切な資産を安心して管理・活用するために、ぜひアキサポの相談窓口を活用してみてください。
この記事の監修者

山下 航平 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
ハウスメーカーにて戸建住宅の新築やリフォームの営業・施工管理を経験後、アキサポでは不動産の売買や空き家再生事業を担当してきました。
現在は、地方の空き家問題という社会課題の解決に向けて、日々尽力しております。








