公開日:2025.11.05 更新日:2025.10.27
不動産売却はどこがいい?初心者でも失敗しない会社選びと高く売るコツ

不動産は高額資産のため、後悔しない売却先と適切なタイミングの見極めが重要となります。
本記事では、初心者にも理解しやすい売却の流れ、不動産会社の選び方、そして高値売却のポイントを体系的に解説。売却成功の第一歩として活用ください。
目次
不動産売却の流れと基礎知識

不動産をスムーズに売却するには、基本手順と必要知識を押さえることが欠かせません。不動産売却の前にプロセス全体を把握しておくと、効率的に準備を進められます。
特に査定依頼や相場調査の段階では、複数社を比較し、自分の物件に最適な売却手法を検討することが大切です。全体像を理解しておくことで、トラブルの回避と納得の取引につながります。
売却準備から契約締結までのステップ
まず物件の相場を確認し、複数社に査定を依頼します。結果を比較検討したうえで信頼できる会社と媒介契約を締結するのが一般的な流れです。
売却成立までの期間は、物件種別や市場動向(需給バランス)によって左右されます。人気エリアのマンションは比較的早く売れる一方、戸建てや地方物件は時間を要する場合があります。
事前にスケジュールを立て、家族や関係者と連携して進めると安心です。契約締結時には、手付金の授受や「宅地建物取引業法第35条」に基づく重要事項説明書の交付と説明など、法的手続きが必要です。書類の不備や金銭管理ミスを防ぐため、チェックリストの作成を推奨します。
仲介と買取の特徴と選び方
仲介(媒介)は、不動産会社が市場に公開して買主を探す方式で、高額売却を狙いやすいのが特徴です。時間をかけてでも価格を重視したい人に向いています。
一方の買取は、不動産会社が直接買い取る方式で、短期間で現金化できるのが強みです。転居や資金繰りを急ぐケースに適しています。価格よりスピードを優先するかどうか、目的に応じて選択しましょう。
不動産売却にかかる費用と税金
売却時に必要な主な費用は、仲介手数料(宅地建物取引業法第46条による上限あり)や印紙税(印紙税法)、所有権移転登記費用などです。手数料は成功報酬型であり、上限を把握しておくことが大切です。
加えて、売却益には「所得税法第33条」に基づく譲渡所得税が課されることがあります。所有期間により税率が変わるため、事前に税理士へ相談するのも有効です。
また、売却時にはハウスクリーニングや軽微なリフォームなど、資産価値向上につながる投資も検討するとよいでしょう。費用対効果を見極め、総合的に出費を管理することが成功の鍵となります。
不動産会社選びはどうする?大手か中小かを見極めるポイント

不動産会社の規模差と選定基準を理解すれば、自分に合った信頼できるパートナーを見つけやすくなります。
不動産売却を成功させるには、適切な不動産会社の選定が欠かせません。大手・中小それぞれの特性を把握し、物件の種類や地域性に合う会社を選ぶことが重要です。特に担当者の対応力・実績・「宅地建物取引士(宅建士)」資格の有無は、高値売却に直結する重要要素といえます。
大手不動産会社を選ぶメリット・デメリット
大手不動産会社は全国ネットワークと広告力を活かし、幅広い買主層にリーチできる点が強みです。多様な媒体を使った宣伝により、早期成約が期待できます。ブランド力による信頼性の高さも魅力のひとつです。
一方で、担当者が多数の案件を抱える傾向があり、個別対応が限定的となる場合があります。大手を選ぶ際は、面談でのコミュニケーションのしやすさや提案力を確認し、信頼関係を築ける担当者を見極めましょう。
中小・地元密着型不動産会社のメリット・デメリット
中小・地元密着型の会社は、地域特化の情報力と柔軟な対応力が強みです。地元需要を踏まえた現実的な売却プランを提案してもらえる点も魅力といえます。
ただし、担当者の経験差や人員不足で対応が遅れる場合もあります。契約前に担当者の経歴・対応方針を確認し、信頼できる担当者かどうかを判断しましょう。地域密着型は、連絡の頻度が高く丁寧なフォローを受けられる傾向もあります。規模だけにとらわれず、実績と対応力を総合的に評価することが大切です。
不動産会社を選ぶ際の共通基準
不動産売却では、「宅地建物取引業法第34条の2」に基づく査定根拠の説明を受け、担当者の誠実な対応を重視することが重要です。過去の取引事例を確認すれば、あなたの物件と似た条件でどれだけ成果を上げているかを把握できます。
また、広告戦略も見逃せません。物件写真や紹介文の質、ポータルサイトでの掲載方法が買主の印象を大きく左右します。最終判断では「担当者との相性」「地域理解」「広告戦略」「価格設定力」を総合的に比較し、短期利益にとらわれず長期的な信頼関係を築ける会社を選びましょう。
査定額に惑わされない!適正な査定価格を見極めるコツ

査定額は会社によって差が出るため、高額・低額の両方に注意し、根拠に基づいた適正価格を見極めることが重要です。
売却先を検討する際、高額査定を提示した会社に惹かれがちですが、相場を超えた査定を鵜呑みにすると、売却の長期化や値下げ交渉に発展する恐れがあります。「宅地建物取引業法第34条の2」に基づき、査定根拠を丁寧に確認することが、後悔しない売却の第一歩です。
査定額の根拠を丁寧に説明してくれるか
信頼できる不動産会社は、成約事例・地価公示・立地条件・築年数など、多角的な視点から査定額を算出します。
また、リフォーム歴や日当たり、眺望などの個別要素を反映しているかも重要です。相場比較を交えながら根拠を明示できる担当者は、市場理解度が高いといえるでしょう。査定額に不明点があれば、遠慮なく質問してクリアにしておくことが大切です。売り出し価格を調整する場面でも、根拠を共有できていれば柔軟に対応できます。
高すぎる査定と低すぎる査定、それぞれのリスク
高額査定は一見魅力的ですが、買い手がつかず販売期間が長期化する恐れがあります。価格調整のタイミングを逃すと、売却機会を逃すことにもなりかねません。
一方で、低すぎる査定では市場価格を下回り、資産を過小評価される危険があります。特に早期売却を希望する場合は、意図的に低い査定を出されても信じてしまうケースがあるため注意が必要です。査定の妥当性を判断するには、複数社の査定書を比較し、根拠資料を確認することが効果的です。数字だけでなく、その背景にある算定プロセスを理解しましょう。
売却実績・運営歴から会社の信頼性をチェック
査定の精度を見極めるうえでは、会社の売却実績と担当者の経験値が重要です。長年運営している会社は、地域市場のデータを蓄積しており、相場を的確に反映した提案が期待できます。
ただし、新興企業でもベテラン担当者がいれば十分なノウハウを持つ場合もあります。企業の信頼性を確かめる際は、公式サイトで成約事例や口コミを確認し、「宅建業免許番号(国土交通大臣/都道府県知事)」の有無もチェックしましょう。総合的に評価し、信頼性の高い会社を選ぶことが、不動産売却成功の鍵となります。
複数社への一括査定で比較するメリットと注意点
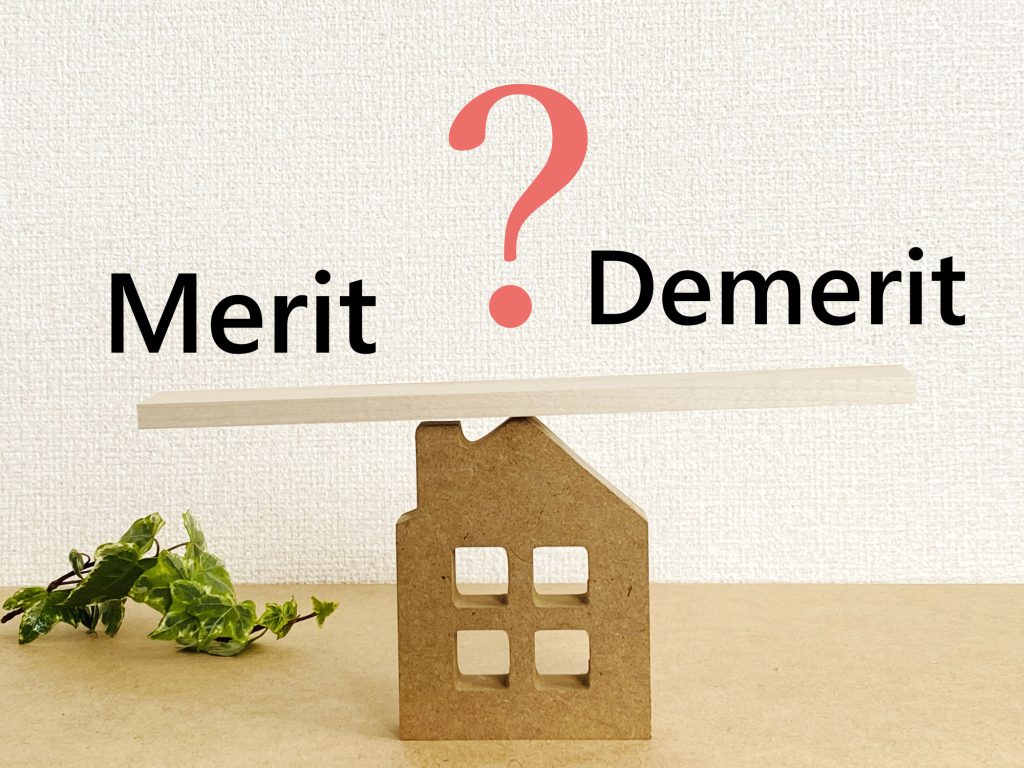
一括査定サイトを使えば、短時間で複数の不動産会社から査定を受けられますが、正しく活用するコツを押さえることが大切です。
忙しい人でも効率的に複数社の査定額や提案内容を比較できる便利な仕組みですが、高額査定にだけ注目すると、スムーズな売却という本来の目的を見失うおそれがあります。効果的に使うには、サイトの選び方と対応の仕方を理解しておきましょう。
一括査定サイトを使うときの流れ
まず複数の一括査定サイトを比較し、掲載会社数・対応エリア・サービス内容を確認します。
物件情報を入力すると、条件に合う複数社の査定結果がメールや電話で届く仕組みです。不明点があれば担当者に直接質問し、対応の丁寧さや説明の明確さも比較しましょう。
契約を急かす会社があっても、冷静に比較する姿勢を崩さないこと。複数社の査定結果を見比べたうえで、候補を絞って面談や訪問査定に進むのが理想的な流れです。
高額査定に飛びつかないための対策
一括査定の結果をもとに売却先を選ぶ際は、高額査定を提示した会社に慎重な判断が必要です。
中には媒介契約を取る目的で、相場を上回る数字を提示するケースもあり、これは「宅地建物取引業法第47条(誇大広告・不当表示の禁止)」に抵触する可能性があります。根拠や周辺相場を示さずに高額査定を主張する会社は特に要注意です。
実際の販売状況を見ながら柔軟に価格調整を行い、現実的な価格帯でスムーズに成約できるよう進めましょう。
広告活動と担当者の対応力も比較する
査定額だけで判断すると、売却活動で行き詰まる可能性があります。不動産ポータルサイトやSNSなど、複数メディアで積極的に広告を展開する会社は、より多くの買主にアプローチできます。
また、担当者の対応力も重要な評価軸です。問い合わせへの回答の速さや説明の丁寧さ、書類対応の正確さは、売却の進行を大きく左右します。初期対応で不安を感じた場合は、疑問点を解消できる別会社を検討しても構いません。
時間をかけて複数社を比較することが、最終的な満足度と安心感につながります。
不動産会社と結ぶ媒介契約の種類と特徴

不動産会社へ売却を依頼する際は、媒介契約の種類を理解し、自分の状況に最も合った契約形態を選ぶことが重要です。
媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、依頼できる会社数やレインズ(指定流通機構)への登録義務、報告頻度などが異なります(宅地建物取引業法第34条の2・第50条)。契約形態を正しく選べば、売却を円滑に進められます。
一般媒介契約のメリット・デメリット
一般媒介契約は複数社に同時依頼できる自由度の高さが特徴です。多くのネットワークを活かした広告展開が可能で、幅広い買主層にアプローチできます。また、自分で買主を見つけて直接契約することも認められています。
一方で、他社との競合により担当者の優先度が下がり、販売活動がやや消極的になる場合もあります。情報共有が煩雑になりやすいため、進捗管理を自分で行う意識が必要です。
専任媒介・専属専任媒介契約で期待できること
専任媒介および専属専任媒介は、1社とだけ契約する形式で、販売活動を集中して行ってもらえるのが利点です。専任媒介では2週間に1回、専属専任媒介では1週間に1回の報告義務があり、売却の進行状況を把握しやすい点も安心材料です。
ただし、他社に依頼できないため、販売方針が合わない場合は調整が難しくなるデメリットもあります。契約前に販売戦略や広告計画を担当者と共有し、納得したうえで締結しましょう。特に専属専任媒介は制約が多いため、信頼できる不動産会社を慎重に選ぶことが大切です。
契約条件でチェックすべきポイント
レインズへの登録時期や報告頻度は、契約時に必ず確認しましょう。専任・専属専任媒介では登録が義務付けられています。契約期間は通常3か月以内で、更新や解約のルールも事前に把握しておくと安心です。
また、仲介手数料の上限や支払い時期、違約金の有無など、金銭条件も契約書で必ず確認しましょう。条件を明確にしておくことで、予期せぬトラブルや出費を防ぎ、計画的な売却が実現します。
不動産をより高く売るためのテクニック

少しの工夫で物件の印象を高め、高値売却を狙うための実践的な方法を紹介します。
大切な資産を高く売るには、価格設定と物件の見せ方という基本を押さえることが重要です。買主が魅力を感じる要素を演出し、市場相場に沿った戦略を立てることで、高額売却の実現性が高まります。
価格戦略と販売タイミングの重要性
売り出し価格は相場を大きく外さず、買主の関心を引きつつ交渉の余地を残す設定が理想です。早期売却を狙う場合は、やや低めに価格を設定すると短期間で成約しやすくなります。
一般的に春と秋は不動産取引が活発なシーズンとされ、引っ越し・転勤需要の高まりに合わせて販売すると、より多くの買主と接点を持てます。
ただし、地域や物件タイプによっては最適な売り出し時期が異なる場合もあります。担当者と相談し、「不動産流通推進センター」などが公表する市場動向を参考に販売スケジュールを組みましょう。
ホームステージングと物件価値の演出
ホームステージングとは、家具や小物、照明の配置を工夫して室内の印象を向上させ、買主の購買意欲を高める販売手法です。
家具が多い場合は一部を撤去し、空間の広がりを演出すると効果的。自然光を取り入れる、部屋ごとにテーマカラーを統一するなどの工夫で、購入後の暮らしをイメージしやすくなります。一定のコストはかかりますが、早期成約や価格上乗せにつながれば十分なリターンが期待できます。専門のホームステージャーや不動産会社の助言を受けるのも有効です。
売り出し前にできるメンテナンスと清掃
目立つ傷や破損を放置すると、物件全体の印象を損ねる恐れがあります。軽微な補修を行うだけでも、買主に安心感を与えられます。
特に水回りやフローリングの清掃は、低コストで清潔感を大きく高められるポイント。プロのハウスクリーニングを利用すれば、内覧時の印象をさらに向上できます。
マンション売却と戸建て売却で違うポイント

マンションと戸建てでは売却に関わる条件が異なるため、それぞれの特徴を正確に理解する必要があります。
マンションは管理費や修繕積立金など、購入後に継続的に必要となる費用が買主にとって判断材料となります。一方、戸建ては土地の境界確認など、建物以外の要素が大きく売却価格に影響を与えるのが特徴です。物件種別によって着眼点が変わるので、売却戦略を立てる際にしっかり区別して考えましょう。
管理費・修繕積立金が鍵となるマンション売却
マンション売却では、管理費・修繕積立金の金額や管理組合の健全性が、買主の購入判断に直結します。これらが高額だと月々の負担が重く、購入をためらうケースもあります。
また、大規模修繕が予定されている場合は、費用負担や積立状況も確認が必要です。管理規約・長期修繕計画・総会議事録などを整理し、事前に提示できるようにしておくと信頼度が高まります。駅近や利便性の高い立地であれば、宣伝戦略次第で高値売却を狙えるケースも多いでしょう。
ただし、築年数や設備の老朽化によって査定額が変動する点も念頭に置く必要があります。
境界や敷地面積に注意したい戸建て売却
戸建てでは、隣地との境界確定や敷地測量が必要になることが多くあります。境界が曖昧なままではトラブルにつながるため、早めの確認が重要です。
また、建物の状態に不安がある場合は、「建物状況調査(インスペクション)」を受けて結果を開示することで、買主に安心感を与えられます。外壁や庭の手入れなど、外観を整えることも有効です。清潔感のある印象は、第一印象を大きく左右し、高値成約の可能性を高めます。
エリア別に強い会社を選ぶ戦略
マンション・戸建てのいずれでも、エリア特性を熟知した不動産会社を選ぶことが、売却成功の鍵です。地元密着型の会社は地域の需要や買主層を熟知しており、物件タイプに合わせた的確なPRを行いやすい傾向があります。
一方で、大手不動産会社にも地域専門の担当者が在籍している場合があるため、両者を比較して検討するのがおすすめです。過去の成約実績や近隣の売出状況を参考に、自分の物件タイプとエリアに強い会社を選びましょう。
契約トラブルを防ぐ!瑕疵担保責任・契約不適合責任への対応

売却後のトラブルを防ぐには、物件の不具合や「告知義務」の内容を正しく理解し、誠実に開示することが重要です。
売却後に欠陥(雨漏り・腐食など)が発覚すると、買主との紛争や損害賠償請求に発展することもあります。契約時の告知義務を果たし、事前調査を徹底することがトラブル防止の第一歩です。
告知義務と不具合の事前調査
雨漏り・シロアリ被害・過去の火災など、物件に関する重要な情報は契約不適合責任(民法第562条以下)および宅地建物取引業法に基づき、買主に正確に伝える義務があります。これを故意に隠した場合、後から契約解除や損害賠償の対象となる恐れがあります。
インスペクション(建物状況調査)を依頼して、補修可能な不具合は早めに修繕しておくと安心です。不動産会社から説明を受けるだけでなく、最終的な責任は売主本人にあることを意識し、情報を整理しておきましょう。
契約書類の確認と瑕疵保険の活用
契約書・重要事項説明書には、物件の状態や契約条件が詳細に記載されます。内容に不明点があれば、行政書士や司法書士などの専門家に相談し、誤解や記載漏れを防ぎましょう。
また、契約不適合責任への備えとして、既存住宅売買瑕疵保険(住宅瑕疵担保責任保険)に加入しておくのも有効です。保険により想定外の不具合を補償できるため、買主の信頼を得やすくなります。
保証範囲・期間・免責条件は契約前に必ず確認し、契約書に明記しておきましょう。
実際に起こったトラブル事例から学ぶ注意点
過去には、雨漏りやシロアリ被害を隠して売却した結果、契約後に多額の損害賠償を請求されたケースもあります。軽微な不具合でも後に大きな問題へ発展する可能性があるため、油断は禁物です。
売却前に専門家へ点検を依頼し、早期発見と適切な対応を行いましょう。契約時には買主とのコミュニケーションを丁寧に行い、疑問や要望を共有しておくことがトラブル防止の鍵です。
離婚や相続など特別な事情がある場合の売却対応
共有者や名義人が複数いる場合など、通常と異なる売却には慎重な法的手続きが必要です。
離婚や相続が絡むと、権利関係や意思決定が複雑化しやすく、専門家の支援を受けながら進めるのが安心です。ここでは、共有名義・相続・離婚財産分与といったケースで注意すべきポイントを整理します。
共有名義や遺産分割協議が必要なケース
共有名義の不動産を売却する際は、共有者全員の同意が必須です。特に相続物件では、相続人が複数いる場合に「遺産分割協議」が必要となります。法定相続人を確認した上で遺産分割協議書を作成し、不動産登記簿上の名義を整理しておきましょう。
手続きを放置すると売却が進まないだけでなく、相続人間でトラブルに発展するおそれもあります。弁護士・司法書士・税理士などの専門家へ早めに相談し、客観的な立場でのサポートを受けることが重要です。
離婚による財産分与としての売却
離婚に伴う不動産売却では、財産分与として売却益をどのように分けるかが焦点となります。共有名義の場合は、持分や住宅ローンの残債処理方法を明確にしておくことが不可欠です。
あらかじめ合意内容を契約書や公正証書として残しておくと、後々の紛争防止になります。話し合いが感情的にこじれやすい場合は、家庭裁判所での調停や第三者機関による仲介も検討しましょう。
専門家への早めの相談でトラブルを回避
相続や離婚に関する不動産売却は、法律・税務・登記など複数の知識が求められます。早い段階で専門家に相談し、最適な売却手法や税務対策を確認しておくことが肝心です。
不動産会社にもこうした案件に慣れた担当者はいますが、法的判断が必要な局面では弁護士・司法書士・税理士が心強い味方です。
遠方物件・空き家の売却で気をつけたいこと

遠方や空き家の売却では、現地管理や清掃などの対策が不可欠で、通常よりも確認すべき項目が増えます。
売主が離れた場所に住んでいる場合、内覧対応や維持管理が難しくなり、売却活動が遅れがちです。特に空き家では、放置による劣化や防犯面のリスクも高まるため、計画的な管理体制を整えることが大切です。
現地担当者や管理サービスの活用
遠方物件の売却を円滑に進めるには、現地に拠点を持つ不動産会社や管理サービスの利用がおすすめです。定期巡回・清掃・通風を行ってもらえば、買主の内覧時にも良好な印象を維持できます。
空き家では特に湿気やカビの発生が問題となりやすく、定期点検を委託することで劣化リスクを抑えられます。管理コストは発生しますが、資産価値維持のための投資と捉えれば、高値成約や早期売却につながる可能性があります。
オンライン内覧と電子契約を活用する
近年は、スマートフォンやカメラを使ったオンライン内覧が広がっています。遠方や海外にいる買主でも、リアルタイムで室内の様子を確認できる点がメリットです。
また、不動産会社によっては電子署名法に基づく電子契約を導入しており、押印や書類の郵送を省略できるケースもあります。これにより、手間と時間を大幅に削減できます。
ただし、オンラインでは伝わりにくい部分もあるため、実際の内覧希望には柔軟に対応できる体制が理想です。デジタルとリアルの両立が、成約率を高めるポイントです。
売却完了までの連絡体制を確認する
遠方物件の売却では、こまめな連絡と報告体制の確立がトラブル防止の鍵となります。担当者から写真や動画付きで進捗を報告してもらえると安心です。
電話・メール・オンライン会議など複数のコミュニケーション手段を併用し、必要に応じてLINE等のチャットツールで迅速に情報共有できる環境を整えましょう。
また、連絡頻度・報告方法・決裁フローなどを初期段階で明確に決めておくと、認識のズレや行き違いを防げます。遠方からでもスムーズに売却を進めるには、「現地サポート × デジタル連携」の両輪が欠かせません。
海外在住者が不動産を売るときのポイント

日本国内に不在の状態での売却は、必要書類や納税関連など国内にいる場合とは違うハードルがあります。
海外在住のオーナーが不動産を売却する場合は、納税管理人の手配や印鑑証明書の取得など、注意すべき手続きを踏む必要があります。時差や言語の壁にも配慮し、海外取引に慣れた不動産会社を選びましょう。
納税管理人と必要書類の準備
海外在住者が日本の不動産を売却する場合、国内で税務処理を代行できる「納税管理人」を指定し、納税地の税務署に届出を行う必要があります。親族・友人のほか、税理士など専門家を指定するケースも一般的です。
また、印鑑証明書の代わりに在外公館で発行される署名証明書を利用できる場合があります。発行には時間がかかることもあるため、余裕を持って準備を進めましょう。売却後も所得税や譲渡所得税などの申告義務が残ります。申告漏れや遅延には加算税のリスクがあるため、手続きは正確に行いましょう。
時差とコミュニケーションを考慮した担当者選び
海外からの売却では、時差の影響でリアルタイムな打ち合わせが難しいことがあります。メールやオンライン会議ツール(Zoom、Teamsなど)で柔軟に対応できる担当者を選ぶと効率的です。
また、英語など多言語対応可能なスタッフがいる不動産会社を選ぶと安心です。契約や書類確認を短期間で行う場合は、あらかじめスケジュールを共有し、時差を考慮した連絡体制を整えましょう。
租税条約の確認と確定申告の手続き
海外在住者は、居住国と日本の租税条約の内容を把握しておくことが大切です。条約によっては売却益に対する二重課税を回避できたり、源泉税・所得税の控除を受けられる場合があります。
確定申告は、通常の申告期限(翌年3月15日)を目安に準備を進めます。海外送金に関する証明書や為替レート明細など、追加書類が必要となる場合もあるため、税理士と密に連携しましょう。
売却後に税務署から問い合わせを受けることもあるため、契約書・送金証明・明細書などの関連書類は必ず保管しておきます。
契約解除や担当変更を検討する際の注意点

売却が停滞したり担当者との相性が悪い場合は、契約解除や担当変更も現実的な選択肢。
まずは契約条項と進行体制を洗い直し、タイミングや費用負担を踏まえて次の一手を慎重に決めます。
媒介契約を解除する場合の留意点(違約金・実費など)
契約期間:専任・専属専任媒介は最長3か月が上限。一般媒介に法定上限はないが、実務上は3か月更新が多い。
解除の可否:媒介は委任型契約のため、原則いつでも解除可。ただし民法により、不適切な時期の解除で相手に損害が生じた場合は賠償責任が生じ得ます。
費用の扱い:仲介手数料は原則“成約時”に発生。途中解除のみでは通常は手数料は発生しませんが、事前合意の広告費・実費は精算対象になり得ます(国交省系標準媒介契約約款の考え方)。
通知方法:書面または電磁的方法など、契約書に定める手順で行う。方法違反は紛争要因になりがち。
条項チェック:違約金/実費負担/独占期間/報告頻度など、該当条項の根拠と金額を確認のうえ判断する。
担当者の交代で対応が変わるか確認する
原因が担当者起因(連絡遅延・提案弱い・相性不一致)なら、交代要請で改善するケースも。社内にはエリア特化・物件種別特化の担当者がいることがあり、戦略・広告導線・フォロー体制が刷新される可能性があります。
一方で、関係の再構築や情報共有の手戻りが発生するデメリットも。効果(改善見込み)とコスト(時間・手間)を比較し、会社内の交代→改善なしなら切替の順で検討が現実的です。
タイミング次第では売却計画の見直しも有効
市況悪化やライフイベントの変化が重なる時期は、延期・中止・賃貸運用への切替も合理的選択です。
「ローン残債」「家族構成の変化」「次住居の予算・金利」「税務影響」を再点検し、総利益(ネット手取り)とリスクで意思決定を。条件が整った時点で再上場(再売出し)へ舵を切ればOK。焦りは禁物、損失最小・成果最大の観点で柔軟に動くのが得策です。
まとめ・総括|自分に合った不動産会社選びが高額売却への近道
不動産売却では、相場の把握から会社選び、物件の演出、税金対策まで多くの要素を総合的に考える必要があります。判断を一つずつ丁寧に重ねることで、納得度の高い売却が実現します。「大手と中小の特徴」「査定の根拠」「媒介契約の選び方」「販売時期や見せ方」など、複数の視点から検討することが重要です。
成功への近道は、情報をバランスよく比較し、自分の目的や状況に合った方法を見つけること。多少の手間を惜しまず、一括査定や担当者比較、ホームステージングを活用すれば、高値売却につながる可能性もあります。
また、契約内容や法的知識を理解し、担当者と丁寧にコミュニケーションを取ることで、トラブルの防止にもつながります。最終的には、十分な下調べと慎重な判断をもとに、大切な資産を最も有効に活かせる売却を目指してください。
この記事の監修者

山下 航平 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
ハウスメーカーにて戸建住宅の新築やリフォームの営業・施工管理を経験後、アキサポでは不動産の売買や空き家再生事業を担当してきました。
現在は、地方の空き家問題という社会課題の解決に向けて、日々尽力しております。








