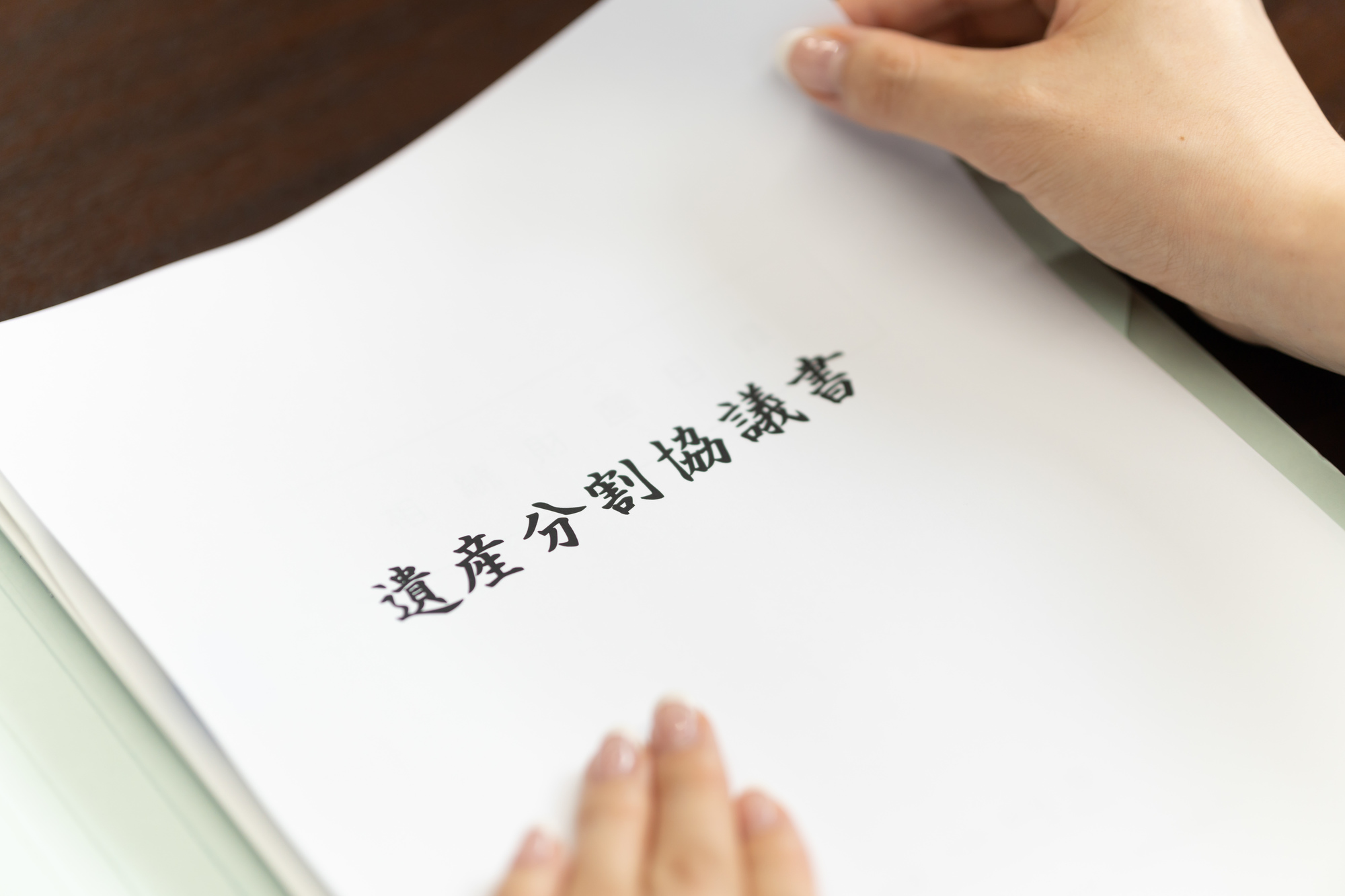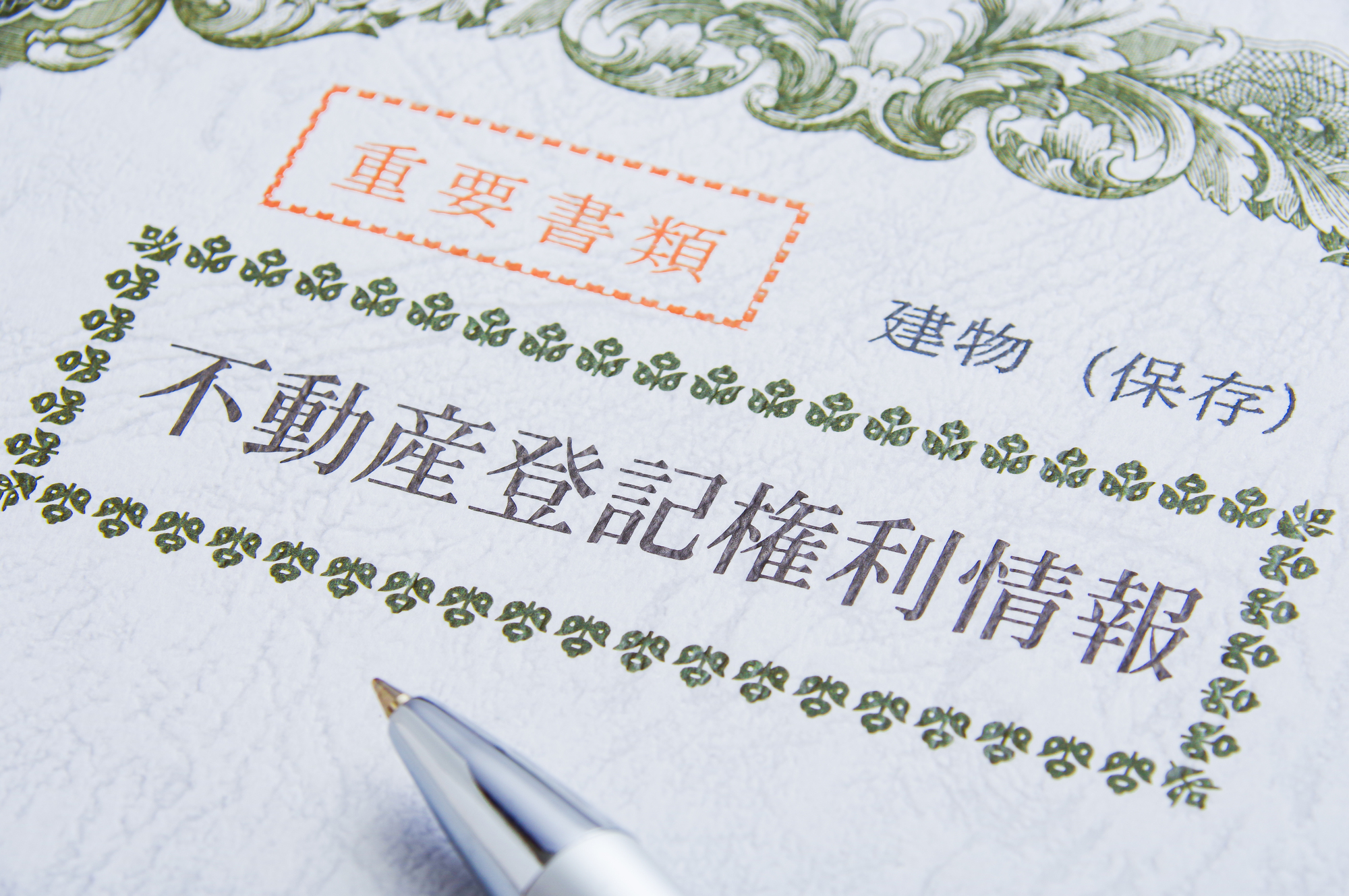公開日:2025.09.14 更新日:2025.07.29
【最新版】相続登記にかかる費用を徹底解説|登録免許税・司法書士報酬・必要書類まで
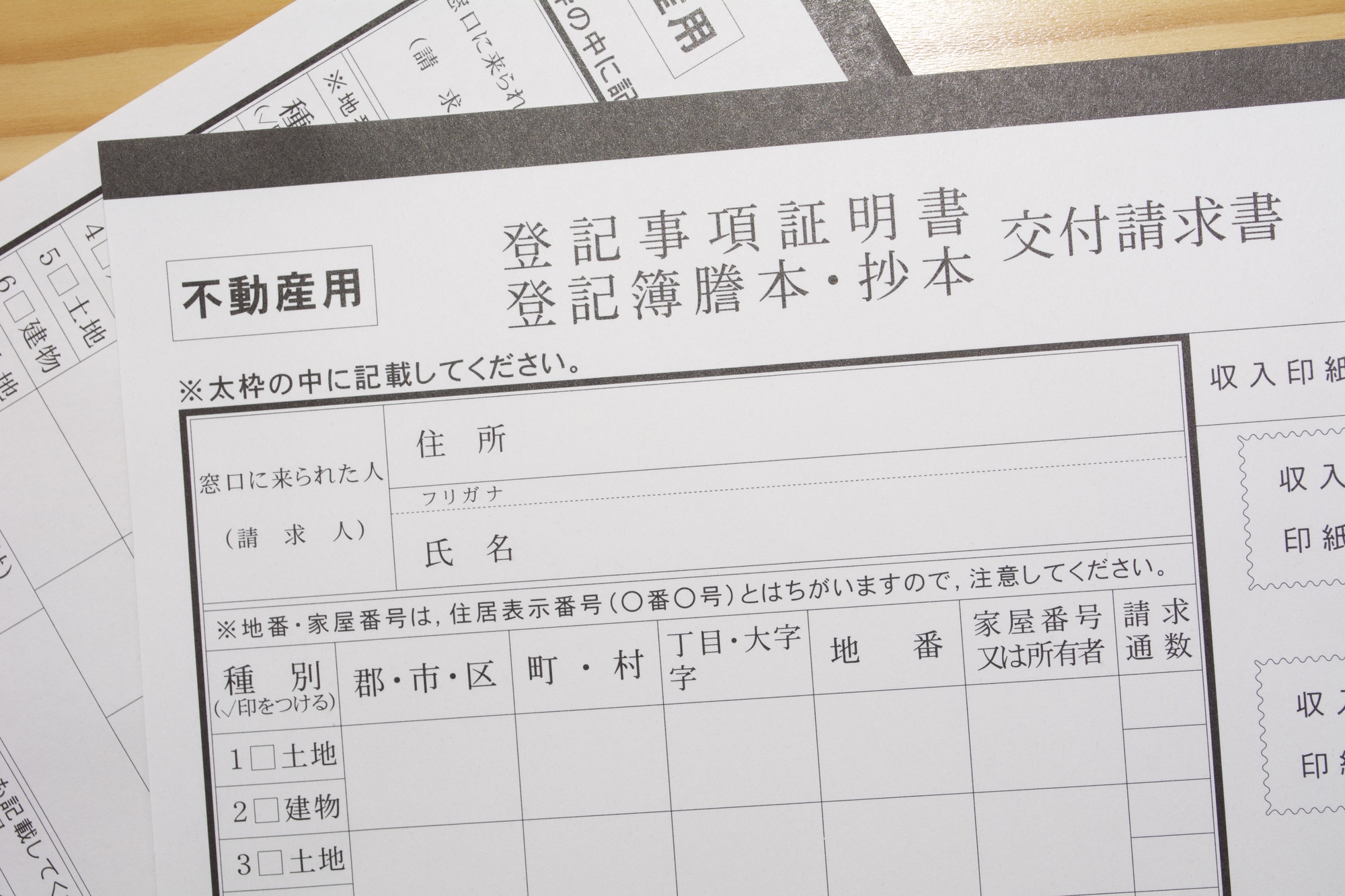
不動産の相続をするとき、特に心配なのが相続登記の費用ではないでしょうか。普段はなじみがないことなので、どんな費用がかかるのか、相場はどのくらいなのか、気になる点が多いですよね。
そこで本記事では、相続登記にかかる主な費用とその内訳、費用を抑えるための具体的な方法まで丁寧に解説します。失敗のない登記を行うために、まずは全体像をしっかり把握しておきましょう。
目次
相続登記とは?基礎知識をチェック

相続登記とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産の名義を、相続人へ変更するための手続きです。手続きを行うには法務局で所定の書類を提出し、不動産の所有権を公的に記録し直す必要があります。
相続登記の手続きを行う目的は、名義人を法的に明確化することにあります。名義がそのままだと、土地を相続した人に登記名義が無いとみなされてしまい、土地を売却する場合や担保にする場合などに手続きが進まなくなる恐れがあります。
また、長期間放置していると、あとから相続登記をしようとしても、関係が複雑化してしまい、誰が相続できるのかを整理するのが困難になる可能性もあります。
これらのトラブルが起こると手間も時間も費用もかさみ、思わぬトラブルに発展することもあります。相続登記が必要な場合は、なるべく早めに対応しましょう。
2024年4月に改正された相続登記の義務化にも注意
上記で相続登記を行わなかった場合のリスクも説明しましたが、このような問題は以前から散見されていました。これに対応するために行われたのが、2024年4月の法改正です。
これにより、相続人は「相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内」に登記申請を行うことが義務付けられ、正当な理由なく期限を過ぎた場合に、10万円以下の過料が科されることも定められました。
相続人が多い場合や相続した土地が多い場合などは、相続人同士の合意形成や書類整理などに時間がかかる可能性がありますので、早めに動き出すのが得策です。
相続登記にかかる主な費用の種類

相続登記をする際には、手続きや書類の取得などに費用がかかります。中には不動産の価値によって費用が変わる項目もありますので「予想以上に高かった」とならないように、あらかじめ全体像を把握しておきましょう。
相続登記にかかる主な費用は以下のとおりです。
- 必要書類の取得費用
- 登録免許税(不動産の名義変更にかかる税金)
- 専門家への報酬(司法書士など)
これらを合計すると、状況によっては10万円〜20万円以上になるケースもあります。それぞれの内訳や注意点について詳しく見ていきましょう。
必要書類の取得費用
相続登記に必要な書類を取得するには、窓口で手数料を支払う必要があります。また、郵送で取得する場合は郵送料もこちらで負担します。
主な書類と取得費用の相場は以下のとおりです。
- 戸籍謄本(1通):450円
- 除籍謄本(1通):750円
- 改製原戸籍(1通):750円
- 住民票(1通):300円前後
- 印鑑証明書(1通):300円前後
- 固定資産税評価証明書(1通):300円〜400円程度
- 登記事項証明書(1通):600円(オンライン請求の場合は490円または520円)
相続関係が複雑な場合や本籍地が複数にまたがっている場合などは、これらの書類を何通も取り寄せる必要があり、合計で数千円〜1万円を超えることもあります。
手続き前に必要通数を確認し、郵送をまとめて請求するなど、取得方法を工夫するだけでもコストや手間を抑えやすくなります。
登録免許税
登録免許税は、不動産の名義変更に必要な税金です。相続登記の場合、不動産の固定資産税評価額に0.4%をかけて算出されます。
たとえば、評価額1,000万円の土地を相続した場合は以下のようになります。
1,000万円 × 0.4% = 4万円
ここで気を付けたいのが、相続ではなく相続人以外が受け取る「遺贈」の場合です。この場合は税率が2%になります。(ただし、受遺者が法定相続人である特定遺贈など、一部0.4%の税率が適用されるケースもあります)。
なお、登録免許税には、不動産の価額が100万円以下の土地に関する免税措置や、相続登記が完了する前に、登記名義人となるべき相続人が死亡した場合の免税措置など、税額を軽減する制度も用意されています。実際に動き出す前に、条件に該当するかどうか確認しておきましょう。
司法書士への報酬
相続登記を司法書士のような専門家に依頼する場合の費用です。報酬の相場はおおよそ5万円〜15万円ですが、不動産の数が多い場合や、相続人が複数にわたるケースでは、報酬が上乗せされることがあります。
また、以下のような条件も報酬額に影響します。
- 書類の取得代行を依頼するかどうか
- 遺言書や遺産分割協議書の確認が必要かどうか
- 相談料・交通費などが別途発生するかどうか
なお、具体的な報酬額は事務所ごとに異なります。費用を節約したい場合は複数の事務所から見積もりを取り、値段とサービス内容を比較しましょう。このとき、基本報酬だけでなく、見積もりに含まれている範囲を確認するのも忘れないようにしましょう。
相続登記の費用を抑えるコツ

ここからは、見積もりの比較以外の、相続登記の費用を抑える方法を紹介します。どれも自分でできることなので、ぜひ目を通しておいてください。
取得可能な必要書類を自分で集める
戸籍謄本や住民票などの取得は、司法書士に依頼することもできますが、取得代行の手数料がかかるため、時間に余裕があれば自分で集めるのがおすすめです。ただ、取得に期間がかかりすぎると手続きが遅くなってしまうので、その点は注意が必要です。
また、手続きには郵送やオンライン申請を活用すると、交通費や時間の節約になります。郵送代はこちらで負担する必要があるので、あらかじめ専門家に必要書類を聞いてから進めるとよいでしょう。
追加の手続きが発生しないように正確な情報を集める
手続きを進めていくうえで必ず心がけたいのが「事前に正確な情報をそろえること」です。あたり前のように聞こえるかもしれませんが、情報が誤っていると手続きがやり直しになったり、書類を何度も取得したり、さらには期限内に間に合わなかったりと、さまざまなリスクにつながります。
特に気を付けたいのが、相続人の続柄や持分、遺産の内訳などです。これらは動き出す前に早い段階で整理しておきましょう。
手続きに不安がある場合や時間がない場合は、書類の取得代行を含めて司法書士のような専門家に依頼するのも手です。費用はかかりますが、ミスやトラブルの防止、手続きを早期に完了できるなど、さまざまなメリットがあるため、結果的に依頼した方が安くつく場合もあります。
相続登記の手続きの流れ

法務局へ行って名義変更の書類を提出するためには、その条件を整えるために多くの準備が必要になります。
一般的な相続登記の手続きの流れは以下のとおりです。
相続登記の基本ステップ(6項目)
- 1.相続人を確定する
- 2.相続財産(不動産)を確認する
- 3.遺産分割協議を行う(必要な場合)
- 4.必要書類を準備する
- 5.登記申請書を作成する
- 6.管轄の法務局に申請する
こうして見ると、一見手続きはシンプルに見えますが、実際には相続人の確認や書類の収集、協議内容の整理など、準備に時間と手間がかかる場面が多くあります。
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて取得し、相続関係を正確に把握する必要があります。これには、本籍地が移転している場合に複数の役所に請求する必要が生じます。
また、遺産分割協議が伴う場合も注意が必要です。遺産分割協議は、相続する人や相続後の持ち分、その後の管理や処分など、具体的な話し合いが必要になるため、時間を長めに取っておく必要があります。また、協議内容は「遺産分割協議書」にまとめて全員の署名と押印を揃える必要があるので、こちらにも時間がかかります。
これらのステップが終了して初めて、必要書類を揃えて、具体的な申請の準備ができるようになります。事前調整に想定外の時間を取られないように、早めの動き出しを心がけましょう。
申請の必要書類
相続登記では、相続人の関係や不動産の内容を証明するために、さまざまな書類をそろえる必要があります。漏れがあると申請が通らず、補正や再提出が必要になるため、事前に書類をチェックしておきましょう。
主な必要書類は以下のとおりです。
- 登記申請書(法務局所定の様式)
- 遺産分割協議書(遺産分割が法定相続分と異なる場合)
- 相続関係説明図
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・住民票の除票
- 相続人全員の住民票(相続登記を申請する相続人のみ)、印鑑証明書(遺産分割協議書に押印した相続人のみ)
- 固定資産税明細書
など
なお、登記の内容や家族構成によっては、遺言書や調停調書などの追加書類が必要になることもあります。不備があると手続きが滞るため、少しでも不安がある場合は、事前に司法書士や法務局へ相談しておくと安心です。
費用を抑えるために自分で登記をするのはあり?

登記手続きを自分で進めれば、専門家への報酬が必要なくなるので、多くの費用が節約できます。手間やリスクはあるものの、書類の準備や申請に一定の自信がある人にとってはアリといえるでしょう。
たとえば、以下のようなケースであれば自分での手続きも選択肢に入ってきます。
- 相続人が1人だけ、または全員がスムーズに協議できる関係性にある
- 相続する不動産が1件だけで、構成が単純
- 遺産分割協議が不要、またはすでに協議書が整っている
- 戸籍や住民票などの書類取得に慣れており、時間にも余裕がある
- 法務局に何度か足を運べる距離感・スケジュールである
なお、自分で登記を進める際には以下の点に気を付けましょう。
- 法務局のホームページや窓口で、登記申請の基本を確認しておく
- 相続関係や不動産の内容を事前に整理しておく
- すべての必要書類を、提出ルールに従って正確に準備する
- 登記申請書は様式通りに作成し、誤字脱字がないか確認する
- 不安な点があれば、事前に法務局で相談しておく
一方で、相続人が多い場合や協議が複雑な場合、不動産が複数ある場合などはリスクが多すぎるので、無理に自分で進めようとせず、最初から専門家に依頼することをおすすめします。
依頼する司法書士の選び方
最後に、相続登記を依頼する司法書士の選び方を紹介します。
司法書士の業務範囲は幅広いため、まず「相続登記に強いこと」「寄り添ったサポートが受けられること」は大前提として欠かせません。
そのうえで、以下のようなポイントをチェックしましょう。
- 相続登記の実績が豊富か
- 初回の無料相談を実施しているか
- 戸籍取得や協議書作成などの代行が可能か
- 費用の見積もりが明確か、サービスの範囲が明示されているか
- 相続人とのやり取りや調整に慣れているか
逆にNGなのは「値段が安い」「事務所が近い」という安易な理由で選んでしまうことです。相続登記は司法書士と二人三脚で進めていく必要があるので、自分の状況をくみ取ったうえで、親身になってくれる人を選びましょう。
まとめ・総括
今回の記事で、相続登記は手続きが複雑なだけでなく、費用面でも意外と見落としがちなポイントが多いことが分かりました。特に司法書士報酬や登録免許税は、依頼内容や不動産の評価額によって変動するので、早めに見積もりを取ったり、試算をしたりと準備をしておきたいですね。
特に大切なのは「早めに動く」「費用の見通しを立てる」「自分でやるか専門家に頼むかを判断する」の3点です。この3点が固まればその後の手続きもスムーズになるので、まずは自分の状況に合った準備から、ひとつずつ始めてみましょう。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。