公開日:2025.10.05 更新日:2025.10.07
おすすめの土地活用とは?ランキング形式で紹介

相続した実家の敷地や耕作していない農地など、遊んでいる土地を活用するにはどうすればよいのでしょうか?所有しているだけでも税金や維持費はかかるので、せめて赤字にならないようにしたいところですよね。
とはいえ、土地活用は駐車場経営やアパート建築、太陽光発電などさまざまな方法があり、どれを選べばよいのか迷う人は少なくありません。
そこで本記事では、土地活用の代表的な方法を比較しながら、それぞれのメリット・デメリットや、向いているケースを整理していきます。収益性からリスク、管理の手間まで網羅的に解説していきますので、自分に合った活用法を見つけるヒントとしてご活用ください。
目次
土地を活用するメリット

土地活用のメリットを把握しておくことは、将来的な土地利用を考えるためにも不可欠です。今まで負担になっていた土地を収益源に変えることで、どのような効果が得られるのか、ここでは主な3つのメリットを紹介します。
土地をそのまま放置するリスクを回避できる
土地活用に成功して管理者が付けば、放置された空き地や空き家が抱える、景観や環境、治安の悪化など、さまざまなリスクを大きく減らすことができます。所有している土地が原因で犯罪や放火が起こると周囲も危険にさらすことになるため、思った以上に大きなメリットといえるでしょう。
固定資産税や相続税の節税効果が見込める
土地活用の大きなメリットのひとつに、税負担の軽減があります。
まず固定資産税については、住宅用地として利用している場合に「住宅用地の特例」が適用され、土地の固定資産税が200㎡以下の部分は6分の1、200㎡を超える部分は3分の1まで減額されます。建物分の固定資産税は課税されますが、地価の高いエリアでは土地部分の減税効果が大きく、トータルで見れば負担を大幅に抑えられるケースも少なくありません。
さらに相続税についても、土地を賃貸住宅用に活用することで「貸家建付地(かしやたてつけち)」として評価され、評価額が下がる制度があります。これは、借主がいることで土地所有者の利用が制限される状況が評価に反映され、相続財産としての評価が下がることで相続税が軽減される仕組みです。
このように、土地をただ持っているだけでは得られない税制上の優遇を享受できるのは、土地活用を検討する大きな理由のひとつといえるでしょう。
資産価値の向上が見込める
土地がただ所有している状態から、建物や設備を設けて実際に利用されている状態になれば、土地の収益性が明確になり、市場での評価も高まりやすくなります。たとえば同じ立地であっても、更地より駐車場や賃貸物件として活用されている土地の方が「収益を生む資産」として見なされ、売却や担保評価の際に有利に働くケースがあります。
また、活用されている土地は管理が行き届いている資産として市場からの印象も良くなります。入居者や利用者がいることで将来的な収益計画を描きやすく、転用や売却の選択肢が広がる点も大きな強みといえます。
土地活用の人気ランキングトップ10
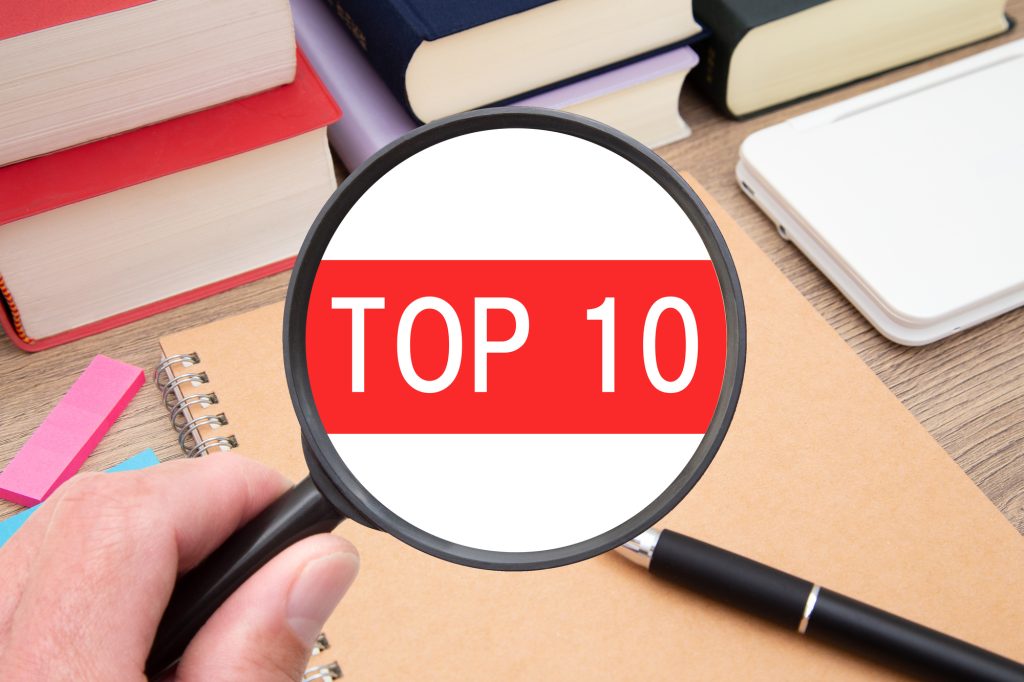
土地活用にはさまざまな方法がありますが、どれが最適かは立地条件や活用の目的によって大きく変わります。とはいえ、多くのオーナーが選んでいる定番の手法には、それぞれ人気を集めるだけの理由があります。
そこでここでは実際に利用者が多い活用法をランキング形式で紹介します。それぞれのメリットや向いているケースを知ることで、自分の土地に合った活用法のイメージがぐっと具体的になるはずです。
1位:アパート・マンション経営
アパートやマンションは家賃収入を得る定番の方法として、多くの土地オーナーから選ばれている方法です。特に交通アクセスの良い場所や人口の多い地域では入居が安定しやすく、長期的な収益につながります。
建物を建てるにはそれなりの資金が必要ですが、相続税や固定資産税の節税効果も見込めるため、税金対策として用いられるケースも多いです。
資産としての価値を維持しながら、老後の備えや子どもへの相続にも役立つため、入居者が安定すれば、収入と節税の両方で効果的な選択肢といえるでしょう。
2位:駐車場経営
初期コストを抑えて始めやすい方法として人気が高いのが駐車場の運営です。建物を建てる必要がないため、活用を始めるまで時間もかかりにくいです。
都市部であれば短時間利用のコインパーキング、住宅地では月極契約など、地域のニーズに応じて運営スタイルを変えられる柔軟さも魅力のひとつです。さらに、更地に近い形で管理できるため、将来的に別の用途に転用しやすいというメリットもあります。
3位:賃貸併用住宅
賃貸併用住宅とは、自宅の一部を貸し出して家賃収入を得る方法です。建物の下層階を貸し出して、上層階を住宅に使うパターンが一般的です。
この方法は、自宅で収益を得ながら住み続けられるのが大きな強みです。新築でもローンの返済を家賃で補えるため、比較的資金計画を立てやすいです。また、設備トラブルや入居者対応などに対応しやすいメリットもあります。
4位:戸建て賃貸
戸建て賃貸はファミリー層を中心に根強い需要がある活用方法です。アパートに比べて居住空間が広く、プライバシーも確保しやすいため、子育て世帯や長期入居を希望する方から選ばれやすい傾向があります。
空室期間が短く、安定した賃貸経営につながりやすいメリットがあるほか、建物の状態を良好に保てば、将来的に売却が見込める点も大きな魅力です。
5位:トランクルーム経営
都市部を中心に需要が拡大しているのが、収納スペースを貸し出すトランクルームです。
トランクルームの大きなメリットは、施工の簡単さと利回りの良さにあります。コンテナを置くタイプであれば、建物を建てるよりも安価かつ短期間で始められますし、利回りも10~20%程度と高い傾向にあります。仮に15%であれば、7年で元手を回収できる計算になります。
ただ、実際の成果は周辺地域の収納需要に大きく左右されます。必ず市場調査を念入りに行い、初期費用の回収見込みを立てたうえで始めましょう。
6位:太陽光発電
建物が建てられない場所や、建物の需要がないエリアで選ばれることがあるのが太陽光発電施設の設置です。電力会社と1kWあたりの単価を決めて売電契約を結ぶことで収益を得ることができます。
ただし、発電量が土地の面積に依存する点や、立地や土地の形状によって発電効率が下がる可能性がある点には注意が必要です。また、山の斜面のような傾斜地では、無理に設置すると大雨のときに土地が崩れるリスクが伴うのでおすすめしません。
7位:老人ホーム・介護施設経営
高齢化が進む日本において需要が高まっているのが、老人ホームや介護施設です。土地や建物を長期間にわたって貸し出すため安定した収入を確保でき、アパートや貸し店舗のように空室リスクもありません。
ただし、都市計画法や建築基準法などの法令に基づく開発許可や建築確認に加え、老人福祉法などの福祉関連法令に準拠した手続きや行政との協議が必須になります。専門知識を持つ事業者と連携し、計画を慎重に進めましょう。
8位:事業用定期借地
事業用定期借地とは、法人や事業者に土地を貸し出すことをいいます。建物の敷地や店舗の駐車場などで貸し出すことができれば、10年以上の長期契約も見込めます。
主な使い道には店舗や倉庫、工場、それらに付帯する駐車場などがあります。もし、まとまった土地を持っているのであれば一度検討してみたい方法です。
9位:コインランドリー経営
共働き世帯や単身世帯の増加に伴って需要が高まっているのがコインランドリーです。
コインランドリー経営のメリットは、基本的に無人で運営できることと、年間10%前後の利回りにあります。約10年で初期費用を回収できる計算なので、長期間にわたって用途を縛られにくいという特徴があります。
ただし、売上が周辺の需要に大きく影響される点には注意しましょう。住宅地や駅前など、人の往来が多く生活動線上にある土地を持っている方には、安定した収益を狙える選択肢になるでしょう。
10位:広告スペース
人通りや車の通行量が多い場所に土地を持っている場合は、広告スペースとして貸し出す方法もあります。狭すぎる土地の活用方法としても考えられるでしょう。
広告スペースのメリットは初期投資がほとんどかからず、設置後の管理もほぼ必要ない点です。広告の募集や管理は、看板を立てた広告会社が行うのが一般的なため、土地の所有者は土地を貸し出すだけでOKです。
なお、看板の設置には屋外広告物法および各自治体の屋外広告物条例に基づく許可が必要になります。許可を得ずに設置すると、是正勧告や撤去命令を受ける可能性があるため、必ず事前に確認し、適切な手続きを踏みましょう。
初期コストを抑えて始められる土地活用方法3選

土地活用というと「多額の資金が必要」というイメージを持つ方も多いですが、建物を建てずに貸し出す形や、小規模な設備投資で運用できる形であれば、比較的少ない初期費用で土地活用を始めることが可能です。そこでここでは、特に初期コストが低く、多くの人が始めやすい活用法を紹介します。
貸地(リース)
更地をそのまま企業や個人に貸し出し、駐車場や資材置き場、仮設事務所などに使ってもらう方法です。建物を建てる必要がないため、基本的に初期投資は必要ありません。ただし、土地の形が悪く整地する必要がある場合や、ブロック塀や擁壁の設置が必要な場合など、土地の状態を整える必要がある場合は初期投資が発生します。
リースのメリットは、契約内容によっては長期的な地代収入が期待できることです。特に事業用地として貸し出すことができれば、10年以上の契約も見込めます。
貸し農園・シェア畑
使わない農地がある場合は、土地を区画分けして、近隣の住民に貸し出すのも一つの手です。自分の区画で野菜や果物を育てられるため、健康志向の方や食育への関心が高い方、子育て世帯などからの需要が増えています。
設備として必要なのは、水道や簡易倉庫、農具置き場程度なので、初期費用を抑えられるのも魅力です。地域交流を促進しながら収益化したい方や、農業体験を通じて地域の活性化に貢献したい方に向いています。
自動販売機・キッチンカー置き場
自動販売機やキッチンカー置き場は、スペースさえ確保できればよいため、準備がほぼ必要なく手軽です。設置・運営は設置者が行うため、場所を提供するだけで定額の使用料を得られます。
ただし、売上が周辺の人口や交通量に大きく影響される点には注意が必要です。省スペースで収益を生みたい方や、土地の一部を活用したい方におすすめです。
土地活用で気を付けるべき4つのリスク

どんなに魅力的な土地活用プランでも、空室が続いて家賃収入が減るリスクや、自然災害で建物が損傷して大きな修繕費が発生するリスク、金利上昇でローン返済が圧迫されるリスクなど、何かしらのリスクは抱えているものです。
こうした事態は、事前にリスクを把握し、対策を講じておくことで予防できる可能性があります。そこでここでは、特に注意しておきたい4つの代表的なリスクと、その回避策を解説します。
空室・賃料下落リスク
賃貸経営では、空室や家賃の下落は避けて通れない課題です。周辺に新築物件が増えたり、地域の人口が減ったりすれば、入居希望者が減って空室期間が長期化することもあります。さらに、家賃を下げないと契約が決まらない状況に陥る可能性もあります。
このリスクを減らすには、ターゲット層を明確にすることと、利用者の需要に合った間取りや設備を整えることが重要です。また、築年数が経過した物件の場合は、内装リフォームや設備更新で魅力を維持することや、写真や広告の質を高めて集客力を強化することが必要になってきます。
自然災害リスク
日本は地震・台風・豪雨といった自然災害が多いため、どこの地域にいても建物や設備が被害を受けるリスクが伴います。特にハザードマップに掲載されている、土砂崩れや水害のリスクが高いエリアにある場合は要注意です。
自然災害のリスクを少なくするには、ハザードマップでリスクを確認し、擁壁の設置や高基礎での建築など、必要な対策を行う必要があります。ただ、土砂崩れのレッドゾーンのように、特にリスクが高いエリアに指定されている場合は、利用者の安全を考えて、無理に活用をしない選択肢も考えるべきです。
金利・ローンリスク
アパートやマンションなどの建設費は高額になるため、多くの場合は金融機関から融資を受けて始めます。それだけに融資額も高額になりやすいため、借入のプランは慎重に選ぶ必要があります。
例えば、借入当時の金利が低かった変動金利を選び、その後に金利が想定以上に上昇した場合、毎月の返済が計画以上に膨らんで資金繰りを圧迫する可能性があります。
これを防ぐには、金利上昇を想定した複数の返済シミュレーションを行い、無理のない資金計画を立てることが不可欠です。また、変動金利よりも金利は高くなりますが、金利が変動しない固定金利を利用するのも有効な選択肢になります。
管理面でのトラブル
入居者同士の騒音トラブルや、設備の不具合、近隣住民との関係悪化など、管理面で問題が多発すると物件評価が下がる恐れがあります。こうしたトラブルは、放置すれば解決が長引き、空室や退去の原因になり、ひいては収益の低下につながる恐れがあります。
管理面でのトラブルを予防するには、契約時に使用ルールや禁止事項を明確にし、定期的な建物点検を行うことが大切です。オーナーが対応できない場合は、信頼できる管理会社に委託し、迅速なクレーム対応や修繕手配ができる体制を整えておきましょう。
【まとめ】土地活用は「資産」を最大限に活かす方法
この記事を通じて、土地活用にはさまざまな種類があり、それぞれ収益性やリスク、管理の手間が大きく異なることが見えてきたのではないでしょうか。立地や資金状況、さらには「土地を残したいのか、収益を最大化したいのか」といった目的によって、選ぶべき方向性も変わります。
同じ土地でも、持ち主の考え方次第で「負担の種」になるか「資産の柱」になるかが分かれるのが土地活用の特徴です。机上の比較だけで終わらせず、実際に自分の土地の条件をあてはめてイメージしてみることで、初めて現実的な選択肢が見えてきます。
今回得た知識をヒントに、どの方法が自分に合っているかを一度じっくり考えてみてください。その小さな一歩が、遊ばせていた土地を将来の安心につなげる大きな転機になるはずです。
判断が難しい場合は、ぜひ空き家や空き地の活用のプロフェッショナルである「アキサポ」の無料相談をご活用ください。多くの実績から、最善の土地活用を提案いたします。
この記事の監修者

岡崎 千尋 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
都市計画コンサルタントとしてまちづくりを経験後、アキサポでは不動産の活用から売買まで幅広く担当してきました。
お客様のお悩みに寄り添い、所有者様・入居者様・地域の皆様にとって「三方良し」となる解決策を追及いたします。








