公開日:2025.10.08 更新日:2025.09.29
【古民家差し上げます】無償譲渡の方法・注意点・活用事例を徹底解説

地方創生や移住支援の観点から注目を集めている「古民家差し上げます」。所有者にとっては固定資産税や管理コストから解放される手段になり、受け取る側にとっては移住支援や田舎暮らしの第一歩になります。
本記事では、古民家を無償で譲渡する方法や、押さえておくべき法的・税金上の注意点、譲渡後の活用事例まで詳しく解説するので、古民家を手放したいと考えている方はぜひ参考にしてみてください。
目次
古民家を手放すメリット

かつては生活の拠点であり、家族の思い出が刻まれた古民家。しかし現在では空き家となり、使われないまま放置されているケースが急増しています。そんな古民家は手放してしまうのもひとつの手。ここでは、古民家を手放すメリットをご紹介します。
管理費や固定資産税など維持費が不要になる
たとえ誰も住んでいなくても、古民家を所有している限り、固定資産税や都市計画税は毎年支払わなくてはなりません。さらに、庭の草刈りや樹木の伐採、雨漏りや害獣侵入を防ぐための点検といった管理コストも積み重なっていきます。無償譲渡によって古民家を手放せば、経済的・精神的負担も軽くなるでしょう。
解体費用の負担がなくなる
老朽化が進んだ古民家は、「このままでは危険だから更地にした方がよい」と判断されることがあります。しかし、延床面積や立地条件によって変動するものの、解体費用は木造住宅でも100万円~300万円程度、場合によっては500万円以上に達するケースも珍しくありません。
さらに、古い建物にはアスベストを含む建材が使われている場合があり、通常よりも高額な費用が発生する可能性もあります。
「古民家差し上げます」は、このような負担を軽減するための有効な手段の一つ。解体することなく新しい所有者へ引き渡すことで、解体費用の支出を免れると同時に、建物が持つポテンシャルを次の利用者に託すことができます。
特定空き家の指定を回避できる
管理されない古民家は老朽化が加速し、周囲に悪影響を及ぼす危険性があります。例えば瓦の落下による事故、倒壊による近隣住宅への損害、衛生環境の悪化などです。こうした状態が続けば、自治体から「特定空き家」に指定される恐れがあります。
特定空き家に指定されると固定資産税の住宅用地特例が外れ、税負担が増加。さらに改善命令に従わなければ、行政代執行によって強制的に解体され、その費用を所有者が負担しなければならない事態に発展します。
古民家を早めに譲渡し、管理や活用を担ってくれる新しい所有者にバトンを渡せば、こういったリスクの回避にもつながるでしょう。
移住支援や地域貢献、地方創生につながる
古民家を手放すことは、単に負担をなくすだけでなく、地域社会にとっても大きな意味を持ちます。地方で暮らしたいと考える移住希望者にとって、住まいを確保することは最初の大きなハードル。無償譲渡された古民家がその受け皿となれば、移住支援の一環となります。
さらに、新しい住民がリノベーションを行い、古民家を住居や店舗として再生すれば、地域経済に新たな動きが生まれます。「古民家差し上げます」は、人口増加と経済循環の再生を促し、地域社会活性化にも貢献できるのです。
「古民家差し上げます」を実現する方法3選

古民家を無償で譲渡する場合、思いつきで「差し上げます」と声を上げても、すぐに引き受け手が見つかるわけではありません。譲渡を成立させるには、現実的で効果的な手段を選ぶことが大切です。ここでは代表的な3つの方法を紹介します。
隣地所有者に無償譲渡する
もっともシンプルな方法が、隣地所有者への譲渡。敷地の境界を広げることで庭や駐車場としての活用、敷地全体をまとめて再開発するなど、合理的な利用方法が見込まれるため、隣接する土地を所有している人にとっては、利用価値が一気に高まります。
また、すでに面識のある相手である場合が多いため、交渉が比較的スムーズに進む点もメリットです。当事者同士の話し合いで完結するため、都市部の不動産売買のように複雑な宣伝活動や仲介も不要。相手の意向や資金状況も把握しやすく、スピード感を持って話を進められるでしょう。
もちろん、無償とはいえ不動産の所有権移転登記や贈与契約書の作成といった手続きは必須です。
空き家バンクを活用する
「空き家バンク」とは、空き家や古民家を所有者と利用希望者の双方に紹介するサービスのこと。多くの自治体で導入されており、地方移住を検討する人にとっての主要な情報源となっています。
空き家バンクは、信頼性の高さと公的支援が充実している点がメリット。自治体担当者が仲介的な役割を果たし、利用希望者とのマッチングをサポートしてくれる場合があります。移住支援やリフォームに対する補助金制度と連動していることも多く、古民家を引き継ぐ側の負担を軽減できる点も魅力です。
一方で、登録からマッチング成立までには時間がかかることもあります。また、自治体ごとに登録条件や掲載基準が異なるため、事前に詳細を確認した上で利用するようにしましょう。
民間サイトを活用する
近年では、空き家や古民家の譲渡を仲介する民間のマッチングサイトも増えています。これらのサイトは全国規模で利用者を募っているため、空き家バンクよりも幅広い層にアプローチできるのが強みです。
「古民家を探している移住希望者」「セカンドハウスとして利用したい都市住民」「リノベーションによる事業展開を考える起業家」など、古民家を探している人のニーズはさまざま。民間サイトを利用すれば、こうした多様な利用者に物件情報を届けやすくなるでしょう。
ただし、民間サイトは自治体の制度に比べて公的保証が少ない分、契約の詳細や責任範囲は自己管理となります。そのため、契約書作成や不動産登記のサポート先を自ら確保しなくてはならない点には注意が必要です。
「古民家差し上げます」と伝える前の事前準備

無償譲渡を検討する際、もっとも重要なのは「準備段階の徹底」です。建物や土地の状態を確認せずに「差し上げます」と声を上げても、交渉の途中で問題が発覚し、破談に終わることがあります。さらに権利関係が曖昧なまま譲渡を進めれば、後に法的なトラブルを招く危険も。ここでは、譲渡を始める前に必ず整えておきたい3つの準備事項を解説します。
建物の状態確認
古民家は築年数が長く、劣化の度合いも物件ごとに大きく異なります。屋根の瓦がずれて雨漏りしていないか、柱や梁が腐食していないか、耐震性に問題はないかなど、物件の状態確認は素人目では難しいため、建築士など専門家の目で調査してもらうことが大切です。
事前に診断を受ければ、買い手に安心感を与えるだけでなく、譲渡条件の説明にも具体性を持たせられます。補修が必要な場合でも、「耐震補強工事に100万円程度かかる可能性がある」といった目安を事前に提示できていれば、後の誤解や不信感を回避できるでしょう。
土地・建物の権利関係整理
古民家の譲渡でもっとも注意したいのが権利関係です。例えば、法定相続分で相続登記が済んでいない物件だと、所有者が誰なのか法的に確定しないため、そのままでは譲渡契約を結ぶことができません。
また、共有名義の土地建物であれば、譲渡には共有者全員の同意が必要です。親族間で意見が分かれると交渉がストップしてしまう可能性もあるため、事前に調整を済ませておくことが欠かせません。
さらに、農地が含まれている場合、農地法第3条(権利移転)や第5条(転用)の許可が必要となります。無許可での譲渡は効力を生じないため、必ず行政書士や農業委員会に確認しましょう。
譲渡条件の整理
「建物と土地を一体で譲渡するのか、建物のみを対象とするのか」「残置物の処分は所有者が行うのか、引き受け手に任せるのか」などの条件を曖昧にしたまま話を進めると、契約直前で食い違いが発生します。
また、譲渡後の修繕やリフォームについても「現状渡しである」「耐震補強は譲受人が負担する」といった条件を明示しておくべきです。さらに、譲渡後に固定資産税や維持管理責任が新所有者に移ることも明確に伝えておくとよいでしょう。
こうした条件整理は、贈与契約書の基盤となる重要な作業です。口頭で説明するだけでなく書面にまとめておけば、後々の誤解を防ぎ、安心して譲渡を進めることができます。
「古民家差し上げます」を行う際の注意点【契約・税金・修繕費】
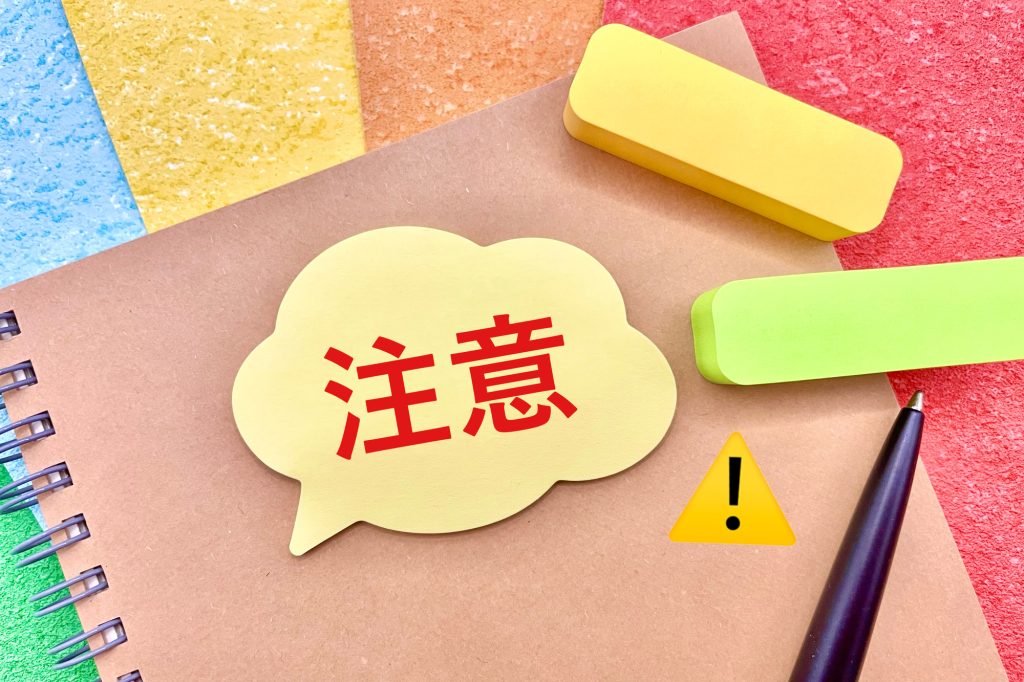
「古民家差し上げます」は、無償だからこそ簡単に手続きを済ませられると考えがちですが、契約や税金、修繕費など重要なポイントを見落としてしまうと、思わぬトラブルが発生することも。
古民家譲渡時の注意点をまとめたので、事前にしっかり確認しておきましょう。
譲渡契約書を作成する
無償譲渡だからといって口約束だけで済ませるのは危険です。不動産の権利移転において、契約書は紛争を防ぐもっとも基本的な手段であり、双方の安心にもつながります。物件の所在地や面積、譲渡条件、引き渡し日、残置物の扱い、修繕義務の有無など、重要事項を必ず文書に落とし込んでおくようにしましょう。
特に「現状有姿での譲渡」と明記することが肝心です。これは現状のまま引き渡すという意味で、譲渡後に発見された瑕疵(欠陥)については、原則として譲渡者が契約不適合責任を負わないことを示します。これを贈与契約書に明記していなければ、譲渡後にシロアリ被害や雨漏りが発覚した際に契約不適合責任を問われる可能性があるため注意が必要です。
不具合や欠陥の有無を伝える
契約書の条項で「現状有姿」を明記することに加え、事前に分かっている不具合や欠陥は誠実に伝える必要があります。屋根の老朽化、耐震性不足、給排水設備の不具合、雨漏りやシロアリ被害などを伏せたまま取引すると、後から「聞いていなかった」とトラブルに発展する可能性が高まります。
もちろん、不具合をすべて修繕してから譲渡する必要はありません。しかし、情報を開示しておくことで、譲受人は必要な修繕費を見積もりやすくなり、契約の透明性も保たれます。
無料譲渡でも費用がかかる点を理解する
「古民家差し上げます」と言うと、費用ゼロで済むと思われがちですが、実際には税金や登記費用、修繕費などが発生します。以下、主な費用をまとめました。
贈与税
無償譲渡は税法上「贈与」として扱われるため、受け取った側には時価に基づく贈与税が課される可能性があります。例えば評価額が高い場合、受け取った側に数十万円規模の税負担が生じるケースも。ただし、親族間での譲渡や基礎控除の範囲内であれば非課税となる場合もあるため、不明な点がある場合は税理士へ相談することをおすすめします。
不動産取得税
譲渡を受ける側には不動産取得税が課されます。税率は土地・建物の評価額に対して数%で計算されるため、築古でも一定の税負担は避けられません。ただし、住宅用地に対する軽減措置や自治体独自の減免制度を適用できる場合も多いため、事前に確認しておくようにしましょう。
登録免許税
所有権移転登記の際には登録免許税が必ず発生します。建物や土地の固定資産評価額を基準に計算され、通常は数万円から十数万円程度。譲渡が無償であっても必要経費として計上しなくてはなりません。
修繕・リフォーム費
古民家を居住や活用のために使うには、多くの場合リフォームや補強工事が必要です。耐震補強、屋根の葺き替え、水回りの入れ替えなど、費用は数百万円単位に及ぶ可能性があります。補助金制度を活用できる場合もありますが、一定の費用がかかる点は把握しておくようにしましょう。
古民家の活用事例—譲渡後の具体的な再生・活用法

無償で譲渡された古民家は、その後どのように生かされるのでしょうか。単に「住む場所」としての役割を果たすだけでなく、リノベーションや地域資源としての再利用によって、新たな価値を生み出す可能性もあります。実際の活用例をご紹介するので、古民家の持つポテンシャルを具体的にチェックしていきましょう。
DIYリノベーションによる移住・セカンドライフ実現事例
都市部から地方へ移住し、譲り受けた古民家をDIYでリノベーションするケースは年々増えています。大工仕事やペンキ塗りを自ら行うことで費用を抑えつつ、自分好みの空間を作り上げていくプロセスは、暮らしの楽しみそのもの。
自分のこだわりが詰まったオンリーワンの家は、ひときわ愛着も生まれ、より充実したセカンドライフを楽しめるはずです。
DIYで生まれる新たな価値―自らもDIY物件に住む担当者が語る、DIYの魅力>>
古民家カフェ・宿泊やコミュニティ拠点としての再生事例
譲渡された古民家を、住居ではなくビジネスや地域活動の拠点として活用する動きも広がっています。代表的なのが古民家カフェや宿泊施設です。歴史ある木造建築の趣を残したまま、内装をリフォームして観光客向けに開放する。これにより地域外からの人の流れが生まれ、経済循環を促す効果が期待できます。
譲渡以外で古民家を手放す方法

古民家を手放す方法は譲渡だけではありません。物件や所有者の事情によっては、別の手段のほうが適している場合もあります。ここでは「寄付」「相続土地国庫帰属制度」「売却」について解説するので、ぜひご自身の物件に当てはまるかチェックしてみてください。
自治体に寄付する
一部の自治体では、公共利用を目的とした古民家の寄付を受け入れています。たとえば地域の歴史的建造物として保存したり、観光拠点や交流施設として活用したりするケースです。寄付が受け入れられれば、所有者は固定資産税や管理責任から解放されます。
ただし、耐震性や利用価値、立地条件などが基準を満たしていることが前提となる上、受け入れが決まるまでに長い審査期間がかかることも。また、自治体側にも維持管理費用の負担が生じるため、容易に実現できるものではありません。
寄付を検討する場合は、まず自治体の担当課に相談し、受け入れ条件を確認した上で判断するようにしましょう。
相続土地国庫帰属制度を利用する
2023年からスタートした「相続土地国庫帰属制度」は、不要な土地を国に返すことができる制度です。相続によって取得したが使い道がない土地や維持が困難な土地を、所有者の意思で国に引き取ってもらえる仕組みです。
ただし、建物が残っている土地は対象外です。古民家を含む建物は解体し、更地にしたうえでなければ申請できません。つまり、相続土地国庫帰属制度を利用するには、先に数百万円規模の解体費用を負担する必要があるため、古民家を残したい人や解体費を捻出できない人には不向きです。
一方で、「どうしても維持できない」「子や孫に負担を残したくない」という所有者にとっては有効な選択肢のひとつとなります。解体後の土地を手放すことで、将来的な固定資産税や管理責任を完全にゼロにできるのは大きなメリットです。
売却する
築年数の古い家でも、立地条件や状態によっては売却が可能な場合もあります。特に観光地に近い古民家や、リノベーション次第で賃貸や店舗利用が期待できる物件は、一定の需要が期待できるでしょう。
ただし、すぐに買い手がつくとは限らない点がデメリット。築年数が経過していることや修繕が必要であることから、数か月から数年を要することも少なくありません。
古民家譲渡を専門家がサポートする「アキサポ」の強み

古民家や空き家を手放したいものの、「どこに相談すればよいのか分からない」という方も少なくないはず。そんな時に心強い存在となるのが「アキサポ」です。ここでは、アキサポが提供する主なサポート内容を紹介します。
空き家や古民家活用に関する相談窓口
アキサポでは空き家に関する相談窓口を設置しており、「古民家を手放したいが、寄付や譲渡、売却のどれが自分に合っているか分からない」「固定資産税や解体費用が負担で困っている」といった悩みに対し、具体的な解決策を提示することが可能です。
一般的な不動産会社では「売却一択」となることが多いですが、アキサポは譲渡や活用の選択肢も含めて中立的にアドバイスを行う点が特徴。まだ空き家をどうするべきか具体的に決まっていない方でも、気軽にご利用いただけます。
専門家ネットワークと法務サポート
古民家の譲渡には、不動産登記、契約書の作成、税務の確認など専門的な手続きが不可欠です。個人が独力で進めるには限界があり、ミスやトラブルに発展する可能性もあります。
アキサポは司法書士や弁護士、税理士など専門家とのネットワークを持っており、必要に応じて法務や税務のサポートも実施。例えば「相続登記が未了なので譲渡できない」というケースでも、専門家の助けを得ながらスムーズに登記を完了させることができます。
移住希望者と空き家所有者のマッチング
「古民家差し上げます」を実現するための大きな課題となるのが、引き受け手探しです。一方で、地方移住を希望する人にとっても「安心して暮らせる住まいを探すこと」が大きな壁となります。
アキサポはこの両者をつなぐマッチング機能を備えており、単に物件を紹介するだけではなく、「この地域に移住したい」と考える希望者と、「この古民家を誰かに生かしてほしい」と願う所有者を引き合わせることが可能。双方の思いを結びつけることで、譲渡が単なる不動産取引にとどまらず、地域活性化やコミュニティ形成につなげやすくなります。
まとめ
「古民家差し上げます」という無償譲渡は、所有者にとっては維持費や解体費用の負担を減らす方法であり、受け手にとっては移住や新しい暮らしを始めるきっかけとなります。さらに、地域にとっても活用や再生による経済効果を生む手段にもなるため、所有者・受け手・地域のそれぞれにとって有益な解決策となるでしょう。
アキサポを通じて専門家のサポートを受けながら、万全の準備を整えて「古民家差し上げます」の実現を目指してみてください。
この記事の監修者

山下 航平 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
ハウスメーカーにて戸建住宅の新築やリフォームの営業・施工管理を経験後、アキサポでは不動産の売買や空き家再生事業を担当してきました。
現在は、地方の空き家問題という社会課題の解決に向けて、日々尽力しております。








