公開日:2025.11.06 更新日:2025.10.27
土地譲渡とは?仕組み・贈与や相続との違いから無償譲渡まで徹底解説

土地の譲渡は、単に売買契約による所有権移転だけでなく、贈与や相続などさまざまな形態を含む幅広い概念です。
土地という大きな資産を動かすにあたっては、税金や手続きの仕組みをしっかり理解する必要があります。特に無償譲渡や相続のような制度面では、思わぬ費用負担や手続きの煩雑さに戸惑うことも少なくありません。この記事では、土地譲渡の基本から費用、無償譲渡や特例制度などを総合的に解説していきます。
土地譲渡の話題は、空き家問題や過疎化の進行といった社会的背景からも注目されています。管理が難しくなった土地を無償で手放したい人と、活用して新たな価値を見出したい人のマッチングが増えているのも特徴です。こうした動きを踏まえ、どの制度を活用できるかを考えることが大切です。
本記事を通じて、有償譲渡と無償譲渡の違い、手続きの流れ、税金の考え方を理解すれば、損を避けて最適な判断が望めるでしょう。
譲渡は一度行うと取り消しが難しい行為です。最後まで読んで、具体的なステップを確認しましょう。
目次
土地譲渡の基本|定義と種類

まずは土地譲渡の意味と種類を整理し、似た制度との違いを理解しておきましょう。
土地譲渡とは、土地の所有権を他者に移転する行為全般を指します。これは、売買契約によって対価を得る「有償譲渡」と、贈与など対価を伴わずに所有権を移す「無償譲渡」の両方を含みます。
一見同じように所有権が移転しますが、その性質によって課税対象や必要な手続きが大きく異なる点が特徴です。どのような目的で土地を譲渡するのかを、事前に整理しておくことが重要です。土地譲渡にはいくつかの方法があり、代表的なものに売買・贈与・共有持分の放棄などがあります。
特に売買では譲渡所得税が課され、無償譲渡では贈与税の対象となることがあるため、両者の違いを正しく把握しておく必要があります。譲渡の種類を理解しておくことで、後に発生する費用や税金の負担を正確に見積もることができます。
土地譲渡の定義とは
土地譲渡の定義は、土地の所有者が持つ権利を他者へ移転することです。有償・無償を問わず広義に「譲渡」と呼ばれますが、一般的には売買契約による売却が多く見られます。
また、相続や遺贈によって所有権が移転する場合もありますが、税制や手続き上の扱いが異なるため、通常は「譲渡」とは区別されます。
譲渡・贈与・相続のそれぞれの特徴と違い
譲渡は売買など有償で行われ、土地を手放す側に譲渡所得税などが課される場合があります。
一方、贈与は無償で行われ、受け取る側に贈与税がかかる場合があります。
また、相続は死亡によって財産が移転し、相続税の対象となることがあります。贈与税と相続税は課税対象や税率体系が異なるため、混同しないように注意が必要です。
土地譲渡にかかる主な費用と税金

土地を他者に渡す際に知っておきたい費用や税金の基礎を整理しておきましょう。
通常の売買による土地譲渡では、譲渡所得税や住民税が発生します。特に譲渡所得税は土地を取得した際の取得費や譲渡時にかかった諸費用を差し引いた上で算定され、さらに所有期間の長短によって税率が異なる点が特徴です。
短期譲渡の場合は税率が高くなるため、譲渡時期をどう設定するかが大切な検討ポイントとなります。税金は確定申告で納めるケースがほとんどなので、必要書類も早めに準備しておきましょう。
無償で土地を譲渡する場合は、贈与として扱われることが多く、贈与税が発生する可能性があります。たとえば親から子へ土地を無償で譲る場合、受け取る子が贈与税を負担する立場となります。贈与税は譲渡所得税とは異なる計算方式のため、正確な税額を見積もるには税理士など専門家への相談も検討しましょう。
譲渡所得税・住民税の計算方法
譲渡所得税は、譲渡収入から取得費用と譲渡費用、そして特別控除を差し引いた譲渡所得(課税所得)とし、その金額に所定の税率を乗じて算出します。
所有期間が5年を超える「長期譲渡所得」は税率15%、5年以下の「短期譲渡所得」は30%と大きく異なる点に注意が必要です。さらに、復興特別所得税として所得税額の2.1%が加算されるため、合計の税負担を正確に把握しておくことが大切です。
贈与税がかかるケース
土地を無償で譲る場合は、一般的に贈与とみなされ、受け取る側に贈与税が課せられる可能性があります。
贈与税は年間の基礎控除額(110万円)を超える部分に課税され、多くの場合、不動産評価額を基準に計算されます。親族間の贈与でも、正式な贈与契約書を作成しておかないと、後々のトラブルにつながることがあります。内容を確認しながら慎重に手続きを進めましょう。
登録免許税・印紙税などその他関連費用
土地譲渡の際には、売買契約書に貼付する印紙税や、登記名義を移転するための登録免許税が必要となります。
登録免許税は土地の評価額や固定資産税評価額によって変わるため、事前の調査が欠かせません。また、土地家屋調査士や司法書士へ登記依頼を行う場合、その報酬も発生するため、諸費用をまとめて試算しておくと安心です。
無償譲渡とは?背景と手続き、法的ポイントを解説

空き家対策や地域活性化を背景に、不動産の「無償譲渡」への関心が高まっています。
無償譲渡とは、土地や建物といった不動産を対価なしで引き渡す行為のこと。不動産取引の一形態であり、法的には贈与契約(民法第549条)に該当します。譲受人にとっては初期費用を抑えられるメリットがある一方で、贈与の課税や、その後の維持管理費といった思わぬ出費が生じる可能性も。
そのため、契約前には書面や登記の確認を含めた十分な準備が必要です。
無償譲渡が増える背景とは?空き家問題と人口減少の影響
日本では少子高齢化と人口減少により、空き家が社会問題となっています。
相続により取得した不動産を維持できず、「手放したくても買い手がつかない」そんな状況から、無償譲渡という選択肢が注目されるようになりました。
特に地方や過疎地域では土地需要が低いため、誰かに有効活用してもらいたいとの思いから譲渡されるケースが増えています。また、国土交通省の「空き家バンク制度」など、自治体主導のマッチング施策も後押ししています。
無償譲渡の具体的な手続き・流れ
無償譲渡を行うには、まず贈与者と譲受人の間で贈与契約書を作成します。
土地の境界、税金の負担、引き渡し条件などを明文化し、トラブルを防ぎましょう。その後、法務局で登記変更手続き(不動産登記法)を行い、所有権を正式に移転します。贈与税の対象となる場合は、譲受人が確定申告を通じて納税する必要があります。
書類の不備や登記ミスがあると、後々の紛争や課税リスクにつながりかねません。不安がある場合は、司法書士や税理士といった専門家への相談をおすすめします。
無償譲渡のメリットとは?

無償で土地や建物を取得できることは、大きな経済的メリットがあります。
中でも最大の利点は、購入費用をかけずに不動産を手に入れられる点。新規事業を始めたい人や、地方移住を検討している人にとって、初期コストを大幅に削減できる可能性があります。
ただし、無償譲渡を有効に活用するには、後述するリスクや法的手続きについても事前に把握しておく必要があります。
費用ゼロで取得できる不動産の価値
購入資金を投入せずに不動産を取得できることで、活用の選択肢が大幅に広がります。
例えば空き家を独自にリフォームしてカフェにする、自宅兼仕事スペースとして再活用するといった事例が増えています。実際に多額のローンを組む必要がないため、資金繰りの面でも安定しやすい利点があると言えるでしょう。
自治体による空き家活用の補助制度も検討対象に
地方自治体の中には、空き家再生や定住促進を目的とした補助金制度を設けているところもあります。代表的なものとしては、国の「地域移住支援事業」や、各市町村が独自に設ける空き家改修補助制度などがあり、改修費用の一部が補助される場合も。
無償譲渡を受けた不動産に対し、これらの制度を活用することで、取得後にかかる費用をさらに抑えることも可能です。
ただし、補助の対象や条件は地域によって異なるため、必ず各自治体の公式サイトや担当窓口で確認するようにしましょう。
無償譲渡のデメリットとは?
無償譲渡には大きなメリットがある一方、事前に確認しておくべきリスクも少なくありません。「無料で手に入る」ことに安心してしまうと、後から税金や維持費といったコストが重くのしかかる場合があります。
また、契約内容が曖昧なまま進めてしまうと、境界問題や登記トラブルにつながることも。リスクを正しく把握し、適切な対応をしておくことで、トラブルを回避しながら無理なく活用へとつなげられます。
贈与税や相続税との比較検討が必要
無償譲渡を受けると、贈与税が課される可能性があります。不動産の評価額が高額になると、想定以上の税額を負担しなければならないケースも。
特に生前贈与としての無償譲渡を検討する場合は、相続による取得とどちらが税制上有利か、あらかじめシミュレーションしておくことが重要です。税理士などの専門家に相談しながら進めると安心でしょう。
維持費・解体費・固定資産税…費用見積もりは必須
無償譲渡された土地に古屋(築年数が古く活用困難な建物)がある場合、リフォームや解体にかかる費用が意外と高額になることがあります。また、更地であっても、草刈り・境界管理・ごみ処理など定期的なメンテナンスが必要です。
さらに、所有している限り固定資産税の支払い義務も続きます。無償だからといってノーコストではないことを理解し、事前に概算で維持管理費を見積もることが大切です。
契約・登記・境界確認のポイントを押さえる
譲渡対象となる土地や建物の境界が不明確な状態で引き渡しを受けると、後々隣地所有者との境界紛争に発展する可能性があります。現地での立ち会いや、必要に応じた測量・境界確認を行っておくことが理想です。
また、契約書では以下の点を明確に記載しておきましょう。
・譲渡対象となる範囲
・贈与税・登記費用の負担者
・引渡しの時期・条件
これらの条件を曖昧にしたまま契約すると、後々のトラブルの原因となります。
不動産登記や契約書の作成には専門的な知識が求められるため、司法書士・行政書士などの専門家に相談することを強くおすすめします。
土地譲渡の手続きと必要書類
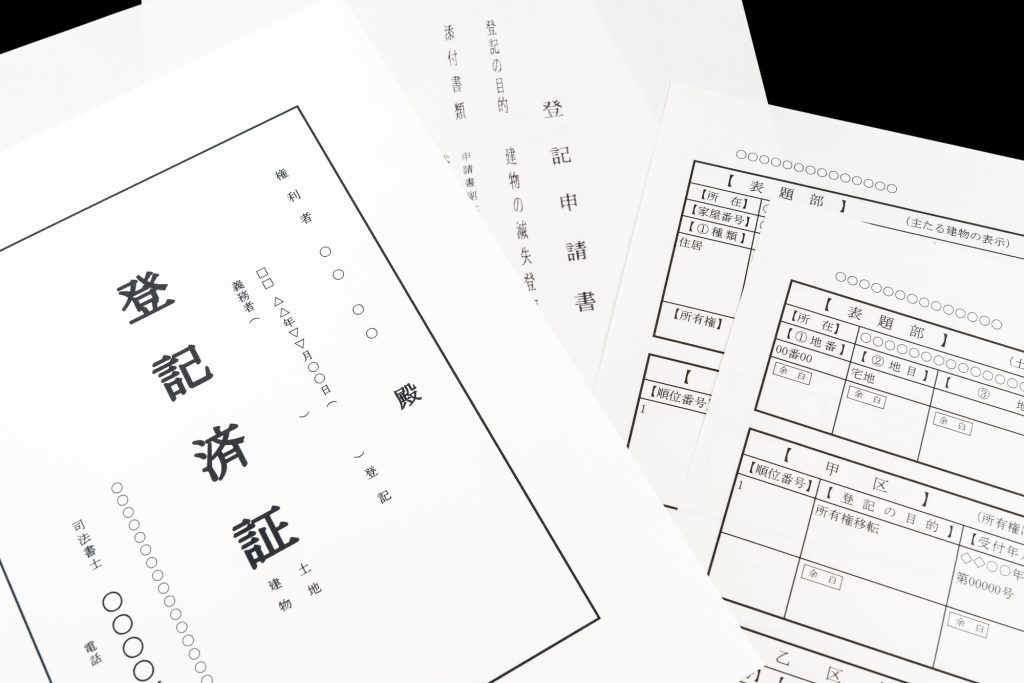
実際に譲渡を進めるには、契約手続きと登記に関する書類が重要となります。
不動産の売買契約は、基本的に売主と買主が条件を合意し、契約書を取り交わすところから始まります。手付金の受け渡しや決済時期、その他特約事項が記載された契約書は、公正証書にするかどうかなどの選択肢も検討するとよいでしょう。無償譲渡の場合でも譲与契約書を作成する手間は同じであるため、口頭だけで済ませないように注意することが大切です。
土地の売買契約フロー
一般的な売買契約では、まず不動産会社に査定を依頼し、売主と相談のうえで売り出し価格を決定します。その後、買主と条件がまとまれば重要事項説明を経て売買契約を締結し、手付金の授受を行います。
最終的には、残金を受け取る「決済」の場で、司法書士によって登記変更(不動産登記法)が実施され、名義変更と引き渡しが完了します。契約書は法的拘束力を持つため、公正証書として作成することで安全性がより高まります。
無償譲渡(贈与)に必要な契約書と登記手続き
贈与契約書は、贈与者と受贈者が合意のうえで作成され、贈与の主旨や土地の情報を明確に記載します。
登記手続きについては法務局で名義変更を行い、固定資産税を受贈者が支払うことになるため、早めの手続きが求められます。贈与税の申告や契約内容の法的トラブル回避にも関わるため、必要なら専門家のサポートを受けて手続きを進めましょう。
土地譲渡時に活用できる特例・控除制度とは?

土地を譲渡する際、特例や控除制度を活用することで課税額を抑えられる可能性があります。
所得税法や租税特別措置法などに基づく制度が複数あり、適用条件を満たすことで確定申告時の税負担を軽減できるのが特徴です。
主な制度は以下の通り:
・マイホーム特例(租税特別措置法第35条)
・低未利用地の特別控除
・相続税の取得費加算の特例(租税特別措置法第39条の2)
自分の状況にどの制度が該当するか、国税庁のサイトや税理士に確認することが第一歩です。
長期譲渡所得・短期譲渡所得とは?税率の違いと判断基準
土地を売却した際の譲渡所得は、保有期間によって課税区分が変わります。
・5年超の保有期間 → 長期譲渡所得(20.315%)
・5年以下の保有期間 → 短期譲渡所得(39.63%)
所有期間は「取得日から譲渡日まで」で判断されます。あと数ヶ月で5年を超える場合など、売却のタイミングを見直すことで税率を大きく下げられるケースも。
ただし、市場価格の動きや生活設計なども考慮し、総合的に判断することが大切です。
マイホーム特例(3,000万円控除)や低未利用地の特例
■ マイホーム特例(3,000万円控除)
自宅として利用していた土地・建物を売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
要件例:
・自ら居住していた物件であること
・売却前に住んでいた期間や売却先に制限がないこと
・直前に他の特例を使っていないこと など
■ 低未利用地の特別控除(最大100万円)
長期間使われていない土地(低未利用地)を活用促進の目的で売却する場合、譲渡所得から最大100万円の控除が受けられる可能性があります。この制度を利用するには、地方自治体が発行する「低未利用地該当の確認書」が必要です。
売却価格や用途、面積などの要件があるため、必ず確認しておきましょう。
相続土地の特例とは?取得後の早期売却で控除の可能性も
相続した土地を、相続開始から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却した場合、「相続税の取得費加算」という特例が適用されることがあります。
これは、相続税を支払った人がその土地を売却することで、支払った相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算できる制度です。結果として、譲渡所得額が抑えられ、譲渡所得税の軽減効果が期待できます。
ただし、要件が細かく、対象者・対象資産・相続税納税状況によって可否が分かれるため、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
まとめ・総括|最適な土地譲渡を行うために
土地譲渡を円滑かつ有利に進めるためには、制度への理解と事前準備が欠かせません。
譲渡には売買・贈与・相続といった複数の形態があり、どの方法を選ぶかによって税金や諸費用、必要な手続きが大きく異なります。特に無償譲渡(贈与)では、贈与税や登記、維持管理費といった隠れたコストへの対策が重要です。安易な口頭合意や確認不足は、境界問題や税務トラブルの原因にもなりかねません。
こうしたリスクを避けるためにも、
・特例制度や控除の活用可否を把握
・必要書類の正確な準備
・契約・登記における専門家(司法書士・税理士等)への相談
といったステップを丁寧に踏むことが大切です。
また、マイホーム特例・相続税の取得費加算・低未利用地の控除など、ケースに応じた節税制度の活用も検討材料となります。最適な土地譲渡を実現するには、「何を譲るのか」「誰に譲るのか」「どう譲るのか」を明確にし、制度・リスク・コストの三点を意識しながら行動に移すことが鍵となります。
焦らず、正確に、一つひとつのステップを確実に進めていきましょう。
この記事の監修者

山下 航平 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
ハウスメーカーにて戸建住宅の新築やリフォームの営業・施工管理を経験後、アキサポでは不動産の売買や空き家再生事業を担当してきました。
現在は、地方の空き家問題という社会課題の解決に向けて、日々尽力しております。








