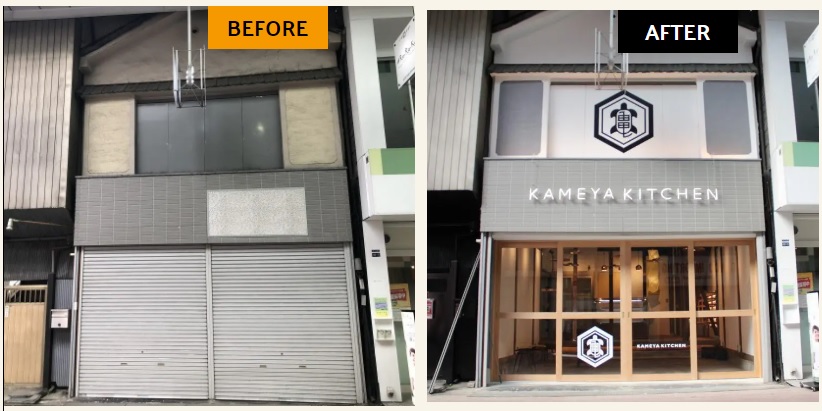公開日:2025.11.21 更新日:2025.11.14
建築面積とは?敷地面積・延床面積・建ぺい率のポイントを基礎から解説

「建築面積」という言葉は、その名の通り「建物が建っている部分の面積」ですが、具体的に建物のどこからどこまでが算入されるのでしょうか?この点を理解できていないと正確な建築面積を算出できません。
そこでこの記事では、建築面積の定義を押さえたうえで、敷地面積・延床面積・建ぺい率・容積率といった関連用語との違いや、建築面積が緩和される条件などの関連情報を分かりやすく解説します。
目次
建築面積の定義と基礎知識

建築面積とは、建築基準法施行令第2条第1項第2号によって定義されている「建物を真上から見たときの水平投影面積」のことです。外壁や柱の中心線で囲まれた範囲が基準となり、屋根やひさしが壁面よりも飛び出している場合は、その先端から1m後退したラインまでが含まれます。
たとえば、1階建ての場合は、1階部分の水平投影面積がそのまま建築面積となります。
また、複数階ある場合は、建物全体のうち「最も広い階の水平投影面積」を建築面積として扱います。たとえば1階よりも2階のほうが張り出して大きい構造なら、その2階部分の投影範囲が建築面積の基準となります。階数や高さではなく、「真上から見て最も広い部分」で判断する点がポイントです。
敷地面積・延床面積・容積率・建ぺい率との違い
建物の規模を把握するための指標には、建築面積のほかに、敷地面積・延べ床面積・容積率・建ぺい率などがあります。それぞれの概要は以下のとおりです。
- 敷地面積:建物がある敷地の面積
- 延床面積:建物のすべての床面積の合計
- 建ぺい率:敷地面積に対する建物の建築面積の割合
- 容積率:敷地面積に対する延べ床面積の割合
似た指標のため分かりにくいかもしれませんが、いずれも把握する目的や関連する法規などが変わってきます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
敷地面積
敷地面積とは、建物が建つ土地そのものの広さのことです。登記簿に記載された「公簿面積」と、実際に測量を行って得られる「実測面積」の2種類がありますが、公簿面積のデータが古いと測量の精度が低く、実測面積と一致しないケースもあります。
土地の広さを端的に把握するのに便利な値で、土地や建売住宅などの売り出しでよく目にすると思います。また、建築における建ぺい率や容積率の算出によく用いられるほか、土地の固定資産税も敷地面積に面積当たりの税額をかけて求められます。
これらの他にも、建築確認申請や土地の売買契約、住宅ローンの審査など、行政手続きや不動産取引のあらゆる場面で参照される項目です。
延床面積
延べ床面積(延床面積)とは、建物のすべての階の床面積を合計した面積のことです。1階建ての住宅であれば、その1階部分の床面積が延べ床面積になり、複数階ある場合は、各階の床面積をすべて合計した値が延べ床面積になります。
たとえば、各階の床面積が、1階50㎡、2階45㎡、3階40㎡の場合は、延べ床面積は「50+45+40=135㎡」となります。
延べ床面積が用いられるシーンとしては、建物を売買や賃貸のように、建物の規模を把握する必要があるときや、建築確認における容積率の算出、建物の固定資産税を課税する際の基準などが挙げられます。
建ぺい率
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合を示す指標です。建物が敷地のどの程度を占めているかを数値化したもので、都市計画法に基づいて指定される用途地域によってエリアごとに上限が定められています。
一般的に、住居系の用途地域のようにゆとりが求められるエリアでは上限が低く、商業系の用途地域のように、なるべく建築面積を広く取りたいエリアでは上限が高くなる傾向にあります。
たとえば、敷地面積が100㎡で建ぺい率の上限が60%の場合は最大で60㎡まで。敷地面積が200㎡で建ぺい率の上限が80%の場合は最大で160㎡までが認められることになります。
なお、建ぺい率は用途地域によって複数のパターンがあるため、用途地域が同じでも場所によって異なる場合があります。また、地区計画や建築協定によって、個別に指定されているケースもあります。
容積率
容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合を示す数値です。都市計画法に基づいて用途地域ごとに上限が定められており、一般的に住宅系の用途地域のようにゆとりが求められるエリアでは上限が低く、商業系の用途地域のように延べ床面積を多く取る必要があるエリアでは高くなる傾向にあります。
容積率が用いられる場面としては、建築確認申請で建物の規模を審査するときや、土地の購入・開発計画を立てる際などが挙げられます。特に新築や建て替えの際には、容積率の上限を超えていないかが建築許可の判断基準となるため、設計段階で必ず確認する必要があります。
また、不動産の売買や資産評価の場面でも重要な指標になります。容積率が高い土地は建物を多層化できるため、将来的な活用の自由度が高く、資産価値が上がる傾向があり、反対に、容積率が低い地域では建物の高さや延べ床面積に制約がかかるため、ゆとりある居住環境を維持しやすいという特徴があります。
建築面積に含まれるスペース・含まれないスペース

建築面積を算出する際に特に注意が必要なのが建物に付随する部分の扱いです。特に、バルコニーや庇、中庭、カーポートなどは、構造によって算入するか否かが変わるので気を付けましょう。
ここでは、以下の3パターンについて、具体的なケースを例示しながら、算入するケースとしないケースを紹介します。
- バルコニーやひさし・庇
- 中庭・カーポート・デッキ
- 出窓・階段部分
バルコニーやひさし・庇の扱い
バルコニーやひさし・庇は、外壁からどの程度突き出しているかによって扱いが変わります。原則としては、外壁面から1m未満の突出であれば建築面積に算入せず、1m以上突出している場合は、その先端から1m後退した部分までを建築面積に算入します。
このとき、庇やバルコニーに柱や屋根があると、その構造が「建物の一部」とみなされやすくなります。特に、固定式の屋根や囲いがあると、室内とほぼ同様の扱いになるケースが多いです。
ただし、開放的な造りで通風や採光を目的としている場合など、自治体によっては緩和措置が設けられていることもあります。最終的な判断は建築確認申請の段階で行われるため、設計時に建築士や自治体へ確認しておくことが大切です。
中庭・カーポート・デッキが算入される範囲
中庭は、屋根がなく完全に開放されている場合は建築面積に含まれませんが、柱や屋根が設けられていると半屋外空間として算入対象になる場合があります。たとえば、中庭の一部に屋根付きテラスがある場合、その範囲は建築面積に含まれることが多いです。
カーポートは、屋根と柱が固定されていれば壁がなくても建築物とみなされ、建築面積に含まれるのが一般的です。ただし、柱の本数や構造によっては緩和規定の対象となることもあります。地域によって運用基準が異なるため、計画段階で確認しておくことが望ましいです。
また、デッキは、地面との高さや屋根・囲いの有無によって扱いが分かれます。単なるウッドデッキであれば除外されることが多い一方、柱や屋根を備えている場合は建物の一部として扱われやすくなります。建ぺい率計算で誤りが生じないよう、設計段階で算入要否を明確にしておきましょう。
出窓・外部階段が算入される条件
出窓は、外壁からの突出度や構造によって算入するか否かが変わります。明確な基準は定められていませんが、実際の運用上では、外壁からの突出が50cm以内で、下部に支えがない構造であれば算入せず、出窓の奥行きが50cmを超える場合や、床面と連続していて下部に柱や支えがある場合は、建物の一部とみなされて算入するケースが多いです。
出窓の扱いについては、自治体によっては細かな判断基準を独自に設けているため、設計段階で担当建築主事や建築士に確認しておくと安心です。
また、外部階段は屋根や外壁で囲まれた閉鎖的な構造であれば算入するのが基本ですが、片側が大きく開放されている階段や屋根のない形式は算入しないことが多いです。出窓や階段はデザイン上のアクセントになる反面、建ぺい率や容積率に影響する要素でもあるため、早い段階で算入の有無を整理しておきましょう。
建築面積が緩和される条件

建築面積は、建物の構造や、立地している敷地の条件などによって緩和されるケースがあります。主な緩和条件は次の3つです。
- ピロティ構造による緩和
- 庇やバルコニーなど部分構造による緩和
- 敷地条件による緩和(角地・歩道状空地など)
では、具体的にどのような条件下で緩和されるのか、それぞれ詳しく見ていきましょう。
ピロティ構造による緩和
「ピロティ構造」とは、1階部分を柱のみで支えた構造のことを言います。代表的なケースとしては、1階部分をピロティ構造にして駐車場として利用し、2階から上を住居にする使い方です。
これにより、限られた敷地でも車庫スペースを確保しながら、建ぺい率の上限を超えずに設計することが可能です。
ただし、ピロティが緩和の対象となるには、以下のような条件をクリアする必要があります。
- 通路や車庫として常時開放されていること
- 外壁で囲まれていないこと(柱だけで支持されている構造)
- 居室や収納として利用しないこと
これらの要件を満たさないと、通常の建築物と同様に扱われて建築面積に算入されてしまいます。ピロティを取り入れる際は、あらかじめ自治体や建築確認の審査機関などに確認しておきましょう。
防火地域における耐火建築物への緩和
敷地が防火地域または準防火地域にある場合、建物を「耐火建築物」とすれば建ぺい率の緩和を受けられる場合があります。
ここでいう耐火建築物とは、建築基準法によって定められた一定の基準を持つ建築物のことで、火災が発生しても一定時間構造体が崩壊・延焼しない性能を持つことが求められます。代表的な例としては、鉄筋コンクリート造や鉄骨造、防火被覆を施した建物が該当します。
この緩和を受けるためには、防火地域の指定内容や建築物の構造種別を満たしている必要があります。個人で調べるのは難しいので、設計時に専門家に確認してもらいましょう。
角地における建ぺい率の緩和
敷地の二方向が道路に面している角地では、火災時の避難や消火活動が行いやすく延焼の危険性も低いとされているため、特定行政庁が定めた条件により建ぺい率が10%緩和される場合があります。
たとえば、建ぺい率60%の地域で角地に該当する敷地であれば、最大70%まで建築可能となります。
また、緩和を受けるには以下のような条件を満たす必要があります。
- 二方向が幅員4m以上の道路に接していること
- 道路に面する長さが一定以上あること(10m以上のケースが多い)
- 角地としての形状が明確に認められること
ただし、場所によっては地区計画や建築協定などの別途制限が設けられているケースもあります。角地なら緩和できると思い込まず、必ず自治体ごとの基準を確認しておきましょう。
まとめ・総括|建築面積を理解して正しい建築計画を
一見単純そうに思える建築面積ですが、じつは細かなルールが定められており、さらにバルコニーやカーポートのように建物の作りで算入するか否かが変わってくる部分もあるなど、面積を算出するには意外と学ぶべき点が多いことが分かったと思います。
特に、庇やバルコニー、ピロティ構造などは判断が分かれやすいため、自分だけで判断せずに、建築士や自治体に確認しておくことが重要です。
この記事の監修者

山下 航平 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
ハウスメーカーにて戸建住宅の新築やリフォームの営業・施工管理を経験後、アキサポでは不動産の売買や空き家再生事業を担当してきました。
現在は、地方の空き家問題という社会課題の解決に向けて、日々尽力しております。