公開日:2025.07.07 更新日:2025.08.12
家の解体費用と補助金制度の全知識|費用相場・申請手続き・相談先まで解説

空き家を放置しているけれど、いっそのこと解体するべき?そんなふうに悩んでいる方は少なくありません。そこで知っておきたいのが、費用の目安や各地の補助金制度の活用方法、申請の手順や相談先など、家の解体に関するあれこれ。空き家を解体すべきかどうかの判断ポイントも踏まえて解説します。
目次
家の解体費用はいくらかかる?相場と内訳を知ろう

家の解体は、同じ坪数でもその建物の構造によって解体作業にかかる手間や時間が異なるため、費用に大きな差が出ます。想定外の出費やトラブルを防ぐには、まず費用の相場を把握しておくことが重要です。解体費用の内訳を確認しましょう。
木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など構造別の費用相場
建物の種類ごとの一坪あたりの解体費用の目安はこちら。
木造:3~5万円/坪
木造の建物は、比較的簡単なつくりになっており、重機の使用も最小限で済むことが多く、解体しやすい構造です。また、木材はリサイクル可能な素材として再利用されることもあり、産業廃棄物の処理コストが他の構造よりも抑えられるという特徴があります。
鉄骨造(S造):4~7万円/坪
鉄骨造の建物は、木造よりも頑丈なつくりで耐久性が高い一方で、解体費用も高くなりがちです。解体には専用の重機を使って鋼材を切断する作業が必要になるうえに、解体後に出てくる鉄くずの分別や運搬処理にもコストがかかるでしょう。
鉄筋コンクリート造(RC造):6〜9万円/坪
鉄筋コンクリート造の建物は、常に丈夫で構造がしっかりしている分、工事にかかる手間や時間がかかり、もっとも高額になりがちです。解体には、圧砕機やブレーカーなどの大型の重機でコンクリートを砕きながら鉄筋を取り除く必要があります。また、コンクリートガラ(破片)は、産業廃棄物としての処分費が高額になる傾向があります。
立地の環境や建物の状態によって異なる費用要因
同じ構造でも、家がどんな場所に建っているかや、建物に特殊な建材を使用しているかなどの条件によって費用が大きく変わってきます。
立地の環境
前面道路の幅が狭く重機やトラックが入れない場合、小型重機の使用や手作業が増えるため、費用が高くなります。また隣家が近い場合、近隣住民への配慮が必要になるため、防音や防塵などの追加費用がかかることも。
建物の状態
1980年代以前に建てられた家には、アスベスト(石綿)が断熱材や外壁に使用されていることがあります。アスベストは吸入すると健康被害を引き起こすため、「大気汚染防止法」に基づき事前調査と専門業者による適切な除去作業が義務付けられています。使われているアスベスト建材の種類によって危険性が異なり、場合によっては数十万円〜数百万円と高額になるケースも。
空き家・老朽化物件ならではの追加費用に注意
空き家や築年数の古い建物を解体する場合、通常の解体費用だけでなく、追加費用が発生する前提で計画を立てることが大切です。
ゴミや不用品の大量放置
空き家の場合、家具・家電・生活ゴミ・農機具などが長年使われずにそのまま残っているケースがあります。解体作業に入る前にこれらを撤去する必要があるため、ゴミの処理費用がかかることも予想できます。
倒壊や腐食による作業リスク
老朽化した建物の場合、壁や天井が崩れたり部材が落下したりすることで、作業中に倒壊する危険性も考えられるでしょう。安全性の確保や解体手順の工夫が必要となり、通常よりもタイムコストをかけて解体を進めなければなりません。
害虫・害獣被害の可能性
空き家はシロアリやネズミなどの害虫・害獣の住処になっているケースがあります。解体中にそれらが発見されると、駆除や処分の別途対応が必要です。
地中埋設物の存在
古い建物を解体する場合、地中から廃材や井戸、浄化槽などが出てくることも珍しくありません。これらはすべて産業廃棄物として処分する必要があり、追加費用と作業時間がかかります。
家の解体で使える補助金制度とは?

家の解体には決して安くない費用がかかるため、少しでも負担を軽減したいところ。実は、多くの自治体で解体に活用できる補助金制度が設けられています。ここからは、補助金制度の概要と目的、対象条件などを解説します。
自治体ごとの補助金制度の概要と目的
解体費用に使える補助金制度は、多くの自治体が導入している支援策です。とくに高齢化や人口減少が進む地域では、空き家の放置が深刻な問題に。空き家の整理は街の安全と再生に直結するため、以下のような社会的課題を解消するために補助金制度を設けています。
・空き家の老朽化による倒壊事故や災害時の被害を防ぐ
・街の治安・衛生・景観の悪化を防ぐ
・土地の有効活用を促して、地域の活性化を図る
対象となる物件の条件と補助金額の目安
自治体が提供している解体補助金制度は、どの建物でも対象になるわけではありません。「長期間使用されていない空き家であること」かつ「老朽化が進んでいて倒壊の危険があること」が主な対象となります。
<家の解体補助金の対象条件とは?>
①空き家である
一年以上使用されていないなど、居住実態がないこと。
②危険性がある
壁のひび割れや崩れ、屋根の破損や雨漏り、傾きや基礎の破損など、老朽化が進んで倒壊の危険があること。
③建物が住宅である
居住用の建物であること。店舗・倉庫・事務所・車庫などは対象外となることが多い。
<補助金額の目安>
一般的には、30~100万円前後の範囲で設定されていることがほとんど。上限は自治体によって異なりますが、実際の解体費用の50%以内とされているケースが多いです。
ただし、補助金の対象となるのは、建物本体の解体や廃材の処理など解体工事そのものにかかる費用です。登記費用や土地の測量費用は、原則として補助金対象外とされており、多くの自治体で明確に除外されています。
地域差に注意!補助金が出る市区町村例も紹介
補助金制度は、全国共通ではなく地域ごとのルールで運用されています。以下は、補助金制度を用意している市町村の実例です。
・東京都板橋区
最大50万円:昭和56年以降に建てられた老朽化住宅で危険な状態である
・神奈川県横須賀市
最大100万円:1年以上使われておらず、老朽化・危険度が高い
・兵庫県神戸市
最大30万円(木造)・最大50万円(鉄筋コンクリート造):景観や治安への悪影響を及ぼす空き家
なお、都市部や空き家の少ない地域では、補助金制度がそもそも設けられていないこともあります。物件所在地の自治体で制度が存在するかを必ず確認しましょう。
補助金を受け取るための申請手続きと注意点

制度を有効に使えば、解体費用の負担を数十万円単位で減らすことができます。申請に不備があって制度を活用できなかった…という失敗を防ぐためにも、申請手続きやルールをしっかりと理解しておきましょう。
申請時期・必要書類・審査プロセスの流れ
家の解体に補助金制度を利用する場合、事前の計画と丁寧な準備は不可欠です。申請方法や必要書類などは自治体ごとに異なるため、ここでは全体の流れを把握するための一般的な例としてご紹介します。
<申請時期>
補助金の申請は、着工後や解体済みの場合は制度の対象外となるのが一般的です。必ず、解体工事をはじめる前に申請しましょう。自治体によっては、申請期間が年度単位で限定されていることもあります。
<必要書類例(自治体により差異あり)>
・解体補助金交付申請書
・所有者(申請者)の本人確認書類
・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)
・使用実態がない空き家であることを証明する書類
・解体工事の見積書
・建物の外観写真(現状把握のため)
場合によっては、自治体が建物の老朽化度判定などの調査をおこなうこともあります。
<審査の流れ(一般的な例)>
①自治体で補助金申請
空き家がある自治体の担当窓口に相談し、必要書類を確認して補助金申請をしましょう。申請後は、自治体による書類確認と現地調査がおこなわれます。
②解体工事の実施
補助金を交付する基準を満たすと判断された結果通知書が届き、解体工事が実施できます。自治体によっては、工事の進捗を自治体に提出する場合もあります。
③自治体へ解体工事完了の報告
解体工事が完了したら、自治体に完了報告書を提出します。内容に問題がなければ、指定の口座に補助金が支払われます。
解体前に申請しないと対象外になるケースも
家の解体費用の補助金制度は、ほとんどの場合、解体工事の前に申請する必要があります。申請のタイミングを誤ってしまうと、補助金制度の対象外となる場合があるため、計画段階で早めに空き家がある自治体に相談しましょう。
申請から着金までの期間とスケジュール感
実際に解体補助金の申し込みから受け取りまでは、一定の時間がかかります。解体業者のスケジュールや天候の影響もあるため、3〜6ヵ月かかるのが一般的です。
①申請・交付決定:約1〜1.5ヵ月
②工事着手・解体完了:約1〜2ヵ月
③完了報告書提出・補助金の振込:約1〜1.5ヵ月
自治体によっては、申請受付期間が「毎年4月から2月末まで」など限定されている場合も。とくに年度末など、申請が重なる時期は審査や支払いに時間がかかりやすいため、早めに動くことをおすすめします。
解体すべきか残すべきか?判断のポイント
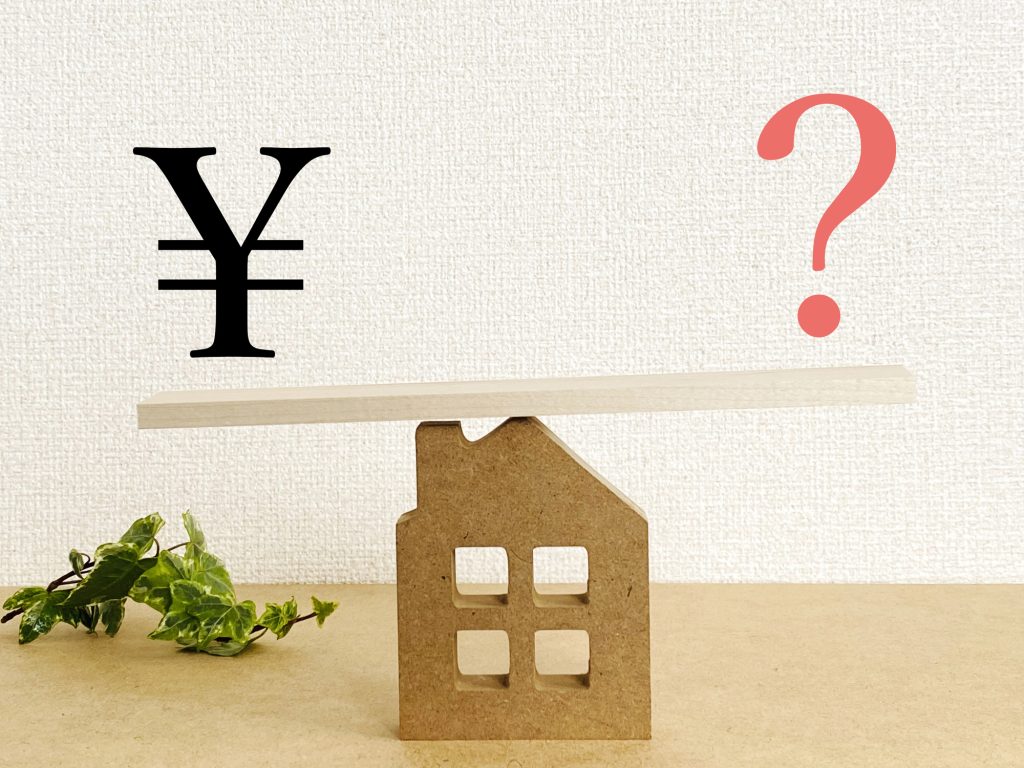
空き家を解体すべきか、それとも残すべきか。この判断は、管理責任・税負担・将来性の3つの観点から考えるのが賢明といえます。
老朽化による倒壊リスクと管理責任
空き家の老朽化が進んでいると、外壁、屋根の落下といった倒壊リスクが高まります。民法第717条では、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、占有者または所有者が損害賠償責任を負う」と定められています。
つまり、空き家が原因で事故が発生した場合、所有者は民法上の不法行為責任や工作物責任を問われる可能性があり、損害賠償を請求されるリスクがあります。実際に、老朽化した空き家の屋根が台風で飛んで隣家の車を破損させてしまった、外壁の一部が落下して通学中の子どもが怪我をしてしまったなどのトラブルから賠償責任へ発展したケースは、全国各地で起きています。
また、危険性の高い空き家として自治体から「空家等対策特別措置法」に基づき「特定空家等」と指定されると、行政代執行による強制解体や固定資産税の優遇除外といった措置が講じられる可能性があります。建物を残すための定期的な管理・補修が難しい場合は、解体も視野に入れて検討すべきといえるでしょう。
固定資産税との兼ね合いと「住宅用地特例」
空き家を解体すると、土地の固定資産税が上がるケースがあるため、税負担の観点も無視できません。現在、日本では「住宅用地特例」により、住宅が建っている土地もしくは、住宅があった土地には税金の軽減措置が適用されています。
そのため、とりあえず解体しよう!と空き家を更地にしてしまうと、翌年から住宅用地特例が使えなくなり、固定資産税が数倍に跳ね上がってしまう可能性もあります。
ただし、これは空き家を残しておくのが吉という意味ではありません。「特定空家」と指定されると、住宅用地特例自体が外されて、結果的に固定資産税が上がるケースも考えられます。
解体後の土地活用・売却可能性も加味して検討
空き家を解体する場合、更地にした後にどのようにその土地を活かすかまで具体的に考えておくことが大切です。たとえば、土地の活用には以下のような代表的なパターンがあります。
・月極駐車場にする
住宅街や駅周辺、オフィス街など、車の駐車需要があるエリアに向いています。
・貸し農園・家庭菜園スペースにする
高齢者層や家庭菜園ニーズの高い地域で有効。必要設備が少なく、小さな土地でも収益化しやすいのが特徴です。
・トランクルームやコンテナ置場にする
狭小地や変形地でも可能。業者に土地を貸すだけで運営を任せられます。
しかし、どんなに魅力的な土地でも、地域のニーズとあっていなければ収益は見込めません。不動産会社や地域の市役所などを活用して、地域の動向を調査したうえで検討する必要があります。また、土地の活用には、多かれ少なかれ初期費用や運営コストがかかります。回収に何年かかるのか、赤字にならないかなど、シミュレーションは必須といえるでしょう。
これらの土地活用のための準備や管理、運用を面倒に感じる場合は、更地にして売却するのもひとつの手です。ただし、売却に向いているのは、すぐに使える・活用しやすいと買手に判断されやすい更地です。交通アクセスやインフラの整備状況、生活環境が良いといった条件がそろっている場合は、比較的早く、高値で売却できる可能性が高いといえます。売却する場合でも、土地の状態や地域の市場に応じて判断しましょう。
アキサポなら補助金・解体・売却まで一括サポート可能です

空き家の問題は、放っておけばおくほどにリスクも負担も大きくなります。アキサポなら、補助金の申請から、解体・売却までトータルでお手伝い。何から手を付ければいいか分からない…という方こそ、まずはご相談ください。
空き家解体に関する無料相談窓口を完備
アキサポなら、物件の現状を診断し、解体が本当に最良の選択かどうかを含めたご提案が可能です。家を解体するまえに、知りたかった…と後悔するまえに、まずは解体に関する不安や疑問を払拭しておきませんか?もちろん無料でご相談可能です。
解体後の買取・売却・利活用までご提案
たとえば、すぐに現金化したいなら土地の買取・売却。相続税対策として更地を活かしたいなら月極駐車場や貸地への転用など、将来を見据えた選択肢を一緒に考えながら、後悔のないプランをみつけるお手伝いをします。
まとめ|解体費用も補助金も「知って得する」制度を最大限活用しよう

家の解体を検討している人が知っておくべき補助金制度や支援策は、全国の各自治体で整備されつつあります。物件を解体するか、それとも活かすのか。正しい判断をするためにも、まずは知ることからはじめましょう。
自治体制度を調べて申請を忘れずに
一定の条件を満たす空き家に対して、多くの自治体がその解体費用の一部を助成する制度を設けています。しかし、申請方法や必要書類のリサーチ不足だったり、解体後に申請手続きをして審査が通らなかったりすると、せっかくの制度が活用できないことになります。事前に確認・準備をしておくことが、将来の後悔を防ぐことにつながります。
アキサポで安心・安全な家の解体と利活用をサポート
やっぱり解体すべき?もし活かせるなら残したい…そんな迷いがあるならアキサポにご相談ください。アキサポなら、解体工事の安心・安全な実施をしっかりサポート。また解体後の更地の活用や家を残したまま利活用するプランもご提案します。
この記事の監修者

山下 航平 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
ハウスメーカーにて戸建住宅の新築やリフォームの営業・施工管理を経験後、アキサポでは不動産の売買や空き家再生事業を担当してきました。
現在は、地方の空き家問題という社会課題の解決に向けて、日々尽力しております。










