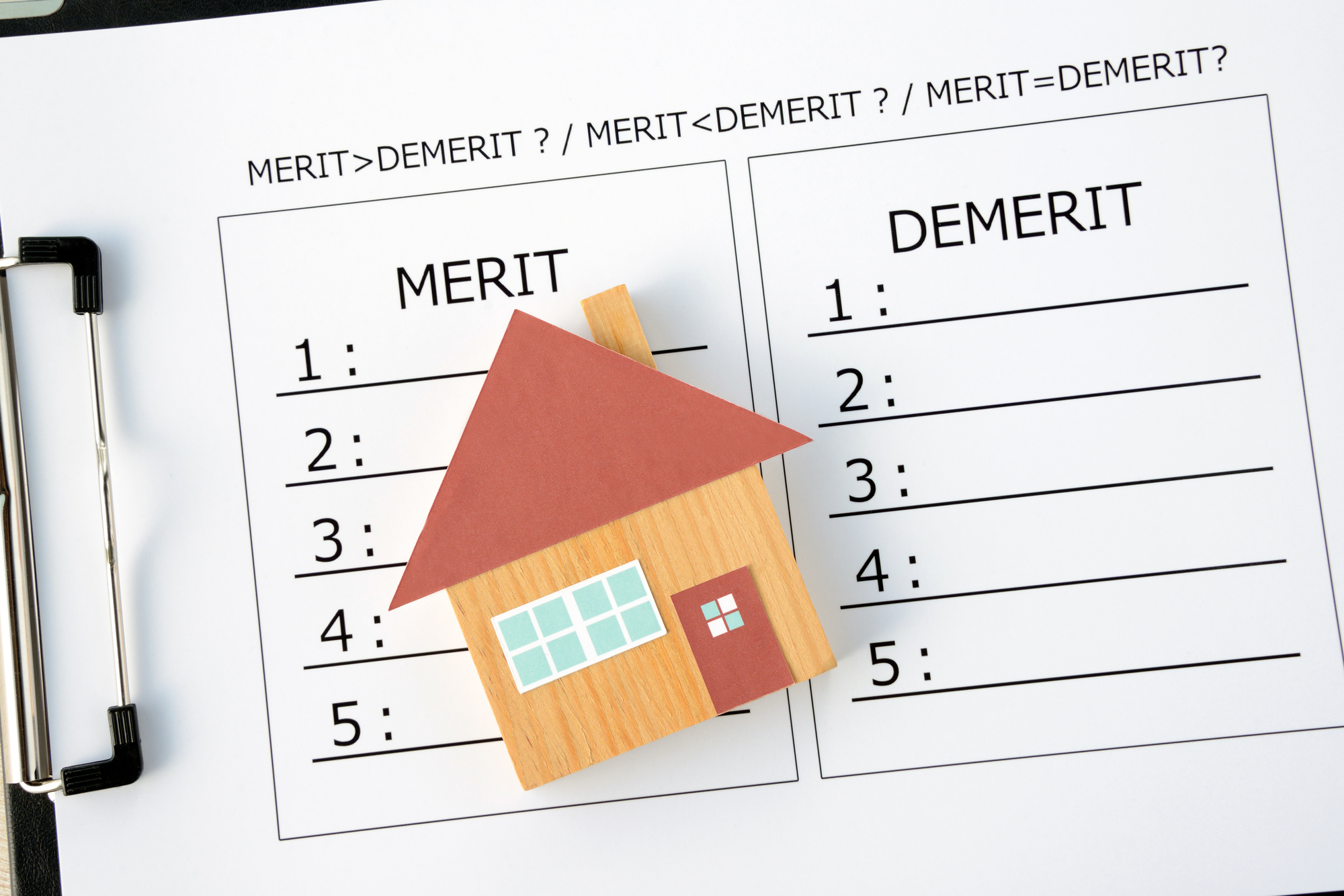公開日:2025.07.21 更新日:2025.07.29
再建築不可物件とは?定義・リスク・対策を徹底解説

再建築不可物件とは、建築基準法に定められた「接道義務」などの条件を満たしておらず、解体後に新たな建物を建てることができない土地付き物件を指します。
このような物件は、老朽化しても建て替えができないため、資産価値の下落やリフォーム制限などの重大なリスクが伴います。一方で、価格が安く税負担も軽いといったメリットもあり、投資用やセカンドハウスとして注目されるケースもあります。
本記事では、
・再建築不可の定義と法律的背景
・接道義務や旧建築基準法との関係
・リフォーム・リノベーションの可否
・住宅ローンの注意点と利用可能な融資商品
・再建築を可能にする具体的な方法(隣地買収・43条但し書きなど)
などを専門的かつ実用的に解説します。
不動産活用を考える方にとって、必ず押さえておくべきポイントを網羅しました。リスクを最小限に抑えつつ、再建築不可物件を賢く活用するために、ぜひ最後までご覧ください。
目次
再建築不可物件の基礎知識

再建築不可物件を理解するうえで知っておきたい基本的な考え方や関連する法律・制度について解説します。
再建築不可物件とは、上記の通り法で定められた接道義務などを満たさないために、解体後の新築が許可されない物件を指す通称です。
具体的には、道路幅員が基準を満たしていない、または敷地が必要距離分だけ道路に接していないなどの理由が多く挙げられます。こうした条件を満たせない場合は建て替えが不可となり、老朽化するほど資産価値が下がる反面、安価に取得できる点が特徴です。
再建築不可物件が生まれた背景とは? 建築基準法と接道義務の歴史的経緯
再建築不可物件が存在する主な理由のひとつは、1950年に施行された「建築基準法」以前に建てられた建物が多く存在することにあります。
現行法では、建物を建てるには「幅4メートル以上の道路に、敷地が2メートル以上接していること(接道義務)」が必要です。しかし、建築基準法が施行される以前はこうした基準が緩く、現在の法律に照らすと接道義務を満たさない土地が多く見受けられます。
さらに、戦後の区画整理や都市計画の変更、道路の拡張や新設によって、かつては建築可能だった土地でも、公道との接道が失われてしまい、再建築が認められなくなったケースも存在します。こうした背景から、再建築不可物件は都市部を中心に現在でも一定数残されています。
接道義務とは? 再建築不可物件との関係と具体的なケース
建築基準法では、原則として建物の敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければ再建築が認められません。これがいわゆる接道義務で、緊急車両の進入路や災害時の避難経路を確保するために定められています。
例えば幅員3mの私道しかない土地や、公道まで敷地が届かない袋地のような場合、原則として建築計画そのものが認められないことがほとんどです。
再建築不可物件のメリット・デメリットとは?

再建築不可物件には特有のメリットとデメリットが存在し、購入や売却、居住にも影響します。
再建築不可物件は、新築ができないという大きな制約があるにもかかわらず、さまざまな目的で購入が検討されることがあります。価格が安価であることや税額負担が低いケースが多いことが背景として挙げられます。
一方、物件としての流動性が低く、金融機関の融資が受けにくいなどのデメリットも少なくありません。
安価で購入しやすいメリット
再建築不可物件は、新築可能物件に比べて土地・建物の資産価値が低く評価されるため、市場価格よりも大幅に安く購入できるケースが多く見られます。
購入コストを抑えたい投資家や、セカンドハウス・趣味の拠点を検討している方にとっては、手が届きやすい物件として購入ハードルが下がるのは魅力です。さらに、評価額が低くなる分、固定資産税や都市計画税などの税負担も比較的軽く、長期保有時のランニングコストを抑えやすい点もメリットです。
建て替えできないリスクの深刻さ
再建築不可物件では、建物が老朽化して耐震性能や設備の老朽度が深刻化しても、現行の建築基準法に基づく新築はできないため、修繕やリフォームによる延命が必要になります。耐震性能の不足や給排水・電気設備の劣化が進んでも、新築で一新できない点は大きな不安材となりえます。
特に地震や火災などの災害で建物が大きく損傷した場合は、解体せざるを得ず、その後の再建もできないため、資産価値が一気に失われるリスクが高い点は大きな懸念材料です。
融資や売却時に不利な側面
銀行融資や住宅ローンの審査では、再建築不可物件は担保価値が極めて低いと評価されることが一般的です。
そのため融資を受けるハードルが高く、購入希望者の多くが現金取引を選択せざるを得ない状況になります。また、市場の買い手が限定されることで売却時の流動性も低くなり、通常よりも売りにくい傾向がある点も覚えておく必要があります。
再建築不可物件でもリフォームできる?可能な工事と注意点

建て替えができない場合でも、リフォームやリノベーションによって快適に利用できる可能性があります。
再建築はできなくとも、既存の構造を活かした大規模リフォームやリノベーションで快適な住空間を実現できる可能性があります。たとえ築年数が古くても、壁・床・天井の間取り変更や断熱・耐震補強を施せば、ある程度快適に暮らせる住空間をつくることは可能です。
ただし、工事内容によっては建築基準法や各自治体の条例に抵触するおそれがあるため、事前に建築士や行政と相談し、法的に可能な範囲で計画を立てることが不可欠です。
建築確認不要な範囲の工事とは
再建築不可物件でも、建築確認申請を必要としない工事であれば、比較的柔軟に対応が可能です。具体的には、内装の模様替え、キッチン・トイレ・浴室などの設備交換、壁紙や床材の張り替えといった内容で、建物の構造体に手を加えない工事が該当します。
例えば間取り変更でも、一部の壁の撤去や造作を行う程度であれば、建築確認を必要としないこともあります。ただし、拡張や構造補強などを行う際には要件を満たすかどうかを必ずチェックし、必要に応じて建築士や行政の担当部署と調整することが重要です。
大規模リフォーム・増改築時の制限と注意点
建物の主要構造部(柱・梁・屋根など)を半分以上取り替える工事や、10㎡を超える増築は、原則として建築確認申請が必要になります。
再建築不可物件の場合、この段階で「実質的な建て替え」と同等とみなされる可能性があり、結局は増改築が認められないケースもあります。大きな投資を伴うリフォームを検討する際は費用対効果を見極めつつ、行政や専門家の見解を踏まえた慎重な計画が欠かせません。
再建築不可物件でも建築を可能にする方法

法的な接道義務をクリアすれば、再建築不可物件でも新築が認められるケースは存在します。
具体的には、敷地の拡張やセットバック、または法第43条の特例などを活用し、建築が可能な状態に変えることが目指されます。しかし、行政機関の許可が必要であったり、隣地と交渉をまとめなければならないなど、実際のハードルは高めです。費用や期間もかかるため、早い段階で建築士や行政書士などの専門家に相談し、具体的な可能性を検討することが重要です。
隣地の買収やセットバックで接道義務を満たす
最も現実的な方法の一つは、隣地を一定部分買収して敷地として取り込み、道路に対する接道面積を確保することです。
また、道路後退と呼ばれるセットバックを行い、敷地の一部を事実上道路として扱うことで法定幅員を満たし、「みなし道路」として再建築が認められるケースもあります。
いずれも隣地所有者との交渉が必須であり、特に相手が所有者不明土地などの場合は交渉が難航することも多いため、早い段階で専門家と協力しながら計画を進める必要があります。
建築基準法第43条第2項の許可取得
建築基準法第43条では、「接道義務を満たさない敷地」であっても、特例的に建築を認める制度(いわゆる「43条但し書き」)が設けられています。(※現在は主に同法第43条第2項第2号の許可を指します)
たとえば、幅が狭い通路や私道であっても、地域の実情に応じて自治体が「建築可能」と判断すれば、再建築が可能になる場合があります。
ただし、審査には安全性や周辺環境への影響が重視されるため、自治体によって審査基準が大きく異なる上、申請書類や現地調査も含めて手続きに時間がかかることが多く、実現には事前準備が不可欠です。
再建築不可物件の住宅ローン事情

再建築不可物件は、一般の住宅ローン審査において担保価値が低いと判断されやすく、融資条件が厳しくなるのが一般的です。将来的に再建築できない点が金融機関にとって大きなリスクとされ、融資が断られるケースも少なくありません。
一方、ノンバンク(銀行以外の金融機関)や特定用途向けローンなどを上手く利用すれば、資金調達の道が開ける場合もあります。自己資金を多めに用意したり、他の不動産を担保に入れたりすることで、融資の可能性を高める選択肢が存在します。
再建築不可物件でも利用できるローンの種類
セカンドハウス向けローンや事業用の不動産担保ローンなど、再建築を前提としないローン商品を取り扱う金融機関であれば、一定条件下で融資を受けられる可能性があります。
たとえば以下のようなローンが該当します:
・セカンドハウス用ローン
・投資用・賃貸併用住宅向けローン
・不動産担保ローン(事業用を含む)
・ノンバンク系の融資(※金利は高め)
これらは一般的な住宅ローンよりも審査基準が緩い反面、金利が高い・返済期間が短いなどの制限があるため、慎重な選定が求められます。
また、親族名義の土地や他の所有不動産を追加担保に設定することで、金融機関のリスクが軽減され、融資が通るケースもあります。複数社から見積もりを取り、条件を比較検討するのが現実的なアプローチです。
融資を受けるためのポイントと注意点
まず、自己資金を多めに用意し、融資額を抑えることで金融機関のリスクを減らす方法があります。
次に、リフォーム計画がある場合には具体的な工事内容や見積書を提示し、物件の将来性をアピールすることが重要です。複数の金融機関をあたって条件を比較し、借り入れコストとリスクを総合的に見極めることが成功のカギといえるでしょう。
2025年建築基準法改正で何が変わる?再建築不可物件への影響を解説

2025年に予定されている建築基準法改正によって、再建築不可物件が受ける影響も変わる可能性があります。
これまでも建築基準法は時代に合わせて何度か改正されており、特に接道義務や耐震性の確保、安全基準については厳格化の流れが続いてきました。
2025年以降の改正では、小規模建築物に対する「4号特例」の適用範囲が縮小されることが大きなトピックです。この改正により、これまで建築確認が不要だった一部の工事にも確認申請が必要となる見込みで、手続きの手間や費用が増える可能性があります。
こうした法改正に伴い、現在は再建築が可能だった物件でも将来的に制限がかかるケースもあるため、継続的なチェックが必要です。
4号特例縮小とリフォーム規制のポイント
4号特例は、木造2階建て以下・延べ面積500㎡以下などの比較的小規模な建築物が建築確認の手続きを簡略化できる仕組みですが、この特例が縮小される見通しです。
結果として、過去に特例を使ってリノベーションを進めやすかった物件でも、今後は建築確認が必要になる可能性が高まります。また、手続きに時間と費用がかかるため、計画段階でより慎重なスケジュール調整が求められます。
建て替えがさらに難しくなる可能性
法改正により接道基準や安全基準が厳しくなると、現段階では再建築不可物件ではない物件も、将来的に再建築が難しくなる恐れがあります。特に、接道する道路の幅が4m未満の「みなし道路」扱いで建築を認められている物件については、制度変更による影響を受けやすいため、注意が必要です。
買い手や所有者の意図にかかわらず、将来の法改正によって建て替えが認められなくなるリスクがあることも視野に入れておくべきでしょう。
再建築不可物件の購入・売却で注意すべきチェックポイント一覧

再建築不可物件を購入・売却するときには、事前にさまざまな項目を確認してリスクを減らす必要があります。
再建築不可物件の購入・売却を成功させるためには、現地の状況、法的制限、隣地との関係、インフラ整備、災害リスクや法的書類の確認を怠らないことが重要です。隣地との境界が曖昧なまま契約を進めてしまうと、将来大きなトラブルに発展する恐れがあります。
資産として維持するには、法令や自治体の条例なども含めて総合的に情報収集をしておくことが欠かせません。
インフラ状況や境界線の確認
まず確認すべきは、水道・下水道・電気・ガスなどのインフラが敷地内まで整っているかどうかです。特に古い地区では設備が老朽化している場合もあり、更新コストが高額になる可能性があります。
次に重要なのは、土地の境界線が明確に確定しているかどうか。測量図・公図・境界確認書などの法的書類をもとに、隣地所有者と合意形成が取れているかを確認しましょう。これを怠ると、売却時やリフォーム時に隣地トラブルに発展するリスクがあります。
災害リスクや周辺環境の把握
再建築不可物件は狭い路地や袋地に位置していることも多く、災害時の被害リスクが高まる恐れがあります。
そのため、自治体のハザードマップや土砂災害警戒区域情報、浸水想定区域などを事前に確認し、災害リスクを把握しておくことが重要です。
また、安全対策の一環として、火災保険・地震保険の加入を検討することも推奨されます。特に再建築不可物件は「全壊=再築不可」となる可能性があるため、万一の損失補填手段を用意しておくことがリスク管理の基本となります。
まとめ・総括|再建築不可物件の活用と注意点

再建築不可物件はリスクも大きい反面、活用方法次第では大きなメリットも得られます。正確な情報収集と専門家への相談が重要です。
再建築不可物件は、建物を新築できないという最大の制約がある一方で、税負担の軽さや安価に購入できるといった魅力が存在します。リフォームや法的特例を活用すれば、一定の実用性や資産価値を引き出すことも可能です。ただし、融資の難しさや法改正による規制強化などリスクも多く、購入・売却・活用には慎重な判断が求められます。事前調査と専門家の助言を活かし、将来を見据えた対応が重要です。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。