公開日:2025.08.12 更新日:2025.07.29
家屋解体で使える補助金制度を徹底解説|申請から活用まで【2025年最新版】

家屋を解体する際、補助金を申請できることをご存じでしょうか?空き家増加や老朽家屋が抱える社会的な課題を解決するために設けられているもので、上手く活用すれば費用負担を軽減できるだけでなく、安全面や地域環境の向上にも貢献します。
本記事では、家屋解体で利用できる補助金制度について、その種類や申請対象、支給金額、手続きの流れなどをまとめました。
目次
家屋解体補助金の基礎知識
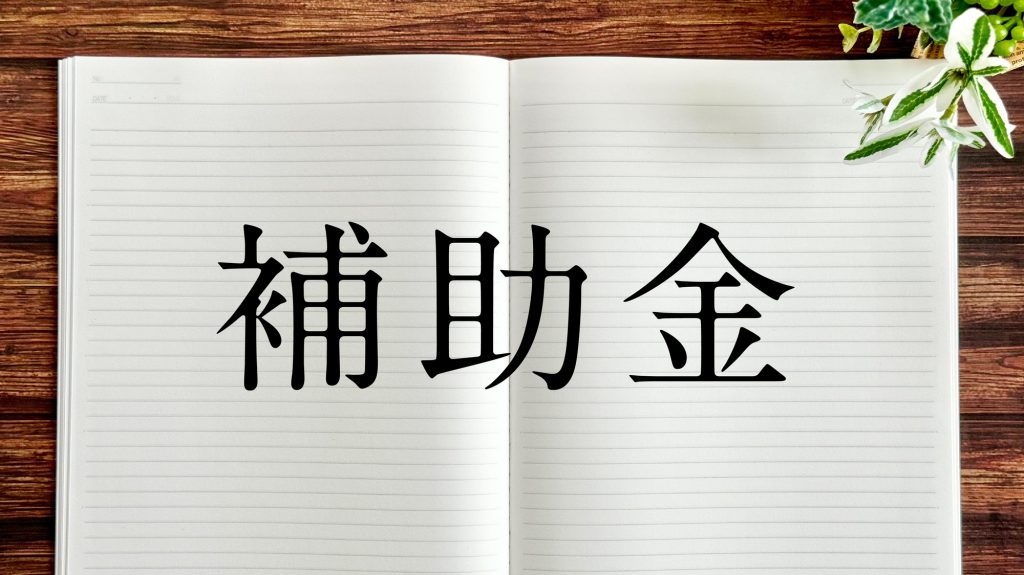
まずは家屋解体補助金の背景や目的、制度の概要など、一般的な基礎知識をおさらいしておきましょう。
家屋解体補助金は、少子高齢化や都市集中化などに伴う空き家の増加を受け、自治体が費用の一部を助成する制度。解体費用の一部を補助することで、倒壊リスクの軽減、地域の防災、環境美化に貢献することが目的です。これは「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき推進されています。特に住宅が密集する地域では、老朽化した家屋を放置すると近隣住民の安全や景観に悪影響を及ぼすため、公的支援の役割は年々重要性を増しています。
この制度は自治体によって名称や対象条件が異なるため、申請を検討する際は各自治体の公式情報を確認することが大切です。受給できる補助金額や申請要件は、物件の老朽度合い、耐震診断の評価、所有者の税支払い状況などによって異なります。まずは家屋の現況を正しく把握した上で、各自治体の公式情報を確認し、該当する補助制度を申請しましょう。
空き家・老朽家屋を解体すべき理由

空き家や老朽化が進んだ家屋を放置するとどんなリスクがあるのかも、確認しておきましょう。
これらの家屋を放置すると、倒壊リスクが高まり、近隣住民や通行人に被害が及んだ場合に所有者が損害賠償責任(民法第717条 工作物責任など)を負う可能性も。また、不法侵入や不法投棄が増加し、犯罪の温床となることで治安悪化につながる恐れも考えられます。
さらに、建物の傷みが進むにつれ資産価値も大きく下がり、いざ売却を検討したときに想定外の出費が必要になることも珍しくありません。
今後活用する予定のない空き家や老朽家屋は、解体することで良好な治安や景観の維持が可能になる上、解体後の土地を有効活用することで経済的な利点を得られ、地域コミュニティの活性化にも大きく貢献できるでしょう。
家屋解体補助金の主な種類と支給団体

家屋解体を支援する補助金制度にはどのようなものがあるのか、主な種類と支給団体の特徴をご紹介します。
老朽危険家屋解体撤去補助金
老朽危険家屋解体撤去補助金は、特に倒壊の危険性が高い家屋に対して、費用の一部を助成する施策です。自治体によって支給割合や上限額は異なるものの、多くの地域で導入されています。自治体が実施する耐震診断や現地調査の結果をもとに支給の可否が決定するケースが多いため、事前に情報を収集しておきましょう。
木造住宅解体工事費補助事業
木造建築の老朽化や耐震不足を解消するために設けられているのが、木造住宅解体工事費補助事業。倒壊から住民を守ると同時に、解体後の再建築や土地の有効活用を促す目的も含まれています。自治体によっては、解体の技術的要件や周囲の住環境を考慮して補助額が変動する場合もあるため、申請時には工事内容を詳細に確認しておくことがポイントです。
建て替え建設費補助金
解体費用だけでなく、その後に新築を行うケースで建設費用の一部までサポートしてくれるのが、建て替え建設費補助金です。空き家問題を根本的に解決するため、家屋の撤去から新築・居住までを総合的に支援してもらうことが可能。地域の活性化や人口流入の促進を目的とした取り組みの一環として、力を入れている自治体が多く見られます。
ブロック塀等撤去費用への補助
家屋本体だけでなく、ブロック塀や囲障物の撤去を支援する制度も広く用意されています。特に地震大国である日本では、ブロック塀が倒壊して二次被害を引き起こす可能性があるため、安全面の確保が重要です。家屋解体と同時に撤去することで、工事費用を抑えられるだけでなく、住環境全体の安全性が向上するメリットがあります。
補助金の申請対象者・物件要件

補助金を利用するには、申請者の条件や対象となる家屋の基準をクリアする必要があります。
まず家屋解体補助金を申請する際、申請者がその不動産の所有者であることが大前提です。また、地方税の滞納がないか、家屋が特定空家等の要件(空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく)を満たしているか、自治体独自の耐震診断や危険度判定で「解体が必要」と判断されたかなどを確認されることが一般的です。
さらに、該当家屋が建築基準法に抵触していないか、不動産登記法に基づく登記がされている建物かどうかなど、細かな条件が課されるケースもあります。加えて、物件の老朽度合いを示す客観的な書類を求められることも多く、建物の概要や築年数、構造の種類が審査に影響する可能性も。補助金申請をスムーズに進めるためには、早めに情報収集を行い必要な資料を漏れなく揃え、要件を満たすかを入念に確認することが大切です。
家屋解体補助金の支給金額・上限目安

では、実際に家屋解体補助金はどのくらい支給されるのでしょうか。
支給額は解体費用の何割かを助成するケースが多く、平均的には解体費用の3割から5割程度が目安。しかしながら、自治体ごとに上限額が定められており、例えば50万円や100万円など、一定額を超えると支給が打ち切られる場合があります。物件の状態や工事規模によって実際の補助率は変わるため、事前に見積もりを取り、申請条件を確認することが重要です。
また、解体後に生じる産業廃棄物の処理費や敷地内の整地費用など、一部対象外となることもあるため、補助対象として認められる費用がどこまでなのかも含め、事前にしっかり確認しておきましょう。
自治体ごとの補助金事例
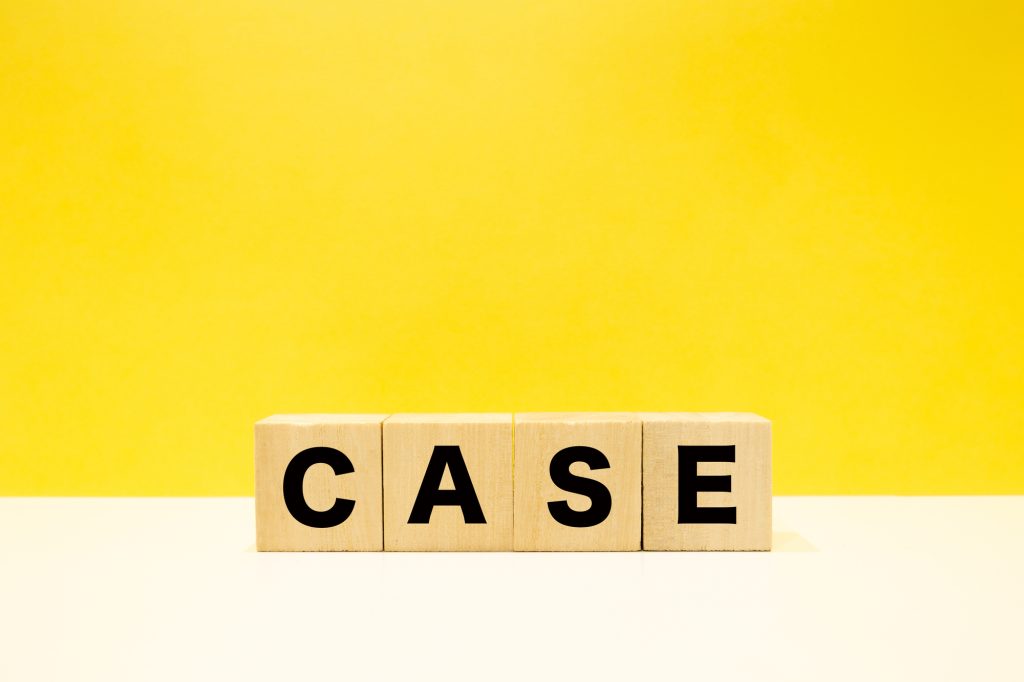
家屋解体補助制度は、各地域の属性や人口密度、空き家の数などに応じて大きく異なります。具体的に補助金制度が実施されているのかを、「都市部」と「地方」にわけて事例をご紹介します。
東京都や埼玉県など都市部の支援策
都市部の場合は地価が高いため、危険な空き家を解体して敷地を有効活用する取り組みに力が入れられることが多いです。例えば東京都や埼玉県などは、住宅が密接しているエリアでの倒壊リスクを低減するための助成金制度を整備し、安全確保と資産価値向上を同時に狙います。これらの制度は募集枠が早々に埋まることも多いため、こまめに情報収集を行い、迅速に申請するようにしましょう。
地方自治体の特徴的な取り組み
地方自治体では過疎化や景観維持が深刻な課題となっているため、積極的に解体費用全般を支援するケースが目立ちます。人口流出を食い止める狙いから、解体後の再利用方法に応じて追加の補助や優遇が行われることも少なくありません。集落の活性化を視野に入れ、古民家を解体せずに再生するプランを支援する自治体もあるため、個々の目的に応じて選択することが重要です。
家屋解体補助金の申請手順と必要書類

補助金を受け取るまでの流れと、手続きに必要な書類の準備方法をステップごとに解説します。
工事前の事前協議と見積もり
家屋解体補助金を受け取るためには、まずは自治体や担当窓口での事前相談からスタートします。解体工事に着手する前に相談し、家屋の現地調査や書面確認が行われ、解体が必要と判断されれば、見積書の取得や申請書類の準備へと進むのが一般的です。
物件の状況や手続きを共有した上で詳細を詰め、複数の解体業者から見積もりを取り寄せて適正価格を把握したうえで、補助金の申請が可能な費用項目を特定します。こうしたプロセスを怠ると、後になって書類不備や費用算定が合わずトラブルになる可能性があるため、初期段階の事前協議を丁寧に行いましょう。
申請時に用意する主な書類
自治体によって異なりますが、一般的に必要とされる書類は以下の通りです。
- 家屋の登記事項証明書
- 住民票
- 解体業者が発行した見積書
- 家屋の現状を示す写真
- 耐震診断結果 など
発行に時間がかかる書類もあるため、余裕をもって準備を始めるのがおすすめ。自分が所有する物件に関する情報を正確に用意することで、スムーズに審査を通過しやすくなります。
解体工事後の実績報告と交付決定
手続きが完了し交付決定が下りた後に解体工事を実施し、工事完了後に実績報告を提出する流れが一般的です。報告内容が認められて交付額が確定すると、実際の補助金が支給されます。ただし、タイミングを誤って工事を先に始めてしまうと補助金が無効になることもあるため、着工時期には注意が必要です。
解体工事が完了したら、実際の工事内容や費用に関する書類を自治体に提出して最終的な確認を受けます。工事完了後の写真、領収書、支払証明書などを添付し、書類審査を経て交付額が確定するのが一般的。必要書類が揃っているかをしっかりチェックし、追加提出がないように管理しておくようにしましょう。
解体工事時の注意点とリスク回避
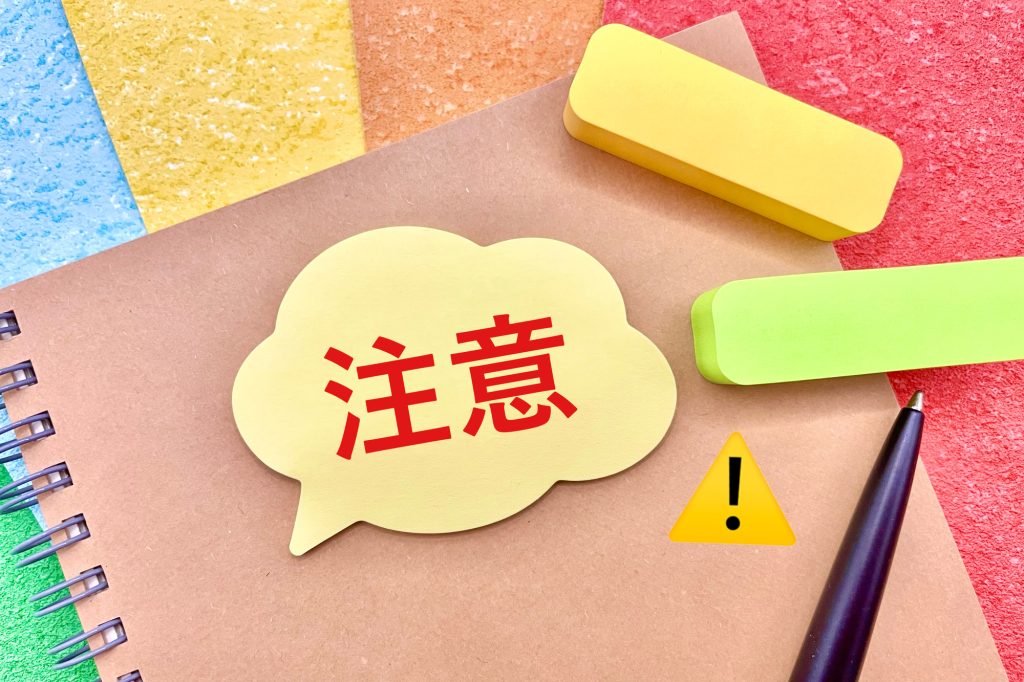
解体工事にはさまざまなリスクが伴います。あらかじめ安全面や法規面で注意すべきポイントを把握し、必要に応じて専門家にも相談しながらスムーズに解体を進めましょう。
アスベスト・有害物質への対処
解体現場でアスベストや鉛などの有害物質が検出された場合、専門の処理業者と連携して安全を最優先に対策を行わなければなりません。作業員の安全管理や近隣への飛散防止策を徹底しないと、健康被害や訴訟リスクが発生する場合があります。自治体によってはアスベスト撤去費用に対する補助制度も存在するため、解体前に確認しておくとよいでしょう。
解体工事の届出や許可手続き(建設リサイクル法、廃棄物処理法など)
家屋解体には、国や自治体が定める建設リサイクル法や廃棄物処理法などの法律に基づいた手続きが必要です。特に工事費用500万円以上または延床面積80平方メートル以上の建築物を解体する場合、事前の届出が義務付けられているため、許可を得ずに着工すると罰則を受ける恐れがあります。適宜業者と連携し、必要な許可申請を漏れなく行うことが大切です。
税制優遇への影響と固定資産税の変更
建物を解体すると、固定資産税の住宅用地特例(地方税法第349条の3の2)など、適用されていた税制優遇が受けられなくなる場合がある点にも注意が必要です。固定資産税は土地区分に応じて算出されるため、住居がなくなった土地は住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税が最大6倍に跳ね上がるなど課税区分が変更され、税額が増加する可能性があります。事前に市区町村の税務担当窓口へ相談し、将来的なキャッシュフローを把握した上で解体を進めることがおすすめです。
解体後の土地活用法

家屋解体後の土地はさまざまな形で活用可能です。主な方法を2つご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
駐車場・賃貸物件への転用
駅や商業施設など人の往来が多い場所では、駐車場経営や賃貸住宅への転用が収益性の高い選択肢となります。駐車場にする場合は初期投資を比較的抑えられ、需要があれば安定した収入が見込める点がメリット。集合住宅や戸建て賃貸を建てる場合は設備投資が大きいものの、長期的な家賃収入や資産価値の向上を期待できるでしょう。
公共施設や地域交流スペースへの活用
公共施設の用地として自治体に貸し出す、あるいは地域住民のコミュニティスペースとして開放するなど、社会貢献や地域活性化に寄与する活用法もおすすめ。地域でイベントを行う広場や子ども向けの遊び場として提供されることで、住民の交流促進に大きな役割を果たすでしょう。補助金を活用して解体を行い、地域社会にもプラスの影響をもたらす形で土地を利用する方法は、多くの自治体からも歓迎されるケースが多く見られます。
まとめ:家屋解体補助金を賢く活用しよう
家屋解体補助金を上手く活用するためには、家屋を放置するリスクや制度の仕組み、申請手順をしっかり把握しておくことが重要です。
家屋解体補助金は国や自治体が用意する有用な支援策であり、老朽化した家屋を解体して安全を確保する重要な手段となります。補助金の条件や対象範囲は自治体によって変わるため、事前に最新情報を入手して、専門家や担当窓口と相談しながら準備を進めることがポイント。解体後の土地はさまざまな形で活用できるため、上手に運用すれば資産価値の維持・向上や地域の活性化に貢献できるでしょう。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。










