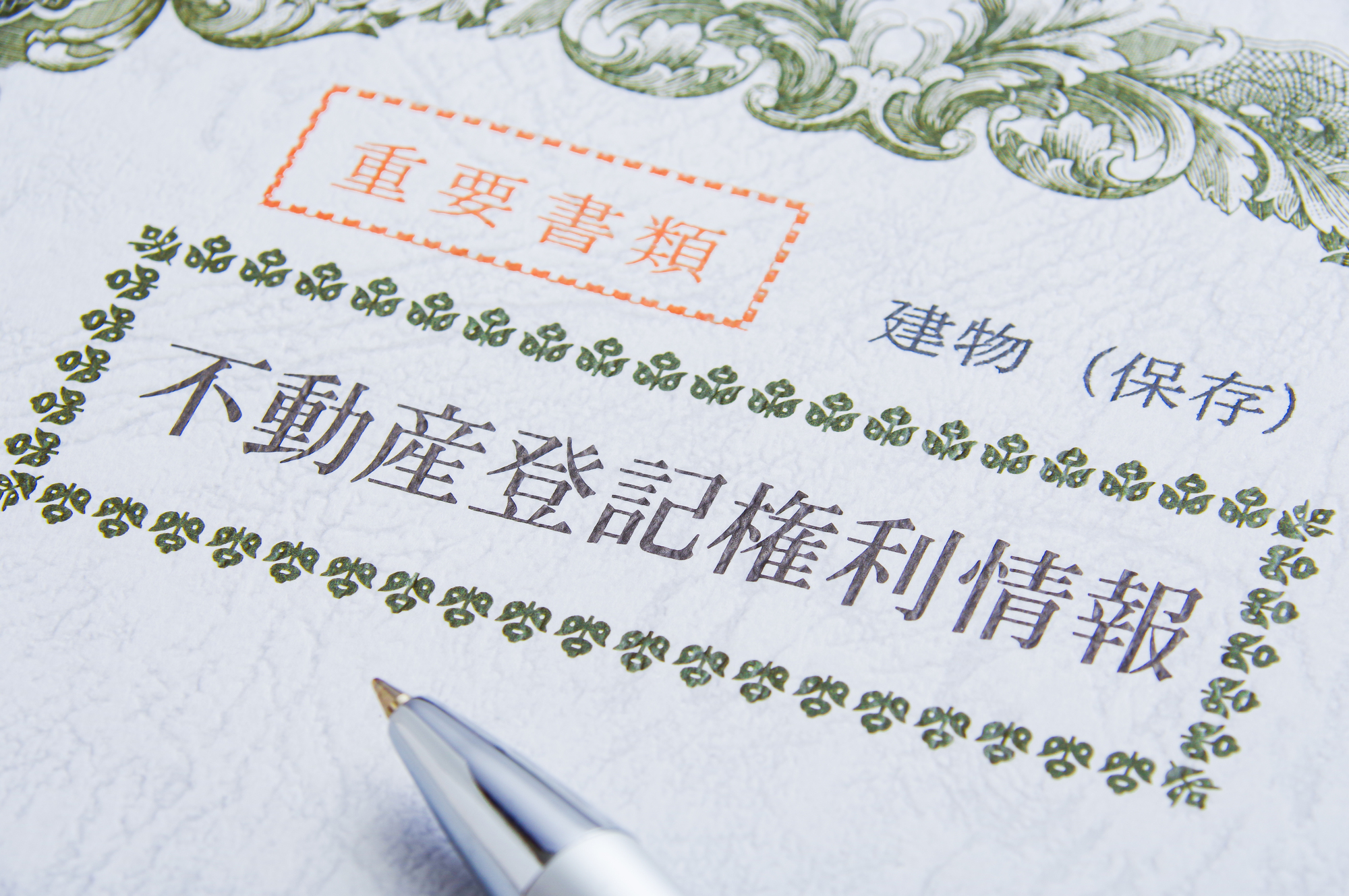公開日:2025.09.03 更新日:2025.07.29
【遺産分割協議書とは】作成方法・記載事項・必要書類・相続手続きの注意点

相続が発生した際、遺言書がない場合や、法定相続分とは異なる方法で財産を分けたい場合に必要となるのが「遺産分割協議書」です。相続人全員の合意形成を明確にし、後のトラブルを防ぐだけでなく、不動産の名義変更や預貯金の解約など、各種相続手続きを進める上で不可欠となります。
本記事では、遺産分割協議書の基礎知識から、作成手順、注意点まで詳しく解説。スムーズな相続手続きを進めるために、ぜひお役立てください。
目次
遺産分割協議書とは?その役割と目的
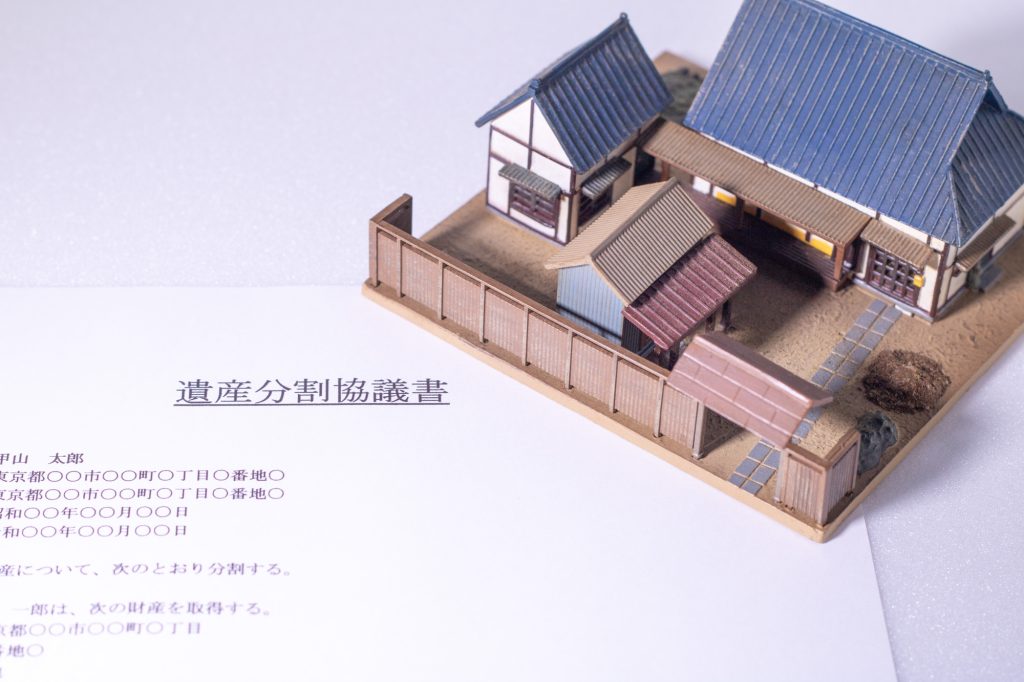
まずは遺産分割協議書の基本情報を確認しておきましょう。
相続トラブルを防ぐ「遺産分割協議書」の重要性
遺産分割協議書とは、被相続人の財産をどのように分けるかを相続人全員で協議し、その内容を文書にまとめたもの。この書類は単なるメモではなく、相続登記や預貯金の解約など、公的な手続きにも使用される重要な文書です。
この遺産分割協議書は、相続に関する合意内容を明文化することで、財産の分配に関する争いを未然に防ぎ、スムーズな手続きにつなげることが主な目的です。相続財産が多岐にわたる場合や、相続人の人数が多い場合には、特に重要な書類になります。
相続人全員の合意形成が必須となる理由
遺産分割協議書の作成においては、法定相続人をすべて把握しておくことが前提です。仮に一人でも相続人が抜けている場合、協議は無効となるため、必ず全員の参加と合意が求められます。養子や認知された子、前妻との子なども含め、法律上の相続資格を持つ人物を漏れなく確認しておくようにしましょう。
また、遺産分割協議書は相続人全員の合意(実印による押印を含む)があって初めて法的効力を持つものです。協議に参加した全員が内容に納得した上で署名し、実印を押印する必要があります。
遺言書との違いと法的な優先順位
遺産分割協議書と遺言書は、どちらも財産の分配に関する文書ですが、その性質と優先順位には明確な違いがあります。まず、遺言書は被相続人の生前の意思を反映するものであり、原則としてその内容が優先されます。遺言書で指定された遺産分割方法と異なる内容で遺産を分割するには、遺言執行者がいる場合を除き、原則として相続人全員の同意が必要です。
一方で、遺言書が存在しない場合や内容が不明確な場合には、相続人による協議に委ねられ、その結果として遺産分割協議書が作成されます。
遺産分割協議書が必要なケース

では、具体的にどのようなシーンで遺産分割協議書が必要になるのでしょうか。主に次の二つのシーンが挙げられます。
遺言書がなく法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合
遺言書がない状態で相続が発生した場合、財産は法定相続分に従って分けられるのが原則です。しかし、実際には不動産や現金の状況に応じて、柔軟な分配が求められることも少なくありません。このようなとき、相続人全員の同意のもとで遺産分割協議を行い、その結果を協議書として残す必要があります。
たとえば、自宅に同居していた長男が不動産を相続し、他の相続人には代わりに現金を分配する代償分割を行うケースが該当します。協議書がなければ、不動産の名義変更などの手続きも進められないため、しっかりと書面を整えることが重要です。
遺言書に記載がない財産が発覚した場合
遺言書が存在していても、すべての財産について詳細が記載されているとは限りません。後から新たに預貯金や不動産が発覚した場合、それらについての分割方法は遺言書ではカバーされていないため、相続人同士で協議が必要です。
この場合も、遺言書の内容と併せて協議書を作成することで、すべての財産に対応した相続処理が可能になり、名義変更や解約といった手続きもスムーズに進められます。
遺産分割協議書の作成手順

遺産分割協議書を作成するための、具体的な手順を解説します。抜け漏れなく適切に進められるよう、しっかり確認しておきましょう。
被相続人の財産を確定させる
まず最初にすべきなのは、被相続人が亡くなった時点で所有していたすべての財産を明確にすることです。不動産、預貯金、有価証券、車両、保険金、さらには負債も含め、財産目録として整理します。
不動産であれば登記事項証明書、預金であれば通帳や取引明細書を用いて確認します。未確認の財産が後から見つかると再協議になることもあるため、早い段階で正確な財産を把握しておくようにしましょう。
法定相続人を確定する
次に行うのが、法定相続人の確定作業です。これは、誰が相続人に該当するのかを明らかにするプロセスであり、戸籍謄本を取り寄せることで確認します。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せ、子どもや配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹など法定相続人の全体像を把握しましょう。相続関係を証明するために、これらの戸籍謄本は遺産分割協議書に添付することもあります。万が一、相続人の一部が漏れてしまうと、協議のやり直しとなり法務局での手続きも進みません。養子縁組や認知された子がいる場合も対象となるため、丁寧な確認が不可欠です。
遺産分割協議を行う
財産と相続人が確定したら、いよいよ遺産の分配方法について協議を行います。協議の場では、法定相続分に準じた分け方をすることもあれば、代償分割や換価分割など、柔軟な分配が選ばれることもあります。
この協議には相続人全員の参加と合意が必要であり、途中で誰かが同意しない場合、協議そのものが成立しません。近年では、専門家の立ち会いのもとで行われることも増えており、トラブルを未然に防ぐためにも、公平で透明な話し合いが求められます。
遺産分割協議書作成に必要な書類を揃える
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成する前に、必要な書類を整えます。主なものには、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などがあります。また、不動産を相続する場合には固定資産評価証明書や登記事項証明書も必要です。
これらの書類は相続登記や金融機関への提出時に使用されるため、不備がないようしっかり確認しておくようにしましょう。
遺産分割協議書を作成する
必要書類がそろったら、いよいよ遺産分割協議書の作成です。内容には、各相続人の名前・住所・続柄、相続財産の詳細、分配の方法などを記載します。誤字脱字や財産の記載ミスがあると、後の手続きが滞る原因となるため注意しましょう。
作成後は、相続人全員が実印で署名・押印し、各自1通ずつ保管します。なお、法律上は書式に厳密な決まりはありませんが、実務上は項目や記載方法に一定のルールがあるため、専門家にチェックしてもらうと安心です。
遺産分割協議書に記載すべき内容とは

遺産分割協議書に記載が必要な内容としては、主に以下が挙げられます。
- 相続人全員の氏名、住所、生年月日、被相続人との関係
- 相続財産ごとの具体的な分配内容(例:所在地・地番・地目・地積などの情報で特定できる東京都〇〇区〇丁目〇番地の土地は長男〇〇〇〇が取得する、預貯金であれば金融機関名・口座種別・口座番号などを記載)
- 協議書の作成年月日
- 被相続人の死亡日
- 協議内容に全員が同意している旨の内容
- 相続人全員の押印(実印)
代償分割を行う場合は、上記に加えて現金での支払い方法や時期も明記しておくとトラブル防止につながります。遺産分割協議書は法務局や金融機関などで活用されるため、誰が何を相続するかが一目でわかるよう、正確かつ丁寧に記載することがポイントです。
協議がまとまらない場合の対応
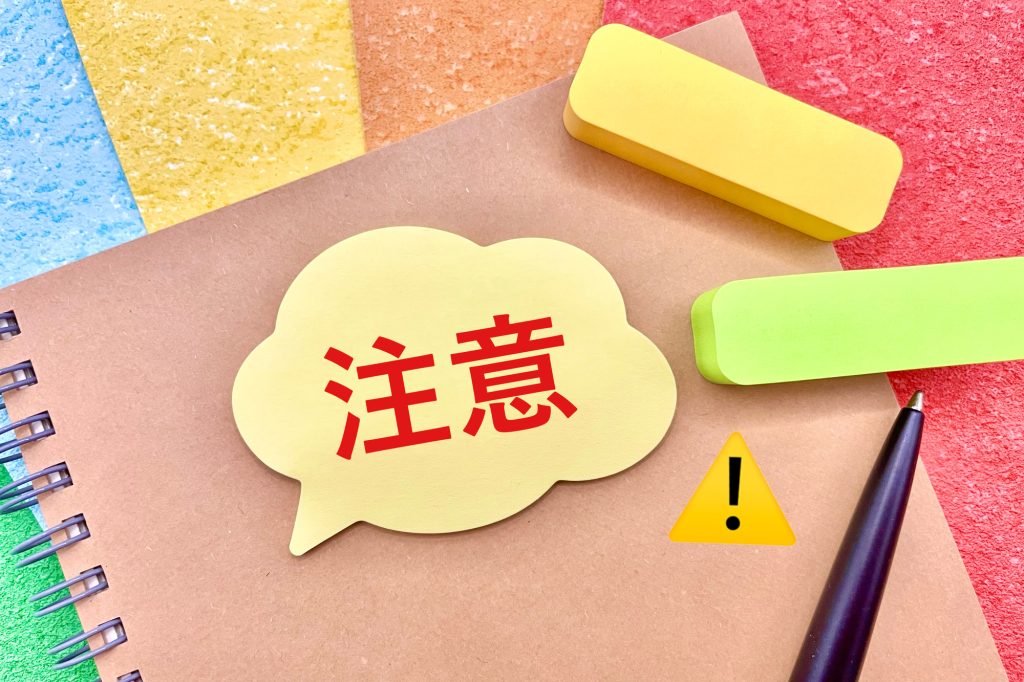
遺産協議の場では、相続人同士で話し合いが難航し、遺産分割協議がまとまらないことも少なくありません。トラブルが起きやすいポイントや裁判を行う場合の流れなどを詳しくまとめました。
トラブルが起きやすいポイントとは
遺産相続の場では、分割方法に関する認識の違いや、被相続人との関係性を巡る感情が対立の原因になるケースが多く見られます。たとえば「自分は親の介護をしていたのに、他の相続人と同じ取り分では納得できない」といった主張や、「被相続人が生前に特定の相続人に贈与していた」といった疑念などです。
また、相続人の中に連絡が取りづらい人物がいる場合や、相続財産が不動産に偏っていて分けにくい場合も、話し合いが進まない要因となります。こうしたケースでは、当事者間での解決が難しいことも多く、第三者の介入が必要です。
特別受益や寄与分の考え方
遺産分割においては、「特別受益」や「寄与分」といった概念が問題になることがあります。特別受益とは、共同相続人の中に被相続人から遺贈を受けたり、生前に多額の贈与を受けたりして特別な利益を得た者がいる場合、その利益を相続財産に持ち戻して(加算して)相続分を計算するという制度です。
一方、寄与分とは、特定の相続人が被相続人の財産形成や維持に特別な貢献をした場合に、通常の相続分に加えて加算される制度です。これらを主張する場合、他の相続人との認識が食い違いやすく、トラブルの火種にもなりかねません。円滑な話し合いのためには、証拠となる資料や専門家の助言が役立ちます。
家庭裁判所による調停・審判の流れ
当事者間での協議が不成立となった場合、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることが可能です。調停では、裁判所の調停委員が双方の主張を整理し、合意に向けて仲介を行います。ここでも相続人全員の参加が求められ、特別受益や寄与分に関する主張も議題に上がります。
調停が成立しない場合には、審判手続きに移行し、。家庭裁判所が一切の事情を考慮して相続分や分割方法を判断。この場合、裁判所の決定が法的拘束力を持つため、当事者の意思にかかわらず執行されます。調停・審判は精神的・経済的負担も大きくなるため、可能な限り協議による解決が望ましいと言えるでしょう。
よくある遺産分割の方法
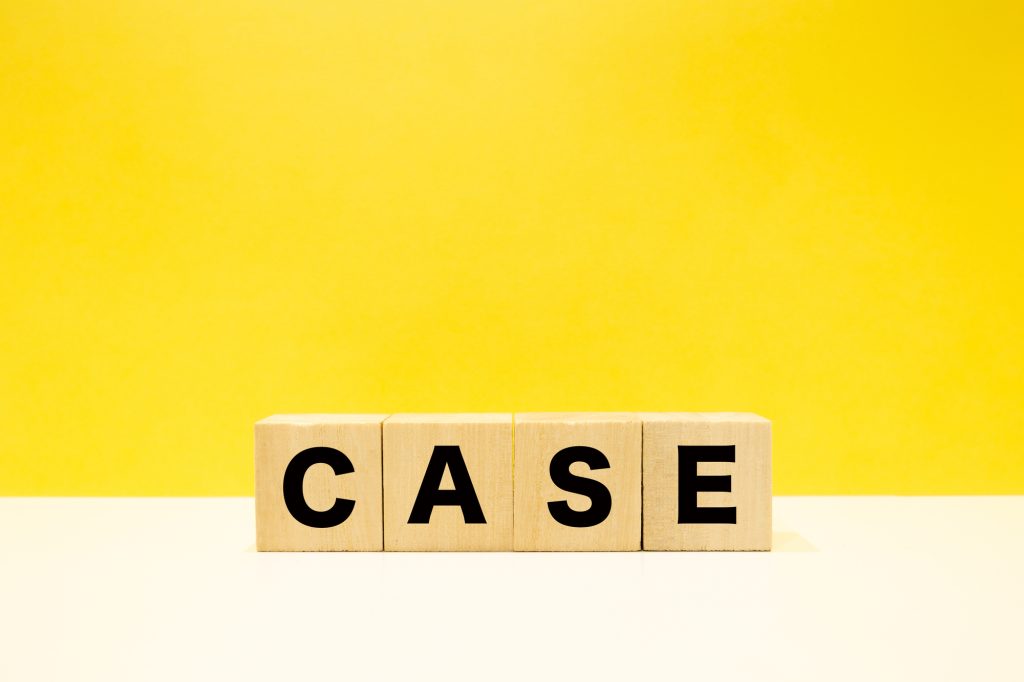
相続財産の分け方にはいくつかの方法があり、財産の種類や相続人の希望に応じて適切な手法を選ぶことが重要です。以下に代表的な分割方法をご紹介します。
現物分割・代償分割・換価分割とは
遺産分割には「現物分割」「代償分割」「換価分割」という3つの代表的な方法があります。
| 現物分割 | 不動産や預貯金などをそのままの形で 相続人に分ける方法 |
| 代償分割 | 一人の相続人が特定の財産を取得し、 その代償として他の相続人に現金などを 支払う方法 |
| 換価分割 | 財産を売却して現金化し、 それを相続人で分配する方法 |
現物分割は、単純で分かりやすい反面、均等な分割が難しいことがあります。代償分割は、たとえば、長男が不動産を相続し、他の兄弟にその評価額に応じた金銭を支払うケースが該当します。そして、換価分割は不動産のように分けにくい資産がある場合に有効ですが、売却には時間や費用がかかることもあるため、慎重に判断するようにしましょう。
不動産を共有にするときの注意点
相続財産に不動産が含まれる場合、複数の相続人で共有とするケースも見られます。しかし、共有状態では売却や利用に際して全員の同意が必要となり、意思決定が難航する可能性があります。
さらに、相続人の一部が亡くなった場合、その持分がさらに他の相続人に分割されることで、権利関係が複雑化する恐れも。将来的なトラブルを避けるためには、共有よりも代償分割や換価分割を選択した方が望ましいケースもあるため、不動産の取り扱いには専門家の意見を取り入れることをおすすめします。
遺産分割協議書の提出先と活用方法

さまざまな相続手続きで必要になる遺産分割協議書。主な提出先と使用目的をまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。
相続税の申告
相続財産が基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要です。この際、遺産分割協議書は各相続人がどの財産を取得したかを明確にする資料として税務署に提出します。
分割が確定していない状態で申告を行うと、相続税の特例が適用できない場合があるため、早めに協議を終えておくことが重要です。たとえば「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などは、分割の内容によって節税効果が異なるため、正確な遺産分割協議書を提出するようにしましょう。
不動産の名義変更
不動産の相続登記は、2024年4月1日より義務化されています。そのため、不動産を相続する際は、原則として相続開始と所有権の取得を知った日から3年以内に、法務局で相続登記の申請を行わなくてはなりません。この手続きにおいても、遺産分割協議書に基づいて該当する相続人の名義へ変更する必要があります。
また、登記申請の際には、被相続人の戸籍謄本や相続人の印鑑証明書、登記事項証明書などの提出も求められるので、漏れなくそろえておくようにしましょう。
預貯金の名義変更、解約払戻し
銀行などの金融機関で預貯金の名義を変更したり、解約・払戻しを行ったりする際にも、遺産分割協議書が必要です。各金融機関ごとに手続きが異なるため、あらかじめ問い合わせて必要書類などを確認しておくとよいでしょう。
遺産分割協議書には、対象となる預金口座の番号や金融機関名なども記載しておくと、後の手続きをスムーズに進められます。
車の名義変更
被相続人が所有していた自動車の名義変更も忘れずに行うようにしましょう。手続きは運輸支局で行いますが、その際に遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書、車検証などの提出が求められます。
名義変更を怠ると、自動車税の請求先や事故時の責任が被相続人の名義のままとなり、トラブルの原因になるため、早めに手続きを行い、実際に所有する相続人の管理下に置いておくようにしましょう。
株式の名義変更
株式も相続財産の一部として扱われます。証券会社に対して名義変更の申請を行う場合、遺産分割協議書の提出が求められるケースがほとんどです。併せて、被相続人と相続人の戸籍や印鑑証明書などの書類も提出します。
証券口座が複数ある場合や、未上場株式を相続する場合などは手続きが煩雑になることもあるため、早めに準備を進め、必要に応じて専門家のサポートも受けるようにしましょう。
まとめ|遺産分割協議書作成は「アキサポ」へ相談を
遺産分割協議書は、相続財産の分配方法を相続人全員で合意し、書面にまとめた重要な書類です。不動産の名義変更や相続税の申告、預貯金の払戻しといった各種手続きに必要とされるため、早い段階での準備が求められます。
一方で、相続の現場では、特別受益や寄与分を巡る争いや、不動産の共有による将来的な問題など、専門的な判断がかかわる場面も少なくありません。
こうした複雑な相続の手続きや遺産分割協議書の作成に不安を感じる方は、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。
「アキサポ」では、空き家や相続不動産に関するお悩みの相談を随時受け付けています。相続登記や不動産の名義変更に精通した専門家と連携し、遺産分割協議書の作成を含む相続全体の流れをトータルでサポート。不動産の売却や活用方法についても、状況に応じた最適なプランをご提案いたします。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。