公開日:2025.09.21 更新日:2025.08.13
【2025年最新】空き家解体補助金ガイド|対象・申請方法・注意点を解説

老朽化した空き家を所有している方の中には、管理の手間から解放されるために、空き家を解体してしまいたいと考えている方もいるでしょう。しかし、解体費用は木造住宅でも100万円以上になることがあるため、費用が捻出できずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
こうした課題を解決するために、多くの自治体では「空き家の解体補助金制度」を設けています。条件を満たせば、数十万円から100万円程度の支援を受けられるため、費用負担を大きく減らせる可能性があります。
そこでこの記事では、代表的な解体補助金の種類や利用の流れなどを分かりやすく解説します。補助金制度を上手に活用して、空き家のリスクを手放し、次のステップへと進むきっかけにしましょう。
目次
空き家解体補助金とは?目的とメリットを解説

空き家の解体補助金とは、放置された空き家や活用が進まない空き家などの解体費用を補助する制度です。この制度は、空き家対策の推進に関する特別措置法に基づいて自治体が独自に設けている場合が多く、地域の安全確保と不動産の有効活用を促進することを目的としています。
解体補助金を利用する大きなメリットは、空き家を解体するハードルを下げることで、建て替えや売却、活用がしやすくなることです。特に土地の価値が高い場合、敷地の使い勝手が向上することで買い手や借り手が付きやすくなる可能性があります。
また、放置された空き家が抱える倒壊や火災などのリスクをなくせるのもメリットの一つです。空き家を原因としたトラブルは周囲に実害が及ぶ恐れもあるので、地域の安全を守るためにも有用な制度だといえるでしょう。
空き家解体補助金の主な種類と対象
空き家の解体補助金は、大きく分けると、主に以下の3種類に分類されます。それぞれ、一般的な補助対象や補助額などを見てみましょう。
- 老朽化して危険な空き家の解体を目的とするもの
- 空き家の活用や流通を目的とするもの
- アスベスト除去やブロック塀撤去に関するもの
老朽危険家屋解体撤去補助金
老朽危険家屋解体撤去補助金は、老朽化によって倒壊や火災の危険性が高まっている空き家の解体費用を補助する制度です。
補助対象となるのは、住宅地区改良法における「不良住宅」に該当する場合や、自治体の判定基準に該当する場合です。補助限度額は30万~100万円程度で、補助助成率は2分の1~10分の8程度が一般的です。具体的な条件は自治体ごとに異なるため、必ず該当する自治体の制度をチェックしましょう。
例えば、東京都墨田区では、不良住宅に該当する場合に上限額50万円、補助率2分の1までを補助していますし、長野県長野市では、市が定めた「補助事業対象要件確認表」の要件に該当する場合に、上限額100万円、助成率10分の8までを補助しています。
木造住宅解体工事費補助事業
木造住宅解体工事費補助事業は、現行の耐震基準に適合しない、築年数の古い木造住宅の解体を補助する制度です。主に、1981年5月31日以前に建築確認を取得した「旧耐震基準」の住宅が対象になります。
一般的な補助上限額は30万~80万円程度で、一般的な補助率は解体費用の2分の1前後です。例えば横浜市の例を挙げると、補助上限額は50万円、補助率は最大で3分の1となっています。
なお、制度を利用するためには、耐震診断や自治体が定めるチェック方法で、耐震基準に満たないことを証明する必要があります。具体的な方法は自治体によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
アスベスト除去・ブロック塀撤去に関する補助金
アスベスト除去補助金は、アスベストを含む吹き付け材や保温材を使用している場合、または使用の可能性がある場合が対象となり、ブロック塀撤去補助金は、高さが一定以上であり、危険と認められるブロック塀で公共の道路に面しているものが補助対象となります。どちらも周囲に危険を及ぼすリスクが高いため、早急な撤去を促すために定められました。
補助対象や補助率は以下のとおりです。
アスベスト除去補助金
- 補助対象:アスベストを含む吹き付け材や保温材を使用している場合、または使用している可能性がある場合
- 補助率:2分の1~3分の2程度
- 補助限度額:30万~200万円程度
ブロック塀撤去補助金
- 補助対象:高さが一定以上であり、危険と認められるブロック塀で、公共の道路に面しているもの
- 補助率:2分の1~3分の2程度
- 補助限度額:10万~50万円程度
自治体独自の空き家解体補助金

自治体の中には、独自の空き家解体補助金を扱っているところもあります。特に多いのが定住促進を目的とした解体補助金で、30万~100万円程度と高額な補助金を受け取れる可能性があります。
例えば埼玉県の東秩父村では、空き家を有効活用して定住促進を図るために、空き家の解体費用を上限30万円、補助率2分の1まで補助しています。空き家バンクに登録されている物件の場合は、さらに10万円が補助されます。
また、千葉県佐倉市では空き家の利活用を促進するために「中古住宅解体新築支援事業」という事業に基づき、補助上限額50万円、補助率5分の1を補助しています。
さらに長野県松川村では、空き家を有効活用して次世代へ継承するために、おおむね1年以上空き家になっている住宅を解体して住宅建築用地にする場合に最大で100万円、補助率2分の1までを補助しています。
このように、定住促進を目的とした解体補助金は、人口減少や空き家問題が深刻な地方部ほど手厚くなる傾向にあります。その他の定住促進事業との併用をできる場合も多いので、地方への移住を検討している場合は、積極的に活用しましょう。
解体補助金を受け取るまでの流れとスケジュール
ここからは、解体補助金を利用する際の流れとスケジュールを5つのステップに分けて解説します。各ステップでの準備や対応を間違えると、補助金が下りないこともあるため、あらかじめポイントを押さえておきましょう。
なお、ここでは各補助金に共通している部分に限定して解説します。細かな流れやスケジュールは制度ごとに異なるので、直接自治体に確認してください。
ステップ1:事前確認とスケジュール調整
最初にやるべきことは、自分の物件が補助対象かどうかを確認することです。補助金の支給条件は自治体ごとに異なるため、対象地域や建物の条件、補助額、申請期限などを調べておきましょう。
多くの自治体では各種条件をウェブサイトに掲載していますが、中には条件が複雑で理解が難しいものもあります。法令独特の言い回しで書かれていることも多く、自分の解釈と実際の意味が異なる場合もあります。判断に悩んだら、迷わず直接問い合わせましょう。
また、今のうちに申請の準備から補助金が振り込まれるまでの期間を見積もっておきましょう。補助金によっては、年度内の工事完了を求められる場合があるので、年度後半に始める場合は特に注意が必要です。
なお、年度末が近づくと補助金の予算が無くなる可能性もあります。あらかじめ予算の残りがあるかを確認し、予算が無くなっている場合は、翌年度も同じ補助金を使えるか確認しておきましょう。
ステップ2:交付申請と審査
対象条件を満たすことを確認できたら、次は必要書類の準備と交付申請をします。間違いなく審査が通るように、あらかじめ窓口で相談・調整をしてから申請するのが一般的です。
必要書類は、自治体で用意している申請書と、建物の情報が分かる書類や工事内容が分かる書類、工事業者が分かる書類などの添付書類などを用意します。よく求められる書類には以下のようなものがあります。
- 建物の登記簿謄本(所有者確認用)
- 固定資産税の納税証明書(税金の滞納がないことの証明)
- 解体工事の見積書
- 建物の外観・内部写真(老朽化の状態確認)
- 耐震診断書(制度によっては任意または必須)
- 解体業者との契約書(着工前に契約済みであること)
ちなみに、工事の内容によっては、審査期間中に自治体職員による現地確認や立ち会いが必要になることもあります。
ステップ3:交付決定と契約内容の再確認
申請書類の審査が終わり、補助金の交付が決まると、自治体から補助金交付が決定したことを伝える「交付決定通知書」が渡されます。この通知をもって初めて補助金の支給対象になりますので、交付決定前の着工は避けてください。
また、この段階で、解体費用の見積金額が補助対象に適合しているか、工事内容やスケジュールが自治体の条件に沿っているかなど工事業者に依頼する契約内容の再確認もしておきましょう。
ちなみに、補助対象が「建物の除却費のみ」の場合は、解体工事時の足場設置費や庭木の撤去費、整地費などが補助対象外になる可能性もあります。契約書の内訳を細かく確認し、補助対象になる工事項目を明確にしておきましょう。
ステップ4:解体工事と完了報告
契約内容に問題がないことが確認できたら、解体工事に着工します。
このとき、工事前と工事中、そして完了時の写真は必ず残しておいてください。工事完了後に自治体による完了検査があるので、問題無く工事が進行・完了したことを書面で確認できるようにしておく必要があります。なお、自治体によっては、職員が工事中や工事完了後に直接現地を確認することもあります。
また、解体で出た廃材が適切に処理されたことを証明するために廃棄物処理業者から「産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)」を受け取っておくことも忘れてはいけません。
以下に工事完了後に提出する一般的な書類をまとめました。
- 完了報告書(工事の概要・実施内容を記載)
- 解体後の現場写真
- 解体業者からの請求書・領収書
- 工事内容が分かる明細付き契約書
- 廃材処分証明書(産業廃棄物の適正処理を証明)
ステップ5:補助金の受領と書類の保管
工事の完了報告をしたのち提出書類に問題がなければ、最終審査が完了し、補助金の支払いが確定した旨の通知が届きます。その後、請求書類を提出し、それから数週間~1カ月程度あとに指定した口座に補助金が振り込まれます。
空き家の解体補助金を使えなかった場合の対処法
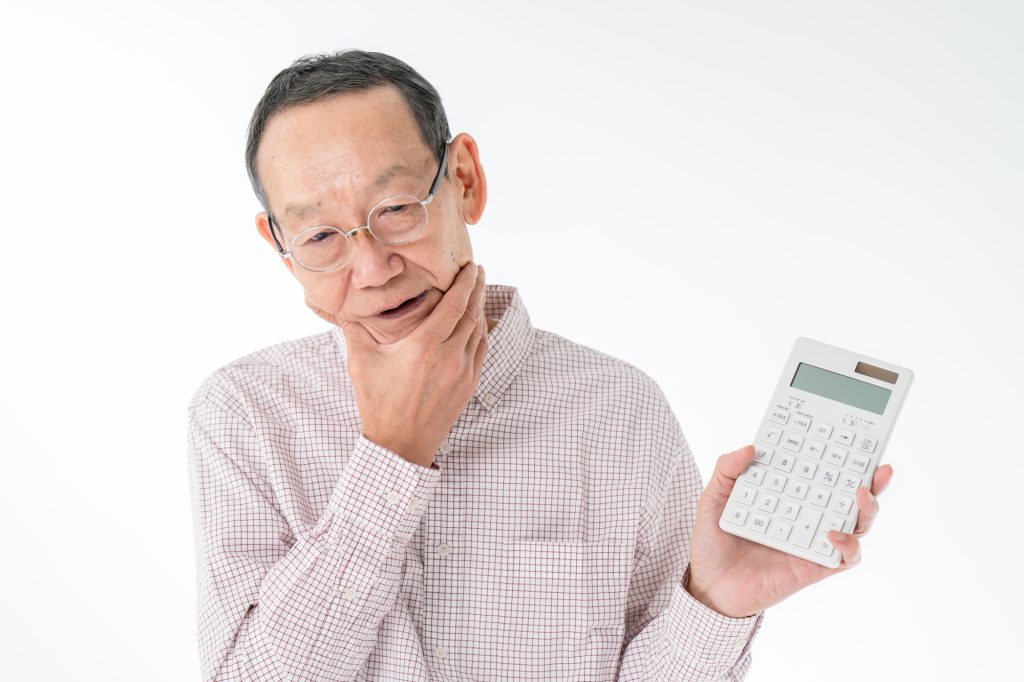
最後に、補助金を利用できなかった場合にできる、解体費の節約方法を紹介します。
補助金は建物が基準に満たないことで不支給になる以外にも、申請者の税金滞納が原因で不支給になったり、そもそも事業が終了していて利用できなかったりすることもあります。そこでここでは、代表的なケースを3つ挙げ、それぞれの対処法を解説していきます。
準備不足の場合は自治体に相談して再申請を
申請が不受理となった場合でも、翌年度以降に再挑戦できるケースは多くあります。
たとえば、固定資産税の滞納が理由で却下された場合は、完納することで翌年の申請条件を満たせる可能性がありますし、書面上では建物の耐震性があると判断された場合でも、実際に耐震診断を受けたら耐震性不足と判断されることもあります。
いずれの場合も、自治体の担当窓口に理由を確認して改善点を明確にすることが大切です。再申請が可能であれば、今度は間違いなく審査が通るように、職員に相談しながら準備を進めていきましょう。
補助金の要件に該当しない場合は見積もり合わせで工事費を下げる
補助金が出ない場合は、工事費そのものを下げる工夫をしましょう。特に有効なのが、複数の解体業者から見積もりを取って、内容と価格を比較検討する「見積もり合わせ」という方法です。
なお、見積もりを比較する際には以下のポイントに注意しましょう。
- 工事項目の内訳が明記されているか(曖昧な項目に注意)
- 廃材処分費や整地費などが個別に計上されているか
- アスベスト処理などの追加費用が含まれているかどうか
なお、このときに説明の丁寧さや対応の早さ、補助金手続きへの理解などのサービス面もチェックしておきましょう。
解体費用の捻出自体が難しければ空き家活用サービスも検討しよう
解体補助金を受け取ることができず、解体費用の捻出が難しい場合は、別の選択肢として、空き家を貸し出す「空き家活用」も考えてみましょう。借り手がつけば毎月賃料が受け取れますし、借り手が日常管理をしてくれるため、管理の手間もなくなります。
特におすすめなのが自己負担0円(※)で空き家活用が始められる「アキサポ」です。「アキサポ」では、空き家の周辺調査から活用方法の提案、リノベーションまでをワンストップで対応可能です。自分の空き家にどのような使い道が見込めるか知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
※建物の状況等によっては、一部費用のご負担をお願いする場合がございます。
まとめ・総括
解体補助金は、空き家を解体するハードルを大きく下げてくれる頼もしい制度です。土地のポテンシャルが高い場合には、買い手や借り手を見つけやすくしてくれますし、空き家の劣化が激しい場合は、内包されるリスクをなくすことができます。
もし補助金が使えなかった場合でも、複数社の見積もりを比較したり、空き家活用サービスを検討したりすることで、費用負担を抑えることが可能です。中には「アキサポ」のように持ち出し0円で始められるサービスもありますので、新たな選択肢として活用を検討してみてください。
この記事の監修者

山下 航平 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
ハウスメーカーにて戸建住宅の新築やリフォームの営業・施工管理を経験後、アキサポでは不動産の売買や空き家再生事業を担当してきました。
現在は、地方の空き家問題という社会課題の解決に向けて、日々尽力しております。








