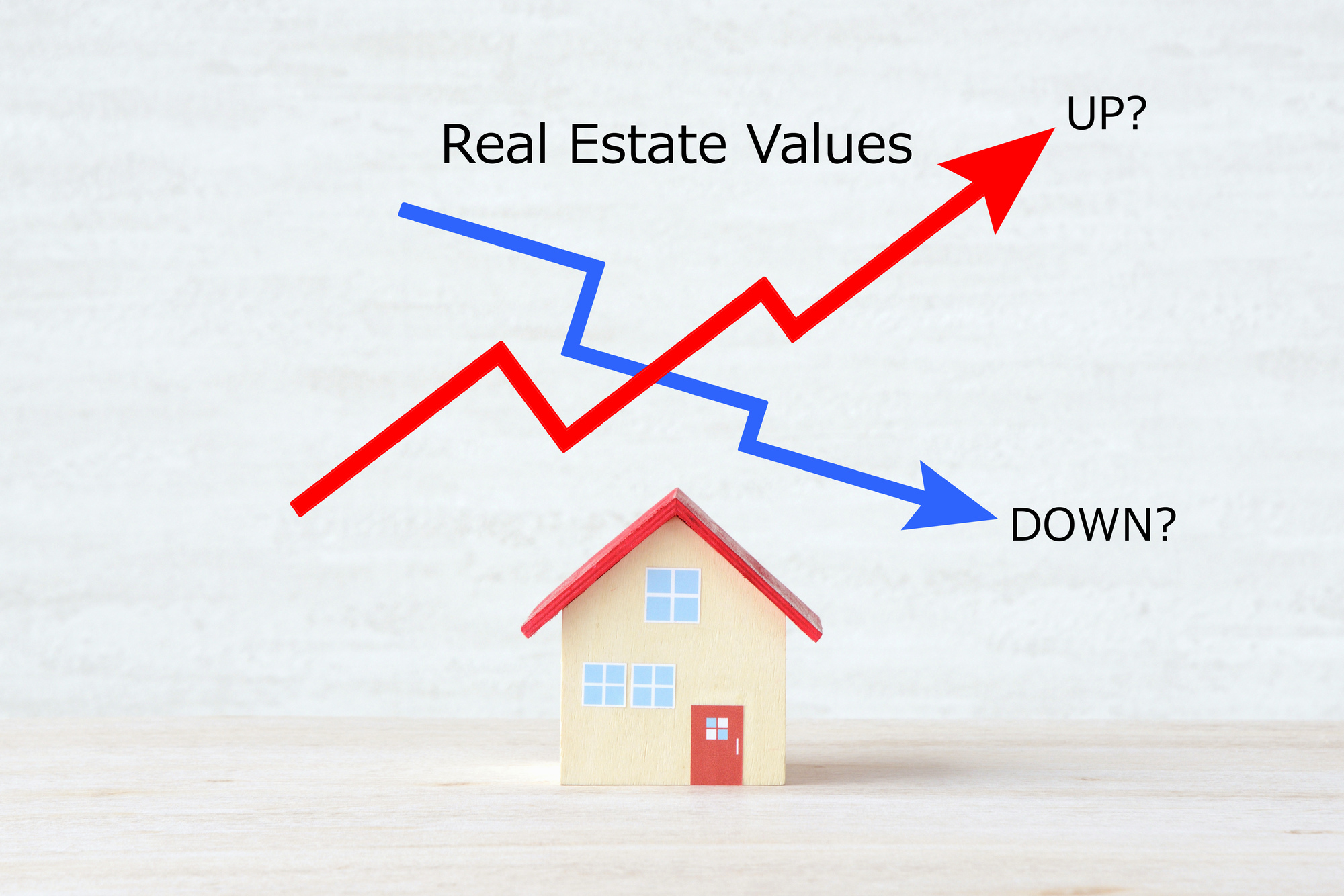公開日:2025.10.03 更新日:2025.09.26
【土地評価額の基礎知識】調べ方・計算方法・税金対策を徹底解説

土地の売却や相続、税金の計算をする際などによく「土地評価額」という単語が登場しますが、具体的な定義や算出方法などを知らない人も多いのではないでしょうか。
実際、土地評価額には実勢価格・公示価格・固定資産税評価額・相続税評価額という複数の基準があり、場面によって使い分けが必要になるため、初めて見る人は混乱しがちです。
そこでこの記事では、土地評価額の種類から、それぞれの調べ方や計算方法、さらには税負担を抑えるための対策までを、分かりやすく解説します。不動産の取引や相続を控えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
土地評価額の基本「一物五価」とは?5つの種類と目的を解説

土地の評価額とは、その土地がどれくらいの経済的価値を持つかを、一定の基準で数値化したものです。不動産の取引や税金の計算、資産の相続など、暮らしや資産管理に関わる場面で頻繁に登場します。
土地の価格には「ひとつの正解」があるわけではなく、売買や相続、課税、公共事業などの用途によって、異なる基準に基づく価格が適用されます。この考えに基づいて、1つの土地に対して5つの評価方法が用いられるため、これらをまとめて「一物五価(いちぶつごか)」と呼びます。
土地評価額に用いられる5種類の評価方法
- 実勢価格(時価)
実際に売買された価格。主に売却・購入時の相場把握に用いられる - 公示価格
国が毎年発表する基準価格。主に公共事業や不動産鑑定の目安として利用される - 固定資産税評価額
市区町村が税金を計算するために定める価格。固定資産税や都市計画税の課税ベースに用いられる - 相続税路線価
相続税や贈与税の評価額を算出するための基準。道路の路線ごとに隣接する土地1㎡あたりの価格が設定されている - 基準地価
都道府県が発表する土地の標準価格。地価の傾向や変動を把握するための指標となる
土地の評価額が必要となるケース

土地評価額が必要となるのは主に「売却するとき」「税金を払うとき」「相続や贈与が発生したとき」です。具体的には以下のようなケースで活用されます。
- 売却価格の目安を把握するため
- 固定資産税や都市計画税の課税額を知るため
- 相続税・贈与税の計算に活用するため
まずはそれぞれのケースにおいて、具体的にどのように利用されるかを見ていきましょう。
売却価格の相場を把握するため
土地の売却価格の相場を把握する際には、評価額の一つである「実勢価格(実際の売買事例)」や「公示価格(国が発表する標準価格)」を参照することが多いです。
ただ、エリアが近くても、土地の形や隣接する道路の広さ、用途地域など、土地の細かな条件によっても価格は変わってきます。これらも含めて、なるべく近い条件の土地を参照するのがポイントです。
固定資産税や都市計画税の課税額を知るため
所有している土地に毎年課される「固定資産税」と「都市計画税」は、「固定資産税評価額」に税率をかけて計算されます。税率は固定資産税が基本的に1.4%、都市計画税が制限税率0.3%です。
たとえば、評価額が3,000万円で、固定資産税1.4%、都市計画税0.3%の場合は以下のようになります。
- 固定資産税(標準税率1.4%):3,000万円 × 1.4% = 42万円
- 都市計画税(制限税率0.3%):3,000万円 × 0.3% = 9万円
なお、住宅用地は課税標準が軽減される特例があり、固定資産税は最大で6分の1、都市計画税は最大で3分の1まで軽減される場合があります。また、都市計画税は都市計画区域内にある土地にのみ課税されます。
相続税・贈与税の計算に利用するため
土地の評価額は、相続税や贈与税の課税対象額(課税価格)を算出する基礎数値としても用いられます。
たとえば相続の場合、財産全体の評価額から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出した基礎控除を引いた残りが課税対象となり、ここに価格ごとに定められた税率が課されます。
贈与の場合も同様で、基礎控除額の110万円を超えた分の評価額に対して、累進課税で贈与税がかかります。
実勢価格(時価)の調べ方と計算方法

実勢価格はいわば「実際に売れた価格」に基づいた「いま現在のリアルな価値」です。具体的な場所や条件が分かれば、その土地がなぜその価格で取引されたのか、その根拠が分かるため、売買する際にとても参考になります。
実勢価格の主な調べ方は以下のとおりです。
- 不動産取引価格情報検索システム(国交省)で近隣の取引事例を検索
- ㎡単価 × 自分の土地の面積で、概算の価格を計算
- 不動産会社の査定額と比較して、相場から大きく外れていないか確認する
なお、実勢価格は景気や金利、地域開発などの影響を受けて変動するため、情報が古いと参考にならない場合があります。なるべく最新の情報を参照しましょう。
公示価格の調べ方と計算方法
公示価格は不動産の評価や取引、公共事業での買収など、さまざまな場面の参考値となります。自分の土地が相場からどれくらいの位置にあるのかを把握するうえでも、押さえておきたい価格といえるでしょう。
公示価格の調べ方は以下のとおりです。
- 国土交通省の「地価公示・都道府県地価調査」ページで検索する
- 近隣の標準地(サンプル的な土地)の価格を確認する
- 自分の土地と標準地の条件(立地、形状、接道状況など)を比較して、参考価格を算出
ちなみに、公示価格の評価時点は毎年1月1日で、発表されるのは毎年3月頃です。上記の方法以外にも、市区町村の窓口に備え付けられている台帳でも確認することができます。
固定資産税評価額の調べ方
固定資産税や都市計画税のもとになる「固定資産税評価額」は、3年ごとに自治体が評価を行い、毎年4月頃に届く「納税通知書」につづられている「固定資産税(土地・家屋)課税明細書」によって通知されます。
出典:埼玉県新座市
上記は埼玉県新座市の例ですが、所有している不動産ごとに評価額が記載されているのが分かります。また、不動産ごとに参考税額も掲載されています。
なお、課税明細書を紛失してしまった場合は、市区町村の役所で「固定資産課税台帳」を請求・閲覧して確認できます。
相続税路線価の調べ方と計算方法
相続税や贈与税を算出する際の基準となるのが「相続税評価額」です。この評価額は「路線価」に基づいて計算されます。
路線価を用いた相続税評価額の求め方は以下のとおりです。
1. 国税庁の「路線価図」ページで住所を検索
2. 該当する道路の1㎡あたりの価格(円/㎡)を確認
3. 土地の面積に路線価を掛け、さらに形状や奥行・間口に応じた補正率をかけて算出
例えば、路線価が20万円/㎡で土地が100㎡なら、基準額は2,000万円です。ここから不整形地補正や奥行価格補正を適用して最終的な評価額が決まります。
なお、路線価は毎年1月1日時点の価格を基準として評価され、毎年7月に国税庁から公表されます。形の悪い土地である「不整形地」や、入口が細い「旗竿地」などは補正により評価が下がる場合があります。
基準地価の調べ方
「基準地価」は発表主体の都道府県で調べることができます。基準地価の調べ方は以下のとおりです。
- 都道府県が運営する「基準地価公表ページ」または国交省の統合データベースから検索する
- 住所や地名で近隣の基準地の価格を探す
- 公示価格と比べて、地価が上がっているか・下がっているかの傾向を確認
なお、基準地価の評価時点は毎年7月1日で、発表は9月頃です。1月1日時点の価格である公示価格と合わせてチェックすることで、年2回の地価動向を把握できるので、売却や評価のタイミングを見極める材料として有効です。
土地評価額を下げたい場合の対策

評価額は国や自治体のルールで決められているため、基本的には自分の裁量で操作できません。ただし、土地の形状や利用状況によって、正しく評価されていないケースもあります。
そこでここでは、土地の評価額を下げられる可能性がある方法を3つ紹介します。
1. 現地調査で評価減の要素を見直す
土地の評価額は、土地の形や状態によって、本来よりも低く評価される場合があります。たとえば以下のような条件に該当する土地において、これらの条件が反映されていない場合は、評価の見直しをすることで価格が下がる可能性があります。
- 土地の一部が傾斜している、または崖地になっている
- 私道部分やセットバック部分が含まれている
- 極端に細長い土地や旗竿地など、不整形な形状になっている
なお、固定資産税評価額の見直しは市区町村の資産税課に相談し、必要に応じた現地調査を行ったうえで判断されます。
一方で、相続税評価額は国税庁が公表する路線価を基準に、納税者自身が不整形地補正やセットバック減価などを適用して計算します。そのため、固定資産税のように役所に「見直しをしてもらう」ことはできません。
2. 小規模宅地等の特例を活用する
相続時に、被相続人(亡くなった方)の住居や事業に使っていた土地を引き継ぐ場合、一定の条件を満たせば、評価額が最大80%減額される「小規模宅地等の特例」という制度が適用される場合があります。
具体的には以下のような場合に適用されます。
- 被相続人が亡くなる直前まで自宅や事業用地として使っていた土地であること
- 相続人がその土地を引き続き居住または事業に使用すること
- 土地の用途に応じた面積制限(例:居住用宅地は330㎡まで)を超えないこと
- 相続開始から一定期間、土地の利用を継続していること(申告期限までの居住継続など)
ただし、適用には細かな条件や上限面積などがあるため、制度の内容を誤解したまま申告すると認められないこともあります。あらかじめ自治体の窓口や税務署などに相談しておくと安心です。
3. 土地の利用方法を見直して相続税評価額を下げる
土地の評価額は「現況主義」で決まるため、利用の仕方を変えると評価基準そのものが下がる場合があります。
例えば、更地よりも建物を建てて「貸家建付地」として活用した方が、相続税評価額が低くなる場合があります。また、宅地の一部を駐車場や資材置き場として利用すると「雑種地」と評価され、宅地よりも評価額が低くなるケースもあります。ただし、この場合は住宅用地の特例は使えなくなるため、どちらが有利かはケースごとの試算が必要です。
もちろん新たな建築費や維持費もかかるため、必ずしもすべての土地で有効とは限りませんが、長期的に利用を続ける予定があるなら選択肢として検討する価値があります。
4. 不動産会社・専門家に相談する
土地評価額を下げられるかを個人で判断するのは難しく、特に、不整形地補正や小規模宅地特例などを適用できるか判断するには、専門的な知識が求められます。
そこで頼りになるのが、不動産会社や税理士などの専門家です。不動産会社に査定を依頼すれば、売却を見据えた相場観を確認できますし、税理士に相談すれば相続税評価額や各種特例の活用可否を具体的に試算してもらえます。また、不動産鑑定士に依頼すれば、地形や利用状況を踏まえて評価が適正かをチェックしてもらえます。
制度や補正を見逃したまま申告すると、余計な税負担につながりかねません。早い段階で専門家に相談しておくことが効率的で安全な対策になります。
【まとめ】土地評価額の正しい理解が賢い資産形成につながる
最後に一点、大切なことを覚えておきましょう。それは、土地評価額は一度調べて終わりではなく、売却・相続・課税など、必要なときに確認し直すことが大切ということです。今回学んだ評価の種類や算出方法に基づいてチェックしておけば、必要な対策が分かりますし、ひいては余計な税負担を防ぐことにもつながります。
もし「自分の土地は正しく評価されているのか」「節税できる制度に当てはまるのか」と不安がある場合は、早めに不動産会社や税理士などの専門家に相談してみましょう。知識だけで終わらせず、具体的な行動につなげることが、損をしない第一歩になります。
この記事の監修者

山下 航平 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
ハウスメーカーにて戸建住宅の新築やリフォームの営業・施工管理を経験後、アキサポでは不動産の売買や空き家再生事業を担当してきました。
現在は、地方の空き家問題という社会課題の解決に向けて、日々尽力しております。