公開日:2025.10.22 更新日:2025.09.26
コインパーキング経営の始め方|初期費用・儲かる仕組み・税金まで徹底解説

コインパーキング経営は、更地のままで始められる手軽な土地活用として人気があります。初期費用を抑えられ、将来的に別の用途へ転用しやすい点が大きな魅力です。ただ、実際に始めるとなると、本当に儲かるのか不安になる方も多いでしょう。
実際に、コインパーキングは立地条件や料金設定を誤ると、稼働率が上がらず思ったほど収益が出ないリスクがあります。さらに、更地扱いとなることで固定資産税が高くなるなど、見落としがちなデメリットもあるため注意が必要です。
そこでこの記事では、コインパーキング経営の仕組みや運営方法の種類、初期費用や維持費の目安、成功するための具体的なポイントをわかりやすく解説します。土地活用を検討している方にとって、メリットとリスクを比較しながら判断する参考になるはずです。
目次
コインパーキング経営とは?仕組みと特徴

コインパーキング経営とは、所有している土地を時間貸しの駐車場にして、利用者から料金を得るビジネスモデルのことです。建築物を建てないため初期費用を抑えやすく、短期間で始められる特徴があり、比較的手軽に始められる土地活用として人気があります。都市部では次の土地活用が決まるまでの間の、一時的な活用法としても用いられます。
また、建築物を建てないため、土地の用途変更がしやすく、将来的な転用が容易な点も大きな特徴です。精算機や街灯など、一定の設備を撤去する必要はありますが、建物の解体と比べれば撤去費用は少なく抑えられます。
コインパーキングの収益は、周囲の人通りや周辺施設に大きく影響されます。商業エリアや観光地のように人や車の往来が多い場所では高い稼働率を期待できますが、需要の少ないエリアでは収益が伸び悩むリスクもあります。
コインパーキング経営の3つの運営方法
コインパーキングの種類は大きく以下の3つに分けられます。
- 自主管理方式
- 管理委託方式
- 一括借り上げ方式(サブリース)
「この方法が正解」という明確な答えはないため、方法を選ぶには、それぞれの特徴を把握することが欠かせません。
そこでここでは、それぞれの方法のメリット・デメリット、そしてオーナーに求められる負担の違いを見ていきましょう。
自主管理方式:自由度が高いが運営負担も大きい
自主管理方式は、機器の導入や料金設定からメンテナンス、クレーム対応までをオーナーが自分で行う方式です。自由に料金を設定できたり、独自のキャンペーンを打ち出せたりするため、運営方針にこだわりたい人には向いています。
ただし、その分だけオーナーの負担は大きくなります。例えば、設備の故障や不正駐車が起こった場合は、それらの対応をすべて自分で行う必要があります。夜間や休日にトラブルが発生することも考えられますので、こうしたリスクを見据えて、トラブル時の連絡体制やサポート体制をあらかじめ決めておくことが求められます。
管理委託方式:専門業者に任せて経営効率を高める
管理委託方式とは、精算機やゲートといった設備の導入から日々の運営業務、トラブル対応までを専門業者に委託する方法です。オーナーは管理費を支払う代わりに、基本的に管理業務を行いません。手間を大幅に減らせるため、初心者でも比較的安心して始められます。
管理費用が差し引かれるため、自主管理よりも利益率は下がりがちですが、業者が持つノウハウやネットワークを活用することで稼働率が高まり、結果的に効率よく収益を確保できるケースもあります。特に、複数の土地を保有しているオーナーや、本業を持ちながら副業として駐車場経営を行う人にとっては現実的な選択肢となるでしょう。
一括借り上げ方式(サブリース):リスクを抑えて安定収入を目指す
一括借り上げ方式(サブリース)とは、運営会社がオーナーの土地を一括で借り上げ、利用状況にかかわらず毎月一定の賃料(保証賃料)をオーナーに支払う仕組みです。稼働率に左右されない安定した収入が最大のメリットです。
一方で、駐車場の稼働率が高くても、追加の利益がオーナーに反映されにくい点には注意が必要です。高収益を狙うよりも、安定性を重視する人に向いており、相続対策や長期的な資産保有を考える場合には有効な選択肢になります。
一括借り上げ(サブリース)契約では、借地借家法に基づき賃料減額請求や中途解約制限が認められるケースがあります。そのため、契約前には保証賃料の見直し条件や解約条項を必ず確認しましょう。
コインパーキング経営にかかる初期費用

コインパーキングを開業するには、土地の整備に加えて、精算システムや防犯設備などをまとめて導入する費用が必要です。建物を建築する場合に比べれば投資額は抑えられますが、一度にある程度まとまった金額が必要となる点は押さえておきましょう。
主な初期費用の内訳は以下のとおりです。
- 敷地整備費用:整地・舗装工事、ライン引きなど
- 駐車設備費用:ロック板、ゲート式機器、車止めなど
- 精算システム費用:現金式精算機、キャッシュレス対応機器
- 付帯設備費用:照明、防犯カメラ、看板、フェンスなど
- その他費用:設計・施工費、管理会社との契約手続き費用
例えば、10台規模の駐車場を整備する場合、整地や舗装で数百万円、精算機1台で100万〜200万円、防犯カメラや照明を含めると総額で500万〜1,000万円程度になるケースが一般的です。
ここで気を付けたいのは、工事の内容は初期費用だけでなく、収益性への影響や、開業後にかかるランニングコストやメンテナンス費用なども踏まえて考えることです。
たとえば、舗装を砂利にすれば初期費用は抑えられますが、雨天時に水たまりができやすく、利用者の満足度が下がる可能性があり、稼働率が下がる恐れがあります。逆に、しっかりと排水設備まで整備すれば費用はかさみますが、長期的に見れば稼働率の向上や修繕コストの削減といったメリットが期待できます。
コインパーキングの開業までの流れ
コインパーキングを開業するまでの一般的な流れは以下のとおりです。
①土地の確保
運営コンセプトに合った土地を選び、所有者や不動産会社と契約を結ぶ
②運営方式の決定
自主管理・管理委託・一括借り上げのいずれで運営するかを決める
③設備導入の準備
精算機やロック板、防犯カメラなど必要機器を選定し、施工業者と打ち合わせる
④料金設定の確定
周辺相場や需要を踏まえて料金を決定する
⑤近隣への周知
開業前に住民や自治体に概要を説明し、トラブルを防ぐ
⑥運営開始と改善
開業後は利用状況を確認し、料金や設備を見直して稼働率を高める
コインパーキングは建築物を建てないため、建築基準法上の建築確認申請や都市計画法上の開発許可は不要です。そのため、比較的スムーズに開業準備を進められます。
ただし、規模が大きい場合は、自治体によっては周辺への影響を考慮して協議を求められる場合があります。また、開業後のトラブルを避けるために、近隣への説明も行っておきましょう。特に住宅街では、騒音や出入りの増加がトラブルにつながる可能性があります。
コインパーキング経営のメリット・デメリット
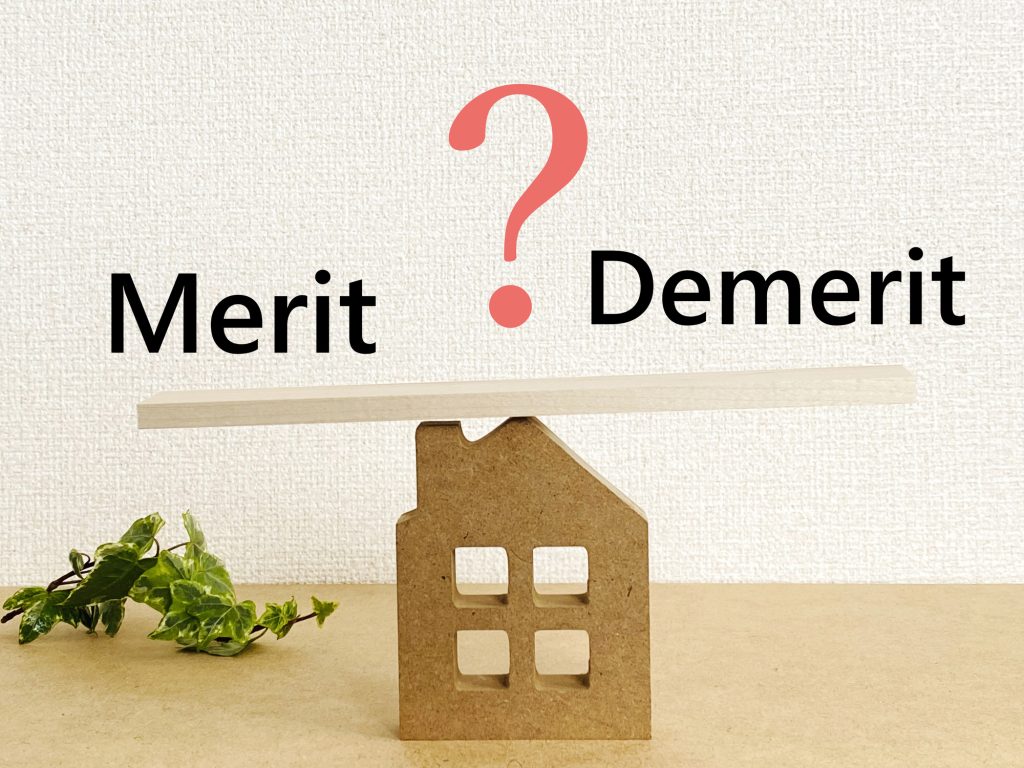
コインパーキングは比較的手軽に始められる土地活用ですが、立地条件や需要の変動によって収益性は大きく変わります。そこで、メリットとデメリットを整理して見てみましょう。
コインパーキングのメリット
- 転用しやすい:建築物がないため撤退がしやすく、将来的な転用がしやすい
- 大規模修繕が不要:建築物がないため外壁や給排水設備などの修繕が不要
- 管理負担が軽い:日常的には舗装や精算機の点検程度で済む
コインパーキングのデメリット
- 収益が立地に依存する:住宅街のような周囲に人の集まる施設がない場合、稼働率が下がりやすい
- 需要の変動に左右される:曜日や時間帯で利用状況が大きく変わるため、安定収益を得にくい場合がある
- 市場調査の継続が必要:定期的に競合や利用傾向の分析を行う負担がかかる
このように、コインパーキングは「転用のしやすさ・管理のしやすさ」という大きな強みを持つ一方で、「需要変動や立地依存」という弱点も抱えています。実際に経営を検討する際は、この両面を理解したうえで計画を立てることが成功のカギとなります。
コインパーキング経営に最適な土地を探す3つのポイント
コインパーキングの収益性は、土地の立地や周辺環境に大きく左右されるうえに、設備面で差をつけにくいため、土地選びの重要性は特に高くなります。ここでは、土地を探す際に必ず留意すべき3つのポイントを解説します。
周辺の人の流れと周辺施設の状況
土地探しの基本となるのが、周辺エリアの人の流れや周辺施設の状況です。たとえば、商業施設や飲食店、イベント会場といった人が集まりやすい場所の近くは、コインパーキングの需要が高くなりやすいです。さらに、利用者が集中する曜日や時間帯を把握できれば、最適な料金設定や、周辺道路への看板設置などで効率よくアピールできるでしょう。
他にも、地域の再開発や新規商業施設の建設計画があるエリアであれば、将来的に需要が高まる可能性もあるため、先行投資をする選択肢も出てきます。特に都市部では周辺環境の変化が激しいため、長期的な経営方針を立てる際には、都市計画や再開発情報をチェックしておくと安心です。
一方で、周囲に特筆すべき施設がないエリアや、各家庭の敷地が広く駐車場を利用する必要性が薄いエリアなどでは収益が期待しにくいです。周囲にどのような施設があり、そこへ来る人が何人程度いて、どれほどの駐車場が求められているのか、という点を考えましょう。
周辺にある競合コインパーキング
周辺の需要と合わせて確認したいのが、競合となるコインパーキングの状況です。近隣に多くの駐車場があれば価格競争が起こり、稼働率を維持するために柔軟な料金設定が必要となりますし、魅力的なコインパーキングがある場合は、開業しても稼働率が上がらない恐れも出てきます。
逆に、周辺に競合が少ないエリアであれば、相場よりやや高めの料金でも利用が見込める場合もあるでしょう。
たとえば、競合が密集する駅前エリアでは、短時間料金を低めに設定して回転率を高めるなど工夫が求められます。一方で、オフィス街で近隣に駐車場が不足している場合は高単価で安定した収益を狙えるでしょう。市場調査を怠らず、競合とのバランスを踏まえた経営判断を行うことが成功への鍵になります。
道路幅・土地形状・段差の有無
駐車場の利用者は「駐車のしやすさ」を重視します。そのため、車がスムーズに出入りできる道路幅があるか、進入口に段差がないかどうかは重要なチェックポイントになります。
たとえば、前面道路が狭い場合は車の出入りに支障が出やすく、利用を敬遠される可能性がありますし、極端に狭い土地の場合は駐車場内での転回がしにくく敬遠される恐れがあります。
また、土地に大きな高低差がある場合は、造成工事や擁壁の設置が必要となり、初期費用が大幅にかさむ可能性があります。事前の土地調査で必ず確認しましょう。
コインパーキング経営を成功させるためのポイント

コインパーキングは初期費用を抑えて始められる一方で、長く安定して収益を得るには工夫が欠かせません。特に料金設定やサービスの充実度、管理体制の強さは、稼働率や利用者満足度に直結します。さらに、撤退時の費用や税金といった見落としがちな要素にも注意が必要です。ここでは、経営を成功に導くために押さえておきたい具体的なポイントを紹介します。
周辺相場を踏まえた料金設定と稼働率の最適化
料金設定は稼働率と時間単価の両方に直結する重要なポイントです。コインパーキングの収益モデルは「単価 × 時間」というシンプルなものなので、ここの設定次第で運用成績は大きく変わってきます。
料金設定は、立地と時間帯による需要の高さに応じて高くするのが基本です。地価が高いエリアや駅前のような多くの人が利用する施設の近くであれば、基本料金が高くても受け入れられやすいですし、通勤時間帯や休日など需要が集中する時間はやや高めに設定しても利用されやすいです。逆に利用が少ない時間帯は、無理に料金を維持するよりも、割安料金で人を呼び込んで回転率を上げるのがよいでしょう。
収入アップを狙う追加サービスや設備投資
コインパーキングは設備面での差別化が難しいですが、それでも、可能な限り安心感や利便性を提供する工夫は必要です。たとえば、利用者に安全な印象を与えるために防犯カメラやLED照明の設置が求められますし、時間単価が高いエリアであれば、キャッシュレス決済への対応も必要になります。
他にも、EV(電気自動車)向けの充電設備の導入のような、特定の需要への対応も考えられます。
また、周辺に飲食店や商業施設が多い場合は、それらの施設と提携して駐車割引を提供したり、ポイントサービスを導入したりするサービスも考えられます。
信頼できる管理会社とのパートナーシップ
コインパーキングを安心して運営し続けるには、信頼できる管理会社との提携が欠かせません。豊富なノウハウを持つ会社なら、効果的な集客方法や料金設定のアドバイスを受けられ、設備トラブルにも迅速に対応してもらえるため、安心して運営を続けられます。
特に、繁華街のように夜間トラブルが懸念されるエリアでは、管理会社の実力が求められるでしょう。管理会社が、どのような警備会社や修理会社と連携しているのかもチェックしておきましょう。
撤退時の原状回復費用と税金の見落としリスク
土地を借りて運営する場合や、将来的に売却する予定がある場合などには、原状回復費用にも注意が必要です。コインパーキングは建築物がないため比較的少ない費用で済むものの、各種設備の撤去や舗装をはがす工事などで数百万円の費用が発生することがあります。
また、固定資産税の負担増にも注意が必要です。土地の固定資産税は、建築物がある場合は「住宅用地の特例」という特例によって最大6分の1まで減額されますが、コインパーキングは更地扱いとなるため、この特例が適用されません。さらに、固定資産税に加えて都市計画税も課税されるため、税負担は増える点に注意が必要です。
まとめ|コインパーキング経営は事前の調査と計画が成功のカギ
コインパーキング経営は、初期費用を抑えながら短期間で始められる土地活用法として魅力的ですが、差別化が難しいだけに、周辺環境や競合状況の調査を始めとした、事前の入念な計画が欠かせません。
さらに、料金設定や管理方式によっても収益性が大きく変わるため、運営の目的や目標値の達成を狙えるプランをしっかり考えておきましょう。
特に、資産形成の一環として行う場合は、専門家や管理会社と連携して長期的なプランを立てることが望ましいです。簡単に始められるからと油断せず、コインパーキング特有のリスクをケアできることを前提に進めていきましょう。
この記事の監修者

岡崎 千尋 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
都市計画コンサルタントとしてまちづくりを経験後、アキサポでは不動産の活用から売買まで幅広く担当してきました。
お客様のお悩みに寄り添い、所有者様・入居者様・地域の皆様にとって「三方良し」となる解決策を追及いたします。








