公開日:2025.10.28 更新日:2025.10.27
【アパート経営の基礎知識】初心者向け成功へのロードマップ

「安定した家賃収入を得ながら資産形成もできる」と聞いて、アパート経営に関心を持つ人は少なくありません。とはいえ、建設費やローン返済、空室リスクなどを考えると、「本当に自分にできるのだろうか」と不安に感じる方も多いでしょう。実際、十分な準備をせずに始めてしまい、思ったように収益が出ないケースも見られます。
そこでこの記事では、アパート経営の基本的な仕組みからメリット・デメリット、考えておきたいリスクとその対策、成功のための具体的なポイントまでをわかりやすく解説します。初めての方でも安心して経営を始められるよう、体系的に整理しました。
アパート経営とは?基本概要

アパート経営とは、所有するアパートを入居者に貸し出して家賃収入を得る不動産投資の一形態です。個人でも、土地活用や資産形成のための投資として行うケースなどがあり、ポピュラーな不動産経営方法として定着しています。
アパートの構造や規模は、立地や予算などによってさまざまです。最近は劣化しにくく建築基準法上の資産価値が下がりにくい鉄筋コンクリート造を選ぶ人も増えています。
ちなみに、アパート経営は相続税対策としてもよく用いられます。特に、アパート自体に適用される「借地権割合(※1)」と敷地に適用される「貸家建付地(※2)」の制度は節税効果が高いことで知られています。
※1 貸家建付地の借地権割合
相続税評価額を算出する際、建物が建っている土地に「借地権」という価値が認められる。路線価図などに記載されているA(90%)、B(80%)、C(70%)といった区分がそれにあたり、土地の評価額に借地権割合を掛けることで、相続税評価額を下げることができる
※2 貸家建付地
建物を第三者に貸している土地は、自由に使えない制約があるため、評価額を下げることが認められており、これを「貸家建付地」と呼ぶ。土地の評価額に一定の補正率が適用されることで、相続税の課税対象額を抑えられる
アパート経営で成功するのはどんな人?向いている人の特徴
アパート経営は、安定的な収入を得ながら資産形成を目指す人に向いています。特に「長期的に不動産を運営し続ける姿勢」を持っている人に向いているでしょう。一方で、短いスパンで資産を増やしたい人には向いていません。
アパート経営はローン返済を重ねながら10年、20年と時間をかけて家賃収入を積み上げていくビジネスです。最初はローン返済や初期投資の回収であまり利益が出ないため、短期的な利益を期待するのは難しいです。
一方で、初期投資の回収とローン完済後は、家賃収入の大半が利益となるため、腰を据えて長期的にアパート経営に取り組める人ほど成功しやすいのです。
ちなみに、アパート経営には一定のリスク許容度も必要です。空室が出たり、想定外の修繕が発生したりすることは避けられないため、ある程度の余裕資金は確保しておきたいところです。
アパート経営と他の不動産経営との違いは?

不動産経営には、マンションや戸建て、テナントといった別のスタイルもあります。では、それらとアパートはどのような点で差別化できるのか、それぞれの違いを整理しておきましょう。
マンション経営との違い
アパートとマンションの違いは、構造や規模、建築コスト、入居者層、そして資産価値の維持しやすさにあります。
アパートは木造や軽量鉄骨造が多く、比較的小規模で建築費や管理費を抑えられるのが特徴です。ただし、木造は鉄筋コンクリート造よりも法定耐用年数が短いため、築年数が経過すると劣化が早く、修繕やリフォームが頻繁に必要になる傾向があります。
一方でマンションは鉄筋コンクリート造が一般的で、法定耐用年数が長く資産価値を維持しやすい特徴があります。ただしその分、建築費や管理費は高額になります。
また、両者は入居者層も異なります。アパートは家賃が比較的安いため単身者や若年層に人気があり、マンションは防音性や設備が優れているため、ファミリー層や長期入居者を惹きつけやすい傾向があります。
その他に、税制面でも減価償却年数や固定資産税額といった違いがあります。不動産経営を投資目的で行うのであれば、これらを比べて、より資産計画に適した方を選ぶとよいでしょう。
一戸建て賃貸経営との違い
アパートと一戸建て賃貸の違いは、収益構造とリスク分散のしやすさ、管理コストの範囲にあります。
アパートは複数室から家賃収入を得られるため、1室が空室になっても他の部屋でカバーでき、比較的収益の安定性が高いですが、一戸建て賃貸は入居者が退去すると収入がゼロになるリスクがあり、空室が続くと経営への打撃が大きくなります。
ただし、アパートは共用部分の維持や定期的な修繕など管理コストが多岐にわたり、経営に手間がかかる特徴があります。一方で戸建て賃貸は、建物全体を入居者が管理するため、アパート経営と比べると運営の手間があまりかからないという特徴があります。
このように、両者を比べる場合は、空室リスクの差と管理の手間の2点を主軸に検討するとよいでしょう。
テナント経営との違い
アパートとテナント経営の違いは、収益の安定性と景気の影響度、契約や管理の複雑さにあります。
アパート経営は、住宅需要を背景にしているため景気変動の影響を受けにくく、比較的安定した収益を得やすいのが特徴です。入居者の対象は単身者からファミリーまで幅広く、日常生活に根ざした需要があるため、長期的に安定した運用を目指す人に向いています。ただし、家賃単価はテナントより低めなので、収益規模を大きくするには一定の戸数を確保する必要があります。
一方でテナント経営は、事務所や店舗といった事業用物件を貸し出す形態であるため、住宅よりも賃料水準が高い特徴があります。しかし、景気や立地の商業力に収益が大きく左右されやすく、空室期間が長期化するリスクもあります。さらに、アパートよりも契約内容が複雑で、法人や個人事業主が借り手となるため、トラブル発生時の対応も難しくなる傾向がある点にも注意しましょう。
アパート経営のメリット・デメリット
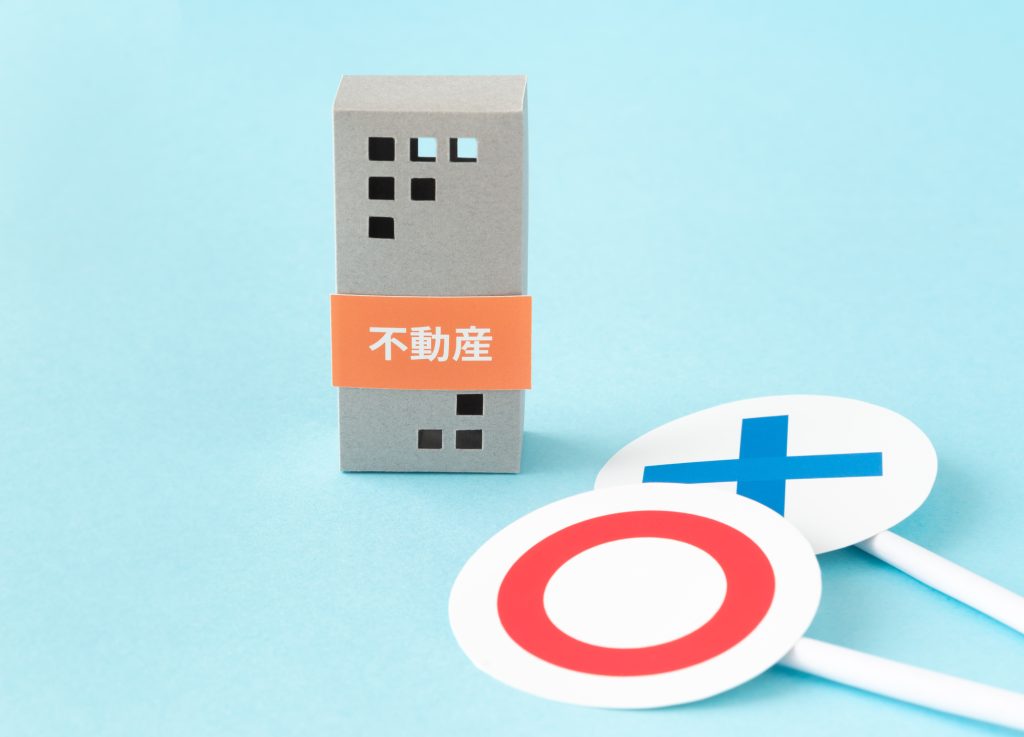
アパート経営には収益の継続性や節税効果といった多くのメリットがありますが、それらの強みを得るためには、高額な資金を用意したり、ある程度のリスクを許容したりといったデメリットを把握しておく必要があります。
これらのデメリットに目を向けないと、リスクの対策ができず、場合によっては経営が立ち行かなくなる恐れもあります。そこでここでは代表的なメリットとデメリットを整理してみましょう。
アパート経営のメリット
まずはメリットからまとめてみましょう。主なメリットには以下のようなものがあります。
- 複数入居者からの安定収入
- 融資を活用した資産形成
- 高い節税効果
アパート経営の大きな魅力は、複数の入居者から収入を得ることで空室リスクを分散でき、安定収入を得やすいという点です。1室が空いても他の部屋から家賃収入が得られるため、戸建て賃貸より安定性が高いといえます。
さらに、ローンを利用することで自己資金以上の規模で投資できる「レバレッジ効果」を効かせられるため、資産形成をより効率的に進めやすくなります。
加えて、前述した相続税や贈与税の対策ができることや、減価償却や修繕費を経費に計上してすることで所得税を軽減できる点も大きなメリットとして挙げられます。
アパート経営のデメリット
アパート経営の主なデメリットは、「建物を建てる」際の資金的な負担が大きい点です。特に、以下の点には注意が必要です。
- 高額な初期投資・維持費
- 空室や賃料下落のリスク
- 金利や災害による不確定要素
アパート経営を始めるには、どうしても資金負担の大きさは避けられません。土地代や建築費に加え、外壁や屋根の修繕、給排水設備の交換など定期的に多額の出費が必要で、1億円以上かかることもよくあります。
また、空室リスクを分散できるといっても、そもそも周辺の需要が低い場合は、思うように入居者が集まらず、家賃収入が想定より下がる可能性もあります。
そして、絶対に対策をしておきたいのが地震や水害などの自然災害のリスクです。この点は、地震の起こりやすさや地盤の強さ、水害時に想定される浸水区域などを調べれば、ある程度対策ができるため、全国地震動予測地図やハザードマップなどで必ずチェックしておきましょう。
アパート経営を成功させるためのポイント

アパート経営の「成功」とは、短期的に満室になるだけでは不十分です。安定した収益を得られている状態が長期的に続き、ローン返済や修繕費の支出にも耐えられる経営基盤を築けていることが本当の成功といえます。
そのためには、資金計画から税務知識、法人化の判断、そして将来を見据えた出口戦略まで幅広い準備が欠かせません。ここでは、特に押さえておきたい4つのポイントを紹介します。
ローン活用を含めた資金計画を立てる
まずは、アパート経営の土台となる資金計画をしっかり立てましょう。
アパート経営は新築・中古いずれの場合も多額の初期投資が必要になります。土地代や建築費、仲介手数料はもちろん、不動産取得税や修繕積立金、管理費なども考慮しなければなりません。
また、ローンを利用する場合は、固定金利か変動金利か、返済期間や自己資金の割合を慎重に検討しましょう。一般的には総投資額の20〜30%を自己資金で用意するのが目安とされますが、あえて自己資金を多く投入することで毎月の返済負担を軽減し、キャッシュフローを安定させるのも一つの手です。
そして、返済計画を立てる際には空室率や賃料下落の可能性も織り込んでおきましょう。楽観的な予想を立てず、少しシビアなくらいの余裕を持ったシミュレーションをしておくと、安全マージンを広く取れます。
税金に関する基礎知識を身につける
次に、お金の流れを正しく把握するために、税金の仕組みを理解しておきましょう。特に押さえておきたいのが、不動産所得としての課税方法と節税につながる制度、将来の相続を見据えた税負担です。
この所得は、必要経費(減価償却費や修繕費など)や各種特別控除などを差し引いた後の金額が課税対象になります。このとき利用できる、不動産所得の青色申告特別控除は要件を満たせば最大65万円を差し引くことができる、節税効果が高い制度として知られています。
また、建物の減価償却や修繕費も経費に計上できるため、課税所得を抑えて節税効果を高められます。さらに、固定資産税や都市計画税といったランニングコスト、将来発生する相続税まで見据えて計画しておくことも重要です。
さらに、不動産所得で赤字が出た場合は、確定申告で給与所得など他の所得と合算して所得を減らせる「損益通算」が可能です。
税制は定期的に改正されるため、専門家に相談しながら最新情報を取り入れることが、無駄な税負担を避ける大切なポイントになります。
規模が大きくなったら法人化を検討する
経営規模が大きくなってきたら法人化を視野に入れましょう。 特に押さえておきたいのが、法人化による税率の違い、経費計上の幅、そして相続時の承継方法です。
まず、法人化をすると所得に対して法人税率が適用されるようになり、一定規模以上の収益がある場合には個人よりも有利になるケースがあります。さらに、役員報酬や出張費などを法人経費として計上できるため、節税の幅が広がるというメリットも受けられます。
また、相続を見据えるなら、資産を法人に移し、その法人の株式という形で承継できるメリットがあります。株式であれば相続人ごとに株数を分けて承継できるため、不動産のように物理的な分割や共有登記をしなくても済み、相続人が複数いる場合でも手続きが比較的スムーズになる傾向があります。
ただ、法人を設立・維持するには、会社設立登記の登録免許税や司法書士報酬、会計処理の専門家費用などのコストと手間がかかります。そのため、税理士をはじめとした専門家に相談して、法人化が本当に有利かどうかを検討するところから取り組みましょう。
出口戦略と長期保有計画を持つ
最後に、将来を見据えた出口戦略と長期保有計画を立てておきましょう。 特に押さえておきたいのが、売却のタイミング、リノベーションや建て替えの判断、そして相続対策です。
まず、売却を検討する際は相場が高い時期や建物が比較的新しい時期を狙うと、高値での取引が期待できます。反対に、老朽化が進んでからでは価格が大きく下がる恐れがあるため、タイミングの見極めが重要です。
また、長期保有を前提とするなら、入居ニーズの変化に合わせてリノベーションを行い、物件価値を維持・向上させることが求められます。大規模修繕や建て替えも視野に入れ、将来の支出計画をあらかじめ想定しておくと安心です。
さらに、相続を考えるなら、誰にどのように承継するかを早めに家族と相談して方針を決めておきましょう。承継計画を明確にしておけば、相続時のトラブル防止や税負担の軽減につながります。
まとめ
アパート経営は、複数入居者からの安定収入や資産形成、節税効果など、多くの魅力を持つ投資方法です。しかし同時に、高額な初期費用や維持コスト、空室や金利上昇といったリスクを背負うことも忘れてはいけません。
特に意識したいのは、成功のカギは事前の徹底した準備と長期的な視点にあるという点です。立地の選定や資金計画、税務や相続への備え、そして将来を見据えた出口戦略をしっかり描き、生活を長期的に支えてくれる安定収入を目指しましょう。
この記事の監修者

岡崎 千尋 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
都市計画コンサルタントとしてまちづくりを経験後、アキサポでは不動産の活用から売買まで幅広く担当してきました。
お客様のお悩みに寄り添い、所有者様・入居者様・地域の皆様にとって「三方良し」となる解決策を追及いたします。








