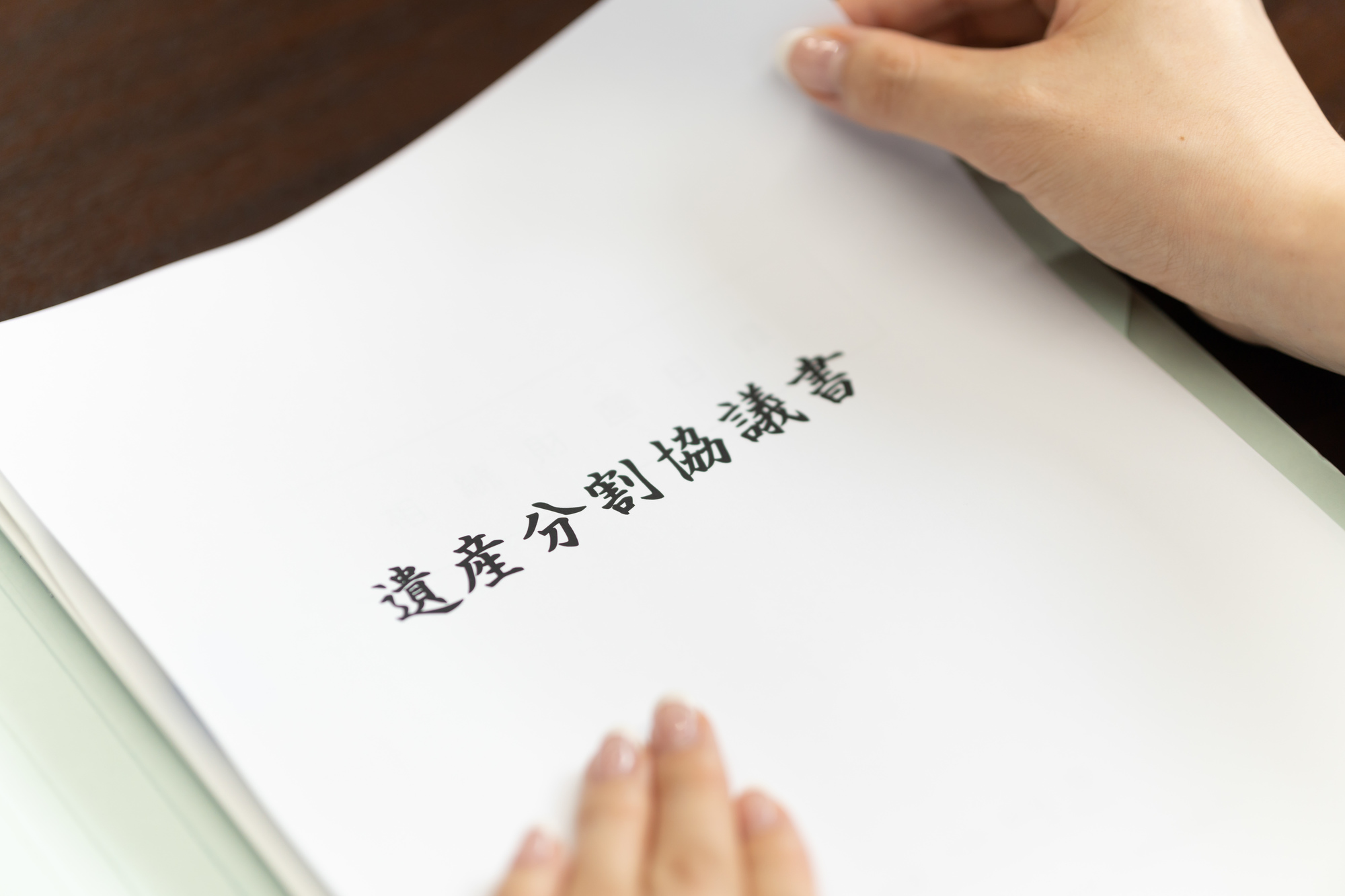公開日:2025.10.29 更新日:2025.10.27
死亡後の手続き一覧と優先順位|期限・窓口・必要書類を徹底解説

死亡後には多様な手続きが発生し、優先順位や期限を理解しておくことが欠かせません。
届け出や申請の期限を過ぎると、受給できるはずの給付金や支援制度を逃すおそれがあります。手続き先や必要書類を事前に整理しておけば、家族や関係者の負担を大きく減らせます。
本記事では、各手続きの概要・期限・必要書類を整理し、円滑に進めるための要点を解説します。期限別の優先順位を把握し、必要に応じて弁護士や司法書士といった専門家へ相談すれば、手続き漏れを最小限に抑えられます。さらに、相続手続き(民法に基づく)や名義変更などは内容が複雑なため、計画的に進めることが重要です。
目次
死亡後に最優先すべき手続きとは

死亡直後に必要な手続きを把握し、優先的に進めることが不可欠です。死亡直後は慌ただしく、特に死亡届を役所へ提出することや、葬儀日程の調整を同時に進める必要があります。
このような状況でも優先順位を明確にすれば、重要な手続きの遅延によるトラブルを防げます。加えて、期限の短い手続きは早期に処理しないと後の流れに影響するため、事前確認が欠かせません。
即時~7日以内に必要な手続き
死亡後すぐに取り掛かるべき手続きとして、医師から死亡診断書や死体検案書を発行してもらい、葬儀社との連絡や故人の搬送方法を決定します。
あわせて、遺体の安置先や通夜・葬儀の日程を早急に固め、弔問客への連絡手段を検討する必要があります。死亡届は戸籍法により7日以内に提出する義務があり、その際に取得する火葬許可証がないと火葬が行えません。限られた時間の中で複数の手続きをこなすため、家族間で役割分担を行うことをおすすめします。
死亡診断書・死体検案書の受け取りと保管
死亡診断書や死体検案書は、死亡後の各種手続きでコピー提出を求められる最重要書類となります。
医師から受け取った原本は厳重に保管し、提出用とは別に複数コピーを確保しておくことが推奨されます。市区町村役場や保険会社への提出でコピーを求められる場面も多いため、余裕を持って数部準備すると手続きが円滑に進むでしょう。
死亡届の提出(7日以内)
死亡届は、戸籍法により「死亡の事実を知った日から7日以内」に市区町村役場へ提出する義務があります。通常、死亡診断書と一体化しており、提出先は死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかを管轄する役場です。
この届出を済ませると火葬許可証が交付され、正式な火葬や埋葬に進むことができます。提出の遅れは相続や保険金請求などに支障をきたすため、速やかな対応が必要です。
火葬許可証の交付申請と火葬の実施
火葬許可証は、死亡届の受理と同時に市区町村から交付されるのが通例です。この許可証がなければ火葬は行えません。葬儀社に火葬手続きを依頼する場合でも、取得済みかどうかは必ず確認しましょう。
また、火葬の実施にあたっては、葬儀や告別式のスケジュール調整も必要。火葬場や葬儀社の予約状況を確認し、スムーズな進行を図りましょう。
葬儀社の手配と葬儀の準備
葬儀社への手配は、できるだけ早めに進めることが望まれます。日程や予算に応じてプランを決定し、通夜・告別式の式場、参列者数、安置場所、装花、役割分担など、詳細を詰めていきましょう。
プラン決定時には、式場の空き状況や地域の慣習も踏まえると、当日の混乱を防ぐことができます。
必要に応じた弔問客への連絡方法
訃報は、親族・近親者・友人・職場関係者などへできるだけ早く伝えるのが基本です。近年は電話に加え、メールやSNSも活用されており、状況に応じて適切な連絡手段を選びましょう。
また、香典や供花の受付可否、参列方法など、事前に周知しておくことで相手も対応しやすくなります。多くの人に短時間で知らせる必要がある場合は、家族と分担して連絡先リストを共有すると効率的。グループチャットやテンプレート文を活用するのも効果的です。
10日~14日以内に行う諸手続き

葬儀後の落ち着いた時期に行う諸手続きの中には、法律で期限が定められているものもあります。とくに健康保険法や介護保険法に基づく手続きは速やかに進める必要があります。
葬儀直後は出費や弔問対応に追われがちですが、行政手続きの遅延は後々の煩雑さにつながるため、早めに必要書類や窓口を確認し、計画的に対応していきましょう。
健康保険の資格喪失(被保険者変更)
故人が健康保険の被保険者だった場合、加入していた協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険などで資格喪失の手続きを行う必要があります。
提出書類には死亡診断書、保険証、戸籍謄本などが含まれます。遺族が保険の継続利用を希望する場合は、新たな被保険者登録や任意継続の申請も並行して進めましょう。
手続きが遅れると、保険証が無効となり医療費が全額自己負担になるケースもあるため、早めの対応が望まれます。
介護保険の資格喪失手続き
故人が介護保険を利用していた場合、死亡によって自動的に資格喪失となりますが、市区町村の介護保険担当窓口に届出が必要です。
保険証の返納や各種書類の提出を行い、利用していたサービスがあれば、ケアマネージャーや介護事業者への連絡も忘れずに。手続きが遅れると、不要な保険料が請求され続けることもあるため、注意が必要です。
世帯主変更届の提出(14日以内)
故人が世帯主だった場合、世帯主の変更は住民基本台帳法により、変更日から14日以内に市区町村へ届け出る義務があります。
住民票や税金関係の情報に矛盾が生じることを避けるためにも、家族間で新しい世帯主を早めに決定し、必要書類を整えて手続きを行いましょう。
運転免許証・パスポートなどの返納や債務整理
故人の運転免許証やパスポートなどの公的証明書は、死亡と同時に無効となります。
免許証は運転免許センターまたは警察署に返納を、パスポートは外務省または都道府県のパスポートセンターで返納・失効手続きを行いましょう。
また、自動車やバイクを相続する場合には名義変更も必要です。放置すると車検や保険の更新に支障が出るため、早めの対応をおすすめします。書類の整理を兼ねて、こうした証明書類の返納も済ませておくと、後の手間が軽減されます。
1か月以内に行う手続きと注意点

葬儀や初七日が終わり、少し落ち着きを取り戻す頃ですが、まだ完了していない公的手続きがあります。なかには名義変更や契約解約など、遺族の生活に直結する重要なものも含まれます。
処理が遅れると、支払いの二重発生や引き落としの停止によるトラブルにつながることも。
雇用保険受給資格者証の返還
故人が失業保険を受給中、または受給資格を持っていた場合は、ハローワークでの手続きが必要です。雇用保険受給資格者証や本人確認書類などを提示し、資格喪失を届け出ます。
この手続きを怠ると、後から不正受給とみなされるリスクもあります。期限が設けられている場合もあるため、できるだけ早めにハローワークへ相談しましょう。
公共料金や各種サービスの名義変更・解約
電気・ガス・水道などの公共料金や、インターネット・携帯電話などの契約が故人名義になっている場合は、名義変更または解約が必要です。
そのまま放置すると不要な請求が発生するおそれがあります。契約内容をリストアップし、利用継続の有無を確認しながら、各社の手続き方法をチェックしましょう。書類提出を求められるケースもあるため、事前に必要書類を確認しておくとスムーズです。
2年以内に行う主な公的給付等の申請

葬儀後は短期的な手続きに意識が向きがちですが、2年以内に申請しないと受給できなくなる公的給付もあります。知らずに期限切れになることも多いため、忘れずに対応しましょう。
葬祭費・埋葬料(埋葬費)の支給申請
故人が国民健康保険や協会けんぽ、健康保険組合に加入していた場合、遺族または葬儀を執り行った人に、葬祭費または埋葬料が支給される制度があります。
申請には死亡診断書、火葬許可証、保険証などが必要で、申請期限は一般的に2年以内。自治体によって手続き方法や支給金額が異なるため、事前に窓口や保険組合に確認しましょう。
死亡一時金・寡婦年金の請求
故人が国民年金に一定期間以上加入していた場合、死亡一時金または寡婦年金の受給対象となる可能性があります。
申請には戸籍謄本、年金手帳、死亡診断書などが必要です。こちらも申請期限は2年とされており、遺族年金との併給ができない場合もあるため、制度内容をよく確認しておくと安心です。申請に不安がある場合は、年金事務所や社会保険労務士に相談するのも一つの手です。
介護保険料過誤納還付金の請求
故人が介護保険料を支払い続けていた場合、死亡後に生じた支払い分や二重払い分が還付対象となることがあります。
還付申請は市区町村の介護保険担当窓口で行い、申請書類や返金先口座情報などを提出します。返金までに時間を要することもあるため、なるべく早めに手続きを進めましょう。
高額療養費の還付申請
故人が生前、高額な医療費を支払っていた場合、高額療養費制度を活用して一部の還付を受けることが可能です。
申請先は加入していた健康保険(協会けんぽ、国民健康保険、健康保険組合など)で、申請期限は2年以内。必要書類には医療機関の領収書や支払証明書が含まれます。
還付金額が大きくなるケースもあるため、申請方法や必要書類をしっかり確認し、確実に手続きを行いましょう。
5年以内に行う主な公的給付等の申請
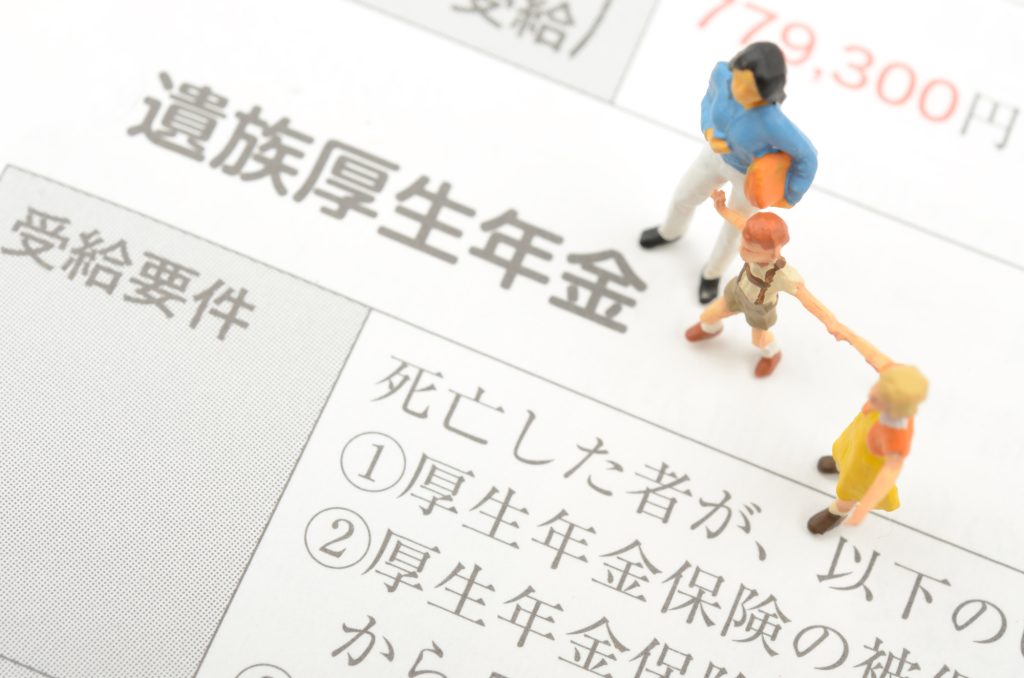
死亡後の手続きの中でも見落とされがちなのが、5年以内に請求が必要な年金関連の給付です。期限が長いため後回しになりやすいですが、申請を忘れると本来受け取れるはずの年金を失う可能性もあります。
生活に大きく関わる制度もあるため、条件や必要書類を事前に確認し、早めに段取りを立てることが大切です。
遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求
故人が国民年金または厚生年金に加入していた場合、所定の条件を満たせば遺族が遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取ることができます。
対象となるのは、主に配偶者や子どもなどで、請求には戸籍謄本、死亡診断書、年金受給権者死亡届などが必要です。申請の原則期限は死亡後5年以内。期限を過ぎると受給できなくなるため、早めに確認・申請しておきましょう。
なお、年金額や支給期間はケースにより異なるため、不明点があれば年金事務所や社会保険労務士への相談がおすすめです。
未支給年金の請求
故人が生前に受給していた年金が、死亡時に未払いのまま残っている場合、それを未支給年金として遺族が受け取れる可能性があります。
請求には、故人および請求者の戸籍謄本や住民票、振込先口座の情報などが必要です。請求できる期間は原則として死亡から5年以内とされており、これを過ぎると受給権が消滅することがあります。また、未支給年金は相続財産の一部として扱われるため、遺産分割協議と並行して検討することが多い点にも留意が必要です。
相続関連の手続きと優先順位

相続手続きは期限も内容も多岐にわたるため、相続人同士で役割を分担し、計画的に進めることが重要です。まずは相続人の確定、財産・負債の調査、遺産分割協議へと段階的に対応していきます。
相続放棄や税の申告などは期限が定められているため、早めのスケジュール管理がトラブル回避の鍵となります。
相続人の確定と戸籍謄本の取得
相続の第一ステップは、故人の出生から死亡までの戸籍謄本を揃えて法定相続人を確定すること。複数の自治体にまたがる場合は時間がかかるため、早めの対応が必要です。
戸籍に基づいて「相続関係説明図」を作成すると、後の手続きがスムーズになります。
相続財産の調査と遺言書の有無確認
相続財産には預貯金・不動産・証券などが含まれます。通帳・契約書・通知などから内容を整理しましょう。
あわせて、遺言書の有無も確認。自筆証書遺言がある場合は家庭裁判所での検認手続きが必要になります。遺言の内容次第で相続分が変わるため、早期の把握が望まれます。
遺産分割協議・協議書作成の流れ
相続人全員による話し合いで財産の分け方を決定し、内容を遺産分割協議書にまとめます。署名・押印のうえ、登記や口座名義変更の際に提出します。紛失すると再作成が困難なため、保管にも注意が必要です。
相続放棄・限定承認の検討(3か月以内)
相続財産より負債が多い場合や、相続を放棄したい場合は、家庭裁判所で相続放棄または限定承認の申請を行う必要があります。申請期限は民法に基づき、相続開始を知った日から3か月以内です。
準確定申告と所得税・消費税の納税(4か月以内)
被相続人の死亡日を含む年の1月1日から死亡日までの所得税や消費税については、準確定申告が必要です。申告・納税の期限は死亡を知った日から4か月以内となり、これを過ぎると延滞税が発生する可能性があります。
相続税の申告・納税(10か月以内)
相続税は、死亡日から10か月以内に申告および納税しなければなりません。
遺産総額が相続税の基礎控除額を上回る場合には、相続人全員の間で財産の評価や分割を決め、適切な配分をもとに申告書を作成します。期限を過ぎると追徴課税のリスクが高まるうえ、税金だけでなく書類作成の手間も増えるため注意が必要です。
相続登記(不動産名義変更)の期限と進め方
2024年4月1日施行の不動産登記法改正により、不動産の相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が必要です。
登記には戸籍謄本、遺産分割協議書、固定資産評価証明書などが必要です。早期に済ませることで名義トラブルを防げます。
その他の手続きや見落としがちなポイント

相続や名義変更以外にも、忘れがちな各種手続きが存在します。
銀行や証券会社などの金融機関は、名義人が死亡すると口座を凍結し、出金や振込ができなくなる仕組みです。また、クレジットカードやローンなどの解約や保険金の請求、SNSのアカウント管理といった細かい手続きも見逃せません。漏れがあると後に追加費用が発生したりトラブルが起こることがあるため、一通りの手続きをリストアップしておくことが大切です。
銀行口座・証券口座の凍結解除と名義変更
名義人が死亡すると金融機関は口座を凍結します。預貯金や有価証券を相続するには、遺産分割協議書や相続関係書類を提出して名義変更や解約の手続きを行います。
必要書類や手順は機関ごとに異なるため、早めに確認・着手するのが望ましいです。
クレジットカード・ローンの解約や名義変更
故人のカードやローン契約は、利用明細や残債を確認したうえで解約や精算を行いましょう。滞納があると遅延損害金が発生する可能性も。家族カードの扱いも要確認です。
不要な通知や勧誘を防ぐためにも、契約はきちんと処理しておくことが大切です。
生命保険金・団体信用生命保険の請求
生命保険に加入していた場合、保険会社に連絡し、死亡診断書・保険証券・受取人の本人確認書類などを提出して請求手続きを進めます。
住宅ローンに付帯する団体信用生命保険では、残債が完済されることもあるため、内容をよく確認しましょう。
SNSやサブスクリプションの解約・名義変更
SNSや動画・音楽配信サービスなどのサブスクリプションは、自動で料金が引き落とされ続けることがあります。利用規約を確認し、必要に応じて解約や名義変更を行いましょう。
ログイン情報がなくても、家族が手続きできる場合があります。放置せず、早めに整理を。
香典・弔慰金の扱いと税務上の注意点
香典や弔慰金は通常は非課税として扱われますが、高額になる場合や法人から支給される弔慰金については課税対象となる可能性があります。
受け取った香典や弔慰金の金額は記録しておき、相続税申告の際に必要に応じて確認することが大切です。万が一、規定を超える額を受け取った場合には、税理士などに相談して正しい扱い方を確認しましょう。
家族信託や死後事務委任契約の重要性
生前に家族信託や死後事務委任契約を結ぶことで、死後の財産管理や事務処理を特定の人に任せることができます。
相続や手続きの負担を軽減でき、遺族間のトラブル防止にも有効です。将来に備えて検討しておくと安心です。
死亡後の手続きが滞るリスクと専門家への相談
専門家への相談を検討することで、ミスや手続き漏れを減らすことが可能です。
法律や税制は複雑な部分が多く、申請期限や手続きの内容を誤ってしまうと給付金や権利を失効させるおそれがあります。特に相続に関する問題は家族間の意見の食い違いが生じることもあり、根本的な理解や適切な進行が求められます。
給付や優遇措置の失効リスクに注意
相続や保険、税務関連の手続きには、7日・14日・3か月・10か月・2年・5年など、さまざまな期限が設定されています。これらを過ぎると、給付が受けられない、税制優遇が適用されないといった不利益が生じます。
スケジュール表やチェックリストで管理し、間に合わない可能性があるときは、速やかに窓口へ相談しましょう。
弁護士・税理士・司法書士などの専門家の役割
弁護士:相続トラブルの予防や、遺産分割に関する調停・訴訟への対応
税理士:相続税や準確定申告の申告支援
司法書士:不動産の相続登記手続きの代理、遺産承継業務
各分野のプロに依頼することで、法的ミスや申告漏れのリスクを大幅に減らすことができます。費用は発生しますが、時間と精神的負担を軽減できるため、特に複雑なケースでは前向きに検討を。
相続手続きを効率化するためのポイント
相続手続きでは、提出先が多く、書類の重複提出も多いため、必要書類をまとめて一括で準備すると効率的です。戸籍謄本・住民票・死亡診断書などは複数部用意し、認印や実印も忘れずに。
家族間で役割分担を決め、協力して進めることで、全体の負担も軽減できます。
まとめ|手続きの優先順位を理解し、円滑な相続と生活再建を目指そう
死亡後の手続きを円滑に進めるためには、各手続きの期限を把握し、優先順位を見極めて計画的に対応する姿勢が欠かせません。
葬儀直後は多忙を極めますが、死亡届や火葬許可申請といった緊急性の高い届出を優先し、その後に健康保険の手続きや名義変更、相続関連の対応へと段階的に進めることが基本です。
特に相続に関しては、放棄や申告、給付申請などに明確な期限が設けられており、条件を満たせば公的給付を受けられる制度も多く存在します。手続きに不安がある場合や家族間での調整が難しい場合は、弁護士・税理士・司法書士などの専門家の力を借りることも有効な選択肢です。
遺族の負担を軽減し、トラブルを未然に防ぐためにも、早めの準備と周囲との連携が鍵。確実な手続きを重ねていくことが、生活の再建と心の整理につながっていきます。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。