公開日:2025.10.30 更新日:2025.10.27
相続税の時効は5年・7年?根拠条文と対処法を徹底解説

相続税の時効とは、国税通則法第70条に基づき、一定期間が経過すると国の課税を決定する権利(賦課権)が消滅し、結果として納税義務もなくなる制度を指します。
一方で、不正行為(仮装や隠蔽など)があったと認められる場合には、時効期間は5年ではなく7年に延長される点に注意が必要です。
本記事では、相続税の時効の仕組み、不正認定に伴う加算税などのペナルティ、さらに相続税と類似する贈与税の時効規定まで幅広く解説します。正確な知識を持つことで、余計なリスクを避け、適切な対応につなげられるでしょう。
目次
相続税の時効とは何か?仕組みと法律上の注意点
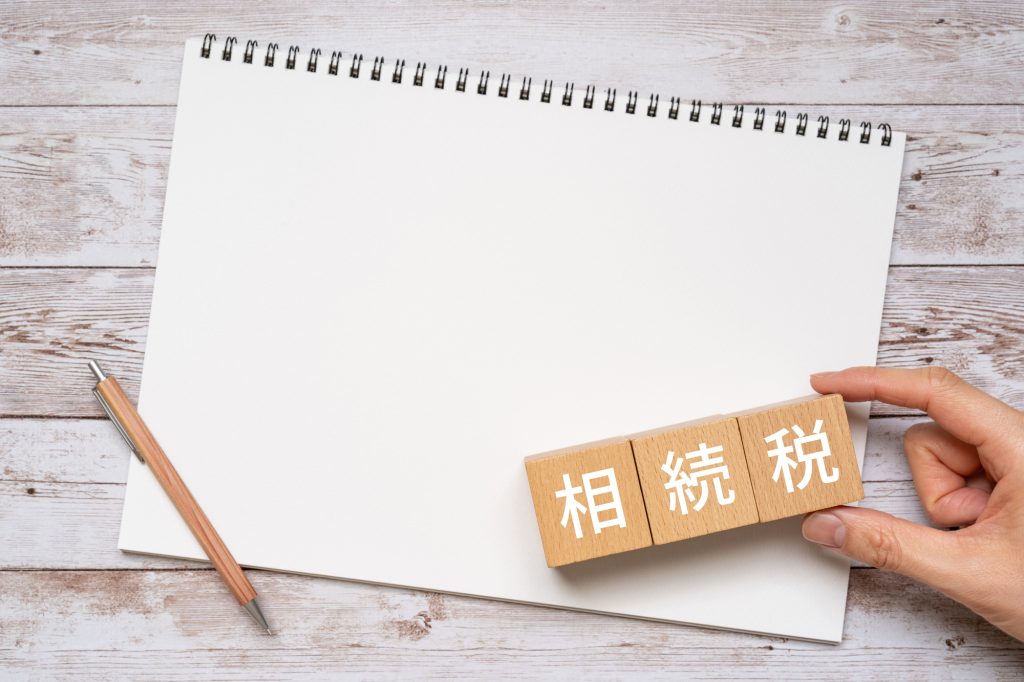
相続税の時効とは、国税通則法第70条などの規定に基づき、税務署が課税処分(更正または決定)を行う権利を失うまでの期間を指します。具体的には、相続発生後に相続税の申告期限(被相続人の死亡の翌日から10か月以内)を過ぎ、一定期間が経過すると、税務署が課税権を行使できなくなる状況を意味します。通常は5年ですが、仮装や隠蔽などの不正と認定されれば7年に延長される点が特徴です。こうした仕組みを理解しておくことで、将来の税務リスクを軽減できます。
混同しやすいのが、相続税の時効と「除斥期間」です。除斥期間とは「権利自体が消滅する」考え方で、時効とは異なり権利行使期間の延長や中断がないなどの特徴があります。そのため、単純に5年や7年をあてはめるだけでは判断できない点に注意が必要です。
また、時効成立前に税務調査が行われた場合、国税通則法第72条に基づき時効の進行が中断されることがあります。特に名義預金やタンス預金といった資産隠しの疑いがあれば、調査は一層厳格です。時効をあてにして申告を怠るのではなく、早期に適切な対応を取ることが望まれます。
時効期間が5年になるケース
通常、相続人が相続税の存在や申告義務を知らなかった場合、5年で時効が成立します。
あくまで「不正行為ではない」ことが前提であり、故意の隠蔽と認められない限り、この5年の期間が適用されます。もっとも、税務署が書類や資産状況から不審点を把握すれば、無申告や過少申告として追及される可能性もあり、単なる知識不足では済まされないこともあります。慎重に手続きを確認し、必要に応じて税理士など専門家へ相談することがリスク回避につながります。
時効期間が7年に延長されるケース
不正行為が疑われる場合や、意図的な財産隠しと判断されれば、時効は7年に延長されます。これは悪質な隠蔽行為とみなされると、通常より厳格な調査対象となるためです。
不正と認定されれば重加算税(国税通則法第68条)などのペナルティが課され、納税負担が大幅に増える恐れもあります。相続税の時効を安易にあてにせず、正しく申告してリスクを回避することが最善策となります。
相続税の時効はいつから数える?起算日と法律上の考え方

相続税の時効は、国税通則法第70条に基づき、申告期限を基準とした起算日からスタートします。いつからカウントが始まるのかを理解しておくことが重要です。
相続税の申告期限は、相続税法第27条で「被相続人の死亡から10か月以内」と定められています。この期限を過ぎた翌日から通常の時効が進行するため、起算日を正しく把握しておく必要があります。無申告の場合は、時効が成立する前に税務署から問い合わせや調査が入ることが多く、早めの対応が求められます。
また、起算日は事情によって後ろ倒しになる場合もあります。例えば、納税義務を遅れて認識した場合や、相続人全員の協議が長引いた場合には、税務上の扱いが変わることもあります。時効に不安があるときは、自己判断に頼らず、税理士など専門家の助言を受けるのが望ましいでしょう。
申告期限の翌日から時効が始まる理由
相続税の申告期限は法律で明確に10か月とされ、この期限を過ぎた翌日から納付義務が確定します。そのため、課税権を行使できる期間もこの時点から数え始めるのが通例です。
相続人によっては時効を待とうとする人もいますが、この期間中に税務署から督促や調査が入れば、国税通則法第72条に基づき時効が中断する可能性が高い点を理解しておきましょう。
時効が中断する場合と「除斥期間」の違い
時効が中断する典型例は、税務署からの更正通知や納税告知、督促が行われた場合です。これにより、時効のカウントはリセットされ、再び期間が進行します。
一方で「除斥期間」とは、民法上「一定時点を過ぎれば権利行使を認めない」とする仕組みであり、時効とは異なる概念です。
多くの人は「待てば時効が成立する」と考えがちですが、除斥期間の存在や中断の仕組みを踏まえると、成立は決して容易ではないことが分かります。相続税を巡るリスク回避のためにも、起算日と期間の仕組みを正しく理解し、疑問があれば専門家に相談することが望ましいでしょう。
時効前に発覚したら?相続税無申告のリスクとペナルティ

相続税の未申告や過少申告が発覚した場合、国税通則法第60条・第65条に基づき延滞税や各種加算税が科される恐れがあります。
時効成立前に税務署が不備を確認すれば、課されるペナルティは一層重くなります。無申告や過少申告は違反行為とされ、追徴課税に加えて加算税が課されるのが通例です。さらに、意図的な隠蔽が疑われる場合は重加算税(第68条)に発展するリスクがあり、申告を怠るメリットはほぼありません。
加えて、税務署は被相続人の過去の収入や資産の移動を正確に把握しています。金融機関の取引記録や不動産登記など、各種データベースを駆使して疑わしい取引を洗い出す体制は整っているため、隠し財産は容易に発覚するのが現状です。そのため、発覚時のデメリットを考慮すれば、正しく申告する方が最終的な負担を軽減できるといえます。
延滞税・無申告加算税・過少申告加算税(国税通則法)
延滞税は、第60条に基づき、納付期限を過ぎてから支払うまでの日数に応じて課される「利息的」な税金です。
無申告加算税は第66条で、過少申告加算税は第65条で規定され、それぞれ申告をしなかった場合や本来より少なく申告した場合に課されます。これらは税金に加えて発生する負担であり、見過ごせない額に膨らむこともあります。
重加算税・刑事罰の条件と内容
意図的な隠蔽や虚偽申告などの悪質行為が認定されれば、国税通則法第68条に基づき重加算税が課されます。これは通常の加算税より高率で計算されるため、想定外の大きな負担となりやすい制度です。さらに、極端に悪質と見なされれば、相続税法や所得税法・国税犯則取締法に基づき刑事罰が科される可能性も否定できません。
重加算税は課税率が高いため、結果として非常に大きな財政的ダメージを受けることが懸念されます。したがって、時効を期待するよりも、正しく申告を行う方が総合的にリスクを抑えられるといえるでしょう。
タンス預金・名義預金は時効まで隠せる?税務調査の仕組みとリスク

相続財産の一部を現金や預金で隠そうと考える人もいますが、税務署の調査網は非常に広範囲に及びます。
タンス預金や名義預金の形で資産を隠しても、税務署はあらゆる角度から財産状況を徹底的に調べます。金融機関からの情報提供や他の相続人の申告・告発によって隠し財産が発覚するケースも少なくありません。時効成立前に発覚すれば、無申告加算税(国税通則法第66条)や重加算税(第68条)など高額なペナルティや追徴課税を受けるリスクが高まります。
また、タンス預金や名義預金が認定されれば、単なる未申告ではなく隠蔽や虚偽の行為とみなされ、無申告加算税や重加算税など通常より厳しい制裁の対象となりかねません。結局のところ、こうしたリスクを負うメリットはなく、最初から正しく申告することが賢明な選択です。
税務署の調査体制と情報収集方法
税務署は銀行口座の動きや不動産売買の記録など公的情報を集中管理し、相続人や被相続人に関連する資産の動きが大きい場合や、不自然な取引が確認されれば詳しい調査を行います。
近年はマイナンバー制度の導入により資産情報の一元管理が進み、隠し財産が見つかりやすくなっているのが現状です。
タンス預金が疑われる典型的なパターン
被相続人が亡くなる直前まで大きな取引や生活費の支出がないのに、相続税申告で現金がほとんど計上されていない場合、タンス預金を疑われやすくなります。さらに、金融機関の預金残高と生活費の乖離が大きければ、預金を現金化していたと推測される可能性があります。
一度疑われれば、税務署は時効前に証拠を集めるため詳細な調査を進めます。結局のところ、後から多額の税金とペナルティを支払うことになるため、最初から正確に申告しておくことが重要です。
相続税の還付にも時効に類似した期間制限(還付請求権の除斥期間)はある?

相続税を納めすぎた場合に受けられる還付についても、国税通則法第23条に基づき、請求権の行使には期間制限(除斥期間)が設けられています。
相続税を計算ミスで納めすぎてしまった場合、税務署に還付請求を行えば差額が戻る可能性があります。しかし、この還付請求には5年の期限があり、一度期間を過ぎれば請求権自体が消滅します。誤った申告は過払いにつながるため、内容を早めにチェックしておくことが重要です。
特に、不動産の評価や特例の適用を誤ると、相続税額が過大になるケースは少なくありません。気づいたときにすぐ修正申告と還付請求を行うのが原則ですが、5年を過ぎればその権利は行使できません。知らないうちに期限を迎えると、せっかくの還付を受けられず損するおそれがあります。
還付請求権の期限(除斥期間)と注意点
相続税の還付請求には、法定納期限から5年という法定の請求期限が設けられています。
この期間を過ぎると請求権は完全に失われるため、注意が必要です。期限が迫っているのに専門家へ相談していない場合は、速やかに確認と手続きを行うべきです。
還付請求は気づいてからでは遅い?よくある落とし穴
相続税の還付は「実は納めすぎていた」と後から判明するケースが少なくありません。
しかし、その時点で既に5年の期限を過ぎていることもあります。特に、不動産評価や控除計算のミスは金額が大きくなりやすく、「こんなに払う必要はなかった」と後悔する可能性もあります。
初回申告で適切に評価や特例を適用していれば、余計な税金を避けられます。そのため、税理士などプロに依頼する選択肢を検討することも重要です。この落とし穴を避けるには、還付請求には5年の期限があることを理解し、申告後も細かく確認する習慣を持つことが大切です。
贈与税にも時効はある?相続税との違いと制度利用の注意点

贈与税にも国税通則法第70条に基づく時効があり、相続税と似た部分もありますが、制度上の違いを理解しておく必要があります。
贈与税は、生前に行う財産移転に課される税金で、相続税との共通点も多い一方、課税のタイミングは相続とは別です。時効も相続税と同様に原則5年、不正があれば7年に延長されます。特に大きな資産を贈与する場合、単なる名義変更では済まないため、制度を正しく理解しておくことが欠かせません。
贈与税の時効期間と延長要件
贈与税の時効は、申告期限の翌日から5年で成立します。
ただし、財産隠しや書類偽装といった不正が疑われれば、国税通則法第70条に基づき7年に延長されます。相続税と同様に、税務署の追及は厳格であり、時効成立前に贈与が発覚すれば高額な追徴課税を課される恐れがあります。
暦年贈与・相続時精算課税制度との関係
贈与の基本である暦年贈与は、毎年110万円以内の贈与で課税を避ける仕組みです。また、相続時精算課税制度は、生前贈与財産を相続時にまとめて精算する制度を指します。一見するとお得に見える制度ですが、後に税務調査が入るケースもあり、正確な申告と資料の保管が重要です。
これらの制度を活用する際は、時効だけでなく、贈与や相続に関わる幅広い税務知識を理解しておくことが大切です。将来的に相続税との関係も踏まえ計画的に進めれば、余計なトラブルを避けられるでしょう。
まとめ・総括
相続税と贈与税の時効(国税通則法第70条)を理解することで、リスク回避と適切な手続きが可能となります。
特に不正行為が疑われる場合には、重加算税(同法第68条)など重いペナルティが科されるため注意が必要です。
通常は5年で時効となりますが、不正が認定されれば7年に延長されるため、安易な税逃れは大きなリスクを伴います。時効を待つよりも、早めに専門家へ相談し、正しい申告や手続きを行うことが最終的な負担軽減への近道です。
また、タンス預金や名義預金を隠すことにメリットはなく、発覚時のデメリットは極めて大きいものです。税務署の調査は金融機関や登記情報など多方面のデータを駆使して進められるため、逃れられる可能性はほぼありません。
時効制度を正しく理解し、適切な相続・贈与計画を立てることが、後悔のない資産管理への第一歩といえるでしょう。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。








