公開日:2025.11.01 更新日:2025.10.27
【完全ガイド】戸建て売却の流れ・費用・成功のコツまで徹底解説

戸建ての売却には、さまざまな手続きと準備が伴います。全体の流れを事前に理解しておくことで、計画的かつスムーズに進めることが可能です。
本記事では、基本ステップ、必要書類、税金・費用、成功のコツまでを簡潔に整理。初めての方でも流れがつかめるよう、要点を押さえて解説します。
目次
戸建て売却のステップと事前準備

戸建て売却は、準備から引渡しまで段階的に進みます。ステップを把握し、必要な手続きを漏れなく行うことが重要です。
まずは、いつ売るかという目標時期を明確にしましょう。不動産市況の影響を受けやすく、時期を誤ると売却が長引いたり、価格交渉が難航する恐れがあります。不動産会社は、査定や販売活動だけでなく宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書や契約書の作成も行う法的パートナーです。実績や得意分野を確認し、複数社に査定を依頼すると市場価格も把握しやすくなります。
売却が進むと、内覧対応や価格交渉に時間と労力が必要になります。準備不足は、売却遅延や価格面での損失に直結します。スケジュールを立て、要所ごとに確実に対応していくことが成功の近道です。
STEP1. 売却前にすべき事前準備と情報収集
不動産売却を円滑に進めるには、事前準備が成否を左右します。まずは、希望する売却額や理由、売却希望時期を明確にし、全体のスケジュールを大まかに立てましょう。たとえば転勤や住み替え予定がある場合、それに合わせた売却計画が必要です。
また、売却に必要な書類も早めに揃えておきましょう。代表的なものには、以下が含まれます。
・登記事項証明書
・重要事項説明書(取得時の原本)や売買契約書(取得時の原本)
・住宅ローン残高証明書(金融機関発行)
これらを事前に準備しておくことで、不動産会社や買主とのやりとりがスムーズになり、交渉や契約手続きの遅れも防げます。
加えて、物件のある地域の相場情報も把握しておくことが重要です。国土交通省の「不動産取引価格情報検索システム」などの公的データベースを活用し、近隣の取引事例から妥当な価格帯を確認しましょう。所有物件の市場価値を客観的に捉えることで、価格設定や販売戦略のズレを防げます。
STEP2. 不動産会社への査定依頼
査定を依頼する際は、「机上査定」と「訪問査定」の両方を活用するのがおすすめです。まず簡易見積もり(机上査定)で相場感を把握し、次に訪問査定で建物の状態や立地を考慮した具体的な金額を出してもらいましょう。
査定額には会社ごとに差があるため、複数社から見積もりを取り、提示額の根拠を丁寧に確認することが肝心です。根拠が不明瞭なまま高額を提示されても、売却段階で値下げを求められるリスクがあるため注意が必要です。
また、査定時の担当者の応対や説明の丁寧さもチェックポイントです。物件の特性に合った提案や誠実な対応が見られるかを確認することで、信頼できるパートナーを見つけやすくなります。最終的には、提示価格だけでなく、販売戦略や担当者とのコミュニケーションの質も含めて総合的に判断しましょう。信頼できる不動産会社を選ぶことが、スムーズな売却への第一歩となります。
STEP3. 媒介契約の締結
不動産会社と媒介契約を締結すると、売却活動が正式にスタートします。媒介契約には3種類があり、それぞれの特徴を理解することが重要です。
・専属専任媒介契約:売主自身で買主を探すことはできず、1社のみに依頼。週1回以上の報告義務あり
・専任媒介契約:1社のみへの依頼だが、自力売却も可。2週に1回以上の報告義務
・一般媒介契約:複数社へ依頼可能。報告義務はなし
これらはすべて宅地建物取引業法第34条の2に基づく制度であり、契約内容に応じて、不動産流通標準システム「REINS(レインズ)」への登録義務も異なります。専属専任・専任媒介では登録が義務づけられ、全国の業者と情報共有されることで買主が見つかりやすくなります。一方、一般媒介では登録義務がないため、不動産会社によって広告の積極性に差が出ることもあります。
契約時には報告頻度・広告媒体・手数料条件などを明確にし、納得できるまで説明を受けてから署名・押印しましょう。
STEP4. 売却活動と内覧対応
媒介契約後は、ネット広告・不動産ポータルサイト・チラシなど多様な手段で買主を募ります。中でもネット掲載は第一印象を左右するため、高画質の写真と詳細な物件情報の準備が欠かせません。
内覧希望が入った際には、次の点を意識しましょう。
・掃除・整理整頓:水回りや玄関は特に重点的に
・生活感の排除:家具配置や装飾を工夫し、モデルルームのような雰囲気に
・照明・換気:明るく清潔な空間演出が印象を左右します。
こうしたホームステージングにより、内覧者が「この家に住む」イメージを具体的に描きやすくなり、成約率が高まります。
また、内覧時に聞かれることが多い内容には以下のようなものがあります。
・現在の住宅ローン残債
・最寄り駅やバス停までの距離
・近隣のスーパー・学校・病院など生活施設
これらを事前に整理しておけば、質問にもスムーズに答えられ、信頼感を与えることができます。
STEP5. 売買契約の締結
買主との条件交渉がまとまれば、売買契約を締結します。契約前には宅地建物取引業法第35条に基づき「重要事項説明」が行われ、権利関係や設備状況などの重要情報が説明されます。売主もその内容を必ず確認し、疑問点は解消しておきましょう。
契約書には売買価格・引渡日・支払方法・手付金・違約金等が記載され、内容に合意することで法的拘束力が発生します。手付金の授受が行われたら、必要書類の準備や住宅ローン完済、諸費用の確認などを進め、引渡しに備えます。
STEP6. 決済と引渡し
決済日には残代金を受領し、同時に抵当権を抹消。不動産の引渡しが完了します。ローン残債がある場合は、事前に金融機関と日程調整を進めておくとスムーズです。
引渡し直前には設備の動作確認を行い、給湯器や水回りなどに不備がないかを点検。とくに築年数のある戸建てでは、老朽化の有無を念入りに確認しましょう。
売却後は、譲渡所得が発生する場合に所得税・住民税の確定申告が必要となります(所得税法第33条)。忘れずに税務手続きまで完了させることが、安心して次の暮らしへ進むポイントです。
売却前に確認したい事前準備

不動産売却をスムーズに進めるには、売却前の準備が欠かせません。ローン残高や建物の状態、書類の整理など、事前に手を打つことで後の交渉や契約が円滑に進みます。
とくに相続物件や共有名義の不動産では、通常より多くの手続きや合意形成が求められるため、早めの対応が重要です。
住宅ローン残高と担保解除のチェック
まずは住宅ローン残高の確認と、売却代金で完済可能かを検討しましょう。不足する場合は、自己資金の準備や住み替えローンなどの検討が必要です。
また、物件に抵当権が設定されている場合、売却時には金融機関と連携して担保権抹消の手続きを進めます。複数の銀行と契約している場合は、それぞれに必要な書類や流れを整理しておくことがスムーズな売却のカギとなります。
築年数や建物の状態を把握する
戸建てでは築年数や建物の劣化状態が査定や購入意欲に大きく影響します。
リフォーム歴や修繕箇所を把握し、必要に応じて軽微な補修(クロス張り替え、水回りの改善など)を行うことで、印象と売却価格の向上が期待できます。
加えて、上下水道・電気などライフラインの動作確認も重要。小さな不具合でも買主に不安を与える要因になり得るため、事前に点検・修理することでトラブルを防げます。
共有名義・相続物件の対応ポイント
共有名義の場合は、売却には全員の同意が必要です。意見が割れると売却が進まないため、早期の話し合いが不可欠です。
相続物件では、相続登記や名義変更、相続税の申告要否など複数の確認項目があります。手続きが完了していないと、買主がローンを組めず売却が頓挫することもあるため、必ずチェックしておきましょう。
また、売却益の配分ルールも事前に共有者間で合意しておくと、トラブルを回避できます。
必要書類のリストと入手先
売却時に必要な主な書類は以下のとおりです。
・登記事項証明書(旧:登記簿謄本) … 法務局
・公図・測量図 … 法務局または市区町村役場
・固定資産税納税通知書 … 市区町村
・建築確認済証・検査済証 … 建築当時の書類や役所
これらは売買契約だけでなく、重要事項説明書の根拠資料としても使用されます。とくに建築確認済証・検査済証は買主のローン審査に影響するため、紛失している場合は早急に確認を。
相続・共有名義の場合には、
・遺産分割協議書
・共有者全員の印鑑証明書
なども追加で必要になることがあります。不備があると契約スケジュールに影響するため、取得先の確認や専門家の相談も視野に入れておきましょう。
仲介と買取のメリット・デメリット
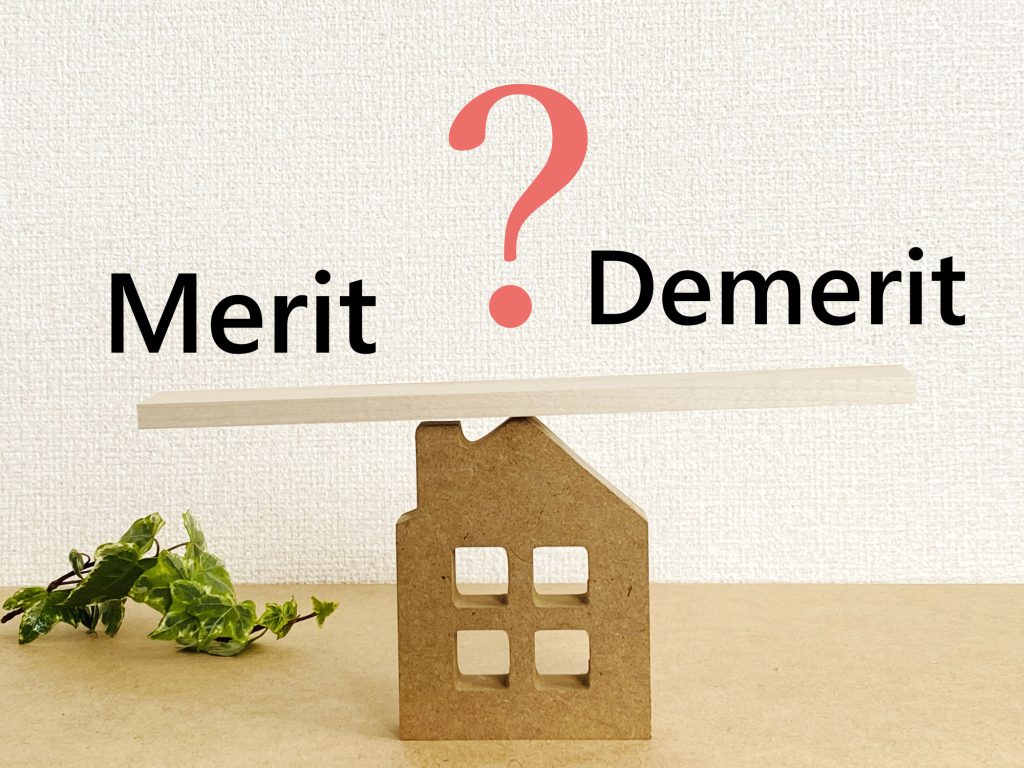
不動産売却には「仲介」と「買取」の2つの方法があります。それぞれ売却スピード・価格・手間に違いがあるため、自身の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
仲介の特徴と仲介手数料
仲介は、不動産会社が買主を探し、媒介契約のもと売買を成立させる方法です。相場に近い価格で売れる可能性が高いため、高値売却を狙いたい人に適しています。
ただし、売却完了までに時間がかかることもあり、資金計画やスケジュールの見通しが立てづらい面もあります。価格設定を高めにすると内覧が入らず、価格調整に迷うこともあります。
仲介を利用する際は、売買成立時に仲介手数料が発生します。これは宅地建物取引業法で上限(売買価格×3%+6万円+消費税)が定められており、高額物件ほど手数料も高額になりますが、その分広告活動や営業努力が期待できます。
買取の特徴と買取価格の相場目安
買取は、不動産会社や専門業者が直接物件を買い取る方式です。数週間程度で現金化できるスピード感があり、転勤・離婚・相続整理など急を要するケースに向いています。最大のメリットは、内覧・広告が不要で、手間が少ない点。契約後にリフォームや修繕を求められる心配も少なく、家族のプライバシーを守りながら売却できる点も評価されています。
一方、価格は仲介と比べて10〜20%前後安くなる傾向があります。これは、買取業者が再販のためにリフォーム費やリスクマージンを見込めるためです。
売り急ぎや早期現金化を希望する場合の選択肢
すぐに現金化したい場合は、買取や「買取保証付き仲介」を検討すると良いでしょう。
買取保証付き仲介とは、一定期間内に売れなかった場合、あらかじめ決めた価格で業者が買い取る方式。高値売却を目指しつつ、売れ残りのリスクも抑えられます。
ただし、保証には審査があり、物件の状態や流通性などから不動産会社が**「買取可能」と判断した場合に限られます。また、対象エリアや条件が限定されることもあるため、契約内容をよく確認することが大切です。
価格を安易に下げて焦ると、想定外の損失につながることもあります。まずは複数社に査定を依頼し、相場感を掴むことが売却成功の第一歩です。
戸建ての査定方法と価格相場の調べ方

戸建て売却で適正な価格を設定するには、査定方法の理解と相場調査が欠かせません。根拠のある価格設定は、納得のいく売却につながります。
机上査定と訪問査定の違い
査定方法には、
・書類ベースで概算を出す「机上査定」
・実際に現地を見て判断する「訪問査定」
があります。
机上査定は、公示地価や近隣の売却事例をもとに短時間で見積もれますが、建物の劣化やリフォーム履歴などの個別事情が反映されにくいため、あくまで目安にとどまります。
一方、訪問査定では、敷地条件・建物状態・接道状況・周辺環境などを踏まえて、より実情に即した価格が提示されるため、最終的な判断材料として有効です。複数社にまとめて依頼すれば、効率よく比較できます。
不動産ポータルサイトや国土交通省データの活用
周辺相場を把握するには、不動産ポータルサイトで類似物件の価格帯をチェックするのが第一歩です。ただし、これらは「売出し価格」であって「成約価格」ではない点に注意が必要です。
より実態に近い価格を知りたい場合は、国土交通省が提供する「土地総合情報システム」や不動産流通機構の成約データ(REINS)を活用すると良いでしょう。駅徒歩圏や敷地面積など条件の近い事例を調べることで、単なる相場感ではなく、価格の“根拠”を得ることができます。
また、地域によっては自治体や地元情報誌に不動産市況レポートが掲載されていることもあります。新築開発の有無、再開発計画、交通インフラの変化といった地域要因が相場に影響するため、ローカル情報も見落とせません。
周辺相場との比較ポイント
売却価格を検討する際は、まず地域全体の需給バランスを確認しましょう。新築戸建てやマンションの建設、駅の再開発などが進むエリアでは、価格にプラスの影響が出ることがあります。
また、交通の利便性や商業施設、学校の有無といった生活環境も重要です。たとえば駅からの距離が数分違うだけで、価格帯が大きく変わることもあります。自分の物件にどれだけ「買いたい理由」があるかを、客観的に見極めることが重要です。
こうした比較視点を持っておけば、不動産会社から提示される査定額が適正かどうかを判断しやすくなります。相場より高めの価格を設定したくなる気持ちもありますが、現実的なラインを見極めたほうが、結果的には早期かつ好条件での売却につながる可能性が高まります。
査定結果の根拠をしっかり確認しよう
査定額を提示されたら、その金額にどういった根拠があるかを必ず確認しましょう。近隣の成約事例や建物の状態、過去のリフォーム歴などが査定にどう反映されているかがポイントです。
とくに根拠が曖昧なまま高額な数字を出してくる場合は注意が必要です。客観的なデータや現地調査の結果が組み合わさった査定こそ、信頼に足る材料になります。
納得できる根拠を得られたら、それを踏まえて売出価格を調整し、無理のない広告活動へとつなげましょう。価格設定の初期段階を見誤ると、売却期間の長期化や交渉時の不利を招くこともあります。
媒介契約の種類と選び方

不動産会社と結ぶ媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があり、それぞれ契約の自由度や販売活動の範囲、報告義務に違いがあります。
どの契約を選ぶかによって、不動産会社の動き方や売主の自由度が大きく変わるため、自分の状況に合った契約を選ぶことが、スムーズな売却の第一歩です。
専属専任媒介契約の特徴
専属専任媒介は、売主が1社の不動産会社とだけ契約を結ぶ形態で、売主自身が見つけた買主とも、必ずその会社を通して取引しなければならないのが特徴です。
その代わり、不動産会社は強い責任を持って販売活動を行い、週1回以上の進捗報告やREINS(指定流通機構)への登録(法定義務)なども求められます。売却活動の状況を密に把握したい人や、不動産会社の全面的なサポートを重視する人に向いています。
専任媒介契約の特徴
専任媒介も、1社のみと契約する点は同じですが、売主が自力で買主を見つけた場合は直接契約が可能です。
報告義務は2週に1回と少し緩和されますが、REINSへの登録は引き続き義務。販売活動は不動産会社に集中しつつも、売主側の動きも許容されるため、知人への売却なども視野に入れている人に適しています。
一般媒介契約の特徴
一般媒介では複数の不動産会社に同時依頼が可能で、より広範囲に物件を露出できます。売主が直接契約することも自由で、報告義務やレインズ登録も任意となっているため、最も自由度が高い契約です。
一方で、不動産会社にとっては成約の確約がないため、積極的な販促が行われにくい可能性もあります。自身で動ける・売れやすい物件を持つ人には好相性ですが、こまめな対応を期待する人には不向きかもしれません。
どの契約形態を選ぶべきか
選択のポイントは、売却スピード、価格、自由度、そして自分の動ける時間や売却経験です。
たとえば、早期売却を目指す人や全面的にプロのサポートを受けたい人は、専属専任または専任媒介が向いています。一方、時間的な余裕があり、複数社を比較しながらじっくり売却したい人は、一般媒介が有効です。
価格重視なら競争原理が働く一般媒介、戦略的な広告展開を期待するなら専任系を選ぶのも手です。どちらを選んでも、不動産会社との継続的なコミュニケーションが売却成功のカギになります。
もし迷う場合は、複数の会社から提案を受けて契約形態ごとのメリット・デメリットを比較し、自分の目的とマッチする方法を選ぶと納得のいく取引がしやすくなります。
売却活動をスムーズに進めるためのポイント

売却活動が始まると、まず重要になるのが内覧対応です。第一印象の良し悪しで検討の本気度が変わることもあるため、丁寧な応対と居心地の良さを意識した準備が欠かせません。たとえその場で決まらなくても、好印象を残せば再検討の可能性も生まれます。
内覧日には、特に水回りや玄関など印象に直結する場所を中心に清掃し、換気や照明の工夫で明るく清潔な空間を演出しましょう。生活感が強すぎると買主が暮らしを想像しにくくなるため、荷物を適度に片付けるのも効果的です。
買主への説明は要点を押さえつつ、過度に情報を詰め込みすぎず、質問にはその場で丁寧に応じる姿勢がベスト。内覧者がリラックスして物件と向き合える雰囲気づくりが、成約への近道です。
広告活動とホームステージングの活用
不動産会社はポータルサイトやチラシ、オープンハウスなどを活用し、広く買主を募ります。中でもインターネット広告は反響が大きいため、写真や物件紹介文の見せ方が重要です。
加えて、ホームステージングによって室内をモデルルームのように整えると、購入後の生活イメージが湧きやすくなります。物件の魅力を視覚的に伝えることで、内覧からの成約率が向上することもあります。
費用はかかるものの、一部の不動産会社では写真撮影や簡易ステージングをサービスとして提供していることもあり、売却スピードや価格を重視する人には検討の価値があります。
柔軟な価格交渉と条件整理
内覧日は、物件をできるだけ清潔感ある状態にしておくことが基本です。特に水回りや玄関など第一印象を左右する場所は念入りに掃除しましょう。加えて、照明を点けて明るい雰囲気を演出し、換気を行って嫌なにおいを消すといった工夫も大切です。
自宅の生活感が強すぎると、買主は自分が住むイメージを持ちにくくなります。余分な家具や荷物はある程度片付けるなど、適度に “生活感を薄める” ことが好印象につながります。
内覧者には部屋の広さや使いやすさをアピールしたいものの、情報を押しつけすぎると負担になりがちです。要所だけを簡潔に説明し、質問があればその都度丁寧に答えるスタンスを取ると、相手にとっても居心地の良い内覧体験になります。
価格調整や購入希望者との交渉
買主からの価格交渉には、事前にどこまで応じられるか自分のラインを決めておくとスムーズです。予想外に大幅な値引きを要求されることもありますが、その際には査定結果や相場データを根拠に、応じるべきか慎重に判断しましょう。
価格交渉が行き詰まる場合は、引渡し時期や付帯物の有無など、別の条件交渉を柔軟に行うのも一策です。すべての交渉条件が価格だけではないため、買主の要望をヒアリングし、双方が納得する落としどころを探ることで円満な合意につながります。
交渉段階で、条件が固まらないまま契約を急ぐと、後々トラブルに発展するリスクがあります。時間が許す限り、疑問や不安点は迅速に確認し、契約書にて明文化することで安全に取引を進められます。
活動状況の報告とフィードバックの活かし方
不動産会社からの問い合わせ状況や内覧者の感想は、売却戦略を見直す重要な材料になります。報告を受けたら必ず内容を確認し、必要があれば物件情報や写真、価格の調整を検討しましょう。
内覧者はいるのに成約に至らない場合は、物件の見せ方や説明の仕方に課題があるかもしれません。買主目線でフィードバックを分析することで、改善点が見えてきます。
たとえば、よくある指摘として部屋の暗さやニオイ、周辺環境への不安などが挙げられることがあります。これらに事前に対処しておけば、次の内覧につながりやすくなり、結果として売却までの期間を短縮できます。
売買契約締結から引渡しまで

売買契約を締結した後も、残代金の受け取りや引渡し準備、確定申告など、完了までに対応すべき工程が多く残っています。各ステップでのポイントを押さえ、スムーズな引渡しとトラブル回避を目指しましょう。
重要事項説明と契約書の確認
契約前には、物件の法的状況や設備の不具合などについて「重要事項説明」が行われます。誤解やクレームを防ぐため、説明内容に虚偽や誇張がないよう注意を。
契約書には、違約金や解除条件など重要な条項が含まれているため、納得できるまでしっかり読み込みましょう。不明点があれば不動産会社や司法書士、弁護士など専門家に相談を。相続物件や特殊な事情がある場合は、第三者のチェックが安心材料になります。
残代金の決済と抵当権抹消
契約締結後、買主から残代金が支払われ、同時に抵当権の抹消手続きを行います。通常は司法書士に依頼し、必要書類の準備や費用負担は売主側が担当。ローンが残っている場合は、事前の完済スケジュールも重要です。
残代金の受領によって法的な取引完了となるため、その後の資金計画(新居購入・住み替え・納税など)もあらかじめ明確にしておくことが求められます。
引渡し前の最終チェックと引越し準備
引渡し前には、給湯器・照明・壁紙・床など設備や室内の状態を再点検しましょう。特に、取り外す家具や設備が契約書に明記されているかを確認し、勝手な撤去でトラブルにならないよう注意が必要です。
引越しのタイミングは、決済・引渡し日とずれないよう余裕を持って調整しましょう。住み替えを伴う場合は、旧居と新居のスケジュールを並行して管理することで、二重の手間やコストを最小限に抑えられます。
確定申告と税金の申告手続き
譲渡所得が発生した場合、翌年の確定申告で納税義務が生じます。売却益から経費(購入費・仲介手数料など)を差し引いた額に対し、所得税・住民税が課税されます。
ただし、以下のような特例も活用可能です。
・居住用財産の3,000万円特別控除
・所有期間が10年超の軽減税率
これらを適用するには、確定申告時に必要書類をきちんと揃えておく必要があります。申告漏れや遅延による追徴課税を避けるため、売却完了時から資料を整理しておきましょう。
戸建て売却で知っておきたい費用と税金

戸建て売却では、仲介手数料や印紙税、譲渡所得税などさまざまな費用が発生します。事前に全体像を把握しておくことで、予想外の出費に慌てることなく、確実な資金計画を立てられます。
仲介手数料や印紙税などの諸費用
仲介手数料は売買価格に比例し、宅地建物取引業法(第46条)で上限が規定されています。広告や交渉業務を含むため、単なる支出ではなく必要経費と考えるのが妥当です。
一方、印紙税は印紙税法に基づき売買契約書に課される国税で、契約金額に応じて税額が変わります。契約書を2通作成する場合は双方に印紙が必要です。さらに、租税特別措置法による軽減措置が適用される時期もあるため、最新情報を確認しておきましょう。
その他、ローン完済時には抵当権抹消登記が必要で、登録免許税や司法書士報酬が発生します。早めに見積もることで資金計画の安定につながります。
譲渡所得税と住民税の計算方法
譲渡所得は「売却価格−取得費用−譲渡費用」で算定され、所得税法第33条に基づき課税されます。取得費用には購入代金・仲介手数料・リフォーム費用等が含まれますが、領収書がない場合は概算取得費(売却価格の5%)が適用され、結果的に課税額が増えることもあります。
所有期間が5年超か否かで課税区分が変わり、長期譲渡所得の方が短期よりも低税率です。所有期間が長いほど税負担は軽くなります。
また、住民税は譲渡所得に連動し翌年度に課税されるため、収入合算を踏まえて資金繰りを計画的に進めることが求められます。
不動産売却で活用できる特例・控除
自宅を売却する場合、所得税法第33条の2に基づき「3,000万円特別控除」が適用され、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。結果的に譲渡所得税・住民税を大幅に軽減可能です。
さらに、「買換え特例」や「障害者特例」など、条件を満たせば追加の控除や税率軽減も認められます。ただし、適用条件は細かく定められているため、自身の状況に合致するか事前確認が不可欠です。特例を最大限活かすには、税理士や不動産会社に相談し、確定申告書類を漏れなく整えておきましょう。
戸建て売却をさらに有利に進める成功のコツ

戸建て売却の成功には、不動産会社選びや販売戦略に加え、物件特性に応じた対策が欠かせません。特に、複数社査定による相場把握と戦略的な販売計画が重要です。仲介会社を慎重に選べば、売却期間短縮と価格最大化につながります。
築古や相続・離婚などの特殊事情がある場合も、リフォームや更地売却を検討することで買主層を広げられます。市場需要を見極め、予算と見合う形で物件を魅力的に整える工夫が求められます。計画を具体的に立てて進めていくことが成功への最短ルートだといえます。
複数社査定と不動産会社の選び方
一括査定サイトや複数社への依頼で査定額を集め、相場を把握しましょう。査定額の違いは物件の強み・弱みを知る手がかりになります。
不動産会社を選ぶ際は、担当者の知識・対応力・実績を確認し、査定額だけでなく提案力や販売戦略も評価基準に加えましょう。複数社と面談するうちに、相性や戦略力に優れた会社が見えてきます。信頼できる担当者と出会えたら、専属専任媒介や専任媒介で密に連携するのも有効です。
早期売却と高く売るための戦略
売却を急ぐ場合は、価格をやや控えめに設定して需要を喚起するか、不動産会社の「即時買取制度」や「買取保証制度」など、スピード重視の手法を選ぶのが有効です。一方で、住み替えまでに時間の余裕があれば、高めに価格を設定して市場の反応を見ながら調整するのも一案です。市場の動向を注視しつつ、状況に応じて戦略を柔軟に変更することが大切です。
春や秋など需要が高まるシーズンに売却活動を始めるのも効果的です。この時期は不動産取引が活発になるため、ホームステージングによる印象付けもより効果を発揮しやすくなります。
高値売却を目指すには、物件の魅力を最大限に引き出す努力が求められます。室内の清潔感やデザイン性に加え、周辺環境の利便性や将来性も積極的にアピールし、購入希望者が理想の暮らしをイメージしやすくなるよう配慮しましょう。
築古物件や特殊事情を抱える場合の対処法
築古物件では、建築基準法(昭和25年法律第201号)による規制や1981年の新耐震基準に適合しているかの確認が重要です。耐震診断を受け、その結果を開示したり、必要に応じてリフォームを実施することで、買主の不安を軽減し、購入意欲を高める手段となります。
また、再建築可能な地域や、土地としての需要が高いエリアであれば、解体して更地として売り出すことも選択肢の一つです。解体費用とのバランスを見極めながら、最適な販売方法を検討しましょう。
相続や離婚による売却では、民法および不動産登記法に基づく権利関係の整理と合意形成が必要です。不要なトラブルを避けるためにも、書類や登記の整理は早期に済ませておきましょう。
売却と住み替えを同時に進めたい場合
住み替えでは、現在の住まいが売れないと次の購入に進めないケースも少なくありません。そのため、売り先行か買い先行かをあらかじめ明確にし、不動産会社と連携してスケジュールを立てることが重要です。
売却を先行させると、予算を確実に立てられる反面、新居が決まるまで仮住まいが必要となるリスクがあります。逆に買い先行では、理想の物件を先に確保できる一方で、二重ローンのリスクが生じる可能性もあります。
スムーズな住み替えを実現するには、資金繰りやタイミング調整に長けた不動産会社や金融機関との連携が鍵を握ります。早めに相談し、無理のない計画を立てることが成功への近道です。
トラブルを防ぐための注意点とよくある質問

売却には予期せぬトラブルがつきものです。特に戸建ての売却に不慣れな場合、契約成立後に買主からクレームが入ったり、共有者の合意が取れずに断念せざるを得ないケースも珍しくありません。こうしたリスクを避けるには、事前の打ち合わせと情報共有が欠かせません。
また、価格交渉が難航したりスケジュールが予定通りに進まなかったりすることもあります。ある程度の余裕を持って資金計画や移住先の予定を立てておくと、柔軟な対応がしやすくなります。
以下は、売却時によくある疑問とその対策です。事前に把握しておくことで、冷静な判断がしやすくなるはずです。
よくある質問1|売却期間が長引く原因は?
もっとも多い原因は価格設定が相場より高すぎるケースです。内覧にはつながっても、成約に至らない状態が続くことがあります。
また、広告手段が限られていると買い手の目に留まりにくくなり、売却の機会を逃しがちです。ネット広告だけでなく、チラシ・看板・オープンハウスなども活用しましょう。
加えて、内覧時の対応や説明不足が買い手の不安を招き、交渉に踏み切れない要因になることもあります。丁寧な対応が信頼感につながります。
よくある質問2|売り先行と買い先行の違いは?
売り先行は現在の家を売却してから新居を探す流れで、資金計画を立てやすい反面、仮住まいが必要になる可能性があります。
買い先行は先に新居を購入し、あとから今の住まいを売る方法です。理想の物件を確保しやすい反面、売却が遅れると二重ローンや維持費の負担が増えるリスクがあります。
どちらを選ぶかは、自身のライフスタイルや資金状況に応じて、不動産会社と相談しながら判断するのが賢明です。
よくある質問3|離婚時の共有名義物件の売却方法
離婚による共有名義物件の売却では、双方の合意が前提条件となります。財産分与の内容は協議書や公正証書で明確にしておきましょう。
売却活動をスムーズに進めるには、どちらが不動産会社との窓口になるか、連絡体制をあらかじめ整理しておくとよいです。離婚協議中に進めると意見の食い違いで契約が中断することもあるため、重要な事項は先に決め、情報は関係者で共有しておくのがベストです。
よくある質問4|相続した物件を売る際のポイントは?
相続した物件を売るには、相続登記が完了している必要があります(※2024年4月の法改正により登記は義務化)。名義が被相続人のままだと、売買契約ができません。
また、譲渡益や相続税への影響も事前に確認が必要です。とくに複数の財産を相続する場合は、売却時期によって税負担が変わることもあるため、シミュレーションしておくと安心です。
共有相続の場合は、相続人全員の同意が必要です。遺産分割協議書を作成しておくことで、意思統一と手続きがスムーズになります。
よくある質問5|住宅ローンが残っている場合に売却する方法
原則として、売却代金でローン残債を完済する必要があります。査定額が残債に満たない場合は、自己資金で補うか、「住み替えローン」を検討することになります。
住み替えローンとは、新居の購入資金と既存ローンを一本化できる制度。ただし、審査はやや厳しく、金利も高めに設定される傾向があるため、金融機関とよく相談して選択しましょう。
万が一売却が長引く場合は、価格の見直しや「買取保証付き仲介」などの代替手段を検討することも視野に入れると安心です。
まとめ・総括
戸建て売却は、正確な情報と段取り次第でスムーズな成約が実現できます。最後に、本記事の要点を振り返り、成功への道筋を再確認しましょう。
まず、成功のカギは初期の情報収集にあります。不動産会社の査定額の根拠を理解し、周辺相場や地域の特性を見極めることで、現実的かつ納得感のある価格設定が可能となります。選択肢を比較しながら、自分に合った売却方法とスケジュールを選びましょう。
また、円滑な売却には段取りと買主との信頼関係が欠かせません。内覧や価格交渉では、買主の不安を払拭する工夫が求められます。ホームステージングや丁寧な説明を通じて、物件の魅力をしっかり伝える姿勢が、成約率を高めるポイントです。
さらに、費用や税制の基本を押さえたうえで、確定申告や抵当権抹消などの手続きも計画的に進めておくと、売却後のトラブル予防につながります。必要に応じて税理士や司法書士などの専門家と連携しながら進めることで、安心して売却を完了できるでしょう。
この記事の監修者

山下 航平 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
ハウスメーカーにて戸建住宅の新築やリフォームの営業・施工管理を経験後、アキサポでは不動産の売買や空き家再生事業を担当してきました。
現在は、地方の空き家問題という社会課題の解決に向けて、日々尽力しております。








