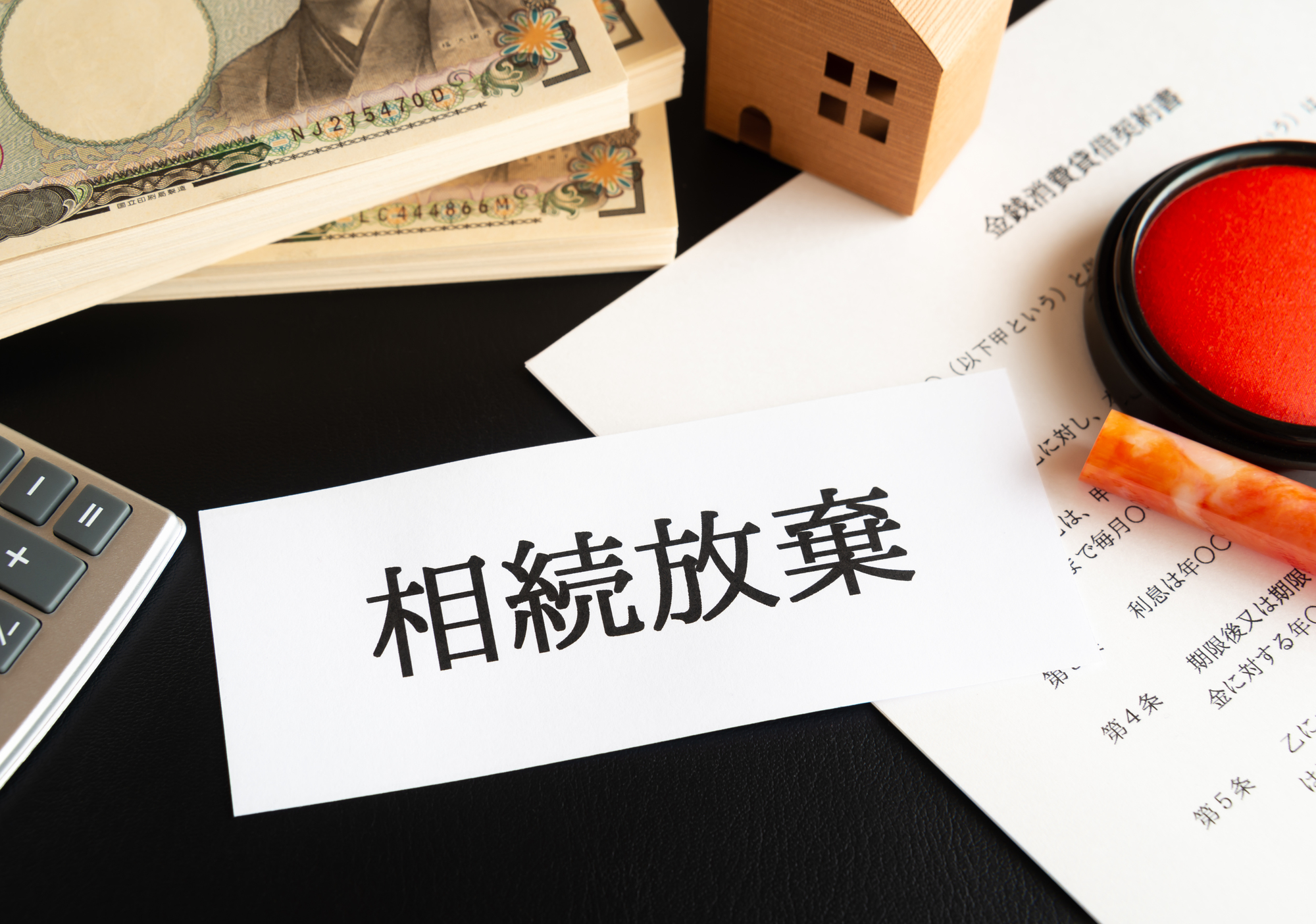公開日:2025.11.04 更新日:2025.10.27
【相続放棄の手続き】必要書類・期限・流れを完全解説

相続放棄は、被相続人の権利や義務をすべて引き継がないために裁判所を通じて行う重要な手続きです。借金や負債などのリスクを避けたい場合は有効ですが、期限や書類準備など厳格なルールもあるため、正しく理解しておかなくてはなりません。
本記事では相続放棄の概要から、必要となる書類や提出方法、そして注意すべき行為などをわかりやすく解説します。
目次
相続放棄とは?財産と負債を引き継がない制度

まずは相続放棄の制度の基本を押さえておきましょう。
相続放棄を行う際には、必ず裁判所へ申述しなくてはなりません。事前に調査を行わずに相続を単純に受け継いでしまうと、後から返済義務を負う可能性があります。また、相続放棄は家族間の協議だけで完結するものではなく、法律で定められた手続きを踏まなければ無効になる点も理解しておきましょう。
単純承認・限定承認との違い
相続には大きく分けて、単純承認・限定承認・相続放棄の3つの方法があります。
そのうち相続放棄は、被相続人が残したプラスの財産だけでなく借金や未払金などのマイナスの財産もすべて引き継がない手続きです。一切の権利や義務を相続しないため、借金返済の責任や財産管理の義務も免れる点が特徴といえます。
単純承認は、被相続人が残したすべての財産と負債を無条件に引き継ぎます。そのため、借金が多い場合は大きなリスクを伴いますが、手続きの手間がほとんどかからない点が特徴です。
そして、相続によって得たプラスの範囲内でマイナスの財産を負担するのが限定承認です。相続人全員の同意が必要というハードルがあるため、手間や状況によっては選択しづらい場合もあります。
遺産分割協議における「財産放棄」と相続放棄の違い
遺産分割協議の場で「財産を放棄する」という表現を使うことがありますが、これはあくまでも遺産分割上の取り決めにすぎません。たとえば、相続人同士の合意で、ある相続人が不動産や預貯金を受け取らない形を決める場合に用いられます。
法律上の相続放棄は、家庭裁判所への正式な申述によってはじめて効力を持ちます。協議の最中に任意で放棄したとしても、法的には単純承認とみなされる可能性があるため注意しましょう。自分の意思で本当に負債を引き継ぎたくない場合は、必ず裁判所へ相続放棄の申述をすることが必須です。
相続放棄の期限(熟慮期間)と延長申立て

相続放棄を検討したら、まず確認すべきは申述できる期限(熟慮期間)です。期限を過ぎると原則として放棄は認められません。
また、相続放棄の申述を準備していても、書類を揃えるのに思ったより時間がかかることがあります。必要に応じて熟慮期間の伸長を申立てることで、さらに調査時間を確保できますが、その申立て自体にも正当な理由と手続きを要するため注意しましょう。
相続を知った時から3ヶ月が原則
相続放棄は、民法の規定により相続が開始したことを知った時点から3ヶ月以内に申述を行わなければなりません。被相続人が死亡した日=相続開始日と考えがちですが、現実には民法上「自己のために相続の開始があったことを知った日」から起算するため、認識が食い違うことがあります。
たとえば遠方に住む相続人が被相続人の死を知ったのが後日だった場合、その日から3ヶ月とカウントされる可能性があります。被相続人の死亡日に必ずしも一致しないため、実際に相続開始を知ったタイミングがいつなのかを正しく把握しましょう。
期限に間に合わない場合は期間伸長を申立て
借金や契約状況を調べるのに時間がかかることから、3ヶ月以内に申述を済ませられないことは珍しくありません。ただし、この3ヶ月は「熟慮期間」と呼ばれ、遺産のプラス部分とマイナス部分をよく調査してから意思決定を行うための猶予期間であることから、間に合わない場合は家庭裁判所に期間伸長を申立てることで、正式に期限を延ばせる可能性があります。
ただし、むやみに伸長が認められるわけではなく、正当な理由が必要です。入院や災害などやむを得ない事情がある場合は、証明書類を整えて速やかに手続きを行いましょう。
熟慮期間を過ぎても認められるケースの有無
熟慮期間を過ぎると相続放棄は認められないため、単純承認になってしまうのが基本です。しかし、相続財産の存在を全く知らず、発覚した時点で初めて相続開始を認識したというような特別な事情がある場合、後から認められる可能性があります。
過去には裁判所で認められた判例もありますが、条件は厳しく個別判断が必要になるため、状況が複雑な場合は早めに法律の専門家に相談して手続きを確認しましょう。
相続放棄の必要書類と取得方法

相続放棄を正式に進めるには、相続放棄申述書をはじめとした多様な書類を用意しなければなりません。それぞれの取得先や手続き方法を把握しておきましょう。
共通して必要となる書類(申述書や戸籍類など)
相続放棄の際には、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書が必須です。これには被相続人と申述人(放棄する人)の詳細を正確に記載し、提出時には必ず必要書類を添付することが求められます。相続放棄申述書は、家庭裁判所から取り寄せまたはオンラインでダウンロードが可能です。
また、被相続人の戸籍・除籍謄本や住民票除票、申述人(相続人)の戸籍謄本も取り寄せておくことを忘れずに。いずれの書類も原本が必要になる場合が多いので、コピーではなく正規の謄本を請求しましょう。
配偶者・子・孫・親・祖父母・兄弟姉妹など続柄ごとに異なる書類
相続順位が異なると、被相続人との関係を示す戸籍の範囲も大きく変わります。配偶者であれば婚姻期間を示す戸籍や除籍が求められ、子や孫の場合は出生からの連続した戸籍謄本をすべて取得する必要がある場合もあります。
また、親や祖父母の相続放棄を検討するシーンでは、さらに上の世代の戸籍で家族関係を整理する必要があるため、書類収集の手間は増えがちです。取り寄せる役所を間違えないように、あらかじめ本籍地や転籍履歴を確認しておきましょう。
管轄の家庭裁判所への提出方法
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。郵送も可能ですが、提出書類に不備があった場合の再提出や質問対応のやりとりを考慮すると、直接持参して確認してもらうほうがスムーズです。
申述書の他に、必要な印紙や切手の準備も忘れてはいけません。裁判所によって求める郵送料が異なる場合もあるので、事前に電話やホームページで確認しておくと安心です。
相続放棄の申述手続きの流れと5つのステップ

相続放棄を遂行するには、財産調査から書類提出、そして裁判所からの通知を受け取るまでの一連のステップを正確に押さえて進めることが大切です。
手続きの流れを詳しく見ていきましょう。
①相続財産の調査
相続放棄をスタートする際には、まずプラス財産とマイナス財産を正確に把握するために調査を行います。銀行やクレジットカード会社、各種ローン残高などを確認し、プラスの財産と比較しましょう。
調査が終わるまで正確な判断は難しいですが、熟慮期間が限られているため、スピーディーに事実確認することが求められます。手間がかかる場合は専門家に相談するのも一つの方法です。
②必要書類の準備・相続放棄申述書の作成
財産内容を把握できたら、相続放棄申述書を作成し、必要書類をそろえて家庭裁判所へ提出します。
この段階で書類が不十分だったり誤記があると、申述の受理が遅れる可能性が高いため、期間内に手続きを終わらせられるように早めに準備しておきましょう。
③家庭裁判所への申述と照会書への回答
すべての書類を揃えたら、管轄の家庭裁判所へ提出します。受理されると、内容を確認した裁判所から照会書が送られてくる場合があるので、期限内に回答して返送しましょう。
照会書には相続の意思や事実関係にもとづく質問が書かれていることが多く、内容に誤りがあると申述が認められない可能性があります。誤解がないように一つひとつ丁寧に回答しましょう。
④相続放棄申述受理通知書の受け取り
家庭裁判所が相続放棄を認めると、相続放棄申述受理通知書が郵送されます。これが届けば、相続人が権利・義務を一切引き継がないことが法的に認められ、手続きは完了です。
万が一この通知書を紛失してしまうと、後日債権者などとトラブルになったときに証明が難しくなる場合があるため、必ず原本を含めて大切に保管しておきましょう。
⑤相続放棄後の対応と注意点
相続放棄申述受理通知書を受け取った後は、被相続人の債務を支払う義務はなくなります。ただし、「その放棄によって相続人となった者」が相続財産の管理を始めることができるまでの間、財産の保存義務(民法第940条)が残るため注意が必要です。
相続放棄が認められた後でも、生命保険金や遺族年金など被相続人の相続財産ではない固有の権利は受け取り可能な場合が多いため、必要に応じて受給手続きを行いましょう。
相続放棄が認められないケース・注意すべき行為

相続放棄の手続き中やそれ以前に特定の行為を行うと、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。ここでは、注意すべき点をまとめたのであらかじめ確認しておきましょう。
相続財産の処分は単純承認とみなされる可能性
相続開始後に被相続人名義の財産を処分したり売却した場合、事実上の単純承認とみなされるリスクがあります。これは借金の有無にかかわらず成り立つため、一度でも財産を使ってしまうと放棄が無効になる可能性が高いです。
そうなると、相続放棄手続きの中断原因になるだけでなく、後からどれだけ主張をしても放棄が認められないケースがほとんどです。
手続き完了を待たずに遺産処分等に介入すると思わぬ負担を背負う結果にもなり得るため、仮に親族からの強い要望などがあっても、裁判所の手続きが終わるまで財産に手を付けるのは避けましょう。
隠匿・消費など悪意ある行為が及ぼす影響
故意に財産を隠したり意図的に消費した場合は、悪意ある行為として他の相続人や債権者から訴訟を起こされるなど刑事的な問題に発展するケースがあります。
相続放棄は法律制度として認められた権利ですが、その手続きを悪用することはできません。万が一、誤った行動をしてしまったときは早めに弁護士など専門家へ相談し、適切な対処方法を確認しましょう。
相続放棄を自分で行うメリットとデメリット

相続放棄は個人で進めることもできますが、その場合のメリットと注意点を押さえておきましょう。
相続放棄を自分で行うメリット
相続放棄の手続きを自分自身で行えば、専門家に支払う報酬分の費用が抑えられます。手続きの進行を自分のペースでコントロールできるため、書類収集や家庭裁判所への提出などを比較的自由に動かせる点もメリットといえるでしょう。
また、相続放棄に関する法律を自力で学ぶことで、今後の生活や家族のトラブルにも対応しやすくなります。相続の仕組みを理解することは、相続放棄以外の選択肢や遺言書の活用などにも役立つでしょう。
相続放棄を自分で行うデメリット
一方、手続きを自分で行うと、法律的に不明点が生じた場合は自力で解決する必要があるため、時間や労力がかかる可能性があります。提出書類を一つでも間違えると手続き全体がスムーズに進まないリスクもあるため、ある程度の法的知識や情報収集が欠かせません。
特に熟慮期間が差し迫っているときに、独力での調査や書類作成が間に合わない可能性も。状況に合わせて必要ならば専門家を積極的に活用する選択肢も検討することをおすすめします。
専門家に依頼するメリットと費用相場

相続放棄の手続きを専門家に依頼する最大の利点は、法的な知識と経験にもとづいて書類作成や手続きを代行してもらえることです。書類の不備によるリジェクトを回避しやすくなるため、結果的に時間を大きく節約できます。
弁護士と司法書士のサポート内容
弁護士は代理人として裁判所での手続きを全面的に行えるため、時間がない方や複雑で争いが生じそうな相続では心強い味方となります。法的な交渉ごとや裁判対応が必要なときにも安心です。
司法書士は書類作成や書類提出の代行業務に特化しており、比較的リーズナブルな費用で進められる場合があります。どの程度までサポートが必要かを考え、状況に合わせて依頼先を選ぶとよいでしょう。
専門家に依頼する場合の費用目安と依頼タイミング
費用はケースバイケースですが、相談料と書類作成費用、さらには代理で申立てを行う場合の手数料などが加算される可能性があります。依頼する際は、トータルの見積もりと作業範囲をしっかり確認し、納得する形で契約を結ぶことが大切です。
また、熟慮期間ギリギリで依頼すると、通常よりも高額な手数料が発生したり、書類準備が間に合わない場合にも対応を求められるなどのリスクも懸念されるため、放棄の意思が固まっているなら、早めに専門家を探して相談を始めましょう。
よくある質問とトラブル事例
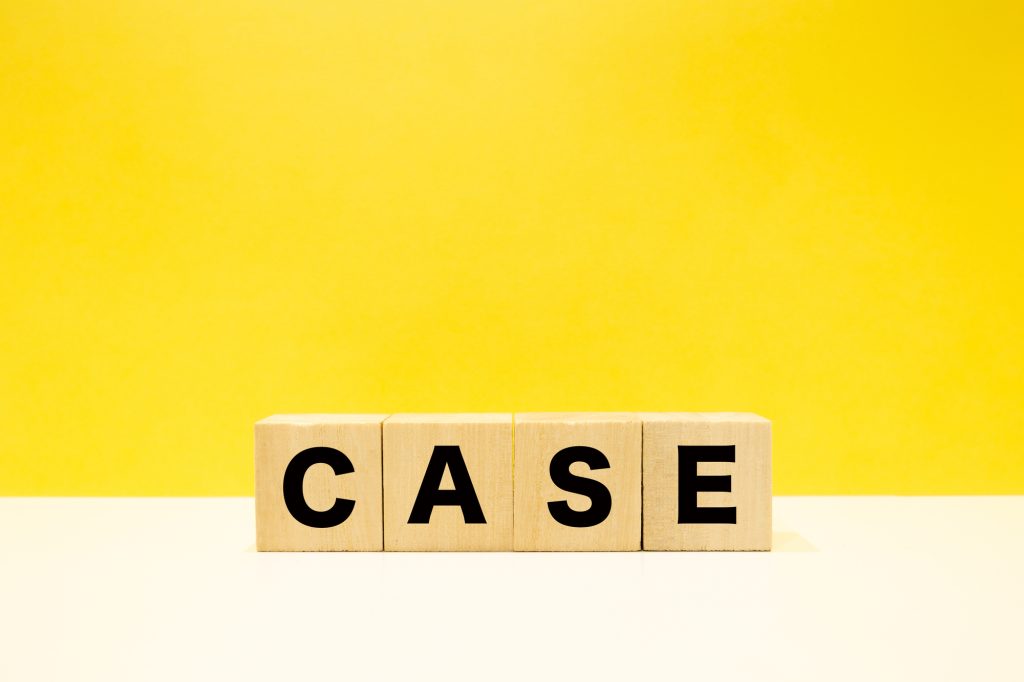
最後に、相続放棄にまつわる疑問点や、実際の現場でしばしば発生するトラブルについて押さえておきましょう。
相続放棄後の生命保険金や遺族年金はどうなる?
生命保険金は契約で指定された受取人の固有の財産とされることが多く、相続財産とは別扱いとなります。そのため、相続放棄をしても受取人の権利として保険金を取得できるケースが一般的です。
遺族年金も同様で、受給資格が個人に帰属するため、相続放棄後でも支給を受けられる場合があります。しかし、念のため制度上の詳細や加入している保険の約款を確認しておくようにしましょう。
複数の相続人が同時に相続放棄をするとどうなる?
配偶者や子など、法定相続人となる人が全員相続放棄をすると、次順位の相続人(たとえば兄弟姉妹や甥姪)に相続権が移ります。ただし、相続の意思がまったくない場合は、その人たちも同様に放棄を考える必要が出てきます。
相続人全員が放棄すると、最終的には相続人不存在の状態となり、利害関係人または検察官の申立てにより家庭裁判所から相続財産管理人が選任され、財産を管理・清算することになります。
子・孫・甥姪など次順位に相続が移るケース
上位の相続人が相続放棄した場合、その下に位置する相続人に権利が移るのが民法のルールです。子や孫、甥姪といった人が急に相続問題に巻き込まれることもあり得ます。
そのため、関係性が遠い親族ほど相続放棄を考えていなかったり、手続きに戸惑ったりするケースが少なくありません。必要書類の収集も手間が増えるため、日頃からの連絡や情報共有が重要になります。
相続放棄の撤回が認められる場合(詐欺・強迫)
相続放棄は一度行うと原則として撤回・取り消しはできませんが、民法上の「詐欺または強迫」による意思表示であった場合には、家庭裁判所への申立てにより取り消しが認められることも。具体的な事例としては、相続人が騙されて申述に至ったり、脅迫を受けて放棄の書類にサインをしてしまったなどです。ただし、このような特例は実証が極めて難しく、家庭裁判所の厳密な審査を経る必要があります。
まとめ・総括
相続放棄は、借金や未払金など大きな負債から自分や家族を守るために有効な手段です。しかし、期限や手続き、書類準備など複数のステップを正しく理解する必要があります。
大切なのは、被相続人の財産状況を正確に調査し、期限内に必要書類を揃えて申述できるよう計画的に進めることです。自分で行うことも可能ですが、なかなか自身での判断が難しい場面も多々あるため、なるべく専門家に頼ることをおすすめします。
「アキサポ」でも、弁護士や司法書士といった専門家と連携しつつ相続周りのサポートを行っています。相続か放棄か迷われている段階からでも、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。