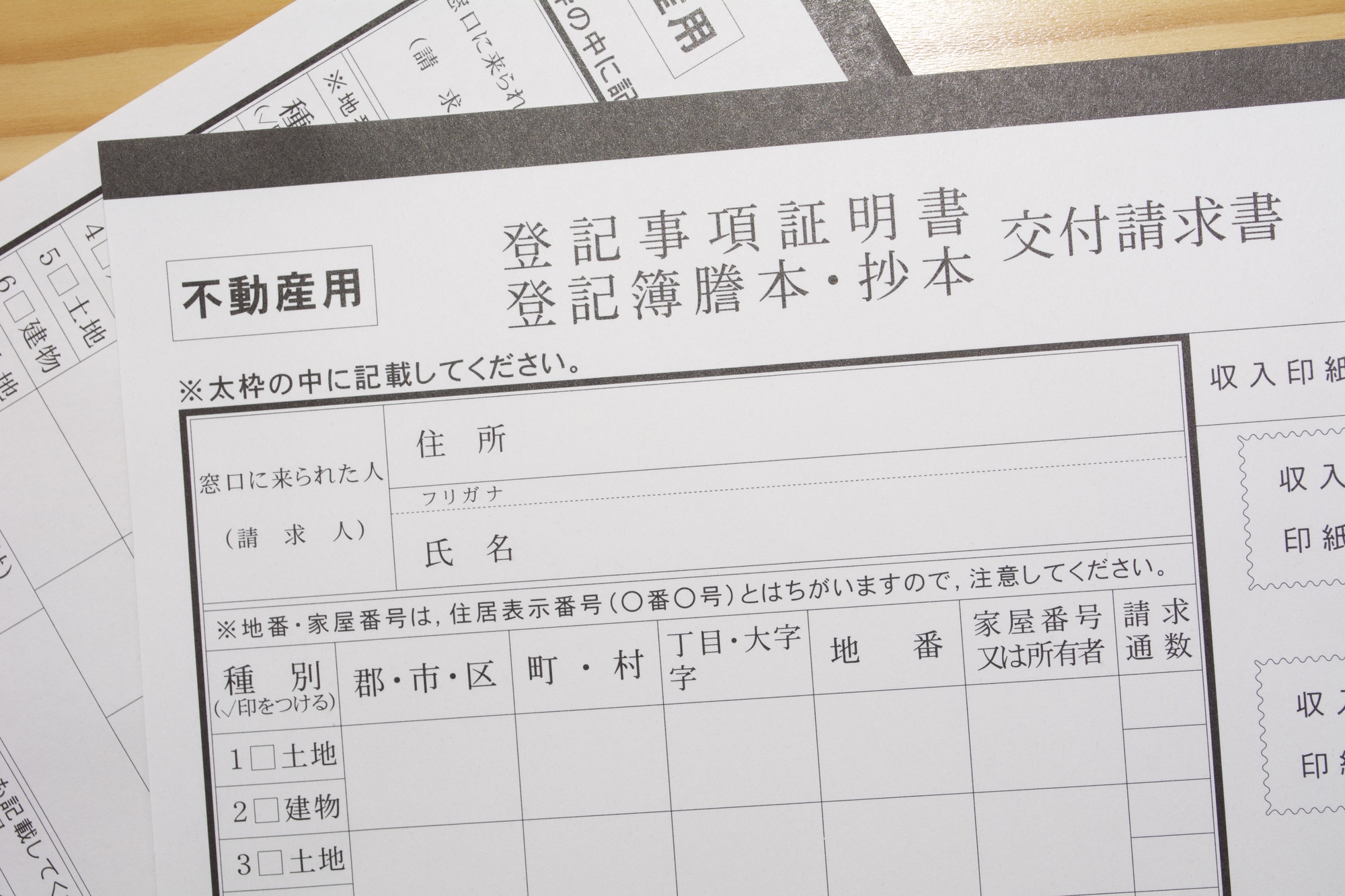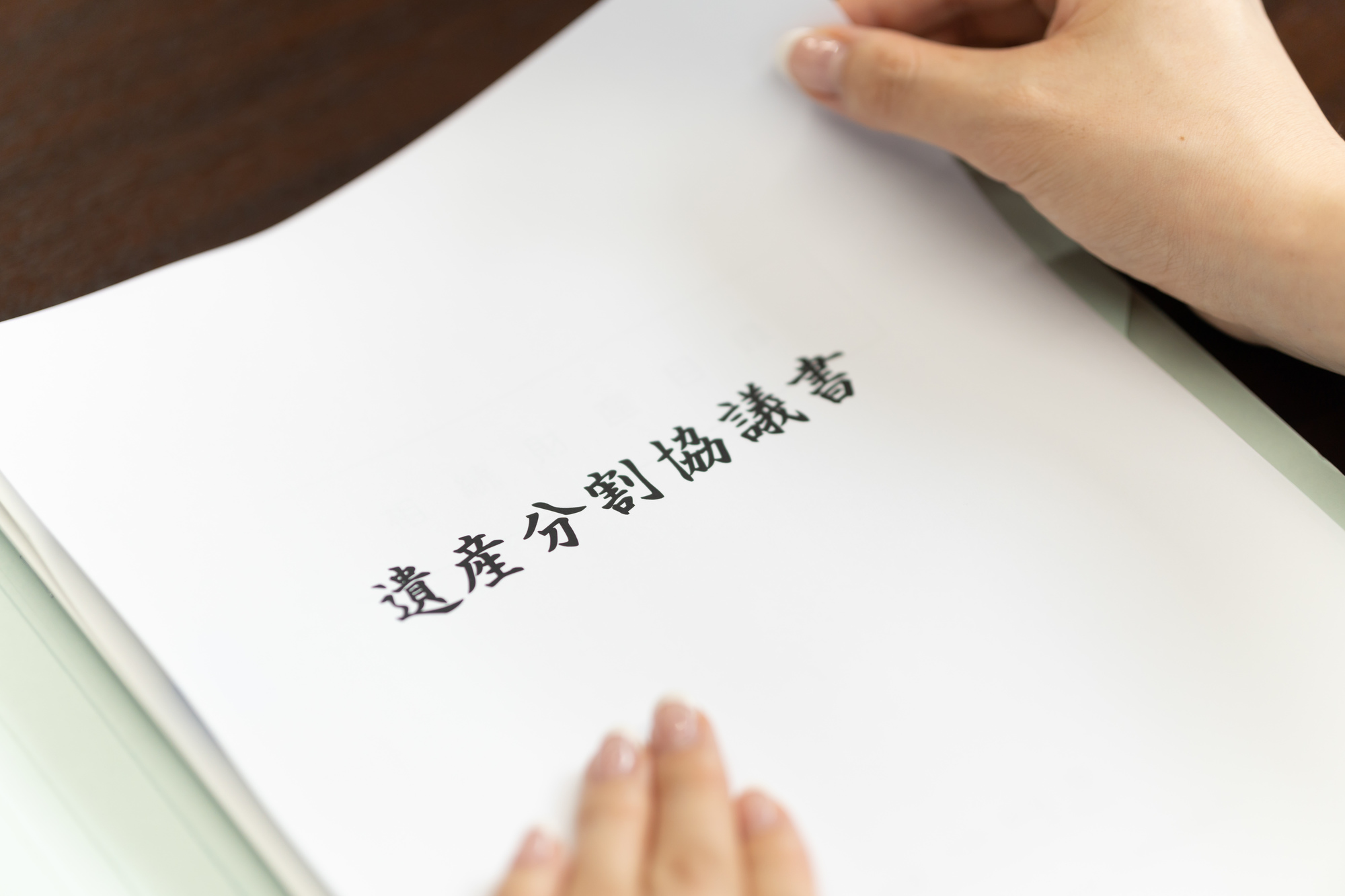公開日:2025.11.08 更新日:2025.10.27
相続登記に必要な書類を徹底解説!ケース別・取得方法・注意点まで網羅

相続登記に必要な書類は、被相続人や相続人を証明する戸籍関係の書類から、不動産の固定資産評価証明書まで多岐にわたります。どの書類も手続きを進めるうえで欠かせないものであり、不備があると登記が完了せず、再取得などの手間が発生することもあります。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化されたことで、より早めの準備が求められるようになりました。戸籍や住民票などは原則として発行時期によって内容が変わる場合はないため、有効期限や提出先でのルールを確認し、申請前に最新情報を確認しておくことが大切です。
そこでこの記事では、相続登記に必要な基本書類の一覧から、ケース別の書類の違い、取得方法、提出時の注意点までを解説します。これから相続登記を進める方は、ぜひ参考にしてください。
目次
相続登記とは?近年の義務化背景と押さえておきたいポイント

相続登記は、不動産の名義を亡くなった方(被相続人)から相続人へと正式に変更するための手続きです。これまでは任意とされてきましたが、2024年4月1日から義務化がスタートしました。(不動産登記法第76条の2)背景には、名義変更されないまま放置された不動産が増え、相続人不明土地問題や固定資産税の未納といった社会的な課題が深刻化している現状があります。
相続登記を行わないまま時間が経つと、戸籍や関係書類の取得が難しくなり、手続きが複雑化してしまうおそれがあります。さらに、将来的に相続人間のトラブルへ発展するケースも少なくありません。
この義務化の背景を踏まえ、今のうちに基本的な流れと必要書類を把握し、早めに手続きを進めることが大切です。家族の安心と不動産の円滑な承継につなげるために、スムーズな登記を心がけましょう。
相続登記に必要となる基本書類一覧

相続登記の手続きでは、被相続人と相続人の関係を証明する戸籍類や、不動産の評価額を示す固定資産評価証明書など、公的に信頼性の高い書類を揃える必要があります。
なかでも戸籍関係の書類は種類が多く、出生から死亡までのつながりを確認するため、複数の役所での手続きが必要になることもあります。そのため、事前にどの窓口で入手できるのかを調べておくことで、効率よく準備を進められるでしょう。
また、相続登記の必要書類の中には、取得までに時間がかかるものもあります。発行手数料に加えて、郵送での取り寄せ費用が発生するケースもあるため注意が必要です。
申請後に書類が不足していると、再度手続きを行うことになり負担が増えてしまいます。手続きを滞りなく進めるためにも、早めに全体像を把握し、計画的に書類を準備しておくことが大切です。
相続登記に必須となる基本書類を一つずつ確認していきましょう。なお、すべての書類が必要となるのは遺産分割協議による場合など、ケースによって異なります。
① 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本は、相続関係を証明するために欠かせません。転籍や改姓をしている場合は、過去の本籍地ごとに戸籍を取り寄せる必要があります。相続人が多いと取り寄せる戸籍も増え、取得に時間がかかるケースもある点に注意しましょう。
② 相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人全員の現在の戸籍謄本をそろえることで、法務局に「相続人が誰であるか」を正式に証明できます。1人でも抜けていると手続きがやり直しになるおそれがあるため、戸籍の確認をする際は漏れのないよう注意しましょう。
③ 被相続人の住民票の除票
住民票の除票は、被相続人の死亡と最後の住所を証明するための書類です。法務局はこの書類をもとに、登記簿上の住所と実際の住居情報を照合します。登記簿上の住所と被相続人の最後の住所が異なる場合、別途、所有権の登記名義人住所変更登記が必要になることがあります。
自治体によっては除票の保存期間が限られている場合もあるため、早めに取得することが望ましいでしょう。
④ 相続人の住民票(新名義人の住所証明情報)または戸籍の附票
新たに不動産の名義人となる相続人の住所を確認するために、住民票または戸籍の附票を提出します。これにより、登記簿上の住所を正確に登録することが可能です。申請前には、住所変更や転居がないかを再確認しておくとスムーズです。
⑤ 固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、登記にかかる「登録免許税」を計算するために必要な書類です。毎年評価額が更新されるため、その年度の最新分を用意しましょう。
取得先は不動産所在地の市区町村役場や都税事務所です。地域によって発行手続きが異なる場合があるため、事前に問い合わせておくと安心です。
⑥ 登記申請書と収入印紙(登録免許税納付用)
相続登記を申請する際には、法務局指定の様式に沿って登記申請書を作成し、必要な金額の収入印紙を貼付します。記載ミスや書類不備があると差し戻されることがあるため、法務局の公式サイトなどで最新の記載例を確認しながら慎重に準備しましょう。
⑦ 遺産分割協議書・印鑑証明書(必要に応じて)
相続人全員の合意に基づき遺産を分ける場合は、遺産分割協議書と全員の印鑑証明書が必要です。
原則として相続人全員の署名・実印の押印が必要で、その実印が本物であることを証明するため印鑑証明書も併せて提出します。印鑑証明書は、実務上作成後3ヶ月以内のものが求められます。署名や押印の不備があると無効になることもあるため、実印の使用や証明書の発行日にも注意が必要です。協議内容は慎重に確認し、全員が納得したうえで作成しましょう。
⑧ 法定相続情報一覧図の写し(添付書類の省略に有用な公的証明書)
法定相続情報一覧図は、相続関係を一覧化した公的な書類で、提出された戸籍謄本の代わりとして、法務局への提出時に利用できます。法務局で無料発行されるため、相続人が多い場合や複数の不動産を相続する場合に特に便利です。書類の添付を省略でき、登記や銀行手続きも効率化が期待できるため、積極的に活用するのがおすすめです。
ケース別に見る相続登記の必要書類

相続登記に必要な書類は、相続の方法によって異なります。法定相続分での手続きなのか、遺産分割協議を経て行うのか、または遺言書に基づく登記かによって、準備する書類や流れが変わります。
ここでは、代表的なケースごとに必要となる書類と注意点をまとめました。自分の状況に合うケースを確認してみてください。
1) 法定相続分による相続登記
法定相続分に従って登記を行う場合、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本など、基本的な書類が必要です。
この方法では遺産分割協議書を省略できる一方で、不動産が相続人全員の共有名義となるため、管理や売却が複雑になることもあります。将来的なトラブルを避けるためにも、相続人同士で早めに協議を行い、分割や名義変更の方針を明確にしておくとよいでしょう。
2) 遺産分割協議による相続登記
相続人全員で話し合い、不動産の取得者を決める場合には、遺産分割協議書の作成が欠かせません。協議書には全員の署名・実印の押印が必要で、印鑑証明書も併せて提出します。
準備に時間がかかることもありますが、合意内容を明文化しておくことで、後々のトラブルを防ぎやすくなります。一度決まってしまえば、登記後の管理や処分もスムーズに進められるのがメリットです。
3) 遺言書がある場合の相続登記
遺言書に基づく登記を行う場合は、その形式によって必要な手続きが異なります。公正証書遺言であれば、検認は不要です。公証役場で作成された遺言書の謄本を登記申請書に添付することで、比較的スムーズに進められます。
一方、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、登記申請に先立ち、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。検認の有無によって登記完了までの期間が変わるため、時間にゆとりを持って進めましょう。ただし、法務局の「自筆証書遺言の保管制度」を利用している場合は、検認は不要です。
4) 法定相続人以外の第三者への遺贈がある場合
遺言書により、法定相続人以外の人へ不動産を遺贈する場合、受遺者が単独で申請できるケースを除き、その受遺者が相続人全員または遺言執行者と共同で新たな名義人として登記を行います。
必要書類は、被相続人の戸籍謄本や受遺者本人の住民票、遺言書の写しなど、基本的には通常の相続登記と同様です。ただし、遺言書の内容確認や検認手続きなど、慎重な対応が求められます。
特に第三者への遺贈では、登記申請に不備がないよう、事前に専門家へ相談しておくと安心でしょう。
書類の取得方法と申請書のダウンロード

相続登記に必要な書類は、各自治体や法務局で発行・取得するものが多く、入手方法を理解しておくことが手続きをスムーズに進めるポイントです。
戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書など、どこでどのように申請すればよいかを把握しておくと、後からの手戻りを防げます。主な書類の取得方法や申請書の入手先を解説していきます。
戸籍謄本・住民票・除票の取得手続き
これらの書類は、被相続人の最後の本籍地または住所地の市区町村役場で申請します。郵送での取得も可能ですが、返信用封筒や定額小為替(郵便為替)の準備が必要です。
役場のシステムや戸籍の種類によっては、即日発行できない場合もあります。特に遠方の役場に請求する場合は、日数に余裕をもって対応しましょう。
固定資産評価証明書を入手する方法
固定資産評価証明書は、不動産所在地を管轄する市区町村役場または都税事務所で取得します。
多くの窓口は平日の日中のみ対応しているため、仕事の都合が付かない場合は郵送請求を利用するのも方法のひとつ。一部の自治体ではオンラインでの請求も可能です。
申請時には「固定資産税納税通知書」などを手元に用意しておくとスムーズに手続きが進みます。年度ごとに評価額が更新されるため、最新年度分を取得するようにしましょう。
相続登記の申請書はどこで手に入る?
相続登記に使う申請書は、法務局の公式サイトからダウンロードできます。同ページには記入例や注意事項も掲載されているため、初めての方でも手順を確認しながら作成できます。
記入の際は、必要書類との整合性を確認しましょう。手書きに不安がある場合は、パソコン入力で作成・印刷して提出する方法も活用できます。
必要書類の有効期限と提出時の注意点

相続登記で使用する書類のなかには、明確な法的期限が定められていないものもありますが、法務局の実務運用では「一定期間内に発行された書類」であることを求められるケースが多くあります。
古い書類を使うと差し戻しや再提出を求められることもあるため、申請時期に合わせて新しいものを準備しておくようにしましょう。続いて、特に注意すべき書類の有効期限と、提出時のチェックポイントを解説します。
戸籍謄本や住民票の有効期限
戸籍謄本や住民票には、法律上の明確な有効期限は定められていません。しかし、不動産登記の実務上では、発行からおおむね3か月以内のものが望ましいとされています。ただし、相続登記においては「作成後3ヶ月以内」を要する印鑑証明書を除き、法定相続情報一覧図の写しがあれば戸籍の有効期限は問われないこともあります。
特に金融機関での手続きや不動産登記などでは、書類の日付が古いと受け付けられない場合もあります。再取得の手間を防ぐためにも、登記の申請時期を見据えて、できるだけ新しい日付の書類をそろえましょう。
固定資産評価証明書は最新年度分を添付
固定資産評価証明書は、不動産の評価額をもとに登録免許税を算出するための重要な書類です。この評価額は毎年度見直されるため、登記申請時には最新年度分を添付するのが原則です。
古い年度の証明書を使うと、税額が誤って計算されるリスクがあります。市区町村役場で発行を依頼する際は、必ず「今年度分でお願いします」と伝えましょう。
書類の綴じ方と原本還付のポイント

相続登記の申請時には、書類を整える段階でも注意が必要です。提出先の法務局が確認しやすいよう整理しておくことはもちろん、返却してもらいたい書類(戸籍や証明書など)は「原本還付」の申請を忘れずに行いましょう。
ここからは、提出書類をまとめる際のコツと、原本を返却してもらうための手続きを確認していきましょう。
提出書類の綴じ方や保管のコツ
提出書類は、不動産の地番や相続人ごとなど、目的別にまとめると確認がスムーズです。提出前にすべての書類をコピーしておくと、内容を手元で確認できるうえに、紛失時のリスク対策にもなります。
原本還付で戸籍の原本を返してもらう方法
戸籍などの原本を返却してもらうには、提出時に原本還付を申請します。返却を希望する書類のコピーを添付し、「原本と相違ありません」と付記し、提出すれば、審査後に原本は戻ってきます。他の相続手続きにも再利用できるため、忘れずに対応しましょう。
相続登記でよくあるQ&A

相続登記は、人生でそう何度も経験する手続きではなく、いざ取り組もうとすると疑問や不安を感じる方も多いものです。
特に「協議書は必ず必要?」「専門家に頼むと費用はどのくらい?」「自分で手続きしても大丈夫?」といった質問がよく寄せられます。
最後に、相続登記の準備や進め方で多くの方が気になるポイントを、Q&A形式で確認しておきましょう。
Q. 遺産分割協議書は省略できる?
法定相続分で登記する場合は協議書の提出は不要ですが、法定相続分での登記は不動産が相続人全員の共有名義となるため、財産の分け方を明確にしておくためには、遺産分割協議書を作成しておくのが安心です。協議書があれば、将来的な誤解やトラブルを防ぐことができるため、可能な限り書面で残しておきましょう。
Q. 相続登記を専門家に依頼した場合の費用相場は?
司法書士に依頼する場合、費用の目安は一般的に5〜10万円です。不動産の数や相続関係の複雑さによって変動しますが、書類収集から申請までを任せられるのはメリットです。費用を抑えたい場合は、必要書類を自分で集めてから依頼する方法も検討してみましょう。
Q. 自分で相続登記する際の難易度は?
相続登記は、書類の取得や申請書の作成など慣れない作業も多いですが、法務局の無料相談や公式サイトを活用すれば、個人でも対応できます。焦らず一つずつ書類を確認し、不明点があれば早めに問い合わせをしましょう。
相続登記に必要書類を正しく揃えて、スムーズな手続きを
相続登記は、戸籍謄本や評価証明書などの書類が多く、最初は複雑に感じるかもしれません。しかし、手順を理解して一つずつ準備すれば、確実に進めることができます。
義務化により、放置するリスクも高まっているため、早めの対応が安心です。また、複数の不動産や相続人が関わるケースでは、専門家のサポートを受けることで手続きが格段にスムーズになります。必要書類を正しく揃え、将来のトラブルを防ぐためにも、今のうちに準備を始めておきましょう。
不動産の相続・活用で悩んだら「アキサポ」へ
不動産の相続は、登記だけでなく、その後の管理や活用方法にも悩むケースが少なくありません。 「アキサポ」では、空き家や古民家などの相続不動産について、売却・利活用・リノベーションまでトータルでサポートしています。 専門スタッフが状況に応じて最適な解決策をご提案しますので、ぜひ一度ご相談ください。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。