公開日:2025.11.14 更新日:2025.10.29
不動産所得の確定申告ガイド|計算方法から節税対策まで解説

不動産を所有していると、毎年気になるのが確定申告。賃貸経営をしている方や、副収入として家賃収入を得ている会社員の方も、一定の条件を満たす場合は「不動産所得」として申告が必要になります。とはいえ、経費の範囲や減価償却の扱い、青色・白色申告の違いなど、実際の手続きでは迷うポイントが多いものです。誤った申告をすると、思わぬ税負担が発生することも。本記事では、不動産所得の確定申告にまつわる基本から計算方法、節税のコツまでを解説します。
目次
不動産所得とは?基本的な仕組みを解説

不動産所得の確定申告は、所得税法で定められた10種類の所得区分のひとつです。アパートやマンションの家賃収入だけでなく、駐車場の貸出収入なども含まれます。
ここでは、不動産所得の基本的な考え方や対象となる収入の範囲、他の所得との違いについて整理しながら、確定申告の準備を進めるうえで押さえておきたいポイントを解説します。
不動産所得の定義と対象となる収入
不動産所得とは、土地や建物などの貸付けによって得られる所得を指します。具体的には、アパートやマンションの家賃、駐車場の使用料、貸家の賃貸料、土地の地代などが対象です。
さらに、礼金・更新料・共益費といった付随的な収入も不動産収入に含まれます。ただし、敷金や保証金のうち返還義務のあるものは収入に含まれません。
不動産所得は「不動産収入-必要経費」で算出され、この差額が不動産所得(課税対象)となります。経費の範囲を正確に把握することが、適正な税負担や節税につながる重要なポイントです。また、不動産を売却して得た利益は「譲渡所得」に分類されるため、不動産所得とは別に扱う必要があります。
事業所得・譲渡所得との違い
不動産所得と混同されやすいのが、事業所得と譲渡所得です。事業所得は、商工業やフリーランスなど継続的な事業活動によって得た所得を指します。
不動産の貸付けも、貸室や戸数が多いなど一定の規模を超える場合は不動産所得として事業的規模とみなされますが、所得区分は不動産所得のままです。
一方、譲渡所得は不動産や株式などの資産を売却した際に発生する所得で、税率や計算方法が大きく異なります。たとえば、相続した不動産を売却した場合は譲渡所得として申告する必要があり、原則として確定申告書を使用します(令和4年分以降、確定申告書Aは廃止され、多くの方が確定申告書を使用しています)。
損益通算のルールも所得区分によって異なるため、誤って申告しないよう注意が必要です。
誰が申告する必要があるのか
不動産所得がある方は、原則として確定申告を行う義務があります。会社員など給与所得がある方でも、不動産収入から経費を差し引いた所得が年間20万円を超える場合は所得税の申告が必要です(原則として、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要です)。
専業で賃貸経営を行っている方はもちろん、副業として物件を所有している方や、年金受給者で家賃収入がある方も対象となります。また、共有名義の不動産を所有している場合は、持分割合に応じてそれぞれが申告を行うのが原則です。
なお、不動産所得が赤字となった場合でも、給与所得など他の所得と損益通算できるケースがあり、税金の還付を受けられる可能性があります。たとえ少額の収入であっても、自身の状況を確認したうえで申告の有無を判断することが大切です。
不動産所得の確定申告が必要なケースとは?

不動産を所有していても、すべての方に確定申告の義務があるわけではありません。不動産所得の確定申告が必要かどうか、所得金額や他の収入状況によって、申告の必要・不要が変わります。誤って申告漏れをしてしまうと、後から追徴課税が発生するおそれもあります。
まずは、ご自身の所得額や生活スタイルに当てはまるケースを確認し、どのような場合に確定申告が必要となるのかを整理しておきましょう。
確定申告が必要な所得の目安
確定申告が必要かどうかは、不動産所得の金額によって判断されます。会社員など給与所得がある方の場合、給与以外の所得(不動産所得を含む)が年間20万円を超えると、確定申告を行う必要があります。
この20万円は「収入」ではなく、「収入-経費」で算出される所得額である点に注意しましょう。たとえば、年間の家賃収入が100万円でも、管理費や固定資産税、修繕費などの経費が85万円かかっていれば、所得は15万円となり、申告義務はありません。
一方で、個人事業主や年金受給者のように給与所得がない方は、不動産所得が基礎控除額(48万円)を超えると申告が必要になります。また、医療費控除やふるさと納税などの控除を受けたい場合は、所得の大小にかかわらず申告することで、税金の還付を受けられるケースもあります。
会社員・副業・年金受給者のケース別
会社員の方が副業として賃貸経営を行っている場合、勤務先で年末調整を受けていても、不動産所得が20万円を超えれば確定申告が必要です。青色申告を選べば、複式簿記での記帳やe-Taxによる電子申告などの要件を満たすことで青色申告特別控除(最大65万円)を活用でき、節税効果が高まります。年金受給者の方は、公的年金等の収入が400万円以下で、かつ年金以外の所得(不動産所得など)が20万円以下の場合は申告不要です。
ただし、住民税の申告が別途必要になることがあるため、自治体への確認を忘れずに。専業で不動産賃貸業を営んでいる方は、他の所得がなく不動産所得が基礎控除額(48万円)を超える場合に確定申告を行う必要があります。
また、副業禁止規定のある会社でも、不動産所得は多くの場合「事業」ではなく「資産運用」として扱われるため問題になりにくいですが、不安な場合は就業規則を確認しておくと安心でしょう。
確定申告が不要なケース
給与所得者で、不動産所得を含む給与以外の所得が20万円以下の場合は、原則として所得税の確定申告は不要です。ただし、この場合でも住民税の申告が求められることがあるため、自治体の案内を確認しておきましょう。
年金受給者も、公的年金収入が400万円以下かつその他の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。しかし、医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除を利用したい場合は、確定申告を行うことで税金が戻ってくる可能性があります。
また、不動産所得が赤字となった場合は、確定申告をすることで給与所得との損益通算ができ、所得税や住民税の負担を軽減できます。空室や修繕費の増加で赤字が出ている年ほど、申告を上手に活用することで節税につながる可能性があります。
不動産所得の計算方法と必要書類
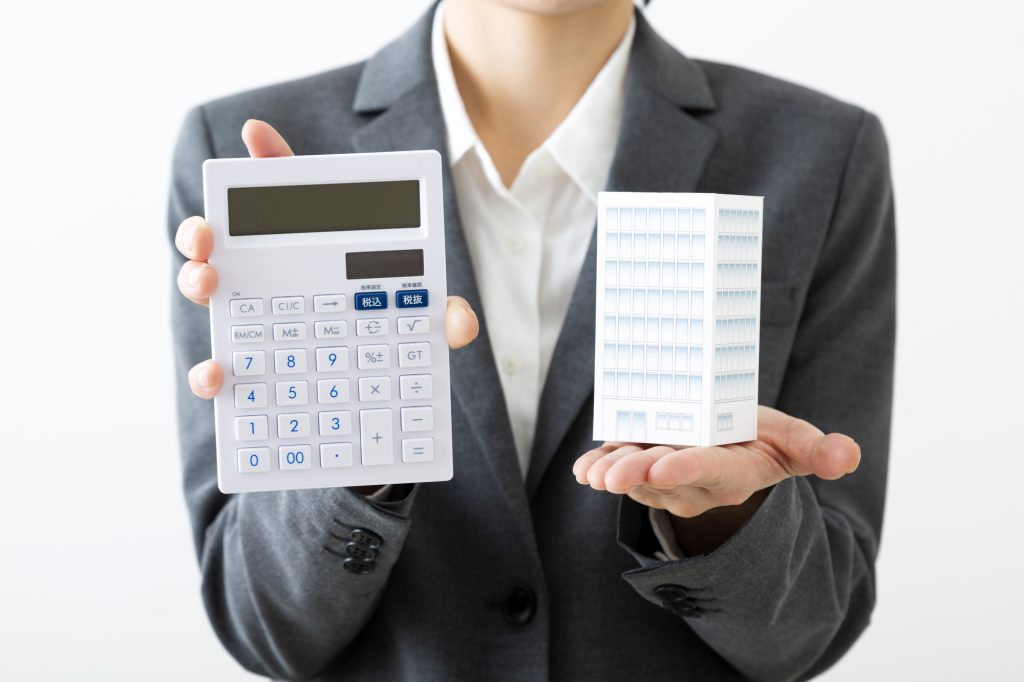
不動産所得の確定申告では、収入と経費を正確に把握することが大切です。家賃収入だけでなく、礼金や更新料なども対象となるため、想定よりも項目が多く複雑に感じる方も少なくありません。
必要な書類をそろえ、計算方法を理解しておくことで、申告時の手間やミスを防げます。ここでは、収入・経費の考え方から減価償却費、書類作成のポイントまでを順を追って解説します。
収入と経費の具体例
不動産所得を求める際は、まず年間の総収入を把握します。家賃や地代のほか、礼金・更新料・共益費・駐車場収入などもすべて含めます。
次に、必要経費を差し引いて所得を計算します。主な経費として、固定資産税・都市計画税・火災保険料・修繕費・管理費・広告宣伝費・通信費・交通費などが挙げられます。
また、減価償却費や借入金の利息も重要な経費項目です。ただし、借入金の元本返済分は経費には含まれません。経費を計上する際は、領収書や請求書を必ず保管しておくことが大切です。
基本の計算式は「総収入金額-必要経費」。この金額が不動産所得となり、課税の対象になります。
減価償却費・借入金利息の取り扱い
減価償却費とは、建物や設備などの取得費を法定耐用年数に応じて分割し、毎年経費として計上できる仕組みです。土地は対象外ですが、建物本体や給排水設備・電気設備などの附属設備、駐車場舗装などの構築物は減価償却の対象になります。耐用年数は建物の構造により異なります。たとえば、木造住宅は22年、鉄筋コンクリート造は47年など、構造や用途によって法定耐用年数が定められています。
中古物件の場合は、残存耐用年数をもとに計算します。借入金の利息は、不動産取得や修繕のための借入れであれば経費として認められますが、元本部分は対象外です。さらに、土地購入資金の利息は、不動産所得が赤字となった場合、その赤字相当額は損益通算できないことが、所得税法で定められているため注意しましょう。
収支内訳書・青色申告決算書の作成方法
確定申告時に提出する書類は、申告方法によって異なります。白色申告の場合は「収支内訳書(不動産所得用)」を使用し、収入と経費を一覧にまとめて所得を計算します。
一方、青色申告では「青色申告決算書(不動産所得用)」を作成し、損益計算書や貸借対照表、減価償却費の明細などを記載します。青色申告は記帳や帳簿付けの手間は増えますが、最大65万円の特別控除を受けられるため、節税効果が大きいのがメリットです。
これらの書類は税務署窓口のほか、国税庁のサイトからもダウンロードできます。確定申告ソフトを利用すれば、数字を入力するだけで自動的に書類を作成できるため、初めての方でもスムーズに申告を進められます。
帳簿付けと領収書管理のポイント
青色申告で特別控除を受けるには、日々の取引を正確に記録した帳簿が必要です。複式簿記による記帳が基本で、仕訳帳や総勘定元帳の作成が求められます。白色申告や10万円控除を選ぶ場合は、簡易的な帳簿でも構いません。
どちらの場合も、領収書・請求書・契約書などの証拠書類は必ず保管しましょう。確定申告における書類の保存期間は青色申告で7年(または一部5年)、白色申告で5年が原則です。
書類は月別や項目別にファイルしておくと、申告時に迷わず整理できます。最近は、スマートフォンで撮影した領収書データを保存する「電子帳簿保存」も認められており、デジタル管理で効率化を図る方も増えています。会計ソフトを使えば、帳簿付けから決算書作成までを一括で行うことができ、確定申告の負担を大幅に軽減できます。
青色申告と白色申告の違いとメリット
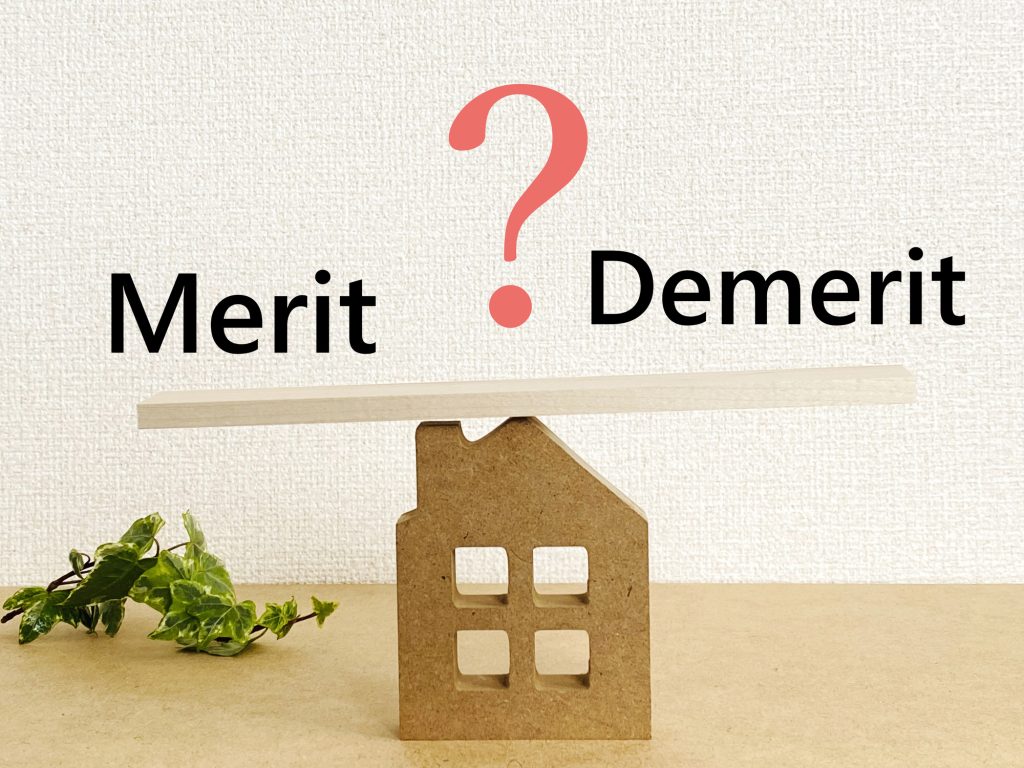
不動産所得の確定申告では、青色申告と白色申告のいずれかを選択できます。青色申告にはさまざまな特典がありますが、要件も厳しくなります。ご自身の状況に合わせて、どちらを選ぶべきか検討しましょう。
青色申告の特典(65万円控除など)
青色申告の最大のメリットは、「青色申告特別控除」です。複式簿記での記帳とe-Taxによる電子申告などの条件を満たせば、最大65万円の控除を受けられます。簡易帳簿や紙での申告の場合は、55万円または10万円の控除が適用されます。この控除は所得から直接差し引かれるため、所得税だけでなく住民税や国民健康保険料の負担も軽減可能です。
さらに、赤字を翌年以降3年間繰り越して黒字と相殺できる「純損失の繰越控除」や、家族に支払う給与を経費に計上できる「青色事業専従者給与」など、節税につながる特典もあります。手間はかかりますが、その分メリットも大きい申告方法といえるでしょう。
事業的規模の判断基準
青色申告で最大65万円の控除を受けるためには、「事業的規模」に該当しているかどうかがポイントです。一般的な判断基準は「5棟10室基準」と呼ばれ、戸建てなら5棟以上、アパートやマンションなら10室以上を所有・貸出している場合に該当します。駐車場であれば、おおむね50台分以上が目安です。
事業的規模と認められると、青色事業専従者給与を経費にできるほか、除却損失や貸倒損失を全額経費にできるなどの税制上の優遇が拡大します。ただし、この基準はあくまで目安であり、規模や実態に応じて総合的に判断されます。判断が難しい場合は、税理士や税務署に相談するのがおすすめです。
青色申告を始める手続き
青色申告を行うには、まず税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。新たに不動産賃貸を始めた場合は、開業日から2か月以内が提出期限です。すでに白色申告をしている方が青色に切り替える場合は、その年の3月15日までに申請しましょう。
たとえば、2025年分から青色申告をしたい場合は、2025年3月15日が締切です。また、家族へ給与を支払う場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出も必要です。申請書は税務署の窓口または国税庁のホームページから入手できます。
提出後、承認通知が届けば、その年から青色申告を適用可能。不明点があれば、税務署や税理士に相談しながら進めると安心です。
不動産所得の節税対策と注意点

不動産所得の確定申告では、適切な節税対策を行うことで税負担を軽くすることが可能です。ただし、経費の扱いや書類管理を誤ると、税務調査の対象となるリスクもあります。
ポイントは、正しく申告しながら、抜けなく控除を活用すること。ここでは、経費計上の基本から損益通算、税務調査での注意点まで解説します。
必要経費にできるもの・できないもの
不動産所得の節税で最も重要なのが「経費計上」です。経費として認められるのは、家賃収入を得るために直接必要となる支出に限られます。代表的なものには、固定資産税・都市計画税・管理費・修繕費・火災保険料・減価償却費・借入金の利息・仲介手数料・広告宣伝費・共用部分の水道光熱費・通信費・交通費などがあります。
一方で、借入金の元本返済や所得税・住民税、自宅部分にかかる支出、私的な費用は経費に含められません。
また、修繕費の中でも注意が必要です。壁の塗り替えなど原状回復のための工事は修繕費ですが、耐震補強など資産価値を高める工事は「資本的支出」として減価償却の対象になります。判断が難しい場合は、早めに税理士へ相談しましょう。
赤字の繰越と損益通算
不動産経営で赤字が出た場合も、申告を行うことで節税につなげられます。赤字は給与所得や事業所得など他の所得と「損益通算」できるため、課税所得が減り、結果的に税金の負担を軽くできます。ただし、生活に通常必要でない資産(別荘など)の貸し付けによる所得の計算上生じた損失は、損益通算の対象外です。
たとえば、給与所得が500万円、不動産所得がマイナス100万円の場合、課税対象は400万円に減少します。ただし、土地取得のための借入金利息にかかる赤字はその赤字相当額が損益通算の対象外となるケースがあるため要注意です。
さらに、青色申告をしている場合は、通算後に残った赤字を最長3年間繰り越すことが可能です。これを「純損失の繰越控除」といい、翌年以降の黒字と相殺することで節税効果を得られます。空室や修繕費の増加などで一時的に赤字が出た年でも、上手に制度を活用することで将来的な税負担を抑えられます。
税務調査でチェックされやすい項目
税務調査では、不動産所得の収入や経費の計上が正しいかどうかが重点的に確認されます。
特に指摘を受けやすいのが、礼金や更新料の計上漏れ、家賃収入の計上時期の誤りといった「収入面のミス」です。さらに、自宅兼事務所での経費按分が適切か、修繕費と資本的支出の区分が正しいかもチェックされます。
大規模なリフォームをすべて修繕費として処理している場合、修正を求められることもあります。また、減価償却費の計算誤りや領収書の不備も指摘ポイントです。普段から領収書・契約書類の整理を徹底し、日々の収支を正確に記録しておくことが、税務調査への最善の備えといえるでしょう。
確定申告の提出方法と期限

確定申告は期限を守ることが何より大切です。遅れてしまうと加算税や延滞税などのペナルティが発生する可能性もあるため、あらかじめスケジュールを把握しておきましょう。
提出方法には、オンラインで完結できる「e-Tax」と紙による「書面提出」の2種類があり、自分の状況に合った方法を選ぶことで、申告作業をスムーズに進めることができます。
提出期間・期限・延滞リスク
確定申告の提出期間は毎年2月16日から3月15日までです。この期間内に、前年1月1日から12月31日までの所得を申告します。
たとえば2025年分の所得は、2026年2月16日〜3月15日が提出期間です。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課されることがあり、無申告加算税は本来の税額に50万円までは15%、50万円を超える部分は20%**(重加算の場合は35%または40%)が上乗せされます。
さらに、青色申告の承認が取り消される可能性もあるため注意が必要です。もしやむを得ず期限に間に合わない場合でも、できるだけ早く申告することで、ペナルティを最小限に抑えられます。
e-Taxと紙提出の違い
確定申告の方法には「e-Tax(電子申告)」と「紙による提出」があります。e-Taxは、国税庁のオンラインシステムを使って申告する方法で、自宅から24時間手続きが可能です。青色申告特別控除の上限が65万円に引き上げられるほか、還付金の振込も早くなるなど、多くのメリットがあります。利用にはマイナンバーカードとICカードリーダー、または対応スマートフォンが必要です。
紙による申告は、税務署への持参または郵送で行います。窓口提出はその場で確認してもらえる安心感がありますが、期間中は混雑します。郵送の場合は、消印日が提出日とみなされるため、余裕をもって投函しましょう。どちらの方法でも、申告書や提出控えは必ず保管しておきましょう。
税理士に依頼する場合のポイント
不動産所得の申告内容は、経費や減価償却の取り扱いなど複雑な点が多いため、専門家に依頼するのも有効な方法です。税理士に依頼することで、正確な計算や節税のアドバイスを受けられるほか、税務調査が入った際にも心強いサポートが得られます。
特に、事業的規模で複数物件を所有している方や、青色申告を初めて行う方にはおすすめです。依頼時は、不動産分野に詳しい税理士かどうか、報酬体系が明確かどうか、相談のしやすさなどを確認しましょう。
報酬の相場は年間数万円〜十数万円程度が一般的ですが、節税効果によって実質的なコスト負担が軽くなる場合もあります。最近は無料相談を実施している事務所も多いため、まずは気軽に問い合わせてみると良いでしょう。
まとめ|不動産所得の確定申告は正確&早めの準備がカギ
不動産所得の確定申告では、収入と経費を正確に整理し、自身に合った申告方法を選ぶことが重要です。青色申告を活用すれば特別控除や繰越控除などの優遇が受けられますが、帳簿作成や書類管理が求められます。
白色申告は簡易的な反面、節税効果は限定的です。固定資産税や管理費、修繕費、減価償却費などの必要経費をもれなく計上しつつ、判断に迷う項目は専門家へ相談するのが安心です。
申告期限は毎年3月15日。延滞税を避けるためにも、早めの準備を心がけましょう。e-Taxや申告ソフトを活用すれば、自宅でも効率的に手続きが進められます。不明点や不安なことがあれば、税務署や税理士に相談しながら、着実に進めていきましょう。
空き家や不動産管理にお悩みの方はアキサポにご相談を
確定申告をきっかけに、不動産所得の管理や活用方法を見直してみませんか?
アキサポでは、空き家の相談から売却、リノベーション、賃貸活用までをワンストップでサポートしています。
専門スタッフが不動産の現状に合わせた最適な活用プランをご提案。何から始めればいいかわからない……という方も、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。










