公開日:2025.09.12 更新日:2025.07.29
生前贈与をもっと活用する!制度・手続き・最新改正を徹底解説

「生前贈与は本当に節税になるの?」「贈与税が高くなる可能性は?」生前贈与にそんな疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。実際、生前贈与の仕組みや税制のルールを正しく理解していないまま贈与を行うと、思わぬ税負担が発生したり、相続時のトラブルに発展したりするケースもあります。
しかし、生前贈与をうまく活用すれば、相続税を節税できるだけでなく、家族の生活費を支援することも可能です。
そこでこの記事では、生前贈与の基本的な仕組みから、贈与税との関係、注意すべき落とし穴、そして改正後の最新動向までを分かりやすく解説します。
目次
生前贈与の概要

まずは生前贈与の定義や特徴を整理し、相続との違いや、制度を利用するうえで必ず押さえておきたい贈与税の基本的な仕組みについて解説します。
生前贈与の制度は、効果的に使うことで相続税の節税対策としても活用できます。財産を計画的に移動するためにも、制度の基本をしっかり理解しておきましょう。
生前贈与とは?
生前贈与とは、贈与者が生きているうちに、自分の「財産」を無償で譲る「贈与」を行うことを指します。この「財産」は経済的価値のあるものと定義されており、現金、預貯金、不動産、株式、有価証券などが対象になります。
本制度の特徴は、贈与者が誰に・どの財産を・いつ渡すかを自分の意思で決められることです。財産を移動させる自由度が高いので、計画的に財産を移しておけば、相続発生時の課税対象となる財産総額を減らし、相続税を軽減できる効果が見込めます。
ただし、贈与された財産は原則として贈与税の課税対象となります。それに伴って贈与税の申告や納税義務も発生しますので、その点は注意しましょう。
相続との違いは?
生前贈与と相続は、財産の移転時期や受け取り方、課税される税の算出方法などが違います。
まず相続は、被相続人が亡くなった時点で開始され、法定相続人に一括して財産が移転する仕組みです。税金は相続税法に基づいて算出され、遺産の総額から基礎控除額やその他の控除額などを差し引いた金額が課税対象となります。
一方、生前贈与は、贈与者が存命中に、贈与先・金額・時期を自らの判断で調整することができます。税金は贈与税法に基づいており、受け取った財産の合計額に対して、贈与者との関係に応じた税率で課税されます。税額を減らす制度には年間110万円の基礎控除や、生活費や教育費、住宅取得等資金の非課税措置などがあります。
押さえておきたい贈与税のしくみ
ここで贈与税の基本的なしくみと算出方法を理解しておきましょう。
まず贈与税の対象となるのは、1月1日から12月31日までの1年間に個人から受け取った財産の総額です。税率と対象額はそれぞれ以下のようになっています。
一般税率(兄弟姉妹や友人、第三者などの直系尊属以外からの贈与)
| 贈与を受けた額 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
| 税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
特例税率(直系尊属から18歳以上の子や孫への贈与)
| 贈与を受けた額 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
| 税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
たとえば、1年間で300万円の贈与を受けた場合は以下のように贈与税額が算出されます。
- 贈与額:300万円
- 基礎控除額:110万円
- 課税価格:190万円
- 税率:10%
- 贈与税額:190万円 × 10% = 19万円
生前贈与のメリット
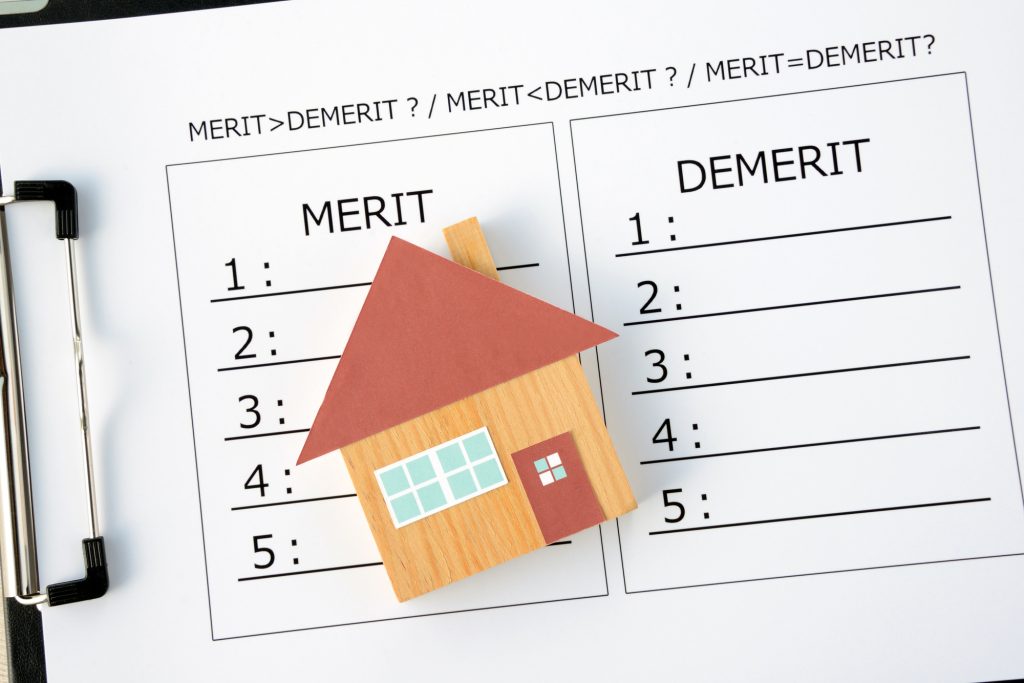
生前贈与は相続税の軽減や家族への資金援助といった多くのメリットがありますが、本人の老後資金が足りなくなったり親族間トラブルに発展したりするリスクもあるため、十分な計画と配慮のもとに行う必要があります。
ここでは、生前贈与を行うべきかを判断するための、生前贈与のメリットとリスクを整理して解説します。
なぜ相続税対策になるのか
生前贈与が相続税対策になる理由は、相続税の課税対象となる財産をあらかじめ減らすことができるためです。特に不動産や株式など、将来的に評価額が上昇すると見込まれる資産を早い段階で贈与しておけば、相続時点での課税評価額を抑える効果が期待できます。
また、贈与税には毎年110万円まで非課税となる基礎控除があるため、この枠を活用して数年かけて計画的に贈与を行うことで、課税リスクを分散することも可能です。
ただし、相続開始前7年以内に行われた贈与は、生前贈与加算(持ち戻し)として相続財産に加算されるので注意が必要です。
家族への財産移転メリット
子や孫に対して、家族のライフイベントに合わせた支援ができるのも生前贈与の大きなメリットです。のちほど詳しく解説しますが、子や孫の学費や結婚資金、住宅取得資金などを贈与する場合に、一定額までを非課税とする制度が用意されています。
また、贈与は贈与者の意志によって自由に相手や金額を決められるのも大きなメリットです。特に、多額の資産を持っている人にとっては、資産の承継に自分の価値観や想いを強く反映させられるので、相続に関する悩み事を減らせるのではないでしょうか。
生前贈与のやり方と注意点

実際の生前贈与の手続きは、ただ現金や資産を渡すだけではなく、贈与契約書の作成や贈与後の税務申告といった手続きも必要になります。そこで、ここでは、贈与の基本的な流れと、失敗を防ぐための注意点について紹介します。
贈与の基本的な流れ(贈与契約書・財産移転・申告)
生前贈与の基本的な流れは大きく分けて以下の3ステップで進めていきます。
- 贈与契約書の作成
- 財産の移転
- 税務申告書の作成
まずは贈与契約書を作るにあたって、贈与者と受贈者の間で「誰に・何を・いつ・どのように渡すか」を取り決めていきます。ここで贈与者の一存で決めてしまうとトラブルのもとになるので、法定相続人に保障された相続割合である遺留分の確保や、各法定相続人との間で合意形成をしてから進めていきます。
贈与の内容が決まったら贈与契約書を作成し、それに従って現金の振込や名義変更などを行い、実際に財産を移転させていきます。
贈与を行ったあとは贈与税の申告を忘れずに行いましょう。申告が必要なのは、贈与額が年間110万円の基礎控除額を超える場合です。申告期間は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。申告を忘れると税務署から指摘を受け、延滞税や加算税などのペナルティが発生することもあるため必ず期間内に行いましょう。
贈与契約書の重要性と作り方
贈与契約書を作るべき理由は、贈与を実際に行ったことや、贈与の金額や時期といった具体的な内容を証明できるためです。
贈与契約書を作成しなかった場合、あとから内容に食い違いが出たり、税務調査があった場合に根拠を示せなかったりと、さまざまなトラブルが起こる恐れがありますので必ず作成しておきましょう。
贈与契約書の作り方ですが、主な内容として贈与の日時、財産の内容、金額、贈与者と受贈者の氏名・住所などを記載し、双方が署名・押印します。形式的には自筆の書類で問題ありませんが、より確実性を持たせるなら、その文書の効力を公に証明する「公正証書」による方法も検討するとよいでしょう。
名義預金・定期贈与に関する留意点
贈与税を回避しながら生前贈与を進めるために、子の口座に積み立てを行ったり、基礎控除額の110万円以下の贈与を毎年行ったりする人は多いのではないでしょうか。じつは、これらは制度を理解して行わないと、思わぬリスクにつながる恐れがあります。
まず、子の口座に親が積み立てる行為は、口座の名義と実際の管理者が異なる預金である「名義預金」と呼ばれます。名義預金は贈与税の観点から対策がされており、名義預金は、形式的に子の口座であっても実質的に親が管理していると判断されると、相続税の対象となります。
また、毎年同じ時期に決まった金額を贈与している場合は、それが110万円以下であっても「定期贈与」とみなされて、贈与の総額に対して贈与税が課せられることがあります。対策としては、毎年贈与の時期や金額を変えたり、贈与を行うたびに贈与契約書を作成したりする方法があります。具体的な方法は、税の専門家である税理士に相談しながら進めましょう。
税負担軽減のために活用できる控除・非課税制度

ここでは、生前贈与の税負担を軽減するための特例制度を紹介します。
これらの制度を上手に活用すれば、より多くの財産を効率的に移転できますので、生前贈与を始める前に必ず把握しておきましょう。
暦年課税制度(年間110万円の基礎控除)
生前贈与でもっとも一般的なのが、年間110万円の基礎控除を活用する暦年課税制度です。
贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた総額に対して課税されますが、110万円までは贈与税がかかりません。そのため、複数年にわたって110万円以下の贈与を繰り返せば、税負担なしで生前贈与が行えます。
ここでの注意点は、先ほど紹介した定期贈与とみなされないよう注意することと、2023年12月31日までの贈与については相続開始前3年以内、2024年1月1日以降の贈与については相続開始前7年以内に行われた贈与は、相続財産に加算される仕組みになっていることです。先ほど紹介した定期贈与とみなされないよう注意することと、相続開始前3年以内に行われた贈与は、相続財産に加算される仕組みになっていることです。特に後者は、贈与者の意志でタイミングをコントロールできないので、節税効果を高めたい場合は早めの計画と継続的な活用がカギとなります。
相続時精算課税制度(2,500万円の特別控除)
大きな金額を一度に贈与したい場合に検討したいのが「相続時精算課税制度」です。
この制度では、60歳以上の直系尊属から18歳以上の子や孫への贈与に限って、累計2,500万円までの贈与が非課税となります。
ただし贈与税が免除された贈与は、制度名のとおり「相続時に精算」されるため、相続発生時に相続税の課税対象として再計算されます。
このとき、相続税の対象となる財産の額は贈与があった際の時価で算出されます。そのため、将来の資産価値の上昇が見込まれる不動産や株式などを早めに移転する際に有効です。
おしどり贈与(配偶者控除)
おしどり贈与(配偶者控除)とは、婚姻期間が20年以上の夫婦に限って、居住用不動産またはその取得資金の贈与について、2,000万円まで非課税で贈与ができる制度です。
この制度は、夫婦の老後の生活基盤を安定させるために設けられたもので、相続ではなく生前に財産を移す際に使われることが多いです。なお、この制度は同一の夫婦間で1回のみ使用できます。また、贈与した財産は必ず住宅の取得のために使用する必要があります。
教育資金・結婚・子育て資金の非課税制度
子どもや孫への支援として活用できるのが、「教育資金の一括贈与の非課税措置」や「結婚・子育て資金の贈与税非課税制度」です。 これらの制度を使えば、一定額までの学費や結婚式費用、子育て資金などを、一定の条件下で非課税で贈与できます。
ただし、制度の利用には金融機関を通じた専用口座の開設や、支出内容の証明書類の提出などが必要になります。手続きがやや複雑な分、計画的に利用すれば高い節税効果を得られますので、ライフイベントに合わせて検討してみてはいかがでしょうか。
税制改正のポイントと相続税への影響

ここからは、生前贈与や相続、贈与に関して近年改正されたことの中から、特に気を付けるべき「相続財産への加算期間の延長」をピックアップして紹介します。
これは、2023年まで相続財産に含める期間が3年だったのが、2024年から7年に改められたもので、制度を理解しておかないと正しい相続税対策ができない恐れがあります。ここでは、改正されたポイント、改正への備え、改正に対応するための相続税と贈与税の関係整理について解説します。
加算期間の延長で何が変わった?
現在の制度では「相続開始前7年以内」に行われた贈与については、その金額を相続財産に加算して相続税を計算しますが、じつはこの制度は、2023年末までは「相続開始前3年以内」が対象でした。
ちなみに、現在は制度改正直後ということで経過措置が取られており、2030年の12月31日までに開始する相続については、相続開始前7年以内ではなく、2024年の1月1日以降の贈与が対象となります。つまり改正後は、2030年まで段階的に加算対象期間が延長される仕組みとなっています。
暦年贈与の見直しにどう備える?
相続財産としての加算期間が3年から7年に延長されたことで、実質的に相続税対策ができる期間が4年間短くなったことになります。相続開始前7年以内の贈与は110万円以下であっても相続税の対象になるため、贈与で相続税対策をする場合は、以前よりも速やかかつ計画的に進める必要があります。
ただ、加算期間が延長されたとはいえ、すべての贈与が加算対象になるわけではありません。教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の贈与など、特定の目的に限定された非課税制度については、相続開始前7年以内であっても相続財産に加算されないので、計画的に活用すれば暦年贈与に頼らずとも高い節税効果が見込めます。
相続というと、まだまだ先のことに思えますが、相続税対策は子や孫が生まれた時点で始まっています。子や孫のライフステージの変化に合わせて、どう資産を移動していくか、家族で相談して決めておくとよいでしょう。
改正に対応するには相続税と贈与税の関係整理が大切
相続税と贈与税は別の制度ではありますが、財産の移転を課税対象とするという点で共通しているため、よく課税の根拠が「相続税か贈与税か」という話になります。そのため、財産を移転する際には、その行為がどちらの法律の範疇で、どの程度の税金がかかるかということを把握しておかねばなりません。
近年は税制改正の流れとして、贈与と相続を一体で管理しようという方向性が強まっており、制度のすき間を狙った短期的な節税対策は通用しづらくなっています。
そのため、改正後の制度を前提に、どの制度を使うか・どのタイミングで渡すか・誰にどう渡すかといった設計を、相続税と贈与税の両面から整理することが求められます。
単に「今贈与しておけば得かどうか」ではなく、「将来どのような課税関係が生じるか」を見据えて判断することが、制度改正後の資産承継ではより重要になっていくでしょう。
生前贈与で起こりやすいトラブルと予防策

最後に、生前贈与でありがちなトラブルと具体的な予防策を紹介します。誤った手続きや家族間での相談不足などが原因で、思わぬトラブルにつながることもありますので、あらかじめケーススタディで予防しておきましょう。
親族間の不公平感が争いの火種に
親族間でよく起こるのが、生前贈与の配分に納得できず、相続人の間に「不公平感」が生じてしまうケースです。
たとえば、長男にだけ住宅購入資金を援助したり、孫の教育資金を特定の家庭に集中して支援したりすると、他の家族が不満を抱く原因になります。このような状況が続くと、相続発生後に遺留分侵害請求のような法的トラブルに発展するおそれもあります。
これらのリスクを回避するには、贈与の内容や意図を文書化しておくことが大切です。また、必要に応じて遺言書の作成を検討しましょう。遺言書の書き方で悩んだ場合は、それぞれが専門とする法律に基づいた遺言書作成のサポートをしてくれる、弁護士、司法書士、税理士、行政書士の力を借りるとよいでしょう。
贈りすぎて老後資金が足りなくなる
贈与を行う際は、「自分の老後資金を圧迫しないか」という視点も忘れてはなりません。
相続税のことばかり考えて、まとまった金額を一度に渡してしまうと、医療費や介護費用といった予期せぬ支出が発生した場合に対応しきれなくなる可能性があります。
また、平均寿命が長くなっていることを受け、想定以上に長い老後が続くことも考慮すべきです。贈与を進める際は、まず自分の生活設計をしっかり立て、そのうえで余裕のある範囲で贈与額を決めていくのが安全です。
申告漏れや書類不備によるペナルティ
税制面で特に注意したいのが、贈与税の申告漏れや契約書の不備です。これらが発覚すると、追徴課税だけでなく、延滞税や加算税といった追加の負担が発生することがあります。
また、名義預金や定期贈与のように、実態の伴わない贈与は税務署から否認されやすく、相続時に問題になることもあります。相続税対策のための贈与を行う際には、あらかじめ税理士のような専門家に相談し、正しい対応方法を理解してから進めましょう。
いつでも相談できる税理士がいれば、制度改正があった際にも、その都度相談できるので安心です。
まとめ|生前贈与を安心して活用するために
今回紹介したように、生前贈与は上手く使いこなせば、相続税を大きく減らしたり、税負担を相続税と贈与税で割り振ったりと、財産の移動を手助けする効果があることが分かりました。
ただし、これらの効果を最大限発揮するには、必要な手続きを把握して、適切なタイミングで手続きを進めねばなりません。知らずに進めてしまうと、本来払わなくてもよい税金まで払うことになってしまいます。
大切なのは、贈与を計画的に進めることと、いつ・誰に・どのように贈与するかを明確にしておくことです。早めに全体の資産設計を始め、必要に応じて税理士などの専門家に相談しながら準備を進めていきましょう。
親が生きてるうちに名義変更はできる?贈与・相続との違いや手続き方法をわかりやすく解説
土地の名義変更|相続・売買・贈与・離婚ごとの手続きと費用を解説
実家リフォーム・リノベーションの費用はいくら?贈与税などの注意点
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。








