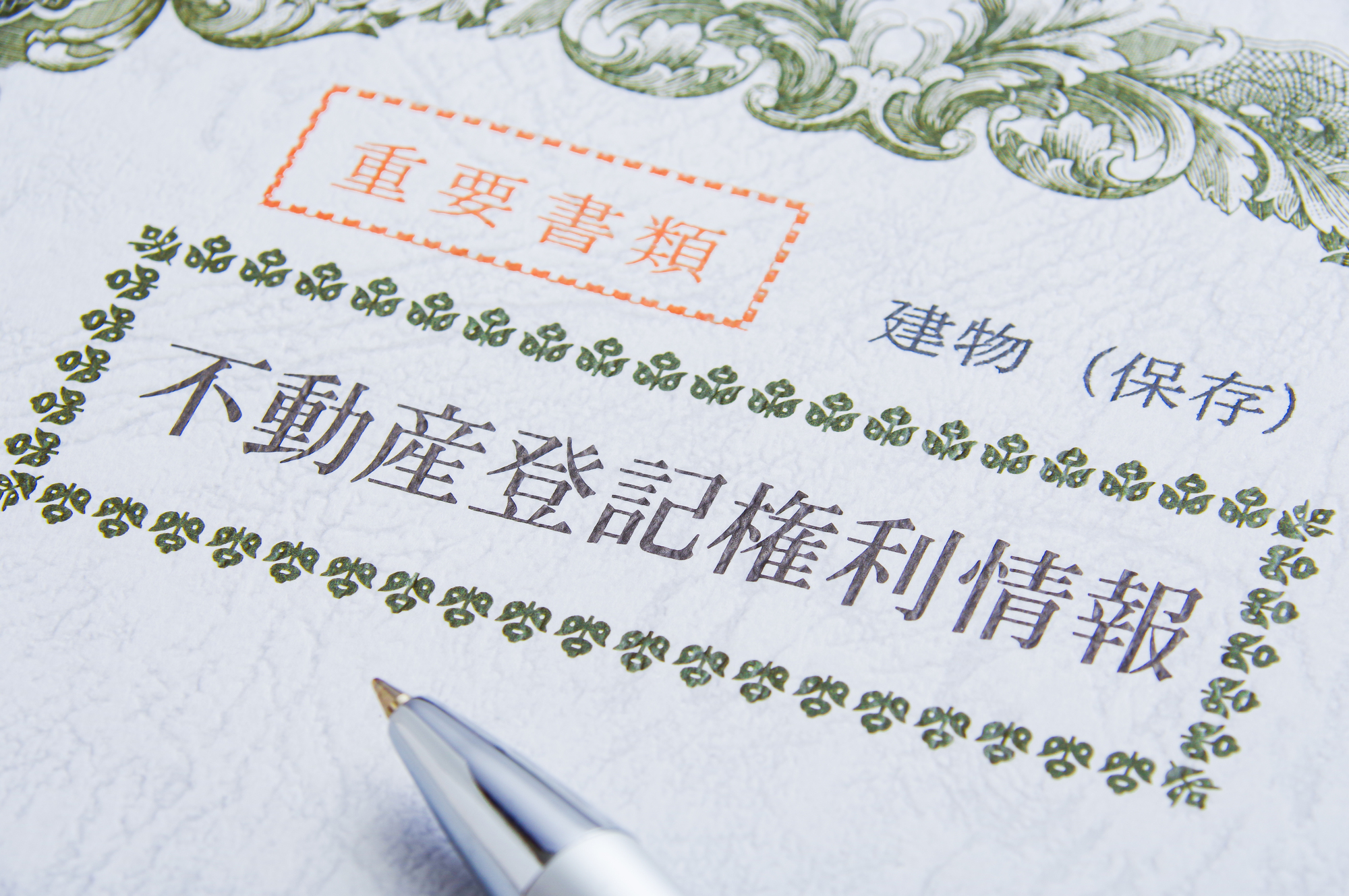公開日:2025.09.13 更新日:2025.07.29
土地の名義変更を何から始める?費用・必要書類・手続きの流れを徹底解説

相続や贈与で土地を受け継いだ場合には土地の名義変更が必要になります。しかし、具体的に何をすればいいのか、どこから始めればいいのか分からない人も多いでしょう。実際、土地の名義変更は専門的な用語や手続きが多く、不安を感じるのも無理はありません。
そこで本記事では、土地の名義変更に必要な書類・費用・手続きの流れを、はじめての方にもわかりやすく解説します。相続登記の義務化や税金のポイント、専門家に依頼すべきケースなどもカバーしているので、読み終えたときには「何から始めればいいか」が明確になっているはずです。
目次
土地の名義変更とは?放置リスクと義務化の流れ

土地の名義変更とは、不動産の所有者を変更するために行う法的な手続きです。名義を変更するには法務局で土地の権利の変更を登記する「所有権移転登記」の申請を行い、登記簿に新たな権利者の情報を登録する必要があります。
土地の名義変更が大切な理由は、土地の実態と名義を一致させるためです。ここが一致していないと、売却や担保設定ができなかったり、相続手続きが複雑化したりといった問題が生じます。
まずは、名義変更が必要となる代表的なケースと、2024年から始まった義務化制度について見ていきましょう。
名義変更が必要なケースとは?
土地の名義変更が必要なのは、何らかの原因により土地の所有者が変わるときです。実態と名義を一致させるために必ず名義変更をする必要があります。
代表的な例としては、親の死去による相続や夫婦間の贈与、離婚時の財産分与、第三者との売買などがあります。
ただ、実情として相続で土地を受け継いでも、利用するうえで特に支障がないことから名義変更を行わないケースも散見されます。登記簿を参照して、名義人が亡くなった両親や祖父母だった場合はこの可能性が高いです。
ただ、このようなケースは土地を売却したり、土地の筆を分けたりする際に支障になる可能性があります。そこで、2024年4月には、相続した土地の名義変更が義務化されました。次の見出しで詳しく見ていきましょう。
2024年からの義務化と罰則について
2024年4月に行われた相続による名義変更(相続登記)の義務化では、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をすること、そして正当な理由なく期限内に完了しなかった場合に最大10万円の過料が科されることが定められました。
今回の義務化は、すべての不動産を対象としており、登記が済んでいるかどうかに関わらず、相続によって名義が変わった土地すべてが対象となります。過去に相続したまま名義変更をしていない場合も、2024年4月1日以降に相続人がその事実を認識したタイミングから起算して、3年以内に登記を行う必要があります。
名義変更の進め方|自分でやる?専門家に頼む?

土地の名義変更は、司法書士のような専門家に依頼するだけでなく、自力で行うことも可能です。ただ、慣れない手続きがあったり、専門知識が必要だったりと、難しい点があるのも確かです。
そこでここでは、専門家に依頼するか自力で進めるかを判断するために、名義変更の基本的な流れや悩んだ場合のポイントを紹介します。
手続きの基本ステップ
名義変更の流れは大きく3ステップに分かれます。これは自分で手続きする場合も、専門家に依頼する場合も共通です。
- STEP1:必要書類の準備
相続や贈与など、原因に応じて必要な書類をそろえる。戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書など、役所や法務局で取得するものが多い - STEP2:登記原因を証明する書類の作成
遺産分割協議書や贈与契約書など、登記の根拠を示す書類を整える。法的効力を持たせるためには、署名や印鑑証明が必要になるケースもある - STEP3:法務局で登記申請
必要書類と申請書をまとめて法務局に提出する。申請後は内容の審査が行われ、問題がなければ数日〜数週間で名義変更が完了する
自分でやるか専門家に依頼するか悩んだら
自分でやるか司法書士のような専門家に依頼するか悩んだ場合は、手続きに必要な費用や時間、リスクを考慮して考えましょう。
たとえば、登記する土地が1筆だけで、法定相続人も1人という単純なケースであれば、自力で手続きしてもよいでしょう。
しかし、相続する土地が複数に分かれている場合や、地目や所在地がバラバラな場合は、それぞれに登記申請が必要になり、書類作成や添付資料の準備も多くなります。さらに、固定資産評価額ごとに手続きに必要な登録免許税を計算する必要もあるため、手続きの負担は一気に増えます。この場合は専門家に依頼した方が確実でしょう。
また、相続人が複数いるケースや、遺産分割協議が必要な場合、共有名義にするか単独名義にするか悩んだ場合など、法的・感情的な調整が求められることもあります。この場合も専門知識や経験が必要なる為、専門家に依頼した方がよいといえます。
必要書類と準備物|相続・贈与・離婚のケース別に解説

土地の名義変更では、手続きの原因によって求められる書類が異なります。この違いを把握していないと、せっかく書類を揃えても登記が受理されず差し戻しになるおそれがあります。
そこでここでは、代表的なケースである「相続」「贈与」「離婚」の必要書類を紹介します。
相続の場合に必要な書類
相続によって名義変更を行う場合は、まずは被相続人(亡くなった方)の戸籍一式を用意する必要があります。これは、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集めることで、相続関係を法的に証明するためです。
被相続人の戸籍が集まったら、次に「誰が相続人なのか」を明らかにするために、相続人全員の戸籍謄本や住民票を集めます。ここまでが終わったら、以下のような書類を揃えて申請を行います。
- 登記申請書(法務局所定の様式)
- 遺産分割協議書(遺産分割が法定相続分と異なる場合)
- 相続関係説明図(戸籍謄本等から作成)
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の住民票・印鑑証明書
- 固定資産税明細書
など
贈与・離婚など他のケースで必要な書類
まず贈与による名義変更では「贈与契約書」が必須です。これは贈与の意思と内容を明文化するためで、贈与契約書には日付・対象物件・当事者の署名捺印が必要です。合わせて、贈与者・受贈者それぞれの住民票や印鑑証明書も必要になります。
また、離婚に伴う財産分与による名義変更の場合は「財産分与協議書」などが必要です。これは夫婦間における土地の帰属に関する合意を文書にしたもので、登記原因を明確にするための根拠書類となります。離婚公正証書や調停調書でも代替できる場合があります。
また、その他にも以下のような書類が必要になることがあります。
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 双方の住民票
- 双方の印鑑証明書
土地の名義変更にかかる費用とその目安

土地の名義を変更するためには、専門家への依頼料だけでなく、法務局に払う手続き費用や必要書類の取得費用など、複数の費用が発生します。費用を理解していないと、費用が想定とずれてしまう恐れがあるので、あらかじめ全容を把握しておきましょう。
そこでここでは、土地の名義変更にかかる主な費用と目安、費用を抑える工夫について解説します。なお、各費用の詳細や節税制度については、別記事で詳しくまとめています。
登録免許税・書類取得費・司法書士報酬の目安
1.登録免許税(税金)
土地や建物の名義変更を法務局で登記する際にかかる税金です。相続の場合、税率は「不動産の固定資産税評価額 × 0.4%」で算出されます。
例:評価額が1,000万円の場合
1,000万円 × 0.4% = 4万円
また、贈与や売買などの場合は、相続と税率が異なり原則として2.0%になります。ただし、売買の場合は2026年3月31日まで、軽減税率により1.5%に軽減されます。
2.書類取得費
役所で戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書などを取得する際にかかる手数料です。1通あたり数百円〜1,000円程度で、必要通数によって総額は5,000〜1万円前後になることが多いです。
3.専門家に依頼する場合の報酬
司法書士のような専門家に手続きを依頼する場合の報酬です。相場は5万円〜15万円程度ですが、不動産の数や書類作成の範囲によって変動します。また、複雑な相続や共有名義の調整がある場合も高くなる場合があります。
名義変更の費用を抑える方法
名義変更にかかる費用をできるだけ抑えるには、以下のような方法を実践してみましょう。
- 書類は自分で集める
手続きに必要な書類を集めるところまで司法書士に依頼すると、書類取得代行の手数料がかかります。時間に余裕があれば、専門家に必要書類を聞いたうえで自分で書類を集めましょう。1万〜2万円ほどの節約が見込めます - 依頼する専門家を相見積もりで比較する
専門家を選ぶ際には、複数の事務所に見積もりを取り、料金体系やサービス内容を比較しましょう。追加料金が発生しないように、報酬の内訳が明確かもチェックしましょう - 免税制度を活用する
相続登記には、登録免許税の免除や軽減が受けられる特例制度があります。たとえば、相続による所有権の移転登記に係る登録免許税について、その土地の価額が100万円以下である場合の免税措置や、所有者不明土地の発生抑制を目的とした、相続人が複数いる場合の共有状態解消を促すための免税措置などが挙げられます。
名義の分け方と後悔しない選び方

土地の名義を決める際には、遺産分割の都合や次の相続時の負担など、意外と考慮すべき点が多くあります。土地の名義は一度決めると簡単には変えられないため、可能な限り最善の選択肢を選びたいところです。
そこでここでは、代表的な単独名義と共有名義のメリット・デメリットと、適しているケースについて説明します。
単独名義のメリット・デメリットと適しているケース
単独名義は、土地の所有権を1人にまとめる方法です。管理がしやすく、名義を変えたあとの活用や売却もしやすいです。
たとえば、売却を予定している土地や、誰か1人が居住・管理を続ける予定のある土地では、意思決定を一本化できるので向いているでしょう。また、税金や維持費もその人がまとめて負担することで、管理の責任が明確になるという特徴もあります。
ただし、相続で名義を変える場合は、他の相続人が納得していることが前提になります。不公平感が残らないように、全員の合意形成をしっかり行いましょう。
共有名義のメリット・デメリットと適しているケース
共有名義は、土地を複数人で共同所有する形です。全員で平等に所有権を持てるため、相続による名義変更では、相続人が多い場合でも不公平感が残りにくいです。
特に、すぐに土地を使う予定がなく、活用方針も未定の場合には、相続人全員で将来の方向性を家族で考える余地も残せます。
ただ、売却や建て替えの際には共有者全員の合意が必要になる点には注意が必要です。手続きや意思決定に時間がかかることはもちろん、名義人同士の関係が良好でないと合意形成が難しくなるリスクも伴います。
名義変更後の活用方法と次に考えるべきこと

最後に、相続で土地の名義変更をしたケースに焦点を当てて、名義変更後の次のアクションプランを紹介します。
名義変更の手続きが終わると、そこで安心する人も多いですが、実はここからが本当のスタートです。土地は維持するだけで固定資産税や維持管理費がかかるので、長期的視点に立って活用方法を考えていく必要があるのです。
代表的な手法には以下のようなものがあります。
- 売却して資金化する
- 賃貸や駐車場として活用する
- 自宅や事業用として建て替える
- 相続対策として次の世代に備える
また、活用の選択肢を選んだ場合には、次の相続への備えを忘れてはなりません。たとえば、土地から得られる収益を使うのか貯めておくのかを決める必要がありますし、複数人で共有している土地であれば将来的に単独所有に変えるかを相談しておく必要があります。
これらの話は時間が空いてしまうと人が集まらなくなったり、話し合いをするのが面倒になったりする恐れがあるので、名義変更をするタイミングで一緒にしておくとよいでしょう。すぐに方針が決まらない場合は、相談をする具体的な時期を決めておきましょう。
まとめ:土地の名義変更は早めに手続きして将来のトラブルを回避しよう
土地の名義変更は手間と時間がかかる手続きですが、ここできちんと整理しておけば、今後の相続や活用の場面で迷わず動ける土台を作ることができます。相続登記の義務化に伴って名義変更を先延ばしするリスクは高まっているので、できるだけ早急に手続きしておきましょう。
必要な書類や費用を把握し、どのタイミングで誰に相談するかを整理しておくだけでも、手続きはずっとスムーズになります。まずは手続きの流れを親族と共有し、今後について話し合ってみてはいかがでしょうか。
名義変更は、いま動くことで、未来の選択肢を広げられる手続きともいえます。この機会に、わが家の土地について一度見直してみてはいかがでしょうか。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。