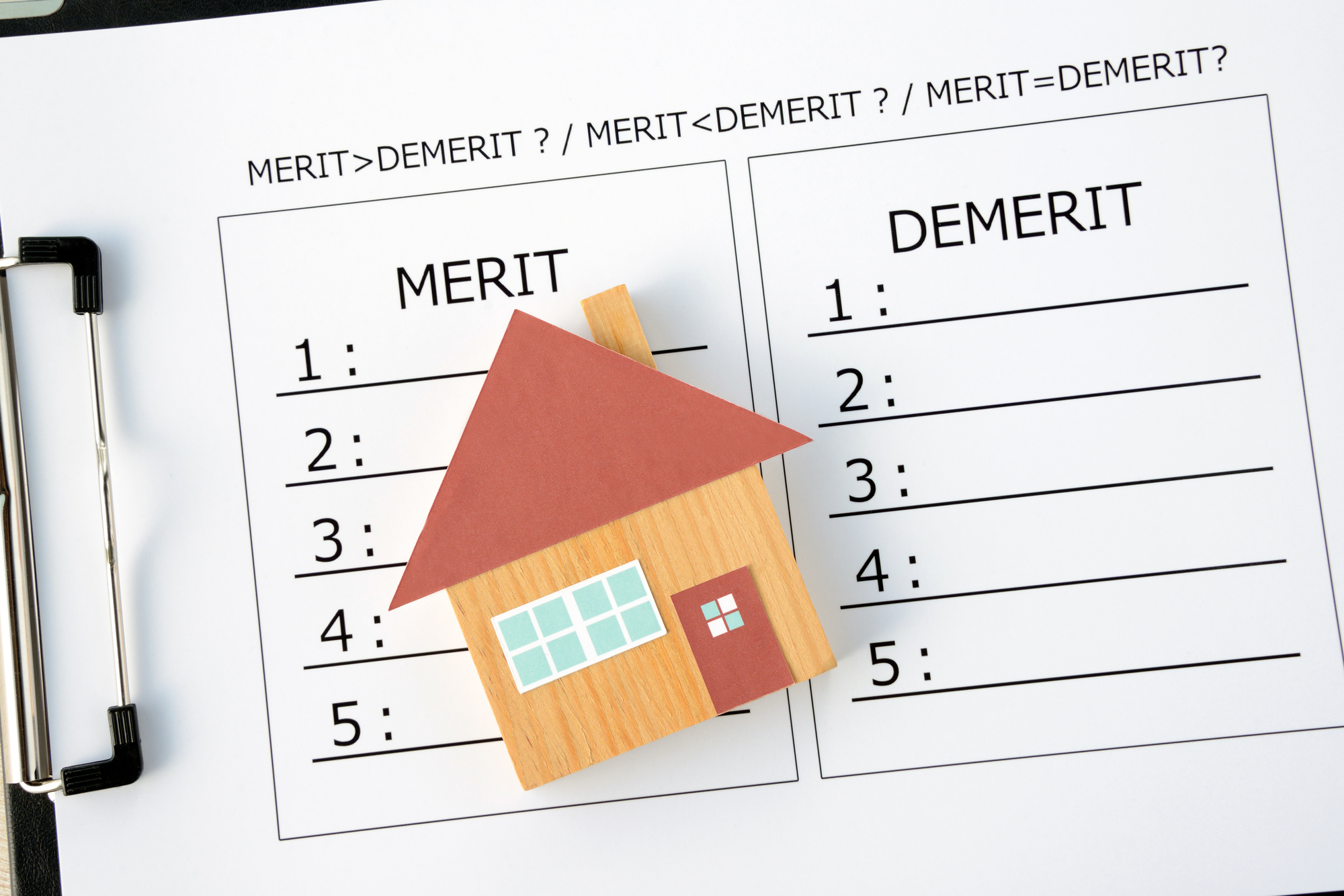公開日:2025.09.28 更新日:2025.08.12
市街化調整区域とは?定義・特徴・開発制限をわかりやすく解説

市街化調整区域は、都市の無秩序な拡大を防ぐために都市計画法に基づいて指定される区域であり、計画的な都市づくりを推進しつつ、自然環境や農地の保全を目的とした重要なエリアです。
本記事では、市街化調整区域の法律上の定義や主な特徴に加え、開発許可の要件、住宅の建築可否、制限がある中での土地活用方法まで幅広く解説します。
目次
市街化調整区域が設定される目的と背景

市街化調整区域がどのような経緯で、どんな目的をもって設定されているのかを解説します。
市街化調整区域は、都市計画法第7条第2項に基づき、市街化区域と明確に区分されて定められる区域です。主に、都市の過密化や無秩序な拡大を防ぎ、農地や自然環境といった地域資源を中長期的に保全することを目的としています。市街化調整区域内であっても、都市計画法改正以前は都市部から人が流入しやすい地域でも、無秩序に開発が進むと社会インフラの整備が追いつかず、住環境の悪化につながる懸念がありました。
その対策として、都市近郊の農地や山林などを守り、将来的な公共投資の効率化や都市機能の適正配置を図ることを目的に、市街化調整区域の設定が進められてきました。これは1970年の都市計画法施行により、「線引き制度」が導入されたことに起因しています。
さらに、各自治体では地元の産業や景観を維持するため、都市計画に基づく土地利用のコントロールや、地域に応じた都市マスタープランの策定が進められてきました。
都市計画法と区域区分の基本|市街化調整区域との関係を解説

市街化調整区域を正しく理解するためには、まず都市計画法や区域区分の基本的な仕組みを把握することが重要です。
都市計画法では、土地利用や都市づくりに関するルールが定められ、都市計画区域内を計画的かつ効率的に管理・運用するための制度が整備されています。これにより、無秩序な建築やインフラ整備の無駄を防止し、防災・安全性・住環境といった観点からも、持続可能なまちづくりが可能になります。
市街化調整区域もこの都市計画法の制度の一部であり、用途制限や開発行為に対する厳格な許可制度が設けられています。そのため、行政の許可がなければ、新たな建物の建築や開発行為は原則として認められません。
都市計画法とは?目的と概要
都市計画法は、1968年に制定された日本の都市づくりの基本法であり、土地の合理的な利用と秩序ある都市形成を目的としています。
その目的は、人口の集中や産業の集積に伴う生活環境の悪化を防ぎ、災害に強く、健康で文化的な都市環境の実現を図ることにあります(都市計画法第1条)。
市街化区域と市街化調整区域という区域区分もこの法律に基づいて設定され、開発行為に対しては原則許可制が導入されています。これにより、限られた社会資本や自然資源を適切に保全・活用することが可能になります。
市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域の違い
市街化区域は、すでに市街化が進んでおり、今後も優先的に都市的整備を進めるべき地域です。住宅・商業施設・インフラ整備などが計画的に行われる対象エリアです。
一方、市街化調整区域は、都市的な土地利用の拡大を抑制し、自然環境や農地の保全、農林水産業との共存が重視される区域です。
非線引き区域とは、市街化区域と市街化調整区域の明確な区分(いわゆる「線引き」)が行われていない区域で、主に中山間地域や人口密度の低いエリアが該当します。
この区域では、人口動態や地域事情を踏まえて、個別に開発の可否を判断する柔軟な運用が可能とされています。
市街化調整区域における開発許可の必要性と流れ

市街化調整区域内で開発行為を行うには、どのような許可が必要で、どのような流れで進めるのかを確認しましょう。
市街化調整区域では、原則として新たな開発が制限されていますが、都市計画法第34条に定められた一定の例外要件に該当する場合に限り、開発が認められるケースがあります。開発許可を取得するには、まず自治体窓口で対象地の状況や計画内容を確認し、開発行為に該当するかどうかの事前相談を行ったうえで、必要な書類を整えて正式な申請を行う必要があります。
審査の際には、周辺環境やインフラへの影響が少ないか、農地や自然環境の保護が適切に考慮されているかどうかが、重要な判断基準となります。
開発許可申請の手順と必要書類
開発許可申請の主な手順は、事前相談→申請書類の作成→提出→審査→許可の通知という流れです。提出先は、都道府県知事または権限が移譲されている場合には市町村長となります。
提出する書類には、敷地の位置図・計画図面・土地利用計画書・周辺関係者の同意書・農地転用許可書(該当する場合)などが含まれます。
申請から許可が下りるまでには、数週間から数ヶ月かかる場合があるため、工程には十分な余裕を持ってスケジュールを組むことが重要です。
専門家に依頼する場合の費用とメリット
開発許可の申請は、都市計画法・農地法・建築基準法など複数の法令にまたがることが多く、専門知識と実務経験が求められます。
そのため、行政書士や土地家屋調査士、測量士などの専門家に依頼するケースが一般的です。専門家に依頼することで、書類の不備や申請内容の不整合による手戻りを防げるほか、行政との協議もスムーズに進むというメリットがあります。
費用は案件によりますが、数十万円程度かかることがあり、規模や内容によってはさらに高額になることもあります。 それでも、時間と労力、リスクを総合的に考えると、専門家に任せる価値は十分にあるといえるでしょう。
市街化調整区域で住宅は建てられる?建築条件と注意点

制限の多い市街化調整区域でも、一定の条件を満たせば住宅を新築できるケースがあります。
市街化調整区域内で住宅を新築するには、その建築行為が都市計画法第43条に定められた例外規定のいずれかに該当している必要があります。※ただし、開発区域外における建築行為の場合。たとえば、地域に長年居住している親から子への分家住宅(いわゆる分家住宅)や、農業従事者がその業務のために建てる住宅などが、認められる代表的なケースです。
また、配置や用途、既存集落との一体性、周辺環境との調和といった細かい基準を満たすことが前提となります。
ただし、市街化調整区域は開発を抑制する区域であるため、インフラ(上下水道・電気・ガス・道路など)が十分に整備されていない地域も多く、注意が必要です。そのため、水道の引き込みや排水処理の方法、接道義務の確認といったインフラ周りの調査・計画が、建築費用や工期に大きく影響します。
行政との事前協議をしっかり行い、費用や法的リスクも踏まえたうえで、慎重に判断することが重要です。
建て替え・増改築に際して押さえるべき要件

市街化調整区域内であっても、都市計画法による「線引き」が行われる前、もしくは合法的な許可を得て建てられた既存住宅については、一定の条件を満たせば建て替えや増改築が可能とされています。
この場合、原則として新たな開発許可は不要とされますが、建築行為の内容によっては例外もあるため、慎重な判断が求められます。特に、用途や構造、延べ床面積などに大きな変更が加わる場合や、農地転用を伴う場合は、開発許可や農地法に基づく手続きが別途必要になる可能性があります。
また、建て替えや増改築の対象となるのは「適法な既存建築物」が前提です。無許可建築や違反建築の場合、そもそも建て替えや増改築が認められないケースもあるため注意が必要です。取り扱いは自治体ごとに異なる場合があるため、都市計画担当部署や建築指導課などに事前相談を行い、法令や条例に基づいた正確な情報を得た上で、計画を立てることが重要です。
市街化調整区域の土地活用アイデア
宅地以外にも多彩な活用方法がある、市街化調整区域の土地。ここでは、具体的な活用アイデアと実現に向けたポイントを紹介します。
市街化調整区域の土地は、住宅用地としての制限が厳しい一方で、地域の自然や広い敷地を活かした非住宅用途での活用には柔軟性があり、法令に基づく開発許可を得れば実現可能なケースもあります。
特に、大規模開発とは異なり、比較的環境負荷の小さい用途や地域に貢献する目的であれば、許可が得やすい場合があります。
利用目的によっては、地域資源を活かした観光や地場産業との連携を図るなど、まちづくりに資する形での活用も期待できます。
駐車場・資材置き場などシンプル活用
駐車場や資材置き場としての活用は、建築物を伴わないケースが多く、比較的ハードルが低い点がメリットです。特に農作業に伴う一時的な資材置き場や、地元住民の車両保管用の月極駐車場などは、地域貢献型の活用として前向きに評価されることもあります。
とはいえ、舗装を伴う場合や長期使用となる場合には、土地の形質変更や雨水排水計画に関する申請が必要になることがあり、自治体の規制や届出制度を事前に確認することが重要です。
太陽光発電や墓地利用など特殊用途
太陽光発電施設の設置は、発電設備を設置するために行う土地の形質の変更が開発行為とみなされる場合があり、一定条件下で許可される例も見られます。
ただし、発電規模が大きい場合や傾斜地・景観保全区域に設置する場合には、環境アセスメントや住民説明会が求められるケースもあります。墓地としての活用も一つの選択肢であり、衛生上の配慮や周辺住民の理解、さらには墓地埋葬等に関する法律(墓埋法)に基づく許可が必要です。
許可要件をクリアすれば、長期的に安定運用できる事業として検討に値する活用方法といえるでしょう。
市街化調整区域の売却と購入時に確認すべきポイント
市街化調整区域の土地を売却・購入する際には、法的な制限や周辺環境を踏まえたうえで、慎重な確認と説明が求められます。
市街化調整区域の土地は、市街化を抑制するエリアとして位置づけられているため、一般的に建築や開発が制限されており、その分地価は市街化区域よりも低めに設定されることが多いです。
その一方で、利用可能な範囲が限られるため、需要も限定的になる傾向があります。購入を検討する際は、まずその土地がどのような条件下で開発可能かを自治体に確認し、都市計画法・農地法などの関連法令に基づく許可や届出の要否を把握することが重要です。
あわせて、造成費用やインフラ(上下水道・電気など)の整備状況、必要となる行政手続きにかかる時間・コストなども事前に確認しておくべきです。
売却する場合には、地目や建物の有無、現況、道路との接道状況、上下水道やガス等の整備状況など、購入希望者が把握すべき情報を整理し、明確に説明できるようにしておくことがトラブル防止につながります。
また、仲介業者に依頼する際は、市街化調整区域に精通した不動産業者を選ぶことで、誤った案内や取引リスクを回避しやすくなります。
インフラ整備と住環境における課題

市街化調整区域では、水道・下水道・ガス・電気などのライフラインが十分に整備されていないケースが多く、住環境面でのリスクを事前に把握することが重要です。
上下水道やガスといったインフラ設備は、市街化区域に比べて整備の優先順位が低いため、未整備のままの地域も多く存在します。新たにこれらのインフラを引き込む場合、自治体の予算だけでは対応が難しく、土地所有者が費用の一部または全額を負担するケースもあり、数十万円〜数百万円のコストが発生する可能性があります。
さらに、商業施設・医療機関・学校などの生活利便施設が近隣に少なく、公共交通機関のアクセスも限定的であることが一般的です。このため、自家用車が前提の生活になりやすく、特に高齢者や子育て世帯にとっては不便さが生活の質に直結する懸念があります。
市街化調整区域のメリット・デメリット
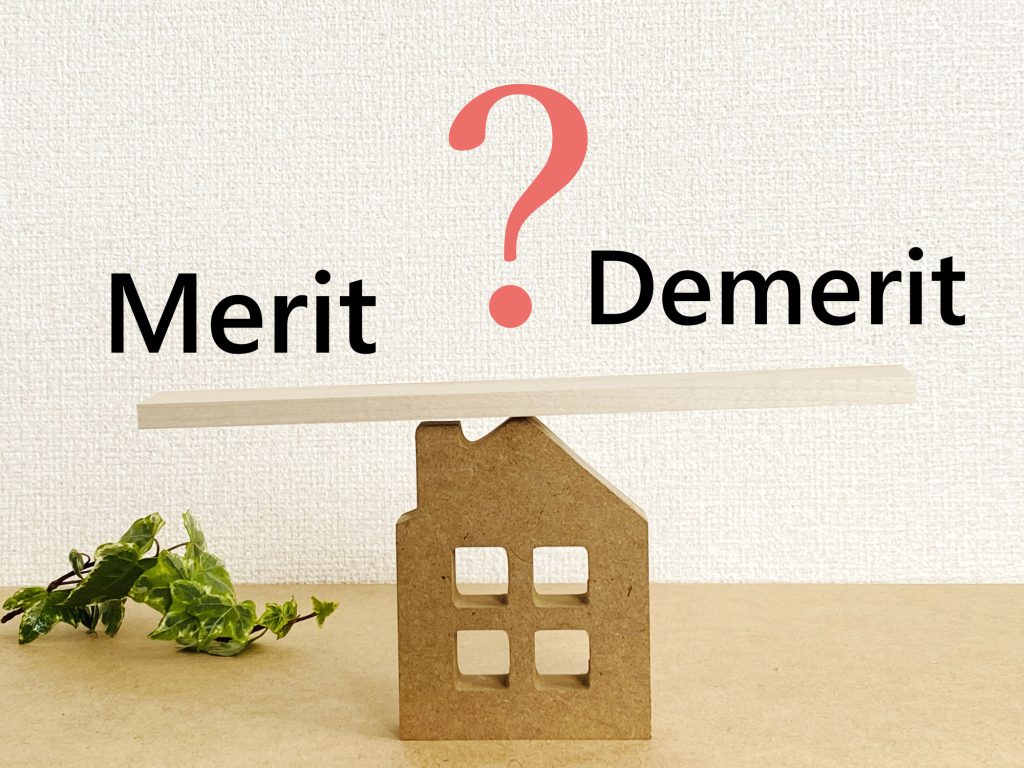
市街化調整区域は、厳しい開発制限がある一方で、自然や土地本来の特性を活かした暮らしが可能であるという利点も存在します。
ここでは、代表的なメリット・デメリットを整理し、活用の方向性を考えてみましょう。
メリット:
・土地取得価格が比較的安価であることが多く、初期費用を抑えられる可能性がある
・豊かな自然や農地に囲まれた、静かで落ち着いた生活環境が得られる
・騒音や高層建築が少なく、プライベート空間を確保しやすい
デメリット:
・住宅や施設の新築・建て替えには都市計画法上の許可が必要で、手続きに時間とコストがかかる
・上下水道や道路といったインフラ整備が不十分で、整備費用が自己負担となる可能性がある
・商業施設・公共交通の利用が制限されることで、資産価値の流動性(=転売のしやすさ)に不安が残る
購入や移住を検討する際には、自身のライフスタイルや将来の生活設計に照らして、想定される用途が本当に実現できるのかを事前に十分に検証し、
「住めるか」だけでなく「住み続けられるか」という長期的視点で判断することが不可欠です。
まとめ・総括
最後に、本記事で紹介してきた市街化調整区域の特徴や、土地の活用・売買において重要となるポイントを総括します。
市街化調整区域は、都市の無秩序な拡大を防ぎ、農地や自然環境を保全するために都市計画法に基づいて設定されたエリアであり、将来的な持続可能なまちづくりに寄与する役割を担っています。
その一方で、開発や建築行為には厳格な制限があり、原則として許可が必要となるため、事前の確認と専門知識が不可欠です。
しかし、都市計画法第34条の特例に該当するなど、一定の条件を満たせば住宅の新築や建て替えも可能です。また、住宅以外にも、資材置き場・駐車場・太陽光発電・墓地など、用途を限定した土地活用であれば許可が得られるケースもあり、柔軟な運用が可能です。
重要なのは、自身のライフスタイルや事業目的に応じて、どのような活用が可能かを自治体に確認し、必要な許認可の内容・インフラ整備状況・費用面までを総合的に把握したうえで判断することです。市街化調整区域の土地は、制限が多いからこそ、活用に成功すれば大きな価値を生む可能性があります。
本記事を通じて、法制度・実務・リスク・可能性の全体像を理解し、将来にわたって後悔しない土地活用を検討する一助となれば幸いです。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。