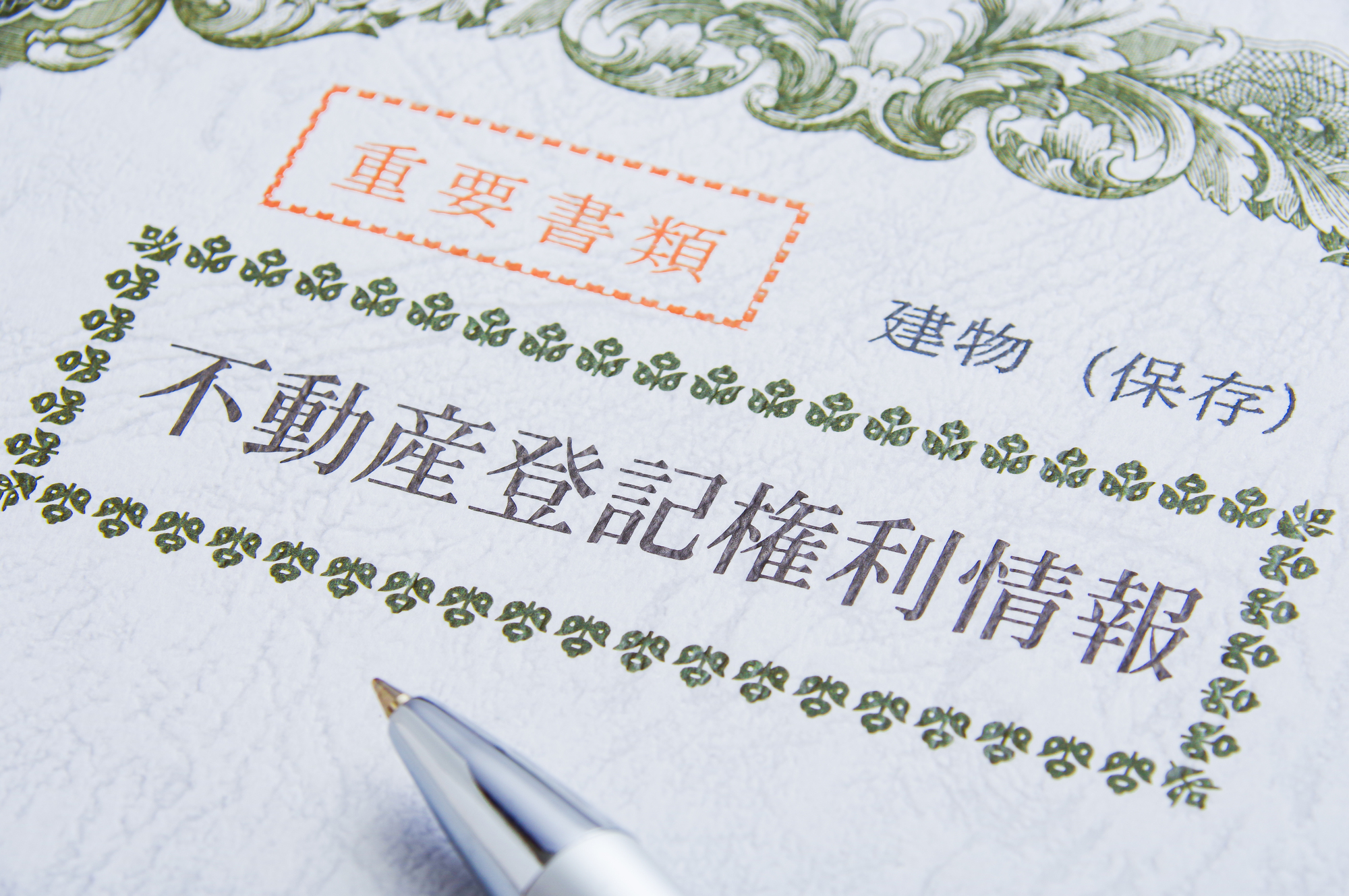公開日:2025.10.04 更新日:2025.10.07
不動産登記とは?基礎知識から手続き・費用・必要書類まで
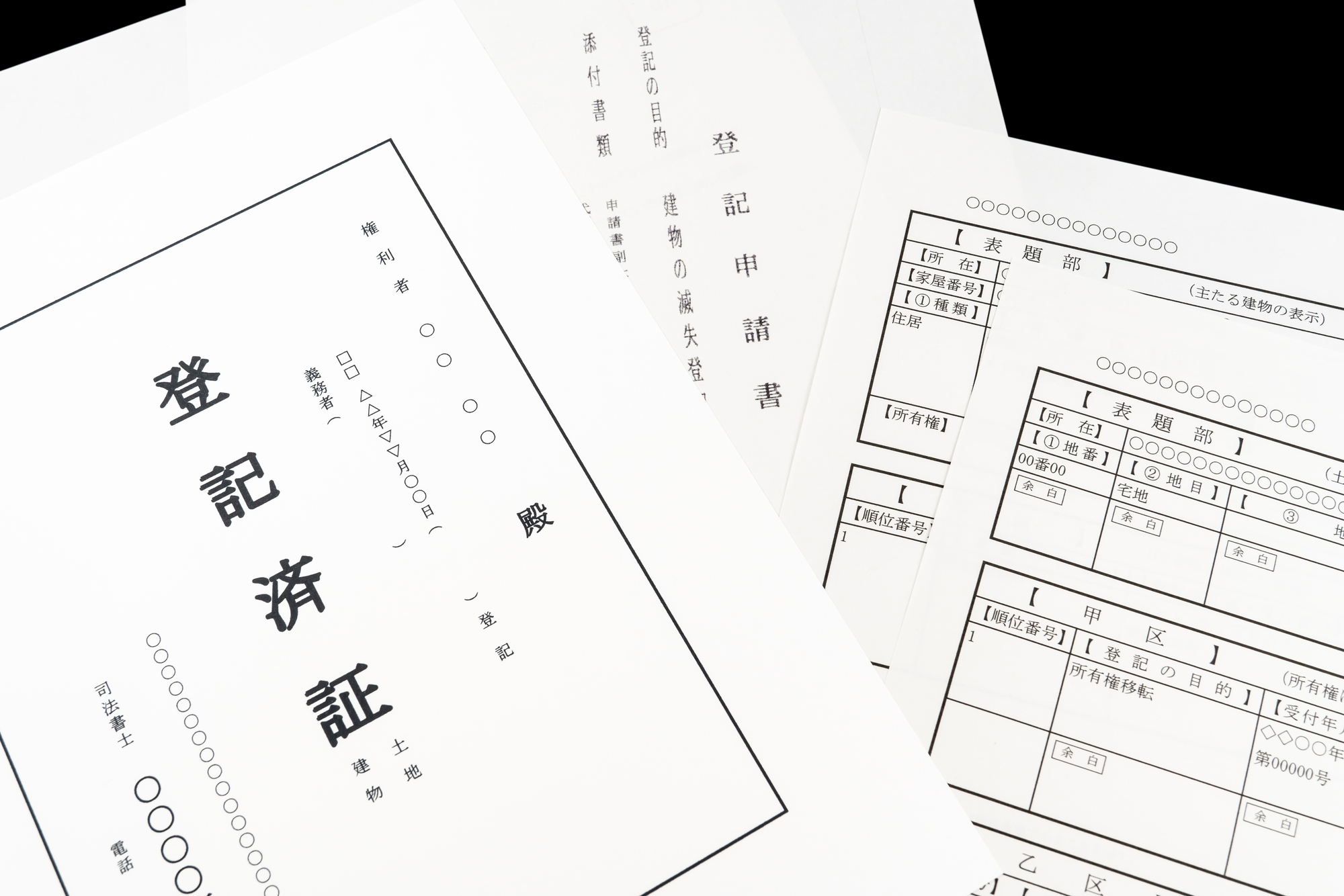
不動産登記は、土地や建物の所有者や権利関係を公的に示す重要な手続きです。しかし、具体的にどのような手続きが必要なのか、登記をしないとどうなるのかなど、その詳細まで理解している方は少ないのではないでしょうか?
不動産登記の仕組みを正しく理解しないまま手続きを進めると、取引の安全性や将来の資産管理に大きな影響を及ぼす可能性があります。そのため、手続きを始める前に制度の基礎をしっかりと学ぶことが大切です。
そこでこの記事では、不動産登記の基本的な仕組みから手続きの流れ、必要書類や費用の目安までを整理しました。初めての方でも理解できる内容にまとめていますので、これから不動産取引や相続を控えている方は参考にしてください。
目次
不動産登記の目的と重要性:なぜ登記が必要なのか?
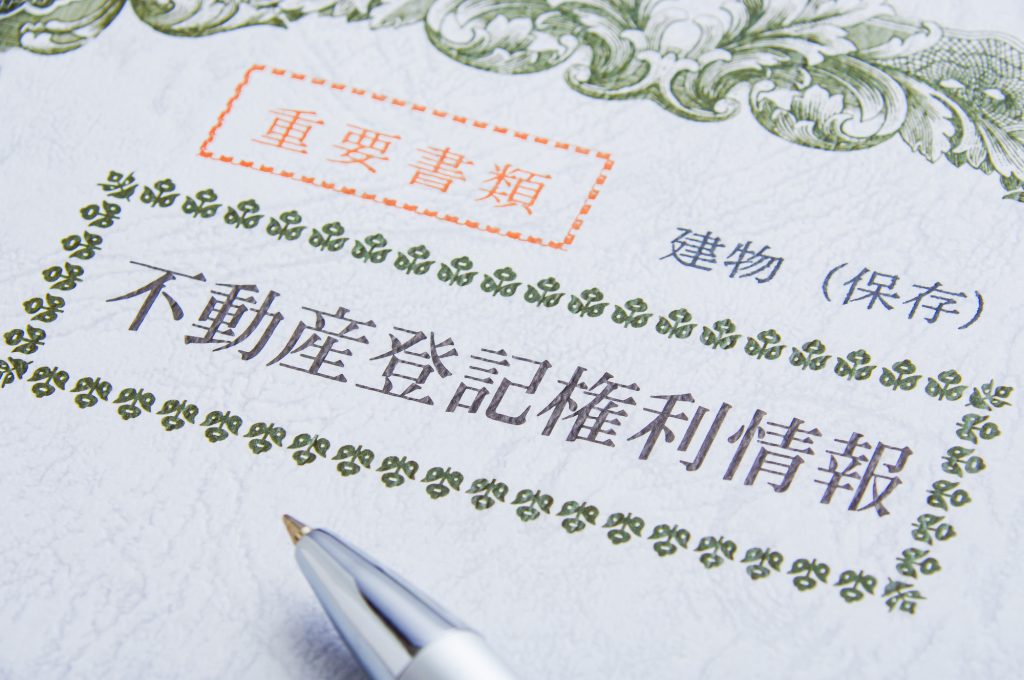
不動産登記とは、土地や建物の所在地・面積・構造といった物理的な情報や、所有者・抵当権などの権利関係を法務局が管理する「登記事項証明書」に登録し、公的に管理する制度です。
登記制度の最大の目的は、権利関係の公示にあります。不動産は、土地の所有者や権利関係を外から判断することができません。そのため、登記事項証明書という形で情報を公的に記録・管理し、第三者が確認できるようにする制度が必要になるのです。
これにより、公に不動産の権利者が明らかとなり、所有者が不動産の権利を主張することができるようになります。ひいては、売買や相続、担保設定などの場面におけるトラブルを未然に防ぐことにも繋がります。
不動産登記の仕組みと法的根拠
不動産登記は、法務省が管轄する全国の法務局によって一元的に管理されています。各不動産の情報は登記事項証明書に記録されており、所在地や面積、所有者、抵当権の有無などの情報が記録されています。
登記を行うには、原則として本人または代理人(司法書士など)が申請し、必要書類を添えて法務局に提出する必要があります。申請内容に不備がなければ、法務局での審査を経て登記事項証明書に正式に反映され、登記完了の通知が交付されます。この手続きを終えて初めて、その権利を第三者に対抗できるようになります。
なお、不動産登記制度は「不動産登記法」に基づいて運用されます。同法では、登記の種類や申請方法、登記官の職務などが定められており、全国一律のルールに基づいて制度が運用されています。
表題登記と権利登記の違い
登記はその性質によって「表題登記」と「権利登記」に分けられます。
まず表題登記は、土地や建物の所在地や地番、面積、構造など、目に見える物理的な情報を登録するものです。新築や増改築をした際に行われるこの登記は、不動産そのものの輪郭を明らかにする役割を担っており、手続きは主に土地家屋調査士が担当します。
一方の権利登記は、所有権や抵当権など、不動産に関する権利関係を記録する登記です。「誰が所有者か」「どの金融機関が担保権を持つか」といった法律上の関係を明確にし、その手続きは主に司法書士が担当します。
不動産登記の種類と費用

不動産登記は主に以下の6種類があります。
- 所有権保存登記
- 所有権移転登記
- 抵当権設定登記
- 相続登記
- 住所・氏名変更登記
- 滅失登記
いずれも不動産に関する権利を登記する手続きですが、それぞれ目的やタイミング、登記の内容は異なります。ここでは、それぞれの手続きの目的や用途、費用などを見ていきましょう。
所有権保存登記
所有権保存登記は、土地を分筆した場合や建物を新築した場合など、その不動産に対して初めて所有権を登記する手続きです。例えば自宅を新築した場合には、まず表題登記を行い、その後に所有権保存登記を行うことで、正式に「この建物は自分のものだ」と主張できるようになります。
この登記によって所有者としての地位が法的に確定し、今後の売買や担保設定、相続などに必要となる前提が整います。なお、保存登記をしないでいると、悪意のある第三者に勝手に移転登記されてしまうリスクもあるため、早めに手続きを行いましょう。
所有権保存登記の費用
- 固定資産税評価額の0.4%(個人が、自己居住用の住宅用家屋を新築または取得した場合は0.15%/2027年3月31日まで)
所有権移転登記
不動産を売買・贈与・相続などで取得した際に、所有者の名義を変更する手続きです。不動産を購入した場合、契約後にこの登記を行うことで初めて買主の権利が法的に認められます。
この登記を怠ると、第三者に先に登記されてしまうリスクや、金融機関からの融資審査で不利になるリスクなどがあります。不動産を取得した場合は、速やかに名義を変更して権利を保護しましょう。
所有権移転登記の費用
- 売買:評価額の2.0%(個人が、自己居住用に購入した場合は0.3%/2027年3月31日まで)
- 贈与・交換・収用など:評価額の2.0%
抵当権設定登記
抵当権設定登記は、不動産を担保に住宅ローンや事業融資を受ける際に、その不動産が担保になっていることを明らかにするための登記です。これにより、万が一返済が滞った場合でも、金融機関は不動産を売却して債権を回収できるようになります。
融資を受けた側は、返済が順調に進めば特に影響はありませんが、ローンの返済が滞った場合には、資金回収のために不動産が競売にかけられる可能性が出てきます。ただ、住宅ローンを借りる際には抵当権の設定がほぼ必須なので、あらかじめ無理のない返済プランを組んで融資を受けましょう。
抵当権設定登記の費用
- 債権額の0.4%(住宅ローンの場合は0.1%)
なお、ローンを完済した後は、抵当権抹消登記が可能となり、担保としての縛りが解除されて自由な売却や活用が可能になります。
相続登記
相続登記は、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産を相続する人に所有権を移す手続きで、2024年4月から義務化されています。手続きを行うには、被相続人(亡くなった人)の戸籍から、すべての相続人を明らかにし、法律に基づく権利の確認や相続人同士の協議を行い、正式に相続する人が決定する必要があります。
相続人が少ない場合や、関係が良好で遺産分割協議がスムーズに進む場合は、新たな所有者が速やかに決定することが多いですが、一方で相続人が多い場合や関係が複雑な場合は、遺産分割協議が難航し、所有者がなかなか決まらないケースも少なくありません。
手続きの期間は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内で、相続人たちで協議が行われている場合は、遺産分割協議が成立した日から3年以内です。
相続登記の費用
- 評価額の0.4%
住所・氏名変更登記
住所・氏名変更登記は、登記名義人の氏名や住所が変わった場合に、登記内容を修正する手続きです。たとえば、結婚や離婚、引っ越しがあった場合などに必要になります。
この登記は任意のため見落とされがちですが、登記事項証明書上の住所・氏名と住民票・戸籍謄本の内容が一致しないと、売却時や相続時に所有者本人であることを証明できず、手続きが滞る可能性があります。優先度は他の登記手続きより低いですが、期間が経つと忘れがちなので、なるべく早めに手続きしておきましょう。
滅失登記
滅失登記は、建物が取り壊された際に、その建物が現存しないことを登記事項証明書に反映させるための手続きです。滅失登記を行うことで、登記事項証明書からその建物に関する情報が削除され、以後の不動産取引や登記における誤認やトラブルを防ぐことができます。
滅失登記を申請するには、所有者が法務局に申請します。この際に、建物の解体を証明する書類(建物取壊証明書など)を添付する必要があります。また、土地家屋調査士による現地調査が必要となるケースもあります。
不動産登記簿の構成と見方
出典:法務省
登記をした内容が記載されている不動産登記簿は、大きく以下の4つの項目で構成されています。
- 表題部
- 権利部(甲区)
- 権利部(乙区)
- 共同担保目録
ここでは、それぞれの項目にどのような情報が記載されているのかを見ていきましょう。
表題部:不動産そのものの情報を記録
一番上の表題部には、土地や建物の物理的な情報が記載されています。例えば、土地であれば所在地、地番、地目(宅地・田・山林など)、地積(面積)などが、建物であれば所在地、家屋番号、構造、床面積などが表示されます。
権利部(甲区):所有権に関する情報を記録
権利部の甲区には、その不動産の所有者や、その所有者が取得した原因や取得日などが記載されています。
例えば、取得した原因としては、売買や相続、贈与などが記され、取得日の項目には、移転日や登記申請日なども明記されています。そのため、この欄を読み解くことで、所有権の変遷を時系列で追うことができるようになっています。
権利部(乙区):抵当権や賃借権など、所有権以外の権利を記録
権利部の乙区には、抵当権・地上権・賃借権などの、所有権以外の権利に関する情報が記録されています。例えば、住宅ローンの担保として設定された抵当権や、土地を借りている場合の賃借権などが該当し、権利の所有者の氏名・住所・債権額・設定日なども明示されます。
共同担保目録:複数の物件にかかる担保関係を一覧で確認
共同担保目録の欄は、1つの抵当権が複数の不動産にまたがって設定されている場合に作成されます。 たとえば、同じローンで複数の土地や建物を担保に入れている場合は、それぞれの登記事項証明書に「共同担保目録番号」として一覧がリンクされるため、担保関係の全体像を把握しやすくなります。
不動産登記の流れ

不動産登記の基本的な流れは以下のとおりです。
- 必要書類の準備
住民票・戸籍謄本・売買契約書・委任状など、必要な書類を用意する。登記の種類によって必要書類は異なる - 登記申請書の作成
法務局指定の書式に、物件情報・登記原因・申請人情報・日付などを記入する - 法務局への提出
完成した申請書類一式を、物件所在地を管轄する法務局へ提出する - 登記官による審査・処理
法務局の登記官が書類を審査し、問題がなければ登記事項証明書に情報が反映される。不備がある場合は修正を求める補正通知が送られてくる - 登記完了の通知
審査が終わると、申請人に対して「登記完了証」や「登記識別情報通知書(権利証のようなもの)」が交付される
なお、登記手続きを行う際には、必ずすべての内容を正確に記入してください。誤った内容で登録してしまうと、登記による効力が正しく発揮されない恐れがあります。
オンライン申請の場合
登記の申請をインターネットから行う場合は「申請用総合ソフト」という、登記・供託オンライン申請システムのホームページからダウンロードしたソフトを利用して申請情報を用意し、必要な添付情報と一緒に、登記・供託オンライン申請システムに送信する必要があります。
オンライン登記申請の手続きの流れは以下のとおりです。
- 申請情報の作成
- 添付情報の作成
- 申請情報及び添付情報の送信
- 登録免許税の納付(電子納付・現金納付・印紙納付)
- 登記識別情報の通知及び登記が完了したことが通知される
なお、内容に不備や誤りがある場合は、原則としてその申請は却下されます。ただし、補正できる範囲のものであった場合は、補正で対応する場合もあります。
なお、オンライン登記申請をするには、あらかじめマイナンバーカードなどを用いた電子証明書が必須になります。
【まとめ】不動産登記は「大切な資産を守る」ための必須手続き
不動産登記は、資産を守り、安全に取引を進めるための基盤を整える手続きです。登記を後回しにすれば、売却や相続の場面でスムーズに進められなかったり、思わぬトラブルに巻き込まれたりする可能性もあるため、「まだ大丈夫」と先延ばしにせず、必要なときは速やかに済ませるように心がけましょう。
もし手続きが複雑で不安な場合や、専門家に依頼すべきか迷っている場合は、自治体が行っている司法書士の無料相談会を利用したり、法務局に相談したりするのがよいでしょう。ここで得た知識を次の行動に移すことが、大切な資産を守ることにつながります。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。