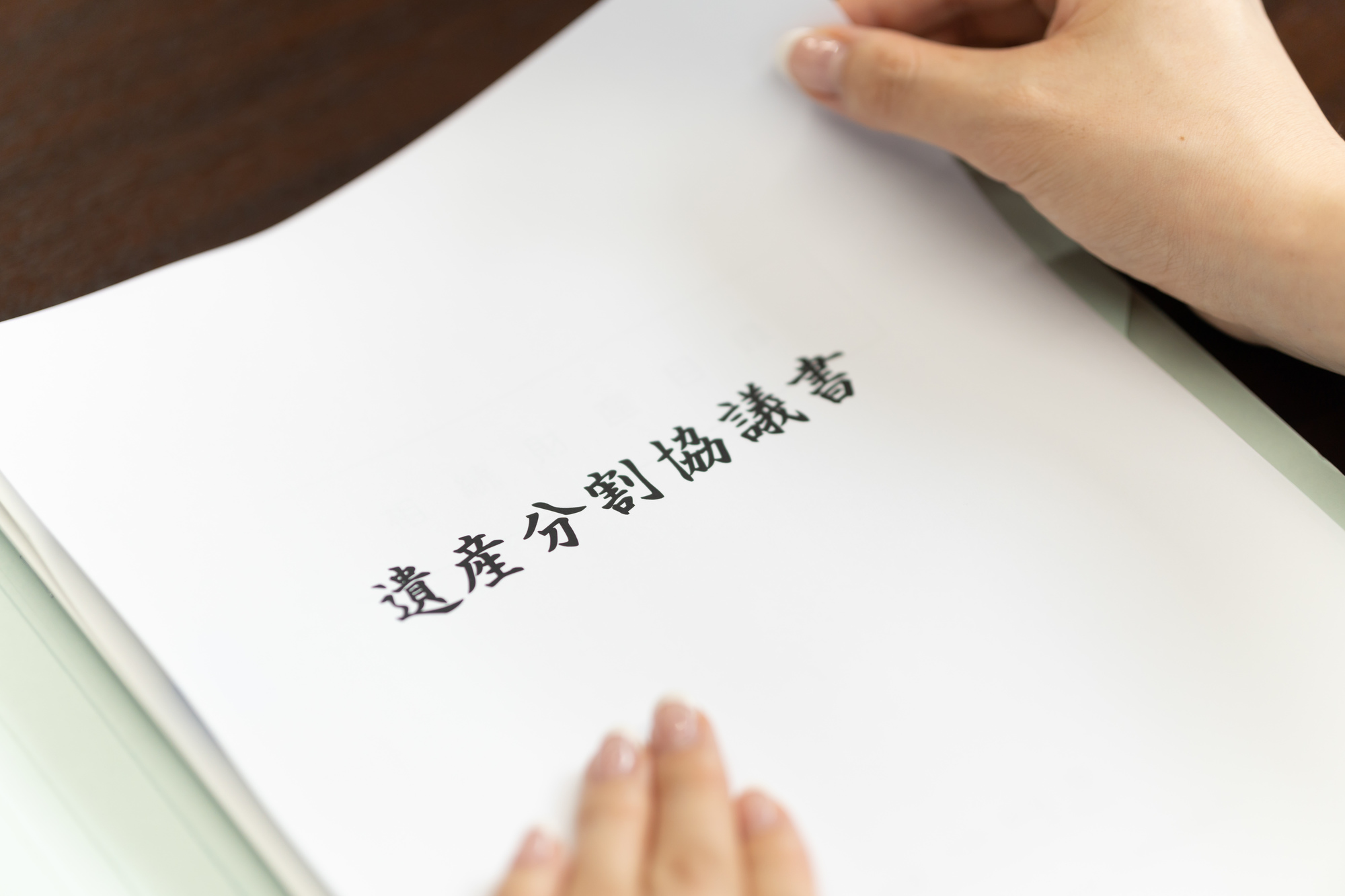公開日:2025.11.03 更新日:2025.10.27
【相続放棄のすべて】期限・手続きの流れ・必要書類を解説
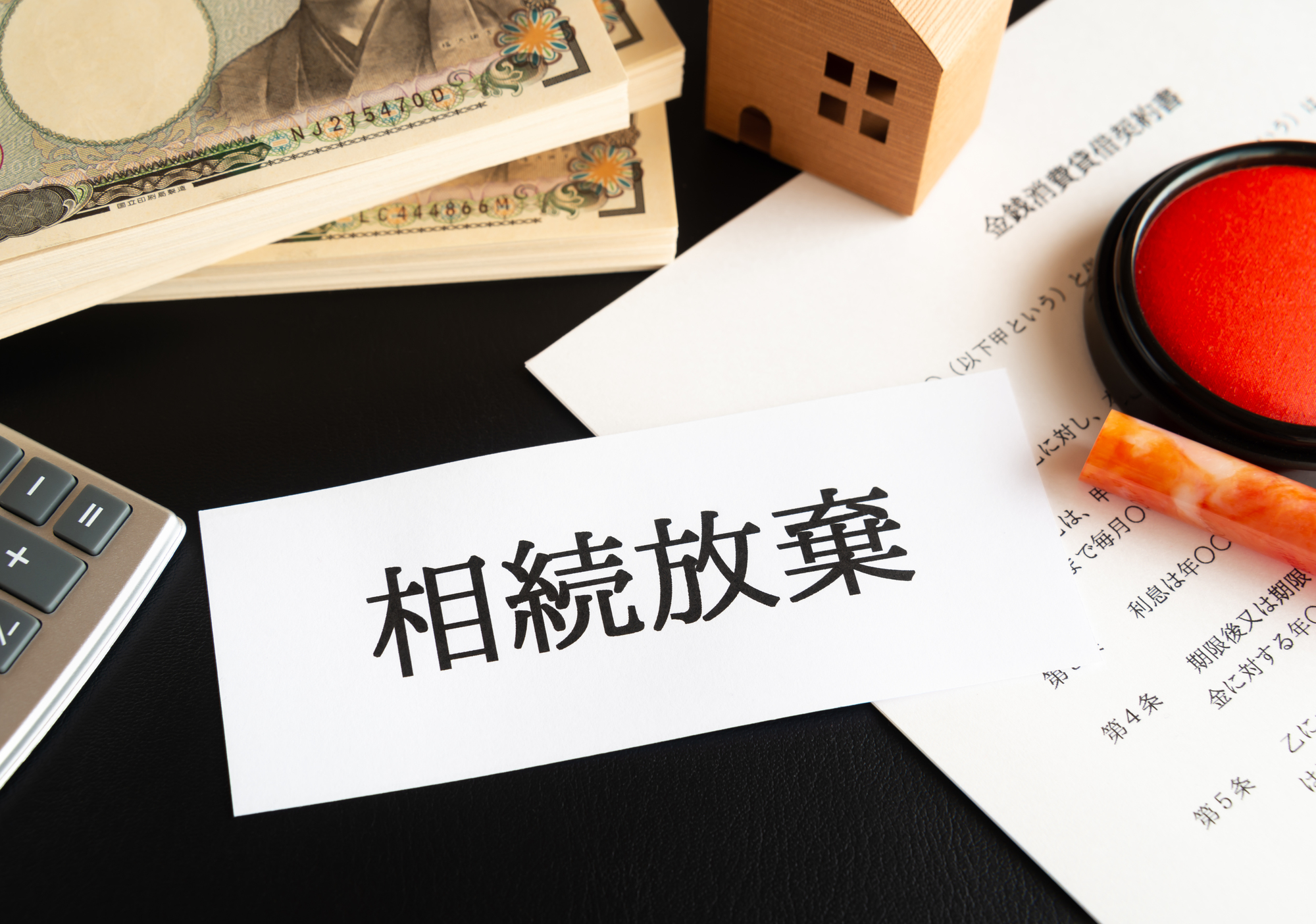
相続放棄は、被相続人の残した財産や負債を一切受け継がない手続きです。一般的には借金を抱えた場合や煩雑な相続争いを避けたい場合に検討されますが、その手続きや注意点を知らずに進めると、後で思わぬトラブルが発生することもあります。
本記事では、相続放棄を検討すべきケースからメリット・デメリット、そして具体的な手続きの進め方までを網羅的に解説し、失敗しないためのポイントをまとめました。相続放棄をする前に押さえておくべき要点を確認し、スムーズに対応できるようにしましょう。
目次
相続放棄とは?基礎知識と単純承認・限定承認との違い

まずは相続放棄の基本的な概要と、誤解されがちなポイントを整理しておきましょう。
相続放棄は、相続人が被相続人の財産や負債を一切引き継がないと宣言する手続きのこと。家族が多額の借金を残していたり、複雑な不動産問題を抱えている場合などに検討されることが一般的です。
相続放棄で注意すべき点のひとつが、単純承認や限定承認との混同。単純承認は全ての資産と負債をそのまま受け継ぐ行為であり、限定承認は相続した財産の範囲内で負債を弁済する制度です。対して相続放棄は、被相続人の正の財産も負債も完全に放棄するため、手続き後の取り扱いが大きく異なります。
また、相続放棄は手続き後に撤回することが原則できない点も重要です。実行タイミングや書類不備、期限の見落としなどで後からトラブルになるケースもあるため、相続放棄を視野に入れる場合は、まずはこうした基礎知識をしっかり押さえましょう。
相続放棄を検討すべきケース|借金・不動産など

前述した通り、相続放棄は借金や複雑な不動産問題を抱える場合に多く検討されます。
まず、被相続人が住宅ローンや消費者金融などの借金を抱えていた場合、単純承認するとそのまま負債まで引き継ぐことになり、相続人自身に返済義務が生じてしまいます。負債の総額や返済能力を十分に考慮したうえで、相続放棄をするかどうか慎重に判断しなくてはなりません。
そして、相続する空き家が遠方にあり管理が難しい場合や、固定資産税を継続して支払う余裕がないといった不動産問題がある状況でも、相続放棄によって将来的な負担を避けられる可能性があります。ただし不動産以外のプラスの財産がある場合、それらも同時に放棄することになる点には注意が必要です。
借金・不動産絡みの問題以外では、親族間の過度な争いが想定される場合にも相続放棄は有効となることがあります。相続放棄を行うことで、財産分配の協議に参加しなくて済む場合もあるため、人間関係のもつれを未然に防ぐことにつながるでしょう。とはいえ、相続放棄を行うことで自分の権利を完全に失うことになるので、すべての事情を踏まえて慎重に判断する必要があります。
相続放棄のメリット・デメリット
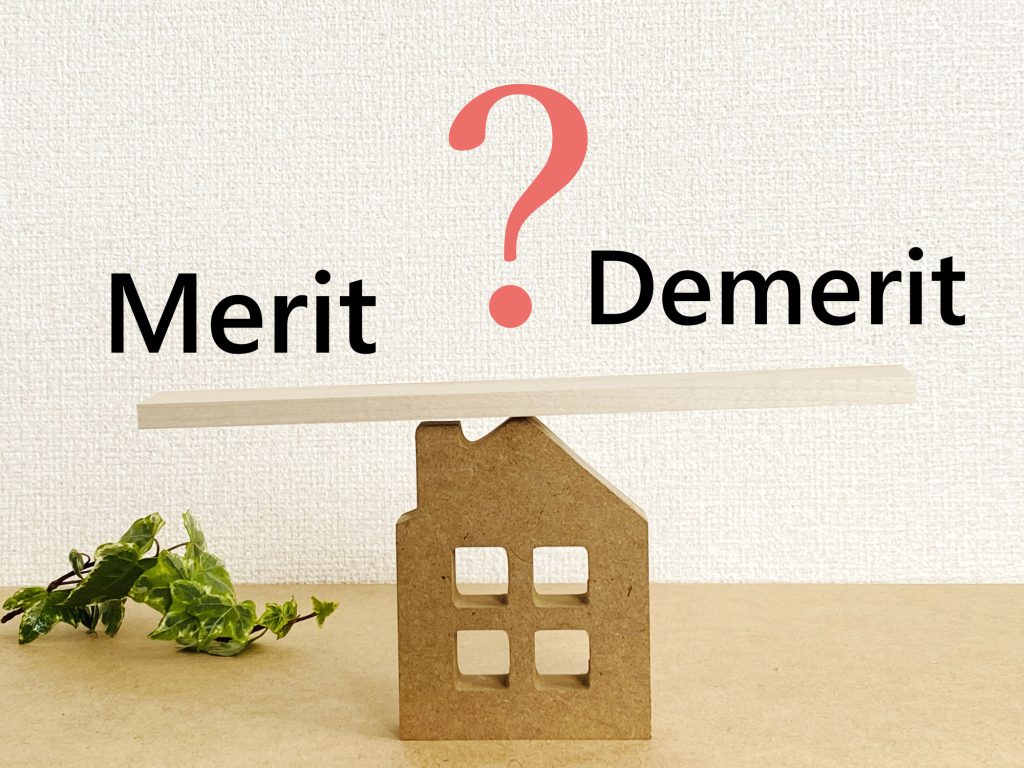
相続放棄には負債リスクを回避できる反面、相続権をすべて失うリスクが存在するのも事実です。ここでは相続放棄のメリット・デメリットについて解説します。
メリット:負債リスクの回避と相続争いの防止
相続放棄は、多額の負債を抱えている場合には特に強力な手段として機能します。また、相続人間での争いが激化しそうな場合でも、相続放棄をすることで論争から離脱し、精神的にも安定した判断を下しやすくなる点もメリットです。
デメリット:相続権を完全に失うリスクに注意
一方、相続放棄を行うと被相続人のプラスの財産も取得できなくなるため、得られるはずの利益を失う可能性があります。しかも、一度相続放棄をしてしまうと原則撤回が認められません。財産の全容を把握し切れないまま放棄を決めることは、予期せぬ損失につながる可能性があり、慎重に判断することが必要です。
相続放棄の期限と延期申立|3カ月以内の手続きが基本

相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3カ月以内に家庭裁判所へ行うのが原則です。これは被相続人の死亡時点ではなく、あくまで自分が相続人となったことを認識した日から計算される点に留意しましょう。期限を過ぎてしまうと相続放棄が認められず、結果として単純承認を選んだのと同じ状態になる恐れがあります。
ただし、相続財産の把握に時間を要するなど、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に対して期限の延長を申立てることが可能です。延長が認められるためには、正当な理由が必要であり、適切な書類の提出や整理が求められます。期限管理を誤ると、後からどれだけ事情を説明しても相続放棄ができなくなるリスクがあることを心得ておきましょう。
延長を申請する方法と注意点
延長の申請は家庭裁判所へ所定の書類を提出し、延長を希望する合理的な理由を示すことで受理が検討されます。具体的には、相続財産の複雑さや相続人間の連絡不足などを挙げるケースが多いですが、すべてが認められるわけではありません。申請が却下された場合は通常の3カ月期限で手続きを行わなければならないため、なるべく早期に行動を起こすようにしましょう。
相続放棄の手続きの流れ|家庭裁判所への申述と必要書類

実際に相続放棄を行う場合の大まかな手順や、必要となる書類などをまとめました。
必要書類の一覧と取得方法
相続放棄の手続きは、まず家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することから始まります。申述書には被相続人と申述人(相続人)の情報や放棄を希望する理由などを記載し、あわせて必要書類を提出。必要な種類は、主に以下が挙げられます。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 など
書類に不備があると修正や追加提出が求められるため、情報を正確に整えておくことがポイントです。書類は市区町村役場や法定相続情報証明制度を活用して取得することが多く、想定より時間がかかるケースもあるため早めに準備しておきましょう。
照会書への回答から相続放棄申述受理通知書が届くまで
家庭裁判所は提出された書類をもとに審査を行い、不明点がある場合は「照会書」を送付してくることがあります。照会書には必要事項を記入して期限内に返送する必要があり、記入漏れや誤記があると手続きがさらに延びるケースもあります。
書類の内容に問題がなければ、最終的に相続放棄申述受理通知書が送付され、正式に相続放棄の手続きが完了します。
相続放棄の注意点|法定単純承認とみなされる行為

相続放棄の検討段階で財産を処分したり利用したりすると、民法上の「法定単純承認」とみなされ、放棄の権利を失います。たとえば不動産の一部を賃貸に出したり、預貯金を引き出したりしてしまうと、後から相続放棄を主張することは原則できません。特に家財道具や自動車など、日常生活でどうしても利用が避けられないものについては注意が必要です。判断に迷う場合は、手続きを済ませるまでは財産に触れず、必要最低限の管理にとどめるようにしましょう。
相続放棄をしても受け取れるもの・受け取れないもの

相続放棄をしても、受取人が明確に指定されている生命保険金は、相続財産ではなく受取人の固有の財産とみなされます。保険会社の約款や契約内容によって取り扱いが異なることもあるため、早めに確認しておきましょう。なお、税法上はみなし相続財産として取り扱われることもあるため、税務面での手続きを忘れずに行う必要があります。
一方で、預貯金や不動産など被相続人名義で保有されていた資産は、相続放棄を選択すると受け取れなくなります。マイナスの財産だけでなくプラスの財産も同時に手放すことになるため、慎重に判断するようにしましょう。
生命保険金や未支給年金の扱い
生命保険金は、受取人が被保険者とは別の独立した権利を得る性質があり、相続放棄を行っても受け取り可能とされる場合があります。ただし、契約内容によっては保険金が相続財産とみなされるケースもあるため、確認が必要です。未支給年金に関しては、受給事由や受取資格者の状況によって扱いが変わるため、専門家に相談しながら適切に対応しましょう。
相続放棄後に残る管理義務|不動産やお墓の扱い

相続放棄をしたからといって、即座にすべての財産管理責任から解放されるわけではありません。民法上は相続財産に対して一時的な管理義務が発生し、特に不動産や動産を放置して他人に損害を与えないよう注意する必要があります。実際、相続人がいない不動産の処分は自治体でも大きな課題となっており、相続放棄後であっても適切な手続きを踏むことが望まれます。
また、お墓や仏壇などの祭祀財産については、相続放棄をしても民法第897条に基づき相続財産とは別個に承継されるため、放棄の対象外となります。別途、慣習により祭祀承継者を定めることが一般的です。ただし、実際には親族内でも誰が所有・管理を続けるのか揉めることがあるため、事前に合意形成を行ったり専門家の助言を得ておいたりするとよいでしょう。
専門家(弁護士・司法書士)に依頼するメリット・費用

複雑な相続放棄の手続きをスムーズに進めるには専門家への依頼が有効です。書類作成や提出先の確認など専門的なノウハウを活用できるため、ミスやトラブルの発生リスクを大幅に減らすことができます。特に相続人が複数いたり、被相続人の財産状況が複雑な場合には専門家の助力が心強いでしょう。
費用については、司法書士より弁護士のほうが一般的に高額となる傾向がありますが、その分、相続人間での紛争対応や裁判手続きに強いというメリットがあります。書類作成や裁判所への提出、法的なアドバイスが主な目的であれば司法書士で十分対応できるケースがほとんどです。複数の専門家から見積もりを取り、費用とサービス内容を比較検討したうえで依頼先を決定すると良いでしょう。
「アキサポ」でも、相続に関するサポートを実施しています。各専門家と連携しながら、相続周りのに手続きはもちろん、相続した空き家の活用や売却についてのご相談も承っているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
よくある質問(FAQ)

実際に寄せられる質問を紹介しつつ対処法を見ていきましょう。
Q.期限内に手続きが間に合わなくても、どうにかなる?
A.基本的には3カ月を過ぎると相続放棄の手続きは認められませんが、正当な理由がある場合は延長が認められる可能性もあります。
ただし、いずれにしても事情を早めに家庭裁判所や専門家に相談することが必須です。
Q.手続きの途中で遺産をうっかり処分してしまったけど大丈夫?
A.相続承認とみなされるリスクがあります。
手続きの途中で遺産を使用したり処分したりして、相続放棄が認められなくなるという事例は後を絶ちません。こうした事態を避けるためにも、相続放棄の手続きに取りかかる前から慎重な行動を心がけるようにしましょう。
まとめ・総括|相続放棄で後悔しないためのポイント
相続放棄は多額の借金や複雑な不動産問題などを回避できる一方、プラスの財産も同時に放棄することになる点が大きな特徴です。後から「やっぱり相続しておけばよかった」と後悔しないためは、早期の情報収集と専門家への相談がポイントになります。
費用はかかるものの、正確な手続きとトラブルの回避を考えれば、結果的に安心を得られるケースがほとんどです。自身や家族の将来を見据え、メリット・デメリットを踏まえた上で適切な選択をするようにしましょう。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。