公開日:2025.11.15 更新日:2025.10.29
【投資用不動産の始め方】初心者が失敗しないための基礎知識・メリット・デメリット・選び方
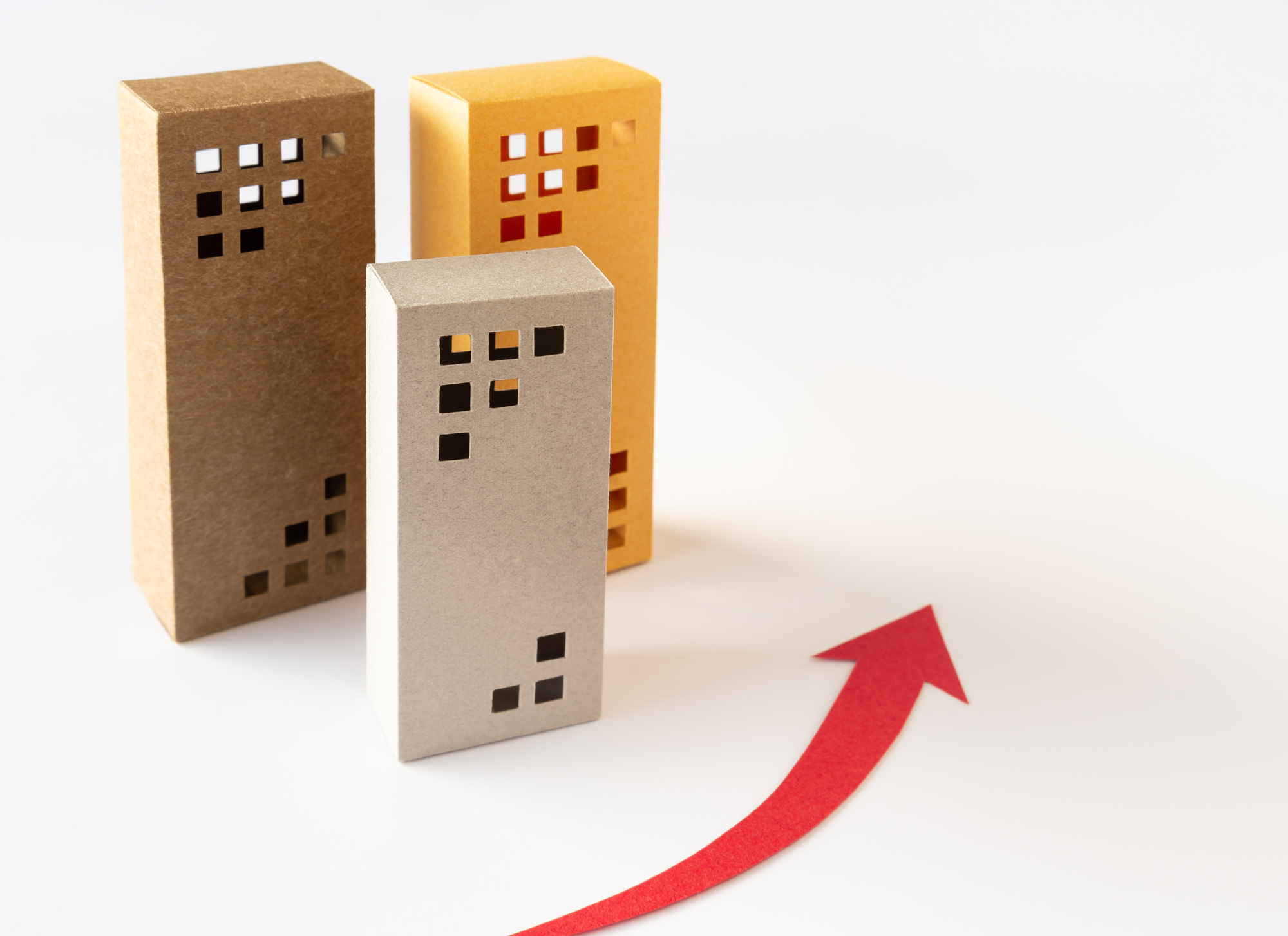
将来の資産形成や安定した収入源として、投資用不動産に関心を持つ方が増えています。老後の生活資金や年金不安への備えとして、賃貸経営による安定した家賃収入(インカムゲイン)が得られる点は大きな魅力です。
しかしながら、空室リスクや修繕費の負担、融資や管理の手続きなど、初心者にとっては不安に感じる要素もあります。本記事では、投資用不動産の基本から物件選び、利回りやキャッシュフローの考え方、運用時に注意すべきポイントまでを解説します。正しい知識を身につけ、堅実かつ長期的な視点で不動産投資を始めましょう。
目次
投資用不動産とは?まず押さえるべき基礎知識

投資用不動産とは、単に物件を購入するだけではなく、賃貸経営(アパート経営、マンション経営)を通じて安定した収益を得ることを目的とした資産運用の一つです。自宅を購入するのとは目的や判断基準が大きく異なり、収益性や市場性などの視点が欠かせません。
まずは、投資用不動産の定義と、実際にどのような方が投資対象としているかを見ていきましょう。
投資用不動産の定義と種類
投資用不動産とは、入居者に貸し出すことで家賃収入を得る「収益不動産」を指します。主な種類には、区分マンション(一室投資)、一棟アパート、戸建て、商業ビルなどがあり、物件の規模や立地によって投資額や利回り、管理の手間が異なります。
たとえば区分マンションは少額から始めやすく、管理を委託しやすいのが特徴です。一方で、一棟アパートや商業物件は初期投資が大きい分、運用次第で高い収益性を期待できます。また、新築か中古かによってもリスクや融資条件が変わります。
いずれも「資産を所有し、自ら経営判断を行う」点が、REIT(不動産投資信託)との大きな違いです。
自己使用との違い
自宅購入と不動産投資は、目的も評価基準もまったく異なります。自己使用の住宅は住みやすさやデザイン性などの感覚的な価値が重視されますが、投資用不動産は「収益性」と「市場競争力」が最優先です。駅近や商業施設へのアクセス、周辺の賃貸需要といった“借り手目線”での魅力が重要になります。
さらに、固定資産税や管理費、修繕費などのコストを考慮し、利回りとのバランスを冷静に見極めることが必要です。感覚ではなく、データと収支計算に基づいた合理的な判断が不動産投資の基本となります。
どんな人が投資対象にしているか
投資用不動産に取り組むのは、40〜60代の会社員や医師、弁護士、司法書士などの士業、自営業者など、安定した収入基盤を持つ層が中心です。将来の年金不安に備えたり、老後の資産形成を目的とした“第二の収入源”として始める方が増えています。
金融機関の融資では、年収や勤続年数、自己資金の有無が重視されるため、信用力のある人ほど有利に進めやすい傾向です。最近では、少額から始められる不動産クラウドファンディングも登場し、若年層や副業志向のビジネスパーソンにも広がっています。
まずはファイナンシャルプランナーなど専門家に相談し、自分の資金力と目的に合った投資スタイルを見極めることを推奨します。
投資用不動産のメリット・デメリット
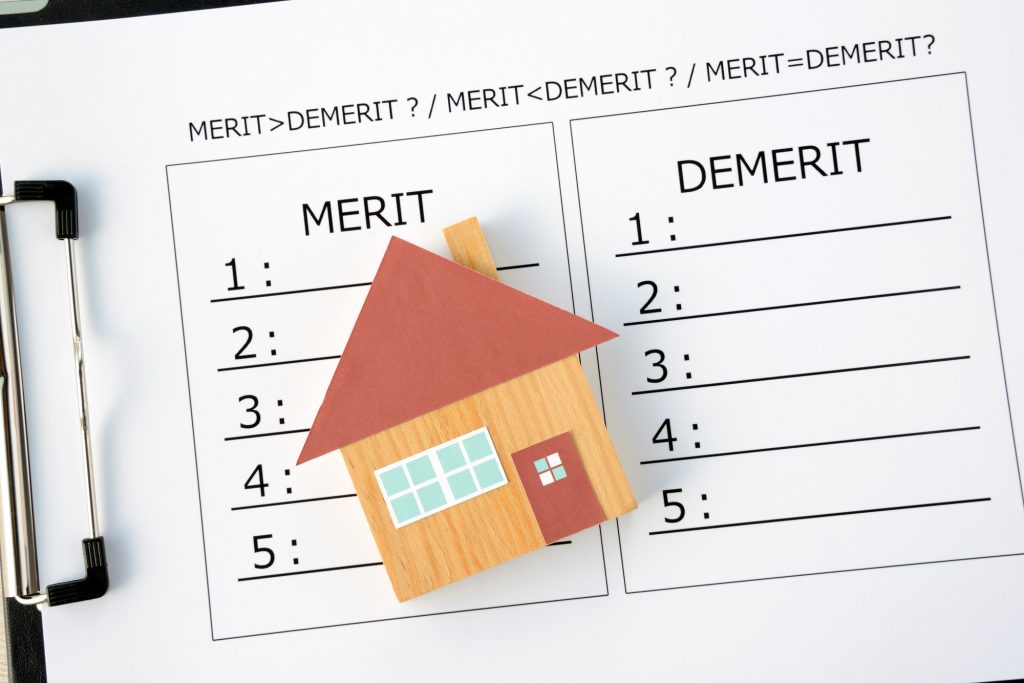
不動産投資は、長期的に安定した収入を得ながら資産形成を進められる魅力的な手法です。その反面、メリットばかりに目を向けてしまうと、リスクを見落として失敗する可能性もあります。
ここでは、不動産投資の主なメリットと注意すべきデメリット、そしてリスクとリターンのバランスの取り方を整理します。
メリット(安定収入・節税・資産形成)
投資用不動産の最大の魅力は、家賃収入によって安定したキャッシュフローを得られる点です。株式投資のように価格変動が大きくなく、長期的に予測しやすい収益が期待できます。
また、不動産所得では管理費や修繕費、固定資産税、ローン金利などを経費として計上できるため、所得税や住民税の節税効果も見込めます。
不動産は現金よりも相続時の評価額が下がる傾向にあり、相続税対策としても有効です。(※評価額の算定には特例適用の可否など様々な要素が影響するため、具体的な対策は必ず税理士などの専門家に相談してください)
ローンを活用すれば少ない自己資金でも資産拡大が可能で、完済後には実物資産として残る安心感も。不動産投資は、安定・節税・資産形成を同時に叶えられる手段といえるでしょう。
デメリット(空室リスク・資金拘束・管理負担)
一方で、不動産投資には見逃せないデメリットも存在します。特に注意すべきは空室リスクで、入居者がいなければ家賃収入が途絶え、ローン返済や管理費を自腹で支払う必要が生じます。
また、不動産は現金化に時間がかかる資産で、売却したいときにすぐ換金できない点もデメリットです。加えて、入居者募集やクレーム対応、設備修理といった管理の手間も発生します。管理を委託すれば費用がかかり、自主管理なら時間と労力が増えます。
築年数が経過した物件では修繕費用の増大や空室期間の長期化も起こり得ます。これらのリスクを把握したうえで、十分な資金計画と管理体制を整えておかなければなりません。
リスクとリターンのバランスをどう取るか
リスクとリターンのバランスを取るには、まず自身のリスク許容度を明確にすることが重要です。高利回りを狙う築古物件や地方物件は魅力的に見えますが、空室や修繕リスクが高く、安定性に欠ける場合があります。
安定した運用を重視するなら、都心部の新築マンションや人気エリアの築浅物件がおすすめです。空室リスクを抑えるためには、賃貸需要の高いエリアを選び、サブリース契約(家賃保証)の活用も検討に値しますが、家賃保証には賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)に基づく重要事項の説明義務があるものの、免責期間や減額リスクがあるため、手数料や条件はとくに慎重に確認を行う必要があります。
さらに、金利上昇や返済負担に備えて、変動金利・固定金利の選択や繰り上げ返済の計画も重要です。無理のない返済計画と分散投資を意識することで、安定した収益とリスク軽減を両立できます。
投資用不動産の種類と選び方

投資用不動産にはさまざまなタイプがあり、それぞれ特徴や収益性、管理のしやすさが異なります。自分の資金力やライフスタイル、目指す投資目的に合った物件を選ぶことが、安定した運用の第一歩です。
ここでは代表的な不動産の種類と、それぞれのメリット・デメリット、さらに購入時に押さえておきたい選定ポイントを紹介します。
区分マンション、一棟アパート、戸建て、商業物件など
区分マンションは、比較的少額から始められることから初心者に人気の高い投資スタイルです。管理会社に運営を委託でき、手間を抑えつつ安定した賃料収入が見込めます。
一棟アパートは数千万円規模の投資が必要ですが、複数の入居者から家賃を得られるため、高い利回りとキャッシュフローが期待できます。
戸建ては、リフォームを行ってファミリー層に長期入居してもらうケースが多く、安定した経営を目指す方に向いています。商業物件(店舗や事務所)は賃料が高い反面、景気や立地の影響を受けやすく上級者向けです。最近では、不動産クラウドファンディングを活用し、小口で複数物件に分散投資する方法も注目されています。
立地と物件の選定基準
不動産投資で最も重要なのは立地です。駅から徒歩10分以内、主要エリアへのアクセスの良さ、生活インフラが整った環境、治安の良さなどは賃貸需要に直結します。
単身者向けなら駅近・繁華街の近く、ファミリー層なら学校区や公園の有無が重視されます。地方物件は表面利回りが高く見えることもありますが、人口減少や需要の不安定さから空室リスクが高まる点には注意が必要です。
また、物件そのものの状態も大切です。築年数、間取り、設備のグレード、管理体制などを総合的にチェックし、現地見学では共用部の清掃状態や周辺住民の雰囲気も確認しましょう。長期的に安定した入居が見込める、需要の続く物件を選ぶことが、投資成功につながるでしょう。
中古 vs 新築の比較ポイント
新築物件は最新設備が整っており、購入後しばらくは修繕費がかからず、入居者もつきやすい点が魅力です。ただし、価格が高めで利回りは低くなりがちです。
中古物件は購入価格が抑えられるため利回りが高くなりやすいものの、老朽化による修繕リスクや融資条件の厳しさがデメリットです。初期費用(登記費用・仲介手数料・取得税など)は物件価格に比例するため、中古のほうが全体コストを抑えやすい傾向があります。
安定志向の方は新築、高い収益を狙う方は中古を選ぶのが基本ですが、築10年以内の築浅中古であれば双方のメリットを両立することも可能です。物件価格と収益性のバランスを見極め、長期的に安心して運用できる選択をしましょう。
収益シミュレーションと利回りの考え方

投資用不動産の魅力は、安定した家賃収入による資産形成にありますが、表面的な数字だけで判断してしまうと、思わぬ支出により想定よりも利益が出ないケースも少なくありません。
投資判断の基礎となるのが利回りとキャッシュフローの考え方です。ここでは、収益計算の方法や、現実的なシミュレーションの立て方を解説します。
表面利回りと実質利回りの違い
利回りには「表面利回り」と「実質利回り」の2種類があります。表面利回りは、年間家賃収入を物件価格で割って算出するシンプルな指標で、広告などでもよく見かけます。たとえば3,000万円の物件で年間家賃収入が180万円の場合、表面利回りは6%です。
一方で実質利回りは、ここから管理費、修繕費、固定資産税、管理会社への委託費用などの経費を差し引き、購入時の諸費用も含めて算出します。
実際の手取り収益を反映した数値であり、投資判断においてはこちらを重視すべきです。特に築古物件や地方物件は、見た目の利回りが高くても経費や空室リスクを考慮すると収益性が下がることが多いため、実質利回りの確認が欠かせません。
キャッシュフローの見方
キャッシュフローとは、家賃収入からローン返済、管理費、修繕費、税金などすべての支出を差し引いた、実際に手元に残るお金のことです。たとえ利回りが良く見えても、ローン返済が重ければ毎月のキャッシュフローがマイナスになる可能性があります。
特に高金利やフルローンでの借入は返済負担が大きく、空室が発生すると赤字になるリスクも。安定した経営のためには、常にプラスのキャッシュフローを維持することが大切です。
また、将来の修繕費や入居者入れ替えに備え、収益の一部を積み立てる余裕も持ちましょう。サブリース契約を利用する場合は、家賃保証料がどの程度収益に影響するかもシミュレーションしておきましょう。
ローン返済・空室リスクを考慮した計算方法
収益シミュレーションでは、ローン返済と空室リスクを必ず織り込みます。返済額は融資額・金利・返済期間で決まり、金利変動の影響を考慮して固定金利と変動金利の両方を比較するのがおすすめです。
空室率は立地や物件の種類によって異なりますが、一般的に5〜10%程度を見込むと安全です。たとえば月10万円の家賃であれば、年間1〜2か月分の空室期間を想定しておくと良いでしょう。
さらに、原状回復費や設備修理費も年単位で予算に組み込むことで、実際の収益に近い数値を把握できます。最終的には、すべての費用を差し引いた上で手元に残るキャッシュフローがプラスであるか確認することが大切です。
シミュレーションに不安がある場合は、ファイナンシャルプランナーや管理会社など専門家の意見を取り入れて、複数パターンで検証するのもおすすめです。
購入・運用にかかる費用と税金

投資用不動産は、物件の購入価格だけでなく、取得時や運用中にもさまざまな費用や税金が発生します。これらを正しく把握しておかないと、思わぬ支出でキャッシュフローが圧迫されることも。
初期費用から管理・修繕などの運用コスト、さらに税金と節税対策まで詳しく解説します。
初期費用(頭金・仲介手数料・登記費用など)
不動産購入時には、物件価格以外にもさまざまな初期費用がかかります。一般的に頭金として物件価格の10〜20%ほどの自己資金が必要で、この割合は融資審査にも影響します。
仲介手数料は宅地建物取引業法に基づき「物件価格×3%+ 6万円+消費税」が上限で、3,000万円の物件なら約105万円程度です。
さらに登記費用(所有権移転登記・抵当権設定登記)は司法書士法に基づき司法書士報酬を含め数十万円、不動産取得税は地方税であり、固定資産税評価額を課税標準に、原則として4%(住宅用不動産は3%)が目安です。このほか、火災保険料、印紙税、ローン事務手数料なども発生します。
初期費用の合計は物件価格の7〜10%程度になるため、購入予算を立てる際には必ず織り込みましょう。中古物件では融資条件が厳しくなる場合もあるため、頭金を多めに準備しておくと安心です。
運用中の経費(管理費・修繕費・固定資産税など)
物件を所有している限り、毎月・毎年の運用経費が発生します。区分マンションの場合、管理費と修繕積立金の支払いが必要で、築年数の経過とともに修繕費が上がる傾向にあります。
一棟アパートや戸建てでは、自身で修繕費を積み立てておくことが欠かせません。さらに、管理会社へ委託する場合は家賃収入の約5%前後が管理手数料としてかかります。自主管理にすれば費用は抑えられますが、入居者対応やクレーム処理など手間が増えます。固定資産税・都市計画税は毎年、物件の評価額に応じて課税されます。
このほか、入退去時の原状回復費、広告費、設備交換費なども発生します。これらの経費を把握し、年間のキャッシュフローをしっかりシミュレーションすることが重要です。
不動産所得にかかる税金・節税方法
不動産投資で得た家賃収入は、不動産所得として所得税と住民税の課税対象になります。なお、海外不動産投資の場合、日本の税制と異なるため、さらに複雑な手続きが求められます。
課税額は「総収入−必要経費」で算出され、経費には管理費、修繕費、固定資産税、ローン利息、減価償却費などが含まれます。
特に減価償却費は実際の支出を伴わずに経費計上できるため、節税効果が高い項目です。中古物件は耐用年数が短く、より多くの減価償却を計上できる傾向があります。
また、不動産所得の「事業的規模」(5棟10室基準が目安)が認められ青色申告を選ぶことで最大65万円の特別控除を受けられ、赤字が出た場合でも翌年以降に繰り越して相殺することが可能です。
ただし、節税目的だけで過剰な借入を行うのは危険です。無理のないキャッシュフローを前提に、税理士やファイナンシャルプランナーと相談しながら、長期的に見た最適な節税対策を行いましょう。
初心者がやりがちな失敗と対策

不動産投資を始めたばかりの方がつまずく原因の多くは、知識不足や判断の甘さにあります。見た目の数字や営業トークに惑わされて誤った選択をしてしまうと、取り返しのつかない損失につながることも。
あらかじめ典型的な失敗パターンを知り、リスクを回避する意識を持つことも大切です。ここでは初心者が陥りやすい失敗と、その防ぎ方をご紹介します。
利回りだけで判断してしまう
初心者が最も陥りやすいのが、表面利回りの高さだけで物件を選んでしまうケースです。地方や築古物件は一見高利回りに見えますが、実際には空室リスクや修繕費の増加により、手取りの実質利回りは大きく下がる可能性があります。
さらに、入居者トラブルや家賃滞納などの管理リスクも軽視できません。対策としては、購入前に実質利回りとキャッシュフローを必ず計算し、現地で物件状態と周辺環境を自分の目で確認することです。
加えて、管理会社から過去の入居率や家賃推移をヒアリングし、長期的な収益性を見極めましょう。利回りはあくまで目安です。数字の裏にあるリスクを冷静に判断することが重要です。
管理会社の選定ミス
不動産投資の成否を大きく左右するのが、管理会社の選び方です。入居者募集、家賃回収、クレーム対応、修繕などを代行してもらうため、信頼できるパートナー選びが欠かせません。ところが、販売会社の提携先をそのまま選んだり、管理手数料の安さだけで決めたりすると、空室が長引いたり対応が遅れたりするリスクがあります。
対策としては、複数の管理会社を比較し、入居率や対応スピード、オーナー評価などを確認することです。契約前に担当者と直接会い、誠実さやコミュニケーションの取りやすさを見極めましょう。サブリース契約を検討する際も、家賃保証の条件や手数料率を丁寧に確認し、安定性とコストのバランスを見極めることが大切です。
過剰な融資と返済不能リスク
フルローンを組んで高額物件を購入し、返済負担に苦しむケースも少なくありません。融資が通るからといって無理な借入をすると、空室や金利上昇などの変化に対応できず、返済不能に陥るリスクがあります。
特にローン審査が通りやすい属性の方ほど、過剰な借入に陥るリスクがあります。対策としては、空室率10%、修繕費、金利上昇分を見込んだうえで、キャッシュフローがプラスになるかをシミュレーションすることです。
頭金を多めに入れて借入額を抑える、固定金利を選んで金利変動リスクを防ぐ、繰り上げ返済できる余力を持つなど、保守的な計画を心がけましょう。不動産投資は、攻めより守りの姿勢が大切です。
まとめ|失敗しないための投資用不動産の始め方
投資用不動産は、正しい知識と計画をもって臨めば、安定した家賃収入と資産形成の両立が期待できる投資手法です。その一方で、利回りの数字だけを見て判断したり、リスクを軽視してしまうと、空室や返済負担に悩まされることもあります。
まずは、ご自身の目的や資金力に合った物件タイプを選び、立地と賃貸需要を重視することが大切です。購入前には初期費用と運用コストをしっかり把握し、信頼できる管理会社や専門家と連携しながら、現実的な収支シミュレーションを行いましょう。
空き家・中古投資用不動産の活用・売却は「アキサポ」へ
投資用不動産を検討中の方、または所有物件の活用方法に迷っている方は、「アキサポ」へご相談ください。 空き家や中古不動産の活用・売却・リノベーションまで、経験豊富なスタッフが最適なプランをご提案します。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。







