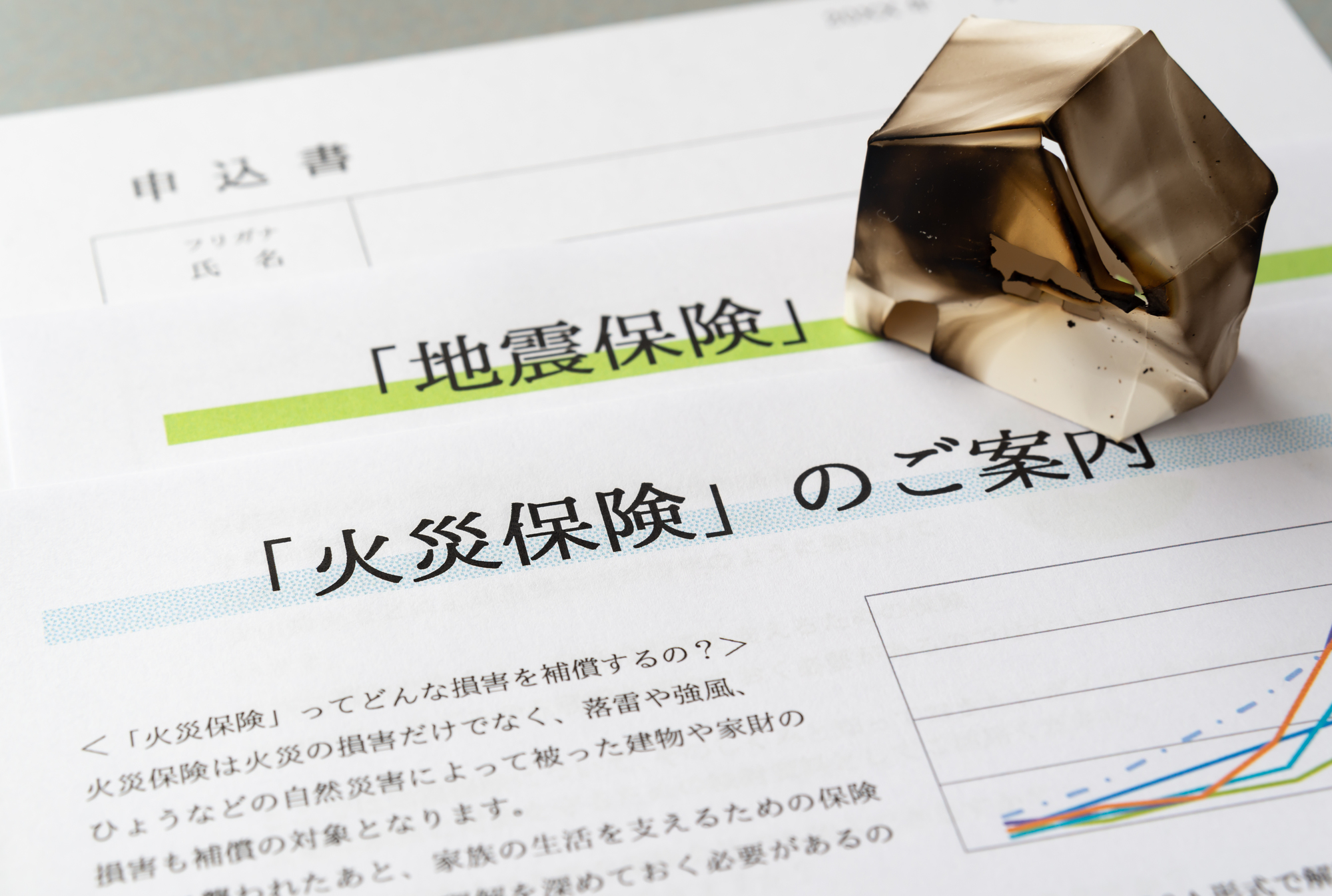公開日:2025.06.18 更新日:2025.09.16
【空き家の火災保険】必要性・リスク・補償内容の選び方を解説
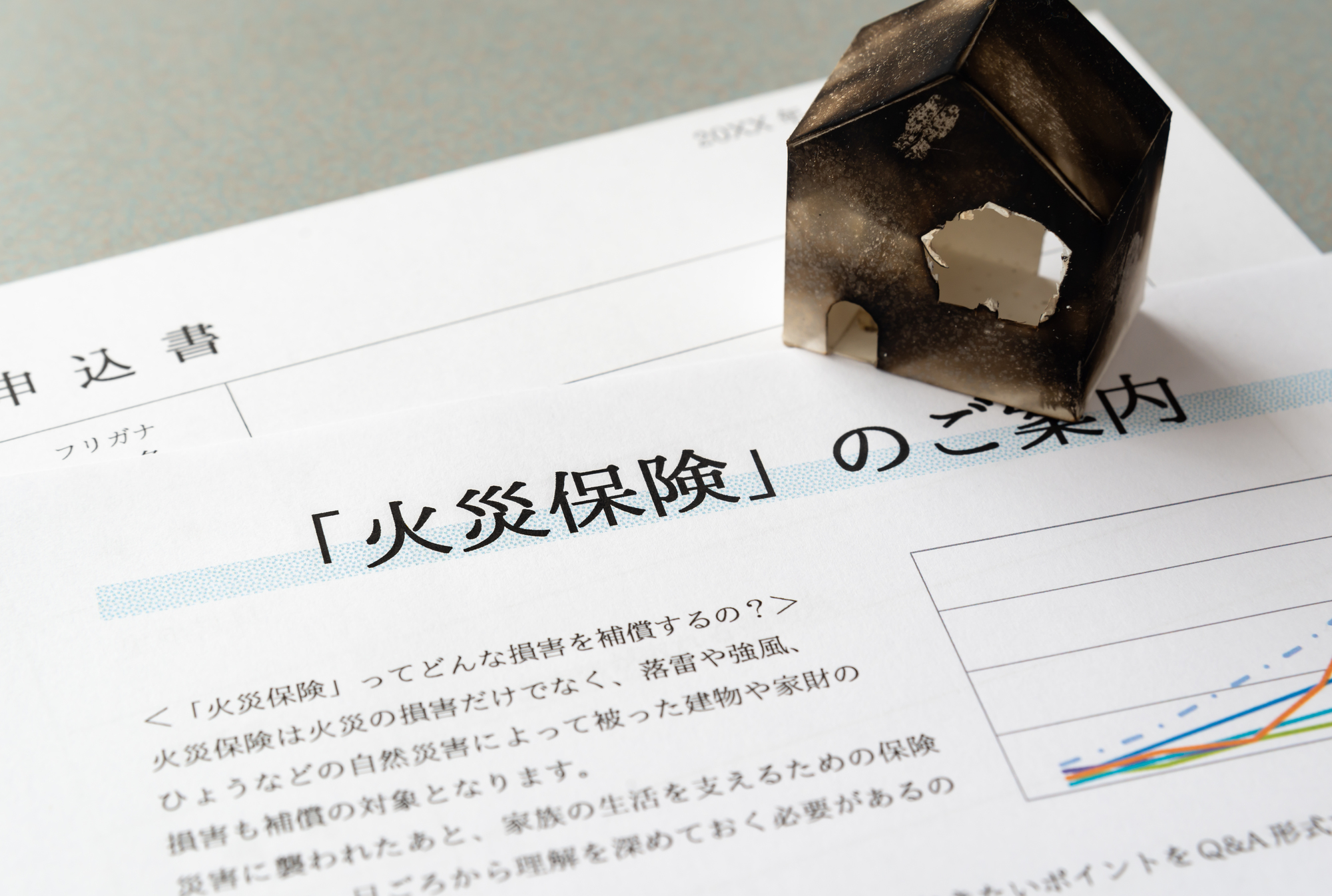
年々増加する空き家。運用や売却はもちろんのこと、管理に頭を悩ませていませんか?
想定される懸念の中でも、特に注意したいのが火災トラブルです。空き家は人の目が届きづらいため、火災をはじめとするさまざまなトラブルのリスクが高まる傾向にあります。
そこで重要となるのが「火災保険」。通常の住宅と同じ条件で加入できるのか、どのようなリスクを想定すべきかなど、気になる点は多いでしょう。
本記事では、空き家における火災保険の必要性や注意点、保険料や補償内容の選び方について、わかりやすく解説します。
目次
そもそも空き家に火災保険はなぜ必要?

空き家は、近隣住民であっても建物に近づく機会が少なく、人の出入りがほとんどありません。そのため、火災などのトラブルが発生しても発見が遅れやすいという特性があります。
どのようなリスクがあり、なぜ保険が必要なのでしょうか。
空き家は人目につかない時間が長くなるため、火災の初期段階に気づかれず発見が遅れがちです。特に漏電による火災は外観からは分かりづらいため、定期的な点検やメンテナンスが重要となります。
こうした火災リスクに対処する手段の一つとして、火災保険への加入を検討する必要があります。
空き家に火災が発生した場合、建物や家財への損害はもちろんのこと、周囲の建物に延焼してトラブルが拡大するケースもあり得ます。所有者は建物の管理責任を負うため、管理不足を理由に失火責任法により、通常は過失による火災では賠償義務を負わないとされますが、空き家の管理不備が重大な過失と認定されると、民法709条に基づき損害賠償責任が生じる可能性があります。
こうしたリスクに備え、カバーする手段として有効なのが、火災保険への加入です。
また、空き家を取り壊す予定があっても、火災の発生による周辺環境への悪影響や解体費用の負担増などを避けるために、火災保険が役立つ場合があります。空き家の保有にともなうコストとリスク総額を考えたうえで、保険を活用して被害拡大を防ぎ、管理コストを抑える必要があります。
放火・漏電・老朽化──空き家が火災リスクを高める3つの要因
火災原因は漏電だけではありません。
人が出入りしていない家屋は、外部から見て人目が少ないと判断されやすく、放火の標的になりやすいです。特に夜間や周囲に街灯が少ない場所は注意が必要です。
老朽化した電気配線やブレーカー、コンセントが火災の原因となる場合もあります。空き家では異常を検知しにくいため、配線部分の破損や裸線になっている部分を放置してしまうことでより一層リスクが高まるケースも。
こうした火災は「失火責任法」によって故意・重大過失があるとみなされると、損害賠償責任が発生します。空き家はこの「重大な過失」が成立しやすいため、注意が必要です。
台風・雪害など自然災害時の被害も大きくなりがち
空き家は普段から点検や修繕を行う機会が少ないため、屋根の破損や雨漏りなどの劣化に気づきにくい場合があります。特に台風や大雪のシーズンに備えた補修が不十分だと、風災による被害が拡大しやすくなります。
台風による強風で瓦が飛ばされたり、積雪の重みで屋根が損傷したりすると、建物内部に浸水し、建材が急速に腐食する可能性があります。状況によっては倒壊の危険もあり、発見が遅れれば修繕コストが膨らむおそれもあります。
また、自然災害は一度発生すると建物全体に甚大な被害を与え、修繕すべきかどうかの判断が難しくなることもあります。
火災保険には、補償対象として風災や雪災、落雷といった自然災害への補償が含まれていることが多く、万が一の被害に備えるうえで重要な手段となるでしょう。
空き家の火災が近隣に延焼した場合の賠償責任
空き家で発生した火災が近隣の土地や建物に燃え広がった場合、所有者が賠償責任を問われる可能性があります。損害額が高額にのぼるケースもあり、経済的負担は非常に大きくなるでしょう。
火災保険に加入していないと、修繕費や慰謝料など、火災による直接的な被害に加え広範囲な費用負担を強いられる恐れがあります。こうした事態に備えるためにも、火災保険で最低限の補償を確保しておくことが重要です。
また、万が一の賠償リスクに備えて、火災保険の特約や個人賠償責任保険の活用も検討すると安心です。空き家であっても、周囲の安全を守る責任は所有者にあり、事前の備えは社会的な責務とも言えるでしょう。
空き家は火災保険に入れない?住宅物件と一般物件の違いを解説

空き家は一般の住居である「住宅物件」とは見なされず、「一般物件」扱いとなる場合があります。その違いは火災保険料や補償内容にどのように影響するのでしょうか。
一般的な火災保険は住宅物件向けに設計されているため、実際に人が居住していない空き家は保険対象外とされるケースも。保険会社によって基準が異なるため、加入の際には、住宅用か一般物件かの判断基準や必要書類など、事前に確認すべき注意点を整理しておくことが重要です。
多くの場合、空き家は「一般物件」として扱われるため、リスク評価が高く見積もられ、保険料が割高になる傾向があります。その結果、通常の住宅向けプランと比べて大幅に保険料が上がることもあるため、慎重な検討が必要です。
一方で、空き家向けの火災保険には、空き家特有のリスクに対応した補償が付帯される場合もあります。不要な補償を外し保険料を抑えることも可能なため、コストと補償内容のバランスを見極め、自分に合ったプランを選ぶことが大切と言えるでしょう。
住宅物件向けの火災保険に加入できるケース
空き家であっても、月に数回程度の清掃や管理のために出入りがあり、ある程度住居としての機能が維持されている場合は、住宅物件として認定されることがあります。これは、保険会社ごとの基準や実際の使用状況に基づいて判断されるのが一般的です。
例えば、水道や電気を定期的に使用し、生活の痕跡が確認できるようであれば住宅物件扱いとして火災保険に加入できる可能性も高まります。ただし、名目上だけでは難しく、現地調査や書類提出が必要になることがあります。
住宅物件扱いになれば、一般物件よりも保険料が割安になる傾向があるため、空き家を時折利用する予定がある方は早めに保険会社へ相談してみる価値があるでしょう。
一般物件扱いになると保険料が高くなる理由
空き家は放火リスクや漏電火災、自然災害時の被害拡大などの危険度が高いとみなされるため、保険会社としては損害率が高くなる懸念があります。その分、保険料が上乗せされるのが一般物件扱いの特徴です。
また、近年では空き家の数が増加しており、管理が行き届かないケースが社会問題になっていることも要因の一つ。保険会社もそうしたリスクを考慮せざるを得ず、結果として一般物件扱いの火災保険料は割高になりやすいのです。
ただし、火災報知器や防犯設備の導入、定期点検の実施など、空き家所有者がリスクを下げる対策を取ることで保険料が一定程度軽減されることもあります。物件の状態に合わせて具体的な見積もりを取り、比較検討するのがおすすめです。
空き家は地震保険をつけられないケースもある?
地震保険の仕組みについても、火災保険との違いを含めて簡単に解説します。
地震保険は火災保険と同時に契約する形が一般的ですが、空き家が住宅物件として認められない場合、地震保険の加入条件が厳しくなる場合があります。これは、地震保険は「地震保険に関する法律」により、住宅または家財を対象とした制度であり、空き家は使用実態がない場合、対象外と判断されることがあります。
地震リスクの高い地域に空き家を所有している場合は、住宅認定を受けられるよう、日常的な維持管理を行うなどの対策を講じることが重要です。
また、地震保険への加入条件は保険会社ごとに異なるため、事前の確認が欠かせません。
もし地震保険に加入できない場合は、火災保険の損害補償を最大限活用するとともに、耐震リフォームや補強など、実質的なリスク管理策を検討する必要があります。
空き家の火災保険料の相場と補償内容の選び方

空き家の火災保険は費用が高めに設定される傾向にありますが、補償内容を厳選することでコストを抑えることが可能です。
空き家の火災保険料は一般的に年間1万円〜6万円程度が相場ですが、建物の構造や立地、補償範囲の広さによって大きく変動します。特に老朽化が進んでいる建物や防犯対策が不十分な物件は保険料が高くなりがちです。
補償対象としては、火災による建物の損害をカバーすることはもちろん、風災や雪災などの自然災害、さらには賠償責任を負う場合の特約を検討することも重要です。空き家特有のリスクを想定しながら、どこまで補償が必要かを見極めることがポイントとなります。
保険料の節約を意識するあまり必要な補償を外し過ぎると、万が一の際に十分な支援を受けられなくなる可能性もあります。リスクとコストのバランスを考えながら、保険会社の提案を複数比較するのが重要と言えるでしょう。
補償内容を絞って保険料を抑える方法
最も基本的な火災補償だけを確保し、台風や雪害などのリスクを自己負担として設定することで、保険料を大幅に抑えることができます。ただし、自然災害による被害額は大きくなりやすい点に注意が必要です。
賠償責任補償も重要な要素ですが、敷地周囲に防火壁がある場合や、近隣との建物間に十分な距離がある場合は、延焼リスクが相対的に低くなります。そのため、補償額を抑えることで保険料を節約できる可能性もあります。保険会社と相談しながら最適なプランを模索しましょう。
火災報知機やオートロック、防犯カメラなどの設備を導入している場合、トラブル発生のリスクが低いと判断され、保険料の割引対象となる可能性があります。火災保険料を抑えるための投資と考え、導入を検討するのも一つの選択肢です。
空き家でも加入できる火災保険会社の事例

近年では、空き家に特化した保険商品を展開する保険会社も登場しています。各社のサービス内容を比較検討することが大切です。
一部の保険会社では、空き家の所有者向けに独自の調査や管理体制をセットにした専用プランが用意されています。放火対策や定期巡回サービスをオプションで付けられる商品もあり、管理の手間を削減しつつリスクを低減できる仕組みを提供しています。
また、住宅物件として認定が難しい物件でも、特別契約を引き受けてくれる保険会社も存在します。一般物件扱いでもある程度の割引が適用されるケースがあるので、複数の保険会社に相談してみることをおすすめします。
依頼する際は、建物の構造や築年数、空き家となった経緯などを正確に伝えることが重要です。事実と異なる説明をしてしまうと、いざ保険金を請求する際にトラブルになる場合があるため注意が必要です。
空き家にかかる維持費と売却の検討

空き家には固定資産税や管理費など、想像以上に多くの維持費がかかることも。
物件を所有しているだけでも、毎年固定資産税や都市計画税が発生します。さらに、庭木の手入れや建物の定期点検といった管理費も重なり、実際には大きな出費となるケースが少なくありません。
そのため、将来的な利用予定がない場合は、早めの売却を検討することも有効な選択肢のひとつです。
火災保険に加入しておけば、いざというときに損壊や被害額の一部を補償してくれますが、継続的な保険料も必要となってきます。総合的な費用対効果を考えると、空き家を長期間維持するよりも売却や解体を検討するほうが安く済むケースもあるでしょう。
今後の活用見込みがない空き家は、築年数や設備状況の劣化が進むほどに売却価格が下がる傾向にあります。そのため、近い将来に活用予定がないのであればできるだけ早めに不動産会社や買取業者に売却相談を行うことが得策です。
まとめ

空き家は人の居住や出入りがないぶんリスク管理が難しく、火災保険が果たす役割は大きいと言えるでしょう。保険料や補償内容を理解しながら、適切な空き家対策を講じることをおすすめします。
まずは空き家特有の火災・自然災害リスク、そして賠償リスクをしっかり把握することが大切です。一軒家の場合は漏電や放火などが原因で大きな被害に発展しやすく、管理責任を問われるケースも少なくありません。
空き家が「住宅物件」として扱われるか「一般物件」とされるかは、火災保険料や地震保険の加入条件に大きく影響します。保険会社と相談や設備投資などを行い、可能な限り安心かつお得に管理できるよう工夫しましょう。
最後に、空き家の維持費は予想以上に高額になることがあります。時には早めの売却が得策となるケースもあるので、リスクとコストの両方を踏まえて最適な選択を行いましょう。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。