公開日:2025.06.20 更新日:2025.09.16
【譲渡税の基本】資産売却時にかかる税金と特例制度をやさしく解説

譲渡税とは?不動産売却時にかかる所得税・住民税の計算方法、3,000万円控除などの特例までを解説。
本記事では、譲渡にかかる税金の仕組みから、節税につながる各種特例の活用方法まで、基本をわかりやすく解説します。
目次
まず押さえておきたい譲渡所得税の基本

はじめに、譲渡所得税の概要と対象となる仕組みを理解することが重要です。基本を押さえることが、正しい申告と税額負担の軽減に役立ちます。
譲渡所得税とは、土地・建物・株式などを売って得た「譲渡益」に対して課される分離課税方式の税金です。分離課税方式といって通常の収入とは別に計算され、譲渡所得専用の税率が決まります。
申告時には、取得費や譲渡費用など、利益を出すまでにかかった費用を引いてから税金を計算できるのが特徴で、他の所得と区別して計算する必要があります。
また、譲渡所得は所有期間に応じて長期と短期で区分され、税率も大きく変わります。税制改正によって特例制度や控除額が頻繁に変更されるため、日頃から最新情報を把握することが重要といえるでしょう。特に、マイホームの売却のように、特例が多岐にわたるケースでは、専門家の助言を受けながら正確に計算することが、適切な節税につながります。
譲渡所得の対象になるケース・ならないケース
譲渡所得の対象となる主な例としては、不動産売却によって得た利益や、土地・建物・株式などの資産の売却益が挙げられます。
一方で、事業用の棚卸資産や山林の売却などは、税法上、「譲渡所得」ではなく「事業所得」などに区分される場合があります。また、公益目的での譲渡は、地方税法や租税特別措置法に基づいて非課税または軽減措置が認められる場合があります。軽減措置が適用される特例もあります。
自身が売却検討している資産の性質や用途を事前に確認することで、意図しない課税を避けることが可能です。
譲渡所得の計算方法:収入金額・取得費・譲渡費用のポイント

譲渡所得を正しく計算するためには、譲渡収入金額・取得費・譲渡費用の考え方を理解する必要があります。
譲渡所得は、次の計算式で求められます:
「譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除」
譲渡収入金額には、売却代金や譲渡時に受け取る権利金・物品の時価なども含まれるため、契約書だけでなく実際の受取内容を丁寧に確認することが欠かせません。間違って計算すると納税額が過大または過小になり、後々修正申告が必要になる可能性があります。
また、取得費や譲渡費用を正しく算出するには、購入時の領収書や仲介業者の契約書など関係資料を適切に保管しておくことが大切です。特に建物などの減価償却費をはじめとする費用の計算は考慮すべき箇所も多く、原則として実際に支払った経費や税法で認められた額を計上します。
そのため、こうした正確な書類の管理が、トラブルを防ぎ適切な税額算定につながると言えます。
譲渡収入金額に含まれるもの・含まれないもの
譲渡収入金額には、売買契約で定められた売却代金や、譲渡時に受け取る権利金などが含まれます。
また、売買代金に上乗せされることのある未経過固定資産税や敷金精算については、契約内容や取引の実態により、譲渡収入金額に含まれる場合とそうでない場合があります。たとえば、実質的に譲渡対価とみなされる場合には収入金額に含まれることがありますが、単なる税負担の精算や預かり金の返還は原則として譲渡収入には該当しません。
契約書の内容や金銭の性質に基づき、税理士や司法書士などの専門家の確認を得ながら慎重に判断する必要があります。誤った判断を防ぐためにも、契約書をよく確認し、不明点は専門家に相談することが重要です。
取得費と減価償却費の計算方法
取得費には、購入代金、仲介手数料、登記費用、改良工事費などの「資産価値を高める目的の支出」が含まれますが、修繕費や維持費は対象外です。
ただし、建物の場合は経年で価値が減ることを考慮し、取得費から減価償却費を差し引く仕組みがあるため、実際の取得費が大きく変化する点に注意が必要です。みなし償却費の計算には「取得日」や「法定耐用年数」の確認が必要で、適切な証憑書類とともに税務署提出が求められます。正しく把握して計算することが譲渡所得の精度を左右します。
譲渡費用になる費用・ならない費用
譲渡費用として認められる主なものに、物件の仲介手数料や売却に要した広告費、契約書の印紙代などが挙げられます。
一方で、不動産の改修費用のように、本来は資産価値の向上を目的とした支出は譲渡費用に該当しない場合もあります。実際にどの支出が譲渡費用に含まれるかは税法上の定義に基づくため、判断が難しい場合は専門家に確認することがリスク回避のポイントです。
長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いと税率

譲渡資産の所有期間によって税率が変わり、納税額に大きな影響を与えます。
一般に、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合は「長期譲渡所得」とされ、約20%の低い税率が適用されます。この税率には、所得税に上乗せされる復興特別所得税(所得税の2.1%相当)も含まれており、実際の納税額はやや高くなります。これに対し、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、約39%の高い税率が課されます。
これは短期間の投機的売買を抑制し、住宅や土地を長く保有することで税負担が抑えられる制度的配慮によるものです。
なお、所有期間の起算日は売却の契約日ではなく、原則として取得日(購入日)から計算されるため注意が必要です。取得時期の判断を誤ると、長期と短期を取り違え、後に修正申告が必要になる場合があります。
売却を検討している場合は、取得日を基準に5年を超えるかどうかを確認し、所有期間に応じた税率での申告準備を行うことが重要です。
マイホーム(居住用財産)に適用される特別控除・特例

居住用財産の場合は、ほかの不動産とは異なる特典が設けられており、要件や仕組みの理解が重要です。
マイホームを売却する場合、一般の投資用不動産と比べて大きな税制優遇を受けることができます。たとえば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「3,000万円特別控除」や、所有期間が10年以上の場合の軽減税率などが挙げられます。これらの特例制度を活用するには、居住実態や保有期間、家屋の利用状況などについて厳格な条件を満たす必要があります。
一方で、これらの特例を適用できない事情も存在します。過去に同じ特例を使った売却を短期間に行っていたり、家族の住民票の移転が間に合っていない場合などは、適用が認められないことがあります。
申告期限に余裕を持ち、抜け漏れなく書類を整えることで、正しく特例を適用して納税額を抑えられるようになります。
3,000万円特別控除の要件
居住用財産を売却した際、最大3,000万円までの譲渡所得が非課税扱いになる非常に強力な特例です。
ただし、この要件として、居住用途として使用している期間や家族の生活拠点があった事実を示す資料などが求められます。短期間で複数回利用するといった濫用を防ぐため、前回の特例適用から一定期間が経過していることなど、細かな条件を満たすことが必要です。
こうした条件についても、国税庁が公表する資料を参照することで正確な確認が可能です。
10年超所有軽減税率の特例
居住用財産を10年以上所有している場合、通常の長期譲渡所得よりさらに税率が軽減される特例です。この制度を利用することで、譲渡に伴う税負担を大幅に軽減することが可能です。
ただし、税負担を大幅に抑えられる一方、要件として売却する家屋が実際に居住事実があったものであることや、所有期間を正確に計算できる書類が必要となります。長期所有によるメリットは大きいものの、取得日と契約日の取り違いなど、誤って所有期間を計算した場合には適用されないため、契約書の日付チェックや所有権移転登記のタイミングに注意が必要です。
買換え特例と譲渡損失繰越控除の概要
マイホームを売却して新たな住居を購入する場合、一定の要件を満たせば、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べできる「買換え特例」を利用することが可能です。
また、売却によって譲渡損失が生じた場合にも、繰越控除を利用して将来の所得と相殺できる「譲渡損失の繰越控除」という制度が設けられています。こうした特例を活用する際には、住宅ローンの借り入れ状況や売却時の残債額なども審査項目に含まれ、条件を満たしたうえで確定申告時に必要書類を添付することが欠かせません。
譲渡所得税以外の税金:印紙税・登録免許税など
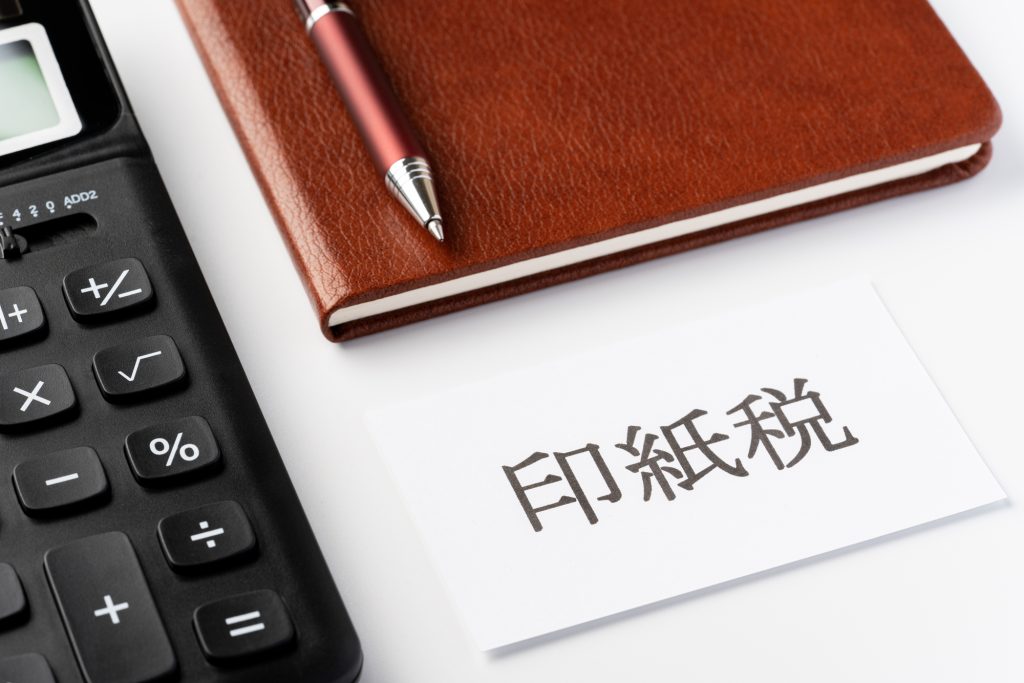
資産の譲渡にあたっては、所得税以外にも印紙税や登録免許税などが発生する場合があります。
不動産の売買契約書には、契約書自体に貼る印紙税が発生します。印紙税額は契約金額に応じて決まり、高額物件を取引する際には税額も増大する点に注意が必要です。また、売却後に所有権移転登記を行う場合には登録免許税が発生するため、コストを見積もる際にはこれらの税金を織り込んでおく必要があります。
これらの税金は譲渡所得に直接影響するものではありませんが、譲渡費用として認められる場合もあり、結果として申告内容に関係する可能性があります。特に契約書を複数作成する場合や、司法書士などの専門家を介する場合は、税金だけでなく印紙代や登記費用、手数料も考慮しなければなりません。複合的な費用負担を把握したうえで、売却金額や申告内容を慎重に検討することが大切です。
譲渡損失が出た際の損益通算と繰越控除

譲渡所得がマイナスになった場合、ほかの所得と相殺したり将来へ繰り越したりする特例制度が整備されています。
譲渡損失が発生した場合、他の譲渡所得や給与所得などと相殺する損益通算が認められ、その損益通算金額によって最終的な課税所得が変わることがあります。特にマイホーム売却による損失では、一定の要件を満たすことで、翌年以降に損失を繰り越して他の所得と相殺できる「繰越控除」の適用が可能です。繰越控除は最大で3年間利用できるケースがあり、大きな節税効果が期待できます。
ただし、損益通算や繰越控除はすべてのケースに適用されるわけではなく、マイホームの買換えや住宅ローン残高など、法律で定められた要件をクリアする必要があります。申告にあたって、損失の発生状況がわかる契約書類や支出の証拠書類をきちんと整備し、制度を活用できるかどうかを検討することが不可欠となります。
相続・贈与で取得した土地や建物を譲渡するときの注意点

相続や贈与で取得した資産を譲渡する際は、取得費や所有期間の扱いが通常と異なるため、特別な留意が必要です。
たとえば、相続や贈与で受け取った土地や建物を売却する際、元の所有者(被相続人や贈与者)の取得費や所有期間を引き継いで計算されることがあります。これは、一般的に相続や贈与を受けた時点では利益確定とはみなされないためです。
また、贈与税や相続税を支払ったケースであっても、譲渡所得の計算には直接反映されない場合があります。後の申告で混乱を避けるためにも、相続や贈与時の手続きをきちんと行い、財産評価額や取得経緯を正確に記録しておくことが必須です。
確定申告の流れと必要書類:申告漏れを防ぐために

譲渡所得の計算内容や特例の適用を正しく申告するために、確定申告の手順や必要書類を整理します。
まず譲渡所得の計算を行い、特例を適用する場合は各特例の要件をきちんとクリアしているかを確認します。続いて、譲渡所得に関する明細書や売買契約書、必要に応じて登記事項証明書、住宅ローン残高証明書などの必要書類を揃えておきましょう。申告書類の記入漏れや書類不備があると、追徴課税や修正申告が発生する可能性があるため、十分な確認が必要です。
確定申告の提出期間は、通常、翌年の2月16日から3月15日までとされており、この期間内に確定申告書と必要書類を税務署に提出します。電子申告(e-Tax)を利用すれば、書類の準備や手続きがスムーズになるケースも増えています。
期日を守り、正確に申告することで、延滞税やペナルティの発生を防ぐことができます。
まとめ・総括

譲渡税対策として使える3,000万円特別控除や買換え特例などの制度を活用し、トータルコストを軽減できるよう、ポイントを改めて確認しましょう。
譲渡所得税は、資産の所有期間や用途に応じて内容が大きく変わるため、計算方法や適用要件を正しく理解することが、誤った申告を防ぎ、節税効果を高める重要なステップです。特に、マイホーム売却に関しては、特別控除や軽減税率など多くの特例が用意されているため、情報を整理し、条件を満たすかをしっかり確認しましょう。
また、譲渡所得以外にも印紙税や登録免許税などの付随費用が発生する場合があり、譲渡全体にかかるコストとして見落とせません。
全体的な費用負担を見据えながら、損益通算や繰越控除などの制度を活用することで、さらに税金を抑える余地もあります。
制度を十分に活かすためには、専門家の助言を取り入れつつ、計画的な準備と確認を行うことが不可欠です。あわせて、国税庁のホームページを活用し、信頼できる情報源から最新の制度内容をチェックしておくと安心です。
円滑かつ有利な譲渡のために、今一度、全体のポイントを整理しておきましょう。
この記事の監修者

山下 航平 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
ハウスメーカーにて戸建住宅の新築やリフォームの営業・施工管理を経験後、アキサポでは不動産の売買や空き家再生事業を担当してきました。
現在は、地方の空き家問題という社会課題の解決に向けて、日々尽力しております。










