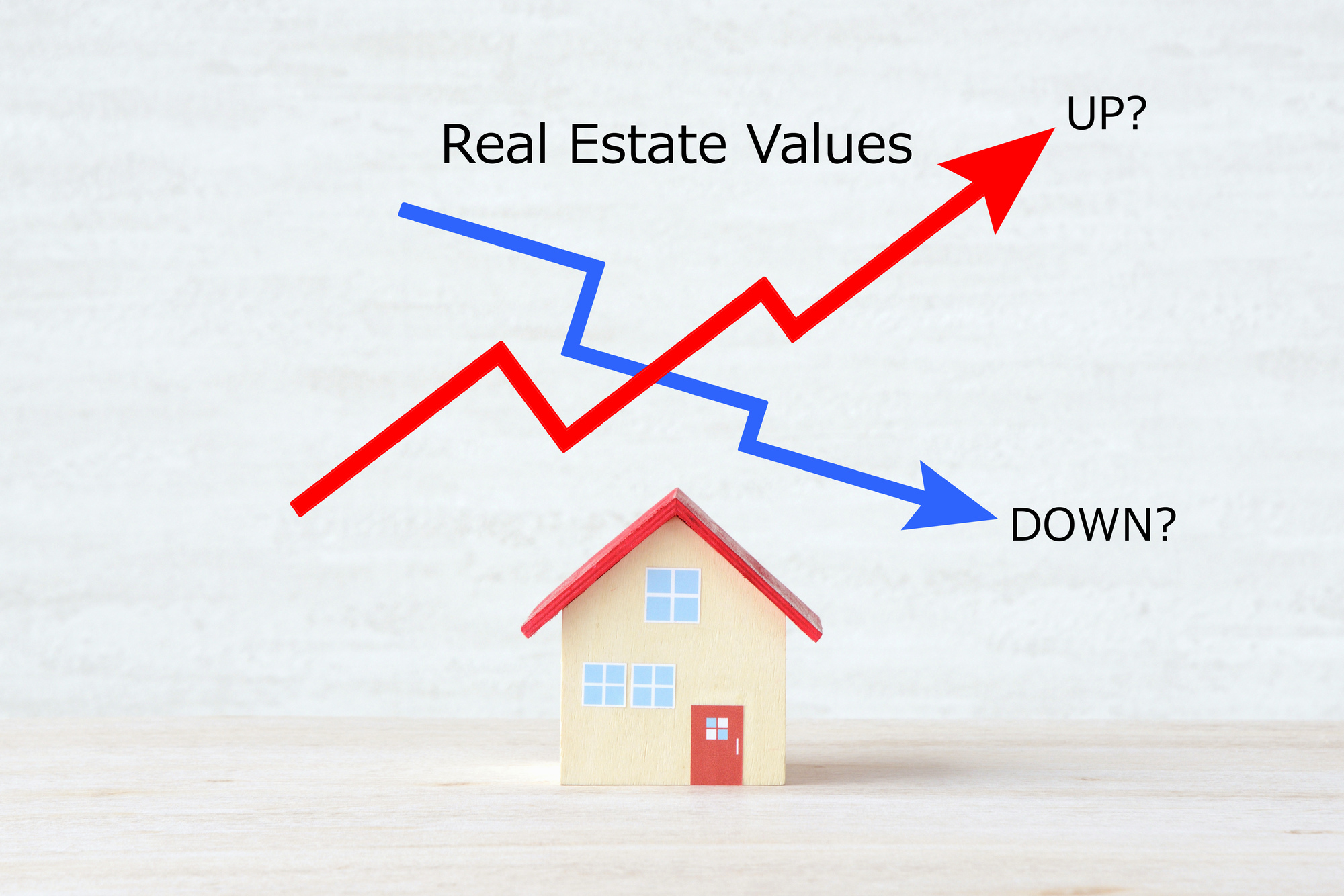公開日:2025.07.02 更新日:2025.09.16
再建築不可物件の全てを徹底解説。売却・活用・リスク回避のポイント
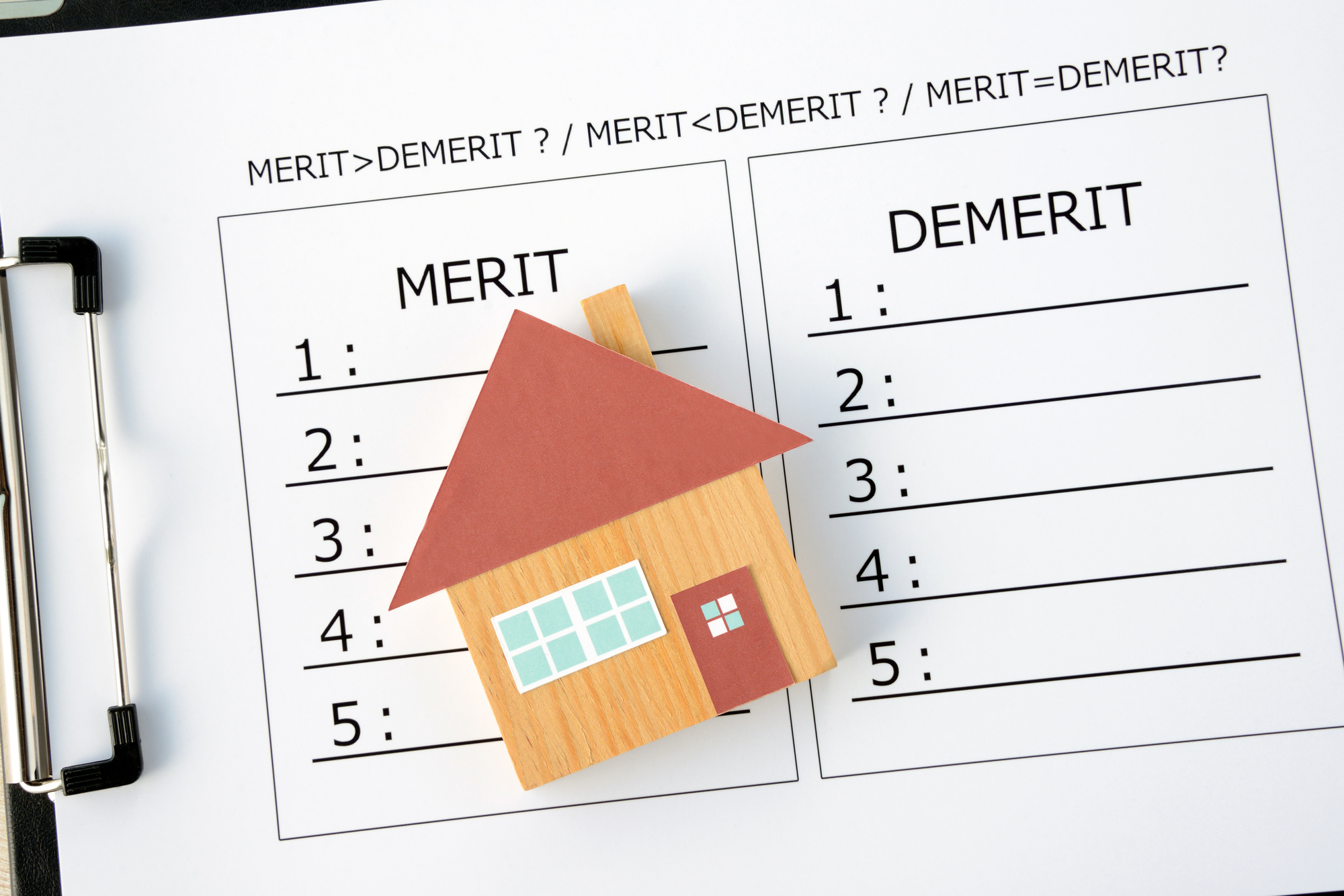
再建築不可物件とは、建築基準法などの法律要件を満たしていないため、原則として新たに建物を建てられない物件のこと。土地の形状や接道状況、市街化調整区域の制限など、さまざまな要因によって決まります。
本記事では、再建築不可物件の基本的な定義から売却・活用のポイント、相続や家族間承継で注意すべき点、リスク回避の具体策まで、分かりやすく解説します。
再建築不可物件とは?定義と特徴

まずは再建築不可物件の基本的な定義と、その背景となる「接道義務」や「市街化調整区域」との関係を確認しましょう。
再建築不可物件とは、建築基準法で定められた要件を満たしていないために、新しい建物を建てられない土地や建物の総称です。主に「接道義務を満たしていないケース」と「市街化調整区域に該当するケース」に分けられ、それぞれの法律制定以前に建てられた古い建物に多く見られます。
再建築不可物件は、購入費用が比較的割安になりやすく、投資用や倉庫・駐車場などの活用を視野に入れる方も増えています。一方で、税制面や価格相場にも大きく影響を与えるため、注意が必要です。また、将来的な建て替えや売却も困難になる可能性があるため、専門家にも相談しつつ慎重に検討するようにしましょう。
接道義務を満たしていないケース
建築基準法では、原則として幅員4m以上の道路に一定以上の長さで接していなければ、建物を建て替えできません。これを「接道義務」と呼びます。
再建築不可物件は、この接道義務を満たしていないために、新たな建築許可が下りない状況にあるものがほとんどです。道路と敷地境界の条件が昔から変わっておらず、改善も容易ではないケースも少なくありません。
実際にはセットバックや隣地との共有通路などで要件をクリアできる場合もありますが、手続きが複雑になるため、事前に専門家へ相談することが必須です。
市街化調整区域に該当するケース
市街化調整区域は、都市計画において将来的な開発を抑制することを目的としており、新築・増改築に厳しい制限がかかります。そのため、この区域内にある物件は再建築が難しくなる傾向があります。
特定の条件を満たすことで建て替えが認められるケースもありますが、実際は申請や許可のハードルが高く、多大な時間とコストを要します。売却や活用を検討する際には、市街化調整区域の制度をよく理解したうえで、最適な方法を検討しましょう。
再建築不可物件が抱えるリスクと問題点

再建築不可物件を所有・利用するうえで、具体的にどのようなリスクが考えられるのでしょうか?代表的なものを3つご紹介するので、さっそくチェックしていきましょう。
建て替えができない
再建築不可物件は、建物が老朽化しても新しく建て替えることができないというデメリットがあります。特に、耐震性能が低いなど、安全面や快適さに懸念がある物件に住み続けるのは、大きな不安要素となるでしょう。また、リフォームや修繕による改善も、法律上の制約があることから、できる範囲には限界があります。
そのため、購入や所有を検討する際には、長期的な視点で物件の状態を点検・把握し、必要な改修費用や保険加入などを含めた総合的な判断が不可欠です。
住宅ローン利用が困難
再建築不可物件は担保価値が低いとみなされるため、金融機関からの住宅ローン融資を受けづらい傾向にあります。融資額を大幅に減らされたり、条件が厳しく設定されたりすることも珍しくありません。
住宅ローンを組めない場合、現金一括など即金での取引が求められるため、購入はもちろん、売却やリフォーム、リノベーションを行うハードルが上がり、結果として流動性が低く、資金面での柔軟性が損なわれる恐れがあります。
地震や火災などの倒壊リスク
再建築不可物件に該当する古い建物は、耐震基準が現行の法律と比べて大幅に緩い場合が多く、大きな地震が起きた際に被害が拡大しやすいというリスクを抱えています。また、建物の構造や建材が旧式であるほど、火災によるダメージも大きくなりがちです。
これらを補強するために、建て替えや改修を試みても、法的な制約で十分な対応ができないため、長期的な懸念材料になるでしょう。
こうした災害リスクを一定程度緩和するには、火災保険や地震保険などの加入に加えて、可能な範囲での補強工事が必要です。ただし、どのような対応を取るべきかは、建築規制や費用対効果の観点を踏まえ、事前に専門家と十分に協議しておくことをおすすめします。
再建築不可物件を再建築可能にする方法

再建築不可物件でも条件次第で再建築が許可されることも。ここでは具体的な方法について解説します。
セットバックによる現行基準のクリア
セットバックとは、道路が狭いために接道義務を満たさない物件について、敷地の一部を道路として提供するように後退させる方法のこと。これにより、幅員4m以上の道路として認められれば建築許可の可能性が生まれます。
ただし、敷地が後退する分、実質的な土地面積が減る点や、セットバック後の土地の形が使いづらくなるというデメリットもあります。
また、行政側と協議しながら進める必要があるため、セットバックに伴う登記手続きや費用、そして周辺住民への理解醸成など、広範な準備が求められる点にも留意しておきましょう。
隣地を購入・借用して接道を確保
再建築不可物件の接道義務がわずかに不足している場合、隣接する土地の一部を購入したり借用したりすることで、道路への接道を確保できることがあります。
隣地所有者との交渉がうまく進めば、比較的短い期間で再建築可能に変えることも期待できるでしょう。しかし、土地の境界調整や費用面などクリアすべき課題も多くあります。
また、隣地が市街化調整区域や建蔽率・容積率など別の規制を受けている場合、思うように交渉が進まないこともあるため、事前の情報収集と法律確認が欠かせません。
43条但し書き道路の特例許可を得る
建築基準法43条の但し書きには、「通常の公道や私道以外でも特定の要件を満たせば道路としてみなせる」という特例があり、これを活用するのも有効な手段のひとつ。
敷地周辺のインフラ状況や安全性確保が前提となりますが、役所が道路と認めるための要件をクリアし、特定行政庁の許可を得られれば、建築可能な物件へ変えられる可能性が期待できるでしょう。
要件は地域の条例や自治体の方針によって異なるため、専門家や行政窓口に相談し、早い段階で可能性を把握しておくことが重要です。
再建築不可物件を売却する方法

再建築不可物件は、通常の物件より売却の難易度は高め。ただし、付加価値を高めるなど、工夫を凝らすことで買い手にとって魅力的な投資対象になり得ます。
ここでは、再建築不可物件の売却を成功させるポイントを見ていきましょう。
リフォームやリノベーションで価値を高める
既存の建物を大きく見直すことは難しくても、内装や水回りを中心にリフォームやリノベーションを実施すると、住みやすさを向上させることができます。見た目や設備レベルを最新に近づけるほか、家具を配置して生活イメージを沸かせる工夫も効果的です。
ただし、大掛かりなリノベーションには建築基準法の制限や費用が伴います。施工業者とよく相談し、改修後の市場価値と投資コストを慎重に比較するようにしましょう。
隣地所有者への売却打診
隣地所有者に売却を打診するのも方法のひとつ。隣地を購入することで敷地が広くなり、将来売却する際も高値で売却できる可能性が高まることから、売却物件の隣地が購入者となるケースが多く見られます。
特に隣地も再建築不可物件の場合、隣地所有者にとっては道路への接道条件などを改善できるメリットが生まれることも。隣地をまとめて再建築可能に変えることで投資価値が上がるため、交渉が円滑に進む可能性があります。
隣地がどのような規制や区域にあるか、相手方に購入意欲があるかなど事前にリサーチしたうえで、権利関係や費用分担を明確にし、信頼感を伴った提案を行うことが重要です。
訳あり物件専門の買取業者を利用
再建築不可物件など、訳あり物件を専門に扱う業者は、想定されるリスクや活用方法を十分に理解しているため、相場に即した価格で買い取ってもらえることがあります。一般的な不動産市況よりも価格は低くなる傾向がありますが、物件が長期間売れずに負担がかさんでいる場合や、急ぎで資金化したい場合には、有効な選択肢の一つとなるでしょう。
相続や家族間承継でのポイント
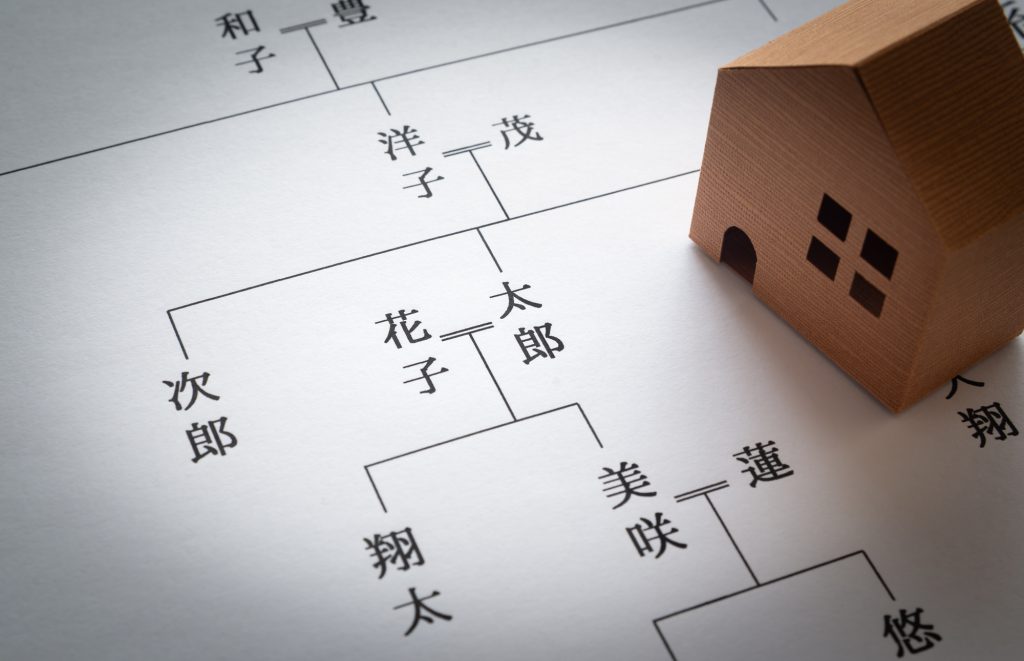
ここからは、再建築不可物件を相続・承継する際の注意点や必要な手続きについてご紹介します。
再建築不可物件を相続すると、老朽化や土地利用制限などさまざまな課題が同時に引き継がれるため、承継直後に予期せぬ出費やトラブルが生じないよう、しっかり対策を講じておきましょう。
相続放棄の判断とリスク
物件を持ち続ける経済的負担が大きい場合、相続そのものを放棄するのも選択肢のひとつ。相続放棄を行うと、今後の固定資産税や修繕費といった負担はなくなりますが、不動産そのものの将来的な価値の上昇を得られないリスクもあわせ持ちます。
相続放棄は法定期限内に手続きを進める必要があり、手続き不備があると意図せず相続することになる可能性もあるため、司法書士や弁護士へ相談しつつ、迅速かつ慎重に判断するようにしましょう。
名義変更や譲渡時の手続き
再建築不可物件を相続する場合、名義変更が必須。法務局での登記手続きや各種の書類作成が必要で、再建築不可物件の場合は、別途法定図面や道路状況の証明を求められることがあります。
また、税金面に関わる手続きも多く、相続税の申告や不動産取得税の減免措置のほか、譲渡の場合だと贈与税の対象になることも。適切な手続きを踏まないと、後々トラブルに発展する可能性もあるため、税理士など専門家に相談することをおすすめします。
まとめ・総括
再建築不可物件は、一般的な不動産売買と比べて安く手に入れられる一方、多くのリスクも内包しています。購入・相続いずれの場合でも、後から大きな問題に直面しないよう、事前に可能な対策を講じておくことが大切です。
リスクを十分に把握したうえで、物件の立地や経済的背景、将来の生活設計などを踏まえて総合的かつ戦略的に計画すれば、再建築不可物件も十分に活用可能な資産となり得るでしょう。
そのためには、専門家のアドバイスを参考にするのもひとつの手。空き家活用のプロである「アキサポ」では、再建不可物件をはじめとする訳あり物件の相談も承っています。活用方法についてはもちろん、買取や建て替え、建物管理など幅広いニーズに対応しているので、何から手をつけたらよいかわからない方も、まずは一度お問い合わせください。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。