公開日:2025.09.11 更新日:2025.07.29
遺産分割協議書とは?正しい作成方法と重要ポイントを徹底解説
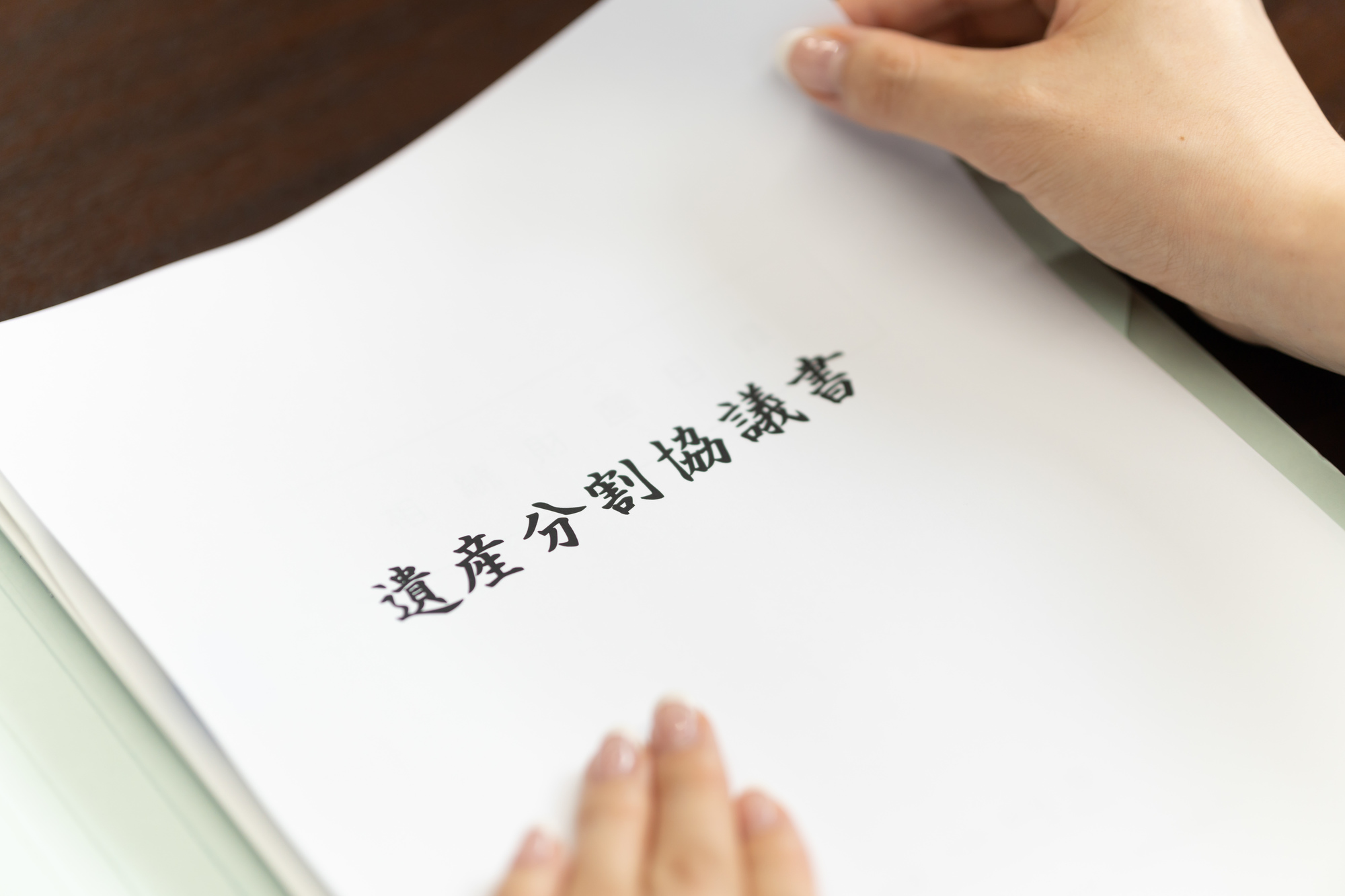
相続人が複数いる場合に、相続手続きで何かと必要になる遺産分割協議書ですが、多くの方は役割や作り方、どんな手続きに使うかなど、具体的な内容を把握できていない方が多いのが実情です。しかも、正しく作らないと財産の移動が進まないこともあるので、悩みの種になっている場合もあるでしょう。
そこでこの記事では、そんな不安を解消するために、遺産分割協議書の正しい作成方法や基礎知識のポイントを具体例とともにわかりやすく解説します。不動産・預金・株式・自動車といった資産別の書き方から、よくある失敗例、専門家に頼むべき場面まで、実際に役立つ情報を網羅しました。
目次
遺産分割協議書の基礎知識

遺産分割協議書とは、相続時に複数の相続人がいる場合に、財産をどのように分けるかについて話し合った「遺産分割協議」の内容をまとめた書類のことです。
通常、遺産分割の割合は民法に基づく「法定相続分」に基づいて決定されますが、その割合と異なる割合で遺産分割をしようとする際には遺産分割協議書が必要になります。
まずは、遺産分割協議書の役割やメリット、必要になるケースを見ていきましょう。
遺産分割協議書の役割と作成するメリット
遺産分割協議書の特に重要な役割は、協議の内容を明文化することで、相続人間のトラブルを予防することです。
分割割合を口頭で合意しただけでは、認識違いや意見の相違が起こりやすく、あとから「言った・言わない」の争いになる可能性もあります。そこで、相続人全員の合意のもとで協議書という「文書」として明文化することで、法的にも有効な証拠として残せます。
いわば遺産分割協議書は、遺産分割手続きの円滑化・紛争予防・税務対応の三本柱を支える書類といえるでしょう。
遺産分割協議が必要になるケースとは
以下のようなケースでは遺産分割協議が必要になります。
- 法定相続分と異なる割合で遺産分割を進めたい場合
- 遺言書が残されているが、その内容と異なる分け方を希望する場合
- 遺言書が残されており、遺言書に記載されていない財産が発見された場合
また、以下のような財産については、名義変更や手続きを行うために協議書の提出が求められます。
- 不動産の登記変更
- 株式や投資信託の名義変更
- 預貯金の払戻し手続き
- 自動車の名義変更
- 相続税の申告
作成前に知っておきたい準備ステップ

遺産分割協議書の基本を理解したところで、次に具体的な作成手順を見ていきましょう。ここでは、以下の4つのステップに分けて解説していきます。
- 相続人の確定
- 相続財産の洗い出し
- 遺言書の有無の確認と対応
- 分割内容の合意と協議書の作成
ステップ1|相続人の確定
最初にすべきことは、遺産分割協議書の作成に関わる法定相続人を正確に把握することです。被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本を取得し、法定相続人の範囲と順位に基づいて、該当する人を調査します。
主な確認事項は以下のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)をすべて取得する
- 相続人の範囲(配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹など)を確定する
- 養子縁組、認知、再婚、非嫡出子などがある場合は特に慎重に確認する
ステップ2|相続財産の洗い出し
次に相続の対象となる相続財産をすべて洗い出し、その全容を明らかにします。この作業では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めて調査していきます。なお、これらの財産を整理する際は、財産の種類や評価額、所在地、現在の名義などの情報を書き出しておきましょう。
主な対象は次のとおりです。
- 不動産
- 預貯金、株式、投資信託などの金融資産
- 自動車、貴金属、骨董品などの動産
- 借金、未払い金、連帯保証債務などの負債
ステップ3|遺言書の有無の確認と対応
財産と相続人が把握できたら、次に遺言書があるかを確認しましょう。以下に、遺言書の有無と主なパターンをまとめました。
- 公正証書遺言がある場合:原則その内容に従う
- 自筆証書遺言がある場合:家庭裁判所で「検認※」を受ける必要あり
- 一部の財産しか記載されていない場合:残りの財産について協議が必要になる
- 遺言がない場合:法定相続分を基に、相続人全員で協議を行う
なお、遺言書があっても、相続人全員の合意があれば別の分け方も可能です。意見が割れそうな場合は、早めに専門家を交えて協議を開始することをおすすめします。
※相続人に遺言の存在と内容を知らせると共に、遺言書の偽造や変造を防止するための手続き
ステップ4|分割内容の合意と協議書の作成
話し合いがまとまったら、最後にその内容を文書として書き起こします。遺産分割協議書は相続手続き全般の根拠となるため、全員のチェックのもと正確に作成しましょう。
作成時の注意点は以下のとおりです。
- 財産の内容は具体的に記載する
- 相続人全員の署名と実印の押印を行う
- 押印は全員が内容に納得してから行う
以上のステップがすべて完了したら遺産分割協議書の完成です。なお、法務局や運輸支局などに提出する際に原本を求められることがあるので、必要な部数(提出先への提出用、相続人各自の保管用など)の原本を作成しておきましょう。
遺産分割協議書の具体的な作成方法

遺産分割協議書を実際に作成する際には、内容の正確性はもちろん、書き洩らしもないように作成する必要があります。書面に不備があると、手続きが差し戻されたり合意が無効と判断されたりする可能性もあります。
そこでここでは、遺産分割協議書作成に関して、特に気を付けるべきポイントを紹介します。
記載すべき基本情報と書き方のポイント
協議書に記載すべき内容は、主に以下の2点です。
相続人全員の情報
- 氏名、住所を正確に記載する
- 同姓同名の場合は、生年月日を補記することで誤認を防止する
分割対象となる財産の明細
- 不動産:登記事項証明書に基づき「所在地・地番・地目・面積・登記番号」など
- 預貯金:銀行名・支店名・口座番号
- 株式や車両など:銘柄・証券会社名、または車検証の情報など
全体のポイントとしては「誰が、どの財産を、どのように取得するのか」を一目でわかる形にすることです。これらの点が曖昧だと、書面から分割割合が読み取れずに手続きが保留される恐れがあります。
ページ数が複数にわたる場合の体裁と押印の注意
協議書が2ページ以上に及ぶ場合には、ページとページの間にまたがって相続人の印鑑を押すことで文書としての一体性を担保し、差し替えや改ざんを防止する「契印(けいいん)」が必要になります。
契印を押す際のポイントは以下の2点です。
- 各ページ間に契印を押す(通常、実印を使用)
- 全ページに通し番号を振る
また、相続人の情報を記載するページは、次の要件を満たすように作成します。
- 相続人全員の名前と住所を正しく記載し、実印を押印する
- 各人の印鑑証明書を添付する
- 書類に間違いや加筆修正がないか、全員で最終確認をする
なお、提出先によっては押印の位置や余白、添付書類などが指定されている場合があります。あらかじめ提出先に問い合わせてから作成することをおすすめします。
資産別の遺産分割協議書作成のポイントと手続き

遺産分割協議書は不動産・預貯金・株式・自動車など、資産の種類に応じて、それぞれ必要な情報を盛り込んで作成する必要があります。さらに提出書類も変わってくるので、複数種類の資産を扱う場合は混乱しがちかもしれません。
そこでここでは、資産の種類別に遺産分割協議書作成のポイントや提出書類などを解説します。
不動産相続登記で必要な書類と手続き
土地や建物などの不動産の名義変更をするには、法務局で「相続登記」の申請が必要です。その際提出する協議書には以下のような内容を記載します。
- 登記簿に基づいた不動産の「所在地・地番・種類・面積」
- 共有する場合は持分割合を記載する
このとき複数の不動産がある場合は、協議書に一覧形式で記載し、どの財産を誰が相続するかを明示しておきましょう。
また、提出書類には以下のようなものが必要です。
- 登記申請書(法務局所定の様式)
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・住民票の除票
- 相続人全員の住民票・印鑑証明書
- 固定資産税明細書
など
ちなみに、2024年4月から相続登記が義務化されており、相続開始から3年以内に手続きを行わなければ過料の対象となります。できるだけ早期に着手しましょう。
預貯金の相続と金融機関での手続き
銀行預金を相続する際には、金融機関ごとに定められた所定の手続きに従って払い戻しを進めていきます。金融機関ごとに書式や手続きが異なるので、事前に確認をしてから進めましょう。協議書に記載すべきポイントは以下のとおりです。
- 銀行名・支店名・口座種別・口座番号など
- 金融資産を相続する人物
また、一般的な提出書類には以下のようなものが必要です。
- 遺産分割協議書
- 被相続人・相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 銀行所定の相続届、残高証明書
など
株式・投資信託の名義変更と配当金の取り扱い
株式や投資信託を相続するには、証券会社で名義変更手続きを行ったのちに相続人の証券口座に移動する必要があります。取扱商品や口座の種類によって、必要書類や手続きが異なるため、あらかじめ証券会社に確認しておきましょう。
まず、遺産分割協議書には、次のような内容を記載します。
- 銘柄名・証券会社名・口座番号など
- 未受領の配当金や分配金の扱い
- 株式の評価額や分割のルール
また、一般的な提出書類には以下のようなものがあります。
- 遺産分割協議書
- 被相続人・相続人の戸籍謄本
- 印鑑証明書
- 本人確認書類
- 証券会社所定の名義変更申請書
など
ちなみに、株式・投資信託は時間で価値が変動するので、遺産分割協議書作成の協議を行う際には、資産価値の変動リスクを踏まえて、売却か継続保有かという取得後の保有方針も整理しておきましょう。
自動車の名義変更や売却時の注意点
自動車を相続するためには、運輸支局での名義変更手続きが必要です。このとき、ナンバープレートの管轄地域が異なる場合には、追加手続きが必要になることもあります。
運輸支局に提出する協議書に記載すべきポイントは以下のとおりです。
- 名義変更をする自動車の車種・ナンバー・車台番号など
- 取得する相続人
また、一般的に必要な提出書類は以下のとおりです。
- 自動車検査証
- 被相続人の除籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 運輸支局所定の申請書類
など
ちなみに、車は保有しているだけで維持費や税金がかかるため、相続後のトラブルを防ぐためにも、あらかじめ使用・売却・廃車の判断を協議しておくとよいでしょう。
協議書作成に関するリスクと対策
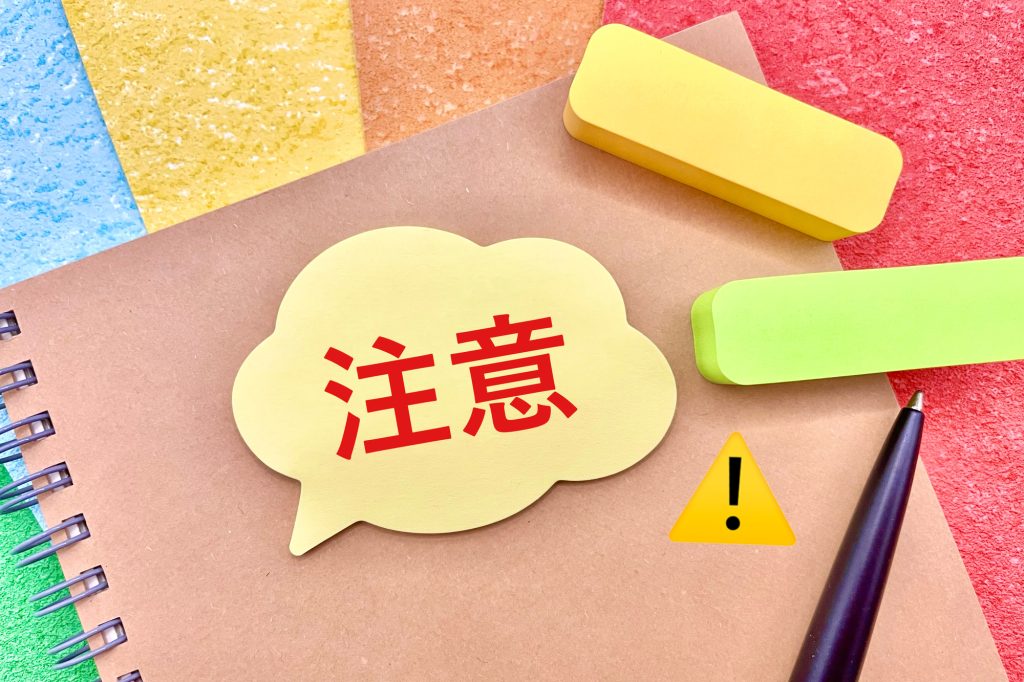
ここからは、協議書の作成に関する代表的なリスクを以下の3つに分けて整理し、どのように対処すべきかを解説します。
- 協議書を作成しなかった場合
- あとから財産が見つかった場合
- 相続人の間で意見が合わなかった場合
協議書に関してトラブルが起こると手続きが止まってしまうだけでなく、名義変更ができず財産が凍結されたり、相続人同士の間で意見の食い違いが生じてトラブルに発展したりする恐れもあります。あらかじめ、よくあるトラブルを理解しておき、先手を打ってリスクを減らしておきましょう。
協議書がないと起こりやすいトラブル
そもそも協議書を作成しなかった場合は、どのようなリスクがあるのでしょうか?たとえば、不動産の相続登記、預貯金や株式の名義変更、金融機関からの払い戻しなど、多くの場面で「遺産分割協議書の提出」が求められます。書面がない場合、次のような問題が生じます。
- 不動産・預金・株式などの名義変更が進まず、財産が「宙に浮いた状態」になる
- 相続人間での合意が曖昧なままになり、「言った・言わない」の争いに発展する
- 時間の経過とともに、相続人の連絡先や意思確認が困難になる
なお、法務局や金融機関、証券会社などでは、財産の名義変更に遺産分割協議書の提出が必須となるケースが一般的です。書面がないと申請が受理されず、相続財産を使えない状態が続く恐れもあります。
後から財産が見つかった場合の対応
相続手続きの途中で、遺産に含まれるはずの財産が新たに判明することは珍しくありません。これらの財産は既存の協議書に記載されていないため、以下のような対応が必要になります。
- 相続人全員で再度協議を行い、新たな協議書を作成する
- 追加された財産の分割方法を明記し、改めて全員の署名・押印を行う
このとき、絶対に避けることが「少額だから見つけた人がもらってしまう」ことです。財産の額が少なくても、相続人の間に不公平感が生じれば、その後の関係悪化につながる恐れがあります。親族同士の関係を良好に保つためにも手続きは厳正かつ公正に行いましょう。
相続人間で意見が合わないときの対処法
財産に対する価値観は相続人によって違うものであり、そのズレが大きいと協議がまとまらなくなったり、対立に発展して手続きが進まなくなったりする恐れがあります。
このような場合には、以下のように冷静かつ具体的な対応が効果的です。
- 司法書士や弁護士など、相続に詳しい第三者を交えて話し合いを進める
- 各人の立場を冷静に整理し、法的根拠に基づいたアドバイスを受ける
- 一度協議が膠着した場合は、調停や代理人による対応も視野に入れる
ここで大切なのは、専門家を間に挟んで感情論ではない建設的な解決策を探すことです。対立は時間と共に深刻化することもあるので、解決が難しいと思ったら早めに相談するのがおすすめです。
司法書士・弁護士・税理士に依頼すべきケースと役割、費用相場依頼先の選び方

遺産分割協議書の作成を相談できる代表的な専門家は、司法書士、弁護士、税理士です。それぞれ法律に基づいて対応できる範囲が決められているので、ケースに応じて最適な専門家を選びましょう。
司法書士、弁護士、税理士に依頼すべきケースと役割、費用相場は以下のとおりです。
| 専門家 | 主な対応業務 | 依頼すべきケース | 費用の目安 |
| 司法書士 | 相続登記、協議書作成の助言、戸籍の収集・整理 | 不動産を相続する、相続人が多く戸籍確認が複雑な場合 | 協議書作成:3万~10万円登記:登録免許税+数万円~十数万円 |
| 弁護士 | 相続争いへの対応、代理交渉、調停・訴訟 | 相続人間で意見が対立している場合、調停が必要な場合 | 着手金+成功報酬(事案により変動) |
| 税理士 | 相続税の申告、評価、税務対策 | 相続財産が基礎控除を超える場合、節税を検討したい場合 | 相続財産規模により10万~数十万円程度 |
また、専門家を選ぶ際には、相続案件の実績や対応の丁寧さ、説明のわかりやすさ、費用体系の明確さなどをチェックしましょう。なるべく自分の困りごとに近い案件の経験が豊富な専門家を選ぶと安心です。
まとめ
ここまで見たとおり、遺産分割協議書は必要な手続きが多いだけでなく、作成しておくことでさまざまなトラブルを防止する役割もあることが分かりました。特に、相続財産が複雑・高額であったり、相続人同士で意見の違いがある場合には、早めに専門家の力を借りて作成しておきましょう。
相続は誰にとっても避けて通れない手続きです。大切な人の財産を適切に引き継ぎ、親族の関係を円満に保つためにも、全員が納得する遺産分割協議書を整えておきましょう。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。








