公開日:2025.08.30 更新日:2025.08.04
公正証書遺言とは?作成手順・費用・メリットまで徹底解説!相続トラブルを防ぐ方法

相続トラブルは誰にでも起こりうるもの。特に不動産を所有している場合、遺産分割をめぐり揉めることは決して珍しくありません。そんなとき、自筆証書遺言と比べて法的効力が高く、被相続人の意思を法的にしっかりと伝える手段として有効なのが公正証書遺言です。公正証書遺言の基本から作成手順、費用、そしてその法的効力まで、重要なポイントをお伝えします。
目次
公正証書遺言とは?基本をわかりやすく解説
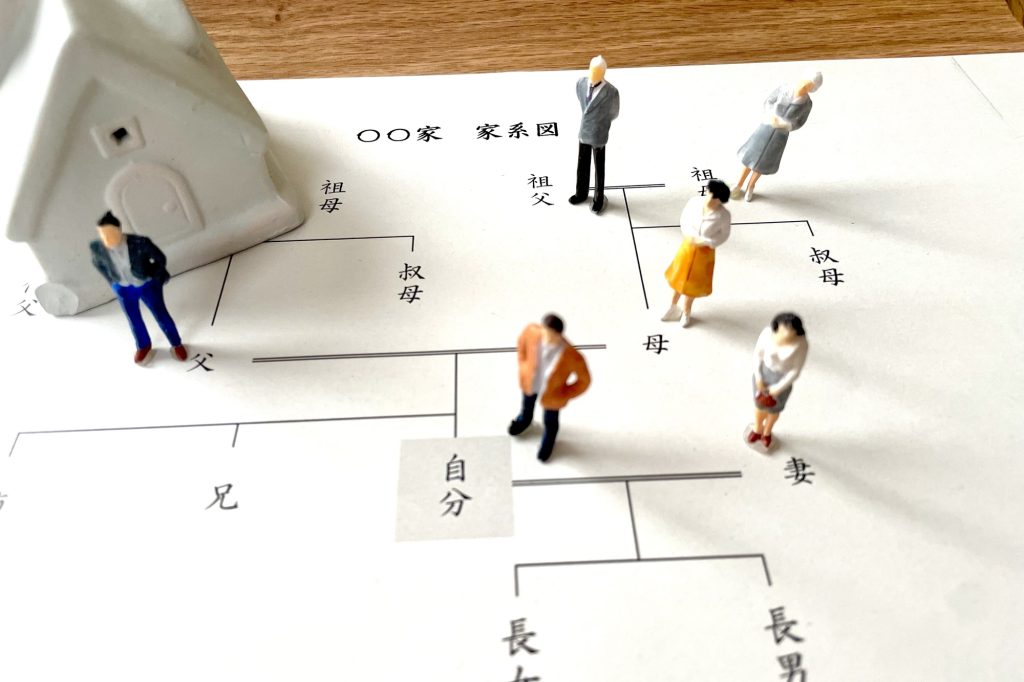
自分の意思をきちんと遺したいと考える方にとって、遺言書の作成は大切な準備のひとつ。なかでも、公証人が関与し法的効力の高い「公正証書遺言」は、安心感のある手続きです。まずは自筆証書遺言との違いや、公正証書遺言の作成の流れをご紹介します。
そもそも遺言書にはどんな種類がある?
民法では、主に3種類の遺言書が定められています。もっとも手軽に作成でき、自筆で全文を書くのが「自筆証書遺言」です。緊急時など特別な状況下で作成される「秘密証書遺言」もありますが、一般的にはあまり利用されていません。
そして法的効力が高く、家庭裁判所の検認手続きが不要なため相続がスムーズに進むのが「公正証書遺言」です。相続や遺産分割の場面でもトラブルを防ぎやすいことから、公正証書遺言の作成を選ぶ方が増えています。
公正証書遺言と自筆証書遺言との違い
自筆証書遺言と公正証書遺言では、作成方法や法的効力に大きな違いがあります。自筆証書遺言は費用をかけず自分で作成できますが、日付や氏名を正確に記載したうえで押印するなど、民法で定められた厳格な方式を遵守する必要があります。相続時には家庭裁判所での検認手続きが必要で、形式不備による無効のリスクもあります。
対して公正証書遺言は、専門家である公証人が関与するため、形式面での安心感があります。遺産分割や相続トラブルを防ぐためにも、公正証書遺言の作成は有効な手段といえるでしょう。
公正証書遺言の法的効力が高いのはなぜ?
公正証書遺言が他の遺言書と比べて法的効力が高いとされるのは、公証人という法律の専門家が作成に関与するためです。公証人が遺言者の意思や判断能力を確認し、法律に則った内容で文書化することで、形式不備などによる無効のリスクが大幅に減ります。
さらに、証人2名の立ち会いが義務づけられているため、内容の正当性を客観的に証明できるのも大きな特徴。家庭裁判所での検認手続きも不要なので、相続や遺産分割をスムーズに進めたい方にとって、公正証書遺言の作成は非常に有効な手段といえます。
公正証書遺言を作成するメリットとデメリット

相続に備えて遺言書を残したいと考える方にとって、公正証書遺言は法的効力が高く安心できる選択肢です。一方で、費用や手続きに注意すべき点もあります。ここでは、公正証書遺言を作成することの具体的なメリットとデメリットについて、それぞれ詳しく解説していきます。
メリット① 遺言無効のリスクが低い
公正証書遺言の作成は、遺言書が無効になるリスクを限りなく抑えられる点が大きなメリットです。
公証人が法的要件を厳格に確認しながら作成を進めるため、形式不備による無効化の心配はほとんどありません。自筆証書遺言で見られる日付漏れや押印ミスといったリスクも回避できます。
また、証人の立ち会いや遺言者の意思能力の確認も行われるため、相続開始後に遺言の無効を主張されにくく、遺産分割の場でも有力な証拠となります。
メリット② 紛失や改ざんの心配がない
公正証書遺言は、公正証書として作成されることで高い法的効力を持ち、原本は公証役場で厳重に保管されます。そのため、火災や災害による紛失、第三者による改ざんといったリスクを避けられる点が大きな特徴です。
遺言者や相続人が原本を紛失した場合でも、公証役場に請求すれば謄本を発行してもらうことが可能です。全国の公証役場を結ぶ検索システムにより、相続時に遺言書が確実に見つかる体制も整っており、遺産分割を円滑に進めるうえで非常に安心できる方法といえるでしょう。
デメリット① 費用がかかる
公正証書遺言の作成には、一定の費用がかかる点がデメリットとして挙げられます。自筆証書遺言と異なり、遺産の総額や相続人の数、内容の複雑さによって費用が変動するのが特徴です。さらに、証人を依頼する場合には、別途謝礼が必要となることもあります。
自筆証書遺言と比べると初期費用は高くなりますが、将来の相続トラブル防止といった点では大きな安心感につながります。ご自身の状況に照らし合わせて判断することが重要です。
デメリット② 証人が必要
公正証書遺言の作成には、証人2名の立ち会いが法律で義務付けられており、これが負担に感じられる場合もあります。証人は遺言書の内容を把握するため、相続に関するプライバシーを重視される方には心理的なハードルとなることも。
また相続人やその配偶者、未成年者は証人になれないため、適切な人選が必要です。知人への依頼が難しい場合は、公証役場や弁護士事務所を通じて証人を手配できますが、追加費用が発生する点も留意が必要です。公正証書遺言の作成を円滑に進めるためにも、信頼できる証人を事前に確保しておくことが望ましいでしょう。
公正証書遺言の作成手順と必要なもの

公正証書遺言の作成は複雑そうと感じるかもしれませんが、手順をひとつずつ確認していけば、決して難しいことではありません。公証人とのやり取りや必要書類を事前に確認しておくことで、公正証書遺言の作成はスムーズに進められます。
準備すべき書類と情報
公正証書遺言の作成には、遺言書の内容に基づいた各種書類の準備が欠かせません。具体的には、遺言者の印鑑証明書(発行から3か月以内)と実印をはじめ、相続人を確認するための戸籍謄本、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し、有価証券に関する証明書類などが必要です。
遺言執行者を指定する場合は、その方の住民票の用意も忘れずに。相続分や遺産分割の内容を整理し、公証人手数料の算定に必要な全財産の評価額も事前に把握しておくと安心です。書類の収集には時間がかかるため、公正証書遺言の作成は早めに準備を進めることをおすすめします。
公証人との打ち合わせと証人の手配
必要書類が揃ったら、最寄りの公証役場に連絡し、公正証書遺言の作成に向けて公証人との打ち合わせを予約します。
初回の打ち合わせでは、遺言書の内容や財産の詳細をもとに、公証人が法的効力を持たせるための確認や助言を行い、必要に応じて修正案も提示されます。同時に、証人2名の手配も必要です。適切な人が見つからない場合は、公証役場に紹介を依頼することもできます。
作成完了までの流れと所要時間
公証人との打ち合わせで遺言書の内容が確定したら、公正証書遺言の作成日を予約します。当日は遺言者、公証人、証人2名が公証役場に集まり、公証人が内容を読み上げて意思確認を行います。その後、遺言者と証人が署名・押印し、公証人が署名・押印することで、公正証書遺言が正式に完成します。
所要時間は30分〜1時間程度。正本と謄本は当日中に受け取れます。原本は公証役場に保管され、遺言検索システムにも登録されるため、確実な公正証書遺言の作成につながります。
公正証書遺言の費用相場と計算方法

公正証書遺言の作成には、自筆証書遺言と異なり、公証人手数料や証人への報酬といったいくつかの費用がかかります。財産額や内容によって費用は異なりますが、あらかじめ相場や計算方法を知っておくことで、安心して準備が進められるでしょう。
財産額に応じた手数料の目安
公正証書遺言の作成にかかる公証人手数料は、遺産の目的価額に応じて、公証人手数料令で定められた額が適用されます。
たとえば、目的価額が100万円以下で5,000円、1,000万円以下で1万7,000円、1億円以下で4万3,000円が基本手数料になります。相続人が複数いる場合は、相続分ごとに手数料が計算される点に注意が必要です。これに加えて、用紙代や正本・謄本の交付手数料などが別途発生します。正確な金額は、公証人に前もって確認しておくと手続きがスムーズでしょう。
証人依頼費用や弁護士報酬は?
公正証書遺言の作成には2名以上の証人が必要です。一般的に、一人あたり数千円から1万円程度の証人費用が発生します。公証役場で証人を紹介してもらう場合も、同様の費用がかかります。
あわせて相続税について税理士に相談する場合は、専門家への報酬が別途発生します。これらの費用は、依頼する専門家やサービスの内容によって大きく異なるため、事前に見積もりを取るなどして確認しましょう。
費用を抑えるためのポイント
公正証書遺言の作成費用を抑えるには、まず必要書類を自分で準備し、遺言内容をあらかじめ整理しておくことが有効。弁護士に依頼せず、公証人と直接やり取りすることで、専門家報酬を節約できます。
さらに弁護士や司法書士に依頼する場合でも、無料相談を活用したり、複数の事務所から見積もりを取ったりすることで、費用を比較検討し、納得のいくサービスを選ぶことができます。
作成後の保管・変更・撤回はどうする?

公正証書遺言を作成したあとも、内容の見直しや保管方法について知っておくことが大切です。相続や遺産分割に備えるうえで、ライフステージや財産状況の変化によって遺言書を変更・撤回するケースも十分にあり得ます。ここでは、作成後の基本的な対応について解説します。
保管方法と「遺言検索システム」について
公正証書遺言の原本は、作成した公証役場で厳重に保管されます。遺言者には正本と謄本が交付され、自宅や銀行の貸金庫での保管が一般的です。万が一紛失した場合でも、公証役場で再発行が可能で、手数料は250円程度です。
さらに、全国の公証役場では「遺言検索システム」が導入されています。平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、相続人が戸籍謄本などを提示することで確認できます。
遺言の内容を変更・撤回するには
公正証書遺言の内容を変更したい場合は、新たに遺言書を作成し直す必要があります。遺言は何度でも作成可能で、法的には日付の新しいものが優先され、以前の遺言と内容が抵触する部分については、以前の遺言は撤回されたものとみなされます。内容の一部を修正したい場合でも、全体を改めて作成するのが確実です。
遺言を撤回する際は、その旨を明記した新しい遺言書を作成するか、公正証書で撤回の意思を示します。ただし、公証役場に保管されている原本は撤回後も残るため、将来的なトラブルを避けるためにも、撤回の意思を明確に表示しておくことが重要です。変更や撤回にも、公証人手数料や証人報酬が発生しますので、事前に確認しておきましょう。
公正証書遺言の有効期限はある?
公正証書遺言には有効期限が設けられていません。一度作成すれば、遺言者が死亡するまで、または新たな遺言書で撤回されるまで効力を持ち続けます。
ただし、相続人の死亡や出生、不動産の売却など、家庭状況や財産内容の変化によって、遺言内容の見直しが必要になることも。また、相続や遺産分割に関わる法律が改正されると、遺言書の法的効力や内容が想定とずれる可能性もあります。
こうしたリスクを避けるためにも、3〜5年に一度は内容を確認し、公正証書遺言を見直しておくことが大切です。
公正証書遺言が役立つケースとは?

相続では思わぬトラブルが起こることもあります。特に遺産分割が複雑な場合や、特定の相続人に意思を伝えたいときには、公正証書遺言の作成が有効です。どのような場面で公正証書遺言が有効なのか、具体的な状況を確認しましょう。
相続人同士の争いを防ぎたいとき
相続人同士の関係が複雑だったり、過去に財産をめぐるトラブルがあったりする場合は、公正証書遺言の作成が特に有効です。法的効力の高い遺言書を残すことで、感情的な対立を避け、客観的な基準に基づいた遺産分割が可能になります。
相続人に行方不明者や判断能力に不安のある方がいるケースでは、遺産分割協議が難航することもありますが、公正証書遺言があれば家庭裁判所での検認手続きは不要です。さらに遺言執行者を指定しておくことで、相続人同士の直接的なやり取りを最小限に抑えることができます。
特定の相続人に多く残したいとき
公正証書遺言の作成は、長男に事業を継がせるために多くの財産を残したい、介護を担った子どもに感謝の気持ちを込めて多めに相続させたい、といった希望があるケースにも適しています。
民法上は遺留分の制約があるものの、その範囲内であれば遺産の配分に個別の意思を反映させることが可能です。公証人が関与することで法的効力も高まり、家庭裁判所の検認手続きも不要となるため、遺産分割を円滑に進めやすくなります。
空き家や不動産をスムーズに相続させたいとき
自宅や収益物件などの不動産は、相続財産のなかでも特に遺産分割が難しい資産です。誰が相続するか、売却して分配するかといった意見で対立しやすく、トラブルに発展するケースも少なくありません。
そこで有効なのが、公正証書遺言の作成です。公正証書遺言で相続人を明確に指定すれば、名義変更手続きが円滑に進み、売却や賃貸管理の方針、収益の分配方法なども記載できるため、将来的な空き家リスクを減らすことができます。
よくある質問Q&A【公正証書遺言編】

公正証書遺言の作成を検討するなかで、不安や疑問が出てくる方も多いはず。証人の選び方、家族への秘匿性、費用対効果など、実際の作成前に知っておきたい重要なポイントを抜粋してご紹介します。
証人は誰でもいい?親族でもOK?
証人は誰でもなれるわけではなく、一定の条件があります。公正証書遺言の作成において証人になれるのは18歳以上の成年者に限られ、推定相続人や受遺者、その配偶者、直系血族(子ども、孫、父母など)、そして未成年者は対象外となります。通常は、信頼できる友人や知人、職場の同僚などに依頼するケースが多いでしょう。適切な証人が見つからない場合は、公証役場での紹介も可能です。
作成した遺言は家族に知られる?
作成した公正証書遺言は、遺言者が話さない限り、家族に知られることは基本的にありません。公証人や証人には守秘義務があるため、遺言の作成内容が外部に漏れる心配はほとんどないといえるでしょう。
ただし、相続が開始されると、遺言検索システムを通じて相続人が遺言書の存在を確認できます。生前に内容を家族へ伝えるかどうかは遺言者の判断によりますが、特に法定相続分と異なる内容の場合は、付言事項に思いを記しておくと理解が得られやすくなります。
秘密を保ちつつ相続を円滑に進めたい場合は、公正証書遺言の作成とあわせて、信頼できる遺言執行者の指定も検討しましょう。
費用をかけてでも作成すべきケースは?
財産額が数千万円以上ある場合や、相続人同士の関係が複雑な場合、公正証書遺言の作成が特に有効です。不動産や事業など分割が難しい財産があるときは、明確な遺言書が遺産分割を円滑に進める助けとなります。
また、自筆証書遺言が無効になるリスクを避けたい方にも適しています。再婚や認知症の相続人がいる家庭、遺言執行者を指定したい場合なども、公正証書による確実な意思表示が重要です。費用は発生しますが、将来的な安心を得るための大切な備えと考えることもできるでしょう。
大切な家族と未来を守る公正証書遺言
公正証書遺言は、被相続人の大切な意思を確実に未来へ繋ぎ、家族間の相続トラブルを防ぐ有効な手段です。専門家である公証人が関与することで、法的効力の高い遺言書を安心して作成できます。費用や証人の確認といった事前準備もありますが、それ以上に得られる安心感は計り知れません。
もし、将来に不安を感じているという方は、ぜひアキサポの無料相談をご活用ください。今できることから始めてみませんか?
公正証書遺言の作成を検討している方へ|アキサポの無料サポートをご活用ください
公正証書遺言の作成は、確実で安心な財産承継を実現します。しかし遺言書の作成は専門的な知識が必要で、一人で進めるには不安も多いはず。アキサポなら、そんな不安を解消し、最適な相続対策をサポートいたします。
空き家や不動産が絡む相続は、専門サポートでスムーズに
空き家や収益物件が関係する相続では、公正証書遺言の作成を含めた専門的な対応が重要です。アキサポでは、公証人との連携をはじめ、相続後の不動産管理や遺産分割まで丁寧にお手伝い。遺言書で不動産の処分方針を明確にしておくことで、家庭裁判所での手続きや相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
初回相談は無料|何から始めればいいかわからない方もご安心を
公正証書遺言の作成に興味はあるけれど、何から始めればいいのか分からないという声は少なくありません。アキサポでは、そんな不安を抱える方に向けて無料の初回相談を実施しています。相続や遺産分割に関するご希望を丁寧に伺い、公正証書遺言書と自筆証書遺言の違いや費用感、公証人とのやりとり、証人の選び方などもご案内します。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。








