公開日:2025.08.29 更新日:2025.08.04
固定資産税評価額とは?仕組み・計算方法・活用シーンまでわかりやすく解説
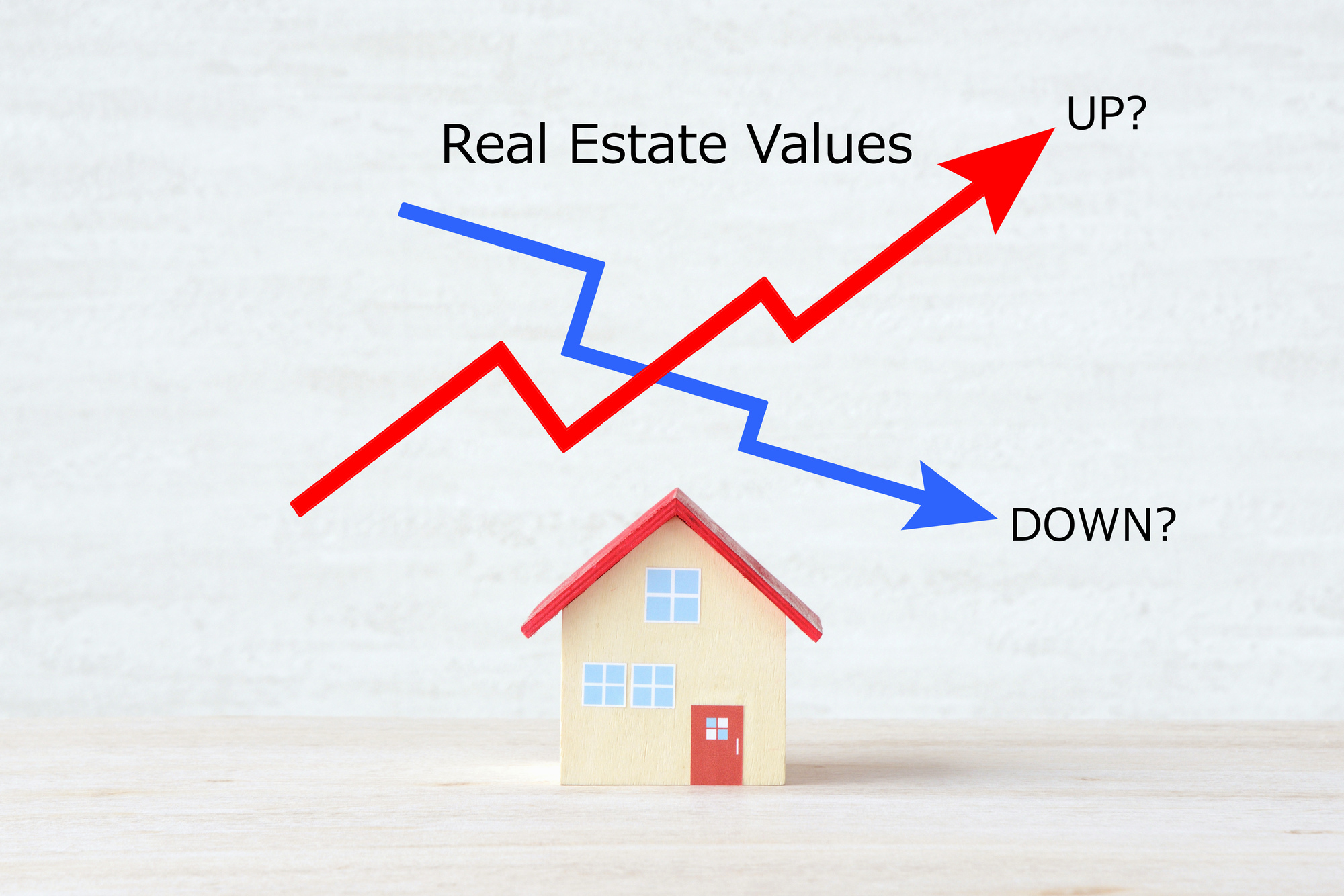
「実家が空き家になったけど、固定資産税ってどうなるの?」「空き家を活用したいけど、まず何を調べればいいんだろう?」そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事では固定資産税評価額の基本から、その仕組み、計算方法、そして空き家活用における評価額の重要性まで解説します。
目次
固定資産税評価額とは?基本の仕組みを理解しよう

まずは固定資産税評価額の基本から解説。課税標準との関係や時価との違い、「評価替え」と呼ばれる3年ごとに行われる見直しの仕組みまで、知っておきたいポイントを順番にチェックしていきましょう。
固定資産税の根拠となる「課税標準」の役割
固定資産税評価額は、固定資産税を算出するための基準となる金額です。ただし、実際の税額はこの評価額そのものではなく、住宅用地の特例などを適用した「課税標準額」に基づいて計算されます。
たとえば、200㎡以下の小規模住宅用地であれば、評価額の6分の1が課税標準額に。税額は「課税標準額×税率(原則1.4%)」で決まり、特例によって税負担が軽くなる仕組みになっています。
混同しがち?時価や公示価格との違い
固定資産税評価額は、市場で実際に売買される「時価」とは異なる基準で算出される金額です。一般的には、評価額は時価の7割程度が目安とされています。さらに、相続税の算出に使われる「路線価」や、土地取引の参考となる「公示価格」ともそれぞれ算出方法や目的が異なります。
これらの価格は類似しているものの役割が異なるため、混同すると判断を誤る可能性も。空き家の売却や相続を考えるうえで、各価格の違いをきちんと理解しておくことが大切です。
評価替えとは何か?3年ごとの見直し
「評価替え」とは、固定資産税評価額を3年ごとに見直す制度のこと。これは、地価の変動や建物の経年劣化といった変化を反映するためのもので、次回の実施は2027年です。
評価替えが行われる年を「基準年度」と呼び、その後の3年間は、原則として同じ評価額が適用されます。ただし、地価が著しく下落した場合や、新築・増改築といった資産の変動があった場合は、基準年度以外でも見直しが入ることも。この仕組みにより、税負担が急激に変わるのを防ぎつつ、公平な課税が保たれています。
固定資産税評価額の調べ方と確認方法

固定資産税評価額を調べるには、いくつかの確認方法があります。ここからは、その手順を丁寧にご紹介しながら、土地の種類による評価の違いや相続にも影響する路線価との関係性についてもあわせて解説していきます。
評価額はどこで確認できる?役所・納税通知書・固定資産評価証明書
固定資産税評価額を調べるには、主に以下の方法があります。用途やタイミングに応じて使い分けましょう。
1. 固定資産税の評価通知書を確認する
もっとも確実なのが、毎年春ごろに自宅に届く「固定資産税納税通知書」に同封される「固定資産評価証明書」または「課税明細書」です。自治体から自動的に送付されるため、最新の評価額を手軽に確認できます。
2. 市区町村役場での縦覧を確認する
所有者本人であれば、4月1日〜5月31日の「縦覧期間」に役所の固定資産課税台帳で無料で確認できます。
3. 評価額証明書を取得する
手元にない場合や相続・売却時に第三者へ提示したい場合、急ぎの場合や最新情報が必要なときは、「固定資産評価証明書」(手数料300円程度)を取得する方法もあります。市区町村役場の窓口や郵送申請で入手でき、手数料は1通300円程度です。
なお、登記事項証明書(旧称:登記簿謄本)では、固定資産税評価額そのものの確認はできません。登記簿謄本に記載されている「不動産の価額」は、登記時に登録免許税を算出するための基準であり、固定資産税評価額とは異なるため注意が必要です。
住宅地・農地・商業地で評価はどう違う?
土地の固定資産税評価額は、住宅地・農地・商業地といった用途によって算出方法が異なります。
住宅地は路線価方式などで評価され、土地の形や道路との接し方も反映されます。農地は地域によって宅地並みの価格が適用されることも。商業地は立地や収益性が重視され、評価額が高くなる傾向にあります。なお、200㎡以下の小規模な住宅用地には、課税標準額が6分の1に軽減される特例もあります。
固定資産税評価額と路線価の関係性
「路線価」は相続税や贈与税を計算する際の基準となる価格で、固定資産税評価額とは別のものです。路線価は公示価格の約80%、固定資産税評価額は約70%を目安に設定されており、同じ土地でも路線価の方が高くなるのが一般的です。
さらに、路線価は国税庁が毎年7月に更新するのに対し、固定資産税評価額は市町村(具体的には市町村長)が3年ごとに見直します。それぞれ異なる目的で算定しているため、空き家を相続する場合は、それぞれの用途や更新頻度の違いをきちんと理解しておきましょう。
固定資産税評価額の計算方法と具体例

土地と建物、それぞれの固定資産税評価額ってどう決まる?そんな疑問点をクリアにするために、それぞれの計算方法を解説。建物に適用される減価償却の考え方や、固定資産税評価額が実際の税額にどう影響するかといったポイントなど具体例を交えてご紹介します。
建物と土地の評価額の出し方
建物の固定資産税評価額は、「再建築価格×経年減価補正率」で算出されます。
再建築価格とは、評価時点で同様の建物を新築すると仮定した際の費用で、構造・設備・延床面積などを基準に決まる仕組みです。たとえば木造住宅であれば、「建築単価×延床面積」で算出されます。
土地の評価額は、「路線価×補正率×面積」が基本で、路線価方式または標準宅地比準方式により計算されます。補正率には、土地の形状や接道状況、角地かどうかといった条件が反映され、条件が良いほど評価額は高くなる傾向にあります。
減価償却の考え方(建物の場合)
建物は時間の経過とともに価値が下がっていきます。この考え方は「減価償却」と呼ばれ、固定資産税評価額にも適用されます。
具体的には、建物の耐用年数に応じて「経年減価補正率」が使われ、築年数が進むほど評価額は減少します。木造住宅であれば、築20年の時点で新築時の約20%まで下がるのが一般的です。
ただし、評価額がゼロになることはなく、最低でも20%程度の価値は残る仕組みです。また、リフォームや増改築を行った場合は、その内容に応じて評価額が見直されることもあります。
一方で、土地の評価額は建物とは異なり、経年によって大きく減少することはありません。地価の動きや周辺環境の変化に影響を受けることはあるものの、基本的には大きな変動は少なく、古い空き家でも土地部分の評価はある程度保たれます。
空き家の活用や売却を検討する際は、建物と土地それぞれの評価の特徴を把握しておくと良いでしょう。
評価額が固定資産税に与える影響とは?
固定資産税評価額が上がれば、必ずしも税額もそのまま上がるとは限りません。
実際の固定資産税は、評価額に税率(通常は1.4%)をかけて算出されますが、住宅用地には特例措置があり、課税標準額が軽減される仕組みです。具体的には、200㎡以下の部分は評価額の6分の1、それを超える部分は3分の1にまで圧縮されます。
この特例は空き家でも適用されますが、建物を解体して更地にすると対象外となり、土地の固定資産税が大幅に増える可能性があるため注意が必要です。
空き家・相続・売却時における評価額の重要性

空き家の相続や売却、活用を検討する際にも、評価額の正しい理解は欠かせません。こちらでは、固定資産税評価額と相続税評価額の違いをはじめ、売却価格との関係性や、空き家活用時に押さえておきたい評価額の確認ポイントについて説明していきます。
固定資産税評価額と相続税評価額との違い
固定資産税評価額と相続税評価額は、どちらも不動産の価値を示すものですが、目的や算出方法が異なります。固定資産税評価額は市町村が固定資産税のために決めるのに対し、相続税評価額は国税庁が相続税や贈与税の課税のために定める路線価などを基に計算されます。
土地の相続税評価額は公示価格の約80%、一方で固定資産税評価額は公示価格の約70%が目安です。建物については原則として固定資産税評価額をそのまま相続税評価額として使用します。
たとえば、公示価格4,000万円の土地なら、相続税評価額は約3,200万円、固定資産税評価額は約2,800万円に。空き家を相続する場合は、この差が税額に影響するため、事前の把握が大切になります。
売却価格との関係性
固定資産税評価額は、実際の売却価格とは異なりますが、おおまかな価格感をつかむうえで参考になります。売却価格は評価額の1.3〜1.5倍が目安とされますが、立地や建物の状態によっては大きく変わるでしょう。老朽化した空き家では評価額を下回ることもあれば、条件のよい土地なら2倍以上で売れるケースもあります。
正確な価格を知るには、専門家や不動産会社の査定を併用するのが安心です。自分では気づきにくい土地の魅力や、より良い活用方法を提案してもらえることもあるでしょう。
空き家活用時にチェックすべきポイント
空き家を活用する際は、まず固定資産税評価額を確認し、将来的な税負担を把握しておくことが重要です。特に住宅用地の特例が適用されている場合、建物を解体して更地にすると特例が適用されなくなり、固定資産税が最大6倍に増額されるケースも。活用方法として賃貸を検討するなら、家賃収入と税負担のバランスを考える必要があります。
また、建物の評価額が低い場合は、リフォーム費用に見合う価値があるかどうかを慎重に見極めることが求められます。
空き家を解体するか、リノベーションして再活用するか、あるいは賃貸に出すか。いずれを選ぶにしても、固定資産税評価額をもとに税負担の変化をシミュレーションしておけば、後悔のない判断ができるでしょう。
固定資産税評価額についてよくある質問Q&A

最後に、固定資産税評価額にまつわる、ちょっとした疑問をピックアップ。評価額と税金の関係や、同じ地域でも評価額に差が出る理由、評価額を下げることができるのかなど、知っておくと安心なポイントをご紹介します。
Q:評価額が高いと税金も高い?
基本的には評価額が高くなるほど固定資産税も上がる傾向にありますが、単純に比例するわけではありません。
たとえば、200㎡以下の住宅用地には「小規模住宅用地の特例」が適用され、評価額の6分の1まで課税標準額が軽減されます。そのほか、新築住宅や耐震・バリアフリー改修などにも軽減措置があります。
たとえ評価額が6,000万円あっても、特例により課税標準額が1,000万円程度まで下がるケースも。実際の税額は「課税標準額×税率」で決まるため、評価額だけを見て判断しないことが大切です。
Q:なぜ同じ地域で評価額が違う?
同じ地域にある不動産でも、土地や建物の条件によって固定資産税評価額が異なることは珍しくありません。
土地の場合は、道路の幅や接道の長さ、形状(正方形・三角形・旗竿地など)、角地かどうか、さらに日当たりや眺望などが影響します。建物については、構造(木造・鉄骨・RC造)、築年数、設備の内容、延床面積などが評価に反映されます。
こうした条件の違いにより、たとえば角地は評価額が10%ほど高くなる一方、旗竿地は20%ほど低くなるケースも。建物も同じ築年数でも構造によって減価償却の進み方が異なり、結果として評価額に差が出てくるのです。
Q:固定資産税評価額を下げる方法はある?
意図的に評価額を下げるのは難しいものの、いくつかの工夫は可能です。
建物の場合、経年劣化による減価償却のほか、使われていない設備の撤去や一部解体によって評価額が下がることがあります。土地については、地盤沈下や土壌汚染といった瑕疵がある場合、再評価を申請できるケースもあります。
また、評価に誤りがあると思われるときは、固定資産評価審査委員会に不服申立てが可能です。ただし、不当に評価を下げることはできません。住宅用地の特例など正当な制度を活用して、課税標準額を軽減するのが現実的な対策といえるでしょう。
固定資産税評価額を理解すれば空き家の扱いもスムーズに
固定資産税評価額は、空き家の売却や相続を進めるうえで欠かせない判断材料です。評価通知書や登記簿、公示価格や路線価との関係を理解し、課税標準額や相続税評価額との違いを把握しておくことで、将来の税負担にも備えやすくなります。情報を整理し、納得のいく選択につなげていきましょう。
空き家や土地活用に迷ったら?アキサポがサポートします
固定資産税や相続税評価額、公示価格や路線価など、土地や空き家をめぐる税の仕組みは複雑。評価通知書や登記簿を確認し、課税標準額や評価額の違いを整理することが大切です。
固定資産税評価額を活かした最適な活用プランをご提案
アキサポでは、立地や物件の状態、将来的な評価替えも視野に入れながら、売却・賃貸・事業活用など、一人ひとりに合ったプランをご提案しています。まずはお気軽にご相談ください。
相続・空き家問題の不安をプロが解消します
「相続したけどどうすればいいか分からない」「評価額が高くて税金が心配」そんなお悩みも、専門スタッフにご相談を。アキサポでは、評価通知書や登記簿、公示価格・路線価との違い、課税標準額や相続税評価額の見方まで丁寧にご説明。現地調査や評価替えをふまえた活用提案も行っております。将来の税負担に備えた計画づくり、まずは一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
この記事の監修者

岡崎 千尋 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
都市計画コンサルタントとしてまちづくりを経験後、アキサポでは不動産の活用から売買まで幅広く担当してきました。
お客様のお悩みに寄り添い、所有者様・入居者様・地域の皆様にとって「三方良し」となる解決策を追及いたします。








