公開日:2025.09.27 更新日:2025.08.12
固定資産税の平均額はいくら?計算方法、軽減措置、支払い方法を解説
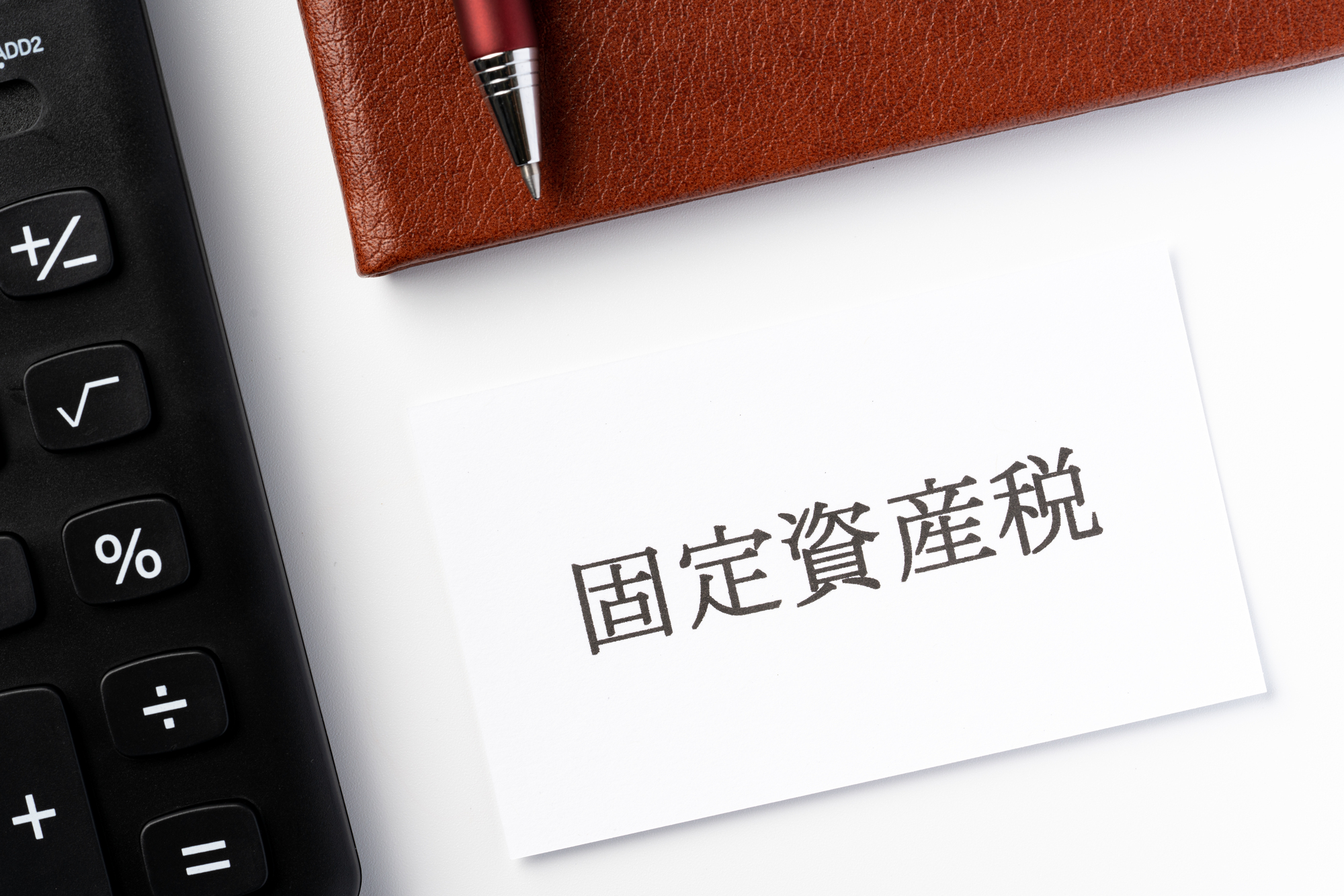
固定資産税とは、土地や建物などの不動産を持っている人が支払う地方税のことです。評価額に基づいて算出され、地域や物件の状況によって金額が変化します。住宅用地や新築住宅など、一定の条件を満たす物件には軽減措置が用意されており、負担を減らせるケースも存在します。
そこで本記事では、固定資産税の平均額や特例措置、納税のスケジュールなどを詳しく解説。固定資産税の全体像を把握でき、住宅購入や所有にかかる費用を正しく見積もれるようになるので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
固定資産税の仕組みと課税対象

まずは固定資産税の概要と、具体的にどのような不動産が課税されるのかを押さえておきましょう。
固定資産税とは何か
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物などの固定資産を所有している人が、その所在する市町村(東京都23区は都)に納める地方税です。地域の公共サービスやインフラ整備などの財源となります。
固定資産の評価額は、3年ごとに評価替えが行われます。この評価額は「固定資産税課税台帳」に登録されており、閲覧することも可能です。固定資産税の税率は市町村の条例で定められ、標準税率は1.4%ですが、財政状況などにより1.4%を超える場合もあります。この場合、地方税法により制限は設けられていませんが、2.1%を超える税率を定めている市町村はほとんどありません。
課税対象となる土地や建物の例
固定資産税は土地と建物は別々に評価され、それぞれの評価額に標準税率をかけて算出されるのが基本です。課税対象は「土地」「建物」「償却資産」が主な範囲。戸建て住宅、マンション、アパートなどの居住用不動産だけでなく、オフィスビルや商業施設、駐車場、農地なども含まれます。
毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となるため、年の途中で不動産の売買があった場合、売買契約時に固定資産税を日割り計算して精算するのが一般的です。これは法律上の義務ではなく、あくまで慣習として行われるものです。
ただし、一部の公共用地や宗教施設、教育目的のための建物などは非課税扱いとなるケースもあります。
固定資産税の平均額はいくら?一戸建てとマンションの目安

続いて、実際に多くの人が支払っている固定資産税の平均額や価格傾向を、一戸建てとマンションに分けて解説します。
予想外の出費を避けるためにも購入前や建築前にしっかりシミュレーションし、住宅ローンとのバランスを考慮に入れつつ、将来の負担をトータルで見極めるようにしましょう。
一戸建ての固定資産税の平均額
一般的な一戸建て住宅の場合、年間支払いの相場は10万円から15万円くらいが目安。ただし、固定資産税の支払額は地域差があり、地方よりも地価が高い都市部では、同じ敷地面積でも納付額が上がる傾向があります。
また、土地の面積や立地、建物の構造、築年数などでも変わる点もポイント。路線価が高いエリア、あるいは再建築費評価額が大きく算出されがちな三階建てや鉄骨造などは、想定以上の税額になるケースも見られます。
マンションの固定資産税の平均額
マンションの場合、共用部分の持分割合といった特性から、一戸建てよりも比較的低い固定資産税になることがほとんど。土地の所有権が区分され、各戸の居住スペース以外は共有部分となるため、一人あたりの負担も抑えることができます。
一方、都心部の人気エリアに建つタワーマンションのように、土地の価格が高い物件ではその分税負担も増加。築年数が浅く評価額が高めに設定される新築・築浅物件では、一時的に負担がかさむことも考えられます。
また、マンションの場合は管理費や修繕積立金も必要なので、これらの費用も含めて資金計画を立てるとよいでしょう。
新築・中古でも変わる?固定資産税の傾向
固定資産税は、新築か中古かでも金額が変わります。
新築物件の場合、評価額は高くなりがちですが、一定期間固定資産税が軽減される制度があり、条件を満たせば通常の税額から数年間は半額程度になることも。一方、中古物件の場合は築年数が経過していることを理由に評価額は下がる傾向にあるものの、自宅のリフォームや増築で評価額が上がり、税額がアップする可能性があるため、長期的な費用対効果を検討することが重要です。
固定資産税評価額と計算方法の基本

固定資産税は、土地や建物の評価額に税率を掛けて計算されますが、そもそも「評価額」はどのような仕組みで決められ、税率はいくらくらいになるのでしょうか?
評価額の構造を理解することで、将来的にリフォームや増築、売却の計画を立てる際に役立つほか、納税額に不審な点がある場合も相談や再評価の申請がスムーズになるので、詳しく確認していきましょう。
評価額の仕組みと家屋調査
固定資産税の評価額は、土地と建物それぞれについて自治体が独自に算出。土地の場合は、エリアごとの路線価や近隣の時価などを参考に、形状や間口の広さ、接道状況などの条件を加味した評価が行われます。これらの公的指標をベースにしているため、実際の取引価格とは異なることも珍しくありません。
建物については、新築や増築時に自治体職員が現地調査を行い、構造や設備のグレード、床面積などを確認します。
これらの評価額は3年に一度見直されますが、それまでの間に大規模なリフォームや増改築、用途変更などがあった場合は、随時変更されることがあります。また、家屋調査の結果に納得がいかない場合は、適切な期間内に再調査を依頼できる制度の活用も可能です。
土地の固定資産税の計算方法
土地の課税標準額 × 税率 = 納税額
土地の固定資産税は、固定資産税評価額に税率を掛け合わせます。固定資産税評価額は、公示価格や都道府県地価調査価格の7割程度になることが一般的です。
税率は1.4%が標準ですが、自治体によっては最大2.1%程度になることも。一方で、分譲地などで宅地として販売されている土地は、住宅用地の軽減措置が適用され、税負担が軽減できる場合があります。
土地の評価額は地価や立地要件に大きく左右され、近隣で大規模再開発が行われるなど外的要因によっても変わるため、随時情報をチェックしておくとよいでしょう。
建物の固定資産税の計算方法
課税台帳に登録されている価格×税率1.4% = 納税額
建物の評価額は、建築素材や構造、用途、経過年数などを考慮して計算された「再建築費評点数」をベースに決定されます。例えば木造より鉄骨コンクリートのほうが、また築年数が浅いほうが固定資産の評価額は高くなる傾向にあります。
都市計画税との違いにも注意
固定資産税とは別に、“都市計画税”という税がかかることがあります。都市計画税とは、市街化区域内に土地や家屋を所有する人が、固定資産税とあわせて納める税金のこと。都市計画区域内にある土地や建物などが対象になるもので、道路や公園などの市街地整備に使われる財源です。
税率は一般的に0.3%以内とされていますが、自治体ごとに異なり、固定資産税と同様に評価額ベースで算出されます。納付書は固定資産税の納付書と一緒に届くことが多いため、あわせて確認しておきましょう。
固定資産税が軽減される場合とは?知っておきたい特例措置

特定の要件を満たせば、一定期間にわたって固定資産税が軽減される制度があり、長期的な税負担を抑えることが可能です。主な軽減措置をご紹介するので、自身の物件に該当するかどうか確認してみてください。
新築住宅の軽減措置
新築の住宅には、一定期間固定資産税が半額になるなどの優遇措置があります。適用されるためには床面積や居住用であることなどの要件を満たす必要があり、また申請手続きが必要になるケースもあるため、建築後に忘れずにチェックしておきましょう。
この軽減措置は新築後3年や5年といった期間が設定されているため、減税期間が終わったあとの負担増を見越した資金計画を立てておくこともポイントです。
土地の軽減措置
土地に関しても、住宅用地として利用していることを前提とした軽減措置があります。具体的には、小規模宅地(200平方メートル以下)であれば評価額が1/6に、それ以上の一般住宅用地でも1/3になるというものです。
土地の利用実態や面積要件、住宅と一体であるかどうかといった要素が適用の判断基準になり、敷地内に駐車場や庭がある場合など、境界の扱いによっても軽減率が変わる点には注意が必要です。
固定資産税の納付スケジュールと支払い方法

固定資産税の納付期限や支払方法には複数あり、自分の都合にあわせて選ぶことができます。ここでは納付の基本について詳しくご紹介します。
納付書の入手と納期限
納付方法は、一括納付か、全4回の期別で分割納付するかのいずれか。納付書は毎年4月頃に各自治体から送付されます。納期を守らないと督促状が届くほか、延滞金が加算される可能性があるため十分に注意しましょう。なお、延滞金の額は地方税法に基づき、延滞した期間に応じて計算されます。
また、万が一納付書を紛失した場合は自治体に再発行を依頼することも可能です。ただし、再発行に時間がかかるケースもあるので、早めに対応することが大切です。
銀行・ネットバンキング・口座振替などの支払い方法
支払方法は銀行や郵便局の窓口で現金払いをするのが定番ですが、近年ではコンビニエンスストアやネットバンキングなどを利用できるケースも増えています。
ライフスタイルなどを考慮して自分がもっともスムーズに納付できる方法を選ぶようにしましょう。
クレジットカード・スマホ決済を使うメリットとデメリット
固定資産税は、クレジットカードやスマホ決済で支払うことも可能です。
クレジットカードで納税する場合、カードのポイントが貯まるため、家計管理においては大きなメリットとなることがあります。また、オンライン上で手続きが完結するため、時間や場所にとらわれず支払いできるのもメリットです。
一方で、クレジットカードでの納付には手数料がかかる場合があるため、ポイントを獲得しても割高にならないかを確認しましょう。さらに、カード決済は引き落とし時期も考慮する必要があるため、口座残高の管理には注意が必要です。
スマホ決済アプリでも納付番号を入力することで簡単に支払いが可能ですが、こちらも決済手数料の有無を確認した上で、期限までに納付するよう心がけましょう。
空き家や古い家に注意!固定資産税が増えるケース

空き家や老朽化が進んだ古い家にも、当然固定資産税はかかります。しかも、長らく放置されて管理不全になっている場合、軽減措置が外れて固定資産税が増加する恐れも。
どんなケースだと固定資産税が増えるのか、詳しく解説していきます。
特定空き家に指定されると税率が上がる
管理が著しく行き届いていない、倒壊などの危険性、衛生面の問題などが認められる空き家は、特定空き家に指定される可能性があります。そうなると、住宅用地の軽減措置が適用されなくなるため、結果として税負担が大幅に増加。さらに、行政からの指導や勧告を無視した場合、是正措置の要請や行政代執行に至るケースも見られます。
そのため、空き家として長期保有する場合でも、定期的な点検や破損箇所の修繕などを行うことがポイント。自身での管理が難しい場合は、不動産会社などに管理を委ねる選択肢も検討しましょう。
管理不全空き家の売却や維持の検討
長期間利用しない空き家をそのまま放置しておくと、固定資産税ばかりでなく維持管理費もかさんでしまいます。特に築古物件の場合は修繕費が竣工当初より増加することが多く、費用面での負担がより大きくなるでしょう。
更地にする方法もありますが、その場合建物にかかる固定資産税の軽減措置がなくなり、結果的に税負担が増えてしまう可能性があるため、慎重に検討する必要があります。空き家のまま維持するのか、解体するのか、もしくは別の方法で利活用するかは、不動産屋などに相談しながら判断するようにしましょう。
固定資産税を抑えるための工夫とシミュレーション

固定資産税は長期的にみると大きな負担になるため、少しでも押さえられるようシミュレーションしておくことも大切です。節税のコツをまとめたので、ぜひチェックしてみてください。
シミュレーションで見える負担額の目安
固定資産税は年ごとに評価額の更新がなくても、建物の減価や土地の地価変動など、長期的には変動要因が多いのが特徴です。そのため、住宅ローン返済と固定資産税の支払いが重なる月や、数年先に取り壊しや売却計画がある場合の負担などを考慮しておくことがポイントです。
オンラインやアプリなどで簡単に試算できるツールを活用したり、不動産会社や税理士など専門家に相談したりして、無理のない資金計画を検討しましょう。
評価額の確認・見直しや再調査を依頼する方法
評価額に疑問がある場合は、遠慮なく市区町村の資産税課などへ問い合わせるようにしましょう。
自治体は所有者からの申立てを受け付ける制度を設けており、場合によっては現地調査のやり直しや評価法を再検討してもらうことが可能です。特に設備や構造の評価に誤りがあれば、税額の減額が認められることもあります。
依頼する際、評価の根拠や調査結果の提示を求められるので、家屋調査時の書類や建築資料などをあらかじめ準備しておくとよいでしょう。
ただし、見直しに時間がかかる場合や、調査が決定されるまでに納税期限が迫る場合は、一旦納付しその後に還付される形で進めるケースもあります。
まとめ|固定資産税の平均額を把握し、賢く不動産を維持・活用しよう
固定資産税は、物件を所有する上で避けて通れないコストです。けれど、正しく制度を理解して対策を取ることで、計画的な納付ができ、物件の条件によっては一定期間税負担を軽減することもできます。
特に空き家や古い家を所有している場合、倒壊や不法侵入、害虫・害獣などによる被害などさまざまなリスクが生じたり、特定空き家等に指定されることで固定資産税が上がったりする恐れがあるため注意が必要です。
固定資産税をはじめとする税負担を踏まえた長期的な資金計画や、軽減措置適用の可否、評価額の再調査などには専門知識が必要になるケースがあるため、もし判断に迷ったり手続きに不安を感じた時は、ぜひアキサポにご相談ください。
アキサポは、空き家の活用支援に特化した専門サービスです。税理士や司法書士など専門家と連携し、税制上の優遇措置の適用可能性や、固定資産税評価額の見直しなどの相談にも対応。ご希望に応じて物件の現状にあわせた活用方法や売却、賃貸の提案もいたします。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。








