公開日:2025.10.01 更新日:2025.09.25
不動産経営の始め方と成功のポイント|メリット・リスクも徹底解説

不動産経営は、アパートやマンションなどの賃貸不動産を活用し、家賃収入を得る資産運用のひとつです。実物資産ならではの安定感や節税効果、土地活用の可能性など、多くのメリットが期待できます。一方で、空室や老朽化による維持費、税金負担といったリスクも無視できません。初期費用や自己資金のバランス、利回り、管理会社との契約内容など、押さえるべきポイントはさまざまです。そこでこの記事では、不動産経営の基本から運営・管理のコツ、リスク対策までを詳しくご紹介していきます。
目次
不動産経営とは?基本的な仕組みと種類

不動産経営は、安定した家賃収入を得るための仕組みを理解することから始まります。投資の目的や物件の特徴を把握し、自分に合った経営スタイルを選ぶことが成功の第一歩。
収益性やリスクは、立地条件や管理体制などさまざまな要因によって左右されます。そのため、事前に市場動向やエリア特性を調べ、長期的な運営を見据えた計画を立てることが大切です。まずは、経営形態ごとの違いや収益の成り立ちについて詳しく見ていきましょう。
アパート経営・マンション経営・戸建賃貸の違い
アパート経営は木造や軽量鉄骨造が多く、建築費や初期費用を抑えやすい反面、入居者は単身者や学生などの若年層が中心になりやすい傾向があります。
マンションは鉄筋コンクリート造が主流で建築費や維持費は高めですが、遮音性や耐久性に優れ、安定した家賃収入を見込みやすいのが強み。
戸建賃貸はファミリー層を中心に需要がある一方で、物件ごとに管理・修繕費が発生するため、利回りや税金、自己資金とローンのバランスを踏まえた計画をしっかり立てることが重要です。
不動産経営の収益構造
不動産経営の収益は、アパート経営やマンションなど賃貸不動産から得る家賃収入(インカムゲイン)と、物件売却による利益(キャピタルゲイン)の2つが柱となります。長期保有で安定した家賃収益を確保しつつ、物件価格が上昇したタイミングで売却し、利益を得ることも可能です。
ただし、人口減少や空室、老朽化による維持費、税金(固定資産税や所得税など)による負担も避けられません。利回りや節税効果、自己資金とローンのバランス、建築費や見積の精度など、実地の運営ポイントを押さえながら、長期的な視点でリスク管理を行う必要があります。
不動産経営のメリット
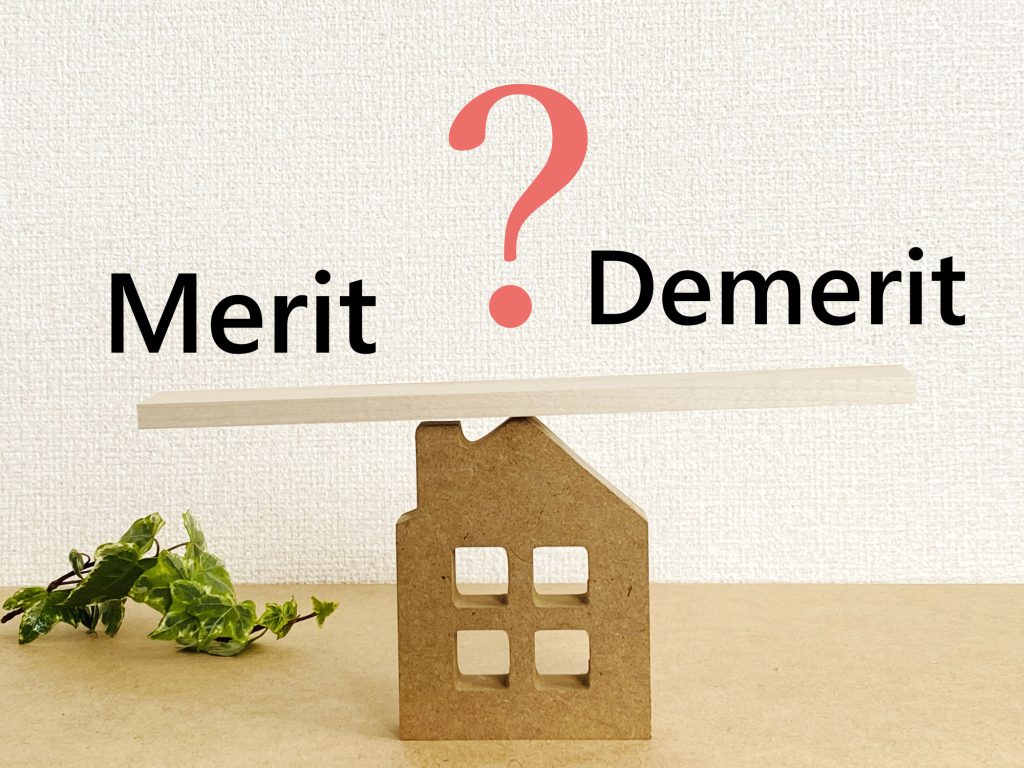
アパートやマンションなどの賃貸不動産を運営し、継続的な家賃収入を得られることは、不動産経営ならではの大きな魅力です。税制優遇による節税や相続税対策に活用でき、長期的な資産形成にもつながります。株式などの投資商品に比べ価格変動が小さく、安定性を重視した運用がしやすいのも特徴です。
また、自己資金や初期費用が限られていても、金融機関のローンを活用すれば資産規模を着実に拡大できます。ここからは、家賃収入の安定性や税務面での利点、将来にわたる資産形成の可能性について詳しく見ていきましょう。
安定した家賃収入
不動産経営の大きな魅力は、景気変動の影響を受けにくく、安定した家賃収入が期待できることです。アパート経営やマンションなどの賃貸不動産は、入居者がいる限り毎月一定の家賃収益が入り、長期的なキャッシュフローの確保につながります。
立地や物件タイプを見極め、需要の高いエリアで土地活用すれば、空室リスクを抑えながら収益を継続させやすくなります。
節税・相続税対策
不動産経営では、賃貸物件の減価償却費や管理費、ローン利息などを必要経費として計上できるため、所得税や住民税の軽減につながるケースがあります。
相続時には不動産の相続税評価額が時価よりも低く評価される仕組みによって、相続税の節税効果も期待できます。こうした税制上のメリットを最大限に活かすには、事前に不動産会社や税理士など専門知識を持つ相談先を確保しておくと安心です。
将来にわたる資産形成
不動産経営は、長期保有によって資産価値を積み上げやすく、家賃収入(インカムゲイン)を得ながら将来の売却益(キャピタルゲイン)も狙える魅力的な運用方法です。アパートやマンションなどの賃貸不動産は、老後資金の確保や子どもへの資産承継にも活用でき、計画的な運用が将来の安心につながります。
また、適切なメンテナンスを定期的に行うことで、老朽化による価値低下を防ぎ、利回りや収益性を維持しやすくなります。土地活用の工夫と合わせ、安定した資産形成を目指しましょう。
不動産経営のリスクと対策

不動産経営は、家賃収入による安定性や資産形成といった魅力がある一方で、空室や家賃下落、建物の老朽化による修繕費、維持管理費の増加など、避けられないリスクも抱えています。加えて、地震や火災といった災害、金利上昇によるローン返済負担の増加など、経営を圧迫する要因は多岐にわたります。
こうした影響を最小限に抑えるには、購入前から市場調査や利回りシミュレーションを行い、物件や立地を慎重に選ぶことが重要です。ここからは、代表的な4つのリスクとその対策を解説していきます。
空室リスクと家賃下落リスク
アパートやマンションなどの賃貸不動産は、入居者がいなければ家賃収入が途絶え、経営に大きな打撃を与えます。さらに、地域の人口減少や供給過多、経済状況の変化によって家賃相場が下落する可能性も考えられるでしょう。
こうしたリスクを避けるには、購入段階で入居需要が高いエリアや物件タイプを選び、定期的な管理や修繕で物件の魅力を維持することが重要です。また、募集条件や賃貸借契約内容を定期的に見直し、空室リスクを抑えることが肝心です。
修繕費・維持管理費の負担
建物は経年劣化による修繕費や、共用部分の維持管理費などが定期的に発生します。屋根や外壁、防水工事など大規模修繕が必要になれば、家賃収入を圧迫する可能性もあります。
こうしたリスクを避けるには、築年数や構造に応じた長期修繕計画を立て、建築費や見積をもとに費用を試算しておくことが重要。毎月の家賃収益の一部を積み立て、予期せぬ出費にも備えましょう。
地震や火災など災害への備え
地震大国とも呼ばれる日本で、アパートやマンションなどの賃貸不動産を運営するなら、災害対策は欠かせません。
購入前には耐震基準や構造、地盤の強度を確認し、地域のハザードマップで災害リスクを把握しておきましょう。火災保険や地震保険への加入や防災設備の導入といった備えを行い、万が一の災害時でも家賃収入や資産価値を守る準備をしておきましょう。
金利上昇リスクとローン返済の注意
不動産経営でローンを利用する場合、変動金利型は将来的な金利上昇により返済額が増える可能性があります。返済負担を抑えるためには、固定金利型への切り替えや繰上返済を組み込んだ計画など、複数の返済シナリオを用意しておくことが必要です。
銀行の融資条件や金利動向を定期的に確認し、経営全体のキャッシュフローを圧迫しないよう資金管理を徹底しましょう。
物件選びと立地調査のポイント

不動産経営を成功させるためには、購入前に想定家賃と価格から利回りを試算し、管理費や修繕費、税金も含めた実質的な収益性を確認することが不可欠です。
そのうえで、交通アクセスや生活環境の利便性、周辺施設の充実度を見極め、安定した入居需要が見込める立地を選びましょう。続くパートでは、利回りや収益シミュレーションの考え方、エリア選定の具体的な手順、中古と新築の特徴について触れていきます。
利回りと収益シミュレーションの考え方
不動産経営では、表面利回りと実質利回りの違いを理解しておくことが重要です。
表面利回りは購入価格に対する年間家賃収入の割合を示しますが、実質利回りはそこから管理費や固定資産税、修繕費などの経費を差し引いた実際の収益率を指します。
物件の比較や投資判断を行う際は、この実質利回りを基準とした精度の高いシミュレーションをもとに検討しましょう。
購入エリアを決める際の調査方法
不動産経営で安定した家賃収入を得るには、購入エリアの調査が欠かせません。人口密度や景気動向、交通アクセスの良さはもちろん、駅やバス停までの距離、スーパーや商業施設、学校・病院といった生活インフラの充実度も重要です。
さらに、将来的な開発計画や再開発エリアは入居希望者が集まりやすく、空室リスクを抑えながら収益向上を狙える傾向があります。購入エリアの特性を的確に把握することで、長期的な経営安定に繋がるでしょう。
新築と中古、どちらを選ぶ?
不動産経営では、新築と中古のどちらを選ぶかで投資計画は大きく変わります。新築は最新設備やデザイン性に長け、入居者の興味を惹きやすい反面、購入価格が高く初期費用が膨らみやすい傾向があります。
一方、中古は価格を抑えやすく利回り向上を狙えるメリットがありますが、築年数に応じた修繕やリノベーション費用を見込む必要があります。
どちらの選択肢でも、初期費用とランニングコストを比較して、目指す経営スタイルや資金計画に合致するかどうかを検討しましょう。
不動産経営の事前準備と計画

安定した家賃収入を得ながら資産を育てるためには、始める前の準備が肝心です。
まずは、不動産経営を始める目的を明確にし、節税や老後資金、資産承継など自分が目指すゴールの具体化を。そのうえで自己資金や初期費用、ローン返済計画を含めた資金計画を立て、想定されるリスクと期待するリターンのバランスを判断しましょう。
目的・目標を明確にする
節税や不動産所得税対策、老後の安定した家賃収入、物件価格上昇によるキャピタルゲインなど、目的によって選ぶべき物件やローンの種類、立地は変わります。
まずは目的に合う条件やエリアを洗い出し、将来の売却や相続まで見据えた経営方針を立てましょう。事前に計画を固めれば、無駄な投資や想定外のリスクを避けやすくなります。
資金計画とローンの選び方
物件価格だけでなく、仲介手数料や登記費用、リフォーム代、各種税金などの初期費用を合算して資金計画を立てましょう。
自己資金とローンの割合を決めたら、毎月の返済額と家賃収入を比較し、長期的なキャッシュフローをシミュレーションしましょう。さらに、固定金利と変動金利のメリット・デメリットを比較し、経営方針や許容できるリスクに合ったローンを選ぶことがポイントです。
賃貸管理と入居者募集

不動産経営は物件を所有して終わりではありません。日々の管理業務を的確に行うことで、空室期間や家賃滞納のリスクを減らし、収益や物件価値を維持していくことが必要です。
さらに、快適な住環境づくりやサービス面の充実は、長期入居や契約更新にもつながり、物件価値の維持・向上にも効果的です。自分で管理するか管理会社に委託するかは、手間やコスト、専門知識の有無を踏まえて判断しましょう。
管理会社に任せるか自主管理にするか
不動産経営では、物件の管理方法によって手間やコストが大きく変わります。
管理会社に委託すれば、契約手続きや家賃回収、クレーム対応などを一括で任せられ、オーナーの負担を大幅に軽減できます。忙しい方や初心者にとっては安心ですが、管理手数料が発生します。
一方、自主管理は手数料を節約できる反面、入居者対応や修繕手配などを自分で行う必要があり、専門知識や手間が求められることを理解しておきましょう。
効果的な空室対策と入居者募集のコツ
不動産経営で収益を安定させるには、空室期間をいかに短くするかが鍵に。入居希望者の関心を引くためには、写真や間取り図を工夫した募集広告の作成や、内見時の印象を良くする工夫が欠かせません。
壁紙や床の張り替えなど小規模なリフォームや、人気設備の導入で物件の価値を高めるのも効果的です。さらに、家賃保証や入居者サポートを整えることで、安心感が増し、入居促進と長期契約に繋がります。
税金と確定申告の基礎知識

不動産経営では、所得税や住民税をはじめ、固定資産税や相続税など複数の税金の管理がつきもの。正しい知識を持ち、確定申告を適切に行うことは、収益を守るうえで欠かせない要素です。
家賃収入が増えれば課税額も上がりますが、減価償却費や借入金利、修繕費などを経費計上すれば、税負担を抑えることも可能に。経営状況をこまめに見直し、税理士や専門家と連携して申告準備を進めることで、申告ミスや節税の機会損失を防げます。
ここからは、不動産所得にかかる税金の種類や申告時の注意点、将来の相続税・固定資産税への備えについて解説していきます。
不動産所得にかかる税金の種類
不動産経営で得た家賃収入は、不動産所得として所得税と住民税の課税対象になります。規模が大きく物件数や収入が一定以上になると、個人事業税がかかる場合もあるため注意が必要です。
また管理費や修繕費、ローン利息、減価償却費などの経費を正しく計上することで、課税所得を抑え節税に繋がります。税金の仕組みをきちんと理解し、確定申告で適切に申告しましょう。
確定申告で押さえておくべきポイント
家賃収入だけでなく、管理費や修繕費、ローン利息など、必要経費として計上できる支出を正確に細かく仕分けることが節税に繋がります。
特に減価償却は、物件の構造や取得時期によって法定耐用年数や計算方法が異なるため、間違いがないよう注意しましょう。また青色申告特別控除(最大65万円)や損失の繰越控除(最長3年)が可能となり、節税効果が高まる場合もあるため、積極的に検討してみましょう。
相続税・固定資産税への備え
不動産を相続するときは、相続税額を左右する財産評価額の把握が欠かせません。土地や建物の評価は相続税法上、時価よりも低く算定されることが多いものの、相続人の人数や物件の種類によって税負担は大きく変わります。
また、固定資産税は毎年1月1日時点の不動産所有者に対し課される維持費のひとつです。長期的に保有する場合は、家賃収入とのバランスを踏まえて物件投資を進めましょう。
アパート経営とマンション経営の違い

不動産経営を始める際、アパートとマンションのどちらを選ぶかは大きな分岐点に。構造や建築コスト、維持費、さらには入居者ターゲットまで異なります。両者の特徴を理解することで、より明確な経営方針を打ち立てることが可能になるでしょう。
コスト構造や運用方法、収益性の差。そして、どのような人に向いている経営形態なのかを、より具体的に解説していきます。
建築コスト・維持費・運用スタイルの相違点
木造のアパートは建築コストを抑えやすい一方で、耐震性や老朽化による修繕の頻度が高くなる点に注意が必要です。鉄筋コンクリート造のマンションは、耐久性や防音性に優れ長期運用に向きますが、大規模修繕や点検費用が高くなる傾向があります。
また、マンションでは管理組合との連携が必須となり、アパートより運営体制が複雑です。自主管理と委託管理の違いを理解し、時間とコストを天秤にかける必要があるでしょう。
ターゲットと収益性の違い
アパート経営は、単身者や学生などを主な入居者層とし、家賃の手頃さや駅からの近さが集客のポイントになります。比較的低コストで始めやすい反面、人口減少や空室リスクに備えた工夫が必要です。
マンション経営は、防犯性や快適性を求めるファミリー層や高所得者層に人気があり、高めの家賃収入を得やすいという特徴があります。ただし、建築費や維持費は高くなりがちです。どちらの場合も、ターゲット層のニーズに沿った物件を確保することが重要です。
どちらに向いている?それぞれの特徴
不動産経営を始める際は、資金力や運用目的に応じてアパートかマンションかを選びましょう。
アパートは建築コストや初期投資が抑えやすく、比較的少ない資金でスタートできます。一方で、マンションは維持費や管理費がかかるものの、耐久性や防音性に優れ、長期的な安定収入や資産価値の維持が期待できます。
さらに、地域の賃貸需要や将来的な売却の視点も踏まえると、より納得感のある選択がしやすくなるでしょう。
収入アップのための具体的施策

家賃収入を安定的に伸ばすためには、物件の価値を高める工夫が必要です。入居者の満足度を意識したリフォームやリノベーションは、空室対策にも直結します。
さらに、周辺の家賃相場を踏まえた適切な賃料設定や定期的な見直しは、収益の最大化に有効です。加えて、複数物件を保有して地域や入居者層を分散すれば、突発的な空室や修繕による収入減のリスクを抑えることも可能。これらの施策の具体的な進め方と成功のポイントをご紹介していきます。
リフォーム・リノベーションの活用
築年数が経った物件でも、適切なリフォームやリノベーションを行えば収益性を高められます。例えば、キッチンや浴室などの水回りを最新設備に交換する、収納スペースを増やす、防犯性を向上させるなど、入居者のニーズに寄り添った改善が効果的です。
そうした付加価値を加えることで、入居希望者からの印象が大きく向上し、家賃アップや長期入居につながる可能性もぐんっと高まります。
家賃相場を踏まえた賃料設定の見直し
近隣の賃貸相場や競合物件の設備・築年数を調べ、自分の物件の条件と定期的に比較しましょう。家賃が高すぎれば空室リスクが増し、安すぎれば収益を逃すことになります。
適正な賃料を保つためには、募集条件や初期費用の調整、キャンペーンの活用なども有効。相場を意識した柔軟な運営で、満室稼働と収益アップの両立を目指しましょう。
複数物件への投資で分散を図る方法
不動産経営で安定した収益を確保するには、複数物件への分散投資が有効です。単一物件だけに依存すると、空室や大規模修繕が発生した際に収益への影響が大きくなりますが、エリアや入居者層を分けて運用すれば、リスクを抑えながら収入源を確保できます。
ただし、物件が増えるほど管理コストや資金計画も複雑になるため、購入前から資金調達方法や管理体制を整えるなど、綿密な計画と確認が求められるでしょう。
不動産経営を成功させるためのポイント

不動産経営を軌道に乗せるには、最新の市場情報を取り入れながら戦略を柔軟に見直す姿勢が大切です。
まずは自己資金や融資条件を踏まえ、自分の目的に合った物件選びを。エリアの賃貸需要や将来の開発計画も調査し、長期的な収益性を見極めましょう。
また、家賃設定や設備の見直しなど、小さな改善を継続することで入居率を高められます。加えて、管理会社や税理士など専門家と連携すれば、実務負担やリスクを軽減しながら安定した運営が可能です。
収支計画の定期的なアップデートと、修繕費やローン返済に備えた余裕資金の確保が、成功への着実な一歩といえるでしょう。
将来を見据えた不動産経営で、理想のライフプランを実現

初めての不動産経営は「安定収益を得たい」「資産を増やしたい」という期待と同時に、物件選びや税金、空室リスクなどへの不安もつきもの。物件探しから管理・税務処理までの全体像を把握し、事前準備を徹底することが大切です。綿密なリサーチと専門家の伴走があれば、修繕費や入居率低下などの課題にも柔軟に対応できるでしょう。
自分のライフプランや資金状況を踏まえた経営スタイルを選び、長期的な視点で不動産経営に取り組むことが、安定した収益と資産形成をもたらす最善策です。始めたい気持ちはあるけれど不安もある…そんな今こそ、専門家の知恵と支えを味方に動き出しませんか?
不動産経営の第一歩はアキサポの無料相談から
アキサポでは、経験豊富な専門スタッフが、物件選びから管理、税金対策までワンストップでサポート。物件の特徴やエリアの市場動向、将来の資産形成まで見据えたアドバイスで、長期的な安定を目指した不動産経営をお手伝いします。迷っている今こそ、プロの視点を取り入れて一歩踏み出しましょう。
この記事の監修者

岡崎 千尋 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
都市計画コンサルタントとしてまちづくりを経験後、アキサポでは不動産の活用から売買まで幅広く担当してきました。
お客様のお悩みに寄り添い、所有者様・入居者様・地域の皆様にとって「三方良し」となる解決策を追及いたします。










