公開日:2025.10.06 更新日:2025.09.26
駐車場経営で安定収入を得るには?基礎知識からメリット・デメリット、成功のコツまで徹底解説

駅前や住宅街でよく見かける駐車場経営は、初期費用が少なく始めやすい土地活用として人気があります。多くの場所で見かけるため、「なんとなく儲かりそう」「自分も挑戦してみたい」と考えたことがある方も多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、駐車場経営のメリットとデメリット、初期費用や税金の仕組み、そして注意すべきリスクについて詳しく解説します。さらに、安定収益につなげるための考え方や管理方法も紹介しますので、駐車場経営を検討している方の判断材料としてご活用ください。
目次
駐車場経営の強みとは?他の土地活用との違いは?

駐車場経営は、土地を駐車スペースとして貸し出すことで利用料を得る土地活用方法です。建物を建てる必要がないため初期費用を抑えやすく、準備から運営を始めるまでの時間が短いため、更地になっている間の一時的な活用方法としても用いられることがあります。
他の土地活用との違いは、始めるためのハードルの低さにあります。アパートや貸店舗などを建てる場合は、多額の建築費が必要で撤退も難しいですが、駐車場経営は比較的少ない資金でスタートでき、撤退もしやすいです。
他にも、管理の手間が少ないのも違いとして挙げられます。建物のように修繕や設備更新に大きなコストがかかることは少なく、清掃や区画の維持といったシンプルな管理で済むケースが多いです。この「小さく始めて柔軟に切り替えられる」という点が、駐車場経営を他の土地活用と差別化する大きなポイントといえるでしょう。
駐車場経営の主な種類3選|月極・コインパーキング・一括借り上げ
駐車場経営には大きく分けて「月極駐車場」と「コインパーキング」「一括借り上げ(サブリース)」の3種類があり、どちらを選ぶかで初期投資や管理の手間、利用者層が変わってきます。確実に収入を得たいなら月極や一括借り上げ、短時間利用の需要を取り込みたいならコインパーキングといった具合に、目的や立地に応じた選択が必要です。
たとえば、オフィスや商業施設が多い地域ではコインパーキングの稼働率が高くなる傾向がありますが、一方で住宅地や郊外では、長期契約を結ぶ月極駐車場のほうが安定した収益につながりやすいでしょう。では、それぞれの強みと注意点を詳しく見ていきましょう。
コインパーキング
コインパーキングは時間貸しのスタイルで、駅や繁華街の近くなど車の出入りが多い場所では高収益が期待できます。短時間の利用者を広く集められるため、稼働率次第では月極より大きな利益を生みやすい強みを持っています。
ただし、精算機やゲート、防犯カメラといった設備が必須となり、初期投資がかさむ点には注意が必要です。さらに、利用状況は時間帯や季節で変動するため、料金設定や集客対策などが適切にできていないと、思ったような利益が上がらない恐れがあります。
月極駐車場
月極駐車場は、1区画ごとに利用者を定め、毎月決まった賃料を支払う契約形態です。安定した収入を見込みやすいのが大きなメリットで、精算機や防犯カメラといった高額な設備投資も基本的には不要です。
ただし契約者数には限りがあるため、立地や住宅事情によっては収益に上限が見えやすい点には注意が必要です。また、一度契約が決まると、需要が高まったときでも料金を上げにくい点にも気を付けましょう。
一括借り上げ
一括借り上げは、駐車場を業者にまとめて貸し出し、決まった賃料を得る方法です。稼働率にかかわらず安定した収入が得られる点が強みですが、実際の利用が多くても契約額以上の収益は見込めないため、利益の上限が決まってしまうデメリットもあります。
ただし、実際の利用状況にかかわらず一定額が支払われる代わりに、利回りは自分で運営するよりも低くなる傾向があります。また、契約内容によっては途中解約や条件変更が難しくなる場合もあるため、いつまで貸し出したいかを明確にしてから契約しましょう。
駐車場経営のメリット
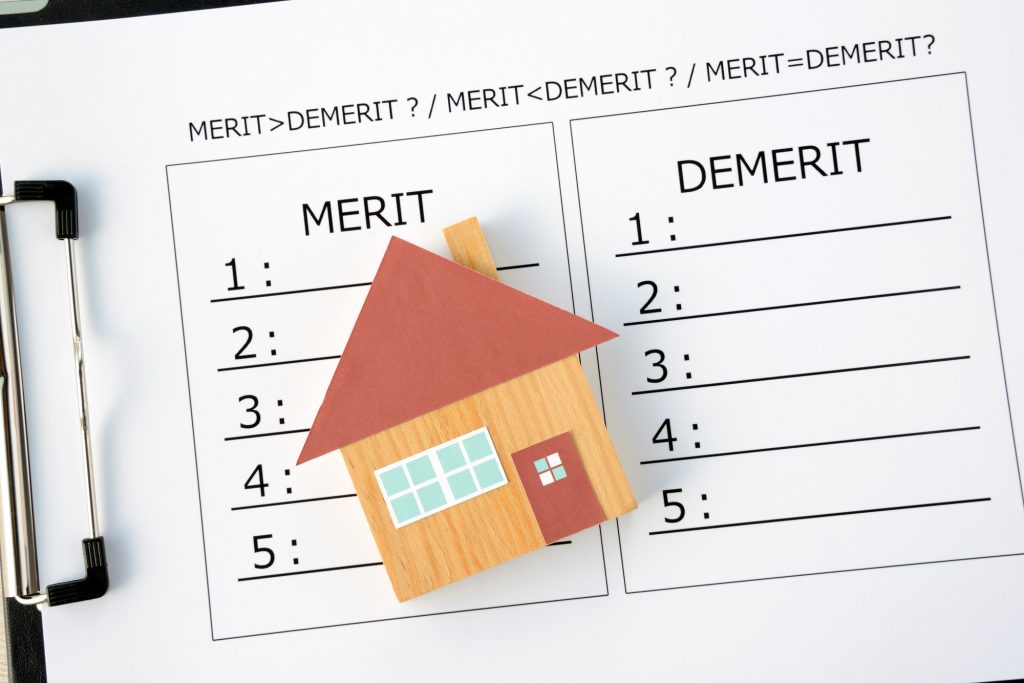
駐車場経営は他の土地活用よりも初期投資を抑えられ、リスクも少ないという大きな強みを持っていますが、それ以外にも以下のようなメリットを持っています。
- 狭小地・変形地の有効活用が可能
- 災害リスクが小さい
- 別の業態への切り替えが容易
建物を建てないという特徴が具体的にどう活かされるのか、それぞれ詳しく見ていきましょう。
狭小地・変形地の有効活用が可能
建物を立てる土地活用は、面積が少ない狭小地や、土地の境界がL字型のような変形地では難しい場合がありますが、駐車場ならレイアウトを工夫することで活用できることも多いです。
家を建てるには中途半端で、そのまま放置している遊休地を持っている場合は、駐車場が具体的な活用法として挙げられるでしょう。
ちなみに、駐車場の区画を考える際には、利用者の使い勝手を考えて、区画数よりも導線を優先した方が良い場合もあります。区画が多くても駐車しにくいと利用者から敬遠されることがあるため、適切なバランスで配置しましょう。
災害リスクが小さい
マンションやアパートといった建物経営では、地震や台風、火災といったリスクに備えて耐震補強や保険加入が必要ですが、駐車場は建物がないため、これらに備える必要性は低く、実際に被害に遭うリスクも少ないです。
駐車場で考えられる災害リスクは、舗装のひび割れや看板の破損、街灯がある場合の電球の割れや支柱の折れなどです。これらの被害があっても部分的な補修で済むことが多く、建物の大規模修繕に比べればコストはかなり低いです。
もちろん車止めやフェンスなど設備の維持管理は必要ですが、建物を持つ事業に比べればメンテナンスコストは軽く、長期的に安心して経営を続けやすいでしょう。
別の業態への切り替えが容易
駐車場はもともと建物がないため、周辺の需要や家族の事情、相続のタイミングなどで状況が変わった場合でも、比較的スムーズに用途を切り替えられます。例えば将来的に賃貸住宅や自宅を建てたい場合でも、建物の解体工事が不要なので柔軟に対応できます。
駐車場経営のデメリット
駐車場経営のコストもリスクも低いというメリットはとても魅力的ですが、その特徴は、裏を返すとローコストローリターンの傾向にあったり、競合が現れやすかったり、建物が無いため差別化しにくかったりといったデメリットにもつながります。
より具体化すると、以下のような点に注意が必要です。
- 土地の利用効率が低い
- 競合増加による収益性低下の可能性がある
- 税金負担が大きい
では、デメリットを軽減するためにどのような点に気を付けるべきか、それぞれ見ていきましょう。
土地の利用効率が低い
駐車場は建物を建てない分、土地一坪あたりの収益率が低くなる傾向があります。特に都市部の一等地では、同じ土地にアパートやマンションを建てた方が、収益性が高くなるケースが多く見られます。
また、駐車場は平面利用が基本のため、土地の広さに対して得られる収益が限られやすいという弱点もあります。建物であれば階数を増やして利用効率を高められますが、駐車場は原則として横にしか広げられません。
こうした性質から、駐車場経営は「短期的な活用」や「将来の建築計画までのつなぎ」として適しているケースが多いといえます。本格的に収益最大化を狙うのであれば、立地条件や土地の将来的な使い道を見据えた運用を検討しましょう。
競合増加による収益性低下の可能性
駐車場は始めやすいがゆえに、立地が良い場所を中心に新規参入が集まりやすく、つねに料金競争に巻き込まれる恐れが付きまといます。特にコインパーキングは開業のハードルが低いため、短期間で供給が急増しやすく、その結果稼働率が落ち込み、収益が思ったように伸びないこともあります。
また、駐車場は建物のような明確な差別化要素が少ないため、競合が増えると埋もれやすい点もデメリットです。ただし、完全に同質化してしまうわけではなく、防犯カメラやキャッシュレス決済、屋根付きスペースなど、利便性や安心感をプラスする工夫によって利用者に選ばれる可能性はあります。さらに、月極契約の導入など長期利用を意識した仕組みを整えれば、安定収入につなげることも可能です。
税金負担が大きい
意外かもしれませんが、駐車場は税金負担の大きさにも注意が必要です。住宅やアパートが建っている土地は、住宅用地の特例が適用されるため、固定資産税が最大で6分の1まで減額されますが、駐車場は更地の状態で運用するため適用されず、満額を納める必要が出てきます。
特に地価の高い都市部や市街地の広い土地を駐車場にした場合、固定資産税の負担感が大きくなりやすい傾向にあります。場所によっては、建物がある方が固定資産税の総額が安くなることもあり得ます。
そのため、駐車場経営を始める前には、必ず固定資産税と事業収支のシミュレーションを行っておきましょう。必要に応じて税理士に相談し、節税策や相続への影響も含めた長期的な対策を検討すると安心です。
収益を高めるための駐車場経営のコツ

最後に、駐車場経営で安定した収益を確保するためのコツを押さえておきましょう。
経営の成否は立地条件や運営方法だけでなく、料金設定や管理体制など、複数の要素がバランスよく機能してはじめて成果につながります。
そこでここでは、駐車場を一時的な活用手段にとどめず、長期的に利益を生み出す仕組みへと育てていくために必要なコツを5つ紹介します。
立地条件と需要をリサーチする
まずは、そもそも駐車場の需要があるかどうかを調べることから始めましょう。周辺の交通量や近隣施設、オフィスや商業エリアとの距離などを確認し、どれくらいの利用ニーズが見込まれるのかを把握します。
さらに、人口動態や将来的な開発計画もチェックしておくと、中長期的な稼働率を予測しやすくなります。都心なら商業施設の近さ、郊外なら住宅需要の動向など、エリアごとの特徴をしっかり捉えることが重要です。
競合相場を踏まえた賃料設定をする
駐車場の収益は、料金設定と稼働率で大きく変わります。周辺の相場をリサーチし、自分の土地や設備とのバランスを見ながら価格を決めていきましょう。
また、いくら稼働率を高く保てても、税金や維持管理費を下回ってしまっては意味がありません。必ず固定費がいくらかかるか把握しておき、そのうえで周囲との価格競争のことを考えてください。
なお、最近では、イベント開催時や繁忙期に料金を変動させる「ダイナミックプライシング」を導入する例も増えています。需要に応じて柔軟に料金を見直す姿勢が、収益を最大化するコツといえるでしょう。
設備投資や差別化戦略を検討する
駐車場はシンプルな施設ゆえに差別化が難しいと言われますが、工夫次第で利用者に「ここを選びたい」と思わせることは可能です。
まずコインパーキングの場合は、精算機やゲートシステム、防犯カメラなどの設備投資が基本になります。導入コストはかかりますが、利便性や安心感を高める設備は稼働率の向上につながりやすいため、費用対効果を見極めて検討してみましょう。
月極駐車場の場合は、照明や区画線、防犯対策を整えるだけでも利用者の満足度は大きく変わります。さらに、屋根付きスペースやEV充電設備といった付加価値を導入すれば、競合との差別化にもつながるでしょう。
その他にも最近では、キャッシュレス決済や専用アプリを通じた予約機能、ウェブからの空き状況確認など、デジタルサービスの導入が利用者に選ばれる大きな要因になっています。特に都市部では「使いやすさ」や「便利さ」が決め手となることが多いため、最新のサービスを積極的に取り入れることが、安定収益への近道となります。
信頼できる業者を選ぶ
設備の維持管理やトラブル対応など、専門的なノウハウが必要になる課題に対応するためにも、信頼できる管理会社は必ず見つけておきたいところです。
選ぶ際にはサービスの料金だけで判断せず、実績やサポート体制、対応の速さなども確認しましょう。サポートが不十分な業者と契約してしまうと、トラブル時に対応が遅れ、利用者の不満につながる恐れがあります。
長期的に安心して任せられるパートナーを見つけられれば、結果として収益の底上げにつながり、安定した駐車場運用が可能になるでしょう。
税金・相続対策をしておく
駐車場経営では、住宅用地の軽減措置が使えないため、あらかじめ固定資産税や都市計画税の負担が大きくなることを見越した収支計画を立てましょう。税金を見落として計画を進めてしまうと、思った以上に利益が残らず、経営が不安定になる可能性があります。
相続の場面でも注意が必要です。建物がない土地は、小規模宅地等の特例が適用されず、評価額が高く算定されやすいため、そのままでは相続税の負担が大きくなる傾向があります。ただし、将来的に建物を建てるプランを組み込んだり、税理士に相談して節税策を検討したりすれば、リスクを軽減できる余地があります。
税務や相続は「避けられない負担」と捉えるのではなく、「計画的にコントロールすべき項目」として扱うことが大切です。事前に備えておくことで、安定した収益の確保につながります。
【まとめ】駐車場経営成功の鍵は「事前のシミュレーション」
駐車場経営は少ない初期費用で始めやすい一方、固定資産税や空車リスクなどを考慮しなければ収益が安定しにくい活用方法です。条件次第で手堅い収益源にもなりますが、逆に想定外の出費で赤字に転じる可能性もあるため、事前のシミュレーションは丁寧に行いましょう。
そして何より大切なのは、その土地をどう活かしたいのかというオーナー自身の考えです。同じ立地でも、短期収益を重視するか、長期的に安定を求めるかによって最適な運営スタイルは変わります。地図上の数字だけでなく、実際に利用者の動きや周辺環境を観察しながら、具体的なプランを考えていきましょう。
迷ったときは、一人で抱え込まずに「アキサポ」のように経験豊富な専門家に話を聞いてみるのも有効です。数字では見えないリスクや可能性を教えてもらえることで、漠然とした不安が「具体的な行動」に変わり、土地が持つ力をより前向きに活かせるようになるでしょう。
この記事の監修者

岡崎 千尋 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
都市計画コンサルタントとしてまちづくりを経験後、アキサポでは不動産の活用から売買まで幅広く担当してきました。
お客様のお悩みに寄り添い、所有者様・入居者様・地域の皆様にとって「三方良し」となる解決策を追及いたします。








