公開日:2025.10.05 更新日:2025.09.26
家賃収入で資産形成!初心者が押さえるべきポイントと始め方

不労所得を得る方法として耳にすることが多い「家賃収入」ですが、「本当に儲かるのか?」「安定性やローン返済の負担は大丈夫か?」など、不安な面ばかりが気になる方も多いのではないでしょうか。
不動産投資は大きな資金を伴うため、十分な知識を持たずに始めてしまうと、収益どころか赤字になってしまうリスクも伴います。
そこで本記事では、家賃収入の仕組みやメリット・リスク、必要な手続きや管理方法などを網羅的に紹介します。さらに、安定収入につなげるための考え方も解説しますので、家賃収入を検討している方はぜひ参考にしてください。
目次
家賃収入とは?基本的な仕組みを解説

家賃収入とは、住宅やアパートなどを貸し出すことで入居者から得られる賃料のことです。毎月安定した収入が見込めるため、空き家を持っている人にとっては資産を有効に活用できる手段といえるでしょう。
ただし、収益の安定度は立地や築年数、さらには経済情勢など、さまざまな要素の影響を受けるため「絶対安定」とはいきません。そのため、実際に貸し出す前には地域の需要や家賃相場を調べ、どの程度の収益が期待できるのかを把握しておくことが必要になってきます。
そこで、まずは家賃収入の仕組みを理解するために、賃貸経営で必ず学んでおきたい3つのポイントを見ていきましょう。
居住用賃貸と事業用賃貸の特徴と違い
まずは、賃貸物件の大きな区分である「居住用賃貸」と「事業用賃貸」の特徴を理解しましょう。
居住用賃貸には一戸建てやアパート、マンションなどが含まれます。生活の場として利用されるため安定した需要があり、景気の影響を受けにくいのが特徴です。ただし安定している分、家賃を大きく引き上げるのは難しいため、長期的に収益を維持するには空室対策や定期的なメンテナンスで物件の魅力を保つ工夫が欠かせません。
一方、事業用賃貸は店舗や事務所、オフィスビルなどが対象で、契約条件次第では高い家賃設定も可能です。その分、景気の悪化やテナントの業績不振によって退去が発生するリスクがあり、居住用に比べて収益の変動が大きい点には注意が必要です。
家賃収入が得られる物件の種類
次に居住用賃貸と事業用賃貸に含まれる物件の種類を見ていきましょう。ここでは代表的な4種類を解説します。
- 居住用賃貸:一戸建て
ファミリー層からの需要が高く、長期入居につながりやすいのが魅力。特に学区や子育て環境が良い地域では、安定した入居者を確保しやすい傾向にある - 居住用賃貸:マンション・アパート
複数の部屋を持つため、1戸空室になっても他の部屋の家賃収入でリスクを分散できるのが魅力。管理会社を活用すれば維持管理もしやすく、初心者でも取り組みやすい - 事業用物件:店舗
家賃水準は居住用より高めで、1件あたりの収入も大きくなる傾向がある。不況や業績悪化による退去リスクには注意が必要 - 事業用物件:事務所・オフィスビルなど
企業や事務所向けに貸し出す物件で、都心部やビジネス街では安定した需要が見込める。景気動向や企業の移転計画に左右されやすい点には注意
家賃収入ビジネスの安定性
家賃収入ビジネスは、地域の需要や入居者のニーズを把握することができれば比較的安定した収益を得ることができます。さらに空室リスクをなるべく下げたい場合は、賃貸物件の運用に強い管理会社と連携したり、サブリース(一括借り上げ)を利用したりといった対策を取り入れる方法もあります。
なお、長期的な運用を成功させるためには、定期的なメンテナンスで物件の価値を保ち、さらに家賃設定の見直しなどが大切です。目先の収益だけにこだわらず、長期的に利用され続ける物件を目指しましょう。
賃貸経営で家賃収入を得るメリット・デメリット
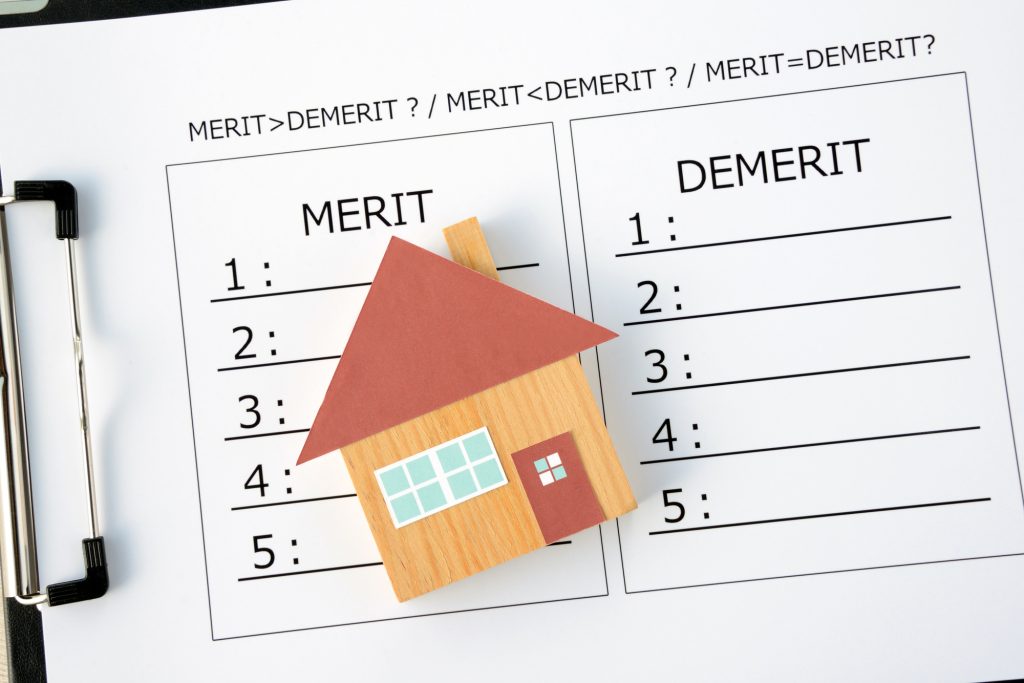
家賃収入は魅力的な選択肢ではありますが、誰にとっても正解というわけではありません。たとえば「安定した副収入を得たい人」には向いていても「短期で大きな利益を狙いたい人」には合わないケースがあります。ここでメリット・デメリットを整理し、自分の資産状況やライフプランに合う投資なのかを見定めましょう。
メリット:安定収入と資産形成が見込める
賃貸経営で家賃を得る主なメリットは、以下のとおりです。
- 毎月の安定収入を得られる
- ローン完済後は手残りが大きくなる
- 将来的に売却益が期待できる
- 節税や相続対策に役立つ
家賃収入は、給与収入とは別に安定したキャッシュフローを生み出せる点が大きな魅力です。特にローンを返済したあとは収益のほとんどが利益として残るため、老後の生活資金や新たな投資の原資として活用しやすくなります。
また、立地や管理状態が良ければ将来的に資産価値が上昇し、売却益を得られる可能性も見逃せません。
その他にも、相続対策の効果が高い点も大きなメリットです。不動産は現金よりも低い評価額で相続財産に算入される傾向があるため、相続税の課税額を抑えやすくなります。さらに賃貸物件の場合は「貸家建付地」として土地の評価額が減額されることもあります。
デメリット:空室リスクや不動産市況の影響
賃貸経営に取り組むにあたって注意すべき主なデメリットは以下のとおりです。
- 空室や滞納による収入減少リスク
- 修繕費や管理コストの負担
- 不動産市況の下落リスク
- 金利上昇による返済負担増
特に注意すべきなのが空室や滞納による収入減少のリスクです。家賃収入が途絶えてしまうと、ローン返済や維持管理費の負担が重くなり、キャッシュフローが一気に悪化する可能性があります。
また、将来的な売却を見込んでいる人にとっては、不動産市況の下落や景気後退によって資産価値や家賃相場が下がるリスクも要注意です。景気悪化局面では賃料の引き下げを求められるケースもあり、想定より低い利回りに落ち込むこともあります。
さらに、変動金利でローンを組んでいる場合は金利上昇が収支を直撃することもあります。これらのリスクに備えるには、管理会社との連携や定期的な市場調査を行い、柔軟に家賃設定や運営方針を調整することが必要です。
賃貸経営における収入の内訳

次に、賃貸経営における家賃収入の種類を把握しましょう。主な収入には以下の4種類があります。
- 家賃
- 礼金
- 更新料
- 共益費や駐車場収入などの付帯収入
収入の構造を把握しておくことは、収支計画を組み立てるうえで欠かせないポイントです。仮に家賃だけを基準にしてしまうと、初期費用や更新料、付帯収入といった実際のキャッシュフローを見落とし、想定よりも収益が少なくなるケースがあります。
投資回収の見込みを正確に計算し、無理のない運営計画を立てるためにも、ここですべての収入源を把握しておきましょう。
家賃
家賃は、入居者から毎月受け取る賃料のことです。賃貸経営の最も基本的な収入であり、ローン返済や維持管理費をまかなう土台となります。
家賃の相場は、主に物件の立地や築年数、間取りによって決まりますが、その他にも周辺の競合物件や需要動向、物価や景気などによっても変化します。家賃を変えずにいると周囲の相場とズレる恐れがあるので、定期的に市場を調査して相場感を把握するよう心がけましょう。
礼金
礼金は契約時に一度だけ受け取る、大家にお礼の気持ちを表すお金です。相場は地域や物件の特性によって異なりますが、1〜2か月分の家賃を設定するケースが多いです。
ただ、最近では周辺の物件と差別化をするために、あえて礼金を低く設定する例もあります。特に都市部の単身者向け物件や競合が多いエリアでは「礼金ゼロ」を打ち出している物件も多いです。
更新料
更新料は、賃貸契約を更新する際に受け取るお金のことです。相場は家賃の0.5〜1か月分程度のケースが多いです。ただし、更新料の有無は地域性が高く、そもそも設定していない場合もあります。
なお、更新料を設定する際には必ず、入居者に長期的に住んでもらうことを第一に考えましょう。更新時に退去されてしまうと以降の収入が得られなくなりますし、逆に原状回復費や新たな募集コストが発生する可能性もあります。
共益費
共益費は、廊下やエレベーターなど共用部分の維持管理のために徴収する費用です。家賃に上乗せして徴収するのが一般的で、これにより定期的な維持管理コストを賄い、物件を健全な状態に保ちやすくなります。
駐車場や駐輪場などのオプション費用
駐車場・駐輪場の利用料や、敷地内の付帯設備などからも収益が見込めます。付帯設備は入居者の利便性向上にもつながるので、上手く使えば満足度向上にも効果的です。
ただし、立地や需要によって利用率が変動するため、過度に収益を当て込むのではなく、補助的な収入として位置づけるのがよいでしょう。
賃貸経営における支出の内訳

賃貸経営で目をそらしてはならないのが、継続的な支出の項目です。この点の見積もりが甘いと、想定よりもお金が手元に残らないリスクがあります。主な支出には次の4種類があります。
- 税金
- 維持管理費
- 減価償却費
- 金融機関への返済と金利
これらの性質を理解しておくことで、収支計画をより現実的に立てられるようになります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
税金
税金でまず考慮すべきなのが、毎年必ず発生する固定資産税と都市計画税です。税率は以下のとおりです。
- 固定資産税:固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)
- 都市計画税:固定資産税評価額 × 0.3%(制限税率)
また、物件を購入する場合は、購入時に以下の税金がかかります。
- 不動産取得税:固定資産税評価額 × 4%(住宅を取得した場合は地方税法附則による軽減措置で3%に)
- 登録免許税
- 所有権移転登記(売買):固定資産税評価額 × 2%
- 所有権移転登記(相続):固定資産税評価額 × 0.4%
- 抵当権設定登記:借入金額 × 0.4%
なお、登録免許税にも軽減税率の特例がありますが、これは自己居住用の不動産を取得した場合に適用されるため、賃貸を目的とした場合は原則として活用できません。
維持管理費
物件の維持管理費用も継続的にかかる大きなコストです。代表的な項目には以下のようなものがあります。
- 修繕費:数万円規模の軽微な修理から、数百万円規模の外壁や屋根、水回りなどの大規模修繕まで幅広く発生する
- 管理費:管理会社へ委託する場合に払う費用。家賃収入の3〜5%程度が相場
- 火災保険料:建物構造や補償内容によるが、年間数万円〜十数万円かかるのが一般的
- 共用部の光熱費・清掃費:アパートやマンションの共用部分の電気代や清掃費など
なお、これらの費用は、青色申告を利用すれば経費として計上することができます。経費の額に応じて所得税や住民税を減らせるため、漏らさず申告しましょう。
減価償却費
減価償却費とは、建物や設備の購入費用を法定耐用年数に応じて分割して計上する費用のことです。実際に現金が出ていくわけではありませんが、帳簿上は経費として扱えるため、税負担を軽減できるのが特徴です。
新築であれば木造住宅は22年、鉄筋コンクリート造は47年といった耐用年数が定められており、その期間にわたって取得額を少しずつ経費にしていきます。
金融機関への返済と金利
投資用物件を購入する際に金融機関から借り入れるローンの返済費用です。家賃収入の中で最も大きな支出になることが多いため、計画段階から慎重に見積もる必要があります。
一般的な金利は、変動金利で年1.5〜4%程度、固定金利で年2~5%程度が目安です。ただ、金利は経済情勢によって変動するため、借入時の水準が将来にわたって続くとは限りません。金利の変動が心配な場合は、金額が変わらない固定金利を選ぶのも手です。
家賃収入を得るまでの流れ

ここからは、実際に賃貸経営を始めて家賃収入を得るために行うべきことを、4つのステップに分けて解説します。一般的な流れは以下のとおりです。
1.物件探し
2.融資審査
3.物件購入から入居者募集
4.家賃回収と管理の方法
では、それぞれを詳しく見ていきましょう。
1. 物件探し
まずは投資対象となる物件選びから始めましょう。ここでは、物件の価格や利回りはもちろん、家賃相場や需要動向、周辺環境なども踏まえて物件の将来性もチェックしましょう。
なお、物件探しはターゲット層を明確にしてから始めるのがおすすめです。たとえば単身者向けなら駅近物件やワンルーム物件など、ファミリー層向けなら学校や公園からの距離や、間取りのゆとりなどがポイントになります。
2.融資審査
物件を決めたら、次は金融機関の融資審査を受けます。チェックされる項目は、年収、勤務先、既存の借入状況、自己資金の割合などです。
ここで注意すべきなのが、融資審査を複数の金融機関から受けることです。審査基準や融資プランは金融機関によって異なるため、少しでも有利な条件で契約できるよう、可能な範囲で比較検討しましょう。
3. 物件購入・入居者募集
融資が下りて物件を購入したら、次は入居者募集に進みますが、その前に物件の価値を高めるためにリフォームやクリーニングを行っておきましょう。物件がきれいだと第一印象が良くなり、空室期間を短縮できる可能性が高まりますし、ここで細かな修繕をしておけば、物件を長持ちさせることにもつながります。
また、賃料の設定もこの時点で行います。地域の家賃相場を調査し、物件の立地・築年数・設備と照らし合わせて、相場感のある適正価格を設定しましょう。高すぎると成約が遅くなったり、空室が長引いたりするリスクが高まり、安すぎると収益性が低下します。
4. 家賃回収と管理の方法
利用者が入居したあとは、毎月の家賃の回収や物件の維持管理などが始まります。
家賃回収と管理を無理なく続けるためのポイントは、仕組み化と役割分担にあります。管理は自分でもできますが、すべてをこなすのは負担が大きすぎるので、可能な範囲で管理会社を活用しましょう。
管理会社は、入居者への迅速かつ適切な対応が期待できるのも大きなメリットです。何かあった時の対応が良ければ満足度が高まり、結果的に長期入居や空室率の低下につながります。
【まとめ】家賃収入は「計画的な運営」で安定した資産に
この記事を通じて、家賃収入を安定させるには、収益の仕組みを正しく理解し、リスクに備えながら計画的に運営することが大切だと分かったと思います。
賃貸経営は、管理方法やリスクの見極め方によって「頼れる収入源」にも「重荷」にもなり得ます。だからこそ、数字に基づいたシミュレーションや専門家への相談を取り入れ、机上の理想ではなく現実的な判断をしていくことが欠かせません。
もし一歩踏み出そうと思ったなら、空き家活用のプロフェッショナルである「アキサポ」が力強いサポーターになれるはずです。数多くの実績に基づいて、あなたが持っている物件の魅力を引き出せる活用方法を提案します。
この記事の監修者

岡崎 千尋 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
都市計画コンサルタントとしてまちづくりを経験後、アキサポでは不動産の活用から売買まで幅広く担当してきました。
お客様のお悩みに寄り添い、所有者様・入居者様・地域の皆様にとって「三方良し」となる解決策を追及いたします。








