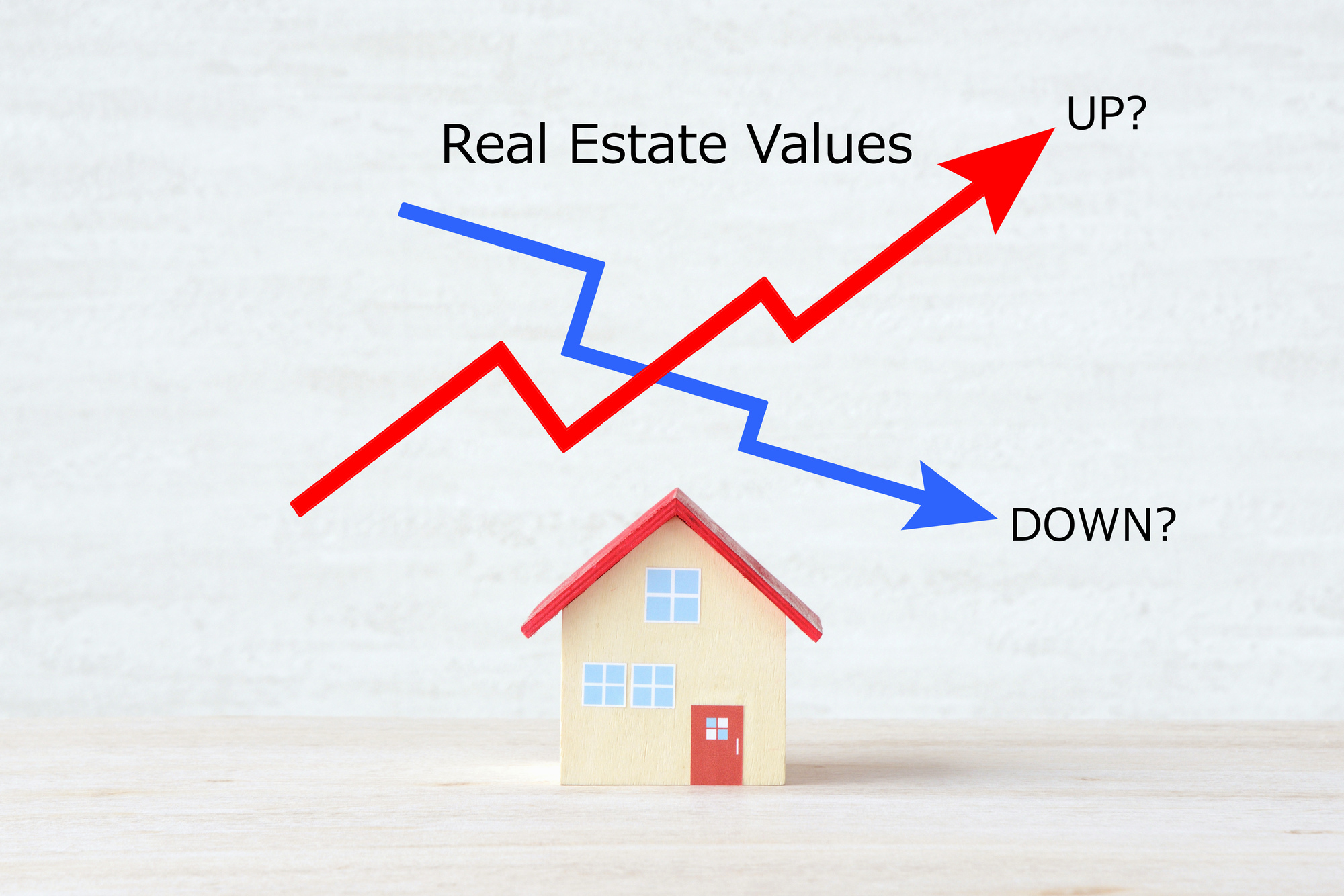公開日:2025.10.06 更新日:2025.09.26
一戸建ての固定資産税はいくら?基礎知識から税率、評価額まで徹底解説

一戸建ての住宅を所有する上で、固定資産税は切っても切れない存在です。しかし、実際にいくらかかるのかが分からず、思ったより高額になるのではないかと不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
実際、固定資産税の金額は、建物や土地の評価額、自治体ごとのルールによって決まるため、一律にいくらと断言できるものではありません。ただ、仕組みを知ればおおよその目安を把握でき、さらに軽減措置を活用することで負担を抑えられる場合もあります。
そこでこの記事では、一戸建ての固定資産税がどのように計算されるのか、おおよその水準、そして活用できる軽減措置までを整理しました。将来の出費を見通し、安心して暮らすための参考にしていただければ幸いです。
目次
固定資産税とは?仕組みと納税義務をまとめて確認

固定資産税は、土地や家屋、償却資産といった固定資産を所有している人に課される地方税です。主に土地と建物が課税対象で、納税義務は毎年1月1日時点の所有者に発生します。年の途中で住宅を売却した場合でも、その年の固定資産税は1月1日の所有者に納税の義務があります。
標準税率は1.4%と定められていますが、市町村は財政上の理由などから、これと異なる税率を定めることができます。これを財政上その他特別の必要がある場合における制限税率といい、一部の自治体では1.6%や1.7%で運用されているケースもあります。
税額が決まる仕組み:評価額と固定資産税の関係
固定資産税額は、不動産の価値を表す「評価額」に税率を乗じて算出されます。評価額は市町村が現地調査や資料をもとに算出しますが、一般的に、建物は建築費の6〜7割程度、土地は時価の7割程度が目安といわれています。
この評価額は3年ごとに価値を算出しなおす「評価替え」によって見直されます。評価替えには、市場価格の変動や建物の老朽化、その間に行った建築行為などが反映されます。
なお、評価額は毎年春に送付される「固定資産税納税通知書」に記載されているほか、自治体が管理している「固定資産課税台帳」でも確認できます。課税台帳は役所で閲覧できるため、納税通知書を紛失した場合は窓口へ行ってみましょう。
一戸建ての住宅にかかる固定資産税の計算方法

一戸建ての固定資産税は、土地と建物それぞれの評価額を合算し、そこに税率をかけることで算出されます。今回は税率を標準税率の1.4%で計算してみましょう。
これを計算式で表すと以下のようになります。
固定資産税額 = (土地評価額 + 建物評価額) × 1.4%
イメージをより具体化するために、以下の条件で計算してみましょう。
- 土地評価額:2,400万円
- 建物評価額:1,200万円
これを計算式で表すと以下のようになります。
(2,400万円 + 1,200万円) × 1.4% = 50万4,000円
この50万4,000円が年間の固定資産税額となり、この額を4期に分けて納めていくことになります。
新築と中古で計算方法は変わる?
新築と中古で基本的な計算式に違いはありません。ただし、築年数によって評価額や適用される軽減措置が異なります。以下に、それぞれの特徴をまとめました。
- 新築住宅
一定の要件を満たせば、建築後3年間(長期優良住宅なら5年間)建物部分の固定資産税が2分の1になる制度がある。特に新築時は評価額が高く算定されやすいため、この軽減措置の有無で初期の負担額が大きく変わる。 - 中古住宅
新築住宅のような減税制度は使えないが、築年数の経過によって建物の評価額が減少するため、税額は低めに算出される傾向がある。ただし土地の評価額は築年数と無関係なので、地価が高いエリアでは中古でも税額がそれほど下がらないケースもある。
なお、新築後最大5年間適用される軽減措置が終了すると、急に税額が跳ね上がることがある点には注意が必要です。これは中古物件でも適用されるため、築浅の中古住宅を購入する際には注意しましょう。
一戸建ての住宅に使える固定資産税の軽減措置

一戸建て住宅には、税負担を抑えるための軽減制度がいくつも用意されています。新築時や耐震改修、省エネ工事、さらには災害による損壊といった状況ごとに適用できる仕組みがあるため、あらかじめ知っておくと安心です。
新築住宅の固定資産税減額措置
新築住宅の固定資産税減額措置は、新しく建てた一戸建て住宅の固定資産税が、3年間にわたり半額になる制度です。住宅取得直後はローン返済や引っ越し関連の費用が重なりやすい時期ですが、この制度を活用すれば出費を抑えながら暮らしをスタートできます。
対象となるのは延床面積50㎡以上280㎡以下の新築住宅と幅広く、マイホームを建てた多くの世帯が利用可能な制度となっています。さらに長期優良住宅の認定を取得した場合は、軽減期間が5年間に延長され、より長く減税を受けられます。
耐震改修に伴う固定資産税の減額
耐震改修に伴う固定資産税の減額は、1982年1月1日以前に建築された住宅が対象です。現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税が2分の1に軽減されます。
対象となるのは、制度で定められた工事内容を満たし、所定の手続きを経て耐震性能が確認された住宅です。築古の戸建てを所有する人や、中古住宅を相続・購入した人にとっては、安全性の確保と経済的メリットを両立できる有効な選択肢といえるでしょう。
バリアフリー・省エネ改修に伴う減額
バリアフリー化や省エネ化を行った場合も、固定資産税の減額制度を利用できる場合があります。
たとえば、一定の手続きに基づいて手すりの設置や段差解消、浴室の改良といったバリアフリー改修工事を行った場合は、翌年度の税額が3分の1減額されますし、一定の基準を満たしたうえで、断熱材の追加や複層ガラスへの交換などの省エネ改修工事を行った場合は、翌年度の固定資産税が120㎡の床面積相当分まで3分の1減額されます。
災害で被害を受けた住宅への減免制度
災害で住宅が被害を受けた場合は、災害発生の日以降の固定資産税が全額または一部免除される制度が利用できる可能性があります。対象となるのは、地震や台風、大雨などで住宅が損壊し、生活に支障をきたした場合で、免除される割合は被害の程度に応じて決定されます。
減額を受けるには、市町村へ罹災証明書を提出して申請する必要があります。修繕や建て替えには多額の費用がかかりますが、この制度を利用すれば税負担を抑えられ、復旧に向けた資金を確保しやすくなります。特に災害後の出費が重なる時期に、大きな支えとなる制度といえるでしょう。
土地に使える固定資産税の軽減措置
住宅用地や特定の条件を満たす土地には、固定資産税の負担を抑えるための軽減制度が用意されています。制度を正しく理解しておけば、無駄な税負担を避け、長期的な資金計画にも役立ちます。
住宅用地の特例(小規模住宅用地・一般住宅用地)
土地の軽減措置でもっとも代表的なのが「住宅用地の特例」です。これは住宅が建っている土地に適用され、住宅1戸あたり200㎡までが「小規模住宅用地」として評価額を6分の1に軽減、200㎡を超える部分が「一般住宅用地」として3分の1に軽減されます。
たとえば、土地の評価額が3,000万円で敷地面積が240㎡の場合を考えてみましょう。
200㎡部分(小規模住宅用地):2,500万円相当 → 6分の1で約417万円
残り40㎡部分(一般住宅用地):500万円相当 → 3分の1で約167万円
この結果、課税標準額は約584万円まで圧縮されます。ここに標準税率の1.4%をかけると、年間の固定資産税は約8万1,700円となり、特例がない場合の42万円から大幅に軽減されることがわかります。
災害による土地の減免措置
災害で土地が被害を受けた場合にも、災害による固定資産税の免除制度を活用できます。基本的な制度は建物と同じで、土地の損害具合によって固定資産税の全額または一部が免除されます。
対象となるのは、地震による地盤沈下や液状化、土砂崩れや地割れなどで居住や利用が困難になった土地で、減免を受けるには、市町村に申請して「罹災証明書」や「被害程度を示す資料」を提出する必要があります。
自治体独自の減免制度
固定資産税や都市計画税には、国の制度とは別に、市区町村ごとに独自の減免措置が設けられている場合があります。たとえば、大規模な公共事業によって一時的に土地の利用が制限されるケースでは、その期間に応じて固定資産税が軽減される制度があります。また、都市計画税についても、高齢者や低所得世帯を対象にした独自の減免を実施している自治体も見られます。
利用するには、役所の資産税課などで申請が必要で、収入状況や利用制限の証明書類を提出することが一般的です。国の一律の制度と異なり、地域事情に合わせて柔軟に設計されているため、条件に合えば思わぬ節税につながる可能性があります。
特に、再開発エリアや公共事業予定地に土地を持っている人、または固定資産税の負担が重く感じられる世帯にとっては、知っておくと助かる仕組みといえるでしょう。
固定資産税が変動する主な要因

固定資産税の額は一律ではなく、建物の築年数や構造、リフォームの有無、さらに土地の価格動向など複数の要素が絡み合って決まります。古い家は税額が安くなる傾向がある一方で、土地の評価が上がったり改修工事を行ったりすると負担が増すこともあります。ここでは代表的な3つの要因を確認しておきましょう。
建物の経年減価補正率
建物の固定資産税評価額は、築年数が経過するにつれて「経年減価補正率」という係数によって減少していきます。これは建物の老朽化を反映させる仕組みで、時間の経過に応じて資産価値が下がることを前提にしています。
ただし、評価額が下がるのは建物部分だけであり、土地には反映されません。そのため、地価が上がっている場合は、建物が古くなっても、トータルの固定資産税があまり下がらないこともあります。
3年ごとの評価替え
固定資産税の評価額は、3年に1度の「評価替え」で見直されます。このときは必ず税額が下がるわけではなく、市場価格の動きによっては上がることもあります。特に都市部のように地価が上昇しやすい地域では、建物の評価が下がっても土地の評価が上がり、結果的に税額が増えるケースもあり得ます。
一方で、人口減少が進む地域などでは土地価格が下がり、建物の評価減とあわせて税負担が軽くなる傾向が強いです。ただし、必ずしも地域一律に下がるとは限らず、場所ごとに差が出やすいのが実情です。
つまり、固定資産税は「築年数が経てば安くなる」と単純に考えることはできないということです。将来の負担を見通すには、建物の老朽化だけでなく、地域の地価動向もあわせて確認しておくことが大切です。
リフォームや建て替え
リフォームや大規模な改修を行うと、建物の資産価値が上がったと判断され、評価額が再計算されることがあります。特に耐震補強や省エネ改修など性能を大きく向上させる工事では、翌年度から固定資産税が増えるケースもあります。
とはいえ、すべての工事が増税につながるわけではありません。耐震・省エネ・バリアフリーといった一定のリフォームについては、法律で軽減措置が定められており、条件を満たせば建物部分の固定資産税が翌年度1年間に限り2分の1や3分の1に減額される制度を利用できます。
また、建て替えをした場合は、評価額が新築として算定し直されるため、従来より税額が高くなる可能性があります。ただし、新築住宅に対する3年間の減税措置や長期優良住宅に対する5年間の減税措置も利用できるようになります。
【まとめ】一戸建ての固定資産税を正しく理解し、負担を最小限に抑えよう
この記事を通じて、一戸建ての固定資産税は毎年同じ金額を支払うものではなく、軽減措置の終了や地価の変動によって大きく変動する可能性があることが分かったのではないでしょうか。とくに新築から数年後に減税が切れるタイミングや、自治体による評価替えの時期は負担が増える分岐点になりやすいです。
だからこそ、固定資産税の仕組みをよく知り、計画に組み込めるコストとして考慮する必要があるのです。まずは住宅を取得したあとに「いつ」「どんな」変化が起こるのかを確認するところから初めてみましょう。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。