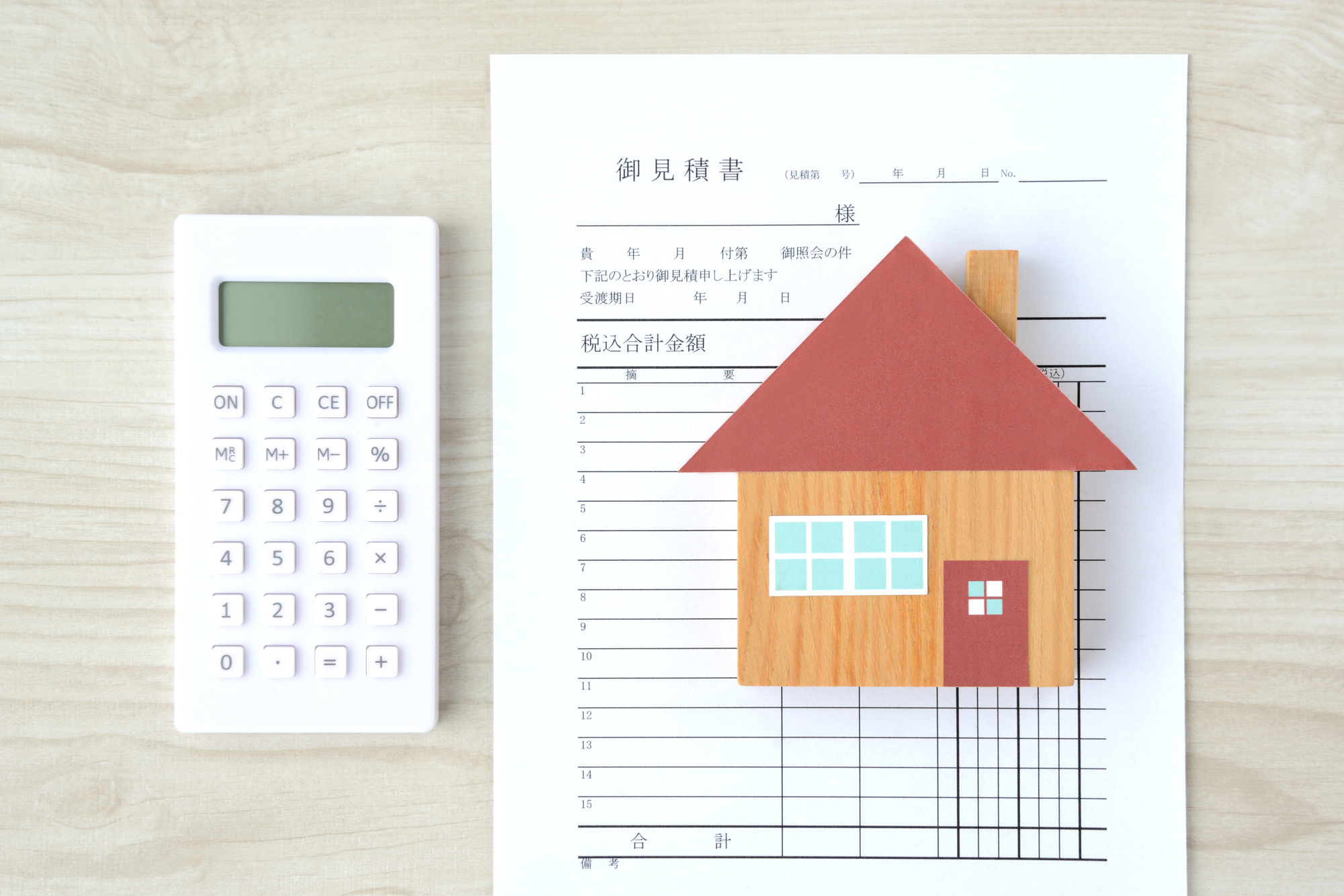公開日:2025.10.09 更新日:2025.09.29
不動産所得の確定申告を徹底解説!家賃収入を正しく計算・申告するポイント

賃貸物件の運用を始める際のハードルのひとつに、毎年の確定申告があります。家賃収入は魅力的でも、正しく申告できるか不安で一歩踏み出せない方は少なくありません。
実際、確定申告を誤ると余計な税金を払うことになったり、控除や還付のチャンスを逃したりするリスクがあります。だからこそ、不動産所得の仕組みと申告の流れを早めに理解しておくことが大切なのです。
そこでこの記事では、不動産所得の確定申告について、その定義から申告が必要になる条件、計算方法、手続きの流れまでを解説します。さらに、会社員が副業で不動産を所有する場合の注意点も整理しました。読み終えたときには「自分はどのケースに当てはまるか」「次に何を準備すればよいか」がはっきりわかるはずです。
目次
不動産所得の確定申告が必要になる条件は?

まずは確定申告が必要になる条件を整理しましょう。
不動産所得の確定申告は、不動産収入から必要経費を差し引いた「所得」があるすべての人に必要です。ただし、給与所得者は、年末調整済みの給与所得以外の所得(不動産所得など)が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要ですが、原則、住民税の申告は必要となります。
また、所得額が20万円以下でも、別に給与を2,000万円を超えて受け取っている場合や、公的年金等を400万円を超えて受け取っている場合、2カ所以上から給与を受け取っている場合でも、主たる給与以外の給与や他の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。
一方で、不動産経営を青色申告で行う場合は、所得が20万円以下でも帳簿を作成し、申告書を提出する必要があります。青色申告には最大65万円の特別控除など大きなメリットがありますが、その代わりに記帳や決算書の作成が必須となります。
所得になる不動産収入の種類
次に、所得を計上する際に対象になる収入の種類を説明します。主な収入は以下のとおりです。
- 家賃
- 駐車場代
- 共益費(オーナーが受け取って管理する場合)
- 礼金
- 更新料
- 名義書換料
- 違約金
- 敷金・保証金(返還を要しないもの)
- 原状回復の実費清算(内容によっては預り金扱いになることがある)
ここで注意したいのは、敷金や保証金など一時金の扱いです。返還義務のある部分は「預り金」ですが、敷引・償却といった返還しない部分は「収入」として計上します。また、明け渡し協力金については、契約書など明確な根拠があれば収入に含める必要があります。
事業的規模の認定と青色申告とは
不動産経営の規模が大きいと「事業的規模」と判断され、最大で65万円の青色申告特別控除が受けられるようになります。
事業的規模と判断される一般的な目安は、いわゆる『5棟10室基準』です。ただし判定は総合的に行われ、棟数や室数のみで一律に決まるわけではありません
ただし、単純に戸数や棟数だけで決まるわけではなく、継続性や収益管理体制、反復して貸し付けを行っているかなどの実態も加味されます。
不動産所得の計算方法

ここからは確定申告に計上する「不動産所得」の計算方法を見ていきましょう。計算は大きく以下の3ステップで進めていきます。
- 1.1年間の総収入金額を集計する
- 2.必要経費を集計する
- 3.総収入から経費を差し引いて不動産所得を求める
例えば、年間の家賃収入が180万円、更新料が10万円、返還しない敷金が5万円あり、合計195万円の収入があった場合を考えてみます。
経費としては、固定資産税12万円、管理委託料18万円、修繕費15万円、保険料2万円、減価償却費30万円、借入利息10万円で、合計87万円とします。
この場合の不動産所得は以下のとおりです。
- 総収入:195万円
- 経費合計:87万円
- 不動産所得:195万円 − 87万円 = 108万円
この108万円が確定申告で申告すべき不動産所得となります。この場合、20万円を超えているので確定申告が必要です。
控除額の求め方
不動産所得を算出した後は、そこからさらに各種控除を差し引くことができます。これにより、所得額をさらに下げることが可能です。
不動産所得に関わる主な控除は次のとおりです。
- 青色申告特別控除(55万円/65万円)
- 青色事業専従者給与や白色の専従者控除
- そのほか基礎控除や医療費控除など、個人全体で使える所得控除
特に青色申告特別控除は影響が大きく、条件を満たせば最大65万円を差し引けます。
例えば、不動産所得が108万円の場合に65万円控除を適用できれば、所得額は43万円
になります。
減価償却費の取り扱い
減価償却とは、建物や設備などの資産の取得費用を、耐用年数に応じて毎年少しずつ必要経費として計上する会計上の仕組みです。不動産所得の計算では、建物本体や給湯器・エアコンといった設備が対象になります。土地は価値が減らないとされるため対象にはなりません。
減価償却費の計算は『取得価額(建物部分) × 定額法償却率』で求めるのが基本です。例えば、建物の取得価額が1,500万円で耐用年数が22年の場合は以下のようになります。
1,500万円 ÷ 22年 = 約68.1万円
ただし、中古物件の場合は耐用年数の考え方が異なります。建物の構造や用途ごとに定められた法定耐用年数を超えている場合は法定耐用年数の20%を耐用年数と考え、その年数に応じて減価償却を、法定耐用年数を超えていない場合は、法定耐用年数から経過年数を差し引いた値に、経過年数の20%を足した値を耐用年数と考えて、その年数に応じて減価償却を行います。
複数物件を所有している場合の計算方法
物件を複数所有している場合は、まず物件ごとに収入と経費を整理し、それらを合算して、全体の不動産所得を求めます。このとき、赤字の物件があった場合は、その分をマイナスで計上します。
なお、広告費や旅費交通費など複数物件に共通する経費は、戸数や面積、収入割合といった基準を決めて按分します。基準は一度決めたら毎年一貫して使うことになるので、あとから大きく変える場合は説明できる根拠を用意しておく必要があります。
例えば、物件Aの所得が60万円、物件Bが−15万円、物件Cが30万円だった場合、最終的に60 − 15 + 30 = 75万円 が不動産所得となります。
不動産所得の確定申告を行う手順

不動産所得に関する確定申告の基礎が分かったところで、実際に確定申告を行う手順を見ていきましょう。
実際に確定申告に取り組もうとしたとき、やるべきことは分かっていても、具体的にどのように手を付けたらよいか分からないことは多いです。ここでは、具体的な手順に基づいて、確定申告全体のイメージをつかみましょう。
一般的な手続きの流れ
不動産所得の申告は、基本的に以下の流れで進めていきます。
- 1.収入と経費を集計して帳簿を作成する
- 2.利用できる控除があるか確認する
- 3.収入・経費・控除額から所得額を確定する
- 4.青色申告決算書または収支内訳書を作成する
- 5.申告書を完成させる
- 6.税務署に提出する
手順が多く複雑に感じるかもしれませんが、実際には1の収入と経費の集計と2の利用できる控除の確認がしっかりできていれば、あとは所定の書式に従って書類を作成して、それを提出するだけです。
なお、青色申告の場合は経費の正確さが所得額を減らすことに直結するため、普段から領収書や契約書を整理し、こまめに帳簿を更新しておきましょう。
申告作業を「年に一度の大仕事」と捉えるのではなく、「毎月の整理の積み重ね」として取り組むことで、負担を軽減できます。e-Taxを活用すれば自動計算や下書き保存もできるので、初めての方でも安心して進められるでしょう。
必要書類
不動産所得の確定申告で必要になる主な書類は以下のとおりです。
- 確定申告書B
- 青色申告決算書(不動産所得用/青色申告の場合のみ)
- 収支内訳書(白色申告の場合のみ)
- 帳簿(収入・経費を整理したもの)
- 借入金の返済予定表
- 源泉徴収票(給与所得がある場合)
- 領収書や契約書の控え
など
また、個人的な医療費控除や住宅ローン控除など、個人的な控除を使う場合は、さらに、以下のような書類が必要になります。
- 医療費控除:医療費の明細書や領収書
- 住宅ローン控除:金融機関の残高証明書
- 扶養控除・配偶者控除:該当する証明書類
なお、 e-Taxで電子申告を行う場合は、一部の書類(領収書や契約書の控えなど)の提出は不要で、申告者が法定の保管期間(原則7年間)手元に保存しておく必要があります。ただし税務署から問い合わせがあったときに提示できるよう、必ず整理して保存しておいてください。
e-Taxを利用したオンライン申請の流れ
e-Taxを使えば、パソコンやスマートフォンから申告書を作成・提出できます。税務署へ行く手間が省けるうえに、提出後の手続きも短縮されるため、積極的に活用しましょう。
- 1.利用者識別番号の取得
- 2.電子証明書の取得
- 3.手続きを行うソフト・コーナーを選ぶ
- 4.所得・経費・控除額などを入力し、申告書を作成・送付する
- 5.送信結果を確認する
なお、オンライン申請では入力に沿って自動計算が行われるため、計算ミスを減らせるのが大きな利点です。また、下書き保存機能があるので、納得できるまで何度でも見直せます。税務署に出向く必要がないため、忙しい方や遠方に住む方にも便利な方法です。
兼業・副業で不動産経営をする場合の注意点

副収入や老後資金を得るために、会社員として働きながら不動産経営を行う人は少なくありません。また、相続した実家を活用するために貸し出したいという人もいるでしょう。
このようなスタイルは安定収入を得ながら資産形成ができるため魅力的ですが、一方で税金や社会保険、会社の規則といった点で見落としやすいリスクが潜んでいます。
そこでここでは、会社員が副業で不動産経営をする際に特に注意すべきポイントを整理していきましょう。
年末調整時の取り扱い
会社員は通常、給与所得について年末調整で税金が精算されます。しかし、副業で不動産所得がある場合は、不動産収入の部分は年末調整では対象になりません。そのため、不動産所得が20万円を超えている場合、自分で改めて確定申告をする必要があります。
このとき、給与所得と不動産所得は合算して計上します。合算後の所得額によっては所得税と住民税が上昇する可能性があります。なお、不動産所得が赤字の場合は、逆に所得税と住民税が下がることもあり得ます。
なお、確定申告を怠ると追徴課税の対象になるだけでなく、税務署から勤務先に通知される可能性もあります。トラブル防止のために必ず確定申告を行ってください。
社会保険や会社規則への影響
不動産所得が増えると所得税と住民税は増加しますが、会社員の場合、健康保険料や厚生年金保険料は給与をベースに計算されるため、通常は不動産所得が増えても直接増えることはありません。
ただし、自営業や国民健康保険に加入している人は所得ベースで保険料が決まるため、不動産所得の増加がそのまま保険料負担につながります。
また、勤務先の就業規則で副業が禁止されている場合は、規定違反とみなされるリスクがあります。あらかじめ会社の規程を確認し、必要な場合は人事担当に相談しておきましょう。
住宅ローン減税や優遇措置の喪失リスク
自宅を賃貸に出す場合に特に注意が必要なのが、住宅ローン減税を利用できなくなるリスクです。 住宅ローン控除は「自らが居住の用に供していること」が要件のため、賃貸に出した時点で適用対象外となります。
この影響は意外と大きく、額が大きい場合、年間で数十万円単位の控除が受けられなくなる場合もあります。そのため、自宅を賃貸に出すことで短期的な賃貸収入が増えても、減税がなくなったことでトータルの利益が目減りする可能性があるのです。
したがって、自宅を賃貸に出すかどうかを判断する際には、得られる家賃収入と、失われる住宅ローン控除額を比較してシミュレーションすることが欠かせません。他にも固定資産税の軽減措置など、別の優遇制度が外れるケースもあるため、自宅を賃貸に出す場合は慎重に進めましょう。
まとめ|不動産所得の確定申告を正しく理解し、税金や資産運用に活かそう
不動産所得の確定申告は、義務を果たすだけではなく、節税や資産運用の基盤を整える大切なステップです。確定申告を「面倒な手続き」ととらえるのではなく、「資産の状況を整理し、今後の運用を見直す機会」と考え、正しい知識をもとに準備を進めることが重要です。
まずは本記事で整理したポイントを振り返り、自分で対応できそうか判断してみましょう。難しいと感じた場合は、税理士や専門家に早めに相談するのも有効な方法です。
確定申告は、しっかりと準備すれば決して難しいものではありません。正しい知識を身につけて早めに取りかかれば、安心して手続きを終えられます。今回学んだ内容をきっかけに、次の申告に向けて一歩先んじた準備を始めてみてください。
この記事の監修者

岡崎 千尋 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
都市計画コンサルタントとしてまちづくりを経験後、アキサポでは不動産の活用から売買まで幅広く担当してきました。
お客様のお悩みに寄り添い、所有者様・入居者様・地域の皆様にとって「三方良し」となる解決策を追及いたします。