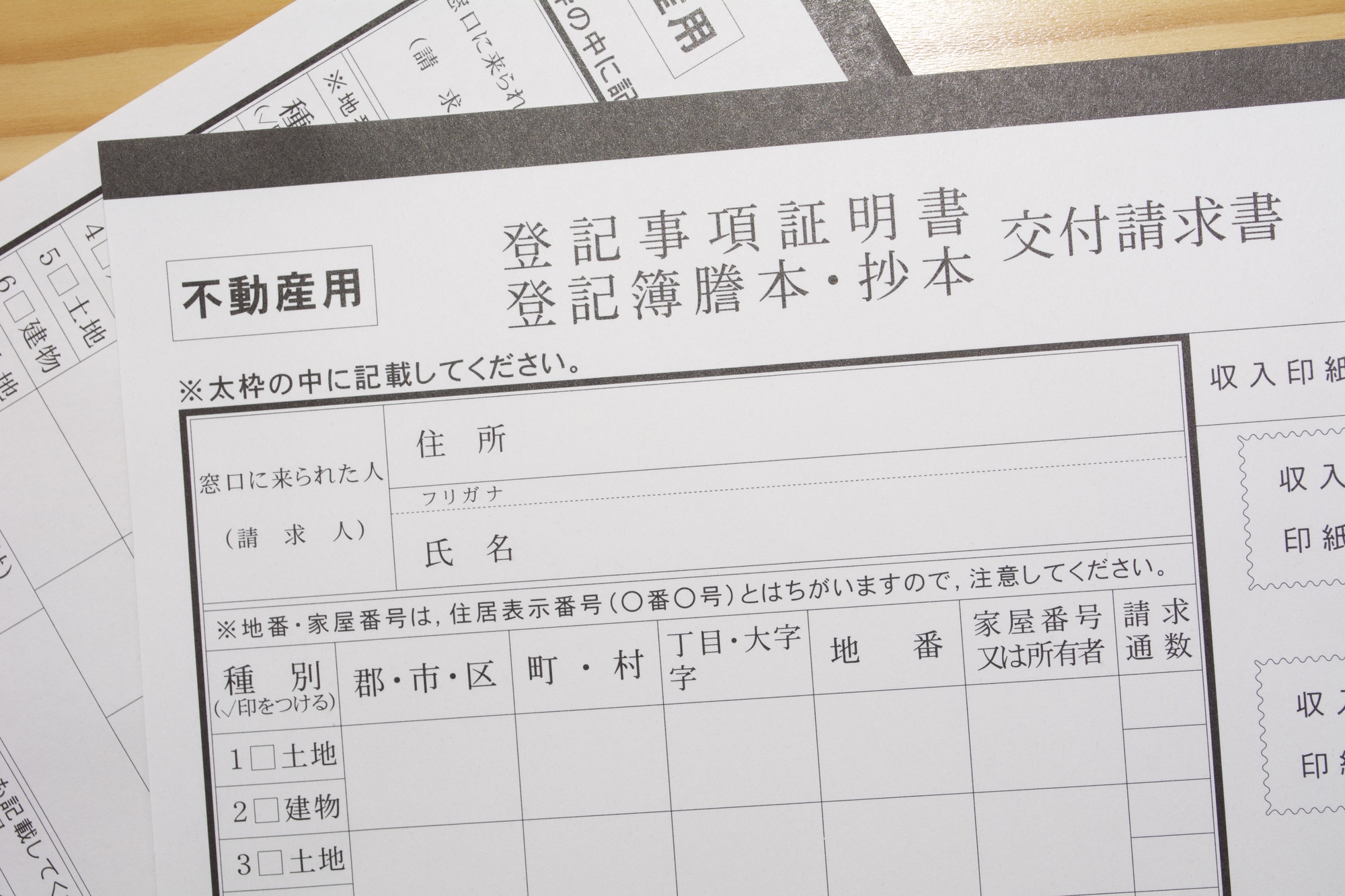公開日:2025.10.24 更新日:2025.10.27
登記費用 所有権移転の完全ガイド|費用と手続き、相場を徹底解説

「不動産の名義変更にはどれくらいの費用がかかるのだろう?」「司法書士に依頼するべき?」不動産の名義変更(所有権移転登記)は、多くの人にとって馴染みのない手続きであり、さまざまな疑問を抱くことでしょう。
実際の費用は、登録免許税のほか、司法書士への報酬や住民票・戸籍謄本などの書類取得費用が加わり、合計で数十万円になることも珍しくありません。費用がかかるからといって手続きを怠ると、大切な不動産の権利を守れなくなるリスクがあります。特に、相続登記は2024年4月から義務化されており、期限内に手続きを完了させる必要があります。
そこでこの記事では、所有権移転登記にかかる費用の内訳や計算方法、具体的なシミュレーション、費用を抑えるための工夫までを分かりやすく解説します。事前に仕組みを理解しておけば、安心して登記を進められるはずです。
目次
登記費用 所有権移転の前に知っておきたい!所有権移転登記とは?
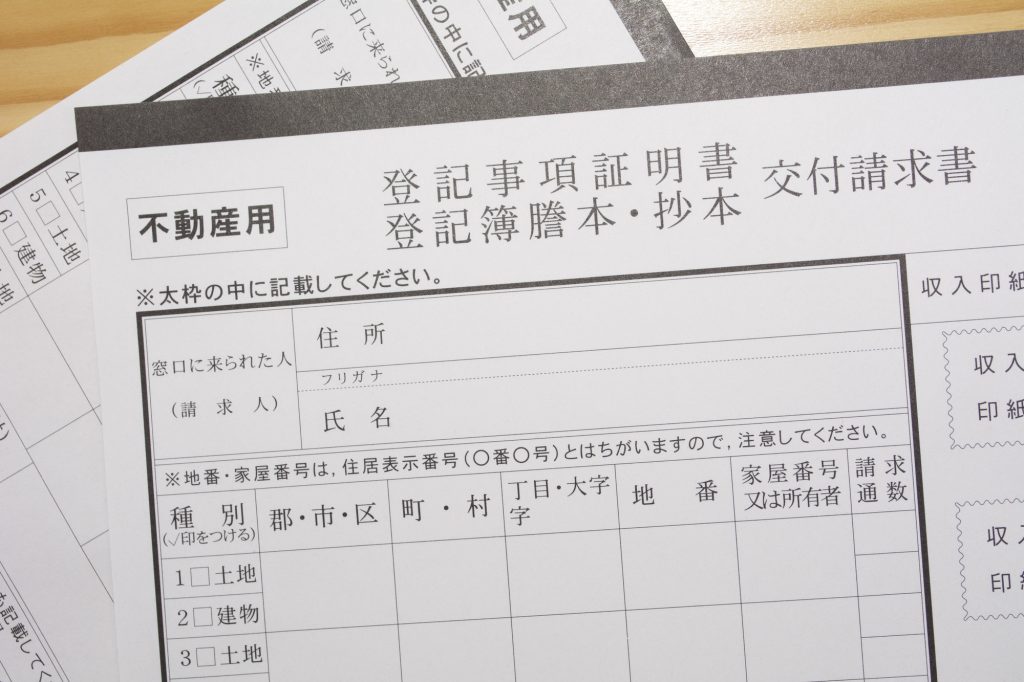
所有権移転登記とは、不動産の名義を正式に変更するために必要な、不動産登記の一種です。この登記を行うことで、不動産の所有者が公的に記録・保証され、第三者に対しても自分が正当な所有者であることを証明できるようになります。
逆に、不動産登記を怠ると、その土地の所有者が不明確になり、権利を主張したい場面で証明ができずにトラブルに発展する恐れがあります。いわば、所有権移転登記は単なる名義変更ではなく、不動産取引や相続を安心して進めるための「権利保全の手段」といえます。
なお、所有権移転登記の手続きは、不動産の登記情報を管理している「法務局」で行います。不動産がある市区町村によって管轄の法務局が決まっているため、法務局のウェブサイトから調べてから行きましょう。
各法務局の管轄は以下のページから調べることができます
管轄のご案内(法務局)
所有権移転登記が必要となる4つのケース
所有権移転登記は、不動産の所有者が変わる場面で必ず必要になります。その中でも代表的なのは次の4つのケースです。
売買による名義変更
不動産の売買契約が成立した後に買主の名義にするために行う手続きです。所有権移転登記を済ませなければ登記簿上の名義は旧所有者のままであり、第三者に対して権利を主張できないため、売買後は速やかに登記を行う必要があります。
相続による名義変更
被相続人(亡くなった方)から相続した不動産の所有権を登記する手続きです。相続があっても、自動的に登記は行われず、自ら手続きをする必要があります。
なお、2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。この期間を過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
贈与による名義変更
親から子へ不動産を譲るなど、不動産を贈与した場合に行う手続きです。口約束だけでは効力が不十分なため、所有権移転登記によって法的な効力を持たせることが不可欠です。贈与税の課税関係にも直結するため、税制を正しく理解した上で手続きを進めることが重要です。
離婚に伴う財産分与
離婚で共有名義の不動産を一方に移すときに行う手続きです。夫婦間で合意している場合でも、登記によって財産分与の合意内容を明確にしておかないと、有効性が担保されません。
特に夫婦関係が円満でない場合、後になって財産分与の有効性を争われるリスクがあります。そのため、所有権移転登記によって財産分与の内容を登記によって公示し、紛争を未然に防ぐことが重要です。
所有権移転登記の内訳と計算方法
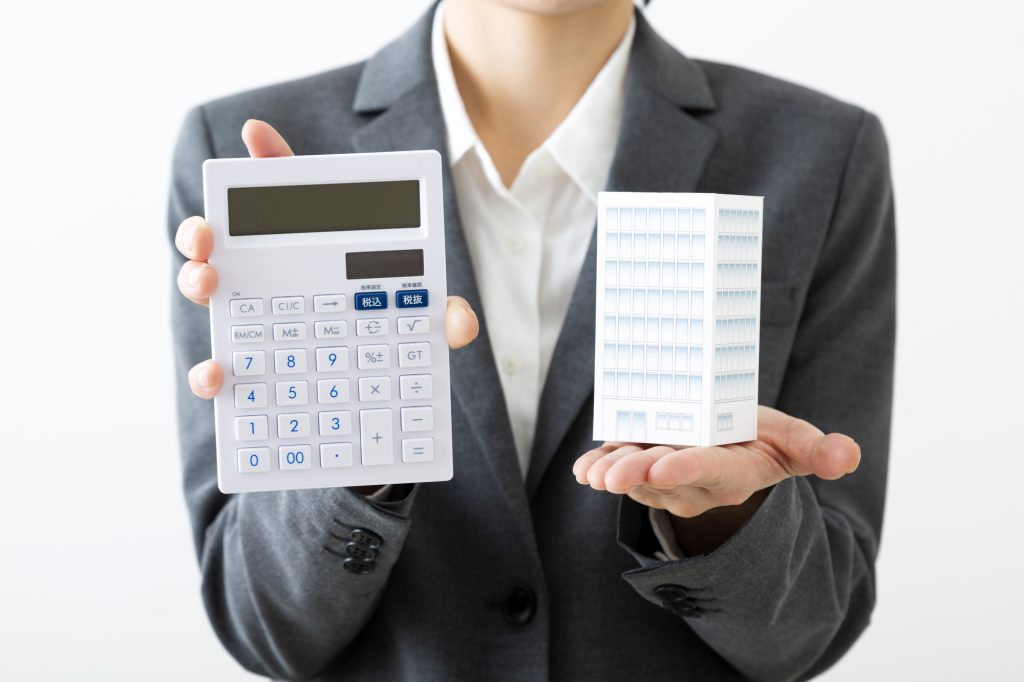
所有権移転登記にかかる費用は、主に登録免許税や司法書士への報酬、必要書類の取得費用などから構成され、合計で数十万円になることもあります。特に、不動産の評価額に応じて金額が変わる登録免許税は、高額になりやすいため注意が必要です。これは、不動産の固定資産税評価額に応じて金額が決まるため、不動産の価値によっては高額になる場合があります。
ここでは、所有権移転登記にかかる主な費用や、その相場、覚えておくべきポイントなどを解説します。
登録免許税
最初に把握しておきたいのが、不動産の価値によって金額が変わる「登録免許税」です。登録免許税の額は、以下の式によって算出されます。
- 登録免許税の額 = 不動産の価額(固定資産税評価額) × 税率
ここで用いる税率は、売買や相続などの原因によって異なり、以下のように定められています。
土地の登録免許税
- 売買の場合:不動産の価額の2%(2026年3月31日までの間に登記を受ける場合は1.5%)
- 相続、法人の合併または共有物の分割:不動産の価額の0.4%
- その他(贈与・交換・収用・競売等):不動産の価額の2%
建物の登録免許税
- 所有権の保存:不動産の価額の0.4%※
- 売買または競売による所有権の移転:不動産の価額の2%※
- 相続または法人の合併による所有権の移転:不動産の価額の0.4%
- その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等):不動産の価額の2%
※ 個人が、住宅用家屋を新築または取得し自己の居住の用に供した場合は、以下の住宅用家屋の軽減税率が適用される
住宅用家屋の軽減税率(いずれも個人に限る)
| 制度名 | 対象 | 登録免許税の軽減税率 |
| 住宅用家屋の所有権の保存登記 | 2027年3月31日までの間に住宅用家屋を新築または建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 | 0.15% |
| 住宅用家屋の所有権の移転登記 | 2027年3月31日までの間に売買および競落によって住宅用家屋の取得をして、自己の居住の用に供した場合の移転登記 | 0.3% |
| 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等 | 2027年3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを新築した場合、または建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をした場合に、それらを自己の居住の用に供した場合の保存または移転登記 | 0.1%(ただし一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記の場合は0.2%) |
| 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等 | 低炭素建築物に該当する住宅用家屋を新築した場合、または建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存または移転登記 | 0.1% |
| 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記 | 2027年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 | 0.1% |
| 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 | 2027年3月31日までの間に住宅用家屋の新築、増築または住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合で、これらの住宅用家屋の新築または取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 | 0.1% |
司法書士への依頼費用
司法書士とは、不動産登記をはじめとする登記業務や、裁判所や法務局への提出書類の作成・申請を代行できる国家資格者です。不動産登記においては、所有権を移転する不動産の調査から書類収集、実際の手続きまで、一通りの業務を依頼できます。
所有権を移転する不動産の数が多い場合や、抵当権など所有権以外の権利が関係している場合、相続人の数が多い場合など、手続きが複雑になるケースでは、司法書士に依頼することが多いです。
依頼費用の大まかな目安は5万円から15万円程度ですが、具体的な額は不動産の評価額や案件の複雑さによって変わります。相続関係が複雑で書類作成に時間を要する場合はさらに高額になることもあります。
必要書類の取得費用
登記申請を行う際に必要となる、添付資料を取得する費用です。代表的な書類は以下のとおりです。
- 住民票:1通あたり200~300円程度
- 戸籍謄本:1通あたり450円
- 固定資産評価証明書:1通あたり300円〜400円程度
- 登記事項証明書(登記簿謄本):1通あたり490〜600円
- 印鑑証明書:1通あたり200~300円程度
発行手数料は自治体によって多少異なりますが、複数の書類を揃えると合計で数千円になるのが一般的です。相続登記のように関係者が多い場合は、さらに多くの書類を請求する必要があるため、費用は数千円から1万円を超えることもあります。
その他の実費・雑費
物件の確認や打ち合わせへ行くための交通費や、書類を取得するための郵送費、証明書の追加交付手数料などの細かな出費です。物件が遠方にある場合は交通費が意外と大きな負担になるため、日程を調整して、なるべく効率的に手続きを進めましょう。
また、管轄の法務局へ書類を送る際の送料や、誤記入による書類再発行などが積み重なると、数千円程度の負担になることもあります。
所有権移転登記費用のシミュレーション

登記費用のイメージを掴みやすいように、具体的な条件を決めて登記費用をシミュレーションしてみましょう。今回の条件は以下のとおりです。
- 所有権移転の原因:親から子への相続
- 所有権移転の対象:実家(2,000万円)、土地(3,000万円)
- 手続きの方法:すべての手続きを司法書士に依頼
- 備考:実家は自宅から遠く、片道の交通費が5,000円かかる
まずは、実家と土地の価額から登録免許税の額を算出します。それぞれの税額は以下のとおりです。
- 実家の登録免許税額:2,000万円 × 0.4%(相続の場合)= 8万円
- 土地の登録免許税額:3,000万円 × 0.4%(相続の場合)= 12万円
- 合計:20万円
その他の各費用は以下のように仮定しました。
- 司法書士への依頼費用:8万円
- 必要書類の取得費用:5,000円
- その他の実費・雑費:2万円(現地への往復交通費 × 2回)
これらの費用を合計すると、30万5,000円となります。
小規模な土地でも費用が積み重なると意外と高額になります。所有権移転登記を始める際には、あらかじめ各費用がいくらかかるのか具体的な金額を見積もっておきましょう。
所有権移転登記の費用を抑える3つのコツ
先ほどのシミュレーションで、所有権移転登記にはまとまった費用がかかることが分かったと思います。それだけに、可能な限り節約をしたいと思った方も多いことでしょう。
そこでここでは、誰でもできる、所有権移転登記の費用を抑える3つのコツを紹介します。
登記手続きを自分で行う
所有権移転登記は、所有者が直接手続きをしてもかまいません。この場合、司法書士への依頼費用が全額かからなくなるため、10万円前後の節約効果が期待できます。
ただし、登記書類に不備があった場合に、修正や再提出が必要になるリスクには注意しましょう。特に、相続登記の場合は、その所有権の取得を知った日から3年以内に完了しないと、10万円以下の過料が課せられる可能性があるので要注意です
また、対象の不動産が遠方にある場合は、現地まで行く交通費がかさんで、結果的に司法書士に依頼した場合と大差なくなってしまう恐れもあります。コストと労力のバランスを考え、自分にとって最適な方法を選ぶことが重要です。
必要書類を自分で集める
登記手続きを自分で行うのが難しい場合は、必要書類を自分で集めるだけでも費用の節約になります。
司法書士への依頼費用の中には、書類を集めるための手間も含まれているため、ここを自分で対応すれば、数千円から1万円程度の節約が見込めます。
特に、不動産が近くにある場合は交通費があまりかからないため、積極的に取り組みましょう。
複数の司法書士から見積もりを取る
司法書士に依頼する場合は、できれば3カ所以上の事務所から見積もりを取り、内容を比較しましょう。司法書士報酬は事務所によって差があり、中には数万円程度の差が出ることもあります。
ちなみに、見積額に差が出る項目は、司法書士が自分で決めることができる「報酬」の部分です。登録免許税額や書類の取得費など、法律で額が定められている部分は安くすることができません。
このとき、報酬額だけでなく、金額に含まれる業務内容もチェックしてください。打ち合わせ費用や必要書類の取得費用、交通費など、細かな項目でも積み重なると大きな差になる可能性があります。
そして、見積もりを取る際には対応の丁寧さや実績、コミュニケーションのしやすさも含めて判断しましょう。所有権移転登記をスムーズに終わらせるためにも、説明が分かりやすく、自分が接しやすいと感じる司法書士を選んだ方がよいでしょう。
まとめ・総括
所有権移転登記は、不動産の売買、相続、贈与、離婚など、名義変更が必要な際に必ず発生する手続きです。費用や手間を考えるとためらってしまいがちですが、放置すると法的トラブルにつながるため、確実に行いましょう。
費用が高額になりそうな場合は、必要書類を自分で集める、複数の司法書士に見積もりを取るなどの工夫で、負担を軽減することも可能です。「費用を抑えつつ、安心できる形で登記を終えること」を目指して、確実に所有権移転を完了させましょう。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。