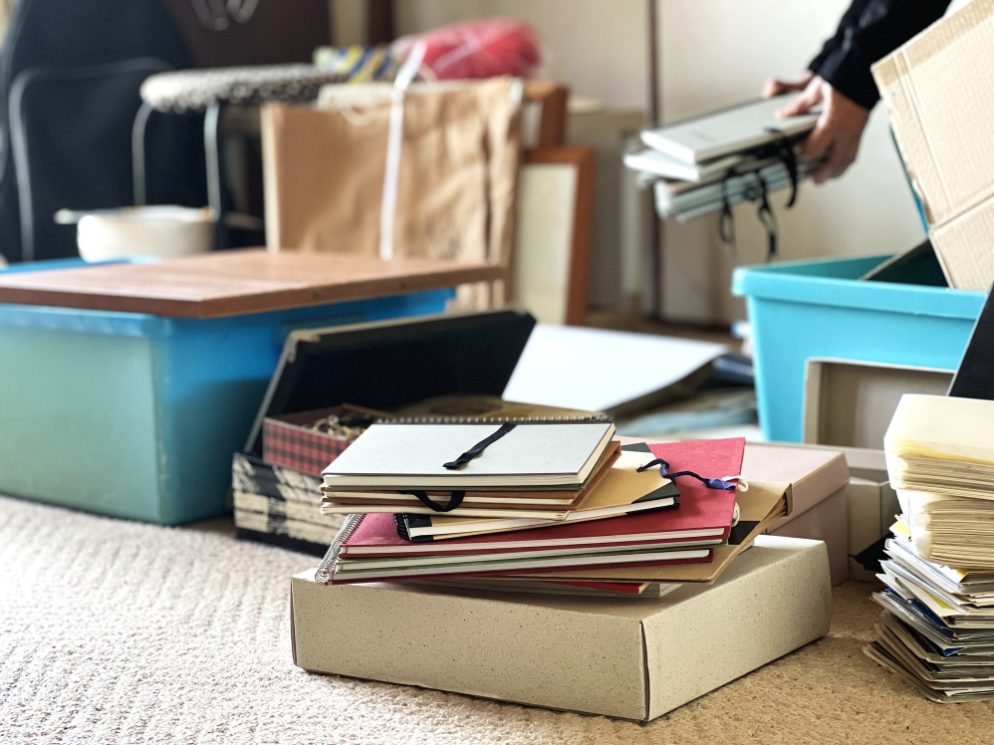公開日:2025.08.11 更新日:2025.07.29
【家じまい】とは?意味合いから進め方、費用、注意点まで徹底解説

家じまいとは、所有する家を整理・処分し、新たなライフステージに合わせて住まいを手放すこと。近年、高齢化や家族構成の変化に伴い空き家問題が深刻化し、家の管理や費用負担が重くのしかかるケースが増えています。このような背景から、「家じまい」の必要性を感じ、検討する方が増えているのが現状です。
本記事では、家じまいの主な背景や進め方、費用面のポイントなどを順を追って解説します。空き家放置のリスクや相続税などの税金問題を回避し、安心して次の住まいへ移行するためにも、基本的なステップを押さえておきましょう。
目次
家じまいを検討する主な理由

家じまいを検討する主な理由として、「高齢化と親の施設入居」「維持管理や修繕費の負担」「空き家による近隣への影響」の3つが挙げられます。
高齢化と親の施設入居
親の介護施設や高齢者住宅への入居は、家が空き家化する大きなきっかけの一つです。介護の負担を軽減したい家族にとって、親の生活を安全にサポートできる施設への入居は安心材料となるでしょう。
同時に、空き家となった実家の管理や費用負担を考慮し、家じまいを検討するタイミングにもなっています。
維持管理や修繕費の負担
家は年数を重ねるほど、屋根や外壁、水回りなどに修理が必要な箇所が出てくるものです。特に長期間住まない状態が続くと老朽化が一気に進行しやすいため、高額な修繕費が発生する可能性が高まります。
こうした負担は生活全体に影響を及ぼすことから、リフォームや維持コストを抑える目的で家じまいを選択する方も多く見られます。
空き家による近隣への影響
人の出入りがない空き家は、防犯面や衛生面で問題が発生しやすくなります。ゴミの不法投棄や雑草の繁茂、建物の倒壊リスクなどは、近隣に暮らす人々にも影響を及ぼしかねません。こうした地域トラブルを回避するためにも、空き家となることが分かった段階で家じまいを視野に入れ、早めに処分や活用策を検討することが求められます。
家じまいの始めどきと見極め方

家じまいを本格的に検討するタイミングを逃さないよう、生活環境や家族状況の変化に注意が必要です。では、具体的にはどのようなタイミングで検討すべきなのか、詳しく見ていきましょう。
子どもの独立や定年退職後
子どもが独立して家を出たり、自身が定年退職を迎えたりなど、ライフスタイルの大きな変化は、家じまいの始めどき。広い家が不要になる一方で、住宅ローンや修繕費の負担が重くのしかかるタイミングでもあります。こうした節目で家じまいを検討することで、新生活の資金確保やリタイア後の生活設計に余裕が生まれるでしょう。
相続や遺産分割が発生する前
親の生前に家じまいをしておくと、相続時のトラブルや遺産分割の難航を回避しやすくなるメリットがあります。空き家を複数の相続人で共有する場合、維持費の負担などを巡り話し合いがなかなか進まなかったりトラブルに発展したりするケースも少なくありません。
相続や遺産分割が発生する前に家を手放すか活用するかを親子や兄弟間で早めに決めておくことで、将来的にスムーズな意思疎通と円滑な手続きにつながりやすくなるでしょう。
家族での早期話し合いが大切
家じまいは、感情的な側面も持ち合わせています。特に、親が住み慣れた実家に対して強い思い入れがある場合は、手放すことに対して抵抗があることも。後々のトラブルを防ぐためにも、生前から家族全員で十分に話し合いを行い、家や資産に対する考え方を共有しておくことが重要です。
家じまいの基本的な進め方

家じまいには複数のステップがあり、ひとつひとつを着実に進めることがトラブル防止につながります。ここでは5つのステップに分けてご紹介するので、あらかじめどのような手続きが必要なのかしっかり確認しておきましょう。
STEP1:家族間での合意形成
まずは家じまいの方針を決めるため、家族全員で情報を共有し、互いの希望や懸念点を出し合いましょう。誰がどれだけ費用を負担するのか、何を残して何を処分するのかといった具体的な話し合いが重要です。ここで合意を得ておくことで、その後の手続きも円滑に進められるようになります。
STEP2:不動産会社への査定依頼
次に、不動産会社へ査定を依頼し、物件の市場価格や売却可否を把握しましょう。不動産仲介と買取のいずれが良いかは、物件の状態や立地、家族の希望によって異なります。納得のいく形で進めるためにも、複数の不動産会社に見積もりを取り、対応の早さや査定額、信頼性などを比較検討した上で選ぶのがポイントです。
STEP3:処分予定の荷物整理
査定額や売却方針が固まったら、家の中にある荷物を整理していきましょう。必要な物と不要な物を仕分けし、思い出の品や価値のある物については家族で相談しながら残すかどうかを決めます。一度にすべてを片付けるのは大変なため、部屋ごとに区切ったり専門業者を利用したりすると効率的です。
STEP4:売却または買取の契約
不動産仲介と不動産買取には、それぞれメリットとデメリットがあります。
| メリット | デメリット | |
| 不動産仲介 | 市場の適正価格で 売却しやすい | 買主との交渉や契約までに 時間を要する |
| 不動産買取 | 短期間で売却が成立する | 売却価格が低くなる 傾向がある |
物件の立地や状態、希望する売却時期などに合わせて、最適な方法を選択しましょう。
STEP5:引渡しと新生活への移行
売買契約が成立したら、決済と同時に家の鍵を引き渡します。リフォームや解体が必要な場合にはその手配を進め、新しい住まいへの引越し準備も行いましょう。
家じまい後の住み替え先候補

住まいを手放した後、新しい住環境をどう選択するかも重要なポイント。家じまいを実行しても、新天地での暮らしを見据えていなければ安心して次のステップへ進めません。住み替えの主な候補先としては、次の4つが挙げられます。
賃貸マンションやアパートへの移住
賃貸を選択する最大の利点は、物件の維持管理が家主側で行われるため、修繕費や固定資産税などの負担がかからないことです。住まいに関する手続きも簡素になり、生活スタイルの変化に合わせて部屋の広さや場所を柔軟に選び直せるでしょう。ただし、毎月の家賃が発生するため、長期的な支出バランスを考慮しながら新生活を設計することが重要です。
シニア向け施設や高齢者住宅
高齢者が安全・安心に暮らせる環境が整った施設や住宅は、介護サポートや食事サービスなど、日常生活をきめ細かく支援してくれます。家族も安心して任せられる一方で、入居一時金や月額利用料など、費用面での検討が不可欠です。事前に見学や相談を重ね、ご自身に合ったサポート体制を選ぶことが後悔しないためのポイントとなります。
二世帯住宅や子ども世帯との同居
子ども世帯との同居は家族間でのサポートや交流が増える一方で、生活リズムやプライバシーの確保が課題となるケースもあります。トラブルを避けるためにも、あらかじめ同居のルールや住み方を細かく話し合い、双方が納得できる形で進めるようにしましょう。
セカンドハウスの購入や活用
別荘や週末用の拠点としてセカンドハウスを所有することも選択肢のひとつ。自分のペースで利用できるため、リフレッシュや趣味の拠点として活用できるでしょう。ただし、メンテナンスや固定資産税などの費用が発生するため、投資目的や将来的な運用計画を慎重に検討することが大切です。
家じまいにかかる費用と税金

家じまいには、売却費用や税金、さらには解体費用など、さまざまなコストが発生します。
仲介手数料や不動産譲渡所得税
不動産会社に仲介を依頼する場合、物件の売却が成立した際に宅地建物取引業法に基づき仲介手数料が発生します。仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が定められており、「成約価格が400万円を超える場合、成約価格の3%+6万円(税別)」の計算式で算出されるため、売却金額が高いほど手数料も大きくなる点に注意が必要です。
また、不動産を売却したことで利益(譲渡所得)が生じれば、譲渡所得税も課税されます。譲渡所得は「収入金額 – (取得費 + 譲渡費用)」で計算され、特に相続物件を売却する場合などは取得費が不明瞭なケースもあるため、売却前に税理士などの専門家へ相談し、税務上の確認を行うようにしましょう。
解体・リフォーム・引越し費用
家を更地にして売却する場合は、建物の解体費用が発生します。解体費用は建物の構造や大きさ、地域によって大きく差が生じるため、複数の業者に見積もりを依頼するのがおすすめです。また、売却前に一部リフォームを行って査定額を上げるケースもありますが、費用対効果を慎重に見極める必要があります。さらに、新しい生活拠点への引越しも大きな出費になり得るため、これらの出費も考慮した上で検討することが重要です。
相続税や空き家特例のポイント
親から相続した家を手放す場合に注意しておきたいのが相続税です。相続税は、基礎控除額を超える相続財産がある場合に支払い義務が発生する可能性がある一方、被相続人が居住していた空き家を一定の条件(例:昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、区分所有建物でないことなど)を満たして売却する際には、特例(空き家に係る譲渡所得の特別控除)として譲渡所得の一部が最大3,000万円まで控除される場合があります。
この特例を受けるには、築年数や耐震基準などの細かな条件をクリアする必要があるため、税理士などの専門家に相談し、適用可否を確認することをおすすめします。
家じまいのタイミングや手続きに迷うなら「アキサポ」へ相談を

「家じまいをしたいけれど、何から手をつけて良いか分からない」「利活用も視野に入れて検討したい」など、家じまいについてお悩みの方は、ぜひアキサポへご相談ください。空き家活用のプロとして、多角的な視点から適切にアドバイスいたします。
空き家の総合支援サービスで家じまいを一括対応
アキサポは、空き家の売却・賃貸・管理・解体までをワンストップでサポートする総合サービスです。家じまいに必要な手続きや作業を一括で任せられるため、手間や時間を大幅に削減することが可能。相続登記や税務に関するご相談が必要な場合は、提携する司法書士や税理士といった専門家と連携し、状況に応じた最適なご提案を行うため、初めての方でも安心してご相談いただけます。
空き家の状態や希望に合わせて柔軟に提案
物件の立地や築年数、利用目的などに応じて最適なプランを提案できる点も、アキサポの強みです。売却だけでなく、賃貸活用や解体して土地を売る選択肢など、多角的な視点から支援いたします。
全国対応&無料相談で気軽に始められる
アキサポは日本全国からのご依頼に対応しており、どこにお住まいでもご相談いただける点もメリットです。地元の不動産会社や行政とも連携しており、地域に即したサポート体制が整っています。サービスの利用を検討している段階でも無料でご相談いただけますので、まずは電話やWEBからお気軽にお問い合わせください。
まとめ:家じまいを成功させ、心穏やかな新生活を迎えるために
家じまいは、ライフステージに応じた最適な暮らし方を実現するための大きなステップです。家族とよく話し合い、最適なタイミングを見極め、専門家の力を上手に取り入れながら進めていくことで、心穏やかな新生活をスタートできるでしょう。
また、家じまいは単に家を処分するだけでなく、自分がこれからどう生きていくかを再設計する意味合いがあります。空き家問題や相続の複雑化が叫ばれる現代だからこそ、家じまいを前向きに検討することで、より充実した暮らしへ踏み出すきっかけになるはずです。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。