公開日:2025.09.18 更新日:2025.08.04
放置空き家にどう対応する?法的責任・リスク・活用方法を解説

近年、増加傾向にある空き家問題の中でも、所有者による管理が不十分な「放置空き家」は、周辺地域に深刻なリスクをもたらす可能性があります。
本記事では、空き家が放置される背景や想定されるリスク、関連法令(空家特措法)に基づく所有者責任、さらに具体的な対策や活用方法までをまとめました。放置によるデメリットと法的リスクを再確認し、所有者として取るべき最適な対応策を考えるための情報を提供します。
目次
放置空き家問題の背景と現状

そもそも空き家が増加している理由や、現在どのような社会的状況が生じているかを整理します。
日本では少子高齢化や都市部への人口集中が進む中、地方を中心に空き家が増加しています。特に、親世代の住宅を相続したものの使い道が決まらず、結果的に放置されるケースが少なくありません。こうした背景のもと、築年数が経過して老朽化した空き家が増えているのが実情です。
また、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)」により管理責任が明確化されているにもかかわらず、実際には所有者が遠方に住んでいるなどの理由で定期的な管理が困難なケースもあります。その結果、倒壊リスクや景観悪化などの課題が顕在化しやすくなっています。
これらの問題は、個人だけでなく社会全体の課題でもあり、行政や自治体による啓発活動も進められています。特に、放置空き家が密集する地域では、防犯や治安への影響が懸念されるほか、周辺環境の荒廃にもつながります。住民の安全で快適な暮らしを守るためにも、早期の対応や利活用が強く求められています。
放置空き家がもたらすリスク

管理不全の空き家はさまざまなリスクを生じさせます。その主なリスクを4つの観点から整理しました。
老朽化が進んだ建物は、地震や台風などの自然災害による被害を受けやすく、放置されたままだと火災や害虫の発生といった二次的リスクも高まります。所有者は空き家を適切に管理する法的義務があり、放置によるトラブルは損害賠償や行政措置といった重大な責任に発展する可能性があります。さらに、不審者の侵入を招くことで地域全体の防犯意識が低下する要因にもなりかねません。
また、空き家が第三者に損害を与えた場合、「民法第717条(土地の工作物の占有者及び所有者の責任)」などに基づき、所有者が賠償責任を問われることがあります。加えて、「特定空き家」の指定を受けると、固定資産税の軽減措置が解除され、税負担が大幅に増すリスクもあります。こうした事態を防ぐためにも、早期の対応と管理体制の整備が不可欠です。
1. 倒壊・火災などの災害リスク
木造住宅が多い日本では、メンテナンスを怠った空き家ほど倒壊のリスクが高まります。耐震性が低くなっている建物は地震の揺れで簡単に大きなダメージを受ける恐れがあるため、所有者の責任は重いといえます。また、建物内部にごみが溜まると放火や自然発火のリスクが高まることも懸念されます。定期的な確認と清掃でこうしたリスクを抑えることが必要です。
2. 近隣への被害と損害賠償責任
空き家の老朽化により、外壁や屋根材が剝がれて隣接地や歩行者に損害を与えた場合、民法上の損害賠償責任を免れない可能性があります。被害が発生すれば、民事訴訟に発展するリスクもあり、時間的・金銭的な負担は大きくなります。損害が発生する前に、劣化部分の修繕や補強を行うことが不可欠です。
3. 不法侵入・犯罪・害虫被害
人の出入りがない放置空き家は、不法侵入や犯罪の温床となるリスクが高まります。建物が荒れていれば、心理的な侵入障壁も下がるため、不審者の滞在や不法投棄などが起きやすくなります。また、放置されたゴミや残留物からは、ネズミ・ゴキブリなどの害虫・害獣が発生し、周辺住民への衛生被害にもつながります。
4. 固定資産税・都市計画税の増加
空き家が「特定空家等」に指定されると、固定資産税や都市計画税の住宅用地特例(課税軽減措置)が適用外となります。これは「空家特措法」に基づく行政措置であり、管理不全が税負担増につながるという実質的ペナルティでもあります。放置が続けば、想定外の出費が生じ、結果として対応がさらに遅れるという悪循環に陥るおそれがあります。
特定空き家とは?指定される基準と行政対応
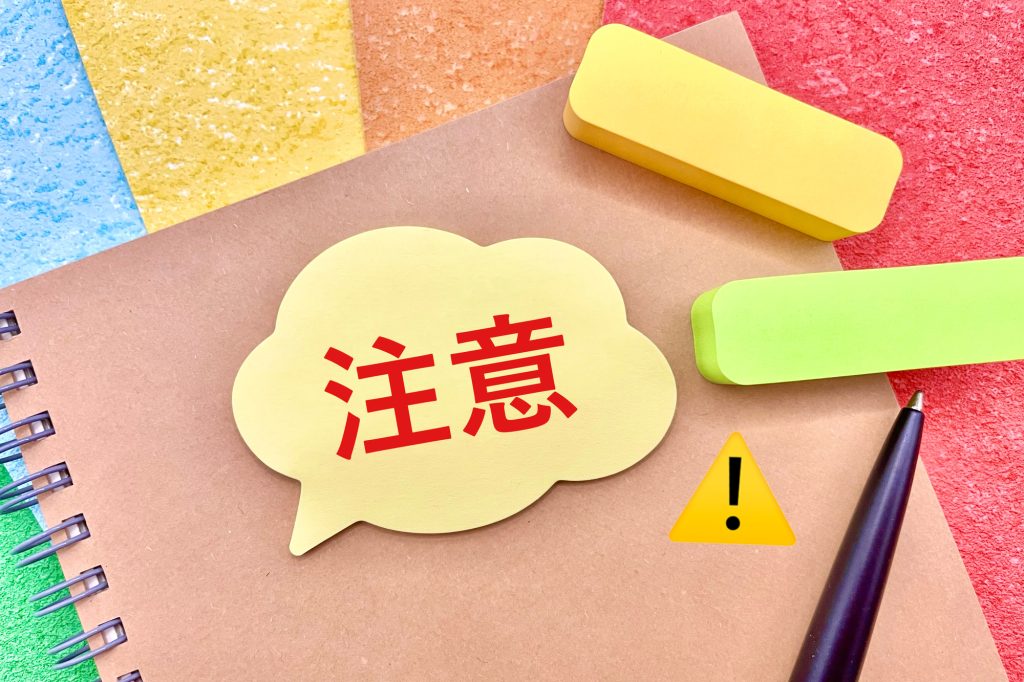
法令上「特定空き家等」と定められる条件や、指定後に生じる行政対応について正確に把握しておくことが重要です。
「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空家特措法)」では、地域の安全・景観・衛生に深刻な悪影響を及ぼす空き家を「特定空き家等」に指定できると規定しています。具体的には、屋根や外壁などの破損、敷地内の雑草やゴミ放置、倒壊や衛生被害の恐れがある場合などが該当基準となります。
所有者が行政からの「指導・勧告・命令」に従わず改善しなかった場合、法的な義務が発生し、行政対応が強化されます。改善命令が発せられた段階で、迅速な是正措置を取ることが求められます。
特定空き家に指定される条件と流れ
建物の老朽化や衛生問題、景観の著しい悪化などを理由に、行政からの現地調査や通報をきっかけに状況が把握されます。その結果、落下物や倒壊のリスクがあると判断されれば、空き家の所有者に対して改善要請が行われます。
一般的な流れとしては、改善計画の提出と実行が求められ、適切な対応が確認されれば「特定空き家」の指定は回避または解除可能です。逆に、改善が見られない場合は、正式な「勧告」「命令」へと手続きが移行します。
指定後に想定される罰則や行政代執行
勧告や命令を無視した場合、最終的には「行政代執行法」に基づいて地方自治体が修繕・撤去を行う「行政代執行」が実施されることがあります。この際に発生する費用は、原則として全額、所有者に請求されるため注意が必要です。
さらに、「住宅用地特例」が適用外となり、固定資産税や都市計画税の優遇措置が失われることにより、税負担が一気に増加します。加えて、周辺住民からの苦情や法的トラブルへと発展する可能性もあり、放置することで損失と社会的信用の両方を損なう結果にもなりかねません。
空き家を管理・維持するための具体策

放置を回避するために、日常的に行うべき管理や維持のポイントを確認します。
空き家を安全な状態で保つためには、定期的な巡回と清掃が欠かせません。ちょっとした異常を早期に発見し手当てすることで、大規模な修繕コストを抑えることにもつながります。特に外壁や屋根周り、排水溝や庭の様子などは放置すると被害拡大の原因になりやすいので、こまめなチェックリストを作成しておくとよいでしょう。
また、空き家特有のリスクに対応した火災保険・地震保険の見直しも重要です。使用実態に即した補償内容に切り替えることで、万一の災害時のリスクを軽減できます。保険契約には「長期不在」「無人建物」に対応した特約が必要になることもあるため、現状の契約を一度確認しておくと安心です。保険は単なる備えではなく、将来の活用や資産保全の一環として戦略的に見直すべき要素です。
定期巡回やメンテナンスのポイント
巡回時は外観の確認だけでなく、建物内部の湿気・カビ・通気不良の有無なども確認しましょう。床下や屋根裏の劣化は目に見えにくいため、専門業者に依頼する定期点検も有効です。また、庭木が生い茂っていると防犯上の死角になりやすいため、草木の剪定や除草を行い、見通しを確保することも防犯対策になります。
火災保険・地震保険の見直し
空き家は人が居住しないことで火災や自然災害のリスクが高まるとされ、保険料が上昇する場合があります。ただし、建物用途や立地に応じて補償内容を最適化すれば、無駄な出費を抑えながら必要なリスクに備えることが可能です。特に風災・雪災は地域によって被害頻度が異なるため、市区町村単位の気象傾向を踏まえた保険設計が望まれます。
リフォームやリノベーションを検討する
空き家を長期的に保持するのであれば、リフォームやリノベーションを通じて資産価値を高めるのも一案です。住宅設備を最新のものに置き換えるだけでも、賃貸や売却の際に評価が上がる可能性があります。都市部だけでなく、地方でも空き家活用の需要が高まっているため、将来的な活用を見据えるならリノベーション計画を早めに検討するのが得策です。
放置空き家を有効活用する方法

長期間放置された空き家は、倒壊・火災・治安悪化などのリスクを高めるだけでなく、所有者にとっても維持コストや法的責任が重くのしかかります。こうしたリスクを回避するには、空き家を積極的に「利活用」する視点が重要です。
売却や賃貸といった収益化だけでなく、地域資源としての再生を目指すことで、社会的にも意義ある選択肢が広がります。
空き家の立地や構造、老朽度によって取るべき活用法は異なります。解体して更地にするという手段もありますが、その前に「活かす」方法がないか慎重に検討することが肝要です。意外にも、地域ニーズとマッチすれば高い需要が見込めることもあります。
1. 売却する(買取や仲介)
不動産会社に買取を依頼する方法は、手続きが比較的スピーディーに進み、売却後のリスクや管理の手間を一気に手放せる点がメリットです。ただし、築年数が古い、劣化が進んでいるといった理由で買取価格が市場相場よりも大幅に低くなる場合もあるため、複数社の査定を取り比較することが欠かせません。
一方、仲介での売却は時間がかかるものの、リフォームや清掃によって印象を改善することで売却価格を引き上げられる可能性もあります。地域の不動産市況やターゲット層を見極めながら、最適な売却戦略を立てましょう。
2. 賃貸や空き家バンクへの登録
自治体やNPOなどが運営する空き家バンクに登録すると、地方移住者や二拠点居住を検討する人たちに物件をアピールしやすくなります。
低家賃やリフォーム前提での入居募集を行うことで、空き家の長期放置を避けながら、地域の活性化にも貢献できるのがポイントです。特に過疎化地域では自治体が補助金制度を設けていることもあるため、費用面の負担を軽減できます。
3. 解体して更地にする場合の注意点
老朽化が進み、リフォーム費用が高額になると見込まれる場合、解体して更地にするのも有力な選択肢です。更地にすれば倒壊や火災といったリスクはなくなり、近隣への迷惑も回避できます。
ただし、注意点として、住宅が建っていた土地に適用される「固定資産税の住宅用地特例」がなくなるため、税額が大幅に増加する可能性があります。また、更地にした後の活用計画が不明瞭なままだと、税負担だけが増して利活用につながらないという悪循環にも陥りかねません。
更地活用を検討する場合は、駐車場や貸し農地など、地域需要に応じた運用方法を事前にシミュレーションしておくことが重要です。
相続対策や特殊な選択肢について

空き家の所有者が亡くなった後の相続問題や、その対応策を見ていきます。
名義変更や相続税申告などの手続きを怠ると、誰が管理責任を負うのか曖昧なまま放置され、結果的に「管理不全の空き家」となるリスクが高まります。
空き家の利活用以前に、まずは相続の整理と権利関係の明確化が最優先課題です。また、相続放棄や寄付といった特殊な選択肢を検討する際も、メリットとリスクを正しく理解することが不可欠です。
相続手続き・名義変更の重要性
相続が発生すると、空き家を誰がどのように所有するかを法的に確定させる必要があります。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、全員の合意を得たうえで登記名義を変更する必要があります。この手続きを怠ると、売却・賃貸・管理といった意思決定が困難になり、結果として空き家の放置につながりかねません。
登記が旧所有者のまま数十年放置される「所有者不明土地問題」の温床にもなるため、司法書士や税理士など専門家の支援を受け、早期の対応を行うことが望まれます。
相続放棄・寄付という特殊な選択肢
空き家の管理が困難であったり、費用負担を回避したい場合には、相続放棄や自治体への寄付という選択肢が浮上します。
相続放棄をすれば空き家を含む全財産の相続権を放棄することになり、その後の管理責任も免れることができます。ただし、この場合は他の資産も一括で放棄することになるため、全体の資産構成をよく確認してから判断する必要があります。
一方、自治体や公益法人などへの寄付は、法的には「贈与」にあたるため、受け取り手側の承諾が必要であり、手続きも煩雑になりがちです。多くの自治体では老朽化物件の受け入れを拒否することもあるため、寄付を検討する際は事前に相手方との協議や条件確認を行っておくことが大切です。
専門家や自治体の力を借りて、空き家問題をスムーズに解決しよう
空き家問題は、不動産・法律・税務・相続といった複数の専門領域が絡む複雑な課題です。とくに放置空き家は管理責任や費用負担、近隣トラブルなどのリスクを招く恐れがあるため、個人の判断だけで対応するのは限界があります。
そこで重要なのが、専門家や自治体によるサポートを積極的に活用することです。近年では、複数の相談内容を一括して受け付ける「ワンストップ相談窓口」を設ける自治体も増えており、効率的に課題解決を進めることが可能です。
弁護士・行政書士・司法書士などへの依頼
相続・名義変更・遺産分割協議といった手続きに加え、空き家を巡ってトラブルが生じた場合には、専門的な法的知見が不可欠です。
弁護士は法的紛争や共有名義の整理に強く、行政書士は書類作成・許認可申請を得意とし、司法書士は登記手続きに精通しています。
特に、相続人が多数いるケースや共有状態が複雑な場合には、早期に相談することで不要な争いを未然に防ぐことができます。
自治体やワンストップ相談窓口のサポート
多くの自治体では、空き家に関する相談窓口を常設し、定期的な無料相談会も開催しています。
建築士や宅建士、税理士など多様な専門家と連携したワンストップ対応を行う自治体もあり、相続・税務・活用の提案まで一貫した支援が受けられる点が大きなメリットです。
また、自治体によっては空き家の活用や解体に対して補助金制度を設けていることもあるため、早めに役所や公式サイトで情報収集することが重要です。地域差が大きい分野だからこそ、自分のエリアの支援内容をしっかり把握することが、空き家対策の第一歩となります。
まとめ|放置空き家は“負動産”になる前に対策を

空き家を放置すると、倒壊リスクや衛生・防犯上の問題が深刻化し、周辺住民や自治体にも大きな影響を及ぼします。特定空き家に指定されると、行政代執行による強制解体や固定資産税の増額など、重いペナルティが科される可能性もあります。
そうしたトラブルを未然に防ぐには、定期的な管理と早期の改善策の実行が不可欠です。リフォームによる資産価値の維持や、売却・賃貸・空き家バンクの活用といった利活用の選択肢を積極的に検討しましょう。
また、相続や名義変更といった法的手続きの不備が原因で空き家が放置されるケースも多く、弁護士や行政書士など専門家への相談も有効です。地域の実情に応じた支援制度や相談窓口を活用し、空き家問題を“自分ごと”として捉え、行動を早めに起こすことが重要です。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。








