公開日:2025.09.29 更新日:2025.08.12
既存不適格建築物とは|違法建築物との違い・売買リスクとリフォーム時の注意点

本記事では、建築時において合法だったものの、後に建築基準法や関連法令の改正により現行基準に適合しなくなった既存不適格建築物について詳しく解説します。
どのように位置づけられ、どのような手続きや制限が伴うのか、その概要や法的な扱いを理解することは重要です。特に売却や購入を検討している方にとっては、将来的なリフォームや金融機関の融資でどのような影響が出るかを把握しておく必要があります。
なお、既存不適格は「当時は適法・現在は不適合」な建物であり、無許可増築などの違反建築物とは明確に区別されます。(建築基準法第9条による是正措置の対象となるのは違反建築物です。)
また、既存不適格建築物とよく混同される違反建築物との相違点を整理し、実際に増改築や用途変更を行う際にどのような条件が求められるのかを確認します。
一定の範囲内であれば、既存部分に新基準の遡及適用を求めない緩和(既存不適格の継続)が認められる一方、大規模な修繕・模様替え等では現行基準が及ぶ場合があります。購入や売却時のリスクや注意点はもちろん、資産価値への影響や耐震基準との関係についても分かりやすく解説していきます。
目次
既存不適格建築物の定義と法律上の位置づけ

かつては合法だった建築物が、建築基準法や都市計画法等の法改正に伴い現行法規に適合しなくなるケースが既存不適格建築物です。法律上どのように位置づけられているのかを確認します。
既存不適格建築物とは、建築時点で建築基準法などの関連法規を満たしていたにもかかわらず、その後の法令改正で新たに適用された基準を満たさなくなってしまった建物を指します。これは建築基準法第3条第2項の規定により、法改正以前に合法的に建てられた建物に遡って法を適用しないとするものです。ただし、増改築等をする場合は、現行法規が適用されます。具体的には容積率・建ぺい率などの面積要件、耐震基準、接道義務、用途制限など、さまざまな条件が改正対象となるため、幅広いケースで発生する可能性があります。
現行法規に即した改修が求められるかどうかは、建物の用途や規模、改修の程度などによって異なるため、まずは所管行政庁(自治体の建築指導課等)や一級建築士などの専門家に相談することが大切です。
このような建物は、法律的に「違反建築物」ではなく、法的には適法に存続できる既存建築物と位置づけられるため、通常の使用においてすぐに取り壊し命令が出るわけではありません。ただし、安全面や衛生面で重大な問題が指摘されれば、特定行政庁から建築基準法第10条に基づく改善命令、または建築基準法第9条に基づく是正命令を受ける可能性もあります。
長期的な利用を前提とするならば、現行基準への適合を意識したメンテナンスや耐震補強工事などを検討する必要があります。
発生する理由|建築時点の法令との関係

既存不適格建築物が生まれる背景には、建築基準法や都市計画法、消防法など関連法令の改正があります。建築時点では合法だったものが、改正後には適合しなくなる仕組みについて解説します。
法律改正によって建築基準や技術的条件が変わると、旧基準で建てられた建物は新たな基準を満たさなくなります。例えば、耐震基準の強化によって補強工事が必要になる場合や、増改築時に現行基準への対応が求められるケースがあります。また、建ぺい率や容積率が厳しくなり、敷地条件によっては増築可能な範囲が大幅に制限されることもあります。
こうした法改正のタイミングは、地震・火災などの災害リスク低減を目的とした安全対策や、都市計画の見直しに伴う場合が多いです。既存不適格建築物が多く存在するエリアでは、老朽化や用途の変化に対応しきれず、結果として街並みの再開発が必要になることもあります。この背景を理解することで、既存不適格建築物に関するリスクや対応策の重要性が見えてきます。
建築基準法や消防法の改正が影響するケース
耐震性能や防火設備など、建物の安全性を確保するための基準が改正されると、従来の仕様では不十分と判断される可能性があります。特に消防法の改正でスプリンクラー設置が義務化された場合や、避難経路確保の基準が厳格化された場合は、追加工事が必須となります。
これらの改正は、建物そのものの価値や利用計画にも直結します。賃貸物件として新たな借主を募集する際や、商業施設として用途変更を行う際にも、法改正後の基準に適合していない部分には是正義務がかかる場合があります。結果的に改修コストの増加や工期の遅延につながる可能性があるため、事前に最新の基準内容を確認しておくことが重要です。
既存不適格建築物と違反建築物の明確な違い
当初から法的要件を満たしていない違反建築物と、変更後の基準に合わなくなった既存不適格建築物の差異を理解しておくことが重要です。
違反建築物とは、建築時点や改修時点で建築基準法や関連法令を遵守していなかった建物を指し、建築確認を受けずに増築したケースや、許可条件に反した用途変更などが典型例です。この場合、当局から是正命令や使用停止命令が出されるリスクが高く、場合によっては行政代執行に至る可能性もあります。
一方、既存不適格建築物は当初は適法であったため、直ちに違法状態とみなされるわけではありません。しかし、増改築や用途変更を行う際、または新たな法令改正で現行基準への適合が必要になった場合には、建築確認申請の段階で詳細な構造調査や補強計画の提出が求められることがあります。
したがって、購入や売却の際は物件が「違反建築物」なのか「既存不適格建築物」なのかを正確に見極めることが不可欠です。金融機関や不動産会社とのやり取りを円滑に進めるためにも、法的な位置づけを事前に把握し、必要に応じて建築士や不動産鑑定士などの専門家に相談することが望まれます。
既存不適格建築物のメリット・デメリット
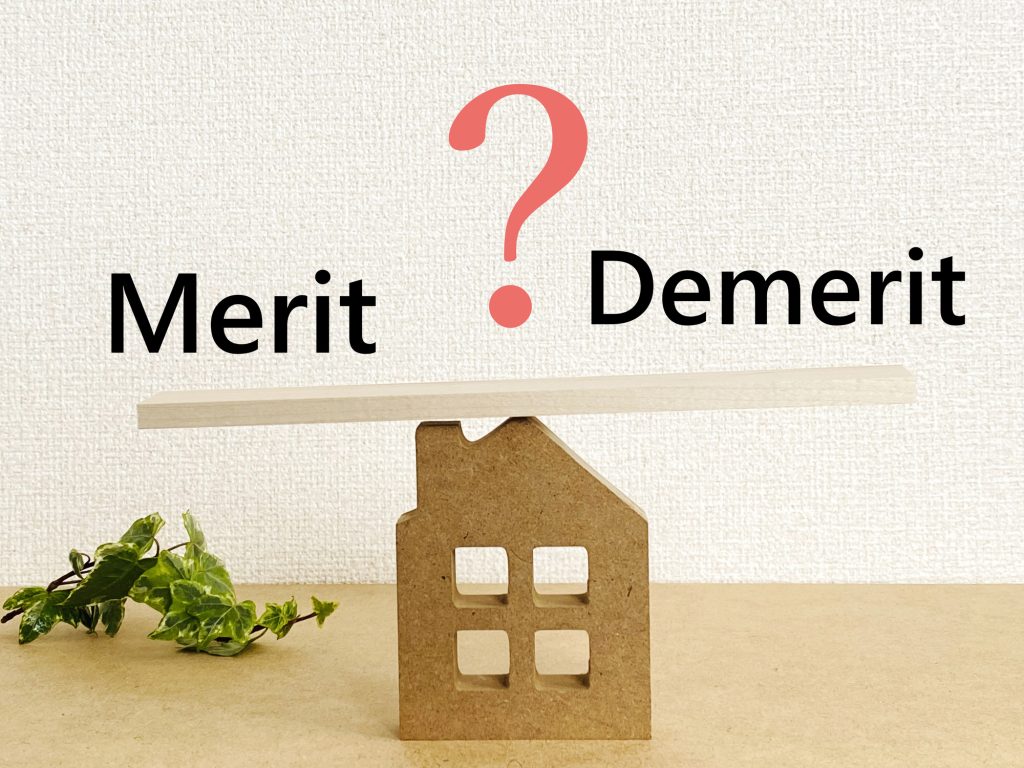
購入費用や場所にメリットがある一方、規制面のリスクを伴うのが既存不適格建築物です。資産価値や安全面に与える影響を見ていきます。
メリットとしては、築年数や立地条件によって市場相場より割安で購入できる場合があり、都心部や用途地域の制限が厳しいエリアなど希少性の高い立地に存在するケースも少なくありません。用途次第では、高い収益性や利便性を発揮する資産となる可能性があります。
デメリットとしては、改修時に現行基準を満たすため追加コストが高額になる可能性がある点です。特に増改築を行う場合、建築基準法86条の7や令137条の規定により既存部分も含めた建物全体の点検・補強計画の提出が求められることがあり、想定外の出費や工期延長につながる恐れがあります。購入を検討する際は、事前に工事範囲や費用を専門家に調査依頼しておくことが重要です。
資産価値とリスクへの影響
既存不適格建築物は、法改正による不適合要素を抱えているため、買い手にネガティブな印象を与えやすく、短期的には売却価格が下落する傾向があります。
しかし、計画的な改修で現行基準をクリアすれば、安全性・耐久性の向上とともに資産価値の回復や向上が期待できます。適切な投資とリスク管理を行えば、長期的に有効な資産として機能する可能性も十分あります。
旧耐震基準との関係
旧耐震基準(昭和56年5月以前)で建設された建物は、震度5強以上の地震に対して倒壊や崩壊を防ぐ設計にはなっていません。新耐震基準と比較すると安全性が劣る可能性があるため、購入や売却の判断時には耐震診断の結果を重視すべきです。
耐震改修工事を実施すれば、地震リスクを軽減しつつ資産価値を高められますが、改修費用や工期が負担となる可能性もあります。旧耐震基準の物件を選ぶ際は、改修を前提とした資金計画と長期的な維持管理のシミュレーションが欠かせません。
既存不適格建築物への措置や緩和はある?
条件付きで現行基準への適合を免除または緩和されるケースがありますが、その要件や申請の流れを把握しておくことが大切です。
現行法規に完全には適合しない場合でも、建築基準法86条の7や令137条〜137条の16に基づき、所管行政庁の判断で既存不適格建築物に対する特例措置が適用されることがあります。例えば、構造上または技術的に現行基準への完全適合が困難な場合でも、耐震性や避難性能など安全性に関する主要部分を改修することで、一部基準の適用免除や緩和が認められるケースです。
ただし、これらの措置を受けるためには事前審査、詳細な設計図書や現況調査報告書の提出が必要で、申請から許可までに相応の時間と費用を要します。特に増改築時には、既存部分と新設部分にどの基準を適用するかの調整が複雑化しやすく、判断を誤ると再設計や追加工事のリスクも生じます。
そのため、特例適用の可否や要件については、早い段階で一級建築士や建築指導課などの専門家に相談して進めることが安全で効率的です。
用途地域変更がもたらす影響
もともとは問題なく建てられた建物でも、都市計画法に基づく用途地域の変更によって、建て替えや継続利用に制限が生じる場合があります。
用途地域とは、都市計画に基づき定められる、建物の利用目的や規模に関する制限区域です。建築当時の用途地域では適法だったにもかかわらず、後に用途地域の変更が行われた結果、現行の規定下では不適合となる既存不適格建築物になるケースがあります。
この場合、増改築や大規模なリフォーム時には現行の用途地域に適合する用途や規模への変更が求められます。例えば、第一種低層住居専用地域へ変更されたエリアに、かつて商業施設として建てられた建物がある場合、将来的に店舗用途を維持できなくなる可能性があります。
こうした用途地域の変更は、資産活用戦略や収益計画に直結するリスクとなるため、売買や活用を検討する際には、都市計画図や自治体の用途地域指定履歴の確認が不可欠です。
リフォーム・増改築時に押さえておきたいポイント

増改築や大規模リフォームを行う場合、既存不適格建築物は現行基準への適合義務が新たに発生する可能性があります。
既存不適格建築物を改修する際は、新設部分だけでなく既存部分にも建築基準法や消防法の現行基準が適用されるケースがあります。大規模修繕や構造変更によっては、建物全体の耐震性能・避難設備・防火性能を現行法規に合わせる必要が生じ、結果として費用や工期が大幅に増加する可能性があります。
さらに、消防設備の更新や避難経路改善など、当初想定していなかった追加工事を求められることも少なくありません。工事前には必ず所管行政庁(建築指導課等)や一級建築士に相談し、必要な改修内容や概算費用を把握した上で計画を立てることが、無理のないリフォーム実現の鍵です。
売却や建て替えを検討する際の注意点
売却時には、物件が既存不適格建築物であること、および「既存不適格」となるに至った経緯を重要事項説明で正確に告知する義務があります(宅地建物取引業法第35条)。
これはトラブル防止だけでなく、金融機関の融資審査にも直結するため、建築確認済証・検査済証、法適合状況調査報告書などの書類を事前に揃えておくことが重要です。住宅ローン審査が通りにくい場合、現金買いに限定されるリスクも考えられます。
一方、建て替えを選択する場合は、現行法規に基づく新築計画が必須です。建て替え後の建物は、建ぺい率・容積率・用途地域などの制限を全て満たさなければなりません。そのため、以前と同規模の建物が建てられない可能性もあります。建て替え後の規模縮小リスクを回避するためにも、都市計画図や法令制限を事前に確認し、将来の資産活用計画を慎重に設計することが不可欠です。
金融機関の融資基準と既存不適格建築物の扱い

住宅ローンなどの融資審査では、既存不適格であることが借入限度額や融資条件に影響を及ぼす場合があります。そのため、金融機関の評価基準を事前に確認しておくことが重要です。
既存不適格建築物は、金融機関から見ると将来的な担保価値に不安がある物件とみなされる可能性が高く、借入額が抑えられたり、担保評価額が低めに算定されたりするケースが多く見られます。特に、耐震性や接道義務など基本的な法適合要件に懸念がある場合、融資審査はさらに厳しくなります。
このような状況を回避するには、購入前に物件の既存不適格の内容を正直に金融機関へ開示し、利用可能な融資形態や評価条件について相談することが有効です。また、購入後や融資実行後に改修計画を進める場合、改修工事完了後に再評価を受けて担保価値を引き上げることも選択肢となります。
まとめ|既存不適格建築物への理解と今後の対応策
既存不適格建築物は、建築当初は適法であっても、法改正や都市計画の変更により現行基準と食い違いが生じた建物です。違反建築物とは異なり、直ちに是正を迫られるわけではありませんが、増改築や用途変更の際には現行法規への適合義務が発生することがあります。そのため、必要となるコストや期間を事前に見積もっておくことが不可欠です。
購入・売却時には、不動産会社や金融機関との情報共有を密に行い、物件の法的地位・価値・融資条件を明確に把握することが大切です。また、安全性や資産性の向上を目的とした耐震補強・防火性能改善などの改修は、長期的な資産価値維持にも直結します。
最終的な判断を下す際には、建築士・不動産鑑定士・司法書士など複数の専門家と連携し、法的リスク・資産価値・将来計画のバランスを踏まえた対応策を講じることが望まれます。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。








