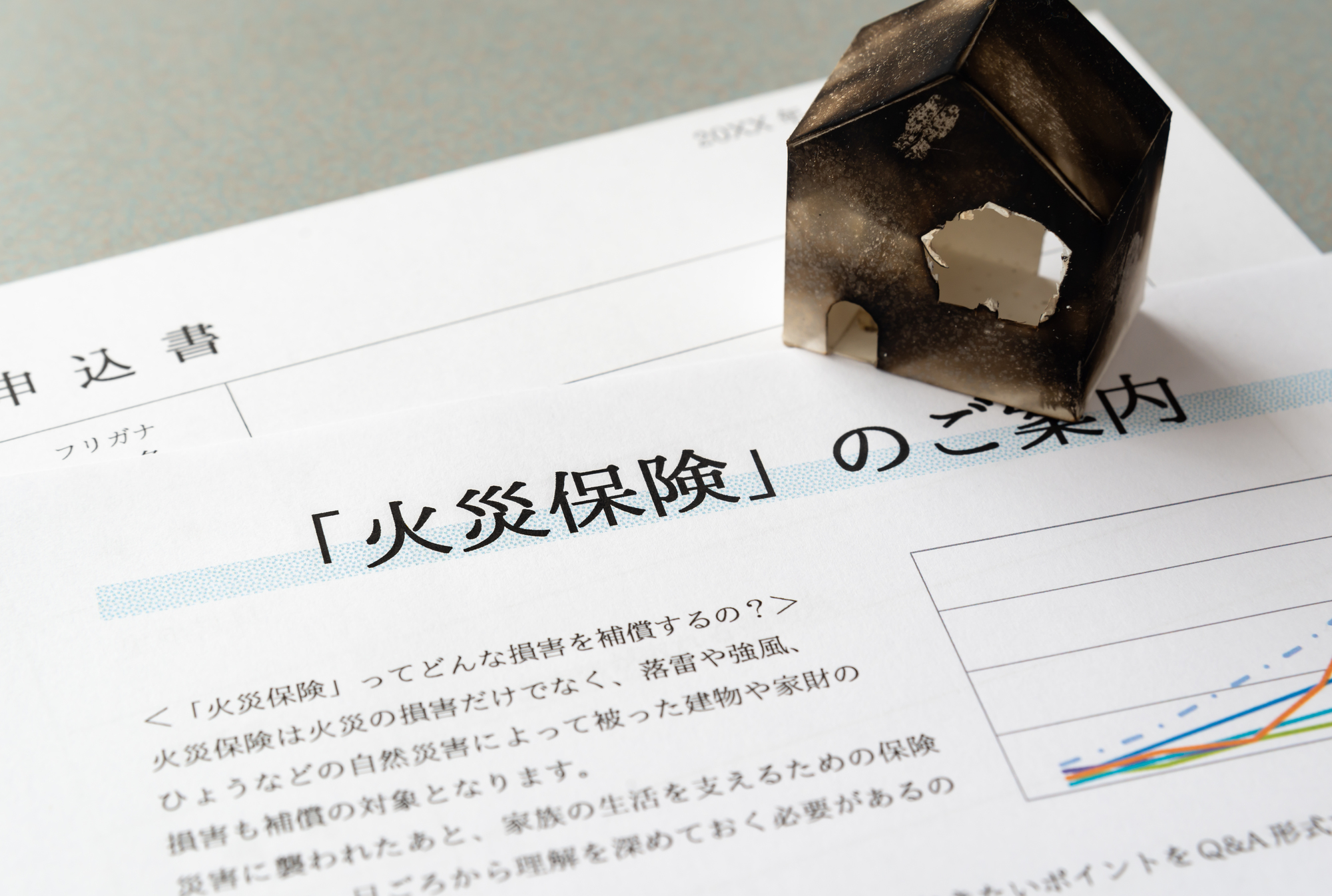公開日:2025.07.13 更新日:2025.09.16
火災保険と地震保険を徹底解説!理解して備える住まいのリスク対策

火災や地震など、住まいにふりかかるリスクは身近にあり、決して軽視できません。そんなときに、火災保険や地震保険は、万が一の被害に備える大切な手段です。この記事では、それぞれの補償内容や保険料の違い、保険金のしくみなどを総合的に解説。保険選びのヒントをお届けします。
目次
火災保険と地震保険の基本をおさらい

火災保険と地震保険、それぞれの仕組みや特徴を正しく理解することは、住まいや家財を守るうえで欠かせません。
特に日本は世界有数の地震多発国。備えは万が一ではなく、いつか来るものとして考えて、まずは保険の基本と重要性をおさらいしましょう。
火災保険
火災保険は、その名のとおり火災による損害を補償する保険です。火災のほかにも、落雷や爆発、風災、水災などによる建物や家財の損害も対象になります。ただし、地震が原因の被害は補償されないため注意が必要です。
地震保険
地震保険は、地震による建物の倒壊や津波による浸水、土砂崩れといった自然災害による損害をカバーする保険です。単独では加入できず、火災保険とセットで加入するもので、地震や津波、噴火による損害を補償します。
火災保険だけではカバーしきれない地震リスク
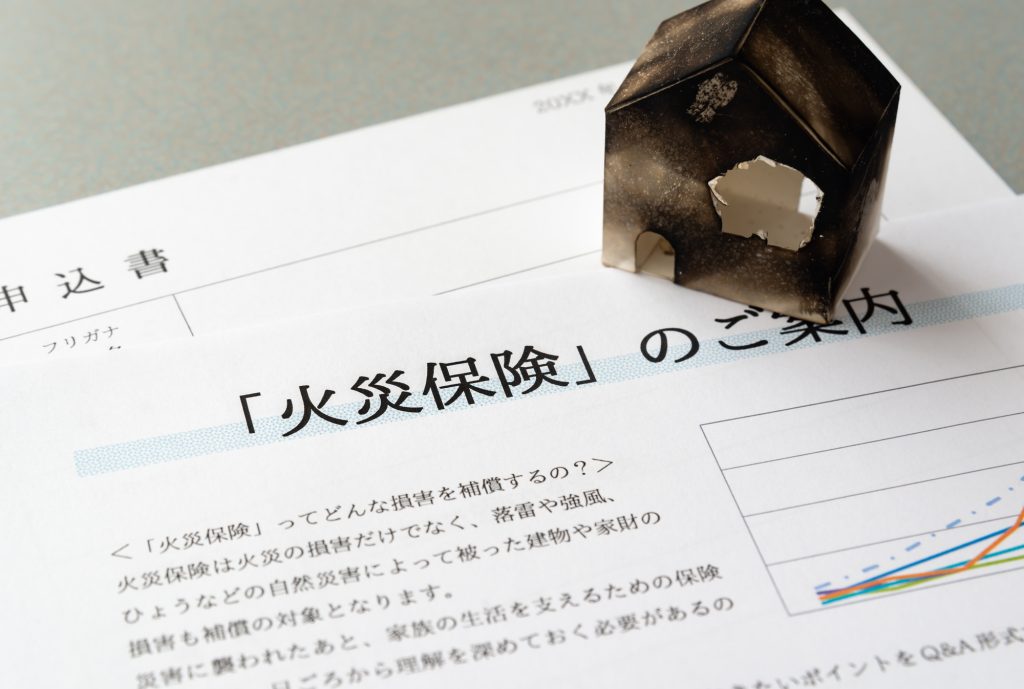
火災保険と地震保険の違いで注視したいのは、火災保険は『地震が原因の火災や損害は補償の対象外』になってしまうこと。つまり、大地震のあとに火災が起きても、火災保険だけでは保険金が支払われません。
そのため、地震リスクを軽く見てしまうと、実際に被災したときに地震保険が適用されず、大きな経済的打撃を受ける可能性もあります。実際に大規模な地震が発生すると、建物の全壊や半壊だけでなく、家財にも深刻な損害が及ぶことも。特に被災後は自宅に住めなくなり、一時的な避難生活や修繕、再建に多くの費用がかかるケースがほとんどです。
こうした経済的な負担を軽減するために、地震保険は重要な役割を果たします。火災保険だけではカバーできない部分を補うためにも、地震保険をセットで備えておくことの意義は非常に大きいといえるでしょう。
火災保険の対象外となる地震被害
実際に火災保険の約款を見てみると、地震や噴火、これらに起因する損害は補償対象外であることがはっきりと記載されています。地震による建物の倒壊や津波による浸水、地盤沈下といった被害は、火災保険だけでは保険金が支払われないことを理解しておく必要があります。
地震保険は、広範囲に大きな被害をもたらす地震に備え、被災後の生活再建を目的に設けられた制度です。国が関与しているため、保険料や補償内容には独自のルールが定められており、建物や家財に対する保険金額は火災保険の30〜50%を上限として設定されています。
地震保険の必要性とセット加入の理由
地震保険は単独では契約できず、必ず火災保険に付帯する形で加入する仕組みになっています。これは地震や津波、噴火といった災害がもたらす損害が、火災保険の補償対象外であるためです。建物や家財が損壊したとしても、地震が原因であれば保険金は支払われないという事態になりかねません。
大きな地震が起きたとき、自宅が半壊あるいは全壊してしまった場合には、修理や建て直し、家財の買い替えに多額の費用がかかります。そんなときに地震保険に入っていれば、被災直後に必要な資金として保険金を受け取ることができ、生活再建までの時間と負担が大きく違ってくるでしょう。
さらに地震保険は、国が関与して制度を運営しているため、補償内容や保険金の支払い基準も安定しています。これは地震保険に関する法律に基づき、大規模災害時の経済的負担を、社会全体で支え合うという考え方に基づいた制度なので、加入者が多いほどリスクが分散され、より確実なサポートが実現されます。
火災保険に入っているから大丈夫!と過信せず、補償の対象範囲を正しく理解し、いざという時に困らないよう地震リスクにもきちんと目を向けておくことが非常に重要です。
地震保険の補償内容と保険金の仕組み

地震が起きたとき、どこまで保険で補償されるのか。その仕組みを知っておくことは、いざというときの安心につながります。地震保険では、被害の程度によって保険金の支払額が変わる損害区分や、火災保険に連動した保険金額の設定など、独自のルールがあります。
ここからは具体的な支払い例とあわせて、補償内容の全体像と設定時におさえておきたいポイントを解説します。
損害区分と支払い例
地震保険では、被害の程度に応じて「全損」「大半損」「小半損」「一部損」という4つの区分があり、それぞれ支払われる保険金の割合が決まっています。これは地震保険に関する法律に基づいた、損害認定基準です。
たとえば、建物が全壊した場合は、設定した地震保険金額の100%が支払われます。一方で、壊れ方がそこまでひどくなくても、大半損で60%、小半損で30%、一部損でも5%と、段階に応じて補償を受けられます。
つまり、たとえ家が完全に倒壊していなくても、壁に大きなひびが入ったり、家具が壊れて使えなくなったりすれば、保険金が下りる可能性があるということです。軽度に見える損害でも申請することで復旧費用の一助になるケースがあります。
ただし、保険金が支払われるかどうかは、専門の調査員が客観的な基準に基づいて被害を査定するため、自己申告だけでは保険金が出ないことがあります。いざという時に慌てないためにも、加入前に「どんな基準で判断されるのか」を確認しておきましょう。
地震保険の保険金額設定とポイント
地震保険の保険金額は、火災保険で設定した保険金額の30%〜50%の範囲で設定できます。これは地震保険に関する法律で定められた上限額です。
たとえば、火災保険で建物の保険金額を2,000万円にしている場合、地震保険では600万円〜1,000万円の間で設定するということです。この範囲の中で、どのくらいの金額が自分にとって現実的かを考えながら決めていくことになります。
設定する金額によって、当然ながら毎月の保険料にも影響があります。高めに設定すれば手厚い補償が受けられますが、その分保険料も上がります。反対に、保険金額を低くしすぎると、大きな地震で被害を受けた際に修理費用が足りず、自費でまかなう負担が大きくなるかもしれません。
また、建物の構造や地域の特性によってもリスクや保険料は変わってきます。耐震性能が高い建物には割引が適用される場合もあり、地盤の強さや過去の地震履歴などによって、地域ごとの保険料の違いも出てきます。こうした条件もふまえて、適切な保険金額を選ぶことが大切です。
契約時には、火災保険の補償内容や住宅ローンの残高なども確認しながら、バランスの取れたプランを検討しましょう。
火災保険と地震保険の保険料比較
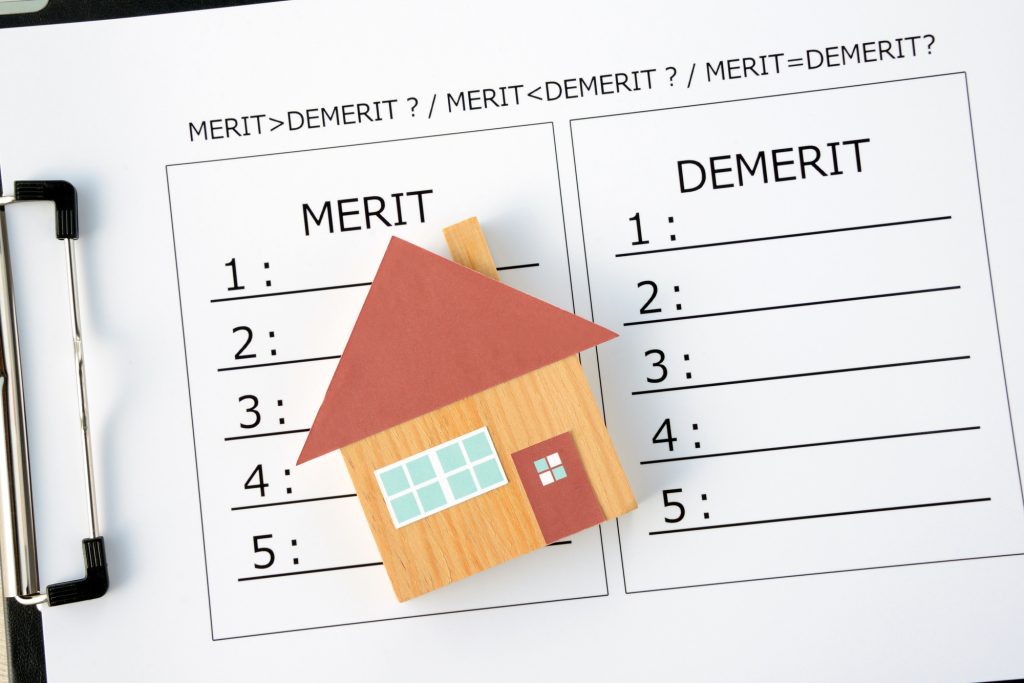
火災保険と地震保険の保険料は、建物の構造や住んでいる地域によって大きく変わるため、両方をしっかり比較することが大切です。
火災保険は耐火建築かどうかや水害リスクの高い沿岸部かなどが影響し、特約の有無でも費用が変わります。なお、火災保険の保険料は、保険会社がそれぞれ独自に設定できます。
一方、地震保険は地震保険に関する法律に基づき、耐震性能や地域の地震リスクが反映されて保険料が決まります。耐震等級が高い住宅は割引もあり、地域ごとの料率確認も重要です。
負担に感じても、災害後の修理費用を考えれば必要な備え。長期契約や割引制度を活用することで、保険料を抑えつつ、安心の備えを続けるポイントも含めて解説していきます。
建物の構造・所在地による保険料の違い
建物が耐火構造かどうかは、火災保険と地震保険の保険料に大きく影響します。一般的に木造よりも鉄筋コンクリート造のほうが耐火・耐震性が高く、保険料は安くなる傾向があります。また、建物の階数や築年数も保険料に影響し、新しい基準で建てられた住宅ほど保険料が抑えられることが多いです。
さらに所在地のリスクも重要で、地震発生の確率や活断層の有無、過去の被害状況などが考慮されます。沿岸部は津波リスクが高いため保険料が高くなることもあり、内陸部でも活断層が近い地域は注意が必要でしょう。
同じ都道府県内でも地域ごとに料率が異なる場合があるので、自宅の立地条件を正確に把握して適切な保険選びが大切です。
長期契約と割引制度の活用
火災保険では、5年や10年といった長期一括契約で保険料が割安になるケースが多くあります。まとめて支払うことで年間の負担が軽減され、更新の手間も減るといったメリットがあるため、長く住む予定があれば検討したいポイントです。
地震保険も最長5年の契約期間で、複数年まとめて契約することで割引が受けられます。また、耐震等級が高い住宅や耐震補強を行った住宅は、さらに割引が適用される可能性があります。耐震性能が高いほど、地震保険料を抑えられる仕組みです。
保険を選ぶときは、こうした割引をうまく使ってコストを抑えることが大切です。新築やリフォームの際に耐震性能をアップさせると、将来的に保険料の節約にもつながるので、長期的なランニングコストの視点でもぜひ意識しましょう。
地震保険料控除の基礎知識

地震保険に入ると、税金の優遇を受けられることがあります。毎年の所得税や住民税の申告時に「地震保険料控除」と呼ばれる控除が適用され、支払った保険料の一部が税金から差し引かれるため、家計の負担を軽くできます。これは所得税法および地方税法に定められた制度。特に地震の多い地域に住んでいる方にとっては、ぜひ知っておきたい節税方法です。
控除を受けるには、確定申告や年末調整のときに、保険会社から送られてくる「控除証明書」を提出するだけでOK。申告を忘れずに行うことで、毎年の税負担が軽くなります。
地震保険は、万が一の補償だけでなく、このような税制のメリットもあるのが大きなポイント。控除には上限がありますが、家族構成や保険料の額によっては節税効果も期待できるため、毎年きちんと活用していきましょう。
控除証明書の発行と確定申告の方法
毎年支払った保険料の合計が記載された「控除証明書」が保険会社から送られてきます。この証明書は、確定申告や年末調整で必ず必要になる大切な書類です。届いたらなくさないように保管場所を決めておくのがおすすめです。
<会社員の場合>
年末調整のときに控除証明書を勤務先に提出すれば手続き完了。
<個人事業主・フリーランスの場合>
確定申告のときに、控除証明書を他の書類と一緒に提出することで手続き完了。
控除される金額は支払った保険料に応じますが、上限があるため控除されるのは保険料の一部だけです。大きな節税効果を期待しすぎず、確実に利用できる制度として毎年きちんと活用しましょう。正しく控除を受けるためにも、保険料の支払い記録や証明書の管理を忘れずにおこないましょう。
火災保険・地震保険選びのチェックポイント

火災保険や地震保険を選ぶときに、どこも大差ないから…となんとなく決めようとすると、のちのちの後悔につながるかもしれません。
実は保険会社ごとに保険料や補償内容、サポート体制などに違いがあります。そのため、慌てずにじっくり比較する時間をとって、自分にぴったりの保険を見つけましょう。ここからは、比較検討すべきポイントや見落としがちな特約・オプションの活用法を解説していきます。
保険会社・保険商品を比較する際の注意点
どの保険が一番いいの?と迷ったとき、保険料の安さだけで決めてしまうのは、ちょっと危険です。自分の暮らしや住まいに本当にマッチする補償が含まれているか、まずは基本から丁寧にチェックすることが大切です。
基本補償は自分に合っているか
火災保険・地震保険を比較する際は、建物や家財の評価額が現実に即しているかを確認しましょう。地震保険についても、万が一の生活再建に十分な金額になっているかが大きなポイントです。
地域のリスクに応じた特約をチェック
保険会社や保険プランによっては、水害や風害といった災害に対応する特約が、細かく用意されているケースもあります。たとえば、自宅が川や海の近くにあるなら、水害補償の特約はつけておくべきでしょう。逆に山間部に住んでいるなら、雪による被害をカバーする雪災補償が重要になることも。
サポート体制や支払い条件も比較
複数の保険会社から見積もりを取り、保険料だけでなく補償内容やサポート体制、支払方法などもあわせて比較しましょう。困ったときの対応が丁寧かどうかは、実際に使う場面でとても大事なポイントです。不明点や不安があれば、保険のプロに相談するのもおすすめです。納得したうえで、自分の生活スタイルに合った保険を選びましょう。
付帯できる特約やオプションの活用
こんなときも補償されるの?と思うようなトラブルも、特約やオプションを活用すればカバーできるかもしれません。火災保険・地震保険は、基本補償に加えて、自分の暮らしに合ったリスクを補うための特約をつけられる場合があります。
予想外の故障や破損などに備えた特約も
たとえば、家具や窓ガラスの破損、空き巣による盗難、給排水設備の水漏れなどは、日常の中で意外と身近なリスクでしょう。こうした被害を補償する特約をつけておけば、いざというときの出費を抑える助けになります。
特に築年数の経った家や、設備の不具合が気になりはじめた家では、こうした補償が大きな安心材料になります。
より実損に近い補償プランも選べる
最近では、地震保険に「実際にかかった修理費」に近い額を補償するオプションを用意している保険会社もあります。標準プランよりも補償が手厚く、被災後の修理費の大部分を補える可能性があるのが大きなメリットです。
大きな地震に備えて負担を減らしたい方には、検討する価値のある選択肢です。多少保険料は上がりますが、そのぶん安心感も大きくなるでしょう。
過剰な特約にも不十分な補償にも注意を
特約やオプションは、必要以上に手厚くしすぎるのも、最低限に抑えすぎるのも避けたいところ。自宅の立地や構造、家族のライフスタイルをふまえて、どの範囲をカバーしたいのかを明確にすることが大切です。無理なく支払える保険料の範囲で、安心できるカバーを広げる。そのバランスを見つけることが、賢い保険選びのコツです。
加入前に押さえておきたい注意点

火災保険や地震保険に加入する前に、あらかじめ準備しておきたいポイントがあります。いざというときに「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも、事前の確認と検討が大切です。
加入前に基本情報を把握
自宅の評価額や住宅ローンの残高、家財の総額を大まかに把握しましょう。保険金額が多すぎると保険料が高くなりますが、少なすぎると十分な補償が受けられない可能性もあります。無理なく無駄のないプランを選ぶためには、自分の資産状況を正しく知ることが重要です。
複数社の見積もりと補償内容を比較
保険会社や代理店を通じて加入する場合は、複数社の見積もりを比較検討することも有効です。保険料だけでなく、補償範囲・特約・オプション・災害時のサポート体制など、実際に災害が起きたときの対応力も比較ポイントになります。
家族やライフプランに合わせた補償選び
必要最低限の補償でコストを抑えるか、手厚い補償で安心を取るかは家庭の事情によって異なります。家族構成や今後のライフプランを踏まえ、自分たちに合った補償を選ぶようにしましょう。
保険の更新時に見直すポイント
一度契約したらそのままになりがちですが、契約は一度きりではありません。建物の老朽化、住環境の変化、子どもの独立や介護など、ライフステージの変化に応じて補償内容を見直すことで、今の暮らしに合ったよりお得な保険が見つかる可能性もあります。
暮らしの変化を確認
火災保険や地震保険は、契約期間が5年〜10年と長期にわたることが多く、その間に生活環境は大きく変わることがあります。たとえば、家族が増えたり、子どもが独立したり、あるいはリフォームをして家の価値が上がったり…といった変化に応じて、必要な補償内容や特約を見直す必要があるでしょう。
家の状態やリフォーム履歴を確認
築年数の経過や設備の交換・強化なども補償内容に関係するため、耐震補強をしていれば地震保険の保険料が安くなるケースも。こうした割引制度を適用するためには、リフォーム内容を証明する書類の提出が必要になるので、手元に控えておきましょう。
まとめ|火災保険・地震保険は安心への第一歩

火災保険と地震保険は、住まいを自然災害から守るために欠かせない備えです。火災保険では火事や落雷、風災などに対応できますが、地震被害はカバーされません。そのため、地震や津波、噴火への備えには、火災保険に付帯する形で地震保険の加入が必要です。
特に日本では、大規模地震のリスクが高く、住宅や家財の再建費用を考えると、地震保険は経済的ダメージを軽減する重要な手段です。保険料が気になる場合も、地震保険料控除や耐震等級割引などを活用することで、家計への負担を抑えつつ、必要な補償を確保できるでしょう。
加入時には、建物の構造や立地条件、住宅ローン残高、家族構成、生活再建費用の想定額などをもとに、どこまでの補償が必要かを明確にすることが大切です。保険会社や商品ごとに特約内容やサポート体制も異なるため、複数のプランをしっかり比較し、自分の暮らしにフィットする保険を選びましょう。
人が住まない空き家こそ、保険は命綱に
空き家を所有している場合は、保険の見直しがより一層重要です。人が住んでいない家は災害やトラブルの発見が遅れがちになり、被害が大きくなる可能性があります。こうしたリスクに備えるには、空き家の現状に合った保険内容を選び直すことが必要です。
空き家の管理や活用に悩んでいる方は、空き家のトータルサポートを提供している「アキサポ」にぜひお問い合わせください。空き家の管理や利活用に関するプロのサポートを受けながら、保険の備えも万全にしておきましょう。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。