公開日:2025.08.15 更新日:2025.07.29
更地の固定資産税とは?建物がある場合との違いと対策を総合解説

空き家を壊して更地にしたら、税金がぐんっと高くなった……そんな話を聞いたことはありませんか?実は住宅が建っている土地には税の優遇があるため、更地にすると固定資産税が跳ね上がることも。この記事では、その仕組みや空き家と更地の税金の違いから、税負担を抑えるコツや売却時の注意点まで解説します。
目次
更地の固定資産税はなぜ高くなる?

空き家を解体して更地にすると、税額が急激に上がる傾向があります。その主な理由は、地方税法第349条の3の2に規定される「住宅用地の特例(小規模住宅用地の特例、一般住宅用地の特例)」が使えなくなることにあります。通常、住宅が建っている土地にはこの特例が適用され、固定資産税の課税標準が大きく軽減されます。小規模住宅用地(200㎡以下の部分)なら評価額の6分の1、一般住宅用地(200㎡超の部分)なら3分の1まで圧縮される仕組みです。
ところが更地になるとこの特例が適用されなくなり、土地の評価額に対してそのまま課税されるため、固定資産税が一気に跳ね上がってしまうのです。自治体によっては地方税法第702条に基づく都市計画税も課税されるため、税負担感はさらに増すでしょう。
建物を解体すれば家屋部分の税金はなくなりますが、土地全体にかかる税負担はむしろ重く感じることもあるでしょう。とはいえ、更地にすることで活用の幅が広がる可能性もあります。
まずは、なぜ税額が上がるのかという仕組みを正しく理解しておくことが重要です。
更地が対象となる固定資産税の計算方法

固定資産税は、土地や建物の評価額に標準税率(通常1.4%)をかけて算出されます。この税率は、自治体によって若干異なる場合があります。住宅が建っている土地には特例があり、小規模住宅用地(200㎡以下)は課税標準が6分の1、200㎡超の部分は3分の1まで軽減されます。
ところが更地にすると、この特例が一切使えなくなり、評価額そのままに税率がかかるため、税額が跳ね上がってしまうのです。
また、評価額は固定資産税評価基準に基づき3年ごとに見直されるため、タイミングによってはさらに負担が増す可能性も。更地の所有を検討する時には、この税負担の違いが家計や資金計画に直結する点を十分考慮しましょう。
固定資産税の基本的な仕組み
固定資産税は、土地や建物の評価額をもとに算出される税金で、評価は固定資産税評価基準に基づき3年ごとに見直されます。地価や建物の築年数・構造などが反映され、自治体ごとに基準が細かく異なるのが特徴です。税率は基本的に1.4%ですが、地方税法第700条に規定される標準税率であり、自治体は条例でこれと異なる税率を定めることができます(制限税率)。
また、都市計画税がかかる地域では、固定資産税とあわせて支払う必要があるため、思ったより負担が大きくなるケースもあるので注意が必要です。
住宅用地の特例が適用されない理由
住宅用地の特例は、住まいとして使われている土地に税の優遇を与えることで、住環境の維持や宅地供給を促す制度です。
ところが、建物を解体して更地にすると「居住用」の条件を満たさなくなり、特例の対象外に。これにより、固定資産税や都市計画税の大幅な軽減が受けられなくなってしまいます。たとえ将来的に家を建てる予定があっても、どのタイミングで特例が外れるのかはしっかり確認しておくことが大切です。
更地と都市計画税の関係

更地にすると、固定資産税だけでなく都市計画税の負担も増える可能性があります。
都市計画税は、都市計画区域内にある土地や建物にかかる税金で、インフラ整備などの費用に充てられます。住宅が建っている場合は住宅用地特例により軽減されますが、更地になるとこの特例が使えなくなり、税額が上がってしまう仕組みです。
特に市街化区域にある土地は影響が大きく、土地評価額が高ければその分税額も上がります。税率は自治体によって異なりますが、上限は0.3%と法律で定められています。
更地は維持するだけでもコストがかかるため、将来的な利用予定がない場合は、売却や活用を含めて早めに見直すことが得策でしょう。
空き家と更地の固定資産税の違い
空き家も更地と同じように、固定資産税が高くなる場合がありますが、実は税制上の扱いに明確な違いがあります。
空き家であっても、住宅としての形態が維持されていれば「住宅用地の特例」が引き続き適用され、税負担は抑えられます。
ところが、建物が著しく老朽化していたり、建築基準法等の法令違反の状態にあると「特定空家等」に指定され、住宅用地として認められなくなる可能性が。その時点で特例が外れ、税額が一気に上がるリスクが生じます。
一方、更地はそもそも建物が存在しないため、住宅用地の要件を満たさず、最初から特例の対象外です。空き家のように管理や改修で特例を維持する選択肢はありません。ただし、更地は売却しやすく、活用の自由度が高いという面もあります。
空き家を残すか更地にするかどうかは、税負担と資産の将来像を踏まえて総合的に判断することが大切です。
特定空家等に指定されると高くなるのは本当?
特定空家等に指定されると、行政から指導や勧告を受ける可能性があり、勧告が出されると「住宅用地の特例」が外れてしまいます。その結果、固定資産税や都市計画税が更地と同じ扱いになり、税額が数倍に跳ね上がるケースも。
老朽化や衛生面で問題があると判断されると、何もしないまま放置するだけで大きな出費につながるリスクがあります。特定空家等に指定される前に、修繕や利活用を早めに検討することが理想的でしょう。
更地化するかリノベーションするかの判断ポイント
空き家を解体して更地として活用するか。それともリノベーションして住宅用地特例を維持するかは、状況によって判断が分かれます。建物が比較的新しく、修繕費がそれほどかからないなら、リノベーションで税負担を抑えつつ活用できる可能性があります。
一方で、老朽化が進み改修費が多額になる場合や、土地相場が高いエリアでは、更地にして売却しやすくする選択肢も。最終的には、将来の資産価値や活用目的を見据えて総合的に決定することが重要です。
更地で固定資産税がどれくらい増える?シミュレーション事例
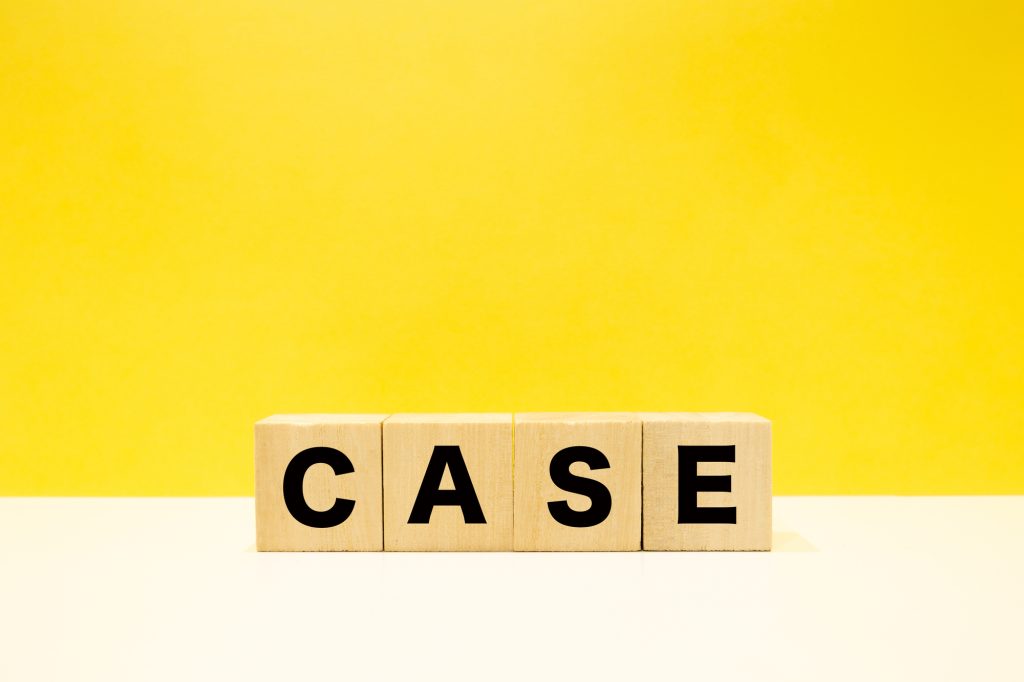
更地にした途端、固定資産税がどれくらい上がるのか、事前に知っておきたいところ。税額は土地の面積や評価額によって大きく変わりますが、住宅用地特例が外れることで、負担が2〜3倍に跳ね上がるケースも少なくありません。地価の高いエリアではさらに大きな差が出ることも。都市計画税も加味すると、年間で数十万円単位のコスト増になる可能性もあります。
所有し続ける予定がある場合、その税負担にどう向き合うかが大きな課題となるでしょう。200平米以下と200平米超のケース別に、具体的なシミュレーションを見ていきましょう。
200平米以下の場合
200㎡以下の土地は、小規模住宅用地として、評価額が6分の1まで軽減される特例があります。たとえば評価額2,000万円の土地でも、家が建っていれば課税対象は約333万円に抑えられます。
ところが更地になるとこの特例が使えなくなり、2,000万円にそのまま税率がかかることに。固定資産税も都市計画税も一気に上がってしまいます。特例の恩恵が大きい分、更地にしたときの税負担の増え方はかなりインパクトがあると言えるでしょう。
200平米を超える場合
200㎡を超える土地は、「一般住宅用地」として評価額が1/3に軽減される特例があります。たとえば300㎡の土地なら、200㎡までは1/6、残りの100㎡も1/3に割引されるので、建物があればかなり税金を抑えられる仕組みです。
しかし更地にしてしまうと、この優遇がすべてなくなり、全体に満額の評価額で課税されることに。特に土地が広いほど税負担の差は大きくなります。とりあえず更地にしておこうと安易に決めると、思わぬコスト増につながるかもしれません。
駐車場経営にすると固定資産税は安くなる?

空いた土地を駐車場にすれば、固定資産税が安くなるのでは?と考える方も少なくありません。でも実は、月極駐車場などで地面をそのまま貸す形では、住宅用地の特例は適用されず、固定資産税や都市計画税は更地と同じ水準で課税されます。
収益性の高いエリアであれば増えた税金をカバーできることもありますが、収益が見込めない場所では、かえって負担が重くなる可能性も。
一方で、立体駐車場や一定の構造物を設置した場合は建物扱いとなり、別の優遇措置(例:建物に対する減価償却費の計上、一定の要件を満たす場合の固定資産税の軽減など)が受けられるケースもあります。ただし、初期費用がかさむ上、適用条件も複雑なので注意が必要です。
税金だけでなく運営コストやメンテナンス費なども含めた経営プランを考えなければなりません。安易に始める前に、長期的な視点で検討してから決めるのが望ましいでしょう。
更地のまま放置するとどうなる?滞納リスクとペナルティ

更地にしたはいいけれど、税金の支払いが追いつかない…そんな事態になると、放置はかなり危険です。
督促状が届いても支払えなければ、最終的に地方税法に基づく滞納処分(財産の差押えや公売など)といった強制執行に発展することも。
また、税金の滞納が個人の信用情報に響いて、将来ローンが組みにくくなるリスクもあります。延滞金もどんどん増えていくので、支払いに不安があるなら早めに売却や活用を検討して、負担を減らす選択をしましょう。
督促状から差し押さえまでの流れ
固定資産税を滞納すると、まずは自治体から督促状が届きます。それでも期限内に支払わないまま放置すると、差し押さえ予告が来て、最終的には財産を差し押さえられることに。公売にかけられれば、多くの場合、市価よりも安い価格で売却される可能性が高いです。こうした強制執行による損失を防ぐためにも、滞納はできるだけ早く解消しなければなりません。
滞納が与える信用リスク
固定資産税の滞納は、ただの支払い遅れでは済まされず、住宅ローンやクレジット契約にも影響することがあります。これは、税金の滞納が個人信用情報機関に登録される可能性があるためです。
金融機関は、税金の支払い状況も含めて信用力をチェックしているため、滞納歴があると信用が低いと判断されてしまうことも。将来的にマイホーム購入や不動産投資を考えているなら、滞納は深刻な足枷となるはずです。資金計画だけでなく、信用面のリスクにも目を向けておくことが大切です。
更地の固定資産税を安くする方法

更地にした後の固定資産税負担は、いくつかの方法で税金を抑えることができます。
解体・建築のタイミングを見極めたり、アパートなどの賃貸住宅を建てて収益と特例適用の両立を図ったりする方法。土地の分筆や一部活用によって、小規模住宅用地特例を生かすケースもあります。また、空き家を解体せずリフォームして特例を維持する手も。
どの方法が自分に合っているのか、将来の資産価値や収益性を含めて、じっくりシミュレーションしてみましょう。税金対策としてだけでなく、今後の土地活用にもつながる大切な判断になるため、専門家の意見を取り入れるのも有効な手段。ここからは、詳しい選択肢を具体的にご紹介します。
1月1日以降に建物を解体・新築する
固定資産税の課税は毎年1月1日時点の土地や建物の状態をもとに決まるため、解体や新築のタイミングによって税負担に大きな差が出ることもあります。
たとえば、1月1日を過ぎてから解体すれば、その年は建物がある前提で計算され、住宅用地特例(地方税法第349条の3の2)が適用されるケースも。ただし、建築工事の遅れや手続きの不備があると、想定外のコストが発生することもあるため、スケジュールや資金計画をしっかりと立て、最適な時期を見極めましょう。
共同住宅・賃貸物件を建てる
更地のままにするより、共同住宅やアパートを建てて賃貸経営を始めるのもひとつの方法です。複数の住戸に住宅用地の特例(小規模住宅用地は課税標準額が6分の1、一般住宅用地は3分の1に軽減)が適用される可能性があり、家賃収入で固定資産税の支出を補えるメリットも大きいでしょう。
とはいえ、入居率や建設費、将来のメンテナンス費用も見据える必要があります。土地の立地や需要を見極めながら、収益と税負担のバランスを冷静に判断しましょう。
分筆などの土地活用の工夫
土地が広い場合は、思いきって分筆するという手もあります。複数の小規模住宅用地として扱えると、固定資産税の軽減特例が適用され、全体の税負担をグッと抑えられる可能性も。
ただし、測量費や手続きの手間がかかるため、誰にでも向いているとは限りません。将来の使い道や分筆後の使い勝手をよく考えて検討しましょう。
空き家を活用して住宅用地特例を継続する
空き家をそのまま放置せず、リノベーションや用途変更で再び住宅として使えば、住宅用地特例を継続できる可能性があります。
たとえ工事費がかかったとしても、更地にするより税負担を抑えられるメリットは大きいもの。特定空家に指定される前に、点検や修繕を早めに進めておくのがおすすめです。
さらに、リノベ後に賃貸や民泊として活用すれば、副収入も見込めるかもしれません。ただし、民泊には住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出や、旅館業法に基づく許可が必要な場合があります。
更地の売却を検討するときの注意点
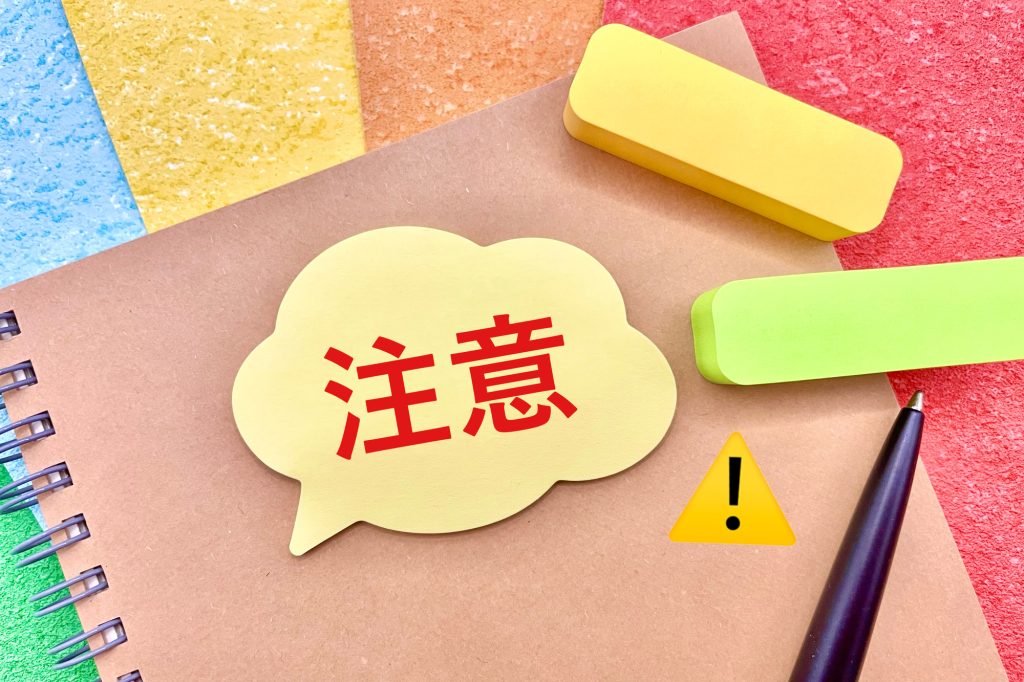
古家付きのまま売るべき?それとも更地にして売ったほうがいい?そんな迷いがあるなら、まずそれぞれのメリット・デメリットを整理してみましょう。
更地にすれば買い手の自由度が高まり、売れやすくなることもありますが、解体費用や税負担がかさむリスクがあります。古家を残して売却すれば、コストを抑えられる可能性も。
不動産会社の選び方や査定時のポイントも知っておくことで、納得のいく売却につながります。不動産会社が宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業の免許を有しているか確認することも重要です。後悔しないための判断材料を一緒に確認していきましょう。
更地売却と古家付き売却の比較
更地で売ると買い手が自由に活用しやすくなりますが、解体費用をこちらが負担することになり、さらに固定資産税も高くなる可能性があります。古家付きで売る場合は解体費を買い手に委ねられる反面、建物の状態次第では敬遠されることも。
どちらが高く・早く売れるかは、地域のニーズや物件の特徴次第。事前に傾向をつかんで判断しましょう。
不動産会社の選び方と査定のポイント
不動産会社にも得意分野があり、更地の売却に強いところもあれば、古家を活かしたリノベ提案に長けた会社もあります。複数社に査定を依頼し、提案内容や販売戦略を比較するのがおすすめです。
固定資産税の切り替え時期や地域特有の事情に詳しい会社であれば、より実践的なアドバイスが期待も期待できるでしょう。査定金額だけでなく、販売実績や担当者の知識も含めて、総合的に判断することが、よりよい選択に欠かせません。
将来のために知っておきたい「更地の固定資産税」
更地にすると住宅用地の特例が外れるため、固定資産税が一気に跳ね上がるケースも少なくありません。空き家でも、しっかり管理されていれば特例を維持できることがあるため、安易な解体はかえって損になる可能性も。
更地にするかどうかは、解体時期や新築計画、売却のタイミングなども含めて総合的に考えることが大切です。将来的な税負担や資産価値を見据えて、自分にとってベストな選択を見つけましょう。
不安がある場合は自分だけで抱え込まず、専門家の知見を借りるのもおすすめ。慎重に決断することが安心につながるでしょう。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。








