公開日:2025.08.24 更新日:2025.07.29
空き家を放置するとどうなる?リスク・対策・活用方法を徹底解説
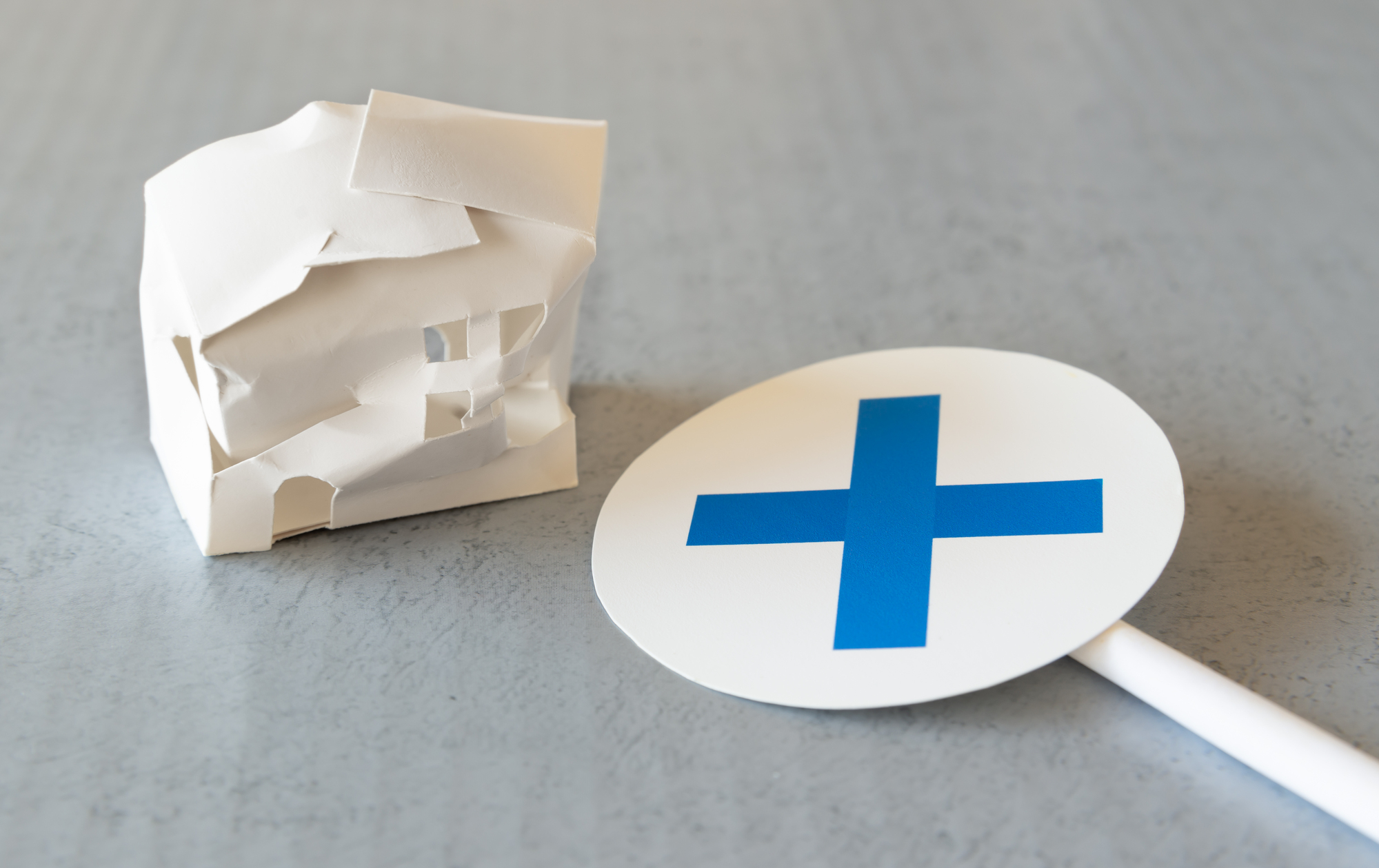
近年、全国的に空き家が増加し、さまざまな社会問題を引き起こしています。空き家を放置すると、老朽化や防犯リスク、税金の負担など、思わぬトラブルにつながることも。この記事では空き家を放置によるデメリットから、空き家の適切な管理方法、賃貸やリフォーム、地域コミュニティへの転用まで解説。相続や今後の活用に悩んでいる方に向けて、今できる対策をご紹介します。
目次
増加する空き家問題と社会的背景

空き家の数は年々増加しており、その背景には人口の減少や都市部への一極集中など、さまざまな要因が影響しています。少子高齢化が進む中で、家族の形態が変わり、住宅を持て余すケースが増えています。
特に、若者の都市部への移住が進み、地方では空き家が増加しています。このような空き家がそのまま放置されると、思わぬリスクを引き起こすことにつながります。
また相続した家が遠方にあり、管理が難しい、または費用がかかるといった理由で放置されてしまうケースも少なくありません。実際に空き家放置の問題は単なる個人の問題にとどまらず、周辺の環境や地域社会にも大きな影響を与える深刻な課題として捉えられています。
空き家を放置する主なリスク

空き家をそのまま放置しておくと、建物の老朽化だけでなく、周囲の環境やコミュニティにも大きな影響を与えることになります。長期間放置された空き家は、屋根や外壁が劣化し、最悪の場合、破損して周囲に危険を及ぼす可能性もあります。もしその被害が近隣に広がれば、修繕費用だけでは済まず、損害賠償問題に発展することもあるでしょう。
また、空き家が害虫や害獣の巣となることもあり、近隣住民の生活環境に深刻な影響を与えることになります。さらに、放置されていることで不法侵入や放火といった犯罪が発生するリスクも増加。加えて、特定空家等に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が増加する可能性があります。
そのため、経済的にも大きな負担がかかります。こうしたリスクを避けるためには、空き家を放置せず、定期的な巡回や活用方法を考えることが非常に重要です。
老朽化・倒壊の危険性と損害賠償リスク
空き家を放置し老朽化が進むと、屋根や外壁の材質が剥がれ落ち、周囲に被害を与えることがあります。特に台風や地震などの自然災害時には、倒壊のリスクが一気に高まります。もし倒壊や落下物が原因で他人の身体や財産に損害を与えると、所有者は民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)に基づき、高額な損害賠償責任を負う恐れがあります。このようなトラブルを未然に防ぐためには、早期の補修や定期的な点検が最も効果的な対策です。
害虫・害獣の発生と近隣への迷惑問題
空き家は通気が悪く、清掃が行き届かないことで、ネズミやゴキブリなどの害虫や、ハクビシンやタヌキといった害獣が住みつくことがあります。これらの害虫や害獣は、衛生環境を悪化させるだけでなく、騒音や臭いも発生させるため、近隣住民とのトラブルを引き起こす原因となりかねません。定期的な巡回と清掃を行うことで、こうした問題を未然に防ぎ、周囲との良好な関係を守ることができます。
不法侵入や放火などの治安リスク
無人の空き家は、犯罪の標的になりやすい場所です。器物破損や不法投棄が行われたり、最悪の場合、放火や不法侵入が発生したりする恐れもあります。これらの犯罪が起きると、周囲の治安だけでなく、住民の生命にも危険が及ぶ可能性があります。空き家を長期間放置する際には、防犯対策を講じ、定期的な巡回と点検を行うことが不可欠です。
特定空家等指定による税金・罰則面のデメリット
特定空家等に指定されると、固定資産税の特例が解除され、税額が大幅に増える可能性があります。空き家放置の大きなデメリットのひとつです。さらに、行政からの指導を無視すると、強制撤去や行政代執行が行われ、その費用は所有者が全額負担することになります。こうしたリスクを避けるためにも、特定空家等に指定される前から適切に管理し、問題を未然に防ぐことが非常に重要です。
空き家管理と法的な位置づけ:特定空家等・管理不全空家等

2015年に施行された空家等対策特別措置法に基づき、空き家は適切に維持管理しなければならないという法的義務があります。管理が不十分であれば、行政からの指導や命令、最終的には行政代執行などの処分を受けることがあります。
最近の法改正で、「特定空家等」の前段階として「管理不全空家等」という新しい区分が設けられました。これは管理が不十分なものの、特定空家等ほど深刻ではない段階ですが、行政からの再三の指導を無視すると、特定空家等に指定されるリスクがあります。
管理責任を怠ると、固定資産税の住宅用地特例の解除をはじめ、さまざまな経済的リスクを引き起こす可能性があります。適切に管理するためには、所有者自身が定期的に訪問するか、専門業者に巡回を依頼する方法があります。どちらの場合でも、建物内部だけでなく敷地周辺も確認し、必要な修繕や害虫駆除を速やかに行うことが求められます。
特定空家等に指定される基準と流れ
特定空家等の指定は、建物の老朽化の程度や周囲への危険性、適切な管理がされていない状態など、いくつかの基準を総合的に判断して行われます。行政は最初に助言や指導を行い、所有者に改善の機会を与えます。
しかし、それでも改善が見られない場合には、特定空家等として正式に指定されます。指定されると、税負担が増加するだけでなく、行政代執行などの法的措置が取られることになり、早期の対応が重要です。
管理不全空家等となるケースとリスク
屋根に破損があり、雨水が建物内部に浸透していたり、雑草が伸び放題になって近隣に迷惑をかけていたりする場合は、管理不全空き家と見なされることがあります。このような状況が続けば、行政から注意を受けることになります。
もし迅速に対応しなければ、特定空家等に指定され、税金の増加や強制執行といったさらなるリスクを抱えることになるでしょう。これらは空き家放置の結果として生じる問題です。
空家等対策特別措置法における行政処分と罰則
所有者が空き家を適切に管理せず放置し続けると、最悪の場合、行政代執行が行われることになります。この場合、代執行にかかる費用は後日所有者に請求され、行政不服審査法や行政事件訴訟法に基づく手続きで争うことも可能ですが、基本的には所有者が負担することになります。空き家を放置した結果としてかかるコストが予想以上に大きくなることがあります。
空き家の放置によるトラブルを避けるためにも、空家等対策特別措置法の趣旨をしっかり理解し、早めに対策を講じることが肝心です。
空き家を放置しないための4つの対策

空き家の問題を早期に解決するためには、状況に応じた適切な選択と迅速な行動が必要です。まず実践的な対策として、定期的に建物の状態をチェックし、老朽化が進む前に修繕を行うことが挙げられます。
また、空き家を放置するのではなく、早めに売却や買取を検討することで、改修費用や管理費用の負担を減らすことができます。収益化を考える場合は、リフォームや賃貸経営のメリット・デメリットをしっかりと検討し、経済的な効果を最大化することが大切です。
もし建物自体の維持が困難な場合は、解体して更地にするのも選択肢のひとつ。これも空き家放置を避けるための有効な手段です。解体費用は一度の大きな支出となりますが、倒壊リスクや有害生物の発生を防ぎ、長期的に維持管理コストを抑えることにもつながります。所有者の状況や地域の特性を踏まえて、最適な対策を選ぶことが必要です。
1. 定期的な維持管理と巡回点検
建物の外壁や屋根、床下などは定期的に点検し、破損や雨漏りが見つかれば早期に修繕することが基本です。できれば月に一度、最低でも数ヵ月に一度は現地を訪れることで、害虫の発生や不法侵入を防ぐことができます。定期的な点検を行うことで、大きなトラブルを未然に防ぎ、最終的には維持費の削減にもつながるでしょう。
2. 売却や買取による早期処分
空き家を所有しているものの、活用の見込みがない場合は、不動産会社に売却相談をするか、買取業者に依頼する方法があります。市場に出すまでの手間や、売却後に得られる資金の活用など、さまざまなメリットが期待できます。売却という選択肢は、所有者が長期的な管理負担から解放されるため、非常に有効な手段となるでしょう。
3. リフォームや賃貸活用による収益化
リフォームして賃貸物件として活用すれば、家賃収入を得るとともに、建物の価値を維持することができます。たとえば古民家の場合、内装を改修して宿泊施設やカフェとして新たなビジネスに転換することも可能です。収益化を実現するためには、ターゲット市場や需要を理解したうえで、適切な活用方法を選ぶことが鍵となります。
4. 解体して更地にする
維持管理が困難なほど老朽化が進んでいる場合、解体して更地にするのも合理的な選択肢。更地にすると、固定資産税の優遇措置が外れることがありますが、倒壊や火災のリスクを大幅に減らせるという大きな利点があります。
解体後の土地は、駐車場や資材置き場として活用できるほか、将来的に売却や新たなビジネス展開にも適した土地となる可能性が広がります。長期的な視点での有効活用が期待できるのも魅力です。
相続した空き家への対応ポイント

相続によって突然空き家を所有することになった場合、法的手続きや管理方法を速やかに検討しましょう。相続した空き家は放置せず、所有するだけでかかる固定資産税や維持管理のコストを考慮しましょう。特に遠方に住んでいる場合や、複数の相続人がいる場合は、管理が行き届かず、トラブルやリスクが増大する可能性もあります。
こうしたトラブルを防ぐために、早めに相続手続きを終わらせ、その後どう扱うかの方針を明確にすることが大切です。もし空き家の維持が困難であれば、売却や解体、寄付などの選択肢を比較して、最適な方法を選ぶことが求められます。特定空家等に指定されるリスクを避けるためにも、管理体制をしっかり整え、後回しにしないことが将来的な負担軽減につながります。
相続放棄や寄付などの選択肢
空き家の維持コストや大規模修繕を避けたい場合は、相続放棄という選択肢もあります。相続放棄を行う場合は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。特に老朽化が激しく再利用が難しい場合には、負担を減らす有効な方法となるでしょう。また、自治体やNPOに寄付できるケースもあるため、一度相談してみることが賢明です。
遺言・相続手続きとの兼ね合い
生前に遺言書を作成し、空き家の処分方法や相続人を明確にしておくと、トラブルを未然に防ぐことができます。遺言書には公正証書遺言、自筆証書遺言など形式があり、要件を満たさないと無効になる可能性があるため注意が必要です。
相続後は、遺産分割協議を通じて他の相続人と合意を得ておきましょう。誰が管理を行い、どのように処分するかを円滑に決定することができます。遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判に移行する可能性もあります。すべてを後回しにせず、速やかに協議を進めることが重要です。
管理維持と活用で注意すべき点
相続直後には、まず建物の状態を確認し、補修が必要かどうかや、虫害などの問題を早期に把握を。さらに空き家をリフォームして賃貸活用を検討する場合でも、近隣住民とのトラブルや法的規制への対応をしっかりと考えなければなりません。
維持管理の具体的なプランを立て、費用対効果を総合的に判断することが、将来的な負担軽減にもつながります。
空き家活用の具体例:地域やビジネスへの展開

地域やビジネスに貢献しながら空き家を有効活用する方法は多岐にわたります。空き家は単なる負の遺産ではなく、アイデア次第で新たな価値を生み出す拠点に生まれ変わります。地域密着型の事業を行えば、地域活性化にもつながり、社会的意義のあるプロジェクトへと発展するケースもあります。
たとえば、古い建物の趣を活かしたリノベーションを施すことで、観光客や若者に人気を集めることができるでしょう。また、自治体やNPOと連携し、地域の暮らしやコミュニティの課題を解決する施設を作るのも効果的。民泊やゲストハウスに転用することで観光資源として活用したり、地域コミュニティスペースとして住民同士の交流の場を提供したりすることで、過疎地域の活性化に貢献できるケースもあります。
古民家再生や民泊などの事業活用
昨今、歴史的な趣を持つ古民家をリノベーションし、ゲストハウスや民泊として活用する方法が注目されています。古民家ならではの風情を活かした宿泊体験は、国内外からの観光客を引き寄せる大きな魅力となるでしょう。
また、地域資源を活用した体験イベントや地元の食事などを組み合わせることで、さらに魅力的な滞在を提供でき、リピーターの獲得にもつなげることができます。
地域コミュニティスペースやシェアハウスとしての転用
住民が集うコミュニティスペースや、若者が共同生活を送るシェアハウスとして空き家をリフォームするアイデアもあります。
特に、地域の行事や子育てサロン、高齢者の交流の場など、多目的に活用できるスペースが不足しているエリアでは、高い需要が見込まれます。結果として地域コミュニティの活性化に貢献し、多世代の交流の場としても機能するでしょう。
NPO・自治体との連携による社会貢献
最近は、NPOや自治体と協力して、放置していた空き家を福祉や子育て支援の場として活用する事例が増えています。たとえば、地域の子どもたちの学習支援や、高齢者の憩いの場としてリノベーションを行うケースが挙げられます。
こうした取り組みは、空き家の再活性化となることはもちろん、地域全体の暮らしを豊かにするため、社会的な意義も大きいと言えるでしょう。
空き家の放置リスクを価値に変える一歩を
空き家を放置すると、老朽化や防犯リスク、近隣トラブルにつながるだけでなく、空家等対策特別措置法により「特定空家等」に指定されるリスクも。その結果、行政指導や固定資産税の優遇解除など不利益が発生することもあります。
しかし、定期的な管理や早めの対応、リフォーム・売却・地域との連携などを通じて、放置された空き家は価値ある資産へと生まれ変わります。相続した場合も早めの方針決定がトラブル防止につながります。
法律や制度も味方につけて、空き家放置の問題を解決し、活用への一歩を踏み出しませんか?
この記事の監修者

岡崎 千尋 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
都市計画コンサルタントとしてまちづくりを経験後、アキサポでは不動産の活用から売買まで幅広く担当してきました。
お客様のお悩みに寄り添い、所有者様・入居者様・地域の皆様にとって「三方良し」となる解決策を追及いたします。








