公開日:2025.09.01 更新日:2025.07.29
土地売却でかかる税金を徹底解説|計算方法・特例・節税対策まで【2025年最新】

土地の売却には税金がつきものですが、その仕組みや特例を理解しておけば、大幅な節税も可能です。こちらでは、所得税法や租税特別措置法に基づく特別控除や空き家特例といった制度から、確定申告の注意点、短期譲渡・長期譲渡による税率の違いまで、土地売却にまつわる税金の基本を2025年最新情報でお届けします。
目次
土地売却にかかる税金とは?基本の仕組みを解説

土地売却で利益が出た場合、その譲渡所得に対して所得税や住民税が課税されます。なんとなく税金がかかるのは知っているけれど、仕組みまではよく分からない……という方に向けて、不動産譲渡所得の課税区分である長期譲渡・短期譲渡の違いや確定申告のポイントも含め、税金の基本をご紹介していきます。
土地売却で税金がかかるのは「譲渡所得」が出たとき
土地売却で税金が発生するかどうかは、「譲渡所得」が出たかによって決まります。購入時より高く売れた場合でも、取得費や仲介手数料などを差し引いて損失が出れば、所得税や住民税はかかりません。
一方、取得費が不明な場合、「取得費不明時の概算取得費」として売却価格の5%を取得費とみなして計算することになり、想定外の課税リスクが生じることも。確定申告の際に困らないよう、購入時の契約書や領収書はしっかり保管しましょう。
土地売却における譲渡所得の計算式を解説
土地売却で発生する税金は、譲渡所得に所得税や住民税がかかる仕組みです。譲渡所得は「売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除」で算出します。
取得費には購入代金や登記費用、譲渡費用には解体費や仲介手数料などが含まれます。これらの費用は、税法上の規定に基づいて計上されます。
契約書が見つからず概算で計算すると、課税額が大きくなる恐れもあります。正確な取得費の把握が節税の第一歩となるでしょう。
土地売却でかかる所得税・住民税・復興特別所得税の関係
土地売却による譲渡所得には、所得税・住民税・復興特別所得税の3種類が課税対象となります。復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源を確保するため、2013年(平成25年)から2037年(令和19年)まで所得税の2.1%が上乗せされる制度です。
これらの税金は「分離課税」により他の所得と分けて計算され、長期譲渡か短期譲渡かで税率も変動します。確定申告では、これら3つの税金をまとめて申告します。所得税と復興特別所得税は税務署へ、住民税は自治体へ納める必要があります(地方税法による)。
土地売却の税金「短期譲渡」と「長期譲渡」で税率はどう変わる?

土地売却によって得た譲渡所得には所得税や住民税がかかりますが、所得税法第33条及び租税特別措置法第31条に基づき、税率は所有期間によって大きく変動します。自分の土地が短期譲渡か長期譲渡かを正しく把握することが、税金の負担を抑える第一歩。確定申告前に確認しておきましょう。
所有期間5年で変わる税率の違い
土地売却による譲渡所得には、所有期間によって「短期譲渡」と「長期譲渡」があり、課税される税金も大きく変わります。
所有期間が5年以下の場合、税率は高く、所得税・住民税をあわせて約39%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)に。5年超の場合は20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)になります。確定申告時の納税額に直結するため、取得日や売却日に注意しましょう。
なお、相続で得た土地は、被相続人の取得日を引き継ぐため、空き家特例や特別控除の適用とあわせて判断が必要です。
売却時期と取得時期に注意!
土地売却にかかる税金を左右するのが所有期間です。譲渡所得の税率は、不動産を譲渡した年の1月1日時点での保有年数により長期譲渡か短期譲渡かが決まります。
たとえば、2020年3月に取得した土地を2025年10月に売却した場合、譲渡した年の1月1日である2025年1月1日時点では所有期間が5年未満となるため短期譲渡扱いに。確定申告の際、税率が約2倍になるケースもあります。節税には売却のタイミングと特別控除の活用がポイントです。
控除後に適用される税率の確認方法
土地売却で発生した譲渡所得には、特別控除を差し引いた後に税率が適用されます。たとえば3,000万円の特別控除や空き家特例を利用すれば、譲渡所得がゼロになり、所得税・住民税ともに非課税となるケースもあります。
ただし、他の不動産売却による損失と損益通算はできません。長期譲渡所得の一部には軽減税率が適用されることもあるため、確定申告前に制度の詳細を丁寧に確認することが大切です。
土地売却時に活用できる特例・控除の種類

土地売却には税金がかかりますが、譲渡所得に対して適用できる特別控除や空き家特例などを活用すれば、所得税・住民税の負担を抑えられる可能性も。今回は代表的な例として、3,000万円の特別控除、空き家の特例、買い換え特例を解説します。
3,000万円の特別控除とは?
マイホームの土地売却では、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特別控除が適用される場合があります。過去に住宅が建っていた土地でも、一定の条件を満たせば対象に。
この特例を適用するには、居住用として使用していたこと、住まなくなってから3年以内に売却することなど、いくつかの要件があります。
空き家の特例(被相続人居住用財産の特例)
相続した空き家を土地ごと売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「被相続人居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除(空き家特例)」(租税特別措置法第35条第1項)が適用されることがあります。
主な条件は、その家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること、被相続人が一人暮らしだったこと、売却時に耐震性を満たすか解体済みであることなどです。本特例の適用には確定申告が必要で、売却は相続開始から3年を経過する年の年末まで、かつ2027年12月31日までに行う必要があります。税金を抑えたい方にとって、見逃せない特例です。
買い換え特例や収用特例も要チェック
土地売却の税金対策として、買い換え特例や収用特例の活用も検討したいところ。
買い換え特例は、売却後に別の土地を取得した場合、譲渡所得のうち差額部分だけが課税対象となります。この特例は「特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡所得の特例(租税特別措置法第36条の2)」として定められています。収用特例では、公共事業による売却で5,000万円の特別控除や代替地購入による優遇が受けられるケースも。なお、この特例は、新たに取得する資産が居住用であることなど、適用要件が細かく定められています。
ただし、空き家特例や3,000万円の特別控除と併用できないこともあるため、確定申告前に税理士へ相談するのが安心です。
土地売却の税金を安く抑えるためにできること

土地売却にかかる税金は決して安くありません。ただし、いくつかのポイントを押さえることで、税金負担を軽減できる可能性があります。
取得費・譲渡費用を正しく把握する
土地売却にかかる税金を正確に計算するには、譲渡所得の元となる取得費・譲渡費用の把握が欠かせません。取得費には購入代金だけでなく、仲介手数料や登録免許税、不動産取得税なども含まれます。これらの取得費に関する計上は、所得税法第38条等に基づいて行われます。
また、売却時に建物を解体した場合、その費用は譲渡費用として計上可能です。ただし、解体費用は、居住用不動産の売却で3,000万円特別控除を適用する場合など、特例によっては譲渡費用に含められないケースもあります。
契約書が見つからず概算で5%とされると、所得税・住民税の負担が大きくなる恐れもあります。確定申告前に、手元の資料を確認し、必要に応じて税理士に相談を。漏れのない取得費の計算を行いましょう。
売却時のタイミング調整で節税
土地売却にかかる税金は、譲渡所得が短期譲渡か長期譲渡かで大きく異なります。これは、租税特別措置法第31条等に規定された税率の違いによるものです。所有期間が5年を超えると、所得税・住民税あわせて約19%の税率差が生まれるため、年明けまで待つ判断が節税につながることもあります。
ただし、空き家特例や特別控除には期限が定められているため、売却時期の見極めが肝心です。確定申告を見据え、複数の土地を売る際は、控除や損益の組み合わせも含めた計画的な進行がポイントになります。
税理士への相談でリスク回避
土地売却に関する税金は複雑です。譲渡所得の計算や特別控除、空き家特例の適用条件を誤ると、後々の追徴課税につながる恐れもあります。
特に相続した土地では、取得費加算の特例など専門知識が不可欠。所得税・住民税の負担を抑えるには、確定申告前の段階から税理士に相談するのが安心です。
報酬を支払っても、節税効果で十分に元が取れるケースも少なくありません。不動産税務に強い専門家のサポートは、税金対策の鍵となるでしょう。
土地売却で確定申告は必須?必要な申告・手続きの流れ

土地売却によって譲渡所得が発生した場合、確定申告が必要になります。申告期間は売却した年の翌年2月16日から3月15日まで。申告ミスは税金の加算や特別控除の適用漏れにもつながるため、手続きの流れや注意点の確認が大切です。
確定申告の対象になるケースとは?
土地売却で譲渡所得が発生した場合、所得税・住民税の計算のため確定申告が必要です。これは所得税法第120条に規定されています。たとえ損失が出たとしても、空き家特例や特別控除を使う場合、損益通算や繰越控除を希望する場合なども申告が求められます。
会社員で年末調整を受けている方も、不動産の譲渡は分離課税の扱いとなるため、確定申告の義務が発生します。無申告によるペナルティを避けるためにも、該当する場合は必ず期限内に申告しましょう。
申告時に必要な書類一覧
土地売却による譲渡所得がある場合、確定申告には各種書類の提出が求められます。売買契約書や仲介手数料、解体費などの領収書は譲渡費用の証明に必要です。
取得時の契約書や不動産取得税の領収書、相続なら被相続人の取得費がわかる資料も欠かせません。特別控除や空き家特例を利用する際は、住民票や登記事項証明書、耐震基準適合証明書などの追加書類が必要になることもあります。
e-Taxを使った申告の流れとポイント
確定申告は、税務署に直接出向くか、郵送で提出する方法の他に、国税庁のe-Tax(電子申告システム)を利用して行うこともできます。自宅からパソコンやスマートフォンで手続きが可能で、郵送の手間を省ける点が魅力です。
マイナンバーカードと対応端末があれば、特別控除や空き家特例の適用申請もスムーズ。e-Taxソフトや確定申告書等作成コーナーを活用すれば、画面の案内に沿って入力するだけで申告書の作成が完了します。初めてでも比較的簡単に申請できるため、ご都合に合わせて活用してみてはいかがでしょうか。
土地の相続・贈与後に売却するときの税金に関する注意点

相続や贈与で取得した土地を売却する場合、譲渡所得の計算や特別控除、空き家特例など独自の税制が関わるため注意が必要です。確定申告の手続きや所得税・住民税の負担を正しく把握し、損のない売却を目指しましょう。
相続税の取得費加算の特例とは?
相続した土地を、相続税の申告期限から3年10ヶ月以内に売却する場合、「取得費加算の特例(租税特別措置法第39条)」を利用すれば支払った相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算できます。
二重課税を防ぐ目的で設けられた制度で、譲渡所得を圧縮できれば、所得税や住民税の負担も軽減されます。ただし、3,000万円の特別控除や空き家特例と併用できないケースもあるため、どちらが有利かを比較検討したうえで選択しましょう。
名義変更(相続登記)を済ませておく必要性
土地売却を検討しているなら、相続登記を早めに済ませておくことが不可欠。2024年4月1日以降、相続登記は義務化されました。不動産登記法改正により、不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。登記が未完了のままでは売却できず、譲渡所得の計算や確定申告も進められません。
手続きには戸籍謄本や印鑑証明書、特別控除の適用に関わる書類など、多くの準備が必要です。司法書士への相談も視野に入れ、計画的に進めることが大切です。
相続後すぐに売ると損になるケースも
土地売却は、相続直後に焦って進めると損をしてしまう可能性があります。譲渡所得の圧縮に使える取得費加算の特例は3年間有効なため、急いで売る必要はありません。
心理的な負担から早く手放したくなる気持ちもあるかもしれませんが、まずは不動産の相場や売却時期を冷静に見極めることが大切です。空き家特例の期限(2027年12月31日まで)や、維持費・管理負担なども含め、税金対策や将来の資産価値を考慮した判断が求められます。
土地売却の税金に関するよくある質問Q&A
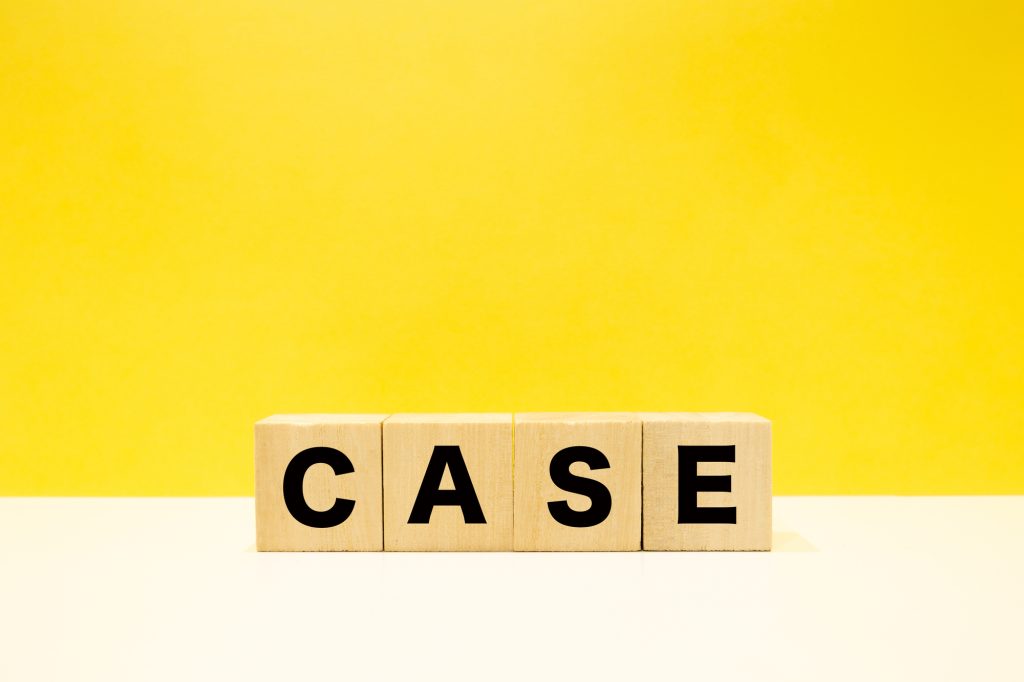
土地売却には税金や確定申告に関する疑問がつきもの。譲渡所得の計算、特別控除の適用条件、農地や山林といった特殊な土地売却など、知っておきたいポイントをQ&A形式で解説します。
更地にしてから売ると税金は高くなる?
土地売却前に建物を解体した場合、その費用は譲渡費用として譲渡所得から差し引けるため、税金が増える心配はありません。むしろ所得税や住民税の負担軽減につながるケースもあります。
ただし、3,000万円の特別控除を利用するには「住まなくなってから3年以内」の売却が条件。また、空き家特例を適用するには、売却前に耐震リフォームを行うか更地にする必要があります。解体のタイミングと特例の適用要件を確認し、総合的な判断が大切です。
農地・山林など特殊な土地の税金は?
農地や山林といった特殊な土地売却では、譲渡所得の扱いや税金の計算方法に注意が必要です。
農地を売却する場合、農業委員会の許可が求められることもあり、条件を満たせば最大800万円の特別控除が適用されるケースも。山林は5年以内の売却で山林所得、5年超なら長期譲渡として扱われます。
山林所得には概算経費率が使える一方、総合課税となる点も特徴。確定申告時の判断に迷う場合は、専門知識を持つ税理士への相談をおすすめします。
土地を分筆・一部売却したときの計算は?
土地売却で一部のみを分筆して売却する場合、譲渡所得の計算には取得費の按分が必要です。通常は全体の面積に応じて取得費を分けますが、地価や形状によっては路線価や固定資産税評価額を用いた按分が求められることもあります。
分筆には測量費用が発生しますが、これは譲渡費用として計上可能。所得税・住民税の負担にも影響するため、確定申告前に税理士や測量士と連携し、最適な対応を検討することが大切です。
土地売却の税金は、事前の知識と計画がカギ
土地売却にともなう税金は、譲渡所得の計算や特別控除、空き家特例など複雑な制度が関わるため、迷いや不安を感じやすい分野。
しかし適切な対策ができれば、所得税・住民税の負担を大きく抑えられる可能性もあります。事前準備を整え、納得のいく土地売却を実現させませんか?
土地売却と税金に強いサポートなら|アキサポにご相談ください
土地売却に関わる税金には専門知識が欠かせません。特に長期譲渡・短期譲渡の判断や相続土地の売却では注意すべきポイントも多く、的確な対応が必要です。アキサポでは、土地売却に関する税務から手続き全般まで丁寧にサポート。不安なく進めたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
売るか活用するか迷ったときも、空き家・相続土地の相談OK
相続で取得した土地や空き家。売却すべき?それとも活用すべき?と悩む方は多くいらっしゃいます。
長期譲渡・短期譲渡の税率差や空き家特例など、税務面も含めたご相談がアキサポなら可能です。売却だけでなく、賃貸や活用を含めたご提案も行っています。また、名義変更や管理のご相談にも対応。状況に応じて最も納得のいく選択を一緒に考えていきませんか?
節税・特例・手続きまで、まとめてサポートできる安心感
アキサポは、税金に関する深い知識を持った専門家と連携し、節税対策から各種特例の適用、確定申告の手続きまでを一貫してサポートします。土地売却は、人生における大きなイベントの一つです。税金に関する知識を深め、信頼できるパートナーを見つけることが、成功への鍵。ぜひアキサポにご相談いただき、安心・納得の土地売却を実現してください。
この記事の監修者

山下 航平 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
ハウスメーカーにて戸建住宅の新築やリフォームの営業・施工管理を経験後、アキサポでは不動産の売買や空き家再生事業を担当してきました。
現在は、地方の空き家問題という社会課題の解決に向けて、日々尽力しております。








